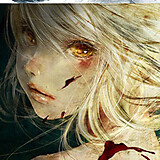GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊のレビュー・感想・評価
全123件中、81~100件目を表示
元祖Three Point Landing
攻殻機動隊のIMAX版のニュースを聞いてから鑑賞できる日を心待ちにしていたが、IMAX Enhancedであることにまず驚いた。巨大スクリーンに目一杯に広がる画角でまず気が付いたことは、背景のリアルさ。看板、ポスターのフォント、文面に至るまで緻密に作り込んである。自分自身が、中華難民街に迷い込んだ感覚に陥る。セル版ディスクを持っていて何度も見ているが、ここまで感じた事はない。
それと音響。体に振動を感じながら見る戦闘シーンは、迫力が全然違う。傀儡謡が始まると、全身があの独特の歌声と和楽器の音に包まれて、鳥肌が立つ。
四半世紀前に攻殻機動隊が予見していた近未来の世界が、本質的な部分において当たっていることに改めて驚いてしまう。「ネットは広大だわ」という素子のセリフは、今となっては解説なしで多くの人が理解できる。
記憶なくして人間足り得るのか、AIに記憶や自我があればゴーストは宿るのか。見る度に深く考えさせられる。A Iが創造主である人間を超えた時に答えが出るのかもしれない。
電脳世界にアイデンティティはあるか?
【今再び大きな意味を持つ、”自分はいったい何者か”という問い】
前に、何かのレビューで、哲学的な問いかけのあるような、頭を揺さぶられるSF小説が読みたいみたいに書いたことがあったけれども、今回、「GHOST IN THE SHELL」の4Kリマスターの上映で、この原作はそうだったと思い出した。
今見直しても、この作品は、古さなど微塵も感じない。極端な話、リマスターしなくても大丈夫のようにさえ思う。
いや、逆に、AIに対する研究が進み、技術革新し、理解が深まるにつれて、この映画の問いかけ...生命とは何か、人間とは何か、自分とはいったい何者かということの意味は、更に重要さを増しているように感じるし、”人形使い”が話す、「子孫を残して死を得る」とか「個性と多様性」、少佐が問いただす「多様性の揺らぎ」とは、代を重ねることによって、そこから得られる”進化”をも表しているのではないかと自問自答を繰り返したくなる。
少佐が話す、この作品の有名なセリフ、新約聖書のコリント人への手紙13章の第11と12も、観る者に、その意味の理解を要求する。
「童の時は語る時も童の如く、想うことも童の如く、論ずることも童の如くなりしが、為人(ひととなり)ては、童のことを捨てたり」「今我ら、鏡もて観る如く、見るところ朧なり」
実は、これには更に続きがある。
「然れど、かの時には顔を対せて相見ん。今我が知るところ全からず、然れど、かの時には我が知られたる如く全く知るべし」
僕は、これを省くことに重要な意味があったのではないかと考えている。
人は、子孫を残して自らは死んでいく、実は、その中に多様性や個性があり、そこから生じる多様性の揺らぎは、すなわち進化をも意味していて、”常に”完全なものなどないのだと。
つまり、いつまで経っても、僕たちは全てを知ることなどないのだと。
だが、しかし、今、僕たち自身は、悠久の時を経て今ここに存在しているのであり、(頭で理解しているかは別にして)それは僕たち自身に蓄積されて、変化も含めて残っていることに他ならないのだ。
それが僕たち自身なのだと。
新約聖書に書かれた言葉だが、この思考のスパイラル感は、考えようによっては仏教哲学のようで、”無常”とか、”色即是空 空即是色”に通じるものがあるようにも思える。
少佐がもう一つ興味深い言葉を残している。
「恐れ、不安、孤独、闇、そしてもしかしたら、希望。海面に浮かび上がる時、もしかしたら違う自分になれるんじゃないか。人間が人間であるための部品が決して少なくないように、自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なのだ。他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めた時に見つめる手、幼かった頃の記憶、未来の予感」
そう、僕たちは僕たちでしかないのだ。
最期に新しい身体を得た少佐の言う言葉「ネットは広大」。
1995年当時の、この作品の斬新さや、それを背景にした哲学的な問いかけは、色褪せず、今更に意味を増している気がしてならないと考えるのは、僕だけではないと思う。
タイトルなし(ネタバレ)
相変わらずおもしろ!ꉂ(ˊᗜˋ*)
草薙素子がビルから飛び降りる冒頭シーンを大画面で観れた。やったぁあ。
やっぱり大画面で改めて観れて良かった。YouTubeなどにも動画が上がってたりするけど、やはり大画面で観ないと。
ストーリーは難解だ。観客を置いていく。
草薙素子たち公安9課は、、、ストーリーはwiki見てね。
最後の戦車との戦闘シーンで、草薙素子は戦車の蓋を開けようとして手足がバラバラになるんだけど、これが理解できなかった。バトーがいなければ多分死んでいた。何故こんな判断ミスを少佐がしたのか不思議。
Wiki見ると人形使いと草薙素子は融合したみたいだ。
もはやS.FではなくS
現代のAIは深層学習と呼ばれる技術によって、プログラミングによって導かれた結論ではなく、エンジニアの意思を介さない擬似的な意思の様なものを得ている。
その為、劇中の人形使いの様に自らを生命体だと主張して亡命を申請する等という事も現実的に起こり得るだろう。
「コンピュータの普及が記憶の外部化を可能にした時、あなた達はその意味をもっと真剣に考えるべきだった」という台詞は2021年現在でも通用する問い掛けだ。
近い将来、人間が生命を構成するあらゆる機能を再現し製造する事が出来る様になった時、はたして人間は新たな生命を生み出す事が出来るのだろうか。
それとも生命を創ることは神のみに許された業なのか。
生命とは何か、生命と呼ぶ為に欠かせない要素は何か。この作品が登場して25年以上経った今でも結論は出ていない。
贅沢なSF体験の85分だった。
IMAX 4Kで見てきました。
音響が格別に素晴らしく、DVDでは分からなかった細かい音がくっきり聞こえたのは感動しました。特に素子とバトーがボート上で聞いたささやき声がはっきり聞こえたのはびっくりでした。
あとやはり数十年前の作品なので、リマスターと言っても素地の限界があるのは仕方がないですが、最後街を見下ろすシーンで綺麗に手直しされてたらそれも違うなって思って、やはりいい着地点だったんだろうなと思いました。
もしイノセンスがIMAX 4Kになったらとんでもなくすごい映像体験になりそうだと思いましたwww
またIMAXの大画面であの美術を堪能できたのは幸運でした。改めて作品を見直してみると、素人ながらに美術の凄さに圧倒されました。最後の対戦車で素子が力づくでハッチを空けようとして、逆に腕の人工皮膚や筋肉が千切れて身体がよじれるシーンは、IMAXの大画面でじっくり見ていると美しいの一言で息をのむおもいでした。
やっぱ難解だけど見応えあり!
士郎政宗作品、数少ない映像化成功例
当時、難解なテーマで消化不良でした
終盤のモタつきが悔やまれる
一人の人間として生きるとき、その時感じる世間の冷たさや静けさ
本作は予告編や、前情報のみを頭に入れ作品をイメージすると
ハイレグ女性刑事がサイバーパンクの世界をベースに
ハイテク技術を使い、ドンパチやっていることがメインのアニメーションという印象を受けるかと思います。
しかしながら実際鑑賞してみると、その世界は
とても冷たく、静かな世界観でストーリーは進みます。
それは、サイバーパンクの世界観を用いた刑事物というよりは
サイボーグ化され、ネットワークで情報を共有できても
アイデンティティは各個人が持ち、他者とは簡単に意識は分かち合えない、
人間は個別であるということを再認識させるような、
哲学的な内容を感じさせてくれる作品です。
もちろん、マトリックス等のハリウッドアクションに影響を与えている
アクションシーンもとても良いのですが、
私としてはこの映画が持つ、とても冷たい、とても静かな世界観から感じられる
『人間関係とは何か』、みたいなところが好きです。
このような視点で見ていただくと、より一層楽しめるのではないかなと思います。
素晴らしい作品だとは思うけど・・・
脳の電脳化、身体のサイボーク化が当たり前になった未来。「人形使い」と呼ばれる凄腕ハッカーを、刑事である主人公が追う物語。
押井守の名前を世に知らしめた作品です。
映像の精緻さ、パトレーバーから引き続きの小倉氏が描いた街並み。そして「サイボーク化された人間」という設定と「アニメ」という表現方法により、魅力が最大化されたアクション。流石の一言です。
ただ、この映画は草薙元子の自我を求めるお話なのでしょう。「電脳化された知能」に対する不信。自我に対する不安。それに悩み、解消しようとした草薙の物語です。
それはそれで素晴らしいテーマですが、上映時間80分では表現仕切れないもののように感じました。
TVのように12話をかけてじっくりとストーリーを作らないと、この映画の結末は唐突感を感じざるを得ません。
押井監督は大好きな監督さんですが、「毒気が強すぎて制御し難い監督」と言う印象が強くあります。そしてこの作品は、以前の作品と比較して、押井色がストレートに押し出された作品のように感じます。
個人的な好みの話で恐縮ですが、私には「あたる達友引高校の面々」や「遊馬達第二小隊の面々」が程よく毒気を中和した、ビューティフルドリーマーやパトレーバーの方が、より良い作品だと感じています。
初日初回 東銀座東劇にて
原作既読。当時買ったパンフレットやテレフォンカード(!)をまだ持ってます。
押井守氏が映画化するということで期待半分で正直不安も半分でしたが、コメディ要素をほぼ廃したゴリゴリハード路線エロスなしで、原作のエピソードを改変しつつ再構成したストイックで硬派な仕上がりは、原作とは違うアプローチながらも別の高みに到達していたように思います。
不満があるとすればフチコマの不在ですが、そうすると後年のテレビアニメ版くらいのボリュームがないと消化不良になったような気もするので致し方ないところでしょうか。
ボイスキャストは個人的にはこれ以外あり得ません(特に田中、大塚、山寺の御三方)。
公開当時は海外でここまで人気が出るとは思いませんでしたが、今はアニメーション映画のマスターピースという認識です。
そして田中敦子氏の訃報に大ショック。少佐…。ネットは広大ですか…。
2025年11月に劇場にて再鑑賞。改めて田中ヴォイスを堪能した。
AIが発達している現代に観るべきテーマ
イノセンスの次に見た!
未だに世界の最前線、最先端にあります
山ほどあるブレードランナーチルドレンの中で、本作こそブレードランナーのテーマに対して真正面から回答をしてみせた正統なる後継作品です
実存とはなにか?
人とは何か?
魂とはなにか?
記憶とは何か?
意識とは何か?
有機ベースとシリコンベースに意識の差異は存在するのか?
生命とは何か?
死とは何か?
本作を見ればマトリックスが如何にうわべだけの理解に過ぎないのかを思い知らされます
正統なる続編のブレードランナー2049も本作で提起された考えを拝借して展開しただけのものでしかないとよく分かります
本作公開から四半世紀が経とうというのに、未だに本作が到達した地点を踏み越えていく作品はありません
如何に革新的であったのか
ブレードランナーはフィリップ・K・ディックの原作が提起したテーマを見事に映像として展開しました
本作はその問題提起に対して、より深くより突き詰めて考察を先に進めています
本作のテーマはそこにあるのです
それこそが本作の価値であり意義なのです
近未来のリアリティなどはその考察の説得力を補強するためのものです
何も未来予測がテーマなどではないのです
マイノリティレポートとは未来技術の描写への立場は決定的に異なるのです
香港ぽい街並みのイメージ
旧式ぽいジェット旅客機機のシルエット
そこに意味はないのです
近未来であり、インターナショナルが進み
ハイテクノロジーとローテクが混在する21世紀というメッセージが伝わる事が重要なのです
いよいよ本作の世界は近づいて居ることは、誰の目にも明らかになってきました
このような世界をリードするクリエーティブを発揮する異才が日本のアニメ分野には集積していたということを本作は証明しています
エンドクレジットの大量のクリエーターの人名はその層の厚みを物語っています
逆にいえば実写の日本映画界にはこのような最先端の才能が集積しなかったということです
このような高い教養とイマジネーションを併せ持った人材を獲得し雇用維持できる業界としての魅力も、活躍する場も提供出来なかったということです
しかし、本作を超えていく作品はアニメにも、ましてや実写にも、四半世紀が経つにもかかわらず無いという現実は、彼らのクリエーティブティを発揮する為のビジネスとしての仕組みの不足、資金を供給する為の仕組みが、不足しているということを示しているのではないでしょうか?
彼らのクリエーティブティにそれが制約を与えているのではないでしょうか?
大変に勿体ないことです
クールジャパンに必要なことはこの制約を無くす事だと思います
そろそろ本作を踏み越えて更に先に、誰も観たことの無い映像、イマジネーションを観てみたいです
閉塞感漂うこの先にどのような地平が広がっているのか
そのパースペクティブを全世界に問う作品を観たいものです
電子の海/魂の在り処/自分という存在
"GHOST IN THE SHELL" シリーズ第1作。
Ultra HD Blu-rayで5回目の鑑賞。
原作マンガは読了済み。
何回観てもムズカシイ。高度に情報化された世界では自分と云う存在を定義することすら容易ではなくなる。
自分はここにいる。しかしそれを確かめる術とは、これまでの自身の記憶や周囲の他者による認識しか無い。
それが全て誰かに植えつけられた幻だったとしたら、じゃあ私はいったい誰なのかと云うことになってしまう。
なんともあやふやな定義で生きているのかと衝撃的だが、ただでさえ混乱する思考を凄腕ハッカー、人形使いの主張が一層強烈に揺さぶる。「私は情報の海で発生した生命体だ」。
つまり、全ての鍵を握るのは情報と云うことだろうか。
登場人物が哲学的なセリフを話したり、何かの引用が登場したりと、押井守監督らしい演出が散りばめられていた。
結局本当のところはと言うと難しくて分からないけれども、己自身を確かに持っていれば揺らがない、と肝に銘じたい。
[以降の鑑賞記録]
2020/10/13:Ultra HD Blu-ray
2025/04/13:Ultra HD Blu-ray
※修正(2025/04/13)
ゴーストの在り処は
全123件中、81~100件目を表示