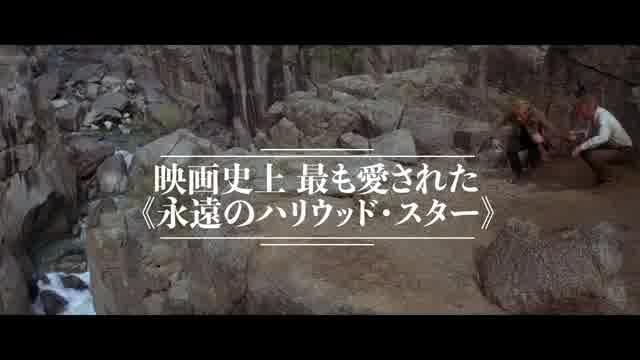明日に向って撃て!のレビュー・感想・評価
全65件中、21~40件目を表示
名作をこぢんまりと観る心地よさ
シリアスかと思いきやコメディタッチの男二人の物語。
ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、キャサリン・ロス。実は初めてみた。
日本語タイトルに引きづられたが、原題Butch Cassidy and the Sundance Kidのほうがスッキリ来る。
銀行強盗、列車強盗から一転強力な追跡のプロが現れ追われる立場に。広大な西部の乾燥地帯の平地、岩や山を駆け巡る。この壮大さは今回劇場で見たからこそ見応えがあった。しかし地域の人たちは強盗の彼らと真に敵対してはいないようにみえる。どことなく憎めずユーモラス。二人は理論派と射撃の名手でいいコンビ。冗談も言い合ったり、けなし合ったり。キャサリン・ロスも二人の間で愛くるしく気丈夫な女性役をこなしている。三人が正装して登場するシーンはカッコイイ。
ボリビアで三人が生活するようになるがここでも強盗などいろいろと事件が起こる。二人は殆どスペイン語ができないが勉強して何とか相手に命令しようとする。一方ボリビア人のスペイン語は日本語字幕がないので、何を言っているか分からず噛み合わないことも。筆者はスペイン語が多少分かるので、スペイン語のやり取りがとても面白かった。
ほとんどは本当にあったこととエンドロールにあったが、そこをエンターテイメント性の高く、優れた俳優を使い、面白い映画に完成させたのはさすがである。見てよかった。
そして、「雨にぬれても」Raindrops Keep Fallin' on My Head は、この映画の挿入曲として製作された。その曲が流れるシーンは、ポール・ニューマンとキャサリン・ロスが自転車ではしゃぐシーン。古き良き時代のアメリカ。とても良い。
「セピア色」という色を初めて知った映画。
ようやく観た(スクリーンで)
シネスイッチ銀座のポールニューマン特集で観た。ありがと、シネスイッチ。
観たことはある。ただ、それは小中学生時代にTVで観たのか、はてまた20歳頃に名画座で観たのか、それすら定かではない。記憶の薄さから言えば前者だろうか。今回は、4Kリマスターを劇場で。至福の時だ。
恥ずかしい話ながら、どっちがポールニューマンでどっちがロパートレッドフォードかわからなかった。頭のきれるブッチがポールニューマンで、早撃ちキッドがレッドフォードだったんだね。
オープニングはモノクローム。列車強盗後に追われるシーン。そこからの5分間はすてき。朝もやの青さ、荒野の茶色、だんだん色づいていく映像。
派手な強盗シーンはあるんだけれど、けっこう多くのシーンは逃げ回っているシーンだったんだな。
終盤に入る前、ニューヨーク、コニーアイランド経由でボリビアに旅立つまでがいい。10分強の静止画の連続。当時のモノクロ写真の中にさりげなく三人の姿が埋め込まれている。動画では時間を要すところを、静止画にすることで、観ているこちらの想像力で補完させて大幅に時間短縮する手法。ストーリー的にも、ここを丁寧に撮ってしまったら、間延びして逆効果だったろう。
これこそ、アメリカンニューシネマって感じ。
うっすら気づいてはいても、突っ走るしかない破滅への道。
今の人たちが観たら「どこが、アメリカン "ニュー" シネマなの?」と不思議だろう。
主人公が正義の味方じゃない、主人公が分別ある大人の男じゃない、最後がハッピーエンドじゃない。そういう映画は今では当たり前だが、当時は驚きだったんだってさ。ハリウッドもこの映画の頃より前は、基本的には「水戸黄門」が基本だったってことかな。それに対して、この映のように、犯罪者が主人公の映画、エンディングシーンは破滅の映画、といったものがニューシネマ。それはフランスでヌーベルバーグ(New Wave・新しい波)として始まり、米国では "アメリカンニューシネマ" として、世界中を1960年代後半から1970年代にかけて席巻する大きな波となったそうです。
アメリカンニューシネマの中にも本作のように今でも色褪せないものもあれば「卒業」のように今観ると首を傾げたくなるものもあり。皆さんも機会があれば、いろいろ観てみてください。映画も、100年のうちに、幅が広がり続けているんだね。
あ〜、自分には面白かった。最後も静止画で、カッコいい!!
おまけ
「明日に向かって撃て」 と言えば 「雨にぬれても」 。この楽しそうな音楽はこんな風に使われていたんだなということを確認できてよかった。
「ゴッドファーザー」の愛のテーマといい、この音楽といい、緊迫感がベースになっている映画の中の "ひとときの安らぎ" というシーンは、俺たちの耳に心に染み渡るものなんだなぁ、とわかる。もちろん音楽がよければ、であることは間違いない。
大好きな作品のひとつ。
ナイスなコンビ
今、見ても新鮮。
この時代的には、かっこいいかな
これぞ映画
定期的に観たくなる
素晴らしい映画です。ストーリー、演出、音楽、全てがハマってる。何より、主演の2人が放つ圧倒的スターオーラに酔いしれることができる、正に古き良き映画です。
リアリズムを追求し過ぎたり、逆に物理法則を度外視したCG満載でゲームみたいになったりと、そんな映画が昨今主流になりつつあると感じる今日この頃、本作のような銀幕の中の世界を味わえる、スクリーンとの程良い距離感がある「映画らしい映画」がいいと感じるようになりました。このご時世だから現実を忘れられる作品を強く求めてるのかも知れません。
近年の作品は特に安っぽく感じるものが多く、ただ単に歳を重ねて好みが変わったのか、フィルム撮影がほぼ無くなってきたからなのか、ハリウッド俳優の私生活やゴシップが求めずとも情報として溢れて作品に集中できないからなのか、よく分かりませんが、本作のような良質な作品を劇場で観たいものです。
永遠の名作
セピア色のラストシーン
ストーリーが、どこに向かって行くのかよくわからない映画だった。冒頭のセピア色のシーンが迫力的かつ芸術的だった。音楽の選び方、使い方、その音楽が流れている最中のカットワークの仕方に監督のセンスが溢れていた。中でも特に自転車のシーンが。あの音楽の使い方によってあの男女がどういう仲であるのかとても短い時間でしっかりと見るものの心に刻み込まれる。そしてその男女の性格まで伝わってくる素晴らしいシーンだった。
ただこの映画のラストの部分に女性の方は出てこない。普通、こういうあらすじだと最後には女性も巻き込まれて主人公たちと同じ結末を迎えるとか、それは描かれるものである。しかしこの映画では彼女がどうなったのか全く描かれていない。なぜならこの映画は二人の男たちの映画だからである。男たちの友情と言うか関係と言うか、つながりと言うかそういうものを描いた映画なのだ。女性がこの映画に登場するのは彼らがホモセクシャルではないということを表現するのが目的だ。また映画に花を添えるのにも女性が必要だった。だからこの女性の存在は映画の中で重要ではあるけどもメインであってはならないのだ。
皆さんが知らなさそうなことをついでに書いておこう。
サンダンス映画祭というアメリカ人ならだれでも知っている有名な映画祭がある。この映画祭をはじめたのはロバート・レッドフォードである。サンダンスというのはこの映画での役柄の名前だ。サンダンス映画祭は映画祭であると同時に映画と脚本のコンクールでもある。映画業界というのは特殊なコネクションを持ってないと入れない狭い世界である。しかし、このコンクールはそういったコネがなくても入選することができ、新しい感覚を持った監督が生まれる可能性の高いコンクールと認識されている。このコンクールをきっかけにしてデビューした有名な監督はタランティーノとロドリゲスだ。実は私もこのコンクールの脚本部門に応募したことがある。このコンクールの応募規定は非常にハードルが高かった。すでに映像関係のプロとして何らかの仕事をしており、かつまた新しい技術ががそこに含まれていないと応募できない。私は応募要項に事実を多少誇張した事を書いて応募してみた。そしたら一次選考を通過した。しかし誇張がバレるとヤバいと思って2次選考は辞退した。チャンスが得られなくて残念であった。
どなたか、我こそはと思う人は応募してみたらいかがだろうか?
アメリカン・ニューシネマの代表作
全65件中、21~40件目を表示