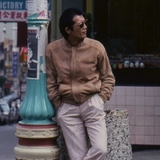乱のレビュー・感想・評価
全44件中、1~20件目を表示
逃れられない負の連鎖
古い映画ではあるが、だからこその生々しさ、臨場感、寂しさがあった。特に緊張感の中で静けさと鳥のさえずりが残るシーンが印象的だ。それは人間の悪行をも超越した自然の平和を感じさせるものだった。
物語はまさに負の連鎖。登場人物らの思惑と欲望にかき乱される様が描かれる。人間の未熟さ故の悲劇を美しく表現されていた。
個人的には大満足だ。何より1番はその映像美に圧倒された。最近のCGを使った迫力のある美しい映像に慣れてしまっているからこそ、この凄さに気づけたとも言える。1度見ておいて損はないだろう。
野次馬のように見入ってしまう
リア王‼️
わが敬愛する黒澤明監督が、シェイクスピアの「リア王」をもとに作り上げた戦国合戦絵巻‼️引退を決意した暴君の3人の息子たちが、やがて君主の座を巡って血で血を洗う争いを繰り広げる・・・‼️「リア王」自体が暗く陰惨な物語なので、今作も面白い物語ではない‼️しかしさすがは黒澤明監督、数多くの人馬が入り乱れる合戦シーン、敵の奇襲になぎ倒される兵隊、逃げまどう軍勢、落城と殺戮、天守閣と城内を焼きつくす火災など、息をのむ凄絶な映像美はホントに素晴らしく、加えて3人の息子の争いに胸を痛める主人公の深い悲しみを描いた人間ドラマとしても一級品ですね‼️仲代達矢さんのメイクアップも凄まじい‼️
欲に溺れる人間の行く末と教訓劇
男の機嫌はいい
順風満帆の人生だった。
ここから物語は始まる。
自ら築いた地位を息子達に譲るが
欲にまみれた次世代の思惑と終焉
シェイクスピアの「リア王」
土台はその戯曲にある。
第三者の立場
この映画で面白く感じたのは
「道化」ピエロの役である。
一番目立つのは秀虎の御付き
狂阿弥役のピーターがいる。
彼は派手に立ち回り親方にも意見を云う
親方の秀虎は時に戒め、時に受け入れる
そんなシーンが何度かある。
もうひとり、道化とまでは行かないが
三男の義理父・藤巻信弘役の植木等がいる。
隣国の領主藤巻は、強く出しゃばらず
優しい言葉の中に的確な意志を入れてくる。
真意は娘婿とその父を立てること、守ること。
そこに徹底している姿は見ていて気持ちがいい。
そして、次男の妻 楓の方・原田美枝子
この人の裏の顔には憎しみが潜んでいる。
人を操り撹乱させるのは、あの映画
「蜘蛛の巣城」の山田五十鈴と重なるが
やはり迫力は先輩の方が上と感じた。
シェイクスピアの戯曲は心の深部に触れる。
この映画、色々な見方があって良いと思う。
主役、子供達、ここに書いた第三者的な人物、
憎む者達、壮大なセット、衣装、構図の意図、
第三者・第四者・第五者たちの心情と死に様、
ラスト・シーンの彼は何を思っていたのか、
全てが虚無の出来事なのか…などなど、
たくさんある。
屋内での戯曲風の演出
オープンセットの演出
舞台劇としての鑑賞
黒澤明監督の見せ方
映画「乱」の創造
面白いと思う。
※
画の迫力にのめりこむ。…けれど、脚本にキレがない。
『マクベス』の翻案として、未だに追従を許さない『蜘蛛巣城』。
それに比べると、『乱』では台詞回しが『リア王』そのままでこなれていない。
シェイクスピアは、掛詞や逆説的な台詞を駆使し、当時の世相・哲学を圧倒的な会話の量で畳み込む。だから、一見、『乱』も哲学的なことを言っているようだけれど…。
それでも、画の迫力はすごい。
『アラビアのロレンス(アカバへの奇襲)』を彷彿とさせる、騎馬隊の躍動感。
アカバへの奇襲でも、ラクダから落ちた人が踏みつぶされないかと演者も鑑賞者である私もハラハラしたが、
この映画でも、落馬した人の中に、馬に踏みつぶされる、蹴られる等で大怪我した人がいないのかと言う映像が目白押し。演じられたのは、スタントマンか、大部屋俳優か、エキストラか。よく引き受けたな。
城炎上。その中で演じられる仲代さん。
『魔界転生』のクライマックスも迫力だが、この映画では飛んでくる火矢。『蜘蛛巣城』でも、演じる三船さんめがけて、本当に矢を放ったと聞くが、今度は火矢。なんたる役者の豪胆さ。仲代さんは、三船さんみたいに、怒りに任せて散弾銃を持って監督を襲撃したりしなかったんだろうか?
城炎上。台詞なし。音楽だけが流れる7分間。滅びへのレクイエム。演技だけで魅せてくれる。仲代さんの無念さ・狂気。
一発の銃声から、その映像で繰り広げられる音の乱射。わずなかな台詞。合戦のすさまじさ。
そのような、迫力ある画の反面、森の緑を背景にした、各兵士の色の美しさ。
大殿・太郎・次郎・三郎、綾部・藤巻…。その兵。眼福。
色とりどりの花が咲き乱れる長閑で天国のような風景に、狂った大殿とその傍らから離れない道化師。妙味。
かたや、一面の鼠色と白い岩。荒涼としつつも地熱を帯びた舞台。
地獄か、そこで会うのは仏か死神か。
とにかく、画に惹きつけられ、魅入ってしまう。
けれど、脚本にキレがない。
『マクベス』の肝要なエッセンスを残して、後は、能の様式美をふんだんに取り入れて、日本の物語に昇華させた『蜘蛛巣城』に比べ、『乱』は『リア王』の台本をそのまま訳したか?と思ってしまう部分が散見される。
その一つ・狂阿彌。
シェイクスピアに生きたエリザベス1世を始めとするヨーロッパの王家・貴族に使えていた宮廷道化師。シェイクスピアの劇によく登場する、役や物語の裏設定や本音を語って見せて、劇に重層的な広がりを見せる役目。深刻な劇のコメディーリリーフであり、バカげた展開の中で、正気を語る役。舞台で繰り広げられる主筋を、外から見ている観客の心の声ーにこちゃん動画のコメントのようなーそんな台詞を投げ込む役。
ピーターさんは善戦。さすが上方舞の名取。若き野村氏の所作に比べるとふらついてはいるが、それでも狂言的な所作も魅入ってしまう。
けれど、日本人に宮廷道化師はなじむのか?台詞があまりにもシェイクスピア的で、『リア王』の台本と比べたくなる。舞台なら、時に観客の方を向いて、主筋と観客をつなぐ役目もするし、緊迫した場面でのちょっとした息抜きにもなるが、この映画では、大殿のお世話係として、物語にどっぷりつかってしまうから、本当の意味での、道化師の役目となっていない。
そして、白けたのが、ラストシーンでの台詞。
今回の上映についていた講師の話では、監督は「天の視点」を描きたかったと聞く。だからか、宗教的な”神”の代弁とでもいうべき台詞がそのまま何のひねりもなく語られる。
エリザベス1世の頃はプロテスタント系と聞くがベースはキリスト教。唯一神を信奉し、神がすべての運命を決定する世界。ソドムとゴモラを消滅させた神。ノアの箱舟のエピソードの紙。『乱』ではその神を仏教に変えているが、そもそもの宗教の存在意義が違う。そこを精査せず、そのままスライドさせているだけ。台詞も練ることなく、ここもあまりにシェイクスピア的な言い回しなので、『リア王』の台本と比べたくなる。
能の世界観も中途半端。監修はつけているが。
『蜘蛛巣城』における鷲津の妻・妖婆に匹敵するのは、楓の方。原田さん善戦しているが、山田さんが能面のような表情ですり足でスーッと動く、浪速さんの存在感に対して、原田さんは生々しくて動きが派手。その分、駆け引きの裏に人間らしい恨みが見え隠れして怨念が漂ってくるが、鷲津の妻や妖婆のような不気味さが無くなる。わざと演出を変えたのだろうか。
そうすると、能の世界観はどこに?大殿の所作と、鶴丸の所作だけ?演者ではなく、もっと大きな舞台装置や兵たちのフォーメーション?
それでも、大殿と楓の方、狂阿彌、藤巻、鉄はまだその人格・生き様がその人らしかった。
他はどんな人物なのかぼんやり。
太郎が楓の方の尻に敷かれている様、次郎の背伸びは見て取れるが、それ以外に人物像が全く見えない。物語のカギを握る人々だけに、物語に面白みが欠ける。三郎に至っては、藤巻が三郎のどこにほれ込んだのか理解不能なくらいに人物像が見えない。大殿に恐れずに反論するところ?大殿に直射日光が当たらないように木陰を作ってあげるところ?それだけで、追放された三郎を娘婿として迎え入れるのか?
そして最大の残念さは中盤のクライマックス後がやたらに長い。予告を見た時点では、これがクライマックスかと思ってしまった。
川を渡っていく兵たちの躍動感、兵のフォーメーション、城が焼け落ちる様と画的には見どころがあるが、物語に緊迫感がない。
武将や楓の方の謀議が長い。『蜘蛛巣城』で三木暗殺を幽霊姿で表現した圧縮した演出と演技に比べるともたつく。物語に勢いが無くなる。
この映画の大殿は監督がご自身を投影されたものという話も読んだ。だから、大殿が地獄を彷徨っているような描写が必要に続くのか。こちらが本当に描きたかったところなのだろうか。
『蜘蛛巣城』では、マクベス夫人の狂気を、たったワンシーンで表現した。山田さんの演技が光る。
対して、『乱』でだって、大殿の狂気を、楓の方の無念と恨みを、ワンシーンで表現しきるだけの技量をもった方が演じているのにと、もったいなく思う。
つい、『蜘蛛巣城』のように、シェイクスピアのエッセンスを咀嚼して昇華した映画を期待してしまい、この映画への満足度が低くなる。
(講演会付き上映会にて鑑賞)
風は吹いている
神は愚かな人間を助けられない存在。
戦国時代の広島の戦国大名が毛利元就でその子息が毛利と小早川と吉川で...
戦国時代の広島の戦国大名が毛利元就でその子息が毛利と小早川と吉川ですが、原田美枝子がその毛利元就に敗けた武将の娘で人質として、その毛利元就の子息の一人に嫁いでますが、その毛利元就家を破滅させて、親の仇と最期に本音を吐き、その毛利元就の子息の側近に首を刎ねられますが、また宮崎美子もその毛利元就の子息に嫁いで、その宮崎美子の息子が目が見えなく、もうその母もいなく一人断崖上でが当映画のラストでしたが、以前にフジテレビの番組で、ダイアナ元皇太子妃がフランスで交通事故で死亡し、その英国の諜報機関がMI6とMI5がありますが、その諜報機関員がそのダイアナ元皇太子妃の電話も盗聴し、結婚をしますも聴き、すぐに上司に報告と思いますが、それを証言してましたが、その後に交通事故で死亡ですが、英王室のヘンリー王子がもうカナダ人ですが、そのヘンリー王子が、ダイアナ元皇太子妃とチャールズ皇太子との実際の子ではなく、ダイアナ元皇太子妃が一時、浮気をした際のその相手との子というのがネットにあり、今がDNA鑑定というのがありますが、またダイアナ元皇太子妃の家も名家のようですが、中世に英国内で騎士同士の争いの薔薇戦争がありますが
破滅と美の交響曲 黒澤の半自伝的映画
視力の衰え、自殺を試みた絶望の淵から、黒澤明がその全てを賭けて創り上げた映画『乱』
日本映画界から追放された巨匠がフランスの支援を受け、最後の作品となる覚悟で挑んだこの大作には、時代を超えて響き渡る慟哭と美が宿っています。
物語の核は、愛する息子たちに裏切られた老人の破滅。けれど、それは単なる物語ではなく、黒澤自身の人生と絶望が刻まれた傷跡でもあります。
序盤、「三の城」の戦闘シーンは、息を呑むほどの構図と動きでスクリーンを彩ります。その完璧さは、後にマーティン・スコセッシが『ギャング・オブ・ニューヨーク』で模範したと言わせたほどだ。そして、黒澤を“先生”と崇めるスピルバーグの「プライベート ライアン」が未熟な映画にすら思える。
だが『乱』が真に恐ろしいのは、主人公が正気を失い狂気に飲み込まれる後半部分。その圧倒的なエネルギーは観る者を呑み込み、エンドクレジットが流れても席から立ち上がれないほどの衝撃を与えます。
原田美枝子が斬首されるシーンでは、黒澤映画の象徴とも言えるダイナミズムがさらに洗練され、美しい残酷さとなって胸に刻み込まれるでしょう。
この映画を絶賛したのは世界の名だたる批評家たちの中でも、最も辛口で知られるロジャー・エバート。彼が最高得点をつけざるを得なかった、『乱』に対する彼の批評もまた素晴らしい。
これは単なる映画ではなく、普遍的な破滅の物語であり、芸術の極み。
神や仏も泣いているのだ。
NAGOYA CINEMA Week 2024でこの日一度だけの上映。たまたま休みと重なったから鑑賞。
カラーになってからの黒澤作品は、なんていうか色がうるさくて、好きじゃなかった。七人の侍や蜘蛛巣城、用心棒、、、何度も何度も観たけど影武者、乱は公開以来観ていなかった。
やっぱり黒澤映画は面白いや。観るたびに発見がありますね。
キャストがオーディションで選んだ影武者より、断然良い。
二郎も三郎も亡くなって、丹後は夕陽評論家になっちゃったな。
野村萬斎だったんだ。
仲代さんは偉大な俳優だけど、あの舞台のメイクと舞台の演技はちょっと受け入れられない人はダメだろうな。
哀しい場面には明るい音楽がより哀しさを際立たせるって言ってたのは、黒澤さん本人なのに、哀しい物語に哀しい俳優、哀しい音楽。
主役が三船敏郎さんで、音楽が佐藤勝さんだったらどんなにか面白かったろうに。(三船さんは、映画スター、アクションスターだもんね)
黒澤明の神視線。
神や仏は戦争という人間の愚かな行いに泣いているのだ。
今こそリバイバル拡大公開して多くの人に観てもらうべき作品だと思う。
戦国合戦物の傑作
毒を飲めというのなら喜んで飲む
神も仏も、救う術なし
狂った世の中で、気が狂ったなら、気は確かですね。
刀剣が乱舞するだけなら、見目麗しいことですが、血ほとばしり、肉弾ける映像は、今の時代、ダメみたい。先日、とある特撮映画観たのですが、血飛沫は不要とのコメントが散見されました。ただ暴力は不快なものです。(興味ある方は「ファ二ーゲーム」ご覧下さい。)昔から否定されている暴力ですが、槍が自動小銃となり、馬がレオパルド2に換わっただけで、今そこにある現実です。どんなに殴られても、翌週には青アザひとつ残らないような、暴力をファション化する映像のほうが、問題だと思います。
CGにせざるを得ない今と違って、城燃やすし、血糊も、文字通り出血大サービス状態。その城攻めシーンですが、鬼気迫る映像が、妙に淡々と描かれています。あるコンセプトに基づいて撮られたからです。わりと有名な話なので、どんなコンセプトなのか、調べてね。
全てを手に入れ、全てを失くす裸の王様。「リア王」読んでませんけど、栄枯盛衰の四文字を描くのに、どんだけ金使うんだよって話です。疾走するお馬さんの側で落馬する、かなりヤバいスタントも大盤振る舞い。大きなスクリーンで観たかったな。
それにしても、女性が非道い扱われ方をする映画ですね。人権の欠片もない。逆説的に、人権の有り難みを痛感します。
神も仏も、ヒトの愚かな苦しみを救う術は、無いようです。と云うか、そもそも、救う義理がない?。ヒトのことは、ヒトがやれってこと?。そんな私の戯れ言も、馬蹄の地鳴りに、掻き消されてゆきました。
乱世の非情さ、非人間性を描いた、理屈抜きの名作です。
この時代に戻りたい?。
インパクトNo.1、楓の方…
一文字家に一族を滅ぼされながら長男に嫁いだ楓の方。積年の恨みを家督相続に付け込み、到頭滅ぼすことに。やり方はエグいが女は強い。原田美枝子の怪演が光る。それに引き換え、男どもは権力争いに執着し、情けない。因果応報、自業自得。ときおり歌い出す道化役ピーターが的確な風刺をしたかと思えば、煩わしいと思うこともあり、狂った時間が長いからか仲代達矢の演技にも食傷気味。城を燃やし、人馬大合戦は黒澤映画スケールならではだった。
巨匠75歳、自虐の詩w
シェイクスピアを下敷きにした時代劇、地位の逆転と相互不信による自滅に至る物語、女にそそのかされ正気を失い道を誤る男。蜘蛛巣城と本作には多くの共通点があります。では、蜘蛛巣城にあって本作にないものは…。
①主人公と監督の若さと勢いが感じられない。
蜘蛛巣城は37歳の三船俊郎&47歳の監督による、下克上で権力を奪取する物語。若さ、反逆、暴発、夢と野望の挫折を描く。一方、本作は53歳の仲代達矢&75歳の監督による、権力の座から引退する物語。年寄、後悔、権威、不和、懺悔と和解を描く。
②女性たちの恐ろしさが足りない。
本作のヒロイン達、原田美枝子(27)&宮崎美子(27)の二人では、山田五十鈴(40)&浪花千栄子(50)の二人の、この世のものとは思えない恐ろしさにはとうてい敵わない。
③幽玄、夢幻を感じない。
阿蘇の大自然の中でのロケシーンで始まる本作。大自然の中でちっぽけな人間共が縁組みだの家督だのごちゃごちゃやってるのが、みみっちく見えてしまう。その他にも太陽光の下でのシーンが多く、人物の内面を凝視するというより、外面を凝視してしまう。
70歳の要介護老武将(仲代達矢)、介護者狂阿弥(ピーター)、忠臣(油井昌由樹)の3人に比べ、息子3人の描き方が薄っぺらい。太郎も三郎も二人とも狙撃され簡単に死んじゃうし。死に方が全然ドラマチックじゃない。一番面白いはずの次郎の内面には迫らないし。本来は息子3人の相互不信といがみ合いがドラマとして最も面白いはずなのに、じいさんにばかりフォーカスしてもつまらない。ただ、監督が自分の分身として小汚いジジイを創造したというのは、大変面白いと思います。過去の悪行の記憶と周囲の裏切りに苦悩し、狂気と正気を行ったり来たりする主人公の姿は、相当自虐的な自画像に見えます。天皇と言われた巨匠も、内心自責の念を抱えていたということでしょうか。
あと、最後に映画のテーマを忠臣の口を借りてセリフで説明されるのもがっかり。冗長かつ退屈に感じてしまう大作観念映画でした。ただ、監督はもう観客を喜ばせようなんて思ってないだろうことは伝わります。「人類への遺言」という言葉が示すとおり、監督はどこか遠くの方を見ている、あるいは自分だけを見ているようで、凡人の自分にはちょっとよく分かりませんでした。テレビにばかり夢中になっている日本の観客に監督は愛想を尽かしていたのかも知れません。海外では多くの賞に輝き評価の高い本作ですが、国内の興行収入では、ビルマの竪琴、ゴジラに次ぐ第3位、16.7億にとどまり、26億の製作費は回収できなかったようです。
よかった!
子供達に裏切られた父親の悲哀
全44件中、1~20件目を表示