ライオン・キング2 シンバズ・プライドは、前作で描かれた王位継承の内部対立(スカーというスペアの悲劇)を受けて、物語の焦点を戦後の統合へと移行させた作品である。
なお、 前作「ライオンキング(1994)」の考察については、当方のレビューを参照されたい。
前作では、 正統な継承を阻害したスカーによる王権簒奪と、外部勢力であるハイエナを用いた国家の混乱が中心に描かれた。スカーは正統な軍事力を持たない王の典型であり、外部の暴力装置に依存することで王国を破壊へ導いた。
一方、シンバが果たした役割は、スカー殺害ではない。むしろスカーを討ったのではなく、ハイエナの裏切りである。したがって、シンバは簒奪者であるスカーが退場した後、王権の正統性を回復し、国家を再び王国として存在させる土台を作り直した王である。したがって前作は英雄譚ではなく、むしろ政治的復古の物語に近い。
しかし、この復古だけでは王国は未完であった。本作冒頭から読み取れるように、スカー一派残党を主とするアウトランダーが残され、事実上の国家内部の分裂状態となった。このような状況におけるシンバの統治は、前作で生まれたトラウマと正統性への過剰な執着に支配されていた。その為、国家統合はシンバの治世において未完の課題として残されたままであった。
ここで象徴的なのが、続編でハイエナが完全に姿を消す点である。1作目でスカーに動員されたハイエナは秩序外の暴力、すなわち戦乱期における傭兵の象徴であった。
前作のレビューで述べたように、ライオン・キングの世界観を中世ヨーロッパに重ねて読むならば、薔薇戦争の後期に見られる歴史構造が参考になる。薔薇戦争の長期化により貴族たちは財政・軍事の両面で疲弊し、外部傭兵を調達する余力を失っていった。
この観点からみれば、王国が外部暴力を抱え込む段階を過ぎていることは自然であり、ハイエナが退場するのは歴史構造ともよく対応している。ライオン・キング2が描くのは戦乱そのものではなく、その後始末としての統合過程であり、そこで傭兵的勢力が姿を消すのは必然である。
なお、ハイエナがスカーの「仇」であったため排除されたという説明も可能だが、それは表層的因果に過ぎず、物語を寓話として読むなら構造的変化として捉える必要がある。
したがって、 続編の物語の重心は 、外部からの脅威ではなく王国内部に残された断裂をいかに修復するかへと移る。 しかし、シンバは依然として外部への恐れを優先し、アウトランダーとコブを危険視したまま関係修復に踏み込めない。統合期に必要な包摂ではなく、防衛と血統の維持に重心を置く姿勢が、王国内部の分裂をかえって固定した。
シンバはスカーの支配から生還した経験ゆえに、外部への恐れと正統性の防衛意識が過剰に働き、アウトランダーとその青年コブを赦すことができない。
彼の政治観は、国家戦略ではなく過去のトラウマと血統意識に支配されており、国家統合に必要な寛容と包摂を欠いている。
そのため、シンバの治世では国家の分裂は解消されず、復古から統合へ移るはずの課題は次世代へ先送りされる。
この未解決の分裂を引き受けるのが、キアラとコブである。正統王家の直系であるキアラと、スカー派残党の青年コブの結びつきは、薔薇戦争を終結させテューダー朝を成立させたヘンリー7世とエリザベスの婚姻に重なる。長く続いた内戦の傷は、権力者その人ではなく、次世代の融和によって癒える。
キアラが歌う「We Are One」は、彼女自身が体現する寛容の統治観を象徴するものであり、王国が必要としていた政治的成熟を示している。
(※補足:Oneは共同体を指す。中世の血統優位な封建王制を超えた、包摂的な統合国家(主権国家体制)の基礎を作る王女として、近世へのアップデートを象徴している)
まとめると、『ライオン・キング2』は前作のスペアの悲劇と王権崩壊を受け、そののち不可避的に訪れる国家統合を、世代継承というかたちで描き出した。物語の中心には、シンバの政治的未熟さと、キアラが示す寛容を基調とした統治観の対比が据えられている。全体として、封建的な血統主義に支えられた中世的世界から、領域と共同体の統合を基礎とする近世的な王国観への更新が描かれている。
こうして本作は、単なる恋愛劇ではなく、戦後政治の寓話が暗喩された作品となっていた。









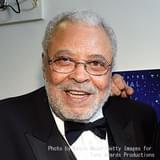












 スカイスクレイパー
スカイスクレイパー スクリーム
スクリーム スクリーム2
スクリーム2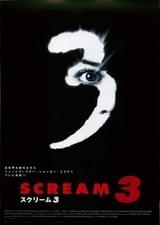 スクリーム3
スクリーム3 スクリーム4:ネクスト・ジェネレーション
スクリーム4:ネクスト・ジェネレーション 天気の子
天気の子 「鬼滅の刃」無限列車編
「鬼滅の刃」無限列車編 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅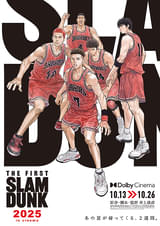 THE FIRST SLAM DUNK
THE FIRST SLAM DUNK






