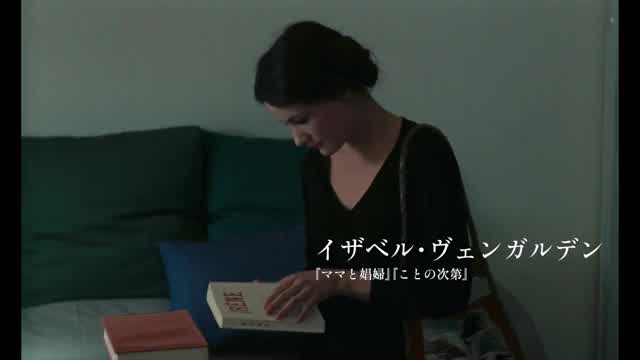白夜(1971)のレビュー・感想・評価
全20件を表示
俺のための物語と思った
個人的なレビューになる。この映画の男にとって恋とは画材である。彼は恋し、妄想し、それをテープに録り、キャンバスに落とし込む。
ブレッソンのこの映画をふくめ、優れた映画は多面的に物語を語れる一方で、人間は一面的にしか物事を観ることはできない。私の場合はこういうふうにこの映画を観たわけだ。
男は恋愛体質である。色欲をキャンバスに落とす。その恋愛はプラトニックであり、それ故の気持ち悪さもある。その気持ち悪さを含めた概念をキャンバスに落とす様はストイックである。そのストイックさを女性は誤解してしまう。故に男の恋は実らない。
正直だからなんなのだ、と思う。しかし、確かに彼は存在し、ボサノヴァとフォークとフレンチポップが流れる世界に確かに二本足で立っている。それを確かに表象できている。結局映画にできるのはこういうことで、だからこそ、素晴らしく、美しいのだ。
一緒に観に行っていた友達は寝ていた。僕は感動していた。
1971年フランスの名作、4Kレストア、原作はドストエフスキーの短...
1971年フランスの名作、4Kレストア、原作はドストエフスキーの短篇。
パリのポンヌフにて。
画家の青年が、思いつめた女性と出会い、事情を尋ねたら
一年前に再会を誓った男性が、誓った日時に姿を見せず、落胆していると。
数日間は一緒に探し、特別の感情も無かったものが、徐々に情が移りそうな。
この青年、もともと惚れやすいようで、
いろんな女性が目線に入ると目で追いかけているような。
女性は、一途なのか、気移りするのか…
ご本人の機微や所作で、都度伝わってきます。
原語および英語の題目は
Quatre Nuits d'un rêveur
Four Nights of a Dreamer
いざ鑑賞後、
un rêveur / a dreamer って誰? どっち?
むしろ deux rêveurs / two dreamers でないの?
と、突っ込みたくなるような感覚は抱きます。
それにしても、
通りがかる人々のたたずまい、
セーヌ川の景色、
ストリートミュージシャンたち、
etc
眺めていて目の保養になる、小気味いい作品でした。
映画を娯楽としてとらえていた私には理解しがたい。
正直に感想を述べるなら、あまり好きなタイプの映画ではありませんでした。私のように娯楽として映画を見に行く人には不向きかもしれません。
他の方が絶賛されている理由がわからず、ネットでブレッソンを調べてみました。すると、これは映画ではなくシネマトグラフ。しかも俳優ではなく、演技経験がほとんどない人を使い、極力感情も出さないようにして作られていると知って、なるほど、そういう作風なのかと納得しました。しかし、私は映画を見ながら感情の持って行き場がなく、少し悶々としました。
この映画は一種のアート作品ですね。しかも、余計なものを削ぎ落とした作品。普通、映画は観客を喜ばせるためにプラスしていくのに、それとは正反対のところにある映画。だからこそ、挿入曲がない分、ストリートミュージシャンの演奏や足音が耳に残り、新鮮さを演出できたのかもしれません。
美しいショットの連なりの童貞処女映画
ポンヌフの恋人未満
思い返せば随分と久方ぶりの再見である。
男女の出会いと別れを四日間に純化して描いた作品だが、主人公の青年は街で見かけた好みの女性のあとをつけていったり、来訪者があると生活の痕跡や描きかけの絵を隠すし、バスの中で唐突に録音した自分の声を再生したりするというかなり挙動不審な人物だ。少なくともヴィスコンティ版のマルチェロ・マストロヤンニとは造形がかなり違う。マルトとの関係が仮に継続していたにしても早晩破綻したような気もする。
それにしても彼がマルトの身投げを止めなかったら、終幕の展開もあり得なかったわけで、本当に因果な役回りだと。これは身投げしかかっている人を救うシチュエーションとして「文七元結」的命題でもある。
顔を映さないクローズアップ・ショットの多用は健在。ブレッソンの文体に慣れてしまうと、いっそ小気味いい。
マルト役のイザベル・ヴェンガルテンは美しかったが、既に亡くなっていたんですね。ヴィム・ヴェンダースと一時期結婚していたとは知りませんでした。
セーヌ川はポン・ヌフの恋
幻燈のような恋の妄想
「白夜」という神秘的なタイトル、原作のドストエフスキーという名前に惹かれたが、原題は「夢想者の四夜」なのだそう。
街で出会う女性と自分が恋をする妄想に取りつかれ、昼も夜もないといったところだろうか。寒い地域の話ではなく、恋の予感が騒ぎ出す初夏を思わせる映画だった。
主人公のジャックは都会の川で身を投げようとしている若い女性のマルトを救い、身の上話を聞く。1年前に留学先に旅立った恋人を待っているのだという。
恋人は、マルトは隣の部屋に間借りしていていた下宿人。同じ家に住んでいる間は彼を拒否していたのに、留学することがわかると運命を共にすることを願う。壁一枚をはさんで、顔も見ようとしなかった彼の存在が徐々に浸透してくるような関係が面白い。
ジャックにしてみれば、すでに恋人がいる女性が自分に振り向いてくれるという妄想が一番の好物なのだろう。テープレコーダーに自分の妄想を吹き込んでは巻き戻してリピートしていたのだが、やがて「マルト」という一言を繰り返すようになる。
そんなマルトに寄り添ううち、ジャックにもチャンスが訪れたように見える。ジャックは途中で「君は彼のことを好きなままでいいのに、その気持ちを隠そうとするから失望した」みたいな複雑な話をするのだが、要は恋の駆け引きをしてみたいということなのかな。
最後はマルトの恋人が現れ、マルトはあっという間に彼と立ち去ってジャックの恋は終了。
人間、他人のものが欲しくなるという心理が描かれている気もするけれど、たぶんリアリティよりも画面の綺麗さのための映画だろう。パリの街も女性も、妄想の中だから美しい。
セーヌのほとりで邂逅した男と女。「月が綺麗ですね」からの残酷にして滑稽なる幕切れ。
ロベール・ブレッソン監督の映画が、ここ数年で何本も4Kレストアのうえ、リヴァイヴァル上映されている。
僕が最初に映画.com に(Yahoo!映画から移ってきて)感想を書いたのが、実は『バルタザールどこへ行く』で、その後、『少女ムシェット』『田舎司祭の日記』『やさしい女』『たぶん悪魔が』『湖のランスロ』『ブローニュの森の貴婦人たち』の計7本を映画館で観たことになる。これで8本目。
実際に観て面白かったかどうか、という話でいうと、最初の『バルタザールどこへ行く』と『少女ムシェット』はそこそこ楽しめたが、残りの映画は世評ほどには感銘を受けなかったというのが正直な感想で、自分はそこまで良いブレッソンの観客ではないと思う。
彼独特の禁欲的な「シネマトグラフ」の手法とショットへのこだわりについては、いちおう興味深くは観られるものの、ストーリー的に引き込まれる類の映画群ではないうえに、たいてい登場人物の言動にほとんど共感することができず、主要キャラとの心理的な距離感は結構大きい。
もともと、ブレッソンの提唱するシネマトグラフという手法自体、客観性と他者性の強い「型」を重視した方式であり、キャラクターたちはあたかも「人形」か「バレエ」のように、監督によって「振り付けられる」。
観客は、登場人物に共感するのではなく、「観察」することを強いられる。
生々しいリアリティをはぎ取られて、能の型のように所作とセリフの「概念」を視覚化していく素人俳優たち。
すべての夾雑物をそぎ落とされた末、映画に刻印されているのは、ロベール・ブレッソンの脳内ですでに完成していたコレオグラフの再現――視線の交錯と、手の動きと、立ち位置と、カメラのアングルによって構成される「純化(記号化)された映画のイデア」に他ならない。
数多の制限のなかでこそ輝く意味性の累積と、映画ならではの刺激的なショットとモンタージュの実験は、たしかに観客を静謐な潜心と知的な興奮へと導いてくれる。
メカニカルに「仕組まれている」と同時に、眩暈を起こすような、先験的で抒情的な詩情が映像にあふれているのも、ロベール・ブレッソン作品の特徴だ。
『白夜』もまた、その文脈においては、実にポエティックで、かつ映画的な示唆に富んだ作品だといえる。
― ― ― ―
ただ、お話に共感できるかといわれると、これはなかなかに難しい。
まず個人的に、僕は「一目惚れ」という現象を信用していない。
妻とも、2年学内サークルで同じ時間を過ごしたあと交際し、さらに6年付き合ってから結婚した。爾来、25年間、一度の浮気もなく仲良くやっている。
見た目で好きになる、という経験が自分には一切ないので、一瞬で恋に落ちる主人公を見ると「ほんまかいな」という想いがつい先に立ってしまう。
まあもともと、主人公のジャックはア・プリオリに監督によって「恋に恋する男」として規定された存在だ。
まだ見ぬ愛する人に宛てて、声のメッセージを録音しつづける画家。彼は絵を描きながら、自分の吹き込んだ声を再生して聴き直す(純粋にやってることがキモすぎるよww)。
彼にとっては、自分のそういう想いや、行動や、あり方それ自体が掛け値なしに「尊い」のであって、ここではその夢の対象(恋人のイデア)として、自殺志願者でよるべない存在のマルトが、ぴたっと「はまった」だけである。別段、この男はマルトの本質が好きなわけでもなんでもない。
ジャックはマルトに言う。「僕はすぐに恋に落ちる――夢に描いた理想の女性に」
彼自身が、そういう内向きに完結した自分を「自認」し、「容認」しているわけだ。
対するマルトにしても、「帰ってこない男を待つ」という物語的行為自体に「淫して」いる存在だとしか言いようがない。
彼女もまた、相手の男が本当に愛しいわけでは、おそらくないのではないか。
だいたい、マルトと下宿人のふたりは、1年後に再会する約束を交わすまで、ほとんど顔すら合わせていないのである。
戻らぬ愛しい男を待つという、関係性と距離感。そのロマン性(文学性)と悲劇性に酔いながら、彼女は死を想い、生を想う。
それは、ある種の舞台症患者のようなものかもしれない。
マルトも、ジャックとは別の形で「恋に恋して」、そんな自分の想念の操り人形として生きている。
ふたりは出逢って、四回の夜をともに過ごす。
だが、彼らは本当に相手を観ているわけではない。
お互いが夢想する「悲恋のイデア」に、
相手の存在が、ただ「嚙み合った」だけだ。
ふたりは、相手の何かを愛したかったわけではない。
相手を恋する「物語」にあこがれていたのだ。
だから、あった瞬間から、ふたりのあいだには「物語」が生まれる。
そうでないと、あった瞬間から恋など生まれない。
本作の原題が『Quatre nuits d'un rêveur』(夢見る者の四夜)というのは、そういうことだ。
― ― ― ―
出逢ってからのふたりの心の動きも、
僕には共感しかねることばかりだ。
身体性を持った女が現れたのに、レコーダーに痛語を録音し続ける男。
待っている人がいるのに、近づいてきた男にわざと「隙」を見せる女。
マルト「私たち、いつまでも一緒よ」
ジャック「君を愛しているんだ」
定時に会って川べりをうろうろ散歩しているだけで、ひたすら盛り上がっていくふたりにドン引きしながら、「俺は、いま何を見させられているのだろう?」という疑念にとまどっていたら、比較的唐突に、あの衝撃的なラス前のシーンがやってくる。
「月を見上げてごらん」(欧米に夏目漱石はいないから、「月が綺麗ですね」=「愛しています」のロジックは通用しないと思うけどw)からの、あの素っ頓狂で、ぎょっとするような変心のラスト・ラン!
ああ、監督はこのえげつない瞬間が撮りたくて、この映画を作ったのか。
そう思わせるくらい、残酷で、滑稽なシーンだ。
なんか、ちょっといきなりすぎて、笑えちゃうんだよね。
それまで、たいして知りもしない女に迫って、口説いて、愛を語り続けてきた、気持ちの悪い夢想男の在り方自体に、盛大に冷や水を浴びせるようなどんでん返し。
同時に、ふたりへの想いを両天秤にかけながら、今の閉塞した生活から連れ出してくれる存在をただひたすら希求していた女の、あまりの判断の早さと即決ぶりに、笑ってしまう。
この嗅覚! この俊敏性! すげえわ。
NTR返しの華麗さ。手のひらくるくるの柔軟性。
このシーンだけは、本当に面白かった。
ブレッソンにしてはロマンティックな抒情をたたえた映画だし、よるべなく孤独で内向きなふたりの語らいからは親密な気配も感じられるのだが、結局のところ、ブレッソンはちっともこの二人に共感なんかしていなかったんだな、と思わざるを得ない酷なエンディング。
演者によりそわない監督の冷徹で厳格な眼差しは、「恋」を口にして「物語」にのめりこむ若いふたりの愚かしさと醜さを鮮やかに描き出して、映画を締めて見せる。
考えてみれば、ブレッソンは『田舎司祭の日記』においても、ある程度自分の分身のようなキャラクターを出してきて、じっくりその陰鬱な精神と独りよがりな思考法を客に見せつけて、存分にうんざりさせてから、ラストでそのキャラクターをあっさり切って捨てて、さくっと「自己否定」してみせるという作劇を仕掛けてきた人だ。
本作のジャックは、まさに若き日のブレッソンの分身のようなものだ。なにせブレッソン自身が若い頃、画家を目指して研鑽を積んでいたのだから。
『ブローニュの森の貴婦人たち』『湖のランスロ』『やさしい女』『たぶん悪魔が』……彼の恋愛要素のあるメロドラマ系の映画を振り返ったとき、女は常に浮気性で病的で執着心が強く、男は常に多情で自分勝手な性格であることに気づく。若い身空で希死念慮をもてあそび、思い込みを前提に濃密な愛憎劇を繰り広げる彼らの恋愛模様は、本質的に「ディスコミュニケーション」の物語でもある。
その意味で、ブレッソンの『白夜』は、まさにブレッソンらしい映画といっていいだろう。
― ― ― ―
その他、寸感。
●冒頭のでんぐり返しは、ロッセリーニの『神の道化師、フランチェスコ』(50)と、パゾリーニの『大きな鳥と小さな鳥』(66)および『テオレマ』(68)を想起させる。「愚者」のメタファーか?
●フロランス・ドゥレ(『ジャンヌ・ダルク裁判』)、アンヌ・ビアゼムスキー(『バルタザールどこへ行く』)、ナディーヌ・ノルティエ(『少女ムシェット』)、ドミニク・サンダ(『やさしい女』)、イザベル・ベンガルテン(本作)、ローラ・デューク(『湖のランスロ』)など、ブレッソンの選んでくる素人ヒロインには、明確な「好み」がある。強いて言えば、北方ルネサンス的というか。
●ブレッソン映画には、唐突に生気が漲る瞬間というのがある。『少女ムシェット』におけるゴーカート・シーンとか、『田舎司祭の日記』におけるバイク相乗りシーンのような。本作の場合、ブラジル音楽の路上演奏や、映画館で流れるノワール風のギャング映画のラストシーンがそれに当たるだろう。ちなみに、本作においても音楽はBGMとしては流れず、あくまで環境音の延長上で、実際にその場で鳴っている音楽として挿入される。
●やたら女々しくて気持ち悪い主人公のわりに、描いている絵画はフェルナン・レジェやモンドリアンを想起させる、三原色の目立つ明朗な抽象画だ。この色彩の調子は、川面に映るネオンサインの玉ボケや、青シャツと赤いマフラーといった服装の取り合わせとも呼応している。
― ― ― ―
川面に乱反射する、街のネオン。
玉ボケする、赤、青、黄の光。
川のたもとで出逢った、男と女。
男は画家の卵で、女には別の男がいる。
ふたりは急速に心を通じさせて……
といった映画を、なんか前にも観たことがあるな、
と思ったら、深作欣二の『道頓堀川』(81)だった(笑)。
あれは、松坂慶子が猛烈にエロくて、
小学生時代、昼日中のTVで濡れ場を観ながら、
激しく興奮したものだったけど……。
思い返すと、意外に深作はブレッソンの『白夜』を意識していたのかもしれないし、あるいはまったくしていなかったのかもしれない。
最後に、これを書く前にネットで『白夜』を検索したら、思いがけず、小林政広監督に『白夜』(09)という映画があることを知った。
ヴィスコンティにも同じ原作の映画があることは知っていたが、こちらの映画は本当に知らなかった。
吉瀬美智子とEXILEの眞木 大輔が主演の二人劇で、リヨンが舞台で、女は別の男を追いかけてきていて、男はバックパッカーで、橋のたもとでかりそめの恋に落ちて……と、明らかにドストエフスキーが原作というよりは、ロベール・ブレッソンの映画版を意識した作品のようだ。フィルマークスでほかの方の感想を読んだら、あまりの皆さんの酷評ぶりに眩暈がしてきた……(笑)。
でもレビューの一つで、監督と実際に会った方が、彼はロベール・ブレッソンの『白夜』のような映画を撮りたかったらしいと証言されていて、なるほどやっぱりね、と。
ただ、他のレビュアーの誰一人としてブレッソンの『白夜』に言及していないし、他の映画サイトや映画の宣伝記事でも、まったく触れられていない。これは一体どうしたことか。
元ネタが「素人俳優を使う」ことに大きな意味を持たせていたブレッソンだと「わかったうえで」観れば、吉瀬美智子とマキダイがどれだけ「大根」でも、観客側も観方(というか心構え)がだいぶ変わったと思うんだよね。
だって、みんなふたりの演技があまりに酷すぎると言ってボロカスに叩いてるんだけど、たぶんロベール・ブレッソンに私淑する小林監督としては、ふたりにはまさに「素人みたいに」演じてほしかったんだろうし、実際にそう演出したんだろうから、ふたりの演技が棒なのは間違いなく「故意」なわけで、そこは責めてあげたら可哀そうなんですよ。
もしかすると、ブレッソンとの「比較」のなかで観たら、随分と印象の変わる映画だったのではなかったのかな? 多分観ないけど(笑)。
魅せられたる四夜
コツコツコツ
タイトルなし(ネタバレ)
鑑賞するのはのは今回が2度目。
初鑑賞は、日本初公開の翌年1979年、ルイ・マル『鬼火』と2本立て、大阪の大毎地下劇場だった。
パリはセーヌ河に架るポン・ヌフ橋界隈での初秋の四夜の物語。
第1夜。
画家志望の青年ジャック(ギョーム・デ・フォレ)は、身投げしようとしている少女マルト(イザベル・ヴェンガルテン)を救う。
翌日、同じ時間に同じ場所で会う約束をする。
第2夜。
身の上を語り合い、マルトには恋する相手がいたが、彼は米国へ留学した。
1年後にここで会おうと約束したが彼は現れない。
マルトは彼が帰ってきているのは知っている。
待って3日。
彼が帰ってきたら必ず立ち寄る親友のところへ、この手紙を届けてほしい・・・という。
第3夜。
手紙を届けたことをマルトに告げるジャック。
マルトはジャックに「あなたを愛している。彼があなたみたいに優しかったなら」といい、ふたりは青年の存在を不安にしながらも恋人同士のように時を過ごす。
第4夜。
前夜のように恋人同士な雰囲気のふたり。
ジャックもマルトに愛を告白し、美しい月を見上げたとき、件の青年が大通りの中を通り過ぎる。
見つけたマルトは青年のもとに駆け寄ってゆく。
という物語。
わかりやすい話なのに、ブレッソンは手強い。
人物にフォーカスせず、どことなくフェティシズム感が漂う被写体の切り取り方で、物語に入るにはもどかしい。
しかしながら、映像そのものは翳の濃い魅力的なもの、随所に織り込まれる流しの音楽も雰囲気はよい(ただ少し過剰な気はする)。
十代の頃に観た自身の感想が「どこがどうというより、全体の雰囲気がいい」としか評していないのもよくわかる。
物語に入り込めない(入り込ませないようにしている)のは、被写体の切り取り方だけでなく、ジャックとマルトの人物造形によるかもしれない。
最終的に残酷さを示すマルトはどちらかと言えばわかりやすいが、ジャックの方はややつかみづらい。
原題の「夢見る男の四つの夜」の「夢見る」青年なのだが、巻頭の道で見初めた女性の跡を執拗についていくシーンなどは、いま見るとストーカーにしかみえないし、画家志望にもかかわらず(スケッチではなく)テープレコーダーで自身の思いを録音して何度も何度も聴いたり、ちょっと偏執っぽい。
にもかかわらず、彼が描く絵はポップな感じ・・・
ややイケてないとはいえ、ティモシー・シャラメ似なのに、「うーむ、どうもなぁ」な感じだぞ、ジャック。
本作、自身のなかではいまひとつ肚に落ち切っていないので、今後どうするか。
パンフレットなどで他者の解説を参照するのが手っ取り早いのだが、そういうことはあまりしない方。
ドストエフスキーの原作は読んだし、他のブレッソン作品と比べるのも手だが、その前に同じ原作をヴィスコンティが撮った『白夜』と比べてみようと思う。
男性の妄想を映像化したかのよう
独特の雰囲気を醸し出す映像、音楽は良かったと思いますが、
高評価の中に、女性が投稿したものがあるのでしょうか
フェミニズムではありません
が、
マルタは男性の理想なのでしょうか こういう作品が名作と謳われていることを残念に思いました
ここから先はネタバレになると思いますので、細かい内容を知りたくない方は
スクロールしないでください
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
見知らなぬ男性にまるで恋をしているかのような、突然のフルヌード
会ったこともない男性に、若い女性が「連れ出して」?しかも肌を許す?
エレベーターを止めて閉じ込める、放置したのに愛され続ける...
下宿人も、そんな男を愛する設定も、
男性本位の身勝手さ、女性を軽視しているような視点が不快でした
面白かった
あまりにも経済的なロベール・ブレッソンのモンタージュ美学
男がおもむろに手を挙げるショットに切り返す形でこちらへ向かってくるタクシーのショット。しかしタクシーが停車せぬうちにカットが切り替わり、次の瞬間には男が完全に停車したタクシーのドアノブを握っている。
タクシーが男に気づいて停車したことは、わざわざ説明せずとも直後のドアノブのショットによって完全に説明される。それゆえの省略。結果、この一連のシークエンスは類稀なる軽妙なリズムを獲得している。
その後、タクシーはすぐさま画面左の闇の中に消えていき、空港の荷物ベルトコンベアを画面右に向かって流れていく荷物の群が映し出される。次いで男が画面右上に伸びるエスカレーターを登っていくショット。そこにオーバーラップするジェット機の轟音。わずか10秒ほどで男が女のもとを去り、異国の地へ旅立ってしまったことが説明される。
あまりにも経済的なロベール・ブレッソンのモンタージュ美学はこうしたほんの些細なシークエンスにおいても力強く発揮されている。
中でも最も瞠目すべきは男と女のドア越しの攻防戦だ。目まぐるしいカット変更にもかかわらず、その部屋の間取りを、男と女の関係値の変容を、我々はいとも容易に想像することができる。そういう意味では『スリ』と並んでブレッソン入門に相応しい映画だといえるだろう。
脚本は至極単純。孤独な画家ジャックは夜のポンヌフでマルトという女と出会う。マルトは一年前に、ある橋の上で恋人と落ち合い、結婚する約束をしていた。しかし恋人は現れず、マルトは悲嘆に暮れる。他方ジャックは彼女を毎夜慰めているうちに彼女のことが好きになってしまう。マルトのほうも恋人への執着をかなぐり捨て「今日が終わったらあなたと一緒になる」と決意を固めるが、まさにその晩、マルトの前に恋人が現れてしまう。
まあ、ロベール・ブレッソンを物語的境位において観るということは、身も蓋もない悲劇を観ることと同義なので不思議はない。それでも、恋人と肩を組んで雑踏の中に消えていくマルトを呆然と見つめるジャックのやりきれない佇まいには思わず感涙を誘われた。
時代柄なのか、ヒッピースタイルの若者が多々登場する。しかし彼らこそが本作の音楽を担う重要人物たちであることは言うまでもない。ジャックとマルトの恋を盛り上げる船上の音楽隊、あるいはマルトに去られてしまったジャックの絶望をセンチメンタルになぞる路上のフォークシンガー。
あとはやっぱり手ですね。ブレッソンは世界で一番手を撮るのが上手い。ドアノブを回し、テープレコーダーを押し、女の脚を愛撫する手。そこには形容し難い神聖さが確かに宿っている。
ブレッソンの橋ものがたり
自分が生まれた頃に作られた見逃していたブレッソン白夜を4Kという復活上映的なイベントで観れた。場内は上映回数の少なさか、かなり混んでいて、時折いびきも聞こえもするが、角川有楽町のスクリーンサイズが好き。
そして映画はびっくりするほど若く、鮮烈。
これはブレッソンのポンヌフの恋人たちというか、ブレッソンの橋物語。パリと橋(と川)。諦めるのか待つのか、待つのか諦めるのかという女と、そんな女に吸い寄せられる男。いづれも若者。2組のミュージシャンがいい按配にカットアウトをする。音楽はうっとりだが、切り込み方は唐突に。それがゆっくり川上から川下に流れ去る。もうそれだけ。更に謎のラジカセ録音機能。愛を記録し、吐き出し、なるほどとは思いつつ、バスの中で徐に再生するのは衝撃的面白さ。向かいで見つめ合う主婦たちと恋にまいっちまった青年との視線の交錯。たけし映画でもこんなのはない。
川面に反射する光はフィルムの優位性を物語る。これはスクリーンで観ないとな、の1本だった。ラストシークエンスが青春そのもの。
パリの街に音楽が流れていた
19世紀のペテルブルグではなく、20世紀のパリのポンヌフ(第9橋)で、現れない恋人を待つ女性と画家の青年が出会う。
彼女は存在そのものが美しい芸術のようだけどロマンティストではない。彼はとても孤独で貧しいけど悪意はなくロマンティストだ。
60年代後半のパリの街には音楽があふれている。吟遊詩人のように街角でギターやバイオリンや笛を演奏する人たちもいる。
セーヌ川を行く船も音楽と共に流れていく。
そうして彼と彼女の束の間の時間も流れて消えていく。
唯一音楽だけがそれを知り惜しんでくれるかのようだ。
なにも救いがないほどつらい孤独の中で、20世紀と言うさらに人間をコンクリートで囲ってしまう孤独の檻の中で、彼はなんとか持ち堪えているんだ。共感しないわけがないじゃないか!
40年前に見た映画だからあいまいなところはあるけど、心に染み付いている。10代のころ、4,5回は見に行ったと思う。池袋に文芸座とかいう映画館があった時に。
流れて過ぎていったあれらの音楽の曲名を知ることはできないだろう。DVDも発売されていないから二度と聞くこともできない。
だからこそ、一層懐かしく、胸がしめつけられる。
記憶が確かなら、あれは1968年のアカデミー賞芸術作品賞かなんかだったような気がします。最高に芸術的であることには間違いないと私も思う。万人に理解されるかは別として。
全20件を表示