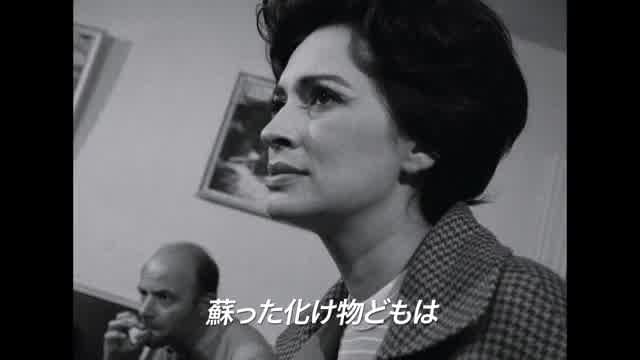ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのレビュー・感想・評価
全38件中、1~20件目を表示
4K映像で体感する、記念すべきゾンビ文化の夜明け
キング牧師が銃弾に倒れたのと同年に公開された本作は「夜8時なのにまだこんなに明るいのね」という他愛もないセリフから始まる。若い兄妹が家族の墓参りを行う中、遠くからゆらゆらと近づく初老の男。そして人類とゾンビとの記念すべきファーストコンタクト。かつて学生時代に見たビデオテープはかなり粗い画質だったが、4K修復版では町の住人たちから成るエキストラまで鮮明に見渡せるし、逃げ込んだ一軒家で顔を合わせる7人の生き残りたちの個性や、なかなか折り合えない目の前の男との分断をどう埋めるのかに四苦八苦する表情も新鮮だ。そして主導権を握るのがアフリカ系の男性という点には公民権運動の影響を少なからず感じる。かけ集められた10万ドルという製作費で、結果的に250倍以上の利益をたたき出したという本作。これがなければ、その後のゾンビ文化は生まれなかったことを思うと、我々はもっと足繁く本作を巡礼すべきなのかもしれない。
令和6年9月28日 新文芸坐「倒錯するカルト映画の世界」にて鑑賞④
令和6年9月28日 新文芸坐「倒錯するカルト映画の世界」の4本目。
この企画の上映作品は4作品。
「イレイザーヘッド」(77年)
「マルチプル・マニアックス」(70年)
「リキッド・スカイ」(82年)
「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」(68年)
時間はもう午前四時をまわっていた。この日、池袋の新文芸坐へ集まった我々観客たちの長い夜ももうすぐ明けようとしているのだ。
途中、一つ席を空けた隣に座る白髪の背広姿の男性が革靴を脱いだ際に、一日かけて熟成された彼の足の臭いが私の鼻腔を突いたり、空腹に堪えかねたらしい観客が煎餅を齧る音が上映中の劇場に静かに響いたりと、どうしたものかと逡巡する幾つかの場面があったものの、おおよそ楽しい夜であったのです。
そしてそんな長い一夜の最後にこの作品を持ってくる劇場側のセンスに心から敬意を表したい思いなのでした。
この晩、劇場の物販では本作の復刻パンフレットが販売されていたわけですが、まぁそのパンフレットを手にしている人の多いこと多いこと。私も昔は劇場で観た作品は、そのデキに拘わらず記念にパンフレットを買っていたのですが、自分の場合ロクに読まずにタンスの肥やしにしてしまう事を経験から学んでいましたので今回も購入は見送りました。しかし開演前や上映作品間の休憩時間で場内が明るくなるたびに至る所で本作のパンフレットに目を落としている人がいるのです。
またパンフレットの他に本作のTシャツも販売されていたのですが、お客さんの中には劇場で販売していた物とは違うデザインの本作のTシャツを着ている人が居るのです。それも一人や二人ではありません。かなりの数の人が何時何処で入手したのか知れないリビングデッドTシャツを着ているではありませんか!明らかに今夜ここに集まった人たちの大半は本作目当てで来ている事が分かるのです。(ただ一番印象に残ったのは「不思議惑星キン・ザ・ザ」(86年)のTシャツを着ている人が居た事なのですが…)
何故に1968年に公開された映画が今もなおこれ程人々の心を掴んでいるのでしょうか?しかも当時日本では公開されなかったような超低予算映画がです。いや、こんなすっ呆けた言い方はよしましょう。そんなの当たり前なのです。この作品は確かに面白いのですから。
今夜これまで観てきた3作品はいずれも確かに私の興味を惹く強い個性を放ってはいたのですが、しかし1本の作品の完成度としては至る所に“難”があるのもまた確かなのです。個人的には1点突破の荒々しい映画も好きなのですが、それを果たして他人に勧められるのか?というとやはり躊躇してしまいます。しかしこの「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」は娯楽作品としての完成度もしっかりしており、胸を張って他人にお勧めできる1本だと思うのです。その事は今回の鑑賞でもやはり再確認させられました。
後に数多のフォロアーを生み出すゾンビ映画の元祖ではありますが、“ゾンビ”というモチーフ自体に観客が何かしらテーマ性を感じてしまう作りには本作はまだなっていない気がします。ゾンビの本作での存在はあくまで登場人物たちを極限状態の窮地へ追い込む舞台装置程度のものだと感じます。しかしそうして未曽有の事態に陥った登場人物達が見せる不安や緊張、焦燥や疲弊、そして対立の様子は日本に暮らす我々にだって身に覚えのある事なのです。
例えば新型コロナウィルス感染拡大騒動の初めの頃など、多くの人は週末だろうが大型連休だろうが自粛ムードに煽られてジッと自宅で息を潜めて外の様子を伺っていた事でしょう、そのくせ自粛を要請していた連中が今度は『GoToトラベル』だとかいう危機的状況の旅行業界への救済政策を始めだした事に様々な思いを胸に去来させていたわけです。
さらにマスクは有効か無効か?ワクチンは打つべきか否か?イソジンが効くとか効かないとか!?アクリルパネルは意味あるのか?いや飲食店に置いてあるアレは流石に意味ないだろ!?と、誰も答えなど知りようもない状況の中で日々錯綜する報道を注視し、更新され続ける感染者・死亡者数に戦々恐々とし、いつまでも感染者数0人を記録し続ける岩手県の事が逆に心配になったりしていたはずなのです。
そして多くの人が感染拡大防止、早期終息を願ってはいたものの、それに向けての意見や方針は対立し、そしてその対立は国政レベルだけでなくもっと身近な会社の同僚間、ご近所間、友人間、果ては家族間でさえも起こっていたのです。
基本的に日本人は面と向かって議論をする性質ではないので表立ってはいなかったでしょうが、誰だってあの当時は身近な誰かしらに対して『よくこのご時世にあんな振る舞いができるな』と非難がましい感情を抱いた覚えがあるのではないでしょうか?そしてそれらの記憶を生々しく想起させる場面の数々がこの映画には確かに描かれているのです。
新型コロナウィルス感染拡大でなくても噴火や台風や地震や原発メルトダウン等々、災害大国に暮らす我々がこれまでに幾度も感じてきた、あの先行きの見えない状況に対する不安や緊張、焦燥や疲弊と対立。その一端と重なる描写が「生ける屍が生者の血肉を求めて徘徊する」なんてなんとも荒唐無稽なこのお話の中に確かに存在するのです。
本来ならこの作品からは、本作が制作された当時のアメリカで起こっていたアフリカ系アメリカ人の公民権運動に対する何かしらのメッセージを感じる方がより正確なのでしょう。しかし日本に暮らす私としてはやはり、極限状態に追い込まれた登場人物達が見せる様々な感情に自身も感じた事のあるそれを重ねて映画に夢中になってしまうのです。
そしてこの映画の物語は片田舎の一軒家とその周辺数メートル以内で起こった、たった一夜の出来事なのです。しかし物語は常に張り詰めた緊張感を維持して観客をその一部始終に夢中にさせてくれます。
1968年公開の映画といえば「2001年宇宙の旅」や「猿の惑星」があるわけですが、それらに比べるとこの映画の製作費はおそろしく低予算です。にもかかわらずこの映画はその低予算振りもスケールの小ささも全く気にならず、それらの超大作に対して面白さで引けを取る事はまったくないのです。優れた脚本と演出があれば映画はちゃんと面白くなることをこの作品が証明しているのです。
さらにこのおそろしく低予算で作られた本作は、その製作費のウン百倍もの興収を稼ぎ出したのです。この映画以降ホラー映画というジャンルは低予算で作って大ヒットさせてこそ“本物”という風潮が出来たような気もしなくはないのです。
どちらにしろこの映画は今に続くゾンビ映画の元祖としてだけではなく、ロクに製作費をもらえない駆け出し映画監督達に成功へのヒントを示した映画だったのではないか?と思えてしまう程、その存在自体が何かとても格好いいのです―。
初めての名画座で初めてのオールナイト上映を無事に完走し、白んだ薄ら寒い池袋の街を駅に向って歩く足取りはゾンビさながらにフラ付いていましたが、とても充実した映画体験だったのです。
正しく生き延びる
今から56年前の作品
まだゾンビと呼ばれなかった死人が襲ってくるという今では定番なのだがそんな昔に思いついたのか
何にでも始まりがある
この作品からも分かるようにヒッチコックの『サイコ』をリスペクトしているのがよく分かる
ホラー映画ではあるがどうやら一番怖いのは生きている人だということがよく分かる
究極の恐怖体験をした時に人はどうなってしまうのか
その人のおかれた状況で臆病にもなり強気にもなる
一概に性格だけでは説明がつかないこともあるように思うのです
ゾンビに着目られることが当たり前の作品ではありますが描きたかったのは人々と恐怖なのだと思う
こんな状況で人々はどう動きどう生き延びようとするのか
人は人として正しく生き延びることが出来るのだろうか
ゾンビよりも天災がより恐ろしく現実にそこまで迫っているのではないだろうか
ただただ怖い
「集団の怖さ」という、人類にとっての根源的な怖さを低予算で描ききった恐るべき傑作
最近のゾンビは全力疾走する。
未見だが作品によっては知性や理性があったりもするらしい。それって屍なのか?と思ってしまう。
もちろん常に新しいことにチャレンジしていくというのは娯楽映画に必要なことだと思うが、今一度初心を思い出してゾンビの本分に立ち返ってみることも大切なのではないだろうか。
ゾンビの本分とは何か?
それは「集団の怖さ」である。
決して一体一体の能力の高さではない。
自分は『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』を今回初めて観たのだが、改めてその思いを強くした。
ジョージ・A・ロメロのゾンビ3部作(話が繋がっているわけではない)と世に言われている作品群の第一作であり、ゾンビという存在を全世界に知らしめた伝説の一本である。
自分はモンスター映画の大ファンなのだが、この世ならぬ異形のモンスターたちが大好きなので、ゾンビという外見が普通の人間すぎるモンスターにはあんまり食指が動かなかったりする。『バタリアン』のゾンビなんかはけっこう異形のモンスターだったけど(笑)。
そんなわけで『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』も長らくスルーしていたのだが、観てみたらやっぱりとんでもなく凄い、恐るべき傑作だった。
原因がわからないまま死者たちが次々と甦り人間を襲いはじめる。
ゾンビ(この映画ではまだゾンビではなくグールと呼ばれている)の群れに囲まれた男女数名が一件の家に立てこもりなんとか生き延びようとする。
ただそれだけのストーリーの低予算映画であり、今のCGゾンビを見慣れている観客の目からするとゾンビもちょっと薄汚れた普通の人がヨロヨロ動いているだけなので拍子抜けかもしれない。
だが、これが地味に怖い。
自分のそばをヨロヨロ歩いているちょっとアブなそうな人がいきなり飛びかかってきたら怖い。
そういう日常生活の延長線上にあるような地味でイヤ〜な怖さがこの映画にはある。
さらに、そこにゾンビが集団で襲いかかってくるという怖さが加わる。
もし自分の家が、話の通じないわけのわからない集団に取り囲まれたらどれだけ怖いか。
人間も一人一人はちゃんと知性があるのに集団でパニックになると知性ゼロで暴走したりするものだが、ゾンビも一体や二体ぐらいならどうにか対処できるけれど、四方八方からワラワラと集まってくると手に負えなくなるのだ。
人類は原始時代から集団生活を営んできたが、その集団生活の中で人類の脳に刻み込まれることになった根源的な恐怖が大きく分けて三つあると自分は考えている。
その三つとは「自分の所属する集団が仲間割れを起こして崩壊する恐怖」「自分の所属する集団から仲間外れにされてはじき出される恐怖」「よその集団に襲われて自分の所属する集団が滅びる恐怖」である。
この三つは食料を手に入れられなくなって死ぬことと結びついてるからだ。
そして、『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』はこの三つの根源的な恐怖をすべてを巧妙に描いている。
一軒家に立てこもった男女たちは小さいながらも集団を形成しているが、お互いに意見の相違があり、いつ仲間割れを起こすかわからない。
ゾンビと戦って避難所に向かうという強硬派、地下室で助けを待とうという穏健派、自分の意見を持たず振り回される者、それぞれが疑心暗鬼になり自分が孤立するかもしれないという恐怖心を抱いている。
一方で家の外ではゾンビ達がどんどん数を増やして中に押し入ろうとしてくる。
人間達の集団は仲間割れの危機を乗り越えて、ゾンビの集団に立ち向かうことができるのか。
ジョージ・A・ロメロは「外側にいる敵の集団も怖いが、内側にいる仲間の集団も油断できない」という、集団生活を営む動物である人間が抱える悲しい宿命をゾンビ映画という形で見事に描いてみせたのである。
衝撃的なラストには、人間集団が犯す愚行や暴挙といったものに対するジョージ・A・ロメロの冷ややかな眼差しがある。
「孤立する人間の集団と、それを取り囲むゾンビ(あるいはモンスター)の群れ」というシチュエーションは、この後も繰り返しホラー映画の中で描かれることになるが、この映画はその原点にして終着点といっていいくらいの完成度を誇っている。
この映画はアメリカ国立フィルム登録簿に永久保存されているが、それも納得である。
この映画はホラー映画という枠組みを超えて、全世界の大衆文化に絶大な影響を与えた作品であり、世界の文化史にその名が刻まれて然るべきマスターピースなのである。
いまや現代アート
兄と墓参りに訪れたバーバラが、夢遊病者のような男に襲われ、兄は死んでしまう。彼女は近くの民家に逃げ込み、そこにやってきたベンとともに立てこもる。その場にあったラジオによると、一帯で夢遊病者のような集団が人々を襲っているという。民家の周りにも、次々やってきて。
特にゾンビ好きではないけど、古典と言うことで観賞。なんとMoMAにも認められ、いまや現代アート扱い。60年代の作品で、モノクロ、劇中ゾンビという表現は無く、多くの死体もあまり汚くない、ということが意外でした。そして、ベンの皮肉な結末。
初体験のゾンビ映画は「サンゲリア」怖かった。確か「復活の日」と同時上映という、田舎あるあるの変な組み合わせ。
ちゃんと怖い初めのゾンビ
言わずとしれたゾンビ映画の始祖であります。「走るゾンビ」「巨大なゾンビ」「踊るゾンビ」…まぁいろんなゾンビを観てきて、ゾンビ映画史に興味を持ち本作にたどり着いたわけです。
その意外性に富んだ内容に驚かされました。てっきりゾンビ中心の映画かと思いきや、極限状態に追い込まれた人間達の醜い争いが描かれていました。結構長い尺使って。そしてこれが面白い!誰かを応援しようとかいう気になれないくらい、お互いに足を引っ張り合ってウダウダあーだこーだ言い争います。どうしようもなく役に立たない虚無姉さんが一番マトモなんじゃないかと思う始末。人間って面白いですね。
もう一つ驚いたのが地下室!今ではおなじみのゾンビ映画あるあるの一つだと思うのですが、地下室の存在はやはり魅力的。そこで行われるゾンビとの凄惨な殺し合い…最高じゃないですか。後のゾンビ映画に影響を与えたのも頷けます。
中盤までは人間同士の争いがメイン、後半はいよいよゾンビとの戦いとなるわけですが、その最中でも諍いが絶えません。「いい加減仲良くなさい!」と思って観ていると、状況は最悪な方向へ…。後味の悪いエンディングは意外でした。
グロ描写も少し有り。当時としてはかなりショッキングな映像だったのでは?BGMも気持ち悪さに拍車をかけてくれます。
ゾンビのジャンル的には「ウロウロゾンビ」といったところでしょうか?こう書くと全然怖くなさそう(笑)ですが、終盤はきっちり怖がらせてくれます。この作品で既にゾンビ映画たるやいかなるものかを確立させていたのは凄いです。
怖い!上手い!ゾンビ映画の金字塔!!
怖い映画は苦手、、だが食わず嫌いはよくないと思い、意を決して初鑑賞。
以下馬鹿っぽい感想。
思ったよりスプラッターシーンが少なくて良かった。
とはいえ腑食われるシーンはきついし、ラストで群れが家に侵入された時の絶望感よ。
サスペンス?として観ると無駄がない、完成された映画!
流石ゾンビ映画の金字塔!これが68年の映画というのが驚き。恐れ入りました。
▽演出
ゾンビの特徴!
ゆっくり歩く、人肉を食う、頭と炎が弱点、噛まれるとゾンビになる、というゾンビのステレオタイプの特徴が出揃っている!
家の中に立て篭もり、ドア窓を板で塞ぐ、というお作法も確立。
▽脚本
前半は物語がどう進むか分からなかったが、
中盤にテレビ中継を見た後、
車で脱出するか(ベン。デュアン・ジョーンズ派)?地下室に立て篭もるか(ハリー。カール・ハードマン派)?という選択軸が明確に打ち出される。
登場人物のドラマが見応えがあった。
主役は実質ベンで、序盤の八面六臂の活躍のため一見彼の主張(脱出案)が正しいように思ってしまうが、結果的にハリーの言うように、地下室引き篭もりで助かってしまう、というのはとても皮肉が効いている!
ハリーは嫌な奴だが、冷静に聞くと、彼の主張もあながち間違ってない(むしろベンより冷静)。
クライマックスで、ベンがハリーを殺し、結果的に彼だけ生き残る、、、なんて都合のいい展開があるわけでなく、ラストで保安官達に殺されてしまうのも話の畳み方として上手い。
ゾンビ誕生の歴史的作品にして原点!
本作は、ジョン・A・ルッソの原作をジョージ・A・ロメロ監督により映画化されたのですが、まさにゾンビ映画の原点となった、歴史的作品となりました。1968年に作られた作品ですが、まさにこの時代に死体が歩く、そして人を食べるなんてことは、誰もが想像すらしていなかった時代ですから、タブーを打ち破った作品でもあります。
現在では、ゾンビ映画なんて当たり前で量産されている状況ですが、その生みの親がジョージ・A・ロメロ監督。歴史的作品は、マスターフィルムがニューヨーク近代美術館に永久保存されていることでも有名です。
さて本作ですが、いわゆるゾンビの原点となった作品なのですが、『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』→『ゾンビ』→『死霊のえじき』で、のゾンビ3部作といわれています。(この後にもゾンビ映画作られてはいます)邦題では分からないのですが、原題だと『Night of the Living Dead』→『Dawn of the Dead』→『Day of the Dead』となっており、ゾンビ映画=of the Dead(オブ・ザ・デッド)も、ここから来ています。
今見ると、「ゾンビ怖くねぇ~」ってのが第一感想です。
それもそのはず、怖い映画なんてほとんど無かったこの時代、低予算で出した結論は、人間の顔に白塗りでゾンビの出来上がりです!でも、低予算でも特殊メイク使わなくても、"伝説"を残せるんです!
また、すばらしいところは、ゾンビ映画ではありますが、ゾンビそっちのけでいがみ合う人間描写です。人間が7名ゾンビに囲まれた家に取り残され、地下室で待機VS地上待機、外に出て逃げるVS家で助けを待つ、などの意見の対立ばかりで協力心全くなし。そして、バービー人形みたいな、おねーさんのやる気のなさったらありゃしない…。
ロメロ御大のゾンビ映画は、一貫してゾンビはおまけで醜い人間の姿を描いていますので、他のゾンビ映画とは一線を画しているのです。
本作で、もう一つ忘れてはならないのが音響効果です。低予算でも、音響効果を使って十分に怖さを出しており、最初の方は、無声映画かとも思えるくらいですが、要所要所で発生する音が恐怖を出してくれます。この時代ならではの技術ですね。
ラストもスッキリさせてくれない!地獄の夜を生き残った黒人男性。助けを求めて窓に近づいた瞬間に眉間に突き刺さる銃弾…。そう、ゾンビと間違われ射殺されてしまうのでした。
死者が蘇り生者の肉を喰うというゾンビの定義を作り、後世に、多くのゾンビ映画を産む作品でした。
ゾンビ伝説ここにあり!
偉大なるジョージ・A・ロメロ監督‼️
偉大なるジョージ・A・ロメロ監督‼️あなたはゾンビとは何たるかを教えてくれました‼️生者の肉を喰らうことを教えてくれました‼️動作がスローなことも教えてくれました‼️脳を破壊したら倒せることも教えてくれました‼️ゾンビに噛まれた者もゾンビになることを教えてくれました‼️おかげでよくも悪くもたくさんの後輩たちがその恩恵を受けて様々なゾンビ映画を作りました‼️でもどの作品もあなたの作品には遠く及びません‼️孤立した一軒家に立てこもる人々、外から忍び寄るゾンビの群れ・・・これだけの設定で不安感と緊張感を全編にみなぎらせるテンションもスゴいです‼️最近のホラー映画にありがちな馬鹿な若者たちがキャッキャとはしゃぐ描写がないのも素晴らしいです‼️モノクロで撮影されたドキュメンタリータッチにもシビれます‼️さりけなく物語に人種差別や放射能汚染といったテーマが含まれているのも深いです‼️そして救いようのないラストシーンにもホント震撼しました‼️このような素晴らしい作品をデビュー作でモノにしたあなたの監督としての手腕に脱帽です‼️今でも大人気の ''モダンホラー" というジャンルは、あなたのおかげで映画界に定着しました‼️本当にありがとうございました‼️
ゾンビ映画の始祖にして最終兵器! と映画『ミスト』の類似性について考えてみる。
はるばる本厚木まで、新宿で見逃してしまった『ジャバーウォッキー』を観に来て、映画が終わったのでさて帰ろうとしたら、15分後に今度は『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』が始まるらしい。
なんか、これは観て帰らないとダメなんじゃないか?
という謎の義務感に駆られて、つい立て続けに観てしまった。
おおお、やっぱり素晴らしいねえ!! マスターピース!!
僕がこの映画を観るのは、おそらく大学生以来だ。
あのころまだDVDはなく、レンタルヴィデオでの視聴だった。
あれに比べたら、今回の4Kリストア版は衝撃的なまでに画質が良くなっている。
アメリカでも、レイトショーで人気が広がっていったと聞いていたから、あのぼやっとした貧乏くさい自主映画みたいな劣悪なモノクロ映像が、いかにもこの映画らしいと決め込んでいたが、どうやらこちらの勝手な思い込みだったらしい。
なんだか、ものすごくちゃんとした映画に「格上げ」になった感じだ。
記憶していた以上に演出は堅固で、カメラワークも堂に入っている。
演技も、女性陣とゾンビ軍団はさすがに素人くさいが、男性陣はけっして悪くない。
特殊効果はチャチいといえばチャチいが、モノクロームと相俟って生々しい。
ああ、全然B級なんかじゃない。れっきとした「古典」だ、これは。
この映画のテーマが、公民権運動と密接な関係があるのではないかという批評自体は、誰しも一度は聞いたことがあるはずだ。
ロメロ本人はそこまで政治的な映画を撮ったつもりはなかったとたびたび言及しているが、たとえそうであったとしても、「その後」のフィルモグラフィを考えれば、彼がある種「政治的な表現者」でありつづけたことは疑い得ない。
ロメロの映画を観れば、彼が社会正義を奉じ、公権力を信用せず、コミューン的な理想に夢を抱いていた人物であることは、そこかしこから、ひしひしと伝わってくる。とくに、『ゾンビ』におけるあのショッピングモールのユートピア描写や、『ナイトライダーズ』のような知られざるコミューン映画の傑作に触れると、切実にそう思う。
ホラー映画は、ロメロにとって、間違いなく社会批評の一手段でもあった。
同時に、彼は「ホラー」であることに、誇りと信念をもって、真正面から取り組んでもいた。
彼は、ホラーを社会批評の「言い訳」「道具」「背景」として、貶めなかった。
全身全霊で、怖い映画を撮ろうとした。
ホラーというジャンルへの「愛」を喪わなかった。
彼はジャンルを裏切らなかった。
真の意味で、「ホラー愛好者」であることと、「社会派」であることを両立し得たホラー監督を、僕はロメロとクローネンバーグくらいしか知らない。
人種問題(公民権運動)への意識の有無に加えて、よく批評家たちによって取りざたされるのは、モノクロームで撮られた本作のニュース・フィルム風映像が、当時の若い観客にベトナム戦争を強烈に想起させたという点だ。
僕自身はそのあたりについては全く詳しくないが、籠城戦&対ゲリラ戦、血みどろの描写、人でありながら人ならぬ敵、闇にまぎれて襲ってくる「モブ」としての集団(The mob has many heads but no brains.)、近代兵器による一斉掃討が可能であるが、完全な掃滅は不可能な点など、たしかに本作の恐怖は、(製作者が意図したしないにかかわらず)異郷の戦地で体験したベトコンの恐怖と大いに重なり合うものだったかもしれない。
ただ、本作のキモとなるのはやはり、「モダン・ゾンビ」の発明という偉業に他ならない。
これまでは「吸血鬼」という形で描かれてきた「パンデミック」の恐怖を、より「実体のあるモンスター」「即物的でリアルな怪物」として可視化し、表現し得たからこそ、『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』はクラシックたり得たのだし、その後のゾンビ映画の隆盛とジャンル化という現象を引き起こし得たわけだ。
本作の脚本家ジョン・A・ルッソが、リチャード・マシスン原作、ヴィンセント・プライス主演のホラー映画『地球最後の男』(64)(のちに『アイ・アム・レジェンド』としてもリメイク)を発想の霊感源としていたことはよく知られている事実だ。
そもそも『地球最後の男』自体が、今の視点から振り返れば広義のゾンビ映画に属する内容の作品だが、ルッソとロメロは、ここで描かれた「吸血鬼」に「カニバリズム」と「無知性」という属性を掛け合わせてみせた。
この「吸血鬼」×「カニバリズム」という独創的なカップリングの妙こそが、本作における最大の「発見」であることを、あらためて強調しておきたい。
もともと「吸血鬼」には、どこかロマンティックかつ貴族的で崇高なイメージがある(アン・ライスの『ヴァンパイア・レスタト』とか、萩尾望都の『ポーの一族』とか)。だから「襲われて眷属にされる」恐怖というのは、必ずしも真の恐怖とはいいがたい部分がある。彼らの眷属になれれば、ある種の「上位種」としての権力と権能を手に入れることができるからだ。吸血鬼の恐怖は、エロティックな憧憬と裏表の存在だ。
ところが、ロメロの創造した「グール」(ゾンビ)は違う。
人肉喰らいで無知性。しかも身体はボロボロのまま。……うーん、およそ、最悪だ(笑)。
明らかにゾンビは、人類の劣化型だ。徹底した即物化といってもいい。
人間の属性のうち、他者に対する攻撃性「だけ」が残存していて、あとは人としての尊厳のすべてがえげつなく剥奪されている。
なにより怖いのは、「無個性」ということだ。すなわち、ゾンビに噛まれて死んでしまったら、たとえ復活して歩き回っていても、彼らはただの「群れ」であり、「個」ではありえない。
「個」としてのアイデンティティを剥奪されて、なお「生なき生」を生きることを強いられる恐怖。
ああはなりたくない。惨めになりたくない。群れに飲み込まれたくない。
「吸血鬼」とちがって、「ゾンビ」には、憧れる要素が一切ない。
で、決め手が、「人が人を食らう」という人類最大の禁忌(タブー)。
こうしてロメロたちは、「人肉食」という要素を「吸血鬼」もののフォーマットに導入することで、同じ「伝染」「パンデミック」の恐怖を扱いながらも、「吸血鬼」のもつ貴族的な「特権性」を剥奪し、怪異を「大衆化」し、「即物化」することに成功したのだ。
のちに「ゾンビ映画」が一大ジャンル化して時代すら飲み込んでいったのも、まさにこの「怪異の大衆化」があったからだといっていいだろう。
で、改めて『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』を観て。
やはり、良く出来た映画だ。
単にホラーとしても十全の出来だし、閉鎖状況下での心理劇としても濃密な仕上がり。
襲撃、食人、伝染、身内のゾンビ化。
試される科学的説明。人間につるべ打ちされるゾンビ。
「ゾンビ映画」としての特徴と要件が、この第一作でほぼ「すべて」出揃っているのもすごい。
しょうじき、さんざん語り尽くされている映画であり、今さら僕が付け加えられることはあまりないのだが、一点、今回改めて観直して気づいたことを記しておく。
それは、フランク・ダラボン監督って、スティーヴン・キングの中編『ミスト』(80)を映画化するさい、間違いなくこの『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』を祖型にしたんだろうなってこと。
映画版の『ミスト』(07)は、びっくりするくらい『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』とよく似ている。
籠城戦。得体の知れない外敵。わからない対応策。
「立てこもるか」「脱出するか」で対立する生存者たち。
「家族」の存在がそれぞれの決断を歪ませる流れ。
何より、「ヒーロー」像の扱いがそっくりだ。
明らかに人を信頼させ牽引する「リーダー」タイプで、「静」か「動」かでいえば、間違いなく「動」のタイプ。常に動きながら、即断即決で随時状況に適応していこうとする。
映画版『ミスト』の主人公も、本作の主人公も、防御に頼って逃げ道を無くすことのデメリットを強調し、最終的には隠れ処から「脱出する」ことを決意し、周囲を説得し、煽動する。
集団のなかで彼の主張は一部の共感を集め、彼と行動を共にするフォロワーを発生させる。
両作が真に似ているのは、「そこから後」の展開である。
(ここから後は『ミスト』も含めて、完全なネタバレになるので、未見の方はお気を付けください)
結果論でいえば、一聴正しそうに思える両主人公の主張は、じつは「間違っている」のだ。
「もう少し待っていれば、破壊兵器を携えて怪異を討伐する力をもった公的な救援部隊が到着した。だから、勝手な行動をとらず、あとしばらく隠れ処(とくに安全な地下室)にこもって我慢していれば、みんな助かっていた」。実はこちらが、サバイバルとしては物語の「正解」なのだ。
両作とも、主人公に「唆されて」一緒に脱出したメンバーは、みんな「死んでしまう」。
『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』の場合は、残っていたメンバーも、主人公が脱出を企てた際に防御をゆるめた箇所をゾンビ軍団に突破されて、結局全滅してしまう。
そして、仲間を全員死なせてしまってから、「対ゾンビ騎兵隊」が登場し、彼らによって周辺のグールはすべて掃討されたことがわかる。で、主人公はその騎兵隊にグールの残存個体として、ゴミのように撃ち殺されるのである。
「正しく戦う」ことが、求めている勝利をもたらすとは限らない。
「怯えて何もしない」ことのほうが、正しいことだってあり得る。
両作品がもたらす「恐怖」の根幹には、この「まっとうな価値観が壊され、反転させられる」恐怖がある。
僕は、『ミスト』を封切りで観たとき、あえて原作から結末を大幅に変えていることに驚き、これって「主人公補正」でなんでも成功に導いちゃう「マッチョな白人アメリカン・ヒーロー」への強烈なアンチテーゼなんじゃないのかな、と思ったのだった。すなわち、『ダークナイト』(08)あたりと軌を一にする、ヒーローの無謬性に対する疑義の提起だ、と考えたわけだ。
だが、こうやって『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』を観てしまうと、単純に、この物語の展開をそのままキングの原作に持ち込んだら、『ミスト』映画版になりそうだな、と。
しかも、祖型となっている『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』の主人公は、マッチョ白人どころか、黒人青年である。
要するに、ストレートな『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』オマージュ(もしくは、キングによる原作中編『ミスト』の淵源がこの映画だということに気づいたダラボン監督の意思表明)ととらえたほうがいいのではないか。
うーん。ちょっと深読みしすぎていたのかも、俺。
とはいえ、「一見正しく思える行動派のヒーロー」が出てきて、観客も心情的にみんな、彼の味方につくのだけれど、彼が下す「究極の決断」が「作り手(神)による庇護」を受けることができずに、周囲まで巻き込んで破滅的なラストを引き起こす、という「後味の悪さ」と「正義の不確定性」が、両作に共通する「怖さ」であることは、疑いようのない事実だ。
真の恐怖に覆われた世界では、
もはやヒーローはヒーローとして生きることを許されないのだ。
本作の成功によって市民権を得た「ゾンビ」は、やがて21世紀の小説界、映画界、ドラマ界を席巻していくことになる。いかなロメロとて、そんな未来はさすがに想像だにしていなかっただろう。
月並な言い方だが、すべてはここから始まった。
そして、この映画には、今も観る価値が十分にある。
ゾンビ映画の全てが、最初からここにはつまっているからだ。
ゾンビ映画の始祖にして、最終兵器。
これは、そういう映画だ。
そんなんで蘇る能?
1968年公開。蘇る死体、噛みつかれることで感染、理性の喪失、緩い動作、不死身、頭部破壊でのみ死ぬ、人肉を喰らう、等々。現在のゾンビ映画の基本法則を作った映画として歴史に残る映画。って言うことで、半分は勉強のつもり、半分は時間つぶしで鑑賞しました。
基本、怖くないです。音楽で盛り上げて、音楽でビビらす、昔の映画です。特撮もへったくれもありません。パリピの死亡フラグも無し。演出のもたつきもあり、イライラしてしまうのは、昨今の現代技術を駆使したゾンビものを見慣れた現代人としては、しゃーないでしょ?
にしてもです。
取りあえずは、死体が蘇るカラクリについての説明がある点。女子供も見逃しませんし、最後の最後で、あーなってしまう情け容赦無さ。などなど。シナリオ的には、結構面白かったし、こんなところも、現代ゾンビもののひな形になってるんだなぁ、なんて感じました。
「民間警備隊」がゾンビ駆除です。州軍は名前だけ登場するも、連邦軍は出て来ません。1968年と言う微妙な時期だけに、そこは配慮したんだろうなぁ、って事で。
面白かった。意外に。
【”熱帯夜の夜はホラー映画だね!”とゾンビ映画の礎になった今作を観たら、ドキュメンタリータッチで製作された、人種差別や、放射能汚染を暗喩した、皮肉を塗した映画だった。】
■父の墓参りにやってきたバーバラと兄のジョニーは、突然蘇った死体に襲われる。
ジョニーを殺され、バーバラは命からがら近くの民家に逃げ込む。
そこに黒人青年のベンが飛び込んでくる。
ベンは家のドアと窓を補強し、2人は助けがくるのを待つことにするが…。
◆感想<Caution! 内容に触れています。>
・民家には、実は白人カップルのトムとジュディ。そして、白人家族のクーパー一家も地下室に隠れていた。だが、彼らはギリギリまで黒人のベンとバーバラを助けずに地下室に居る。
ー 民家を取り仕切っているのは、黒人のベンである。白人の人々は、トムとジュディにように、ベンの指示に従うか、クーパーの様に保身に走るか、茫然と成り行きを見ているバーバラである。-
・民家の周りを取り囲む”リビング・デッド”達。漸く、トムとジュディはベンと共に近くに止めてあったピックアップトラックに給油し、脱出を図るが・・。
■ハリー・クーパーは、そんな状況下でもベン達に協力せず、地下室に立てこもる。だが、娘のカレンは”リビング・デッド”達に噛まれており・・。
ー 非常に、シニカルな展開である。
更に言えば、ラジオから流れるアメリカ東部で起こっている状況を刻々と流すドキュメンタリータッチの手法が、効果的である。-
<ラスト、夜が明け人々が”リビング・デッド”の残党狩りに出るシーンも印象的である。一人生き残った黒人のベンを、”リビング・デッド”とみなし、撃ち殺す白人中年男性。
今作後、ゾンビ映画が世界中に拡散して行った事は、周知の事実であるが、礎となった今作は、人種差別、放射能汚染など、様々な暗喩を含んだ作品であった。>
これが原点
頭から尻尾まで詰まった恐怖、しっかり練られたストーリー。
全38件中、1~20件目を表示