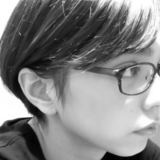天国と地獄のレビュー・感想・評価
全18件を表示
映画作りの教本だが完成された犯罪映画
リバイバル上映で二十代の時に見た映画で、その後私の黒澤映画Top1から落ちる事なし。晩年の数作と戦前の初期二作品以外は全て見ています。娯楽性と映画芸術の融合した作品である事がTopの理由。
全体の構造(製靴会社の重役と苦学生)、ストーリー前半と後半の舞台転換。カメラワーク、人物の配置の意図。捜査に関する様々な描写。犯罪捜査についてはその後の映画やドラマの構成に影響を与えたそうです。
勉強になる所が満載で、見なければならないポイントは何十何百とあります。
ゾクゾク1 権藤邸でみんなで這いつくばるシーン
ゾクゾク2現金の受け渡しシーン
ゾクゾク3権藤邸を見上げるドブ川近くでの捜査員と犯人
ゾクゾク4多国籍なカオスな飲食店での薬の受け渡し
ゾクゾク5麻薬常習女に狙いを定めてサングラスきらり
ゾクゾク6共犯の家に入る犯人の頭がニョキ。
いくつかのシーンはスピルバーグやコッポラに影響を与えましたね。
あ、権藤邸での子供二人の遊びのシーンを忘れた。その後の転換を先取りしたシーンです。
オシャレなシーンが沢山あるのです。映画の宝物館です。
若き山崎努さんの存在感が印象的ですが脇役の使い方が贅沢ですよ。黒澤監督の頂点の時期の作品です。
なんちゅう撮り方、なんちゅうアイディアの連続。
三船さんの存在感は当然素晴らしいです。重役役がセクシー。
ソコから見上げたホシ
體の上は 頭に被る帽子
體の下は 足に履く靴
帽子と靴は 違っている
7センチの鞄ふたつ
二種類の仕掛けふたつ
流れゆく特急と
沈む夕日と
ずっと聳える富士山
いつも眺めていたら欲しくなる
羨ましいは 恨めしい
上には行けないから
自分のところまで
下に落としてみたくて
足を引っ張ってみた
誘拐? 捜査
「まだパクるな 軽い罪だから 泳がせよう」
まさか そんなこと
言うかい? そうさ
それが黒澤明監督の 天国と地獄
最後に 呼んでみて 明らかにわかった
あなたと私は 違っていた
シャッターが遮る
もうダメだ 失敗だぁ
桃色のけむりが 空を流れる...
舞台劇の重厚さと誘拐犯追跡のサスペンス映画が合体した黒澤現代劇の傑作
誘拐事件に巻き込まれたある会社重役の良心と野心の葛藤から犯人逮捕までのサスペンスを終始重々しく緊迫感のある演出で創作された黒澤現代劇の傑作。脚本はアメリカの推理小説家エド・マクベインの『87分署シリーズ』の第10作『キングの身代金』(1959年)を原案とし、身代金3000万円(現在の価値に換算すると約4億円)と引き換えに誘拐された少年を救出する前半の骨子になっていて、後半の犯人を泳がせ共犯者殺人を立証する捜査はオリジナルの創作と言います。この2部構成の表現法と映画論法の対比にこそ、この作品の面白さと不確実性が絶妙に絡んで独特な社会派映画の特徴を強烈に印象付けることになりました。
前半の主人公は製靴会社ナショナル・シューズの工場担当常務の権藤金吾で、自分の持ち株比率28%に抵当や借金で工面した5000万円(現在の価値で約7億円)を投資しその後47%まで引き上げ、次期株主総会で会社乗っ取りを計る野望の男。現社長と馬場専務ら3人の重役を合わせた株比率の46%とギリギリの社内攻防戦に挑む、その大事な決断の時に息子純を誘拐したと犯人から電話をもらう。このお金と数の力が支配する資本主義の分かり易い見取り図に裂け目を入れるのが、後半の主人公竹内銀次郎という、貧しい家庭で育つも内科医師になろうとして努力したであろうインターンの青年。しかし、そんな彼が何故誘拐犯罪に手を染め、資産家に見えた権藤に膨大な身代金を要求して憎悪を募らせるのか、その真意の全容は分からない。完全犯罪に至るような巧妙な作戦を練る頭脳と、逮捕されれば仕事もそれまでの努力もすべて失うリスクを考慮しない無謀さに矛盾が残ります。時代背景は、戦後の高度成長を象徴する東京オリンピック開催と新幹線開通を翌年に控えた躍動の日本社会。焼け野原の最貧国から18年足らずで急激に経済復興して、富める者と貧しい者との格差が顕著になるのは、ある程度仕方ない。1960年の所得倍増計画から右肩上がりが継続し中流階級が増えた時代の流れを顧みれば、もう少し我慢して仕事に邁進していれば報われていたはずです。仮に竹内を24歳と仮定すると、生まれは1939年の戦前で小学校入学が1945年の終戦の年になります。戦前の教育を全て否定され、アメリカから与えられた民主主義の洗脳を受けた最初の年代です。日米安保条約で政治・社会が混乱した1960年には成人になり、社会に対して意見と批判を持つ自立に目覚める年頃でした。自由と平等を標榜する民主主義教育の理想を学びながら、現実の貧困に一個人でどう対処すべきなのか。しかも凶悪犯罪ほど、その動機の本当の理由を他人が理解することは難しい。これは黒澤監督始め脚本家の人たちアヴァンゲール(戦前派)の大人世代が共通して抱いたアプレゲール(戦後派)世代の若者に対する、理解不能の世代断絶を意味しているとみても興味深いかも知れません。
丘の上に建つ権藤金吾の瀟洒な邸宅の応接間を舞台にした、身代金を準備するまでの黒澤演出は、ミステリー小説を戯曲化した演劇そのものでした。屋外が映されるのは、権藤に追い払われた重役3人が車で去るショットに西部劇扮装遊びに夢中の子供2人が現れるところと、刑事が百貨店の店員に扮装して権藤宅に忍び込むショットだけで、サスペンスフルな密室劇になっています。見知らぬ男からの電話で権藤の息子純が誘拐された衝撃と身代金3000万円の要求に戦慄が走るも、その居間に純が現れて一端悪戯かと安堵する意外な展開から緊張感が始まります。ここで運転手青木の息子進一が居ないことに気付く大人たちの動揺から、子供たちが保安官の服を交換していたことで犯人が人質を間違えて誘拐したこの事件特有の複雑さがあります。自分の子供が事件に巻き込まれた時は警察に連絡するのを躊躇った権藤が、他人の子供と分かった途端に警察へ通報する人間性、そこには3000万円を手放したくない、否手放せない権藤の追い詰められた状況が支配している。演出で印象的なのは、大阪のホテルへ秘書河西に手付金を持たせ交渉をまとめる電話の前に鳴る置き時計の時報と、妻怜子が呟く“ねえ、大丈夫?私 何だか怖いわ”の台詞です。勿論これは5000万の手付金と残り1億円のお金で会社を乗っ取ろうとする夫権藤金吾を心配して掛ける言葉ですが、同時にこの時に進一少年が拉致されたことを暗示する演劇的な表現です。映画本来の表現ならば、隠れて待ちわびる純少年のカット、進一少年を連れ込み走り去る車のカットなどでカットバックするものです。しかし、これではその後の居間で展開する大人たちの動揺から安堵、そして衝撃の心理表現や、身代金を渡す渡さないの権藤の心の迷いまで重厚に描くことが幾分削がれるでしょう。3000万円の身代金をどうするか逡巡する権藤を中心に、子供の命最優先の妻怜子、会社乗っ取りを他の重役に密告して己の出世しか考えていない秘書河西、息子の生存をただひたすら願う運転手青木、そして誘拐事件の犯人に対して怒り、罪の報いの軽さに憤る戸倉警部ら冷静沈着な刑事が、入れ替わり立ち代わり居間を行き来します。各自の台詞が各登場人物の動きやポジションを決め、この意志と立場を持った言葉で変化する人間模様の深さと面白さ。黒澤演出の考え尽くされた画面構成と人物配置、それを自然に写す斎藤孝雄と中井朝一のカメラワーク、それはシネマスコープとほぼ同じ東宝スコープのワイドスクリーンを生かした演劇映画の完成度を誇ります。敢えて5000万円の小切手のアップ、鞄に匂いと色の細工を施す権藤の手先の動きを映さない。演劇と映画が融合した演出で光るのは、翌朝カーテンを閉め切ったままの不自然さを指摘され遮光カーテンまで全開にするシーンです。戸倉、田口、中尾の刑事がテーブルの下に身を隠すショットがいい。
続く特急第二こだま号に乗って犯人の連絡を待つシーンからは、映画らしいスリリングな黒澤演出が冴えわたります。中尾刑事が列車内を巡回して進一少年が見当たらないことをメモで渡す、そのアップショット。前日から徹夜で紙幣の番号を写して疲労困憊の荒井刑事がうとうとするところで車内放送が掛かる演出の切れ味。鉄橋を過ぎたら洗面所の窓枠の7センチの隙間から3000万円が入った鞄2個を投げ落とせとの犯人からの指示。ここで警察が先頭車両と最後尾の窓から8ミリカメラで共犯者を記録するシーンの映像の迫真性が凄い。流れる映像から見える共犯者と進一少年、鉄橋を挟んで鞄の落とし場所に待機するもう一人の共犯者。列車1編成をチャーターして撮影に挑んだ緊張感がこの短いシークエンスに鮮やかに生かされ、映画でしか表現できないモンタージュの素晴らしさでした。
進一少年が無事解放されて犯人追跡の捜査がメインになる後半では、主人公権藤金吾の会社内の境遇は最小限に抑えられ、抵当に入っていた邸宅が競売に掛けられ全財産を処分する失意のどん底まで追い詰められていきます。進一少年が描いた絵と録音した犯人の電話音声記録からアジトと思われる場所で微かに聴こえる電車の音の特徴から、捜査が進展するシチュエーションがいい。鉄道会社で聞き込み江ノ電と分かるものの、オタクっぽい職員の止まらない解説から荒井刑事が逃げるように立ち去るシーンが可笑しい。そして、多額のお金の犠牲を払った権藤の無念と憤怒に少しでも応えようと、進一を連れてアジトの場所を探す青木の居た堪れない心理も分かります。田口刑事と荒井刑事が追い掛け、偶然青木親子と出会うところの映画的な映像処理の巧さ。その前に車のリアガラスから景色を眺め記憶を思い起こす進一少年のシーンもいい。お父さんと声を上げ、僕あそこでおしっこしたよ、の台詞が可笑しい。そこから徐々に江の島が島に見えない角度の高台に辿り着く細かさ。しかし、そこでヘロイン中毒で死んでいる共犯者カップルが見つかる意外な展開から、映画は麻薬中毒に陥った人間の闇世界に入っていきます。ここで興味深いのは、警察が共犯者の死を報道しないようマスコミへ協力依頼することでした。更に犯人に危機感を与えるために番号を記録した1000円紙幣が見つかったとの嘘の報道を流すことも加えます。鞄の写真も記事にあり、慌てふためく犯人竹内の動揺振り。ここで注目に値する、寄り過ぎたカメラワークの演出がありました。前半には一切なかったアップショットを後半でも必要最小限に抑えたカメラワークを貫いてきて、犯人竹内が札束を鞄から風呂敷に移し、鞄を段ボールに入れてひもで縛る緊迫のシーンを、意図してありきたりな絵の構図に収めていないのです。これは説明ショットではなく、余裕が無くなった竹内の感情の混乱を表現する映画的な表現です。ここで思わず唸るくらい、見事な演出と撮影でした。鞄が病院の焼却炉で燃やされ、モノクロ映像に牡丹色の煙が引き立つ権藤邸から街を見下ろす眺望ショット。ここでは秘書河西が恩着せがましく権藤に重役のポストの話を持ってくるも、男のプライドから権藤が相手にしない場面がいい。進一が描いた犯人の絵を観ているときに、純少年が煙にいち早く気付くところも巧い。そしてついに権藤邸の近くに住むインターンの竹内銀次郎に行きつく捜査の最終段階にきて、直ぐに逮捕せず江の島のアジトに誘き寄せる作戦の巧妙さ。捕まえた後の刑罰に殺人罪を加えるだけに行うトリックまで、理に適った展開で閉めます。
しかし、この後半で最も素晴らしいのは、犯人竹内を演じた山崎努の演技でした。1960年に映画デビューもこの作品で一躍注目されたのは当然でしょう。三船敏郎始め当時の名立たる男優たちが数多く出演する黒澤映画の中にあって、一際存在感のある演技を見せます。特に最後の拘置所で権藤と面会するシーンの、笑みを見せても淋しく、嘆きを虚勢で誤魔化しているような、死刑の恐怖に慄いていないと言い張るも、何も確実な事は一つもない竹内という犯罪者の曖昧さゆえの怖さ。ただ一つ明らかなのは、彼の根源には憎しみの感情しかなく、その憎悪に支配された地獄を生きていたことだけです。金網を掴み、震える身体を抑えながら言い訳ばかり言い、頭を抱えて発狂する竹内の惨めな姿を山崎が雄弁に演じ切っています。黒澤監督も認めたこの熱演で映画のラストカット、シャッターが下ろされるエンディングも見事でした。
主演三船敏郎、助演仲代達矢の重厚な演技が作品を締め、曲者秘書役の三橋達也も巧い。青木運転手役の佐田豊は適役の好演、刑事役では志村喬に藤田進、土屋嘉男、名古屋章。新聞記者に千秋実、北村和夫、それに37歳頃の大滝秀治がいました。仲代達也と行動を共にする石山健二郎、木村功、加藤武の其々のキャラクターもほど良く絡み、会社重役に伊藤雄之助、田崎潤、中村伸郎と錚々たる男優陣です。紅一点の香川京子は、「悪い奴ほどよく眠る」の役より単調で、もっと物語に加わって貰いたかったと少し心残り。誘拐される進一役は、小津安二郎監督の「お早よう」で次男坊を好演した島津雅彦でした。純役江木俊夫はその後アイドルグループ・フォーリーブスで人気スターに。私の年代ではテレビドラマ「マグマ大使」が懐かしい。
刑事ドラマの真髄を見た!
タイトルはお馴染みですが、内容は、よく知らない黒澤作品の一本です。誘拐事件の映画ってくらいの知識しかありませんでした。
オドロオドロしいテーマソングから始まり、非常に期待値が上がりました。また、音楽に合わせて表示される役者さんの名前に、懐かしい〜、この人も出てる、と一喜一憂でした。
映画を見ている時にも、自分が若い頃から見ていた今は亡き昭和の名優たちの若かりし姿に、興奮しっぱなしで喜ばせてもらいました。
初っ端から三船敏郎さんの登場。今までは時代劇ってイメージが強かったけど、先日見た「悪い奴ほどよく眠る」で、カッコいいスーツ姿を見てたので、本作品では違和感も感じませんでした。
それどころか、自分の子供と間違えて誘拐された運転手の息子のために、全財産投げ売って身代金まで用意する、メチャクチャカッコいいオヤジを魅せてくれました。
ここに、仲代達矢さんを筆頭とする、黒澤作品ではお馴染みの面々が演じる警察陣が加わり、緊迫した雰囲気で展開していきます。
【ネタバレ】
前半は、誘拐犯とのやりとりに、三船さんが自身の野望との間で苦能する様を描いてくれます。会社の乗っ取りを考えていた矢先の事件。ここでこのお金を使うと、計画が破綻するだけでなく、生活すらままならなくなる恐れがある。
それでも、身代金を用意した三船さんが、ホンっとカッコいい。
要所要所にニヤッとするようなお笑いを交えながら、緊迫感を維持する展開に、心底引き込まれました。
身代金の引き渡しも、電車を使った頭脳的な方法で見応え十分です。
後半は、犯人の山﨑努さんも登場し、徐々に追い詰めていく警察の姿が描かれます。
今現在放送されている刑事ドラマの原典がここにあるって感じで、見たことあるような場面が幾つかでてくる。
でも、そこが昭和の風景で、懐かしいっていうか、生々しいっていうか・・・
汗じみのついたシャツを着て、密接した部屋で行われる捜査会議。容疑者を尾行する刑事たちの変装。そして、人々であふれかえる街中、ヤク中や売春婦等、荒ぶれた人々でごった返すドヤ街。
とにかく、ワンシーン、ワンシーンに生きているっていう躍動感を感じる。
いや〜、ホンっと面白かった。
犯人逮捕に向けての警察のやり方も、どうかと思われる部分もあったが、まぁ、悪い奴には容赦なしってのは嫌いじゃないんで、スッキリさせてもらいました。
ラスト、犯人の山﨑さんから呼び出され、三船さんが面会に行って話す場面。何を話すんだと思っていたら、何故恨みを抱いたのかを語り出す。差もない会話の中で、徐々に変わっていく山﨑さんが印象的だった。明確な説明ではなく、見た人それぞれの判断に委ねる終わり方だと思う。恐らく、見た時の気分や状況によって感じ方が変わるんだろうなって気がする。
衝撃のラストに頭抱えた
黒澤明監督の名作をついに鑑賞。圧倒的な緊張感と重厚なドラマに、ただただ引き込まれました。作品はサスペンスと社会的テーマが見事に融合し、見る者に強烈な印象を与えます。
前半は権藤氏の葛藤と決断を描いた密室劇、後半は犯人を追う捜査劇に分かれていますが、どちらのパートも心理描写や人物設定が非常に練り込まれており、重厚な群像劇として見応えがあります。
後半の捜査パートでは刑事たちが犯人の手がかりを追う様子がリアルに描かれ、次の展開が気になって仕方がありません。細部まで計算された捜査の考察や緊張感のある追跡劇は、まさに手に汗握る展開です。
そして、衝撃のラスト!犯人が語る「産まれた時から地獄だった」という言葉。彼の叫びには一体どんな思いが込められていたのでしょうか?権藤氏はその言葉を聞いて何を思ったのか?しかし、最後に映るのは権藤氏の無言の背中のみ。彼の表情は映し出されません。このシーンは観客に多くの問いを投げかけ、深い余韻を残します。非常にショッキングで、忘れがたいクライマックスでした。
単なるサスペンス映画にとどまらない、格差や社会の不平等といった普遍的なテーマを内包した作品。犯人の人生、権藤氏の葛藤、そして「天国」と「地獄」とは…。倫理的な問いと社会的な問いを投げかける本作。現代においてもその衝撃は色褪せません。
タイトルなし
横浜映画であり、湘南映画。
竹内はもう一人の権藤であるというか、紙一重の存在である。ラストシーンはその象徴で、度肝を抜かれる。そこへむかってポンと置かれるタバコの火をつけ交わすシーンが印象的。
天丼100円カツ丼100円安い!
『天国と地獄』と言うが、この映画には天国が登場しただろうか?権藤は会社を追い出され、犯人は結局。どちらも、天国とは言えない。天国があるとすれば、権藤を追い出して、経営を手中に収めた悪徳重役って事になる。
さて、そうなのだろうか。
権藤が『新しく始めた靴屋』なのだろうと思う。権藤が本当の天国を最後は掴んた、と黒澤監督は言いたかったのではないかと思う。
やっぱり、この映画は傑作だと思う。
こう言った『阿片窟』の様な所が、黄金町にあったのかは知らないが、25年くらい前まで、この辺(黄金町駅)は『オランダ、アムステルダムの飾り窓の女』の様な店が軒を連ねていた。入った事はなかったが。日本の様でなかった。川崎の堀之内にもそんな所があった。
黄金町のゴーゴー喫茶のお品書きの看板に天丼100円カツ丼100円安い!阿片窟の宿屋のお休みも100円だった。全く地獄だ。
さて、今では、そんな所なくなったのだろうか?
追伸 この頃世間を騒がせたのは『吉展ちゃん事件』を始めとした誘拐事件だったと記憶する。日暮里の大火とこの事件が妙に記憶に残っている。
不信なことが、 エド・マクベインの原作だから?
映画レビューのクラスで使おうかと思ってみてみた。 黒澤明は大好きなので、これを何度か見ている。 1963年の作品だと改めて背景を考え、どこに焦点を当てて書こうか?
権藤金吾(三船敏郎) の権力に屈しない頼もしさや自分の地位や資産や株を諦めて、お抱え運転手の子供を救おうか葛藤していくところ?人間の善悪を金の価値で決めない行い? それとも、医学生、竹内銀次郎(山崎努) に焦点を当てて、彼の貧困育ちや環境悪や孤独への責任転嫁からくる自業自得。いや、果たして、自業自得なのか、自助だけでは生きられないという人間性?それとも、大金持ちの育ちで、世間知らずの天使の心を持った権藤の奥さん。 それとも、権藤のお抱え運転手で、息子を誘拐された父親、青木の心境と行動?それとも、戸倉警部の操作側や戦後の社会情勢(黄金町(こがねちょう))?竹内を泳がしたことによりまた一人殺させちゃったね。こう言うこと当時の警察側ではどう判断するんだろう?薬中だからいいの?それに権藤さんのために星を泳がせるが、前向きな権藤がこんなこと本当に望むだろうか!それに、こう言う捜査の善悪の判断は?
色々考えているうちに、一番感情移入しやすいのは権藤。彼の心の葛藤はあるが、マスコミのせいもありあまりにも聖人になってしまったので、ちょっと、書きにくい。それに、役員から職工にと初心に戻ってでなおせるこの人物は大物過ぎる。二足三文ではなく、靴の価値の意味、全体重を乗せる靴の重みをよく知っている。個人的にだが私も靴だけは結構高く素材や質や縫製のいいものを履く。全体重を乗せるから。
医学生、竹内銀次郎(山崎努) に焦点を当ててみたい。彼は自分が貧しかったことを、そして、権藤家の暮らしは天国で、自分の夏は暑く、冬は寒いアパートは地獄だと。彼は権藤家が気になるようになって、毎日、望遠鏡で、眺めて、羨望の気持ちが、いじめ(ここでは誘拐犯罪)に発達していったということだ。子供の頃も貧乏であったようだ。ただ、医学を学んでいるようだから、賢かったに違いないし、論理的なことも得意だったようだ。 当時のこだま号、在来線特急のトイレの窓が鞄の厚み7センチだけ開くことや電話があることも調べ上げていた。黄金町の麻薬や青線地帯にも詳しく、ちょっと不良インターンと言ったほうがいいかも。
高度成長の波の下敷きになった竹内家はどんな生活だったのか!知る術もない。そこは焦点じゃないからねえ。高度成長期に生きるたくましい権藤がヒーロー化される時代だったかもね。
竹内は永山則夫の世界だったのかもしれないねえ。
でも、息子をどうやって医科大学に出せたのか。エド・マクベインの原作がそうなっていたから?竹内家が貧しくても子供を大学に行かせたのか?町の有志が援助したのかわからないが、当時としてはこの設定は不自然かもね。それに手に大きな傷があるがなぜが何も分からない?ただ手掛かりの一つ?違和感が残る竹内の背景。最後のシーンで竹内が権藤に会いたがって留置場で面会するシーンだが、精神的に天国と地獄の立場は変わらない。権藤は苦難を乗り越え天国の階段にいる。苦難を乗り越えかたを知っていると行ったほうがいい。竹内は苦難が嫉妬に変わってしまっている。そして、自分が地獄へ落ちていくことに対する恐怖感?傷がついている方の手の震え? 権藤を地獄に落としてほくそ笑みたいと思っていたが自分が死刑になる。
はっきり言って、警察の横暴が現れている。一人の人間をもっと犯罪を犯させるようにする事は倫理的だろうか? 胸糞が悪い映画だ。
4/20/22 追加
映画レビューのクラスで使った。 英語圏の学習者で中級の上(ACTFL)以上の学習者。1.5x2=3時間弱のクラス。 まず、時代背景が重要なので1960年安保闘争から、1064年のオリンピックに向けて、政治・経済・社会の動きについて学習者に調べさせ発表させた。 この映画の登場人物の誰に感情移入できるかとか、なぜできるかとか、一番好きなシーンはとか話し合った。ズームのブレイクアウトルームを使っているので、ペアで話しているが、クラス全員に戻った時、数人に意見をいってもらった。権藤の秘書、川西に感情移入できるといった学習者の理由は現代社会においてよくあったり見たりするケースで感情移入しやすいと。好きなシーンは最後の、権藤が竹内のいる監獄を訪れたシーンだというのが多かった。竹内の絶叫hシーンは映画の締めくくりにぴったりだったようだ。学習者の一人は、『竹内は狂ってしまったのか』と疑問を投げかけ、このシーンで『初めから狂っていた』と言っている。それは彼の立てた綿密な犯罪計画からしても、誘拐犯罪に対してこういう計画を立てること自体狂っていると。こういう頭の良さを医学に使えと。れいこ、戸倉警部、権藤、竹内、マスゴミが焦点になったが、警察のマスコミ利用により、もう一人の麻薬患者を殺させて、社会が麻薬患者をどうでもいい存在として扱っているという意見があり、これについて、クラスは2つに分かれた。一方はそれは操作の過程であって、故意に、もう一人の人間を殺したわけではないという。
私も個人的な意見をちょっと述べた。特に竹内の孤立感、追い越せ、追いつけという高度成長期に自分をどう確立していく方法かわからなく、負の方向の動きに走ってしまう。 『共助』の動きはどうなっているのか?今の社会との共通性が多くある。
古さを感じず、引き込まれる…
前半は三船敏郎が中心に描かれ、テンポも良く、どんどん次の展開に引き込まれる。特に身代金受け渡しのシーンは印象深い。後半は仲代達矢ら刑事の執念の捜査、犯人が山崎努とわかってからの張り込みなど、緊迫感ある。黄金町のドヤ街などインパクトあり。三船の会社の立ち位置や、捜査模様が丁寧に描かれていただけに、ラスト、なぜそうまでして、恨みをもって犯行に及んだのか、もう少し描いてほしかった。結局、高台にある三船の豪邸が天国に見え、下界で暮らす自分の境遇が地獄と言うことだったのだろうが、医者の卵?インターンの青年が地獄の境遇と言うのが、あまり腑に落ちなかった。三船敏郎は渋く、力強く、今の役者では中々代わりはいない。
人の本質で現代でも変わらない
最近SNSでの特に有名人への誹謗中傷が社会問題の一つになっているが、犯人の動機もそれと本質的には同じで、表面的に見て、雲の上の天国にいる様に見える有名人を恨み、叩き、不幸があると喜ぶ。多くの人の根底にあるそんな感情が今誰もが平等に発信できるようになったことで、SNSに溢れているのだけではないか。ただそれを人の本質と理解しながらも、人を恨むのではなく自分にとっての幸せを目指すことが大事だとも気付かされた。
息が詰まる場面も多く、あっという間に見終わってしまった。
シンドラーのリストでもオマージュされたシーンを始め、刑事達が夜に車に乗っている時の灯りなど、見ていて美しいシーンも多く、このシーンどこかで観たような、と思ってしまうほど後に多くの映画シーンに影響を与えていることがわかる映画でした。
人間それぞれの地獄
映画館やDVDで何回も観ているのに、改めて観ると、これって黒澤版『罪と罰』のような気がしました。靴職人から身を興した重役に対する自己チューな逆恨みと、インターンでありながら冷酷な殺人者と言う矛盾を抱える悪役は、今観ても鮮烈な印象を受けます。クライマックスの面会室のシーンは、山崎努の鬼気迫る演技と叩きつけるようなシャッター音に打ちのめされるようでした。
後半の展開に見応えあり
十数年前に見た時は新幹線開業前の「特急こだま号」を利用した身代金受渡しのシークエンスまでが強烈な印象で その後は肩すかしを食らった印象があったのですが、時間の経過を経て再見すると 犯人像が明確になってからの後半50分の展開こそがスリリングで抜群に面白いと感じました。
高度成長期における日本のダークサイドを徹底的に暴いてみせる作品であり、特に横浜繁華街やスラムのシーンは現代ならば炎上必至の描写かも。50数年前も今と同じように東京オリンピックに向け日本のイメージアップ作戦真っ只中だったはずですが、よくここまで突き放して冷徹に描けたなー とビックリです。 さすが黒澤、当時を代表する演劇人が総動員されており、三船仲代山崎努はもちろん ちょっとしか映らない脇の俳優たちに至るまで アンサンブル演技の素晴らしさに圧倒されました。 戦後 日本中にはびこった薬物依存患者に目を背けず描いている点でも注目に値します。
誘拐事件の現金受け渡しと犯人を追い詰めるスリルある展開。
単純に面白かった。143分もあるが、その長さを感じさせない。大きく二部構成になっており、一部は誘拐からの身代金の受け渡しでの犯人との攻防をスピード感たっぷりに描く。まず、会社を乗っ取るために必要なお金を身代金として渡さなくてはならなくなる権藤(三船敏郎)と運転手青木とのやり取りが面白すぎる。権藤の右腕として長年働いてきた者の裏切りなど、ただの誘拐事件だけではなく、そこに関わる人物達のそれぞれの状況がそのキャラクターも相まって、話を飽きさせなくしている。
そうとにかく飽きないのだ。脚本が秀逸。次から次へと起こる出来事に登場人物達がそれぞれの思惑で動く姿が実に面白い。
白黒映画だが1シーンだけ色がついている演出があるのだが、当時どのようにやったのだろう。知りたいところ。
惜しいなと思ってしまったところは犯人の動機。もっと深い怨恨みたいなのを想像していたため、ただの嫉妬だったのか、、、とガクッとなってしまった。ま、人を恨む動機なんて人それぞれだから良いのだけど、その動機が薄いためか地獄のインパクトが減ってしまったかなと言った感じ。
天国も地獄
DVDで2回目の鑑賞。
原作は未読(*現在は読了済み)。
思惑が交錯する権藤邸でのやり取りが中心の前半から、警察が誘拐犯を追い詰める後半へ、緊迫感を維持しながら駆け抜けていく演出が凄まじい。
特急第二こだまでのあっと驚く身代金受け渡しやパートカラーのインパクト、犯人を追い詰めるクライマックスなど、印象的な場面が目白押しだ。
横浜の表通りやスラム街の路地裏は、戦後の混乱が生み出したカオスそのもののようで、当時の様子を知ることの出来る貴重な映像となっている。
夏真っ盛りのある日、犯人が、クーラーなど無いボロアパートの自室から、世間を睥睨するかの如く佇む丘の上の豪邸を見上げる。そこに住む者たちの豊かな暮らしを想像し、自分の住処は地獄に思えただろう。募る羨望と嫉妬の末に聡明な頭脳は天国に住む者たちを苦しめ、己の虚栄心を満足させんがための狡猾な犯罪計画を練るに至ってしまう。
しかし、天国に住む者たちが幸せなのかと問われれば、決してそうとばかりは言えそうに無い。会社内のパワーゲームに勤しみ、権謀術数の張り巡らされた網を掻い潜って殺伐とした空気の中を突き進むような、欲望にまみれたものだった。それは果たして天国と言えるのだろうか。豪奢な屋敷も単に見栄っ張りの象徴のようで虚飾の城に思える。
そんな城の主、権藤金吾が葛藤の末に決断した良心と倫理観は、地獄(天国)に花と言ったところだろう。だが、この決断で権藤の会社での地位は失われた。もしも会社の地位を優先していれば、ひとりの子供の命が失われていたかもしれない。残酷な天秤だな、と⋯。三船敏郎氏の、人質奪還後の権藤のシーンに漂う寂寥感の演技に心が痛くなった。
天国と地獄にはそれぞれの思い描くビジョンがあって、羨んでみたり妬んでみたりする。だが一皮剥けば、どちらも相応に辛いことがある。
一括りにするのは的外れで、天国も地獄もそう変わらないのかもしれない。格差問題への黒澤監督の冷徹な目線が反映された名作である。
[鑑賞記録]
2017/09/20:DVD
2019/07/27:DVD
2025/11/09:UHD Blu-ray
*修正(2025/11/09)
とてもよかった
冒頭の自宅から電車まで舞台劇のように人が出入りするだけで場所が動かなかったがすごくスリリングだった。捜査会議も丁寧すぎるのではないかというくらい全部説明していた。
阿片窟みたいな横浜のスラムっぷりがすごかった。
子どもがかわいかった。
三船敏郎が昔の道具を床にばらまいて、かばんの加工をし始める場面がとてもかっこよかった。
犯人が医学生で、頑張れば数年でセレブ生活できるのに金持ちを憎むのがちょっと不自然だった。丘の上の家より、自分の病院の院長の方がずっと憎くなかったのだろうか。八つ当たりすぎる。
警察と犯人の人物像が希薄
総合70点 ( ストーリー:70点|キャスト:70点|演出:65点|ビジュアル:65点|音楽:65点 )
子供を誘拐をされそうになった三船敏郎演じる権藤の存在感が大きかった。犯人逮捕のために可能性を探ったり潰したりして地道に捜査をする警察も良かった。
しかし犯罪者と警察の人物像に焦点が当たっていなくて、どんな経緯があってどんな犯罪者が生まれたのかが伝わってこない。人も羨む医者の卵という出世街道まっしぐらの犯人が、何故そこまで劣等感に苛まれ、身代金の獲得だけでなく平気で人殺しまでするようになったのか。いくら夏暑く冬寒い安下宿に住んでいるといえど、もうじき金持ちになれるではないか。最後の言葉による告白だけだと納得できなかった。
また警察も犯人を追跡するための捜査についてはしっかりとした描写があって面白かったが、どんな人が捜査をしたのかの描写が少ない。だから警察の登場人物はただの捜査をする人に過ぎず、魅力的な人物像になっていなかった。結局権藤だけが目立っていた。
不可解なタイトル
学生の頃、名画座で観て以来、約40年ぶりにDVD で観ました。
何十年ぶりに観ると大概、こんなシーンあったっけ、とか記憶と異なることが多々ありますが、この作品は記憶通りでした。相当インパクトが強かったということでしょうか。贅肉を取りすぎたシナリオに古さを感じるものの、さすが黒澤といった作品です。
ただ、この『天国と地獄』というタイトルが内容と一致してなく、不可解です。
だって犯人は、今は苦学生かもしれないが将来を約束された職業です。主人公の生活を『天国』と言うが、自分もその位置に行ける立場にある。一般人から見ると、全く説得力が有りません。それに今の生活を『地獄』としても、それは希望を持てない犯人の個人的な問題。いっそのこと、それをテーマにすればもっと深い作品になったかもしれません。
全18件を表示