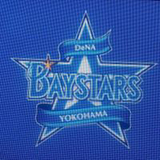戦場のメリークリスマスのレビュー・感想・評価
全162件中、81~100件目を表示
Powered by ATG
デビッド・ボウイがカッコいい
1942年、第2次世界大戦中のジャワ島日本軍捕虜収容所で、日本軍のヨノイ大尉、ハラ軍曹達と、連合軍捕虜ロレンス少佐、セリアズ少佐などとの、多少の信頼と愛情、捕虜の扱いでの衝突など、日本軍人と西洋人捕虜との関係を描いた作品。
テーマ曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」は知ってたが、映画は初めてだった。いい曲だと思う。
捕虜をジュネーヴ条約に則って扱わないといけないのに、日本軍の戦況が良くなかったのか、条約違反をした上官の姿は海外に向けては恥ずかしい事だと思う。
とにかく、セリアズ役のデビッド・ボウイがカッコいい。
ロレンス役のトム・コンティは安倍総理に似てておかしかった。
坂本龍一、ビートたけしも良かった。
愛のコリーダに続き、大島渚監督作品を観れて感激でした。
ビートたけし礼讃
はじめて女の子と観た思い出の作品。
当時、男子校の生徒だった僕は、待ち合わせ場所にいく途中、吐きそうになるほど緊張していた。
デートらしいデートなんてしたことなかったし、その女の子にも会ったことがなかったからだ(友達に紹介されたのだ)。
僕らは三宮で落ち合い、とりあえず喫茶店に入った。
女の子は予想以上に可愛く、おまけに予想以上にスカートの丈が短かったので、僕は心臓バクバクでクリームソーダをすすりながら何とか会話をつづけた。
そのあと、観たのがこの映画だった。
とにかく、緊張してドキドキするし、スカートの丈も気になるしで、当然のことながら映画にはほとんど集中できなかった。
そんなわけで僕は、その後しばらくしてこの映画を一人でもう一度観にいった(と記憶している)のだった。
1983年の夏のことだ。
件の女の子とはそれっきりになってしまったけれど(悲)、YMOを熱心に聴いていた僕にとって、“教授”が音楽を担当し、主演までつとめた本作はひじょうに印象深い作品となった。
デヴィッド・ボウイ、内田裕也、ジョニー大倉、三上寛といった、音楽畑からの面々の出演も刺激的だった。それに加えて、お笑い界の寵児ビートたけしである。
これらの個性的なキャストが功を奏して、結果、映画は大ヒット、「戦メリブーム」とも呼べるような興奮を生んだ。
この映画は我々YMO世代に大きな刺激を与えたのだった。
しかし、刺激は受けたものの、本作の内容に感動したかと問われれば、「うーん……」と躊躇するところがあった。
僕は、80年代を象徴するこの映画に「恋」をしていたのかもしれない。東南アジアの捕虜収容所を舞台にして、旬の役者陣や音楽が織りなす、独特の雰囲気を持った「戦争映画」に酔っていた節がある。
正直に言って『戦メリ』が何を表現しようとしているのか、当時の僕には理解できなかったのである。
あれから38年が経って、三度(みたび)『戦メリ』を観た。
やっぱり、「うーん……」という感じがした。
けっきょく何回観ても、この映画が何を言おうとしているのか、僕にはわからないのかもしれない。
ただ、「ビートたけしは、とてもいい」とあらためて思った。
たけしが絡むシーンだけ、妙にリアリティーがあるのだ。まるでホンモノの日本兵がそこにいるように。
これはビートたけしを観るための映画だ、と言ってしまいたいくらいだ。
同じように収容所を舞台にして、よくわからん同性愛色を排除して、たけしを主演に据えて撮っていれば、もっと骨太な、もっと面白い、ホンモノの「戦争映画」ができたのにと思った(まあ大島さんは、そんなもの撮りたくなかったのだろうけれど)。
まあそれはそれとして、絶妙のタイミングで流れる“教授”の音楽には、やはり心を動かされるものがあった。それは38年前と同じだった。
そして、あのエンディングの場面は、やはり日本映画史に残る名シーンと言っていいだろう。
それにしても、最近の映画で何十年も後に再映されるものがどれくらいあるだろう?
いまの若い人が中年になって、「そういえば、あのとき、あの子と観たなぁ」と懐かしく思えるようなものが何本上映されるだろう?……。
ヨノイの苦悶の表情と音楽サイコー!
4K修復版観ての気づき
作品について個人的評価は満点。
今回最低3回観賞予定で2回終了。どちらも今までになく前方で観賞した。
真っ白い土が印象的で違和感アリアリだったが、あの日2.26と東京は雪シーンで、なぎさはなるほどそうゆう演出かスゲー!と勝手になっとく。
宗教についても、セリアズはキリストの見立てと考えればいい気持ちになる。抱擁するために歩くシーンで近くの日本兵に全く気づかれないのはリアリティーないなと今まで思っていたが、キリストなんだからこれぐらいの奇跡なんでもないか。背中の傷・誤解されて裁判・種・処刑・クリスマスと結びつけるもの満載。
じやーヨノイハラロレンスは何の見立て?と考えるのもおもしろい。ハラはたしか実家お寺さんの設定でロレンスは二つの文化や精神を解するしヨノイは死に遅れた神か。
ハラがロレンスにメリークリスマス言うシーン2回あるが、同じように少し微笑んで振り向くロレンスの横顔が特に印象に残った。
劇場で観られるのは最後?
1983年ベストムービー!⭐️⭐️⭐️💖
セリアズがヨノイ大尉の頬にキスする場面に初めて泣かされました…
…素敵な作品です。
*久しぶりに観て気づいたのは、トム・コンティの日本語…何を言ってるのか聞き取れん。そして、同じくたけしと教授の日本語もよく聞き取れん笑
ジョニー大倉がどういう役どころだったのかは、あらかじめあらすじに目を通しておいたから良かったものの、そうでなかったら、なぜあんな仕打ちを受けているのか、多分理解出来なかったと思った。
私と同じくセリフの聞き取りに自信のない方は、ウィキペディア等で簡単にあらすじをおさらいしておくのが良いかも知れません…。
一部の隙もない
異端にして最高峰、愛と縁の究極の形
全てを咀嚼出来なかった自分を悔やむ。それ程まで大きなモノを見ているが故だと思い込みたい。大島渚監督による、人間の痛みや正義の奥の奥を観た。
ジャワ島の戦禍で、日本兵と捕虜による究極の愛と縁を描く。「Mr.ロレンス」は何者なのかすら知らなかったので、捕虜として囚われた通訳だったこと自体衝撃だった。そんなロレンスと親しい距離にいるハラはビートたけし。人間の倫理観も欠けたような言動も目立つが、上には従順。また、坂本龍一も昭和顔のイケメンでビックリ。
デヴィッド・ボウイもそうなのだが、表現者たちが大島渚監督の元で演技をするという貴重さと凄みが、特異な作品の色を出している。そこにある痛みは直接的で、今なら間違いなく躊躇するような描写に思わず体が強張る。
大学の制作で、大島渚監督の日テレのドキュメンタリーを見たことがあるのだが、その痛みや怒りを共に寄り添い、拡声させるような映像だった。今作も単にドラマとして魅せるのでなく、それ以上に突きつけるような重さが来る。怪物のような作品に出会った。
最後のセリフと坂本龍一の音楽が頭にいつまでも残る。劇場で観てよかったと本気で思える、異端にして最高峰の作品。
何回見たかな?この映画
君に胸キュン
あのテーマ曲とともにタイトルが出た瞬間、十代に時が戻ったような気がした。当時、小娘だった私は、ボウイの美しさにやられ、4回この映画を見た。同じ映画を複数回見たのは、初めてのことだった。原作本も読んだし、デビッド・ボウイのアルバム「レッツ・ダンス」も擦り切れるほど聴いた。コンサートにも行った。私の青春はボウイに彩られたと言ってもよい。今回見直しても、やっぱキレイです〜。あの緑がかった灰色の目!くう〜。
強烈に記憶に残っていたところもあったが、忘れてたところもあった。ヨノイが2.26に決起できなかったのを悔いていたのは、当時の自分はスルーしていた。どういう意味か、完全にわかってなかった。勝手な想像だけど、ヨノイの祖父は薩摩藩の人で、幼少からビシバシ武士道を叩きこまれ、常にもののふの美学を意識して生きてきたのではないか(あくまでも妄想)。散るべき時を見逃してはならない。散るなら美しく。ヨノイは2.26を逃してしまった。
セリアズの容姿が美しいのはもちろん、捕らわれた身でも毅然とした姿に、ヨノイは美学を見てしまった。原作では、セリアズの歩く様子を、爪先に重心を置く「動物のよう」と評している。野生の動物は自由で気高い。ヨノイはセリアズを理想化してしまった。
しかし、セリアズは自分の過去に苦しみ、ヨノイの理想と実際は違っている。彼は頭も良く、見た目も良く、恵まれているが、満たされることはなかった。心のどこかで死に場所を求めていた。ヨノイの激情を止めるため、勇敢な行動をしたようでいて、実は自殺に向かっていたのではないか。
あと、ジョニー大倉演じるカネモト。昔見た時、やはり彼のことはわかってなかった。つらい。なぜハラキリさせられるんだ。日本人じゃないのに。最後の言葉も韓国語。今見ると悲しくてたまらない。でも、こんな理不尽、戦争中はゴロゴロ転がってたんだろうな。
セリアズの弟の歌、透明なボーイソプラノ。これも確かサントラを買ったのか、かなり正確に記憶していた自分にびっくり。十代の記憶力すごい。寄宿学校の新入生へのイニシエーション。歌がうまいらしいから歌えと言われ、言葉通り朗々と歌ってはいけなかったんだよ、弟よ。
坂本龍一のメイクは多少違和感あるけど、あのボソボソしゃべる人が、あれだけ早口で腹から声出してるなんて、ずいぶんがんばったなと思う。たけしは目がきれいで、ハラの最大のチャームポイントだから、とても説得力があった。
大島渚ってほんとに海外向けに製作してたんだなぁ。クレジットが全部アルファベット。文字が赤ってのも、おしゃれだ。音楽も国境を感じさせず、とても良かった。鐘のような音を使ったテーマ曲は、教授の代名詞になった。歌手のボウイが音痴の役というのは、ご愛嬌。
2023.4.4追記
坂本龍一氏がとうとう亡くなってしまった。
悲しい…。
どうか安らかにお眠りください。
同じ時代を生きることができて、本当に良かった。感謝。
そうなんです、ボウイの美しさは悪魔なんです
心から愛していますデビッド・ボウイ様😍
私もヨノイ大尉同様、あなたに狂いました。
小学生の時に一目惚れ❤︎
もぅ、仕方ないんです、そう、悪魔なんです。
大島渚監督、良く見抜きました。
大画面、映画館のスクリーンのボウイはまた一段と不敵で美しい。ストーリー、というより映画館でまた戦メリを観ることが出来たというだけで号泣でした。
ヨノイがセリアスを、ハラがローレンスを、それぞれ好意的に扱った意味ということを今回深く考えました。
難しい、大変に難しいストーリーですが、観るたびに何かがつかめそうで、でもつかめない、モヤモヤの残る映画です。
思うのは、この時の武さんは本当にすごい何かを出している。デビッド・ボウイにも負けないあの存在感と輝き、得体の知れないは生命力は何なのでしょう。
配役と名曲と永遠の謎のストーリー、これからもエンドレスで見続けます。
【感想文】魂の交流なんだと思う
戦場のメリークリスマス、有名すぎる名曲そのメロディは知っていても映画をまったく知らないでいた。冒頭から流れ、心捕まれる。
文化の違いは思想・価値観の違いを生み、解りあうことは困難となる。この時代の日本の思想、集団意識は恐ろしく感じた。いや、現代もまだ変わっていないかもしれない。
戦争という異常の中で、人間としての心を失くさずにいることも困難かもしれない。
ヨノイ大尉はセリアズに対し自分と同じ何かとは別に自分にはない孤高な気高さを感じ、惹かれたんじゃないか。その内側から滲みでる美しさに惹かれたんじゃないか。
セリアズもまたヨノイ大尉に自分自身をみた、だからこそ救いたかったんじゃないか。
彼らのシーンで2度流れた曲『種を撒く』が素晴らしかった。
絶望的なあの状況で、彼のキスにより、どれだけ多くの魂が救われただろう。彼は彼の命をもって種を撒いた。
集団として個人を失くし、軍人としての役割のなかで生きているハラ軍曹に対し、ひとりの人間としての関わり続けていたロレンス。彼のおかげで失くさないでいられた人間としての心。お酒とクリスマスを理由にして、サンタクロースとして、ひとりの人間としてロレンスとセリアズを釈放する。
最後のメリークリスマス!ミスターロレンス!には、17の時から軍人として生きてきた彼が、個人として選択した行為(自由)を誇りに思っているようにも感じたし、ロレンスに対する感謝と敬意と愛を感じた。
異常環境の中で生まれる性愛というテーマだけでは片付けられないものがあったし、友愛や性愛は混同していったとしても、根底にあるのは愛だと思う。
セリアズはたとえ弟に対する贖罪であったとしても、大我の愛をもって人間を救おうとしていた孤高な戦士。
デヴィッドボウイは本当に美しかったし、たけしの瞳も美しかった。
各人物の放つ美しさの表現として個人的な解釈として、セリアズの美しさはデヴィッドボウイ自身が放つ美しさで十分表現されていて、坂本龍一はメイクする事でヨノイの足りない部分もしくは背伸びしている部分を表現としているような気もした。
目の美しさだけを表現したたけしも見事だなと。
大島監督って凄い人なんですね。
原作『影の獄にて』を読んでから再び観たい。
初見…
初見から25年後に見たのは「狂気の中の強烈なホモイズム」
若い頃見た映画を大人になってから見ると、印象が大きく変わることがある。
小学生の時みた「となりのトトロ」では妹が行方不明になる姉の不安が痛いほどわかったが、子供をもった今では完全にそれは健気な兄弟を応援する親からの目線になる。
結局物語というのは作り手よりも受け手の感覚の違い次第でどんな形にも変わるということなのかもしれない。
今回UPLINKの閉館間際に駆け込みで再見した「戦場のメリークリスマス」もそうだった。
18歳で美術大学に入ったばかりの頃、見ておくべき映画としてレンタルでVHSを借りた。
初見当時の自分は戦争末期の狂った日本人の姿にただ眉をひそめたものだったが、25年経って見たそれはまさに「狂気の中にある強烈なホモイズム(そんな言葉があるか知らないが)」だった。
ビートたけしのサディスティックなホモイズム、切腹させられたジョニー大蔵の「真夜中のカーボーイ」的ホモイズム(本編ではあまり触れられていないが、傷ついた俘虜の手当てからの求愛の流れはそれに近いものだと思う)、デビッドボウイの魔性的ホモイズム。ローレンスとたけしの間、デビットボウイと幼少期の弟との間にも、強い精神的なホモイズムを感じられる。
極度に閉鎖的な男の世界で男同士が(言葉にこそ出さずとも)性愛を求めてしまうのはある意味で必然なのかもしれない。共感や同情、憧れや思い込みを愛情と勘違いすることは何も男女の間だけに存在するものではないだろう。本作で大島渚の描きたかったそれは、例えば戦国時代合戦の場や刑務所の中、学生男子寮の世界でも同じことなのだろう。
熱血スポ根の祖、梶原一騎的な「男の世界」も、見方のよってはホモイズムの極みだ。
制作の裏側など詳細は知らないが、メインキャストのほとんどは当初想定されたものではなかったという。製作サイドの意向なのか予算的にやむを得ない故の結果なのか、いずれにせよ見事な配役だった。
※本文での「ホモイズム」表記に差別的な意図はなく、同性における恋愛・性愛感情の象徴として書き記したものです。
【戦場と男色】音楽はやっぱり最高!
わたしには“全く響かなかった”、“理解できなかった”というのが予備知識などなく本作を観た最初の感想。
まぁ〜、とにかく日本軍の鬼畜ぶりに終始イライラしっぱなし、彼らの、いや、戦争の愚かさ、おっかなさ。さらに洗脳の恐ろしさと、自分の正しさを信じて疑わないことの恐ろしさがありありと描かれている。
ところが、鑑賞後に詳しく調べてみると、なるほど!と、私が鑑賞時にひっかかっていたすべての謎が解けた。
ヨノイの狂気に満ちた行き過ぎた行動は自身のセリアズに対する恋心への自制心と葛藤からきているのだろう。
セリアズを初めて見た時、上半身の裸を見ただけでのあのヨノイの動揺っぷり。ホッペにキスをされた際の失神(どんだけウブなんだw)。恋に関しては驚くほどに奥手で純粋なのね。
実際に男色行為は兵士や士官の間で蔓延していたらしい。
戦争映画だけど美しい、景色も映像も音楽も。しつこいようだけど私は日本軍兵士達の鬼の所業に対する怒りの感情が勝り、本作を深く見ることができなかった。だけど不思議と最後は感動しちゃう。ビートたけし演じるハラの無邪気な笑顔に泣けてくる。
音楽はやっぱり最高、よくピアノで弾く曲が『戦場のメリークリスマス』聞けてよかった。
内容よりも話題性やエンタメ的な作品
全162件中、81~100件目を表示