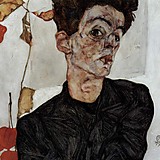プラットホームのレビュー・感想・評価
全4件を表示
1979〜1981 中国社会の劇的変化の貴重な記録でもある切ないドラマ
先月見たジャ・ジャンクー監督の2007年公開の映画「長江哀歌」に感激。監督の一連の作品が早稲田松竹で上映される機会に、その第1作となる本作(2000年)を鑑賞することができた。
舞台は、1980年頃の中国山西省の小さな街。地方の小劇団に所属する幼なじみ4人を主人公にしたドラマだ。現在につながる経済の自由化、文化開放政策で激変する社会、そこで生きる個人の変化を見事に捉えた素晴らしい作品であった。
本作の実現にオフィス北野が大きな役割を果たしているとのことで、それも同じ日本人として誇らしく感じる。
物語はフィクションだけれど、リアリズムであり時代の貴重な記録でもある。そうした映画として撮影されたことが、映画館に貼ってあったジャンクー監督のインタビューでも確認できた。
「私たちの親の世代は“革命の時代”を生き、私たちは“改革開放”の時代を生きた。その変化を経験した者たちの心の中にどんな傷跡が残ったのかは、誰も語ろうとしなかった。私はそれを映像の中に残したかったのです」
本作「プラットフォーム」(1979~1981の中国)「青の稲妻」(2001)「長江哀歌」(2006年ごろ)と3作で、現代に至る市場経済化による社会の変化がはっきりと見えてくる。
その変化と痛みは、行きすぎた新自由主義の反動に揺れる現在の西側諸国の現在とも完全に重なる。中国の場合は、急激な変化だけに、それを描いた本作からは、市場経済がどうやって共同体を破壊するのかがはっきりと見て取れる。民主主義国家の僕らから見ても深く共感できるものなのだ。
1979〜1981年の3年間の物語。この短い時間の中で、社会は劇的に変わっていく。
まず冒頭の1979年。まだ文化大革命時代の影を残す社会主義体制のもとで登場人物たちは小さな地方劇団に所属している。そこで上演する演劇は毛沢東の偉大さを讃えるものだ。
この冒頭で描かれる中国の人々は、その後のジャンクー作品で描かれる人と全く違っている。生き生きと楽しそうで、お互いが共同体の仲間としてつながっている。抑圧的な社会の暗さは全く感じられない。共同体のアイデンティティの中に個人が埋めこまれていて、それはとても安心できることなのだ。古き良き前近代的な共同体社会といのが71年生まれの監督の幼少期の記憶なのだろう。
つまり、ジャンクーが本作で描くのは、ここからの変化、一言で言うなら〝自由を手にした時に人は孤独になる〟ということだと思う。革命が終わり、国家も社会も人生を導いてくれるものではなくなった時に、何をよりどころにして生きていくのかーー。その問いがジャンクー監督も含む〝改革開放の子どもたち〟の宿命であるし、自由な社会での私たちの宿命でもある。
映画では、1980年に改革開放が始まり世界が一気に変わっていく。
文化的には、テレサテンの恋愛ソングに象徴される。個人として人を愛し、その人と繋がれないことに切なさを感じるという主体を持った個人の文化に触れることで、何かに目覚め、また癒されている。(映画では描かれないが、)ニーチェやフロイトも1980年から入ってきた。実存や個人的主体という思想が突然やってきたのだ。
問題は仕事だ。映画では、劇団を存続するために、誰か個人が資本家としてその経営を引き受けなければならず、劇団の中で冴えなかった小金持ちの男がいきなり経営者となる。
計画経済の中では、仕事と役割、仕事の方針まで全ては与えらるもので、創意工夫の余地などなかった。それがいきなり会社にさせられたのだ。
鄧小平の「黒い猫でも白い猫でも、ネズミを捕るのが良い猫だ」の言葉通り、イデオロギーはなんでもいいから、稼ぐ人間が良い人間だとされた。いわば拝金主義へと、いきなりルールが変わったのだ。
この辺りから、どんどん幼なじみの仲間の関係が危うくなり、家族もバラバラになっていく。開放前の方が抑圧されていると思うけれど、むしろだんだん息苦しくなっているように描かれている。
印象的なのは、遠くから聞こえる汽車の音に気付いた彼らが、飛び起きて、線路に駆け上がり、走り去る汽車に向かって叫ぶ場面だ。ここではない別の世界への憧れが詰まっていて切ない。
実際、開放政策下でも人の移動が制限されていたから、民主主義文化に触れることはできても海外には行けないし、それどころか先に発展し始めた中国沿岸都市に行くことすら叶わない。
国も地域も守ってくれないし、生活は苦しい。でもその中で個人主義的な目覚めを果たしていく。ジャンクー監督自身がまさにその一人であり、自分の中のモヤモヤと切なさと懐かしさをこうして映画として表現した。
映画の中では、劇団の女性が真っ赤なドレスでフラメンコを踊る。もう一人別の女性は、深夜一人、台湾のラジオ放送から流れる歌に合わせて、作業服のまま踊る。この2つのダンスは振付通りに踊るものではなく、その場で内面を自由に表現したようなダンスであって、とても美しく印象に残った。
ジャンクー監督は50代のはずだから、まだまだ新作を撮れるだろう。それを楽しみに期待したい。まずは早速「新世紀ロマンティクス」を観に行こう(明日が早稲田松竹では最終上映だ)。
ジャ・ジャンクーの映画は〝変化の時代を生きるとはどう言うことか〟を突きつけてくる。変化と発展は現代社会の宿命でもあり、良きこととして語られることも多いけれど、それは人の心の中に痛みをもたらす。その痛みをどう引き受け、どう解消していくのか……その問いに向かうために重要な作品群であると思う。
中国山西省、海抜1000mほどで雪も舞うあたり、 小さな町で劇団員...
中国山西省、海抜1000mほどで雪も舞うあたり、
小さな町で劇団員をしている若者4人の模様。
共に過ごす日時の長いこと、練習とか巡業とか。
かつて中国の象徴だった、人民服や革命歌。
それらが、80年代の文化開放で、徐々に影を潜めだしたころ
西洋的なものが次々に取り込まれて。
劇団の演目も、かつての象徴=政権万歳ではなく、時代に沿うものを求められ、
劇団員らが迷い葛藤する様子。
変動の時代に直撃した若い団員たちの様子、
俯瞰した長尺の映像、
流れる音楽も新旧まるで違い、
映画の始まりと終わりとでは、違うものを見ている感覚を抱きました。
きわめて叙事詩的。
ギリシャの傑作 "旅芸人の記録" と並べて語られるのも納得です。
ジャ・ジャンクー監督は、このギリシャ映画は見てないそうですが。
青春群像‼️
历史意味
全4件を表示