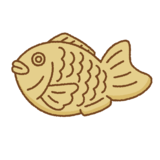七人の侍のレビュー・感想・評価
全30件中、1~20件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
1954年製作の黒澤明監督作品『七人の侍』、新4Kリマスター版を「午前十時の映画祭」で鑑賞しました。
改めて映画の内容を説明することはないでしょう。
2016年の4Kデジタル版でも音が良くなったと感じたが、今回はさらに向上。
台詞のほとんどが聴き取れる。
ゆえに、休憩までの前半がすこぶる面白くなった。
なにせ、フィルム版だと百姓たちの台詞の多くが聞き取れなかったから。
画質も恐ろしく向上。
毛穴のひとつひとつが見えるほど。
汗のぎらぎら感も凄まじい。
ただし、カットによっては、かつらの盛り上がりなどもわかる。
前回鑑賞時も感じたが、歳を経てから観ると、爽快感が乏しく感じられる。
これは、戦いのリアリズム、特に農民の戦いをおぞましく感じたからでしょうね。
さて、全長版は今回も含め何度か観ているが、短縮版はどうだったのかしらん、などとどうでもいいことが気にかかった。
自身の鑑賞履歴初期に16mm版で2度観ているが、これが160分のバージョンだったかもしれない。
全長版リバイバルの際に、前半、記憶のないシーンがあった覚えがするので。
なお、16mm版の鑑賞1度目は、映写機の故障で野武士が来るところに至らず中止。
2度目になって、全編通しで観た。
以下、2016年鑑賞時のレビュー。
『生きる』の続いて「午前十時の映画祭」での鑑賞は『七人の侍』。
20年ほど前にニュープリントの全長版(207分)のを2度ほど鑑賞しているが、それ以来か。
前回はセリフの大半が聞き取れなかったが、今回はよくわかる。
画面の陰影もくっきりしており、今後はこの4Kデジタル版が決定版となるだろう。
さて、映画。
戦国の世、収穫期に野武士の集団に略奪される山村あり。
業を煮やした村人は「野武士討つべし」との長老の言葉のもと、腹をすかせた侍を雇うことにした・・・
というハナシは有名なので書くまでもない。
映画はすこぶる面白い。
特に面白いのは前半で、侍を集める件が面白い。
そして、村をどのように守るか、墨書きの地図と照らして、ここをこのように守る、という戦術を考えるあたりまでが特筆すべきだろう。
この前半、ほとんど活劇らしい要素はなく、それゆえ黒澤明のドラマツルギーが凝縮しているともいえる。
ドラマにアクションは要らない。
必要なのは、モティベーションとエモーションといわんばかりに、名台詞とともにそのふたつを描いていく。
曰く、長老の「討つべし」。
曰く、勘兵衛の「この飯、おろそかにか食わぬぞ」。
曰く、勘兵衛が果し合いをする久蔵とその相手をみて、「無益な。結果はみえておる」。
曰く、勘兵衛が菊千代をみて「おぬし、侍か」などなど。
後半は、野武士と侍+百姓の戦が描かれるが、ドラマとしては百姓を出自とする菊千代の物語ぐらいしかないが、ほとんどドラマらしいドラマがなく1時間以上も保たせるのは尋常でない脚本ともいえる。
そもそも、村を守るのに何故七人必要なのかをあらかじめ説明しておき、40騎いる野武士をどのように倒していくかを克明に描いていく。
それも、説明的な説明を用いずに。
ここいらは、後に模倣乱造される「七人もの」アクションと一線を画し、この映画をこの種の活劇の頂点に押し上げている所以である。
まぁ、そんなことは20年前にも思ったことなので、今回、再鑑賞して思ったことを少々。
黒澤明の監督作のフィルモグラフィでいうと『羅生門』(1950)、『白痴』(1951)、『生きる』(1952)ときて、本作(1954)である。
その後が『生きものの記録』(1955)である。
個人的には、『生きものの記録』を「黒澤明作品の中で、黒澤らしいヒューマニズムに溢れた作品」として推すのだけれど、『生きる』以降、黒澤のヒューマニズムが少しずつ揺らいでいるような感じがする。
これは『生きる』の再鑑賞のときにも感じたことだが、『素晴らしき日曜日』(1947)のように、市民(小市民)に激励の言葉をかけるのを止すようになっている。
本『七人の侍』にける小市民の代表は、農民である。
そして、七人の侍たちのなかにも、彼らに近い人物が「ふたり」いる。
ひとりは三船敏郎演ずる菊千代だが、もうひとりは千秋実の平八である。
平八は、腕は「中の下」であるが「苦しい時には頼りになる(場を和ませる)性格」と評せられるにもかかわらず、野武士との初戦で敵方の鉄砲によってあっけなく死んでしまう。
そして、その「苦しいとき」に場を和ませる役は、求道者然とした久蔵(宮口精二)が代わることになる。
小市民的キャラクターをあっさりと、もっとも武士的人物に肩代わりさせてしまう。
もうひとりの菊千代については、いわずもがなな扱いで、映画を快活に進めるトリックスターであり、その出自を百姓だと前半に明らかにし、かつ後半に入ってすぐの水車小屋の見せ場で、焼き討ちにあった水車小屋で生き残った赤子を抱きしめて、「こいつは俺だ。俺も、こうだったんだ」という絶叫を描きながらも、彼は最後むなしく、かつあっけなく死んでいく。
その上、彼に「百姓はずるいんだ」云々というすこぶる的を射た台詞も吐かせつつである。
さらには、合戦のシーン。
戦術を立てるのは、侍(中心は志村喬演じる勘兵衛)であるが、野武士たちに止めを刺すのは武鑓を持った百姓たち。
終盤では、追い詰められた野武士に、百姓の女房たちが鋤鍬を持って止めを刺そうと襲いかかる。
さながらホラー映画のように。
小市民に激励の言葉をかけていた黒澤は、前作の『生きる』と同じく、この時期、小市民をかなり嫌悪しているのではありますまいか。
ラストは、晴れ晴れとした田植え歌が流れるのではあるが、まるで心は晴れない。
4つの侍たちの土饅頭と十数の百姓たちの土饅頭を前に勘兵衛がいう台詞「また負け戦だったな。勝ったのは、あの百姓たちだ。儂たちではない」は、いまなら「また負け戦だったな。勝った百姓たちの喜びも、いっ時に過ぎぬ」というとこになるのかもしれない。
観る齢、観る時期により、感じ方が異なる作品かもしれませんね。
昔の俳優さんは体力あったんだなぁ
んー、長かった。良かったけど長かった。途中休憩があるのが嬉しかった。スクリーン上に「休憩」の字幕が出てBGMが流れて5分、そこから上映中断して5分の計10分、トイレに行って一息ついて上映再開。おかげで中だるみせずに鑑賞することができた。
ウラ話は知らないけど俳優、スタッフみんなで一本の作品を作り上げたというエネルギーが画面を通して伝わってきた。志村喬と三船敏郎、静と動で正反対だがその存在感がスゴい。志村喬は戦を何度も経験し知識も経験も豊富な正統的な武士、三船敏郎は若くぶっきらぼうで危なっかしいが勇気があり力もある百姓出の武士。他の武士たちもそれぞれに魅力的で話を引き立てていた。
最後は百姓&武士側が勝利するが志村喬と数々の戦をともにしてきた加東大介、一番若い木村功の3人以外の他の武士たちは戦死してしまう。「勝ったのは百姓で我々ではない」という志村喬の言葉に考えさせられた。一見貧乏そうに見える農村だが落ち武者狩りで得た鎧や槍、弓矢などの武器、ふんだんにある米や酒。百姓に足りなかったのはそれらを活用できる力の存在だった。七人の侍は百姓にうまく利用されたとみることもできる。志村喬の言葉はその虚しさが込められているように感じた。
タイトルの意味は俳優さんがやたらと走っている印象が強かったから。とにかく皆さんお疲れ様でした。
義を見てせざるは勇無きなり…但し、言うは易く行うは難し。
日本映画の金字塔が一つ。確実に。
噺のプロットは王道中の王道……ん?てか、今作が王道元?😁
強者による多勢に無勢で困窮している弱者の為に、少数精鋭が助太刀する…
多額の報酬や褒賞なんてもモノは全く無い、立身出世にも全く関係無い。
それでも…助ける心粋。
滾るよね、燃えるよね、奮えるよね。
そして、憐れな筈の百姓も…ただ哀れな存在じゃない。
弱者面していても、その言動には一癖も二癖もある。
近くで戦が起きれば、機を見計らって落ち武者狩りをして装備品を掠め盗るし、米を出せ!麦を出せ!と云われても平気の平左で、嘘を付いて「ない!」と云い…その実、床下や納屋の土の下や時には墓の下にまで穀物やら酒やら何でも備蓄する強かさや狡賢さを持っている…
途中…侍達と百姓達の間に、そういった蟠りが出来た時、
二つの相容れない水と油な両者を取り持ち、マヨネーズに於ける酢みたいな貴重な存在となったのが、
野犬の様に荒々しく侍の作法も常識もそっちのけだった菊千代と云う異端。
彼は云う…
「お前ら!百姓を何だと思ってんだ!仏様とでも思ったか?奴らほど悪ズレした生き物はいないんだ!平気でウソはつくし、落ち武者狩りもするし、米や麦や小豆、酒だって…探せばどっかから必ず出てくる!何でも隠すし、卑怯で、卑屈で、見てるコッチが泣けてくらぁ…でもな!連中をそんなケモノにしたのは、何処のどいつだと思う!お前ら侍だよ!…戦の度に田畑は潰す!米でも何でも奪ってく!村の女には手を出す!歯向かえば殺してくる…じゃぁ、百姓は一体どうしたらいいってぇんだ!」と。
菊千代の魂の叫びにも似た涙混じりの独白に、他の侍達は、何かしら心当たりが有る風に神妙な面持ちになる…
日本人の弱さと強さ、邪なトコと清いトコと、何だかんだ総てが詰まっている様に思う。
侍をスカウトに来た4人の百姓達を、最初は鼻で嗤ってバカにしていた荒くれの人足三人衆も、嫌味を垂れながらも、彼らの苦心を理解しながら助太刀に二の足を踏む勘兵衛らに…
「おい!この白飯を見ろよ!あんたら侍に白飯食わせる為に、コイツらは何を喰ってると思う?ヒエだけなんだぜ?…コイツらだってコレで精一杯なんだ!」
…と、助け舟を出す。
こういうところが観る者の胸を熱くする。
時として、大を助ける為に小を切り捨てる苦渋の決断を迫られる事が有るかもしれない…その時、無関係な連中は、涙を飲んで我慢した人々を、利他的な所作を美徳として美談として賞賛するかもしれない…
そんな胸糞悪い美辞麗句よりも、
利己的な言動はいつか己をも滅ぼすから…と、血反吐を吐く思いで、歯軋りしながら、自らを納得させた自分自身を誇りに思うしか無い。
それでも、その悔しさや苦悩を、ちゃんと見ている人は見ているし、分かち合おうと理解を示してくれる人もきっといる。
そういった何とも言えない人生の機微が、今作には沢山詰まっている。
今、この令和に、今作をリメイクしたら、どんな陳腐な駄作が生まれてしまうことやら。
だいたい…今じゃ、肉厚ちゅうか、、濃いぃぃぃ感じのアブラっぽい?ギラついた役者さんってめっきひ減っちゃったもんね。
中年以降の俳優さんも…皆んなイケメン、イケオジだし。
かといって、Vシネで893役ばっかやってる強面や悪人面な役者さんは野武士役に取っておきたいし、、
勘兵衛はどうせ役所さんで、五郎兵衛は堤さん、平八はムロさん、久蔵は佐藤健さん、七郎次が鈴木亮平さん、勝四郎は…童顔の若手イケメン俳優?
で、菊千代だよ、菊千代…当時の三船さんは、あの風貌で33歳か34歳…
いる?今のアラサー俳優で、菊千代役に耐えうる人…
まぁ、やっぱ無理だわな。
え?山崎賢人?…駄目だよ、ダメ!ダメ!…利吉でしょ、ピッタリなの。
じゃぁ、、山田孝之さん?……ん〜、ん~~、なんだかなぁ、
つか、皆んな全体的にキレイ過ぎるし、痩せ過ぎなんだよなぁ、スタイル良過ぎでさ。
結果、リメイク意味あんの?ってね。
漫画やアニメの実写化断固反対!ってのはあるけど、
実写のリメイク向いてないって、やっぱもう至高の完成形なんだよなぁ、原典が。
なんといっても映画館
何度か黒澤映画を挑戦しましたが、いつの間にか、手悪さをしていて、見失う…を繰り返していました。これは映画館で観るものだ…と言い訳をし、あきらめていたところ、なんと上映するとな!!もう、行くしかない!長丁場でありましたが、よそ見をすることなく、夢中で鑑賞しました。途中の「休憩」!!で急いでトイレ!ありがとう。
さて。志村喬。こんなシブいおじさんがいたんてすね〜三船さんの青い感じも勢いがあってよかったですね。弱々しい村人おじさんもよかった。
なんといっても馬!!あれだけの数を全力で走らせる、乗りこなす技術、切られて落馬、映像のイメージと綿密な撮影計画。村人!!ぞくぞくと出てくるあの数、これぞ群衆の動き。向こうからどんどん近づいてくるのが、ず〜っと見えている映像。ドキドキしました。
最後の終わり方も好きです。全員勝者ではなく、亡くなった侍もいて。そして、村を守られた村人にとっては、また戦いなど侍など必要ない日常がかえってきていることが、描かれていて、きれいごとではない普通の日々で終わっているところです。
スタッフも同じ思いで準備をし、撮影しているのでしょう。もうコレくらいでいいんじゃないですか〜では完成しなかったと思います。黒澤明という男の強烈な魅力で、出演者、スタッフを引きつけて突き進んだのでしょう。人を一つに束ね、一つの大作を作る黒澤明監督の偉大さに圧倒されました。
黒澤時代劇
DVDでも幾度も観たが映画館では初。
矢張、エンターテイメント。
黒澤時代劇。
40騎の野武士に立ち向かう多士多彩の7人の侍。
あの明るくて、ちょっと抜けてて、頼もしい
そして哀しみも感じられる。
厳しい中にも笑い、涙、仁義、人情、恋
も入る見事な演出。
脚本の凄まじさを痛感する。
相当時間をかけて練りこまれており緻密だ。
カメラを幾つも使用して撮影された
雨の決闘シーンは見応えあり。
画期的なアイデアだったに違いない。
百姓と武士の佇まいの違いの演出も良かった。
そして、あの映画音楽だ。
早坂文雄さんは絶妙な音を映像に当てはめる。
黒澤監督のイメージをより理解してるのだろう。
見事な相乗効果だと思う。
勘兵衛はかなりの人格者だし
菊千代は愛すべき男。
あの水車小屋から子供を抱きかかえて
『俺もこの子と一緒だ』は印象的でぐっとくる。
勘兵衛、菊千代、久蔵、藤四郎、五郎兵衛
平八、七郎次この7人にスクリーンで会いたく
なるんだよね。
70年経過しても色褪せず楽しめる黒澤明監督の
作品は圧倒的である。
モノクロでも色褪せない名作
午前10時の映画祭にてあの伝説の作品をついに初鑑賞!
なんだこれ!すっごいおもしろかった!
ものすごく古い映画なのに今でも一線級で、
お手本のような面白さだった!
主要キャラが7人もいるので登場人物はけっこう多いが、
どの人物も分かりやすいキャラづけや濃いストーリーがあって印象に残りやすかった。
特に最初はすごくウザかった菊千代も百姓の生まれだと分かるシーンで一気に好きになった。
なので菊千代が戦死したのはかなりショックだった😢
戦さには勝ったのに侍側にとっては負け戦さだったという
勘兵衛の言葉と4人の侍の墓のあの極まった哀愁は当分は忘れられないと思う。
点はつけれませんがそれはできないようなので
三船敏郎 志村喬 と出てくる南がとてもカッコ良い
ただ千代丸が最後死んでしまったのはショックだった
いろんな映画がこの映画を見て参考にしているのだなーと思った良い意味で
最初は言葉が何を言っているのか分からなくてあーこの映画見れないなーと思っていたら途中から耳が慣れたのか聞こえるようになりました
この映画が私が生まれる何年も前に作られとは思わないくらいすごい映画でした
ただ長い とにかく長い ダブルヘッダーやってるような感じだったのでみる時はきちんとした時間が必要かも
あと映画館寒すぎて風邪引く
光り輝くお米
午前10時の映画祭で人生で初めて観ました
名作とは聞いていたけど、今まで観れてなく
このタイミングで観れました
3時間30の時間を感じさせない、怒涛の面白さに圧倒されました
極上の映画体験が出来ました
七人みんなそれぞれ良いキャラクターをしてて、それぞれの見せ場がちゃんとある
からみんな好きになる
登場シーンで、そのキャラがどんなキャラかどんな過去があったり、どんな考えをしているのかが、それぞれ会話の中で分かるようになっているため、キャラクターがとても分かりやすく、その後の没入感へと繋がっていました
農民の苦労が分かると言って入ってきた侍のアップになってからの満面の笑みには人柄の良さが溢れ出ていて、その一瞬でもう好きになりました
書くとキリがないのでこのくらいにしときますが、
それぞれのキャラクターの
「カッコよさ」
「優しさ」
「信念」
などがストーリーが進めば進むにつれて分かっていく過程は
人生や、人間というものを学んでいるように感じます
三船敏郎さんの演技も素晴らしかったです
コミカルなシーンではめちゃくちゃ笑えて、
真面目なシーンではこちらの心に訴えかけてくる演技をしていて
本当にカッコよかったです
菊千代がキレるシーンは三船敏郎さんの演技も相まって、もう、真の名シーン‼︎
元農民というバックボーンが分かりることでセリフの重みが増していました
ラストの戦闘シーンも、圧倒されたとしか言いようがないです
泥臭くて、汗臭くて、這いつくばりながら、全力で戦う姿は、
侍、いや、人としての生き様を堂々と観させられたように感じました
師匠の初登場シーン、侍を探してた時に一騎討ちでやりあっている所の侍の構え方、
侍達の全力疾走シーンのカッコよさ、
えいえいおーと百姓達を励ます姿、
種子島を1人でかっさらって帰ってくるシーン、菊千代が百姓達や、子供達を笑わせる姿、
輝いていて美味しそうなお米、師匠の弟子が銭を分け与える姿、
師匠の強すぎる作戦、
それぞれの侍の生き様、
最後の戦への問題提起、
パッと上げるだけでもこれ以上、好きな所が出てきます‼︎
でも1回じゃ全ては吸収出来てないと思うから、もう1回観たい‼︎
『七人の侍』─群像劇が映す人間の尊厳と近代の予兆
世界のクロサワの不朽の名作『七人の侍』が4Kリマスターでリバイバル公開中ですね。
この作品は単なる時代劇ではなく、封建的秩序の終焉と、個の自立が芽生える過渡期を描いた日本映画史上最大の人間ドラマだと感じました。
農民が侍を雇うという倒錯した関係構図は、戦国という時代を背景にしながらも、公開当時における戦後日本の社会構造の転換を予見していたものでしょうか。
武士はもはや支配階級ではなく、経済的弱者のために「雇われる存在」となっています。
そこには、かつての権威や理念が空洞化しつつある「職業人」としての侍像が立ち上がります。
黒澤監督は、武士を英雄ではなく“失業した労働者”として描くことで、封建倫理を超えた近代的ヒューマニズムを提示したかったのではないでしょうか。
物語の中心にいる勘兵衛(志村喬)は、旧来の武士道を体現しながらも、人間の尊厳を理解する数少ない人物として描かれています。
彼の行動は「義」ではなく「慈悲」に根ざしていて、まさに近代的人格者としてのリーダー像を提示しているように見えます。
対照的に、菊千代(三船敏郎)は身分制度の犠牲者であり、侍の模倣によってしか自己を確立できない男。
だけど、最も激しく、最も人間らしい叫びをあげるのも彼です。
黒澤監督はこの対比を通して、「人間とは何か」という問いを制度の外に押し広げ、観客に突きつけたかったのではないでしょうか。
農民が勝ち、侍が去るラストカットに至るまで、この作品は「勝者なき勝利」という矛盾を抱え続けています。
墓標の前で勘兵衛が呟く「勝ったのは百姓たち」という台詞は、戦後の民主化とその代償を予見する預言のようでもあります。
結局のところ、『七人の侍』が描いたのは、英雄譚ではなく“共同体の再構築”だったと思います。
黒澤監督は、個と集団、理念と現実、誇りと生存、そのせめぎ合いを、戦国という寓話に託して描ききったのです。
だからこそ、この作品は70年以上の時を経た今も古びることはないのでしょう。
刺さらなくて残念。。
傑作と言われている作品だったので、せっかくのリバイバル上映だから見てみよう、と思いましたが。。
セリフが聞き取りづらいのは、考察動画などを見たら監督の考えでリアリティを追求した結果、農民がそんなにクリアに話すはずない、ということから日本語なのに聞き取りづらく、日本語字幕が欲しい感じになったそうなんですが。。
やっぱり登場人物が何を話してるのかよく分からない部分があるというのは視聴のストレスなので、私には合わなかったです。
*****
そして場面場面での説明が足らない。
例えば農民の中で、女房の話になると取り乱し、さらに敵の陣営にいる女性について「あれは俺の女房なんだ!」的な発言をしていたように思いますが、
かつての襲撃でさらわれてしまったのか?例えばそうなら何故味方の侍達に事情を言わなかったのか?敵陣営にいる女性なら戦いに巻き込まれて怪我や命の危険があるんだから「こういう女性がいたら俺のさらわれた女房だから先に助け出してからの攻撃にしてもらいたい」とか説明しなかったのが不自然に思いました。
*****
あと村の娘と恋仲の感じになった味方の若侍。幻滅しました。身分制度のある時代とはいえ、彼女が父親に怒られていた時、きちんと名乗り出もしない。すぐそこに居るのに彼女を庇って父親から守ることもせず、「生半可な、遊びの気持ちなどではありません!」とかを宣言するわけでもなく、ただうつむいて佇んでるだけ?最低。。
そりゃ今すぐ正妻として娶るのは無理かもしれないけどなんかこう、もうちょっと何かちゃんと自分の気持ちを表明出来ないの?情けない。。!
で、映画的にもこの2人の行く末を何もフォローすることもなく、
ただ彼女は傷ついて彼に目も合わせず、彼も声をかけることもなく(せめて元気でとか、また会いに来るとかぐらい言ってくれればまだしもなーんにも台詞すら無く。。)
ボーっと彼女を見つめて映画も終わり。
え?モヤモヤしすぎで、村を40騎もの野良侍達?から守ったことも何もかも全部チャラになってしまいました。。
時代背景?男尊女卑が普通の時代だったから?身分が違うから遊びでしかないの?え?何なの???と疑問ばかり。
*****
あと。。三船敏郎さん、賑やかしでなんかぶっきらぼうなだけであまり主役級の存在感がなく。。
作戦も1騎ずつ村に入れて1人ずつ倒そう、というのは最初はいいけどいつまでもこの侵入の仕方に何故敵はいつまでも乗ってくれるのか?騎馬がもっと密集してくるなり。。敵側の作戦会議とかの場面が無いのでなんか敵の考えが分からず、作品に没入出来ませんでした。
最初に2〜3人が倒されたら、いったん作戦立て直さないの?普通。。こういうものなんだろうか。
七人の侍のリーダー格のお侍さんは思慮深いし村の防衛作戦も立てて頼もしいし人望もあるキャラクターで良かったけど、映画そのものとしては驚くほど刺さらなくてとても残念でした。
決戦シーンのすごさ
午前十時の映画祭で観ました。
タイトルの通り、雨が降る中の決戦のシーンはすごいですね。
雨で土もぬかるむ中、人も馬もみんなぐちゃぐちゃになって戦う。派手すぎるバトルアクションではなく、雨と土の匂いが感じられそうな、文字通り泥臭い戦いの様子が伝わってくる映像で感動しました。
また、初めは百姓は弱い立場で侍に頼るほかないという構図だったものが、最後は取り戻した平和を謳歌する百姓と墓を前に沈黙する侍たちという全く違う構図になってしまうのは印象に残りますね。完全なハッピーエンドでもなく、かといってバッドエンドとも言えない、でも物語の終わりとしては綺麗だと思いました。
誰か一人、物語の軸となる明確な主人公がいるわけではないのに(いないからこそかもしれませんが)、個性豊かな侍たちのしっかりとしたストーリーがある、良い作品だと感じました。
刮目して大局を見よ
「素晴らしき日曜日」から「七人の侍」までの映画は黒澤の
戦後年代記とも見ることが出来る。
戦争。それを体験してない人には、それを体験して人にとって何だっのかは全くと言ってよいほど分からない。分かってるつもりでも、何も分かってやしないのだ。
戦後。それもしかり。
・・・ただ、その時代の人が作った映画を見たときに、それが彼らにとって何だったのか?それとどのように向き合い、戦い、苦しんだのか・・少し・・ほんの0.何パーセントか・・伝わってくるだけある。
「素晴らしき日曜日」から「七人の侍」までのクロサワ映画がまさにその、伝わってくる映画だ。
以下、すべてネタバレ注意。
「素晴らしき日曜日」
背景に移っているのは、本当の焼野原となった東京である。そこでデートしている若い2人の、希望の見え無い未来が描かれている。センチメンタルストの黒澤明でさえ、この時代をハッピーエンドには書けなかったのだ。
「酔いどれ天使」
この映画に写っている池は。汚いものがたまり込んでいる。腐敗社会のシンボルみたいな池。街の秩序をつくっているのは警察ではなく、ヤクザ。この池は本当にB29の爆弾によってあいた穴に水が溜まった池だ。その池を撮影に使った。映画はこの池の周辺で、もがくように生きている人々を描いて描いている。それは・・戦後のすべての人々が、そうだったに違いない。
「野良犬」
この映画の主人公は警察だ。復興が進んで来て、警察が機能していることが描かれている。そして犯人と主人公の類似性。ちょっとした運の違いで同じような人間がこうなってしまうということが書かれていて、クライマックスの対決シーンがとても恐ろしいものに見える。
「羅生門」
この映画は本来、長編映画としては持たないぐらい短い脚本だった。そして、何がなんだか分からない、とても変な物語だ。なぜこのようなものを黒澤は作品化しようとしたのか?・・それは、あの戦争の真実性がわからない、その不気味さをこの作品に託して表現したかったからだ。
「生きる」
この映画は池をうめて公園を作るという話だ。ここに登場する池は「酔いどれ天使」に出てきたのと同じ池だ。埋める計画が立てられていたのだが、それを延期して映画を撮った。この池を埋めろと主婦たちが押しかけてくるところから物語は始まる。つまり、どんどん復興しているという時代の話なのだ。これからもっと世の中が良くなっていくことを夢見ながら、主人公は死んでゆく。
「七人の侍」
「また、負け戦だった。勝ったのはオレたちではない。この百姓たちだ」このセリフが表現しているのは結果から見る勝ち負けだ。戦争に負けたのは、軍人。政治家や資本家たちだ。一般庶民は戦争に負けたんじゃない。見ろ、この復興の力を!ということが、あの台詞には込められている。
ここまでの「素晴らしき日曜日」から、「七人の侍」に至る映画は個々が、それぞれ独立した物語であると同時に。この作品までが一連の復興オムニバス映画なのだ。だから全部見ていただきたい。我々はそこから追い詰められるとはどういうことなのか。追い詰められた人々がどんな力を発揮するのか?ということを学ぶことができる。
面白さ破格! これはリメイクしたくなる。部分的にも、全体通してでも。
でも、日本ではリメイクしないでね。これだけの役者を揃えられないから。
とにかく、侍が格好良くて、気持ちよい。
そこに惹かれる。
人格者の知将・勘兵衛。外から戻った勘兵衛に、七兵衛が当然の如く「すすぎを」と立ち上がるだけで、元は格のある家の出と知らせる。
とはいえ、人格者といえど、リーダーは時に敬われ持ち上げられるかと思えば、些細なことで恨まれ背かれる。そこを絶妙にフォローするもう一人の人格者の知将・五郎兵衛。この五郎兵衛が、勘兵衛の人柄に惹かれていて、出すぎないのが良い。
勘兵衛の古女房・七郎次。勘兵衛からこの戦いに誘われて、仔細も聞かずに応じる。「今度こそ死ぬかもしれぬ」にも、一瞬真顔の沈黙はあれど、笑ってほほ笑むだけ。格好いい!!! それだけでなく、自分が率いる農民チームを常に気遣い、元気づける。怖気ることは即、死だから。竹槍練習よりも、「走れなくなったら死だ」という心構えを教えるのが、歴戦の兵であり、農民を思うアドバイスで心に沁みる。
対して、青臭さの残る勝四郎。子犬のようだ。一番弟子を自認しているが、七郎次には後れを取ってしまう。弟子の役目を果たしきれない、豊かな郷士の末っ子という甘さ・自由さも残している。初めて、人が死ぬ時を見た時の反応、人を殺してしまった時の反応が初々しい。
求道者・久蔵。己の能力に求められる役目を黙々とこなす。勘兵衛が勝四郎に郷土に帰るように諭すシーンでの台詞を聞いている表情が何とも言えない。そして、勘兵衛に心酔していた勝四郎から絶賛された時の反応がかわいい。
ムードメーカー・平八。「子どもだって、大人扱いしてやれば、へたな大人以上に働く」と勝四郎の仲間入りを、「なんとかと鋏は使いよう」と菊千代の仲間入りを助ける。菊千代とは別の意味で頓智が効いている。菊千代が家系図を出したときに、勘兵衛の後ろで、指を折って、菊千代の年を確かめているところがかわいい。
トリックスター・菊千代。その破天荒なふるまいで、活路を開いたり、窮地に陥ったり、大切なメンバーを失ったり。勝四郎よりオミソ扱いされるが、侍仲間に入れただけで、嬉しいのか。彼なりに一生懸命ではある。感情表出も派手。他の侍たちが感情を封印して勝ち目を考えていることとのバランスが良い。勘兵衛に叱られてシュンとするところもかわいい。
そして、菊千代を除く侍の立ち振る舞いがこれまたキレッキレである。
全力疾走しているときも、陸上選手のように前かがみでなく、上半身はきちんと立て、目の前の状況を判断しながら、腰を落とし、腰のものがぶらつかないように支えながら走る。
勘兵衛演じる志村氏も、動くとなると機敏で驚いた。剣や弓の扱いも堂に入ったものである。驚いたが、まだ未見だが『姿三四郎』で主人公の好敵手を演じられていたなと思い出す。
七郎次を演じる加東氏。まだ、『羅生門』『用心棒』『早春』『ここに泉あり』『浮雲』くらいしか拝見していないが、大変失礼ながら、こんなに格好いい加東氏は初めて。
対して、菊千代演じる三船氏。わざと大ぶりで泥臭い演技をする。『羅生門』の時にもライオンとかの動物を意識して演じられたと聞くが、この映画もその延長であろうか。尤もライオンと言うより、孫悟空であるが。佐々木小次郎かくやという長い刀を持ち歩くが、実際の戦闘には、落ち武者狩りや敵から奪った普通の刀を何本も用意して対戦。『羅生門』と違うのは、今回はコメディセンス全開。そして、ふんどし姿に甲冑をまとい、その足の長さ、お尻を始めとする肌に美しさ、体操選手?と言いたくなるような体の動きに目が奪われる。
こんな侍集団だが、こんな不利で益にもならぬ戦いに力を貸すだけあって、”侍”然としてふんぞり返っていないのがすごい。ちゃんと目の前の相手の意見をきく。辛酸舐めつくして生き抜いてきた心の広さなのだろうか。
利吉達に相談されて勝ち目がないと勘兵衛が断った時に、人足から、利吉達が用意した報酬の意味を聞き、その価値と村人の願いに、はっとして、考え直す。
せっかく来てやった村なのに、その村の歓待にむっとするところもかわいい。儀作が一生懸命言い訳するのも「これで、何をしろというのだ(守れない)」と突っぱねる。なれど、半鐘(板木)が鳴るや、侍達の機敏なこと。惚れてしまう。そして、菊千代と儀作のやりとりに笑い、村を守ることにする。
そして、村人の落ち武者狩りを知って…。久蔵の言葉も当然であろう。久蔵たちの同胞を殺して奪ったものなのだから。そして彼ら自身の忘れられぬ記憶。だが、この時も、菊千代の言葉に思い直す。
村人が約束した報酬でさえ、村の現状を見て、弱きものに分け与える。勝四郎の行いからの流れが良い。
”侍”はこうあるべきと言うのにも、とらわれない。トリックスターである菊千代の言動は、自分を大きく見せたいのか、とても大げさで騒がしい。そしてその大言壮語にも関わらず、できていないことも。できていないだけでなく、手抜きすることも。正直、近くに居たらはた迷惑でもある。だが、勘兵衛たちは命令違反やさぼりには叱咤するが、平八のリフレーミング的な意味づけの助けもあり、菊千代のことを許容してしまう。排除するのではなく、受け入れる。笑いに変える。懐の大きさよ。
侍達は、そんな場面が多い。状況だけを見れば、不安で先行き真っ暗なのに、常に笑いを忘れない。おおらかな勘兵衛・五郎兵衛・平八だけではない。生真面目そうな久蔵・七郎次も大口を開けて、村人と一緒に笑う。決戦前でカチコチになっている村人に対しては「(勝四郎も)夕べからもう大人だ」といじって、笑いを取って、わざと緊張を緩める。菊千代も、彼らにいじられても、すねることもあるが、許容している。不思議な輪ができている。
そんな侍と村人のアンサンブル。
一見、ドンパチのアクション/戦争映画に思える。
そういうふうに、楽しむのもありだ。
でも、侍の生き様を描くとともに、村を始めとする社会を描いた映画だと思う。
村人の談合から始まる。
爺様・儀作の提案で侍探しが始まる。
一番積極的なのは利吉。そのわけは、映画の中盤の明かされる。
侍頼みにしたいのに、父とはしては当然と言えば当然の不安から、村を侍拒否に陥れるのは万造。
その間を取り持つ茂助。村を守る作戦上、自分の家が犠牲になると知った時は反発するが、実際に野武士が襲来、家を焼かれた時には、それで慌てふためく村人に持ち場に戻るように叱咤する。個人的には次期村長に推したい。
与平はコメディリリーフ。がちがちの3人に対して、ドジをしたり、泣き言を言ったりして、なんだかんだ言って仲を取り持っている。演じるのは左卜全氏。集団訓練時の、あの間の外し方が芸術的。侍への報酬を盗まれたりするが、村では唯一?馬を持っている。落ち武者狩りで手に入れた槍を持ってきて、落ち武者狩りをばらしてしまうという、物語が動くきっかけを作る。
その4人を中心に、その他大勢の、戦乱の世での生き様を描く。
生き方が違い、意見が分かれても、爺様を始めとする仲裁の力を借りて、その時なりの落としどころを見つけて共存。
婆様の言動。野武士との取引・犠牲。野武士に囚われていた女性が切ない(涙)。
村人の仲裁をしていた儀作とその息子夫婦の最期。譲れぬもの。
常に、したたかに、自分たちが生きていく方法を模索し実行する。決戦の前、勘兵衛と五郎兵衛が「菊千代のいうとおりだな」と苦笑するように。
物語の展開も秀逸。
前半はこんな無理な願いに応えてくれる人はいるのか、いても烏合の衆では戦えない。どんな人が集まってくるのか。どう集めるのか。どう見極めるのかに心躍らされる。また、村内部の分断と結束もどうなっていくのかにハラハラさせられる。
後半は、利吉の秘密、野武士の隠れ家襲来という派手なシーンはあれど、斥候、作戦遂行、ロマンスと地道な場面が続く。そしてためにためて、壮絶な決戦、エンディングと流れが良い。
ラスト。
村の様子と、侍の姿。
未来に続く慶びと、達成感はあるものの、失ったものも大きい。その時感じるのは虚無感か?
しのの決断。
有名なラストの言葉が心に沁みる。
でも、私は以下のようにも思うんだ。
★ ★ ★
≪以下、ネタバレに触れています≫
オープニングの、戦乱に巻き込まれ、窶れはてた村人の表情と、
ラストの、自信に満ち溢れ、喜びに満ちた村人の表情の違い。
単に、野武士がいなくなって、平和に農作ができる喜びだけではないと思うんだ。
侍達とのやり取りの中で、侍たちも農民に対する意識が変わったであろうが、
農民の方にも、侍にもいろいろな人がいると意識が変わったであろうが、
ただ、侍に守ってもらったのではなく、一緒に戦って野武士をやっつけたという自信も得たのではないか。
この村人の自信に満ちた表情は、侍と過ごした日々の賜物であると思うんだ。
自分たちには絶対にできないという思いにとらわれていた人々が、できたんだという自信を得た表情だと。そんな自信を村人に与えたのは侍達。
もし、侍たちが野武士を追い払う手助けをしなかったら、村人は怯えた表情で田植えをしていたはずだから。
だから、勝ったのは村人と侍達だと私は思う。
尤も、もう一つの考え方として、農民の雑草の如くの生命力を「勝ったのは農民」と言っているのかもしれない。
ついこの前まで、怯えていたのに、村人にも犠牲者は出ているのに、気持ちを切り替えて、祝い唄を歌いながら村総出で田植えをしている。その逞しさを言っているのだろうか。
何かを生み出すことのできる農民。生きるために、したたかな農民。
奪うことしかできない侍。
その生業のことを言っているのだろうか。
いろいろな複合的な意味に捉えられ、心地の良い迷宮をさまよってしまう。
それでも、明るい村人の顔や歌が一つの達成感と始まりを感じさせてくれ、
鑑賞後にすぐにリピートしたくなる。
(台詞は思い出し引用。日本語字幕なしとありとを見たけれど、大方の感想は変わらなかった)
日本映画の最高峰!影響与えまくりの超名作!
「侍タイムスリッパー」を見てから、無性に時代劇が観たくなった。
そこで、満を持しての名作の登場です!久し振りの鑑賞でしたが、ホンっと素晴らしい。何回見ても楽しめます。
モノクロ映像で、古臭さはどうしようもないものですが、この画面からあふれでる迫力?って言えばいいんでしょうか。とにかく大興奮です。
オープニングからの音楽も最高!思いっきり、昔懐かしいって感じの音ですが、これがまた良い。もちろん、場面の途中途中で差し込まれるサントラも絶妙のタイミングで名曲揃いでした。
志村さん、三船さんを筆頭とした、今は亡き役者さん達の熱演も素晴らしい。
セリフがイマイチ聞き取れないって部分もありますが、そんなの気にならないほど、作品の中にのめり込んだ感じです。
もちろん、途中休憩が入るほど、長尺な映画ではありますが、無駄な場面が無いってほどに魅入っちゃいました。
最初のメンバー集めから、百姓たちとの交流、そして、クライマックスの戦闘シーン。 まさに世界に誇る日本映画の名作!黒澤監督の名前を世界に知らしめる1本です。
【今さらネタバレってことも無いかもしれませんが】
とにかく、クライマックスの戦闘シーンは大迫力です。 ひとり、またひとりと野武士たちがやられていく様が凄い!逃げ惑う野武士を大勢の百姓たちが追い詰めて滅多刺しにする。
それに伴い、味方も次々と命を落としていく。
最終決戦の大雨の中の戦いは特に凄い!まさに歴史に残る名場面の数々。生と死の狭間をまざまざと見せ付けられる感じがする。 ホンッと素晴らしいの一言に尽きる一本でした。
1954年、自分が生まれるはるか前の年ですが、この年には「ゴジラ」も公開されています。後の映画界に大いに影響を与えた2本の邦画が生まれた年として記念すべき年じゃないだろうか。
3時間をまったく退屈させないストーリーとキャラが魅力
白黒映画なんてつまらない、15年前まではそう思っていた。しかし、高校生のとき映画の授業で観てあまりにも面白くて衝撃を受けた。以来、定期的に鑑賞している。
3時間をまったく退屈させないストーリーとキャラが魅力。話は強力な仲間を集めて悪に立ち向かうという流れでシンプル。今の少年漫画やRPGゲームでもよくある構成で古臭さを感じずとっつきやすい。
当時の百姓の扱いの酷さも描かれ可哀想に思えてくる。野武士狩りをしてた闇の部分もあり、良い所だけでなく悪い一面を見せたことでより人間らしくリアルに感じた。
特に好きなキャラは久蔵と菊千代。
久蔵は無口でクール、やることは黙って済ませるのがかっこいい。特に種子島を1人でささっと取ってくるのはシビれる。勝四郎が惚れる気持ち分かるなぁ。
菊千代は動きが面白い。ぴょんぴょん跳ねたり、奇声を上げたり、人間というよりはまるで動物のようだ。
トリッキーなキャラかと思いきや、カンカン鳴らして百姓を集めたり機転を効かせて活躍する場面もありギャップが良い。
百姓の落武者狩りがバレた時、涙ながらに百姓の気持ちを代弁するシーンは何度見ても感動する。
たまに無償に観たくなるので、これからも何度も見返すことになるだろう。5点じゃ足りない、10点をあげたい傑作。
自分史上最高の日本映画
・3時間半にもかかわらす無駄なシーンが一切無い。
・戦シーン序盤で七人のうちの1人が死んでしまう。これにより残りの侍が死にはしないかとハラハラしながら観ることになる。
・自分は侍を集めるシーンが特に好きだ。1人1人集まる度にワクワクする。
・お荷物的な存在だった菊千代は侍と百姓が団結するうえで重要な存在となっていく。
・七人の侍の中で1番好きなのは片山五郎兵衛。
本当に勝ったのはだれ?
あまりにも有名だからいまさら自分ごときが書くこともない気さえしてしまう。
しちめんどくさいこと抜きにしちゃってもおもしろい。
それは何故か。
スクリーンの中の人間がどれも生き生きとしているからだと思う。
おのおのの事情を抱えながら立ち上がる姿に、現代のわれわれも共感する部分、あります。
最後に勝利を勝ち得たのは農民なのか武士なのか盗賊なのか。
私は何事もなかったかのように戻っていく「日常」を持ってる人たちだろうと思いました。
もう少し短かったらなあ。
善さと不条理みたいなもの
【あらすじ】
戦国時代後期の日本は、士農工商の身分はすでにはっきりと現れかつ戦に負けた武士たちも多く、野武士と呼ばれる盗賊団になる集団も蔓延っていた。野武士が村を襲うことを画作していることを知った農民たちは、村を守るため、下級武士に村の護衛を依頼することを思いつく。十分な報酬を準備できるわけのない仕事であったが、話を聞いた勘兵衛がその話を承諾する。米を作っているはずの農民は稗しか食べられず、その米を食べる武士が農民を守らないのか?という不条理を考えるのである。
こうして仲間探しを始める勘兵衛であるが、彼自身の人柄もあり、村の護衛に必要と思われる7人は次第に揃う。
農民は武士に護衛を依頼をしつつも、抑圧する階級である武士に不信と恐怖を持っており、村に到着した一行をまったく歓迎しない。そこで、一味に加わっていた菊千代は野武士の襲来を装い農民と武士との対面させることに成功すると、野武士の攻撃に備え準備を進めていく中で、この両者の結束が生まれてくる。けれども互いを知るほどに、農民への武士の不信、また逆の武士から農民への無自覚な侮蔑も炙り出された。
いよいよ野武士が襲いかかってくる。勘兵衛の優れた統率力で徐々に野武士は数を減らす。しかし戦況は悪くないながら、農民と武士も痛手を負う。最終決戦を終え、野武士を撃退した村に残ったのは、田植えを始める農民と、3人の侍であった。
【感想】
そのタイトルは聞いたことがありながら、見たことがない名作と呼ばれる映画。こういうものは、結局のところ観た方が良いんだなと、素直に思いました。200分越えの長編ながら、飽きるということがなかった。本当にすごい映画なんですね。すごく面白かったです。
何が面白いのか。登場人物の魅力ということを挙げたいです。勘兵衛を始め、7人の武士たちはそれぞれにはっきりとした個性を持っています。経験豊富で統率力があり、大きな器と線を引く決断力を持った勘兵衛(志村喬)が1人目っていうのが良いんでしょうね。他の武士がその人となりを信頼していくように、こちらもついつい勘兵衛の行動に引き込まれていくんです。その勘兵衛を取り巻く6人についても皆が魅力的で、例えば農民出身の菊千代(三船敏郎)には野蛮でありながら、弱者であったが故の純粋な正義感には心打たれるものがありますし、五郎兵衛(稲葉義男)勘兵衛をサポートする大らかな存在感もそうですし、とにかく農民も含め、それぞれが魅力的。そこに個人単位の交流が描かれるのも微笑ましくて良いんです。
けれど、次第に登場人物だけでなく僕らも驚くような事実が垣間見えてきます。虐げられるだけの存在のように見えた農民の思わぬ強かさと残酷さ、一番若く、若いが故に農民の女との恋沙汰で問題を起こす勝四郎(木村功)など、それぞれの個性でありながら、しかし普遍的に人間が持つ善と悪。常にその両面を持った存在である人間が映画には描かれていきます。途中、戦に備えて旗を作るシーンがあります。武士を表す6つの○と△がひとつ、そして農民全部を表すおおきな「た」の文字。これは、それぞれのキャラクターが持つ善徳と悪徳を表すような象徴性を持っているようにも思えました。
昔の映画ですし、台詞もよく聞き取れなかったり、カツラのクオリティも最初は気になったんです、正直。けれどそんなことは問題ないんでしょうね。
ダイナミックな戦闘シーンもちろんすごいです。けどもっと良かったと思うのは、今の僕たちにも共感できるような人間の善さ醜さが、魅力的な登場人物を通して素朴でリアルに感じられることです。
合間に挟まれる「休憩」のインパクトもすごい、、!
全30件中、1~20件目を表示