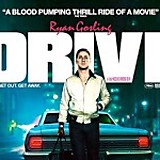七人の侍のレビュー・感想・評価
全223件中、1~20件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
1954年製作の黒澤明監督作品『七人の侍』、新4Kリマスター版を「午前十時の映画祭」で鑑賞しました。
改めて映画の内容を説明することはないでしょう。
2016年の4Kデジタル版でも音が良くなったと感じたが、今回はさらに向上。
台詞のほとんどが聴き取れる。
ゆえに、休憩までの前半がすこぶる面白くなった。
なにせ、フィルム版だと百姓たちの台詞の多くが聞き取れなかったから。
画質も恐ろしく向上。
毛穴のひとつひとつが見えるほど。
汗のぎらぎら感も凄まじい。
ただし、カットによっては、かつらの盛り上がりなどもわかる。
前回鑑賞時も感じたが、歳を経てから観ると、爽快感が乏しく感じられる。
これは、戦いのリアリズム、特に農民の戦いをおぞましく感じたからでしょうね。
さて、全長版は今回も含め何度か観ているが、短縮版はどうだったのかしらん、などとどうでもいいことが気にかかった。
自身の鑑賞履歴初期に16mm版で2度観ているが、これが160分のバージョンだったかもしれない。
全長版リバイバルの際に、前半、記憶のないシーンがあった覚えがするので。
なお、16mm版の鑑賞1度目は、映写機の故障で野武士が来るところに至らず中止。
2度目になって、全編通しで観た。
以下、2016年鑑賞時のレビュー。
『生きる』の続いて「午前十時の映画祭」での鑑賞は『七人の侍』。
20年ほど前にニュープリントの全長版(207分)のを2度ほど鑑賞しているが、それ以来か。
前回はセリフの大半が聞き取れなかったが、今回はよくわかる。
画面の陰影もくっきりしており、今後はこの4Kデジタル版が決定版となるだろう。
さて、映画。
戦国の世、収穫期に野武士の集団に略奪される山村あり。
業を煮やした村人は「野武士討つべし」との長老の言葉のもと、腹をすかせた侍を雇うことにした・・・
というハナシは有名なので書くまでもない。
映画はすこぶる面白い。
特に面白いのは前半で、侍を集める件が面白い。
そして、村をどのように守るか、墨書きの地図と照らして、ここをこのように守る、という戦術を考えるあたりまでが特筆すべきだろう。
この前半、ほとんど活劇らしい要素はなく、それゆえ黒澤明のドラマツルギーが凝縮しているともいえる。
ドラマにアクションは要らない。
必要なのは、モティベーションとエモーションといわんばかりに、名台詞とともにそのふたつを描いていく。
曰く、長老の「討つべし」。
曰く、勘兵衛の「この飯、おろそかにか食わぬぞ」。
曰く、勘兵衛が果し合いをする久蔵とその相手をみて、「無益な。結果はみえておる」。
曰く、勘兵衛が菊千代をみて「おぬし、侍か」などなど。
後半は、野武士と侍+百姓の戦が描かれるが、ドラマとしては百姓を出自とする菊千代の物語ぐらいしかないが、ほとんどドラマらしいドラマがなく1時間以上も保たせるのは尋常でない脚本ともいえる。
そもそも、村を守るのに何故七人必要なのかをあらかじめ説明しておき、40騎いる野武士をどのように倒していくかを克明に描いていく。
それも、説明的な説明を用いずに。
ここいらは、後に模倣乱造される「七人もの」アクションと一線を画し、この映画をこの種の活劇の頂点に押し上げている所以である。
まぁ、そんなことは20年前にも思ったことなので、今回、再鑑賞して思ったことを少々。
黒澤明の監督作のフィルモグラフィでいうと『羅生門』(1950)、『白痴』(1951)、『生きる』(1952)ときて、本作(1954)である。
その後が『生きものの記録』(1955)である。
個人的には、『生きものの記録』を「黒澤明作品の中で、黒澤らしいヒューマニズムに溢れた作品」として推すのだけれど、『生きる』以降、黒澤のヒューマニズムが少しずつ揺らいでいるような感じがする。
これは『生きる』の再鑑賞のときにも感じたことだが、『素晴らしき日曜日』(1947)のように、市民(小市民)に激励の言葉をかけるのを止すようになっている。
本『七人の侍』にける小市民の代表は、農民である。
そして、七人の侍たちのなかにも、彼らに近い人物が「ふたり」いる。
ひとりは三船敏郎演ずる菊千代だが、もうひとりは千秋実の平八である。
平八は、腕は「中の下」であるが「苦しい時には頼りになる(場を和ませる)性格」と評せられるにもかかわらず、野武士との初戦で敵方の鉄砲によってあっけなく死んでしまう。
そして、その「苦しいとき」に場を和ませる役は、求道者然とした久蔵(宮口精二)が代わることになる。
小市民的キャラクターをあっさりと、もっとも武士的人物に肩代わりさせてしまう。
もうひとりの菊千代については、いわずもがなな扱いで、映画を快活に進めるトリックスターであり、その出自を百姓だと前半に明らかにし、かつ後半に入ってすぐの水車小屋の見せ場で、焼き討ちにあった水車小屋で生き残った赤子を抱きしめて、「こいつは俺だ。俺も、こうだったんだ」という絶叫を描きながらも、彼は最後むなしく、かつあっけなく死んでいく。
その上、彼に「百姓はずるいんだ」云々というすこぶる的を射た台詞も吐かせつつである。
さらには、合戦のシーン。
戦術を立てるのは、侍(中心は志村喬演じる勘兵衛)であるが、野武士たちに止めを刺すのは武鑓を持った百姓たち。
終盤では、追い詰められた野武士に、百姓の女房たちが鋤鍬を持って止めを刺そうと襲いかかる。
さながらホラー映画のように。
小市民に激励の言葉をかけていた黒澤は、前作の『生きる』と同じく、この時期、小市民をかなり嫌悪しているのではありますまいか。
ラストは、晴れ晴れとした田植え歌が流れるのではあるが、まるで心は晴れない。
4つの侍たちの土饅頭と十数の百姓たちの土饅頭を前に勘兵衛がいう台詞「また負け戦だったな。勝ったのは、あの百姓たちだ。儂たちではない」は、いまなら「また負け戦だったな。勝った百姓たちの喜びも、いっ時に過ぎぬ」というとこになるのかもしれない。
観る齢、観る時期により、感じ方が異なる作品かもしれませんね。
時代が、人が、技術が進んでも絶対に追いつけない映画
世界トップクラスとして認められている
日本映画で“動”を感じたければこの映画
“静”ならTOKYO STORY でしょうね。
七人の侍の中の距離感
人と人の慈しみ合いと絆
自己犠牲の果ての感謝
表現する人達の情熱と姿
それが詰まっている。
極限状態で作られた
そういう映画です。
※
迫力が違う
今尚間違いなく傑作
採点4.8
これは本当に見事。
こうしてスクリーンで観れるとは、しかも4Kリマスターを大きなスクリーンでですよ。これは嬉しい。
今観ても大胆なカメラワークやダイナミックな演出に殺陣。それと皆の分厚い芝居。
黒澤作品のレギュラーと言える志村喬はストーリーテラーのどっしりとした立ち振る舞い、反して野猿のような自由奔放な芝居で魅了する三船敏郎。この相反する二人の相乗効果が凄い。
そして個人的に宮口精二演ずる久蔵です。最初から最後まで最高に格好良い。
剣術の経験があるのか、立ち合いで見せた後ろ下段の構えなどはかなりでした。
あとDVD(前後)でしか観たことがなかったのですが、劇場版ではインターミッションあったのですね?これは驚きました。
前後に分けながらも大きく三遍に分かれた作り、信綱や卜伝のエピソードを盛り込んだりと脇も緩めぬものすごい意欲作。実に驚くばかりです。
スクリーンで観れて本当嬉しかった、今尚間違いなく傑作です。
昔の俳優さんは体力あったんだなぁ
んー、長かった。良かったけど長かった。途中休憩があるのが嬉しかった。スクリーン上に「休憩」の字幕が出てBGMが流れて5分、そこから上映中断して5分の計10分、トイレに行って一息ついて上映再開。おかげで中だるみせずに鑑賞することができた。
ウラ話は知らないけど俳優、スタッフみんなで一本の作品を作り上げたというエネルギーが画面を通して伝わってきた。志村喬と三船敏郎、静と動で正反対だがその存在感がスゴい。志村喬は戦を何度も経験し知識も経験も豊富な正統的な武士、三船敏郎は若くぶっきらぼうで危なっかしいが勇気があり力もある百姓出の武士。他の武士たちもそれぞれに魅力的で話を引き立てていた。
最後は百姓&武士側が勝利するが志村喬と数々の戦をともにしてきた加東大介、一番若い木村功の3人以外の他の武士たちは戦死してしまう。「勝ったのは百姓で我々ではない」という志村喬の言葉に考えさせられた。一見貧乏そうに見える農村だが落ち武者狩りで得た鎧や槍、弓矢などの武器、ふんだんにある米や酒。百姓に足りなかったのはそれらを活用できる力の存在だった。七人の侍は百姓にうまく利用されたとみることもできる。志村喬の言葉はその虚しさが込められているように感じた。
タイトルの意味は俳優さんがやたらと走っている印象が強かったから。とにかく皆さんお疲れ様でした。
七人の侍と荒野の7人どっちがお好き?
念願かなって、ようやく観れた!
私、黒澤作品、初です。
途中休憩10分が入るが間延びすることなく、ラストもよかった。
日本映画のパワフルさが詰まっていた。
子どもの頃は、毎日家族で時代劇を観ていた。
夕方に再放送で、夜には人気の時代劇が曜日ごとに放映されていた。
端正なたたずまいの「大岡越前」加藤剛さん。
男性を初めて色っぽいと感じた「遠山の金さん」杉良太郎さん。
あり得ない設定なのに、毎回将軍と分かるシーンが大好きだった「暴れん坊将軍」松平健さん。
親は放任でも、昭和の子どもがまともに育ったのは、時代劇で何度も何度も観て、勧善懲悪を刷り込まれたからかもしれません。
「七人の侍」の時代背景はあまりよく分からなかったけれど、こんなふうに命を懸けた戦いを経験することは、私はないだろう。
だからこそ、この平穏な毎日の真の価値を実感しないまま死ぬのかもしれないと思った。
ぜひ映画館で(4kリマスター午前10時の映画祭)
世界を魅了した三船敏郎の最強演技
トイレ休憩は稲刈り前
2025年映画館鑑賞105作品目
11月3日(月)イオンシネマ新利府
ハッパーマンデー1100円
新4Kリマスター版
モノクロ
1954年(昭和29年)初公開
監督と脚本は『酔いどれ天使』『野良犬』『羅生門』『生きる』『蜘蛛巣城』『隠し砦の三悪人』『用心棒』『椿三十郎』『天国と地獄』『赤ひげ』『影武者』『乱』の黒澤明
脚本は他に『羅生門』『生きる』『蜘蛛巣城』『隠し砦の三悪人』『八甲田山』の橋本忍と『隠し砦の三悪人』『椿三十郎』『天国と地獄』『赤ひげ』『乱』の小国英雄
粗筋
時代背景は戦国時代
天正14年(1586年)
貧しい農村では村人たちが野武士たちの略奪に苦しんでいた
村人たちはこれ以上我慢ができなり村の長老に相談
その結果村人の有志4名が町に出て村を野武士たちから守ってくれる侍を勧誘することに
報酬は白米の握り飯のみ
なんやかんやで七人の侍が集まり村人と共に野武士たちを迎え討つ
世界に最も影響を与えた邦画作品
日本映画代表
不朽の名作
3時間27分
映画館でトイレ休憩がある作品を鑑賞するのは今作が初めて
映画館以外のスクリーンとなるとソフト化(DVD化)される前に大谷翔平の地元奥州市水沢の公共施設で鑑賞した『黒部の太陽』が初めてだが
冒頭を除き七人の侍が守る村に野武士が攻めてくるまではコメディー路線
平八が戦死してからは緊迫したシリアス路線
最大の見せ場は土砂降りの中で決戦
もはや俺ごときが語るに及ばない
その前に平八と五郎兵衛が亡くなっている
七人中四人が亡くなっているがいずれも銃殺
村人も数名が矢で射抜かれるなどして亡くなっている
実質主人公は志村喬演じる島田勘兵衛
三船敏郎演じる菊千代はコメディーリリーフ
椿三十郎同様通称で本名ではない
左卜全が良い味を出している
村娘代表として志乃を演じた津村恵子
別嬪さん
侍から娘を守るため父に髪を切られ男装に
七人の侍の最年少勝四郎と結ばれる
やることやって小屋から出てきてなぜかおどおどしている勝四郎
遅れて出てきた志乃は処女喪失ながら「良かったわ」と言わんばかりに余韻に耽る色っぽさ
濡れ場で惜しみなくヌードを披露しなくても十分にそれと表現できる俳優の演技力と監督の演出力が見事
平和とはなんなのか
単に戦争がない状態なのか
いやそうではない
誇りを取り戻すため
本当の意味で「いきる」ため
我々の日々の生活を守るため
野武士が度々攻めてきて命乞いする他なくその代わりに食糧や女たちを奪われる無秩序な状態は平和ではない
なぜウクライナはロシアと戦い続けるのか
なぜイスラエルは建国以来平和が訪れないのか
ヒントはこの映画にもある
配役
七人の侍のリーダー格で冷静沈着温厚な性格で経験豊富な島田勘兵衛に志村喬
七人の侍の一人で百姓出身の荒くれ者で半人前の菊千代に三船敏郎
七人の侍の一人で裕福な武家出身だが末っ子のため家を出て旅の末に勘兵衛に出会い師事する半人前で最年少の岡本勝四郎に木村功
七人の侍の一人で勘兵衛の人柄に惚れて仲間入りし参謀的ポジションを担う片山五郎兵衛に稲葉義男
七人の侍の一人で元々勘兵衛の股肱で過去の戦で離れ離れになったが再会した七郎次に加東大介
七人の侍の一人で剣の腕は中の下だが冗談をよく言うムードメーカーで「◯6△1た」の軍旗を制作した林田平八に千秋実
七人の侍の一人で修行の旅の途中で勘兵衛に誘われ仲間に加わった凄腕の剣客の久蔵に宮口精二
離れの水車小屋に住む村の知恵袋的存在の長老(爺様)の儀作に高堂国典
村に住む若い百姓で女房を野武士に奪われたためか侍探しに最も積極的な利吉に土屋嘉男
村に住む壮年の百姓で利吉たちと共に浪人を探した茂助に小杉義男
戦うことには消極的だが儀作の提案で渋々利吉と共に浪人探しに行く壮年の村の百姓で志乃の父親の万造に藤原釜足
村に住むマヌケな中年の百姓で利吉と茂助と万造と共に侍探しに出かけた与平に左卜全
万造の娘で勝四郎を好きになる志乃に津島恵子
収穫物の代わりに野武士に強奪された利吉の女房に島崎雪子
柴刈りの最中に野武士を最初に目撃する村人の伍作に榊田敬二
儀作の息子に熊谷二良
息子の嫁に登山晴子
かつて野武士に家族を殺された経験を持つ久右衛門の婆様にキクさん
久右衛門の婆様の声に三好栄子
百姓に峰三平
百姓に松下正秀
百姓に池田兼雄
百姓に川越一平
百姓に鈴川二郎
百姓に夏木順平
百姓に神山恭一
百姓に鈴木治夫
百姓に天野五郎
百姓に吉頂寺晃
百姓に岩本弘司
百姓に山田彰
百姓に今井和雄
百姓に中西英介
百姓に伊原徳
百姓に大塚秀雄
百姓に大江秀
百姓に大西康雄
百姓に下田巡
百姓に河辺昌義
百姓に加藤茂雄
百姓に川又吉一
百姓に篠原正記
百姓に松本光男
百姓に海上日出男
百姓に田武謙三
百姓に山本廉
百姓女に本間文子
百姓女に小野松枝
百姓女に一万慈多鶴恵
百姓女に大城政子
百姓女に小沢経子
百姓女に須川操
百姓女に高原とり子
百姓の娘に上遠野路子
百姓の娘に中野俊子
百姓の娘に東静子
百姓の娘に森啓子
百姓の娘に河辺美智子
百姓の娘に戸川夕子
百姓の娘に北野八代子
百姓の娘に記平佳枝
町の人足Aに多々良純
町の人足Bに堺左千夫
町の人足Cに関猛
木賃宿で売れ残った饅頭を売りに来た饅頭売に渡辺篤
木賃宿の客の琵琶法師に上山草人
盗賊の人質になった子供を助けるためにか僧侶に扮する勘兵衛の剃髪を行い袈裟と数珠を貸す僧侶に千葉一郎
豪農家の子供を人質に小屋に立てこもる盗人に東野英治郎
勘兵衛に誘われるも村助けを断る強そうな浪人に山形勲
久蔵と果し合いをし竹刀で相打ちを主張するも否定され逆上し真剣勝負をするも惨殺される浪人に牧壮吉
村助けをお願いした利吉を蹴飛ばす長槍を持った浪人に清水元
平八に薪割りをさせていた茶屋の親爺に杉寛
木賃宿の客の一人で博打も剣術もからっきし弱い情けない浪人に林幹
豪農家の祖父に小川虎之助
豪農家の娘に千石規子
豪農家の亭主に安芸津広
豪農の前の百姓に堤康久
豪農の前の百姓に片桐常雄
豪農の前の百姓に岡豊
豪農の前の百姓女に馬野都留子
町を歩く浪人に仲代達矢
町を歩く浪人に宇津井健
町を歩く浪人に伊藤久哉
町を歩く浪人に加藤武
四十人の野武士集団を率いる頭目に高木新平
片目に眼帯をつけた副頭目に大友伸
村を偵察に来たが菊千代に捕獲され村に連れていかれる斥候Aに上田吉二郎
村を偵察に来たが待ち伏せしていた久蔵に斬られる斥候Bに谷晃
村を偵察に来たが待ち伏せしていた久蔵に斬られる斥候Cに中島春雄
鉄砲の野武士に高原駿雄
屋根の野武士に大久保正信
離脱する野武士に大村千吉
離脱する野武士に成田孝
野武士に西條悦郎
野武士に伊藤実
野武士に坂本晴哉
野武士に桜井巨郎
野武士に渋谷英男
野武士に鴨田清
野武士に広瀬正一
野武士に宇野晃司
野武士に橘正晃
野武士に坪野鎌之
野武士に中恭二
野武士に宮川珍男兒
野武士に砂川繁視
野武士に草間璋夫
野武士に天見竜太郎
野武士に三上淳
映画の真骨頂!
義を見てせざるは勇無きなり…但し、言うは易く行うは難し。
日本映画の金字塔が一つ。確実に。
噺のプロットは王道中の王道……ん?てか、今作が王道元?😁
強者による多勢に無勢で困窮している弱者の為に、少数精鋭が助太刀する…
多額の報酬や褒賞なんてもモノは全く無い、立身出世にも全く関係無い。
それでも…助ける心粋。
滾るよね、燃えるよね、奮えるよね。
そして、憐れな筈の百姓も…ただ哀れな存在じゃない。
弱者面していても、その言動には一癖も二癖もある。
近くで戦が起きれば、機を見計らって落ち武者狩りをして装備品を掠め盗るし、米を出せ!麦を出せ!と云われても平気の平左で、嘘を付いて「ない!」と云い…その実、床下や納屋の土の下や時には墓の下にまで穀物やら酒やら何でも備蓄する強かさや狡賢さを持っている…
途中…侍達と百姓達の間に、そういった蟠りが出来た時、
二つの相容れない水と油な両者を取り持ち、マヨネーズに於ける酢みたいな貴重な存在となったのが、
野犬の様に荒々しく侍の作法も常識もそっちのけだった菊千代と云う異端。
彼は云う…
「お前ら!百姓を何だと思ってんだ!仏様とでも思ったか?奴らほど悪ズレした生き物はいないんだ!平気でウソはつくし、落ち武者狩りもするし、米や麦や小豆、酒だって…探せばどっかから必ず出てくる!何でも隠すし、卑怯で、卑屈で、見てるコッチが泣けてくらぁ…でもな!連中をそんなケモノにしたのは、何処のどいつだと思う!お前ら侍だよ!…戦の度に田畑は潰す!米でも何でも奪ってく!村の女には手を出す!歯向かえば殺してくる…じゃぁ、百姓は一体どうしたらいいってぇんだ!」と。
菊千代の魂の叫びにも似た涙混じりの独白に、他の侍達は、何かしら心当たりが有る風に神妙な面持ちになる…
日本人の弱さと強さ、邪なトコと清いトコと、何だかんだ総てが詰まっている様に思う。
侍をスカウトに来た4人の百姓達を、最初は鼻で嗤ってバカにしていた荒くれの人足三人衆も、嫌味を垂れながらも、彼らの苦心を理解しながら助太刀に二の足を踏む勘兵衛らに…
「おい!この白飯を見ろよ!あんたら侍に白飯食わせる為に、コイツらは何を喰ってると思う?ヒエだけなんだぜ?…コイツらだってコレで精一杯なんだ!」
…と、助け舟を出す。
こういうところが観る者の胸を熱くする。
時として、大を助ける為に小を切り捨てる苦渋の決断を迫られる事が有るかもしれない…その時、無関係な連中は、涙を飲んで我慢した人々を、利他的な所作を美徳として美談として賞賛するかもしれない…
そんな胸糞悪い美辞麗句よりも、
利己的な言動はいつか己をも滅ぼすから…と、血反吐を吐く思いで、歯軋りしながら、自らを納得させた自分自身を誇りに思うしか無い。
それでも、その悔しさや苦悩を、ちゃんと見ている人は見ているし、分かち合おうと理解を示してくれる人もきっといる。
そういった何とも言えない人生の機微が、今作には沢山詰まっている。
今、この令和に、今作をリメイクしたら、どんな陳腐な駄作が生まれてしまうことやら。
だいたい…今じゃ、肉厚ちゅうか、、濃いぃぃぃ感じのアブラっぽい?ギラついた役者さんってめっきひ減っちゃったもんね。
中年以降の俳優さんも…皆んなイケメン、イケオジだし。
かといって、Vシネで893役ばっかやってる強面や悪人面な役者さんは野武士役に取っておきたいし、、
勘兵衛はどうせ役所さんで、五郎兵衛は堤さん、平八はムロさん、久蔵は佐藤健さん、七郎次が鈴木亮平さん、勝四郎は…童顔の若手イケメン俳優?
で、菊千代だよ、菊千代…当時の三船さんは、あの風貌で33歳か34歳…
いる?今のアラサー俳優で、菊千代役に耐えうる人…
まぁ、やっぱ無理だわな。
え?山崎賢人?…駄目だよ、ダメ!ダメ!…利吉でしょ、ピッタリなの。
じゃぁ、、山田孝之さん?……ん〜、ん~~、なんだかなぁ、
つか、皆んな全体的にキレイ過ぎるし、痩せ過ぎなんだよなぁ、スタイル良過ぎでさ。
結果、リメイク意味あんの?ってね。
漫画やアニメの実写化断固反対!ってのはあるけど、
実写のリメイク向いてないって、やっぱもう至高の完成形なんだよなぁ、原典が。
最高の映画を最高のクオリティで
4Kリマスターされたブルーレイは既に購入して家庭でも何度か鑑賞済みです。
何度かリマスターされてきた本作ですが、画面の傷やチラツキ、ハイライトの飛びとシャドーの潰れ、音声がが大きく改善され、これが最終版と言えるほど非常に観やすくなりました。
私が名画座で初めてこの作品を観た時は画面の傷やノイズが著しく、さらに海外版で1時間位がカットされた非常に粗悪な物で、日本の映画に対する文化的価値観に失望したものです。
しかし 、今回の4Kリマスター版は70年以上前の作品とは思えないクオリティで、モノクロという点を除けば現代人の鑑賞にも十分耐えうるものだと思います。そして、出来るならば映画館の大スクリーンで大勢の観客の一緒にスペクタルと感動を共有しながら観ることをお勧めします。
因みに、昔から三船敏郎さんのセリフが聞き取れないというのが定説ですが、私には音の悪い頃から十分聞き取れました。逆に今回のリマスター版を通しても聞き取りづらいのが左卜全さんのセリフです。まぁこれが左さん味なのですが、ブルーレイの日本語字幕で確認してやっと理解出来ました(笑)
たいへんだ!野武士が来たぞ!!
レビューではありません。私の今の気持ちです
初めてこの映画を観たのは…
記憶では「ニュープリント完全版」、地元の東宝の劇場、フィルムでの上映…50年近く前の話。
80年代ビデオやDVDが普及してもソフト化はなかなかされなかった。黒澤作品への欲求を満たすため映画が観れないのなら…と図書館でみつけた「黒澤作品シナリオ全集」を何度も借りて読んだ。
ながい年月を経てソフト化、BSや配信で今では…いつでも観ることが出来る。
この作品に関しては、何度も何度も観た。テレビ画面で…。しかし、どのバージョンもフィルムの傷や汚れ、画面の揺れなど”玉に瑕“なものばかりだった。
そして今回、4Kリマスター版を劇場で観ることが出来た。
長年夢にみた…いや、実現するとは考えもしなかったこと…
とても幸せです。
好きなタイプの演技
なんといっても映画館
何度か黒澤映画を挑戦しましたが、いつの間にか、手悪さをしていて、見失う…を繰り返していました。これは映画館で観るものだ…と言い訳をし、あきらめていたところ、なんと上映するとな!!もう、行くしかない!長丁場でありましたが、よそ見をすることなく、夢中で鑑賞しました。途中の「休憩」!!で急いでトイレ!ありがとう。
さて。志村喬。こんなシブいおじさんがいたんてすね〜三船さんの青い感じも勢いがあってよかったですね。弱々しい村人おじさんもよかった。
なんといっても馬!!あれだけの数を全力で走らせる、乗りこなす技術、切られて落馬、映像のイメージと綿密な撮影計画。村人!!ぞくぞくと出てくるあの数、これぞ群衆の動き。向こうからどんどん近づいてくるのが、ず〜っと見えている映像。ドキドキしました。
最後の終わり方も好きです。全員勝者ではなく、亡くなった侍もいて。そして、村を守られた村人にとっては、また戦いなど侍など必要ない日常がかえってきていることが、描かれていて、きれいごとではない普通の日々で終わっているところです。
スタッフも同じ思いで準備をし、撮影しているのでしょう。もうコレくらいでいいんじゃないですか〜では完成しなかったと思います。黒澤明という男の強烈な魅力で、出演者、スタッフを引きつけて突き進んだのでしょう。人を一つに束ね、一つの大作を作る黒澤明監督の偉大さに圧倒されました。
無情な哀愁
邦画に於ける金字塔
全223件中、1~20件目を表示