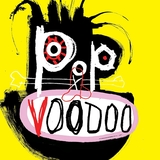エレファントのレビュー・感想・評価
全33件中、1~20件目を表示
傑作!アメリカのトラウマ的大事件を、幽霊になって観察する
22年前の2003年公開作。カンヌで作品賞パルムドールと監督賞を受賞とのこと。それほどの作品なのに、まったく知らなかった。
かなり変わった構造・構成の映画だ。主人公がいつまで経っても特定されない。というか主人公はいないのだ。そういう映画なのだと気づくまで、主人公探しをしてしまった。
そうした映画だから、物語を見る推進力にもなる、何かの事件的なことも最後まで起きないし、主人公のなんらかの解決すべき課題や動機も描かれない。
ただ、神様の視点――いや、自分が幽霊になってアメリカの地方の普通の高校を漂い、平凡な一日の高校生たちを観察しているような感覚を味わえる。
長回しで生徒の背中を追いかける映像は、誰の視点にも同一化せず、ただそこを漂う。
今回は、コロンバイン高校の事件をモデルにした映画ということだけ頭に入れていた。だから、何事もない高校の一日のように見えるが、この先何が起こるかは知っている。
一人、または2〜3人のグループの高校生をしばらく追いかけて観察しては、また別の高校生に観察の対象を移す。おそらく誰かが犯人のはずだが、みんな普通である。
ただ普通の高校生活というのは、仲間づきあいにしても、恋愛にしても、あるいはちょっとした陰口など、かなりしんどいものだなあということも伝わってくる。確かにもうずいぶん昔のことだが、学生時代はしんどかったことを思い出した。
そして唐突に凄惨な事件が始まる。
幽霊となって観察した身としては、いくら自由に飛び回って現場を監視していても、誰が対処すべき問題を抱えているのかはわからないし、事件の原因はなんなのかなど、見ていても事件を語ることはできないものだということを実感させられる。そして、現実というのはそういうものだろうということも、教えられた思いがした。
この展開から、タイトルの「エレファント」とは「群盲象を撫でる」ではないかと思った。会場に貼ってあった監督紹介で、そうであることが確認できた。パーツパーツをいくら観察しても、真の姿は見えてこないという諺だが、それを見事に表現している。
同時に、同名の1989年作『Elephant』(アラン・クラーク監督)を参照しており、“暴力は理解不能である”というメタファーが二重に込められているのだそうだ。
危機的状況においては、それが危機であるとは認識できない。まずは「大丈夫だろう」と考えて終わり。正常化バイアスだ。
でもなんかおかしいと疑いが芽生えたら、「何があったの?」と説明を求め、情報収集したくなる。
いずれも、それが本当に危機なら無駄で愚かな行動だ。野生の反応を発揮して「逃げるか、戦うか」そのいずれかを直ちにするべきなのだ。
しかし、現代人はもはや“逃げるか戦うか”という原始的反応を忘れてしまった。いや、必要な時に発揮できなくなったのだ。「にげるか、戦うか」反応で人間関係を壊したり、ビジネスなどで失敗することはビジネス書などで嫌というほど解説されている。
コロンバイン高校の事件についてはかなり研究も進んだようだが、現在でも全てが公開されたわけではなく、不明な点も残っているようだ。
ソシオパス的な犯人のメンタリティが明らかになったようだが、同級生にも教師にもその予感はまったくなかったという。
人の心の本当のところのわからなさ、そして今日自分が無事に一日を終えられるのかのわからなさ、そうした“わからなさ”を体感させてくれる不思議な傑作だった。
この事件は、アメリカ人にとってはトラウマ的な大事件だ。
この事件の後、学校には校内警察が導入され、カウンセリングも大々的に導入された。また、生徒の言動やSNSから問題の予兆を探る試みもされているようだ。
そうした取り組みにもかかわらず、模倣犯を思わせる同様の乱射事件はその後数十件も起きている。
どう見ても再発防止には銃規制しかないように見えるのだが、そこはアメリカにとっての聖域であり、現在も規制法案が成立する見込みは立っていない。
淡々とした描写が、むしろ「食らい」そうな一作
1999年に米国コロラド州コロンバイン高校で起きた、同校生徒による銃乱射事件は、米国内外に大きな衝撃をもたらしました。この事件を題材にした映画はこれまでに、マイケル・ムーア監督の『ボーリング・フォー・コロンバイン』(2003)などいくつも登場しており、本作もその一つに当たります。
本作はドキュメンタリー作品ではなく、実際の事件に基づいた創作、ではあるのですが、ガス・ヴァン・サント監督は様々な試みを取り入れることで、事実と創作、そして当事者と非当事者の境界線をあいまいにしています。
たとえば、演技経験のない高校生たちを配役して、思いのままに台詞を喋らせるという作劇手法もその一つです。出演者達は、全くの架空の人物ではなく、自分たちがこの作品世界の当事者であり、言葉を紡ぐことで場に意味を与える役割を担います。もちろん大多数はプロの俳優が学ぶ「メソッド演技」の訓練も受けていないでしょう。
即興劇とも当事者作品ともつかないこの斬新な手法が、出演者に過度の精神的負担を与えなかったか、特に暴力を含めた演技をさせたことに問題はなかったのか、といった議論の余地はあったものの、本作はカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞するなど高い評価を受けました。
こうした経緯を知らなくとも、ごく普通の日常生活を送る高校生たちが、実は「あの時」に向かって時を刻んでいる、ということを観客は知っているため、最終盤近くまで淡々とした描写が続くにもかかわらず、異様な緊張感が続きます。このあたりは、山本直樹著『レッド』も連想しました。
上記の制作背景を知るとさらに個々の登場人物への感情移入の度合いが高まるので、観客によっては直接的な暴力を見せられるよりも「食らう」かも。
なお本作の特徴的な作劇は、サント監督がこれまで描いてきた人間観、死生観を色濃く反映しているものの、全くの独創ではなく、同名のイギリスのドラマの影響を受けているとのこと。この不可解な題名の由来についてはいろいろな情報があるみたいだけど、原案の題名をそのまま使っているとなると、これは元のドラマに対する作り手の誠意…と見ていいのかな?
運命を感じる稀有な映画
『進撃』のエレンのように、少年少女たちの他愛ない日常が営まれている場を沈黙で満たしたかったのだろう。その景色がひと目見たかったからクエスト気分で殺した。校舎外に人間は存在しないかのように、中にいた生徒達だけを。個々に対する憎しみはなく空間そのものを憎悪した。そこにたまたま人がいただけだ。
日本の校舎のように真っ直ぐな廊下に教室が接続している形式ではなく、広い平面でいろんな活動が行われている回遊式の校舎が方向感覚を狂わせる。さながら迷宮のようだ。平面図を用意するのも無理はない。カメラの独特な動きもそれを助長し、『バイオハザード』感というか狩りの場としての禍々しさが募っていく。
ジョンがケツを叩くおバカシーンが3回登場するが、それがひとつの結節点として異なった視点からプレイバック、オーバーラップされ、不意に実行犯の周到な準備も重なって垣間見える。ただし、別アングルから重曹的に物語るという形式ではない。
結局、最後の虐殺へ向けて、カメラが生徒を執拗に背後から追ったり、群れて中身が空っぽそうな生徒達を映していく。まるで、この運命以外あり得なかったかのように。
あらすじ通り。
人はいとも簡単にあっけなく…
学校を語る前に見ておきたい傑作
被害者、加害者の数人の視点から事件を描く
コロンバイン高校での銃乱射事件を題材に、被害者数人と加害者2人、それぞれの視点から事件を描いた映画。当時の高校生を実際に出演させているということで、疑似的なドキュメンタリーと言ったらよいか。それぞれの視点で、時間がだぶった形式で事件を描写していることで、それぞれを追体験しているような感覚になる。それぞれの日常を描くことで、どんな日常が失われたのか、どのような接点で事件が起こったのかが明かされる。刑事の視点になったら、こんな感じの理解の仕方になるのでは。ウィキペディアで、コロンバイン高校銃乱射事件で調べると、実際の事件は、この映画とは大きく違うことがわかる。
気になったのは、逃げ惑う学生が、「逃げろ!」とか「銃をもった学生が乱射している」などと叫んで、他の人に知らせようとしないこと。これって、実際もそうだったのか。
最小限のBGMと効果音、ベートーベンのピアノソナタ「月光」と「エリーゼのために」が耳に残った。
加害者の若者が、何故事件を起こしたのかということについて、ここでは詳しくは描かれない。授業中でのいじめらしき行為、ナチスに対する興味、銃を通信販売で購入だけが示されている。
主となった加害者は、かなりいかれた少年で描かれる。共犯者まで殺すように描いた意図は何故なのか?(実際の事件では、二人の犯人は自殺) 日常から、この事件が起こる非日常とのギャップが大きく、事件や災害ってこのようなものだよって思う。
事実を描くことの難しさを理解し、決めつけやレッテルを排除すれば、このような描き方になるのかもしれない。
カンヌ映画祭のパルムドールを受賞したとのことだが、そこまでの作品だろうかって自分には思われた。
まぢむり
【”苛めの話をチャンと聞け、校長!”と犯人は言った。”普通の高校生が通販でライフルを購入出来た国で起こった悲劇を淡々としたトーンで描く。】
ー コロンバイン高校銃乱射事件は、当時大きな衝撃を世界に与えた。今作は、彼の事件を淡々としたトーンでガス・ヴァン・サント監督が描いている。
が、それ故に、後半の凄惨なシーンは恐ろしい・・。-
<Caution !内容に触れています。>
・ジョンは酔った父のために、学校に遅れ、校長に叱られ
・イーライは、趣味の写真を撮り
・アメフト選手のネイサンとキャリーは仲良く話し
・ミシェルは図書委員として、働き・・
と、前半はジョン以外の犠牲者の普通の高校の朝の風景が描かれる。
・アレックスが苛められるシーンが少しだけ映るが、エリックとアレックスは見た目は普通の高校生で、アレックスの自宅に届いたライフルを数発撃ち、二人でシャワーを浴び、普通に
”今日、死ぬんだよな・・”と言い、二人で計画を立て、学校にアーミールックで乗り込んでいく。
・その二人の異様な姿と、”来るなよ、地獄を見るぞ・・”と言う言葉を掛けられたジョンは皆に”学校に入るな”と言って回るが・・。
<エリックとアレックスに高校のヒエラルキーを変える手段は他になかったのか・・。
ガス・ヴァン・サント監督が、敢えて淡々とした高校の朝の風景や、生徒達の他愛無いお喋りを写した前半と、平凡な日常がエリックとアレックスにより、地獄と化していく様を描いた後半の対比が恐ろしい作品である。>
□今日、私の居住区で、中学生が同級生を刺殺するという事件が起きた。犯人は”嫌な事をされた”と話しているようであるが、暗澹たる気持ちになってしまう。
アメリカで、頻繁に起きる学校内での殺傷事件は、日本でも、対岸の火ではないのである。
"BowlingforColumbine"
一人一人が感じるささやかなことが。
エレファント、て、そういうことなのかな、
高校生、家族、教員、スクールカフェテリアのスタッフ、
ひとりひとりに固有の人生があり悩みや問題があり、日々、いや気分になったりいやな気分にさせられたり、そんなことの連続。生きていけなくなるほどのことにも人を殺したくなるようなことにも傍目にはそうとは思えないような小さな日常の中の不快、ストレス、イライラ、悪戯やいじめ、悪口、軽口。傷ついたり傷つけたりの積み重ねが、、乱射事件とか無差別殺傷とか、自殺とか、そう言うことにつながっていく危うい世界に否応もなく住んでいる。そういうことなんだなとよく理解する。少年というにはあまりに大人に近くあまりに幼稚でナイーブ(ばか)な子が、ベートーベンのエリーゼのためにを弾き、月光を弾き、Fワードを叩き尽ける、それだけではおさまったかも知れないことが、現代の現在状況ではおさまりつかない、ナイーブ(ばか)な世界にその危険なジャングルに日々繋がれて生きていることを教えてくれる作品
深い精神性を追求した浅薄な映画
「コロンバイン事件からインスピレーションを受けて作りました」なフィクション映画。同じテーマを扱った映画なら、マイケル・ムーアの『ボーリング・フォー・コロンバイン』はドキュメントで、起こった事実を取り上げて、社会的結論を求めてるので、正攻法な姿勢。
こっちはフィクションなので変化球。マリリン・マンソンの楽曲云々からだろうけど、実際の事件と何の関係もない「ベートーヴェンの曲」が登場したり、犯人は「恋愛もマトモに云々~」と「深い考察でしょ」の押し付け、「思考してまっせ感」の押し売り。
いずれにせよ、実際の事件と無関係な話やし、監督のオッサン「抽象的な部分を入れたのは、観客に事件について考えさせる余地を残したかった」とか言ってるけど(—お前は万物創造の神か?)、実際の事件について考えさせるなら、尚更、事実と無関係な話(フィクション)を付加すべきではないし。
ガス・ヴァン・サント、『誘う女』だと、恐ろしく表層的な浅い思考回路の映画を作っていたけど、他を観ても「良い映画」と思った試しがない。Nirvanaのカート・コバーンをテーマにしたのも、酷かったし。
ピアノの旋律の目
事件の全体像を示す
ボーリング・フォー・コロンバイン
ごく日常の高校生活の一幕。役者もわざとらしい演技をすることもなく自然に高校生を演じている。数人にスポットを当てて同時刻を違う角度で撮影していて、背後から彼らを撮っているのだ。イーライがジョンにポーズをとってもらうシーンが何度も出てきて印象に残りました。
おなじみ『ボーリング・フォー・コロンバイン』で衝撃を受けた実際の事件をモチーフにしているのだが、様々な意見を読んでしまった後で観ると、この映画の衝撃度が薄くなってしまった。しかも、前日に戦争映画を4本観たせいもあるのだろうか、残酷で血なまぐさいリアリズムに対し感覚がマヒしてしまったようだ。それでもネット・ショッピングで簡単に手に入る銃の描写はゾッとしてしまった。
観終わってからしばらくすると、恐れを知らぬベニーの不可解な行動と、イーライの写真はちゃんと撮れたのかどうかが気になってしょうがない。
「それまで」と「その時」を描く群像劇
全33件中、1~20件目を表示