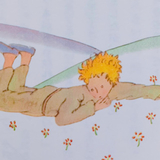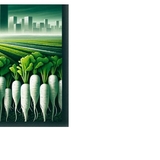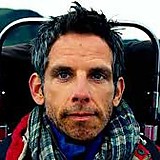ペイ・フォワード 可能の王国のレビュー・感想・評価
全64件中、21~40件目を表示
自分の中での最高傑作です
この作品は、情けは人の為ならず!という考え方と似た作品です。
誰か3人に優しくすることで、その3人もまた誰か3人に優しくし、と繰り返されることで世界が良くなるのでは!?と考えた男の子の話です。
自分はこの作品を見ながら自分と重ねました、自分が同じ歳の時にこの考えで人に優しくできたら、みんながこの考えを持っていたらと思ってしまいました。
自分は学校では誰かに優しくしたり積極的にできた人間では無かったため、この映画にもっと早く出会っていれば!と無い物ねだりをしてしまうほどにです。
もちろん子供では無い今からでも誰かに優しくすることを心情に生きることはいい事です、でも大人は子供ほどに純粋に善意で物事をすることが出来ないのも事実です。
名作と言われる映画は沢山あります。でも自分はこの作品を最高と言い続けます、ラストで死んでしまう必要は無かったとみなさんが言います。ですが自分はペイ・フォワードとは初めの1人(この作品では主人公)は世界の自分以外の全員が幸せになるまでは幸せになれないのです(誰も主人公に返せないから)。
この言い方が正しいかは分かりませんが主人公は神と同じ行いをしたのです。100%の善行。
だからこそ主人公は死でその代償を払ったのだと思います
出来るなら子供に見て欲しい作品です。大人と一緒に見ることで語り合って新しい考え方をしてほしいです。
これを見て見てくれる人がいたらペイ・フォワードを初めて見てください。
長くなりましたが読んでくれてありがとうございます少しでもこの作品の魅力を伝えられたらよかったです
一粒の麦が地に落ちて死ねば、多くの実を結ぶ。
「シックスセンス」のオスメント君とケビン・スペイシー共演の話題作だと聞いていて結局今まで見れずじまい。やっと見れた。ただ、主演のオスメント君は今や見るも無残な中年のおっさんに、そしてスペイシーの方もえらいことになっちゃってます。
でも私は作品と俳優個人とは別物だとして割り切る方なので気にしません。ただ、撮影中スペイシーがオスメント君をどういう目で見ていたんだろうという思いが脳裏に浮かぶたびに鑑賞中気持ちが作品から離れそうになってしまった。やっぱりもっと早く見とくべきだったな。
欧米では日本のような知識の詰め込みではなく、思考力を養うためにソフトスキル習得を重視した教育がなされており、その一環として社会科の教師シモネットは生徒たちに課題を出す。世界を変えるために何ができるかと。正しい答えを出すのが目的ではなくあくまで思考力を養うのが目的で。
しかし、トレバーが考えたアイディアにみなが驚かされる。それはいわゆることわざの「情けは人の為にあらず」にも通ずるアイディアだった。
自分が親切にしてあげた人がさらにほかの人に親切にしてあげる、これが延々と世界中に波及していけば皆が幸せになれるだろうと。彼がそのように考えたのにはその複雑な家庭環境に理由があった。
そのアイディアをトレバーが実行したことからやがて周りの人たちにその影響が及んでいく。心を閉ざしていたシモネットやアルコール依存症の母、そして同じく依存症の祖母にも良い影響が。そしてその影響はトレバー自身思わぬところにまで。
とてもいいお話で、温かい気持ちになれる作品。と思っていたら衝撃的な結末が。正直この悲劇的な結末には戸惑った。でもラストシーンを見て納得してしまった。
そうか、キリスト教圏の国の作品だもんな。トレバーをキリストと見立ててるんだ。ヨハネ福音書には「一粒の麦が地に落ちて死ねば、多くの実を結ぶ」の一節がある。これはキリストの死と復活を意味している。
キリストが死ぬことでその志を継いだ多くの人が生まれる、それはつまりキリストの生まれ変わり、復活だということ。トレバーの家の前には延々と続く人の列が遥か彼方まで連なっている。まるで聖地巡礼に訪れた人々のように。
本作、さすが演技派ぞろいだけあって要所要所で泣かされた。ただやはり最後は宗教色が強く出てしまった感はある。
少年の切なる思いが世界に伝播して奇跡のような出来事が起きた、みたいな話で終わっておけばよかったのかも。話題作のわりに意外に評価が低いのも納得。
あらすじに騙されないで
まず「ペイ・フォワード」という言葉の意味を知らなかった事から知人にこの作品を薦められました。良い話だからぜひ、と。
確かにラスト直前までは感動できる部分もあります。
しかし、最後の最後に主人公の少年トレバーが死んでしまうという結末に驚愕し、ひどく落胆しました。最悪です。
後味が悪過ぎて、時間の無駄・大損をした・こんな事なら見なければよかったと激しく後悔しました。
なぜこの話の流れで彼が命を落とさなければいけなかったのか、必然性も全くなく、どうしても納得がいきません。あまりにも酷過ぎます。
大勢の人々が彼に祈りを捧げる様子で感動させようとしているのか何か知りませんが、その意図も不可解で、終盤は一体何を考えて作られたものなのかさっぱり理解不能です。
人の為になら自己犠牲もいとわない?それは「ペイ・フォワード」とは何の関係もありません。人の力になるのは、命あってこそ意味をなすものです。助けられた相手が死んで喜べる人がどこにいるでしょう?
本来の「恩送り」の意味とは逆に、まるで「所詮人の善意なんて無意味、何にもならないんだよ!」という強い悪意が込められているかのような印象を受けるほどです。一刻も早く忘れてしまいたいのに、トラウマになり記憶から消えてくれないのが恨めしいです。
印象の選択肢に該当するものがありません。
怒りが湧く・失望する・最低といったところでしょうか。
キャッチコピーやあらすじに騙されて観てはならない、絶対におすすめできない作品です。
タイトルなし
ラストが糞。
現実世界でも同じような事が起これば自分も悲しむだろうし映画の様にキャンドルを持った人達が彼の家に集まってくる事だと思う。ただ、このシーンを見せたいと思って製作された映画だと思うと気持ち悪くなる。公開当時のアメリカ情勢とか分かってくると納得できるのかな?
悲しい結末
人に受けた恩を3人に返す
非常に大切な考えだと改めて感じさせてくれる作品。
最後、悲しい終わり方をしてしまう必要性があったのか疑問が残るが、全体として良い作品。
エピソードの枝葉を広げていく展開でも面白かった気がするが、これはこれで良いのかも知れない。
私も恩を3人に渡せるような活動、行動を取っていきたい。
世界が変わるのを見たい
タイトルなし(ネタバレ)
またいい作品を見ました。
「日々に慣れきった人たちは変えられない
でも諦めたら終わりなんだ」
という主人公の言葉ですが、私は人を思いやるということは
決して自分のためではなく100%相手のためであり
見返りを求めたりしてはならないですし、また
相手の為に愛を持って行うことは、実はそんなに簡単なことではないと、主人公を見ていても思いました。
必ずしもそれが相手にとって良いわけではありません。
愛の押し付けになってはならないですし
見返りを求めることではない。
ただそこに困ってる人がいたら助ける。
そしてそれを受けたら、今度は同じく困ってる人がいたら
自分が手を差し伸べるという
純粋な心をまた、思い出させてくれたように思います。
必ずしもうまく行くことばかりではなく、
善意を行っても悪運が降りかかることももちろんある
ということを主人公の死をもって伝えてもらえた気がします。
物語の本質は人として大切な事
日本人の宗教観では理解できない。
2001年。監督:ミミ・レダー
《ペイ・フォワード=善意を他人へ回す》
新任の社会科教師シモネット先生(ケヴィン・スペイシー)は
「世界を変える&自分を変える」
この2つを今学期通しての課題とすると、言い、板書した。
影響を受けたトレバー(ハーレイ・ジョエル・オスメント)は、さっそくヤク中のホームレス(ジェームズ・カヴィーゼル)を家に入れて食事とシャワーを使わせる。
トレバーは母子家庭で、母親アーリーン(ヘレン・ハント)は、夫は行方不明で本人はアルコール依存症だ。しかし仕事を2つ掛け持ちして頑張って息子を育てている。
このトレバーに旋風を起こしたシモネット先生。
この人も、父親から虐待され火を付けられ大火傷をしたことで、心と身体に深い傷を負っている。
シモネット先生の方こそ、助けの必要な人だ。
ペイ・フォワードの運動はマスコミも知る所となる。
多分この映画は心暖まる話なのだろう?
と期待して観ていた。
その予想は大きく外れた!!
むやみに他人には優しくするな!!
善意を悪意に取る腐った人間が多い。
シモネット先生は性格が破綻している。
「世界を変える」そんな課題を出す資格はない人間である。
この映画のテーマはあまりに偽善に満ちている。
ラストまでみて、トレバーの死を教訓にする・・・みんなが!?
そんな戯けたことは聞きたくない。
なぜトレバーがこの映画で犠牲になるのか?
ラストが酷すぎる。
ネバダ州の荒野!
人の感情や思想はその風土を抜きにしては語れない、とこの映画を観てつくづく思う。ラスベガスの町はあまりに人工的で嘘臭く、その周りに広がるのは果てしない荒野。映画のストーリー自体よりもその風景にばかり心が捕らわれていた。このような場所でまともに生活していくのは、想像する以上に難しい気がする。明日への不安を酒で紛らわすか、自分の立てた予定通りにきっちりと一日を過ごすか、人を虐めて自分を慰めるか…(異常な宗教に没入して現実を忘れるという方法もあるかもしれない)。
生活の参照とすべき伝統もなければ助け合う共同体もない世の中で、それでも正常を保とうとするならば、自分が変わり周りを変えるしか方法がないと考えるのは当然といえる。ゲンコツを与えるか慰撫を与えるか。その実践の困難さを描くのがこの映画。フォレスト・ガンプのように無心の行為が世界を変えるのとは違い、実践は誠に難しい。世界はクソだから。そんなクソの世の中でも、続ければ一輪くらいの花は咲くんじゃないかというのが主題。みんなクソまみれになりますけど。
カタルシスはない。大成功、万々歳な終わりかたではない。しかし、主役の男の子がメディアの注目を浴びた後クズ人間になる可能性もないので、そこは安心できたかなと思う。
気になっていた映画なので、消化できてよかったというのが正直な感想。可もなく不可もない。
人はまっすぐな良心に共感し、集う
NetFlixのおすすめに出てきて、引き込まれるように観た。
先生の板書からストーリーは始まる。「幸せを連鎖せよ」と。
少年は真正直な心でそれに答えようとする。
そしてその感動の波が広がって、お母さんとおばあさん、そして先生とお母さんが結ばれた直後。。悲劇が訪れる。
しかし皮肉にも「Pay Forward」のストーリーは感動の波を呼び、その悲劇を弔う人でラスベガスの片田舎の家の前は一杯になる。
正直言って感動のストーリー展開から、「あのラストは無いだろう」と私も思った。脚本家や監督に直接聞いてみたいと思ったぐらいだ。
でも最後のシーンで、まるで「フィールドオブドリームズ」のように「良心」というハートランドに集まる人々の姿を見て、「人は自分の捨ててでも人の役に立ちたい人に心を寄せる」ということが素直に心に入ってきて、「なぜだ」と思いながら、何とか受け入れることができた。
「パラサイト 半地下の家族」を観た後のような、複雑な感情が入り混じった気持ちだ。しかし。。理解したい、きっと意味があると。
あのラストは必要だったか?
3人に良い行いをし、連鎖させることがテーマ。
期待しすぎた。
思ったよりもストーリーの起伏がなく、
中盤で繋がりがわかっても大きな感動もなかった。
・読める大筋
・惹かれ合う描写のない急な恋愛
・不自然なほどに大人びて、大人の仲を取り持つ子ども
・不要なラスト展開
始まりは主題の規模の大きさを感じさせる展開だったので
わらしべ長者的に小さなことが大きくなっていく、
広がっていくことを期待していたが
終始主人公の周りの小さなことがメイン。
離れた場所での広がりは本当に前段に過ぎず
ガッカリ。
そしてラストは急に起伏を持たせたかったのか?
ああである必要は全くなかった。
なんと悲劇的な…と思わせたかったのだろうが、
全く感情は動かなかった。
途中から早送りで観るくらいだったので
2度は観ないな。
面白かった
話題になった話だと思うけど、きみに読む物語とかみたいなぺら感ある感じなのかなーと思って見ずに今まで来たけど、全然面白かった。ケヴィン・スペイシーは、やっぱり良い役者だなー残念だなーと思った。でも、最後死ぬ必要あるかな?
もうちょっとで名作になったのに
人間の性善説を元にしたおとぎ話のような物語は嫌いではない。もしかしたらこの映画は、あの昔の名作「素晴らしき哉、人生!」のような名作になるのではないかと思って見ていたら、何とあのラスト。まさに開いた口が塞がらないとはこのことだ。
学校の宿題で、「もし、君たちが世界を変えたいと思ったら何をする?」に対して、主人公の少年の答えは「見返りを求めないで困っている人を助け、助けられた人は同様に3人の困っている人を助ける。その結果ネズミ算式に世界が善意に満ちあふれる」というもので、実際に少年が実践する心温まる展開だった。
主人公役のハーレイ・ジョエル・オスメントは、悲しい映画が多いので、最後はどうなるかと心配していたら、案の定その通りになってしまった。
事件のあとの意外な展開(私にとって想定外の展開だった)には感動したが、事件自体はやや唐突で不自然な感じは否めなかった。
ここまで主人公にかなり感情移入してしまっていたので、最後に突然崖から突き落とされた気分で、納得できなかった。別の展開(殺されない)になっていたら、かなりのお気に入り映画になっていたはずなのに、非常に残念である。
現実に起きて欲しい
自力作善は当然破綻する
例えば「歎異抄」の親鸞の言葉にはこうある。
「慈悲に聖道浄土のかわりめあり。聖道の慈悲というはものをあわれみかなしみはぐくむなり。しかれども思うがごとく助けとぐること極めてありがたし」
人間が、自分の力で何かを助けようとしてもそれが理想的な形でかなうことはまずないし、ましてや助け続けることなどほとんど不可能だ、という意味である。
現代のアメリカ人の知恵は、800年前の日本人の智慧に遠く及ばない。
伝統を知り、ある程度の教養がある真っ当な日本人がこれを観れば、この映画は「世に無数にある、幼稚な自己中の偽善が、単に失敗しただけのさま」以上の評価はできないのではないか。
終幕もお粗末。
死をもって美化するのがアメリカ映画の王道とはいえ、あんなので感動するとか…ないな。
時間の無駄でした。
確かに泣ける(ネタバレあり)
泣ける作品ではあるものの
冒頭から中盤まで何をしたいのかが
あまりわからなかったのですが
お勧めされたので頑張って最後まで見ました。
最後まで見たのですが
正直平凡な感動映画という感覚です。
この作品が好きになれない点は
学校の先生と自分の母親を
くっつけようとする発想が
理解できない感覚であるためです。
そして、最後のシーンも
誰かが死ぬとは思ってましたが
子供が死んでしまうとは
思ってませんでした。
感動はするものの
この作品を見て何かなかったかと言われると
特に残るものが無かったのでこの点数にさせていただきます。
Pay it Forward
種まきは続いている
遅まきながらの鑑賞。キャスティングが見事はまっていて、すんなり観れます。まさかのボン・ジョビさんまでご出演だったとは。サプライズ。
社会は変えられるか。
新学期に社会科の先生が、中1のクラスに課題を出す。1年間かけて、自分で何か考えてアクションを起こしてみて、と。主人公のトレバー君が言うように、ほんとに「この世はクソ」です。ほぼ母子家庭の一人っ子、鬱屈した思いを抱えてる。でも彼はやってみることにした。
そして、どうなったか。
きょうも世界のどこかで、小さな優しさの種をまいている人はいると思います。
失望や絶望だけじゃないよと、私も思いたい。
だって希望がないと、クソみたいな世の中を生きていけないから。
変わらない人もいれば、変わる人もいる。
変わりたくなければ、変わらないし。
変わりたいと思っても、そうそう変われないってこともある。
でも変えたいと思わなきゃ、何も始まらない。
それでもやっぱり失敗して、その度に落ち込む。
人間は、弱いから。
臆病で、面倒で、不安で怖いし。
この世には、支配欲が生きがいの人もそこそこの割合でいて、そういう支配者は偽の愛情や偽のリーダーシップで人を牛耳ることも多い。だから家庭内が支配者の欲望を満たす場になっていたりする。
職場も学校も同様だ。
DV、パワハラ、モラハラ、セクハラ、スクールカースト、ママカースト...etc。支配される者の抑圧と失望をベースに作られていることは珍しくない。
課題を出した先生にも、辛い過去がある。
おいそれとは人に話せないくらいの。
自分に殻を作り守っている。
でも希望がないと、生きていけないこともわかっている。
だから教師をやっている。
だけど先生が生徒から、大人が子供から、
大事なことを教えてもらうことだってある。
ペイ・フォワードは、種を蒔いても、いつ芽が出るのかわからないし、芽は出ないかも。
そんな不確かなもの。
ユートピアか!って突っ込み入れられて、「それって、理想的ってこと?」
理想的って、いけないの?というトレバー君の純粋なきり返しが、最高にいけてる。
人には必ずいつか死が訪れます。
それまでにどれくらい種を蒔けるだろうか。
花が咲くのも実が成るのも、この目では見れないかもしれない。でもたくさん種を蒔けたら、死ぬ時少しだけ安心した気持ちで逝けるような気がします。
全64件中、21~40件目を表示