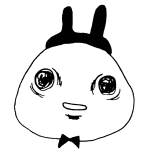ダ・ヴィンチ・コードのレビュー・感想・評価
全140件中、21~40件目を表示
観ながら理解するのはほぼムリだけど
ラングドン教授の専門としている、宗教象徴学とは何か。ざっくり言うと、何が描かれているか?描かれている物に付加されている意味は何か?そして作者の意図は何か?を読み解く学問だ。
暗号を解くのに相応しい学問と言えなくもない。
「ダ・ヴィンチ・コード」はダ・ヴィンチの絵画に隠された謎を解き明かし、現代に起こった殺人事件の解決を目指すミステリーで、普通のミステリーとしても楽しめる。
一方で、物語の本質に迫ろうとするならば、ラングドン教授の手法に乗っ取り、「その意味するところ」を解かなければならないだろう。
もろもろ考えることが多い、という点でもこの映画は面白い。
ラングドン教授の手法に則ってこの作品を捉え直すならば、謎解きミステリーの体裁は、誰が見ても明白な作品の表層理解である。
そして、その意味するところという作品に直接描かれない知識補完を必要とする領域(映画ではわりと丁寧に説明されているが)として、キリストの神性を問う物語が描かれる。
聖杯を巡る攻防は三つ巴の争いだ。「聖杯」が何なのかは知らないが、それを手中に収めることでキリストの人智を超えた力を証明しようとするオプス・デイ。「聖杯」が何を示すのかを突き止め、それを白日のもとに晒すことで現在までの欺瞞を暴こうとするリー博士。「聖杯」の在りかを知っていて、秘匿することで血脈を守ろうとするシオン教会。
それぞれの目論見が一致している部分としていない部分が混ざりあう為に事件は起き、ラングドンとソフィーは巻き込まれるのである。
オプス・デイとシオン教会と博士、それぞれが考える「聖杯」の記号的意味は相容れないものであり、具体的に言ってしまえば「キリストは神か?人か?」という価値観の問題である。
この事件の裏で進行している出来事とは「自分達の価値観を守るための戦争」なのである。
ラングドン教授が巻き込まれたのも、その意味性を考えれば当然のことだ。彼が専門としているのは一般的な意味を失った古い記号と、現代に流通する記号の連続性や歴史の研究であり、一見して意味の掴めないものから意味を読み解く研究をしている人物なのだ。
現在一般的とされている記号、すなわち常識を覆す力を、ラングドン教授は持っている。
そこから更にもう1つ掘り下げて考えるならば、この物語で真に表現されていることとは以下の三点に集約できる。
一般的とされている記号の認識を「常識」とするならば、「常識」は長年の教育(思い込みや願望を含む)によって形成されたものに過ぎず、たった1つの「常識」が大きく変革することによって現在の世界が受ける影響は甚大で、「常識」の持つ脆さという問題は無視されたまま世界の根本を形成している、という恐ろしい事実だ。
乱暴に言うと、長いこと正しいとされてきたことは別に正しくもなんともなく、それが間違いだとすればあっちもこっちも間違ってることになり、しかもその根拠はあやふやなのが私たちの住んでいる世界、ということだ。
常識は、そんな脆いものの上に作られている。
そう考えると結局は「何を信じるか」が全てなんだな。そして、どうして信じるか?を導くために、やっぱり知識は多い方がいい。
「ダ・ヴィンチ・コード」観てそんな事を考えてるのは、私だけかもしれないが。
最後に。
ラングドン教授がこの三つ巴の中で、中立であり続けたラストシーンは素晴らしいと思う。
オプス・デイの思惑通り「聖杯」を探し出し、シオン教会の願い通りソフィーを守り、リーの言った通りマグダラのマリアの棺に祈りを捧げたのである。
ラングドン教授が読み解いた末に信じるものとして選びとったのは、「人と争ってはいけない」という、歴史の教えなのだろうと思う。
原作の方が圧倒的に面白い
原作を読んでから映画を鑑賞した。原作小説の『ダ・ヴィンチ・コード』は上中下3巻の構成になっていて、それなりに長くしかも内容が濃厚。そのためそもそも一つの映画にするのは難しかったと思うので、原作の方が面白いのは仕方がない気がする。
映画は原作を短く要約しただけという感じだ。原作で多くの時間を割かれていた謎解き部分はあっという間に終わってしまう。この謎解きが、驚きや興奮を味わえる部分であり、『ダ・ヴィンチ・コード』の面白い部分なので、ここが省略されていると驚きや興奮も半減してしまうと思う。
また、映画は次から次へとストーリーが展開していくので、原作を知らないと分かりづらいのではないかと思える部分も多かった。
ガラスのピラミッド
昔、電車の中で必ず1人は「ダ・ヴィンチ・コード」のハードカバーを読んでいたくらい、すごい流行したことがあった。まさに、ダン・ブラウンブームだった。何年かに一度、書籍が旋風を巻き起こすことあるよね。「1Q84」とか。
キリストの秘密と、教会と対立組織の争い、謎解き。なさそうでありそうな、微妙な設定がうまい。スピード感ある展開に、歴史と宗教のうんちくで、一時も画面から目を離せない。脳みそもフル回転させないと、付いていけない。味方かと思えば敵だったり、逆パターンもあり、ジャン・レノ好きとしては、彼が悪役なのかどうか、ハラハラしてしまった。
あのガラスのピラミッドは、できた当初パリっ子にすごく評判悪かったらしいが、新しく建造したものをあんなふうに物語に利用するとはなかなかうまい。本当にそんな意味がありそうに思えた。あー、パリ行きたい。
エンドロールでオドレイ・トトゥのクレジットを見たら、英語読みではオードリーなのね。なんてことない発見で自己満足。
BS12の放送を視聴。
原作は最高だった。でも、原作に忠実な映画が最高だとは限らない。
ルーブル美術館館長が残したダイイングメッセージから、有史以来の謎に迫る主人公の活躍を描く物語。
ダン・ブラウン原作の世界的なベストセラーを映画化。原作は読了しての鑑賞です。
一度鑑賞済みのはずですが、何故かまったく記憶に残っておらず再度の鑑賞。何故記憶に残っていないか・・・を再確認してしまいました。
理由は、原作との比較になるのでしょうね。
この映画は、比較的原作を忠実に再現している作品だと思います。映画上映時間は長めの149分。それでも、原作の持つ壮大さや悠久の歴史の奥深さを描写するには不十分だったように思います。
テンポは良く観やすい映画だとは思いますが、一つ一つの謎をもう少ししっかりと描かないと、原作に大きく見劣りしてしまうように感じました。
ま~、しっかりと描こうとしたら、13話位のTVドラマになるのかもしれませんが・・・。
私的評価は普通にしました。
キリスト教に疎い人には難解じゃわ。
話しが壮大過ぎて、ところどころよく分からない部分はあったが、おもし...
映像美とミステリー
数年前、ルーブル美術館に行ったあとに帰国してから鑑賞した。
その時も難しすぎて、そして途中眠くなってしまったりで…良さを完全には理解せずに不完全燃焼だったが
今回はちゃんと観た…!!
やっぱり難しくて、もう一度観たいなと思うけど、この謎解き感がたまらない。
一つ一つ謎を解いて、次に進んで、周りはみんな味方に見えてもそうじゃなかったり…もうそれがすごく楽しい。
みんな欲しいんだね!知りたいんだね!
そりゃそうか…!!
そしてフランスの街並みやルーブルがキレイで、また行きたくなる。
この絵画に込められた色んな意味を読み解くのも楽しい。そういった視点で観るから奥が深いんだろうなぁ。
それを知った上でまた観たい。
宗教やキリスト生誕の物語やらは難しいけど、そこもまた調べたらより楽しめそう。
可もなく不可もなく
世界的ベストセラーの映画化
まず思ったこと。
ソフィーの存在が、あまりに軽いです。
全世界で2億部以上の発行部数というダン・ブラウン原作「ダ・ヴィンチ・コード」を、
ロン・ハワードが監督して映画化された。
キリスト教の様々な教義や研究を独特な感性で謎解きに構築した歴史サスペンス。
著者が「この小説における文書・秘密儀式の記述は事実に基づいている」と断りを入れているが、
信じるも信じないのも自由・・・だと思います。
まずヒロインのソフィー・ヌヴー(オドレイ・トト)が開始5分位で登場します。
この映画を見終えて感じることは、ソフィーほどの、この映画の鍵を握る人物が、
いとも簡単に現れる・・・
しかも主役のロバート・ラングラン教授(トム・ハンクス)の片腕として謎解きを担う・・・
そのことに違和感を感じます。
しかも最初の殺人事件の被害者・ルーブル美術館の館長・ソニエール。
このソニエールはソフィーの祖父なのです。
マグダラのマリアがイエスの子供を出産した・・・
結果的に、イエスの子孫の血脈は現在に受け継がれている・・・
この事を信じている「シオン修道会」が黒幕なのですが、
イエスの子孫の血脈を引く○○○をこんなに簡単に野放しにしているなんて
信じられますか?
宗教の象徴(シンボル)として崇め、マリアとして、宗教指導者として、
シオン修道会の要職を担い布教活動に勤しむのではないでしょうか!?
見終えて、この話しは「謎解きのための謎解き」
ダンテの「神曲」やレオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」も
「聖杯」も全てのキリスト教の知識は、面白いサスペンスを描くための
小道具・大道具だった。
カトリック教会が反発するのも、よく分かります。
しかし膨大な知識で仮説や想像や嘘を交えての大仕事。
騙されても面白かった・・・と言うしかありませんね。
原作は読んでいるけれど、さすがに上中下の原作を映画にするのは無理が...
歴史ミステリー満載の原作を映像が更に膨らました
原作の面白さが際立つ
キリスト教徒だともっと入り込めるのかな
全140件中、21~40件目を表示