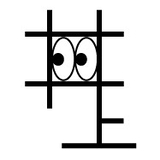ルノワールのレビュー・感想・評価
全155件中、81~100件目を表示
半分こどもで半分おとな
フキの姿はぷくぷくと自分のペースで呼吸しながら泳いでいく魚のように
知りたがる顔もせず
知らん顔もせず
ただひとりでじっと感じとりながら
その先をみつめている
キャンプ場で過ごしてるいるときの表情だけが他のみんなと変わらない気がしたけれど
そんな様子は自分にも記憶があるところだ
ポーカーフェイスも操りはじめ
半分おとなの半分こどもはみている、きいている
いいこともわるいことも隣り合わせで
喜びと哀しみは繰り返し
表と裏が重なりあう世界を知っていく
あの頃の独特なみずみずしさ、危うさ、賢さ、強さ、弱さをフキを演じる鈴木唯さんのナチュラルさが等身大で渡っていく未知なる海のなか
時には一緒にもぐり感傷的に
あるいは空から覗きこみ懐古的に
大人になったわたしは
そんな半分こども半分おとなの心の前で
どんなふうに居られるかな
水からあがった気だるさを包む乾いたタオルのやさしい感触とふんわりしたまどろみの心地よさを思い出しながらいる
修正追加あり
「家族を持つ」働き盛りな父(母)は観るべき心締めつけられる家族ドラマ
がんを患い闘病中の父親と家計を担うため働く母親、そして小5の娘・フキの一夏の生活が描かれる家族ドラマ。
フキを軸に一家の生活を映し出すが、そこには治療の手立てがなく近いうち死が訪れる父親の現実が、家族3人それぞれに重くのし掛かり、いつもの日常を過ごそうとしながらも、どこか歯車が狂った不安定な日々を過ごしていく。
病を克服するため医療情報を漁り、さらに詐欺まがいな民間療法にも手を出す父親。
いずれ迎える夫の死を見据えて、一人で娘を育てる現実に、恐れながらも向き合おうとする母親。
そして、死の概念すらまだ理解しづらい子供にも関わらず、「父親の進行中の死」に直面しているフキ。
フキはその現実を受け入れられず、理解不能状態のまま、一見穏やかに日常を過ごすが、その内面は静かに乱れていく。本来、救ってくれるべき父親、母親も彼女と同じように、「死」を受け入れられていないから……。
家族と過ごすフキの「感情を抑制した表情」と、学校の級友と過ごすフキの「天真爛漫な表情」の対比は、幼いからこそ感情の発露が不連続である様が、とても切なく胸が苦しくなった。
さらに終盤、元気だった頃の父親と過ごすフキの表情は、とても明るく朗らかだったのが映し出されると、もう心が締め付けられて痛い痛い。
全編に渡って物哀しく心が締め付けられる、心痛極まりない作品でしたが、それは一重に「がん」によって家族が欠けてしまうことの悲痛さを物語っているとも言える。
観るものは自分ごとと感じて、がん検診を受けて早期発見、早期治療を心がけたい。本心。
美しい画角、陰鬱とした雰囲気
好奇心に満ちた子供視点の大人の世界の陰鬱さを描いている作品。案外気付く子は気付くし見てるし聞いているし、簡単に一線なんていつでも越えられる。
作中にずっと漂う淡い陰鬱さと何かが起こってもおかしくないぼんやりとした物々しさが時折、下手なホラーよりもよっぽど怖かった。
子供の好奇心とは恐ろしいものである。けれども自分の幼少期を顧みてみると、実家の親戚の集まりでは、確かに寝静まった後大人たちが話す会話が気になったりしたものだったし、成長してみると親戚の叔母さんからしたらあの時の自分の言動なんて溜まったもんじゃなかっただろうな、などとの回想をすることが難くはない。
しかし映像で観ると余りにもグロテスクでなんだか虚しくなった。腹の裏にどす黒いものを抱えた大人たちの情けない姿、あまりに虚しすぎる。だけども、決して大人の世界も悪いことばっかりじゃ無いんだけどな。
物語性を求めすぎかもしれないが、もう少し何らかの救いよう、落とし所があって欲しかった。
まあ、それはフキが成長しながらいずれ知っていくということだろうか。
印象派の画家ルノワールの名がタイトルに使われている。作中で出てくる代表的な肖像画「イレーヌ」。美しき絵画であるが、このモデルとなった家族も本人もこの作品を気に入らず、往年彼女の手元に来るも競売に掛けたという皮肉なエピソードが過る。あんなに美しい絵なのに、切ない。皮肉オブ皮肉。この世は皮肉だらけだよ。
画角や写し方は好みだった。光と影の使い方が美しく、少女フキの朴訥とした雰囲気と相まって記憶に残る絵が多く、印象的だった。
携帯電話がなかった時代
壊れ切った家族像
出てくるキャラが、全員コミニュケーション能力が「壊れている」上に、根底が邪悪。
主役の小学生の女の子は歪みきった承認欲求に支配され、「もし自分が死んだら」「死んだ私の身体を見て欲しい」しか考えておらず、しかも時はオカルトブームで超能力や新興宗教に抵抗なく受け入れ、伝言ダイヤルにハマり、そこで知り合った犯す気満々のペド大学生と無警戒に遊びに行く……
キャリアウーマンだが、仕事が出来ない人間の気持ちが分からずナチュラルにパワハラする母親。
末期癌で、知識欲に偏りすぎて、未承認の薬を試したいと医者に詰め寄りすぎて、医者から疎まれる父親。
ここまで壊れ切った家族像は初めてで、むしろドン引きした。
瞬間瞬間の画(え)はすごかったが、これ映画として楽しいのかな?という疑問が拭えなかった。
いろいろ詰め込みすぎ
石田ひかりさんとリリーフランキーさんの個性が強すぎて肝心のフキさんに感情移入できなかった。そしてとことん無神経なフキさんが好きになれませんでした。
美しいシーンがたくさんあったけど、もう少しシンプルでも良かった気がします。
ポスターの写真がこの場面なのかいっ⁈と
ずっこけました。
フキちゃん危機一髪
フキちゃんとは鈴木唯さんという11歳の子役が演じるこの映画のヒロイン。リリーフランキーさん扮する末期ガンの父、石田ひかりさん扮する今で言うパワハラで「研修」を命じられた母とのひと夏の物語。
最近自分の観る映画は「壊れていく女子」を鑑賞することが多いが(悪趣味)この映画も正にそれ。(母娘ともども)フキちゃんとお母さんとお父さんのエピソードが時系列プラス、フキちゃんの妄想?が展開していく。
鑑賞者によってどのエピソードが刺さったかは違いがあると思いますが私は二つ挙げておきます。
一つ目はやはり坂東龍汰さん扮する薫とフキちゃんとのエピソードです。監督さんはギリギリのところを攻めていますね。本当に危機一髪、壊れていくどころか物理的に壊されてしまう(笑)私はこの時代、小学校高学年の担任でしたが、タイムスリップして夏休み前にこの場面を見せたい(勿論反面教師として)
もうひとつは夏休みが明けてからフキちゃんが通っている英語塾の外国人女性の先生とのやりとりです。フキちゃんが先生の質問に答えると先生は大粒の涙を流します。ネタバレになるのでこれ以上はいいませんが、この先生の感性こそ「まともな」「普通」の感性だと私は思うのでフキちゃんがその方向に成長して欲しいと思いました。
エンタメではない。でも自分の映画体験を信用したい
中途半端
期待し過ぎたわけではない。カンヌ出品だけど賞を取ってはいない時点で、「まあ、だいたいこんな映画やろな」と、ある程度出来の良し悪しは想像していた。何より、今誰より注目している河合優実が出演して、リリーさんも出ているということで、めちゃ良いということはなくても料金の価値はあるやろうと判断して鑑賞。
観た感想はまさにその通りという感じ。他の方も投稿しているように、何が描きたいのかイマイチ焦点が絞れておらず、いろんなエピソードを次から次から流して、数うちゃ当たる的なショートフィルムの連打みたい。1本の映画としてはなんとも中途半端。主役の女の子の演技は悪くないが、いかんせん脚本が弱く、観ている方が感情移入できるだけの魅力に欠ける。明確な個性がなく、メインテーマ(?)である(と思ってた)「父親が亡くなることを経験して大人へ成長すること」もあまり描かれていない印象で、80年代にこだわる理由も不明。結局すべて雰囲気だけ、そこそこきれいな映像だけで乗り切っただけみたいな。いかにもカンヌでは好まれそうな題材とは思うが、やはりそれだけで賞を取れるほど甘くない。
ただ、ショートフィルム連打の中で白眉だったのは河合優実演じる未亡人のエピソード。ほぼひとり語りしているだけなのに映像が浮かんで、ここだけ別の作品みたいな感じで強烈に印象に残り、演者の格の違いを感じた。そもそもこのエピソードは丸ごとカットしてもストーリーに影響ないのだが、これがなかったら星ひとつ減ってると思う。
深堀りや考察好きの映画ファンなら好意的に、「あのシーンにはこういう意味がある」とか「このシーンが良かった」といろんな感想を出すと思うし、それは映画の楽しみ方のひとつですが、まずその前に「ああ、いい映画だった。見ごたえがあった」と思えることが第一かなと。
大人の境目ってどこなんでしょうね。
主人公11歳女子の目線で見えた, 周囲の人々 とくに大人たちの物事...
主人公11歳女子の目線で見えた, 周囲の人々 とくに大人たちの物事.
父は癌の末期, 母は多忙で苛々が募り.
両親や, 学校など友人らのまわりで日々が過ぎ.
この女子, 飄々としたような, 繊細なような, 掴みづらく. 両側面ともあるんでしょう.
時代はどうも80年代のよう
超常現象ブーム, ウォークマン, 子供による親殺し事件,
学級のマスゲームで YMO "Rydeen" が使われたような当時.
主人公目線で諸々が描かれ,
結論や見え方が画一的にならず, 言語化もされず.
そういう見え方, 心当たりは多々あります.
私的にも, かつて見た諸々の出来事に, いちいち理由や結果を追求してはいないですし.
途中で聞こえたオペラ的な歌 Klaus Nomi "Cold Song"
とてつもなく冷たく感じました. 凍り付いて死ぬような歌詞をもつ歌ですしね.
生死観 - この女子, 学校の作文で "寝ている間に何者かに絞殺" や "孤児になりたい" と書いたり, 物語上の父が実際に余命わずかであることと, 辻褄が合うような.
そういう意図かはわかりませんが.
題目の画家ルノワールさんは, 劇中で話題には挙がりますが, 意味を深く持つものではない様子.
絵画のレプリカ販売が盛んだった, 当時はそういうこともありましたしね.
当時, 絵画の展示を見学に出掛けたら, 終盤で販売員さんらに囲まれて逃げづらくなった... なんて販売手口もありましたね. ルノワール, ラッセン, エバハートとか.
童心を思い出すような, 澄んだ心を持っていた頃もあったねえと感じるような.
そのままで美化も劣化もされてない,この年代,この世代のリアル.
切なくて温かくて, 耳と胸が少し痛くなる, 鑑賞体験でした.
人が死ぬと泣く
「こちらあみ子」を思い出しながら観ていた。あちらのあみ子も、この映画のフキのように周囲と溶け込めていなかったが、関わり合っていた。こちらのフキは、家族とも学校でもどこか世間と隔たりがある。だけど、それを苦にはしていないようだ。というか、そういう感情を持っていないのか?そんな、無感情というか、冷めているというか、愛想なしというか。無垢であり、残酷であり、無遠慮であった。だけどむしろ、だからこそ観察者としての視点で世間と距離を取っているようにも思えた。感情がないと言っておきながら、半面、瑞々しいほどの感性を内包してるようにも見えた。
そして周りの大人たちが、はた目にはどこにでも居そうでいながら、ひと癖もふた癖もある。言い換えればちょっと嫌なところや弱いところを皆抱えている。だけど、そんな大人の集合体こそが、リアルな世間なのだろう。
おそらく、友人宅の引っ越しとか、母親の秘めたる内面とか、描かずとも察することで味わえる、じんわりと面白味を感じる深みのある作品であることは間違いないが、そこを不満と思う人もいるだろう。だけど自分としては嫌いではない。ただ、配役として先生役はどうなのか。どうみても定年過ぎにしか見えない。父親役のリリーフランキーもどうなのか。あの風貌で小学5年生の父親って無理がないか。いや待てよ、もしかしたら結婚が遅く50歳を過ぎてからできた子宝だと想定したら、なるほどこの映画の空気もさらに楽しめるかも知れないな。そして、「人生って素晴らしくて素晴らしくて素晴らしくて、いつか終わるもの」この言葉が妙に引っかかって、離れない。たぶん僕は、フキが夢の中で踊っていたような快楽と厭世観のごちゃ混ぜになった気分で、この映画の世界にふわふわっと翻弄されているのだろう。
「お引越し」???
少女が見つめていたもの
小学5年生の眼から観た大人と呼ばれる人間たちの行動はときに滑稽です。
不思議な事象を超能力と面白がったり、
小学生の書く作文に過剰に反応してみたり、
子どもの泣き顔を集めた動画を観賞してみたり、そんな夫との死別を淡々と受け止めてみたり、
素敵な家族として体裁を整えてみたり、
見えない何かを信仰してみたり、
電話で気の合う人を探してみたり、
懲りずに誰かを好きになってみたり。
たとえ、自分の親であっても理解に苦しむことがあります。
死を覚悟したような佇まいながら、仕事のことを考えながら病床を過ごしたり、何かにすがるように足掻く様子を見せたり。
そんな夫よりも仕事や段取りを優先させてみたり、その職場では言動を問題視されてみたり。
それでいて父母ともに、どこか奥深い場所で家族のことを考えていたり。
そんな大人たちが紡ぐ「社会」と呼ばれる環境を、少女はまっすぐに冷静に見つめながら上手に泳いでいきます。それは楽しんでいるようにも見えましたし、その眼はトランプの模様と数字を見透かすような眼差しでした。そして、どちらが大人なのか?と思えるような姿勢でした。
いろんな人間に出会い、多様な経験を積むことでたくましい大人になっていく未来が予想されるような締めくくりでした。
いつの時代の設定かとか気にならない空気感でしたが、途中YMOの「ライディーン」が流れた瞬間、小学校でこの曲をバックに行われた縄跳び大会が思い出されて一気に昭和に引き戻されました。
純粋、爽やか、冷徹に大人の価値観、固定観念を揺さぶる
タイトルの意図は不明だが、
映像が、光と影のコントラスト強く、やや粗めの質感も手伝って、
絵画的な見方、鑑賞の仕方を求められているようで面白い。
それは、全編にわたって一応の話の流れはあるけれど、セリフの無いシーンが多く、
観る人それぞれで心情を想像してくださいというようなスタンスからも感じた。
内容については、
子供の純粋な心、強い眼差しが、大人の矛盾や勝手な都合を冷徹に炙り出し、
生死も含めた固定観念や価値観に揺さぶりをかけてくるのが面白い。
物語の時代を数十年前に設定しているのは、
胡散臭い迷信や他人に依存してしまうそんな大人の弱さ、情けなさを強調する
キーアイテムが豊富なのが理由だろうか。
ラスト近くに女の子が手を振るシーンは、
まさしく相米監督の”お引越し”のオマージュのようで
少女の成長の暗示に対して、思わず”おめでとう”と言いたくなりました。
とてつもなく味わい深い作品
早川千絵監督による映画『ルノワール』は、1980年代の日本を舞台に、11歳の少女・フキのひと夏の体験を、繊細かつ静謐なタッチで描き出した傑作である。
とはいえ、この作品は単なる少女の成長譚ではない。物語は直線的な時系列で語られるのではなく、相米慎二監督の映画「お引越し」をはじめ様々な作品からの引用、断片的で印象的なカットの連なりによって進行する。そこに見られるのは、日本の80年代にさまざまな表現領域で取り入れられたポストモダン的アプローチ、すなわち脱構築的なサンプリング、カット&リミックスの手法だ。
ビデオテープ、ロリコン文化、超能力、狼男、怪しげな民間療法……。こうした時代の記号の羅列が濃密に織り込まれ、80年代という時代の空気が再現される。そしてその中に、言葉では語りえない感情や傷が、ひっそりと浮かび上がってくる。この手法は、ジャン=リュック・ゴダールが80年代に行った映画言語の解体と再構築にも呼応しているようにも思える。
なかでも特筆すべきは、フキの「抑圧された哀しみ」が、劇中で直接語られることがないという点だ。フキは語らない。だがその沈黙の豊かさを、早川監督は映像と音の配置によって丁寧に、精緻に語っていく。それは「物語」ではなく、「構造そのものが語ってしまう」という、極めて現代的で冷徹な視点がある。
それはまさに早川千絵という作家の映像表現の真骨頂である。
——と、ここまでやや理屈めいたことを書いてきたが、後半、あの雨のシーン以降、フキの喪失と愛と哀しみが、ぐっと押し寄せてきて、涙が止まらなくなった。
名場面が幾重にも折り重なる、宝石箱のような映像体験。ぜひ劇場で、味わってほしい。
タイトル回収って言葉知ってる?
全155件中、81~100件目を表示