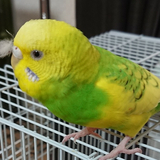8番出口のレビュー・感想・評価
全1069件中、301~320件目を表示
現代の8.1/2ですね。
この映画はフェリー二の8.1/2の影響を深く受けていますね。影響を受けた映画は沢山ありますが、出色の出来です。
海岸の場面は甘い生活ですか。
観客は何も考えずに画面を眺めることで自己の魂と向き合い、何かに気づいて劇場を後にするでしょう。
とはいえまだまだフェリー二の領域からは遠い。
初回観賞時と2回目ではかなり違った印象を受けました
初回の鑑賞時には、いろいろ見落としてしまったようで、あまりおもしろいとは思えませんでした。
(元書いていたレビューも、かなり否定的な内容にしてしまっていました)
レビューにコメントいただいたのをきっかけにもう一度鑑賞し直しました。2回目の観賞後でも、突っ込みたくなる要素はゼロにはなりませんでしたが、かなり印象が変わりました。
「迷う男」さんの結末は、良い方向に進みそうに描かれていて良かったです。ノベライズ小説には、映画でよりももっとはっきり、文章でも書かれていたので、間違いないようです。
話題にはなっている作品と思いますので、私も見たよと友人・知人への話のネタにさえなれば、というくらいの気持ちで気軽に見に行くと良いかもしれません。期待以上であれば儲けものですし、好みでなかったとしてもショックは少なく済むと思います。
思ってたより全然よかった
酷評多い理由も、その内容に対しても、正直「まぁそりゃそうだね」と思う。映画として完成度高いかと言われたら、どうやってもB級映画の枠は出ないとも思う
今回は友人に誘われて鑑賞。原作ゲーム既プレイ勢で、映画は観る予定はなかったけど友人が観たいとのことで付き添い
何故観る予定なかったかというと「映画の限界が既に見えていたから」に他ならない
これを題材に、どう風呂敷を広げても限界がある。1時間30分ある時点で「8番出口をどうやって1時30分に広げんねん」と正直に思ったし、実際1時間30分必要な映画だったかといわれると、そうではない
けれど、8番出口という題材でできる最大限の脚本、演技、演出だとも思った。8番出口を題材に映画を作ってね、と言われてこれ以上のものを出せるか、と言われると、それもまたそうは思えない。8番出口を題材としたという前提で見れば、これ以上出来のいい作品はないだろう。普通にハードルは超えてきたし、そもそもが全く期待せずに観たおかげもあってか、個人的に楽しむことができた。
個人的には全然楽しかったけど、つまらなかったという人の気持ちもよく分かる。期待して観にいっていたら、あるいは原作ゲームをよく知らずに話題性につられて観にいってたら「なんやねんこのクソ映画」と思っただろうな、と
子供の正体とか、子供が出てきた瞬間に「あぁこれはこうで、こういう展開になって、こういうオチだろうな」と浮かんで、実際その通りになった。よく言えば脚本としてまとまりがいい。悪く言えば想像通り、と言えるのだろうか。
喘息の設定だってもっと上手く活かせたと思う。薬が足りなくなって、それがタイムリミットだから早く抜け出さなきゃ、みたいな展開ならもっとスリルを演出できたと思う。けれどそれをすると話のオチが繋げにくくなるので、じゃあそもそも喘息設定いらなくね?みたいな
あそこまで発狂するのもよく分からない。ループして3日とかなら水もないし食料もないし、それならまぁまだ分かるけど、いくらなんでもSAN値が溜まるのがあまりにも早すぎである。
とは言え、だ。ホラー映画としてそれなりに怖さもしっかりとあるし、8番出口をプレイしてる(見たことがある)人なら、「この視点は想定してなかった!」みたいなサプライズというか、観てみたかった視点も見れたし。
まぁあれをするなら、歩く男目線の歩く女目線の歩く男がニノで〜という風呂敷の広げ方をすればもっと色々な展開を作れた気もしないでもないんだけど、別にそういう訳でもなかったので、シンプルに迷う男がゲームオーバーになるとこうなるよ、みたいな失敗例としての意味合いしかなかったんだろう
長々とレビューしたけど、全然思ったよりは楽しめた。プレイ済み、視聴済みなら「あるあるネタ」として楽しめると思うし、話題性の為に話題になったゲームを無理くり映画にしたという条件の中ではよくできた映画だと評価できる映画だ
ただ人にオススメできるかと言われると、俺には流石にその自信はない
初めて劇場でガッツリホラージャンル作品を観ましたが
思ったより怖かった!!
それなりに面白かった
あのゲームがどんな映画になるんだろうと、期待を胸に鑑賞。
基本はゲームと同じルールなので理解は早かった。
ゲームでもお馴染みの不気味な感覚はそのまま、叔父さんがいい味出してました。
ゲームにはなかった子供との関連性など、感慨深いシーンもありそれなりに楽しめました。
ただし!!
格子模様の白タイツおじさんは是非とも採用して欲しかった、、、
ずっといつ登場するか待ち続けて終わっちゃいました、、、
でも、あーあれね!という感覚を持ちながら映画を見ることが普段ないので、新鮮な感覚でした。
うーーーん
ゲームをやってるとより楽しめる
ゲームはやってましたが、正直あの内容で映画化するのってどうなの?と思いましたが予想に反して良い内容だと思いました。
特にあの歩くオッサンのスピンオフみたいなのが凄い気に入りました😊
欲を言えば異変のイベントをもう少し増やしてほしかったですね。
ヒカキンはあの一瞬だけだったのでしょうか🤭🤭🤭
髪型で気付きましたけど😳
この映画にオチなどない
原作はプレイ済み。
原作が原作なので仕方ないところもあるが、映像がまったく代わり映えしないのでとても退屈。主人公と彼女の話がつまらないのでとても退屈。近くに座っていたガキンチョが携帯を触り始めるほど退屈。携帯触んな。
歩くおじさんはまだしも、子どもは主人公を何となく成長させたっぽくみせるためだけのギミックでしかないのでいらなかったかな。
8番出口が何なのか?なぜ主人公は8番出口に迷い込んだのか?そういう謎はいっさい明かされない。確かに原作もそうだけど映画としてはどうなのかなぁ。
映画もゲームもある意味でまったく同じなので、原作ゲームをやったほうが有意義な時間を過ごせると思います。
あれはもう人間じゃない
ゲームの雰囲気をほぼそのまま再現しつつ、映画としての物語に昇華したのは凄い。
世にも奇妙な物語やサイレントヒルのようなサイコホラーみを感じた。
順番に異変を追いかけるだけでなく途中で「おじさん」にスポットが当たったりなど、ゲーム進行を知っていればえっ!?となる展開。カメラワークも上手く進めたのかリセットされたのか解らないようなタメが合ったりと全体的に映画としてレベルが高かったです。
そういえば元カノからの電話の声が明瞭すぎてちょっと違和感だったかな。
途中の元カノからの電話は異変だったのか、それともほかにまだ見落としがあったのか。
考察すると結構深い気がする。
失つたものを求めて
映画は監督がテーマを投げかけ見る人はその解釈に頭を悩ますもの。この映画もそう、しかし相当分かりやすい投げかけであり、見た人のほとんどはそのテーマを理解できるのではないか。この映画、特に都会に住む人に見てほしい。自分はあの無言で歩き続ける男と同じではないのか、するとどうやれば自分の8番出口にだどりつき、失くしたものを取り戻せるのか?。子供が二宮にあげたお守りが示唆しているのだろう。ジャンルは違うが養老孟司氏が良く話をしていることとの共通性を感じた。脳が考え必要なものしかない都会に暮らし人が失っていくもの......。あなたはすでに失ってないですか?、幸運にもそれに気づいたら、それを取り戻しませんか?。これは単純なホラー、サスペンス映画ではありません。
予備知識なくこのタイトルに誘われ見た、誰でも出口には何かあるのだろうと考えるもの。不気味な無言歩き男の役者は掘り出し者。総じて良品の映画と思います。
中途半端かも
電車男?
素直に映画内で語られず主人公がこれから対処しないといけない事項は2つあり
1つ目は電車男に対する対処、2つ目は分かれた彼女の妊娠の対処
2つ目は、彼女の事を1番に考えてあげて結婚という形をとるのかあるいは他になるのか彼女と話し合って結論を出すしかないです。
1つ目の電車男の対処をどうするか?を考えてしまいました。
当然、電車男とケンカすることなんか母子は望んでいないだろうし
電車男を静かにさせる良い方法が思い浮かびません。
そればかり考えてしまいました。
ヒカキンが出てきたところは気付きませんでした。
8番出口を下りる
おもしろくなかった
あくまでライトな大人向け。
主演がニノ?
監督が川村元気?
人気ゲームが題材?
カンヌで喝采?
どーせ、話題性だけで観客に媚びた映画なんでしょ?
そんな、何の根拠もない「誹謗中傷」気味のスタンスでいた私。
当然、劇場での鑑賞はスルーの方向で予定していたが、どうも私の周りの映画好きからは好評を得ている様なので、重い腰を上げてみた。
いやいや、どーしてどーして。
ちゃんと楽しめる映画でございました。
冒頭、ゲーム上では「自分」だったあの主人公が「嵐のニノ」となり、物語上の設定が与えられたワケだが、私はその設定に感情移入しにくかった分、途中で主観が入れ替わった辺りはすごく楽めた。
この地下道でのループからの脱出が本当に幸せな行為なのか、現実という煉獄に戻るだけでは?という問いかけも、日雇い派遣の主人公より、会社員然としたあの男性の方が当然説得力があるし。
また「ここ曲がったら、壁の数字が増えてる…はず…だよな?」という疑心暗鬼のドキドキというゲーム由来の楽しみも堪能できた。
YouTuberたちによる実況配信で劇的に認知度を上げたことがこの人気の要因だと考えれば、ターゲットは小中高校生といった若年層を中心に、その親世代を含めた広い範囲になる。
でも、このシュールなゲーム内容を映画にすれば、どうしても「尖った」作品にならざるを得ない。
結果、現実に完成した作品自体はすごく尖った部分もありながら、すごく大衆的(悪く言えば「古くさい」「使い古された」)な部分も併せ持つ、微妙なバランスの出来上がりになっていた。
そこが気になるといえば気になる。
あのラストも、「そりゃ、そうなるよね」と受け入れながらも、「主人公の成長、あっぱれ!」という人もいれば「あれ?ヒネリなし?」という人もいるだろう。
その辺りの、「安定の着地」を受け入れるか否かという感想の差はしょうがないんだろうな。
ただし、明らかに「ホラー」に分類されるこの映画を、こういう広いターゲットに向けて宣伝した功罪は、間違いなく劇場の客層にも影響していて、私の観た日曜日朝イチ上映回は、結構な数の小さなお子さん(小学校低学年)連れがおられたが、映画の途中で退席される家族も複数見られた。
ホラー演出・津波表現・望まぬ妊娠・父になる覚悟・繰り越される日常という地獄…
どう考えても子供向けではない演出が繰り広げられるこの作品に、説明なしで子供たちを劇場へ誘い込んだ責任は軽くはない。
おそらく良くも悪くも「こんな映画とは思わなかった」という方も多かっただろう。
ただ、「8番出口」という不条理なゲームの世界観を、挑戦的に物語化したことは評価されるべきだし、大人が楽しめる作品であることも事実。
平均の★評価はどうしても低くなってしまうのは、こういう作品をこういう売り方で拡散させた以上、仕方のないことだし、それでも興行収入は「大ヒット」であれば、それにケチつけるのもおかしな話だし、この数年の洋画のパワー不足の中では頼もしいことだと思っている。
大袈裟ではあるが、いろんな意味でのチャレンジが、一つの結果を生んだという実例として面白い。
全1069件中、301~320件目を表示