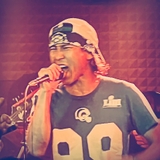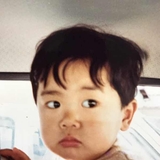木の上の軍隊のレビュー・感想・評価
全208件中、121~140件目を表示
このような映画が作られ続けることが大切。
山田裕貴さんのような若い人にも人気のある人が出演しているのもよかった。(個人的に山田さん大好きです)
この時期になると戦争の映画の上映が急に増える。多分私も、この夏、旧作を含めて何作か見ることになるだろう。
映画自体は、(表現は適切ではないが)口当たりのよい、一番醜いところや見たくない箇所を避けたような映画だった。それでも、若い人が戦争のことに興味を持つ入口として、かえってよかったように思う。実際に劇場には若い人が多かった。
とはいえ、もしも可能であれば、「遠いところ」の工藤将亮監督に、しっかりリサーチして、潤沢な金を使って、同じような俳優さんたちに出演してもらい、同様のテーマで映画を撮って欲しい。(でも、有名な俳優を使ったり、贅沢な金をつかったりすると、いろいろな「しがらみ」から、普通の映画になってしまうのだろうか?)
追記
米軍が九州に上陸する際には、宮崎平野からの上陸を考えていたそうだ。堤さん扮する上官の出身地が宮崎だったことは偶然だろうか。
もしも、終戦が遅れていたら、宮崎や鹿児島でも、沖縄と同様のことが行われたのだろうか。
生き延びることを正面から肯定的に描いてくれたことに感謝
ふたりの兵士の木の上の2年間を描いた映画と聞いて、
間が持つのかしらと思っていたがまったくの杞憂だった。
純粋な性格の安慶名役の山田裕貴さん、
厳格でありながらもちょっぴり虚勢を張った感じの山下少尉の堤真一さんの雰囲気が、
それぞれの役にぴったりハマって魅力的なキャラクターで、物語の世界に引き込まれる。
戦争を描きつつもシリアスな場面だけでなく、
サバイバル生活を通じたふたりの会話が時に楽しく、
また、カメラのアングルも二人がメインではあるけれど、
クローズアップだけでなく、広視野で景色を入れた画面構成など多彩で、
最後まで集中力が途切れることなくみることができた。
沖縄は日本の戦争と平和に関するジレンマ、矛盾の集約された地で、
本作でも随所にその要素が織り交ぜられているが、
全体に暗く、悲劇的、否定的になりすぎない調子で、
なにより生き延びることを正面から肯定的に描いてくれたことに感謝。
いつも沖縄の人たちが生来持つ明るさには救われます。
舞台では何回か上演されている作品というのは知っていたが事実を元に...
舞台では何回か上演されている作品というのは知っていたが事実を元に作られた作品とは、初めて知った。それが映画に〜
誤解を恐れず感想を一言で言うと「面白かった〜」
二人それぞれのアイデンティティがとても魅力的そしてカッコ悪い〜それが魅力的だ。けして強くなくてだからとても強くて誰かをとことん愛してる。もしかしたらこれが日本人のアイデンティティなのかも〜と思った 知らんけど〜
人間、極限的な状況下置かれると精神的におかしくなってしまいそうなの...
もっと前に観たかった!
記憶を風化させない、戦後がずっと続くように、戦争映画は必要。
匿名性、代表性、記号性に欠ける演出
やはり舞台とはかなり異なった印象の作品となってしまった。
二つの主題を挙げることができる。一つ目は「軍隊」について。本作はあくまで「木の上の軍隊」。木の上の男たちでも、木の上の兵隊たちでもない。上官と新兵の二人だけだがそれは軍隊組織なのである。組織である以上目的がある。それは敵を殺すこと。生きのびることだという人もいるが、生き残ることは再び敵を殺せるようになること。国を守る、家族を守ることだという人もいるが、それも再び、国を富ませて敵を殺すことに繋がる。
戦争はもちろん悪であるが、戦争をするのは軍隊である。原案の井上ひさし氏が、この実話に着目して戯曲化しようとしたのは、軍隊を最小単位まで解体してその本質を浮かび上がらせるためだった。軍隊の存在的悪とその存在的矛盾について。舞台では上官と新兵の会話劇としてそこが徹底的に掘り下げられる。
二つ目のテーマは沖縄。沖縄戦の悲惨さとその不条理についてはあえてここで語るまでもないが、要は、人の土地で外から来た者同士が戦い自分たちは巻き込まれ土地も家も親兄弟も奪われるという構造。映画でも安慶名セイジュンがはっきりとそこは表明している。
繰り返しになるが、この2つの主題を徹底的に掘り下げてみせたのがこまつ座の「木の上の軍隊」だったのである。シンプルな舞台装置、最低限の出演者によって、メッセージは色濃く、そして明確に届けられる。
この映画では、必要以上にドラマ性を持ち込むことによって、残念ながらメッセージが薄れてしまったと思う。だから、ゴミ置き場でヌード雑誌を拾うのが嫌だったとか、虫をたべるのが嫌だったとか、戦闘シーンに迫力がない、とか枝葉末節のところに目がいってしまう。そしてメッセージがなんだか分からなかったとか、何があっても生き抜くのが大事だと思いました、といった感想まで出てくるのである。
私は堤真一と山田裕貴という役者は好きでも嫌いでもない。インタビューを読む限りよくこの芝居を理解して頑張って演じているなとは思う。でもここまで顔をよく知られTV等でも活躍しているいわば現代的な役者による演技は、80年前に木の上で怯えながら過ごしていた名もなき顔も知らない兵士の姿とはなにか違っているようにしか思えない。それは匿名性とか代表性といったところなんだろうけれど。
時に笑えるちぐはぐな会話を繰り広げ、いつの間にか樹上での生活に慣れていく2人の変化を演じ切った堤と山田は見事でした。
終戦80年の夏、戦争に関する映画が続々と封切られています。今作は、民間人を含む多くの犠牲者を生んだ沖縄戦にまつわる物語です。戦闘を直接的に描いたシーンは少ないけれど、終戦に気づかないまま2年間もガジュマルの木の上で生き抜いた2人の日本兵の実話を通じて、争わずにはいられない人間の愚かしさと、それでも協力して生き延びていくことができる人間への希望を描き出しています。
実話に着想を得た井上ひさし原案の同名舞台劇を、堤真一と山田裕貴の主演で映画化した作品です。脚本、監督は沖縄出身の若手、平一紘。
●ストーリー
太平洋戦争末期の1945年4月。戦況が悪化の一途をたどる中、飛行場を占領するために米軍が沖縄・伊江島に米軍が侵攻します。激しい攻防の末に島は壊滅的な状況に陥っていました。
宮崎から派兵された山下一雄少尉(堤真一)と地元の伊江島で生まれ育った新兵・安慶名セイジュン(山田裕貴)は敵の銃撃に追い詰められ、大きなガジュマルの木の上に身を潜めます。
太い枝に葉が生い茂るガジュマルの木はうってつけな隠れ場所となり、木の下には仲間の死体が広がっていき、遠くの敵軍陣地は日に日に拡大していくのです。圧倒的な戦力の差を目の当たりにした山下は、援軍が来るまでその場で待機することを決断します。
やがて戦争は日本の敗戦をもって終結しますが、そのことを知る術もない2人は終戦を知らぬまま2年もの間木の上で2人きりの“孤独な戦争”を続けることに。戦闘経験豊富で厳格な上官・山下と、島から出た経験がなくどこか呑気な安慶名は、噛みあわない会話を交わしながらも2人きりで恐怖と飢えに耐え続けたのでした。
やがて食料がつき心労も重なった時に2人の意見の対立が始まります。
きっかけは、米兵の残飯を安慶名が発見したこと。当初は山下は「敵の飯が食えるか」と意地を通し、米兵の残飯を漁ろうとする安慶名を怒鳴りつけて、口論となったのでした。厳格な軍人で、敵国の物を食べたり使ったりすることを拒んでいた山下でしたが、何も食べないままではみるみる衰弱していきます。安慶名は、米軍が残していった缶詰を日本製の缶詰に移し替え、日本産と偽って、食べさせたのでした。
しかし樹上生活が長くなるにつれて当の山下も規律や恥の意識が薄れ、何かと理由をつけて米軍の物を利用するように変わっていきます。朗らかでのんきだった安慶名は、そんな上官の変化に複雑な思いを抱き始めるのでした。飢えを鸚いだ2人はやがて、なんと、米軍のゴミ捨て場を発見します。それによって、2人の生活は大きく変わっていきます。
●解説
脚本がよくできています。悲劇を語りながら、ユーモアを忘れません。厳粛と滑稽、強さと脆さ、涙と笑いが常に背中合わせになっているという認識が根底にあるのでしょう。例えば、たばこを探し当てた安慶名とヌード雑誌を拾った山下の掛け合いなどまるで漫才のようです。堤と山田の息も合っていました。
また米軍の残飯を見つけて食糧事情は好転したふたりの変化も見所です。「援軍を待って反転攻勢」という“作戦”は次第に空文と化し、階級も意味を失っていきます。米兵の余り物で命をつなぎながら米軍への憎悪を抱き続ける、2人の矛盾と滑稽さから、戦争のむなしさをあぶり出したのでした。そこには、生きようとする本能と人間関係の原型が語られていると思います。
しかし、勘所は県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦の歴史。2人だけの軍隊は、日本軍によって「捨て石」として扱われた沖縄の隠喩以外の何ものでもありません。
特に 木の上の“戦い”が始まるまでの序盤の描写で、沖縄戦の本質を凝縮。軍国主義者と庶民の目線の相違を時にコミカルに見せる脚本は奥が深く、人間性とそれを踏みにじるものを力まずに提示して出色でした。
実際のガジュマルの樹上で撮影し、ガジュマルの上からの目線など、映画ならではの映像が見応えありました。主演の2人も体重を落として役に臨んだといいます。米軍の気配におびえ、空腹に苦しみ、時に笑えるちぐはぐな会話を繰り広げ、いつの間にか樹上での生活に慣れていく2人の変化を演じ切った堤と山田は見事でした。
陰惨な描写を避けた点にも、幅広い世代に戦争を考えるきっかけにしてほしいという作り手の願いが感じられました。
●最後に一言
個人的には、解放感が漂うラストとそこに至る過程を描いた演出に好感が持てました。
あることで終戦を知らされた安慶名は、山下に向かってまるで子供のように何度も帰りたいと泣きじゃくりながら訴えかけるのです。これまでの山下なら、そんな軟弱な安慶名を怒鳴り散らして叱るところですが、なぜか神妙になっていくのです。山下が見つめていたのは、安慶名ではなく、泣きじゃくるわが子の姿だったのです。そこに堤がありったけの万感の思いを詰め込んで演じていました。
だからこそ、堤が放つ最後の一言の台詞にとても解放感を感じたわけです。
戦争は考えもつかないような悲劇を起こす
そろそろ帰ろう
太平洋戦争末期の1945年。沖縄県伊江島に米軍が侵攻し、
激しい攻防の末に島は壊滅的な状況に陥っていた。
宮崎から派兵された山下一雄少尉と沖縄出身の新兵・安慶名セイジュンは
敵の銃撃に追い詰められ、大きなガジュマルの木の上に身を潜める。
圧倒的な戦力の差を目の当たりにした山下は、
援軍が来るまでその場で待機することに。
戦闘経験豊富で厳格な上官・山下と、島から出た経験がなく
どこか呑気な安慶名は、噛みあわない会話を交わしながらも
2人きりで恐怖と飢えに耐え続ける。
やがて戦争は終結するが2人はその事実を知るすべもなく、
木の上で“孤独な戦争”を続ける。
といったあらすじ。
私が幼いころにも、実際に数十年も潜伏し続けた、
横井さんとか小野田さんのニュースがあったけど、
今回の話も実話に基づいた話らしい。
圧倒的戦力で、次々と戦死するシーンが前半描かれ、
生き延びた二人も食料がなく、飢えとの戦い。
後半はゴミ捨て場を見つけて、捨てられたゴミから食料確保ができるようになり、
飢えの苦しみからは脱出するも、援軍がくるのを待ち続け、木の上に身をひそめる。
潜伏し始めてから2年以上経過するとは。
帰りたいと訴える安慶名、お国のためと頑な姿勢を崩さない上官山下。
しかし、最後は優しい顔で「そろそろ帰ろう」と。。。
今年は戦争の映画が多いと思ったら、終戦から80年なのか。。。
旧日本軍の歪さと戦争の愚かさ
7~8月恒例の終戦関連映画であり、戦争の愚かさ、当時の軍の在り方の歪さを今に伝えたいという意図がよく伝わってくる、よい作品だと思いました。
原作自体、原案・井上ひさし、舞台化・井上真矢親娘によるもので反戦色が強い。
それを、沖縄生まれ・現在も在住の平監督によって、沖縄出身の新兵・安慶名セイジュンを主人公に据えた「沖縄人(うちなんちゅう)視点」の沖縄戦を描いた本作だけに、派手な銃撃戦や自己犠牲による美談など一切なし。
前半は、理不尽に戦力として男性を徴兵、農地を軍用に徴収、残った女・老人に軍事教練を強制しながら敵襲においては民間人を盾にして司令部だけ洞窟内の防空壕に逃げ込むなど、いかに沖縄を軍が蹂躙したかを描き。
後半は舞台からの映画化らしい、堤真一と山田裕貴の会話劇。
堤真一演じる、本土出身の山下少尉(局長)の命令がいかに体裁と自尊心を守るためだけの狂人の戯言(たわごと)なのかが露わになっていくのがいたたまれない。
少し単調と言うか、前半は恐怖・後半は飢えという戦争定番の表現が続き、眠くなったところもあり。
独特の緊迫感
主演二人に魅せられる
ガジュマルの木の上って守られているようで安心しますね。それが映像でも伝わってくる。
極限状態を演じきった堤真一さんと山田裕貴さんの想いが作品をより素晴らしいものにしているんだと思う。主演のお二人が堤さんと山田さんで良かった。実直で厳格な上官と素朴で優しい青年との2年間は映像で見て想像する以上に過酷な潜伏期間だったと思う。
沖縄の食べ物や植物、危険な生き物、地盤、そして人間一人一人の性格や表情など、そこに住んでいる人にしか分からない描写もあって、悲壮感だけじゃない優しさとあたたかさもあった。
一番好きなシーンは、海に佇む安慶名の名を呼ぶ、というより叫びながら走り寄る山下のところです。もう終盤になると、二人の姿がほとんど同じですね。汚れた服や顔、痩せ細った体。同じ環境に身を置いたからこそ体現された似姿、生き抜いたことに心震えた。もっと広まってほしい作品です。
木の上の2年間。 それは、“戦争が終わらなかった男たち”の静かな記録。
戦争映画というより、“生き延びること”そのものに焦点を当てた人間ドラマとして描かれる作品だった。
実話に基づく物語であるからこそ、演出も過剰なドラマ性には走らず、どこか冷静に歴史を見つめている印象があり、堤真一と山田裕貴、二人の俳優が徐々に体現する「生きるしかなかった人間の姿」に自然と引き込まれていった。
ただ、物語の中盤以降、木の上での生活が本格的に始まると、シチュエーションの特性上、場面展開は少なく、緊張感も徐々に薄れてしまい、視覚的な動きも少ない分、観る側に「思考」や「感情」を委ねる時間が多くなる。
退屈と感じるか、静けさに浸れるかは、観る人の心持ち次第かもしれない。
• 世界へ入り込む度:★★★☆☆
• 感情ゆさぶられ度:★★★☆☆
• エネルギー消費度:★★★☆☆
• 配信でも観ます度:★★☆☆☆
• 人にすすめたい度:★★☆☆☆
【制作エピソード】
作中、極限状態の兵士がウジ虫を食べるシーンがあるが、山田裕貴は「当時の過酷な現実を嘘偽りなく演じたい」と、美術チームが用意したダミーではなく、自ら志願して本物のウジ虫を食べて撮影に挑んだ。
サバイバル生活(加筆修正)
最初の方で戦争によるシーンが終わり、後はひたすら木の上で暮らす二人のドラマ。
終戦(と言っても当人達は知らない)したあたりで攻撃がなくなる。米軍の週末パーティの残飯を漁り、攻撃の機会を伺うが、心の片隅では残っているけど多分途中で本命を忘れてると思う。まあ生きるのが先。
二人の関係性が上官と部下というより、上下関係があってももう少し近い関係性になる。まあ、二人しかいないしね。戦争そのものをダイレクトに伝えるというより緊張感ある非日常を日常として木の上で生活を送る二人のヒューマンドラマを通して何か訴えたいのかな。
⭐︎3.7 / 5.0
全208件中、121~140件目を表示