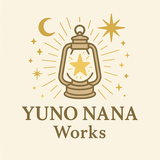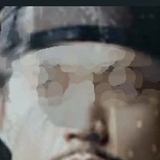木の上の軍隊のレビュー・感想・評価
全208件中、1~20件目を表示
井上ひさし氏が生涯をかけて伝えたかった「戦争の記憶」
本作の原案を手がけた井上ひさしさんは、日本を代表する劇作家。
『木の上の軍隊』は、彼の「戦後三部作(戦争三部作)」のひとつとして位置づけられる作品です。
『父と暮せば(広島)』『母と暮せば(長崎)』に続き、沖縄を舞台にした本作は、わずか2行の構想メモだけを遺してこの世を去った井上氏の“遺志”を、娘であるこまつ座社長・井上麻矢さんが継いで完成させた、親子の情熱が宿る舞台作品です。
そして終戦80年を迎える今年。
この実話をもとにした日本兵の物語が、映画としてスクリーンに蘇るという事実は、非常に大きな意味を持っています。
井上さんは生前、広島市で行われた講演会にて、「同年代の子どもが広島、長崎で地獄を見たとき、私は夏祭りの練習をしていた。ものすごい負い目があり、いつか広島を書きたいと願っていた」「今でも広島、長崎を聖地と考えている」と話しています。
彼の知られている創作モットーは、
「難しいことを易しく、
易しいことを深く、
深いことを愉快に、
愉快なことを真面目に書くこと」
だからこそ、彼の作品(遺志として受け継がれた作品も含めて)にはユーモアと人間味があります。
どんな極限の状況でも、“人として生きる”ための小さな楽しみを忘れない──。
そのやさしさがあるからこそ、観客の私たちは、最後まで希望を持って向き合うことができるのです。
決して、戦争という重いテーマを軽んじているわけではありません。むしろ、軽やかだからこそ、その言葉はストレートに、私たちの心に届いてくるのです。あなたもきっと、最短距離で届く言葉の切実さに胸が締め付けられるはず🧐
木の上で奇跡的に生き延びたふたりの背後には、数えきれないほどの“失われた命”がある。
そのことを、観る私たちは決して忘れてはいけない。
前編ほぼ2人きりで物語を牽引した、主演の堤真一さんと山田裕貴さんには、心からの拍手を送りたい👏 ガレッジセールの川田さんは…あまりに現地に馴染みすぎて、発見できませんでした😅エンドロール曲Anlyの「ニヌファブシ」沁みます。
※ 「ニヌファブシ」は、沖縄の言葉で“北極星”の意。
生きることは、食べること。
生きることは、希望を持つこと。
生きることは…
最後に僭越なら、ご提案
『火垂るの墓』と並び、
この映画も毎年、終戦日前の金曜ロードショーで放送したらいかがでしょうか?──🤫
ほんの少しでも多くの人に、この作品が届きますように。
心から応援しています。
今多くの人に見てほしい映画
正直この作品は、戦争映画が苦手と言う人の、苦手な理由となるシーンが多くある。
でも見てほしい。
80年前に実際に起こったことから、少しでも多くのことを学ぶことが、今の私たちに出来ることだと思うから。
過去沖縄戦を題材にした作品は数多くあれど、沖縄出身・在住の監督が脚本も書き、沖縄のプロダクションが中心となって作られた作品というのはそこまで多くはない。
そして大手の制作会社の戦争映画は、興行収入などを意識すると仕方のないことだけれど、少しエンタメ要素が強くなり、派手さや大袈裟な演出が見え隠れするなと、個人的には感じる。
けれど、この作品はそれが無い。だからこそ感じるものがとても多い。日本で唯一地上戦の歴史があるウチナーンチュの方々が描く沖縄戦だからこそ、生きることへの想いや、戦争が何を奪うかを、私たちの目線で描いてくれている。
そして、演じた山田裕貴さんと堤真一さんが本当に素晴らしすぎた!
後半はほぼ2人の会話劇だったけれど、一瞬も見逃せなかった。
政治に関心がなく、どこか現代の若者たちと似ている、山田くん演じる新兵の安慶名。そんな彼と対極にいる、典型的な「日本軍人」の堤さん演じる山下。
そんな年齢も育ちも考え方も違う2人の距離感の変化や、考え方の変化によって、戦争という環境がいかに人の価値観を破壊し、狂わせるかを描いていた。
特に蛆虫を食べることまでした山田くんの本気度には脱帽。完全に役に憑依していた。
このふたりのモデルとなった方の壮絶な体験が、こうして映像作品となって世に残ることは、戦争経験者が減っていく今、本当に意義のあることだと思う。
戦後80年の今、多くの人が見るべき作品。是非。
時間が長いのはもったいない
配信(アマゾンレンタル)で視聴。
戦争を題材にした作品は個人的にはあまり好まないが、今回は兵士がテーマ。原作は井上ひさしだが、井上ひさしのカラーが存分に出ていた作品。
色々考えさせられた作品出し、堤真一ら出演俳優の演技も良かった。ただ、時間が長いのはもったいない。もう少し短く出来たはず。
戦中の悲壮感、日常、笑い、葛藤が良いバランス
低予算ながら予想外におもしろかったです 戦争の恐ろしさから隠れ忍び...
タイトルなし
木の上だけの話だと物足りなかった。
何かさめる
沖縄地上戦の「伊江島」で2年間生き延びた2人の軍人を描く
場所は伏せますが…(本文に続く)
そろそろ、帰ろう
本島最後の防衛線である沖縄の島に米兵が上陸…。圧倒的な戦力差の前に逃げ込んだ木の上にて極限状態となる2人の様子を描いた作品。
序盤から胸が締め付けられる展開。軍人民間人関係なく容赦なく吹き飛ばされていくシーンは目を覆いたくなる程。大艦隊が見えた時の絶望感よ…。
そして始まる木の上での日々。ただでさえいつ敵が来るかわからない緊張感の中、渇きと飢えも2人を襲い…正気じゃいられませんよね。
山下少尉も、心のどこかじゃわかっていたんじゃないかな…。当時を知らないワタクシ達からすればセイジュンに寄り添いたくなるが、負けた方の家族…確かにこの意味を考えると、少尉もただ盲目的に日本の勝利を信じていたわけではないのだろうな。。
ここの描写は胸が張り裂けそうになった。
その後も、大切な人や家族に対する想いがこれでもかとぶつけられてくるが、ちょっと同じ様な場面が続いて、映画としては体感3時間を越えるような冗長さも少しあったかも…。
思いの外、コミカルなシーンも挟んできたのは良かったけど。
終戦を知ったときはどんな気持ちになったのだろう…我々には計り知れませんね。それでも希望のあるラストだったと信じたいです。
そして…前まではこういった戦争映画に感動できていたが、最近ではなんだか観てて本当に怖くなってしまいますね。
各地で争いは終わらないし、ここ日本も治安の悪化の一途を辿り…取り返しのつかないことになる前に、なんとかなって欲しいものですね。
考えさせられる
戦争が終わった事を知らずに米軍の攻撃から逃れるために木の上で2年も過ごす2人。
毎年、この時期に戦争映画が上映されますが、当時の人達に思いを馳せて気持ちが落ち込んでしまう…のは予想した上で、大好きな沖縄が舞台なのと好きな俳優さんなので鑑賞しました。
予想通り、というかそれ以上に2人に感情移入してしまい、国のためにという洗脳と家族を思う気持ちの板挟みに心が痛みました。
今なお、そんな気持ちで誰かが戦っているんですよね。現代の日本人に自国のために命をかけて戦うなんて可能なのか??そんな事を考えさせられました。
そして米軍がゴミとして捨てていった物資が何と豊かなこと!2人の命を繋いでくれてありがたいけど、食糧も軍事力も差がありすぎましたね。
世界平和を願わずにいられません。
「命こそ宝(ぬちどぅたから)」
沖縄本島、美ら海水族館がある辺りから西側に伊江島がある。島の中心に城山(タッチュー)という高い岩の山があるのみで(ここからの見晴らしが最高!)、あとは穏やかな平地が続く小さな島
1945年4月16日、米軍は沖縄本島攻略の足掛かりにするため、伊江島に侵攻
物語の冒頭は伊江島を沖縄を護るための飛行場造成に駆り出される、島民たちと日本将兵たちの心理的衝突が描かれる。安慶名セイジュン(山田裕貴)と、与那嶺幸一(津波竜斗)は、身近に迫る米軍の恐ろしさも知らず、キツイ労役の合間にぼやきつつも、青年らしいささやかな楽しみを見つけて、日々を生きている
山下少尉(堤真一)は戦闘に陥ったら島民を逃す方法を上官に相談するも、上官は島民を捨て石としか捉えていないことに絶句するが、上官自身も捨て石になる覚悟をしていることに気づく
冒頭30分以上(もしかしたら40分?)、過酷な労役〜突然の米軍侵攻〜民間人も巻き込む悲惨な戦闘シーン〜二人がガジュマルの木の上に逃げ込むまでを描き、初めて「木の上の軍隊」というタイトル出ます
戦闘シーンが短いというレビューもありましたが、私としてはきちんと描いているなと思いました。壕に逃げようとする民間人を、ここは日本軍のいる所だからと素気なく断る兵隊、民間人も軍人も構わず撃たれる戦闘。今冬に人気コミック「ペリリュー〜楽園のゲルニカ〜」の映画が公開されるそうですが、それに連なるであろう戦闘の泥臭さ、命のはかなさが描かれていました
子どもの頃、戦時中を描くドラマ等を見ていると、母が「こんなにきれいな軍服など見なかった、みんな泥まみれで垢がこびりついた、ボロボロの服着てた」とよくケチをつけてましたが、この映画ではそばに寄ると臭ってきそうなクタクタな服をセイジュンや幸一が着ていて、雰囲気がよく出ていた。島民の女の子も沖縄の衣服を適度に緩く着ていて、髪形や、沖縄の家も寄せていて、昔ののどかな沖縄の生活をよく表していたように思う
木の上に2年間近く潜んでいた…という流れについては、何故もっと早くに降りてこなかったのか?という疑問はスッキリしたりはしない。横井庄一軍曹、小野田寛郎少尉らも何と30年近くジャンクルに潜んでいた訳で、本人の手記やドキュメンタリーを読んで、本人達の心持ちがわかるのかと言われたら、現代の史実を知っている者には理解できない
圧倒的な米軍の侵攻の中、二人が必死に生き抜こうとしたこと
(※島民1,500人、軍人2,000人が死亡)
日本軍が救援に来たら、反攻に転じると信じたこと
たった二人の間にも、上官と、島民の軍隊の下働きという上下があったこと
史実では二人の年齢が逆だったことを、映画鑑賞前の新聞記事で知っていた
(具体的な年齢は少尉が28歳、島民が36歳)
この年齢差だったら、また物語は異なったことだろうとも思える
土地の恵みや水の在処、危険な生物(ハブの見分け方)等、セイジュンの島民ならではの知識が二人を生かしたのだろう
二人が隠れたガジュマルは、「ニーバンガズィマール(命を救った神木)」と呼ばれ、後に台風で倒れたりしたけれど、土を入れ替えて、まだ力強く生きている
「命こそ宝(ぬちどぅたから)」
沖縄の命の輝きが映画ラストにきらめいていた
全208件中、1~20件目を表示