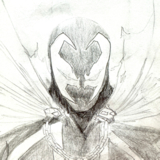シンシン SING SINGのレビュー・感想・評価
全135件中、61~80件目を表示
今年ベスト級!
アートとというプロセスが如何に人間性の回復に寄与するか。
実際にRTA"(Rehabilitation Through the Arts)演劇・ダンス・音楽・文芸・視覚芸術などのワークショップを通年開催する更生プログラム"を修了者は全米の再犯率60%に対し、3%となっているようで、また、本作の出演者の多くが実際のRTA修了者で構成されているということもあり、非常にリアリティある話となっていた。
さらに映画が描いているのはRTAに限った話ではなく、アートというプロセスそのもの(映画をつくること、さらに映画を観るということ)まで、本作は讃えてくれるような暖かさがある。観賞中何度も目頭が熱くなった。
また、劇中のRTA演劇の演出家ブレントが行ったワークショップで「あなたの人生で最高だった瞬間を思い浮かべて〜(中略)」から、それぞれが自分の人生のことを語り、「さぁあなたはもう役者だ。」というシーンがとても印象に残っている。まさにアートというプロセスが人間性を取り戻すという瞬間である。とても活力が湧いて来るセリフだ。
「怒る演技のは簡単。」、「傷付く演技は難しい。」、このセリフは他人に弱みを見せられないという刑務所内での鉄則のようにもみえるが、ディヴァインGを通して上手く他人に助けを戻られない、1人で頑張りすぎてしまう全ての人に当てはまることだと思った。
プロセス
Sue
アカデミー賞ノミネート作品組なので無条件で鑑賞。
囚人が監獄の中で行う舞台演劇とは?というところも面白そうでした。
ドキュメンタリーみたいなタッチで進み、演劇をするためのワークショップの様子を眺めているようでした。
更生プログラムのための演劇という、日本では中々観ることのない風習でしたし、厳しい面が強く描かれがちなムショ映画なのに開放感があったのが良かったです。
演技を通しての友情や信頼、演技があるからこそ生まれる乖離、演技をやっていたからこそ気づいた大切なものなどなど、演技と収監生活がここまでリンクするとはという驚きが確かにありましたし、演技力が裏目に出てしまうシーンもあったりと感情は大変でした。
主にGとアイの2人がメインで衝突したり、マイクマイクが賑やかしてくれたり、メンバーがそれぞれの境遇を語って和気藹々としたりするので安心して観れるな〜と思っていたところに後半では急展開が入ったりと、ここが監獄だっていう事を時折思い出させるシーンがある作りはリアルで良かったです。
ただ全体的には会話劇メインという事もあり、演劇でステージに立っている時は場面の移り変わりがあるんですが、どうしても素でやっている時の画面に華やかさは無く物足りなさを感じてしまいました。
カメラワークにうんたら言えるほど偉くはないんですが、アップで映しているシーンが多く、どうしてもノイズになってしまいました。
舞台ならではの臨場感もどうしても盛られ具合が過ぎてしまい、演劇よりもしっかり映画になっていたなと思いちょっと残念でした。
出演者のほとんどが囚人だったというのも素晴らしく、その雰囲気を知っているからこそ醸し出せる雰囲気がありましたし、ぶつかり合いもスリルがあったりと見応えがありました。
ラストシーンはちゃんとそこに繋がってくるのねというラストで、みずみずしいまでの空が美しかったです。
役者陣の振り分けかたがここでも活きてくるなんて、配置がうますぎるわ〜となりました。
日本では中々刑務所の様子が公開されることは無いので、日本の刑務所でもどんな更生プログラムが組まれているのかなという興味が出てきました。
なんにせよアカデミー賞ノミネートは納得な1本でした。
鑑賞日 4/17
鑑賞時間 18:35〜20:25
座席 B-11
独居房は狭いアパート程度に個性的にカスタマイズ
とても興味深い映画。
アメリカ・ニューヨーク州のシンシン刑務所が舞台。シンシン刑務所は、ローゼンバーグ事件のローゼンバーグ夫妻が電気椅子で死刑になるまで収監されていた刑務所。
主要な出演者は、主役など4人を除いて全てシンシン刑務所の元収監者が本人役で出演しているみたいです。
特に、準主役とも言えるクラレンス・マクリン(本人役)は良い演技でした。
とても興味深かったのは、凶悪犯が収監されている刑務所なのに、独居房が狭い安アパート程度に、個性的にカスタマイズされていたこと。
壁に絵が貼ってあったり、本棚があったり、ペンや色鉛筆が沢山あったり。
日本の刑務所のこれまでイメージとかなり違うと思いました。
しかし、調べてみたら、日本の刑務所もかなり様変わりしているようで、独居房にも各々液晶テレビがあるらしい。びっくりです。
網走番外地の時代ではないのですね。
【実在の最も重い警備で有名なNYシンシン刑務所を舞台にした演劇による更生プログラムを受ける"as himself"元収監者出演多数映画。今作はそこにこそ、この映画の価値があると思った作品である。】
ー ”今週のシネコンの収益はコナン君に任せた!”と思いながら、久しぶりに名古屋のミニシアターの殿堂へ。
映画好きの人達が集う映画館であり、上映中の映画のフライヤーも刈谷日劇同様にババーンと置いてある太っ腹の映画館である。で、今作も含めた上映中の映画や他の映画館ではお目に掛かれないフライヤーを多数ゲットしてから、予約してあった席へ。-
■実在の最も重い警備で有名なNYシンシン刑務所を舞台にした演劇を通して、ムッチャ怖い顔の収監者たちが人間関係を育みながら変容する過程を追ったヒューマンドラマ。
無実の罪(本人曰く。ここら辺はキチンと描かれない。)でシンシン刑務所に収監されたディバインG(コールマン・ドミンゴ)。だが、彼は更生プログラムRTAの演劇活動が、自由を感じる唯一の場である。
そこに、白人の収監者を脅しているディバイン・アイ(クラレンス・マクリン:"as himself"第一号)が志願してくる。ディバインGは共にプログラムを仕切っているマイク・マイクと彼の演技を見て参加を認めるのである。
最初は”仕切ってんじゃねーよ!”などとディバインGに突っかかるマクリンだが、演技を練習するプロセスで、彼の態度は徐々に変化していくのである。
◆感想<Caution!内容に触れています!>
・冒頭から、ムッチャ強面の”俳優”多数出演で、”どっから集めて来たんだろ?コールマン・ドミンゴくらいしか知らないぞ?”と思って観ていたらエンドロールでビックリ。多数の"as himself"俳優で”マジっすか!”である。
・演劇活動の題目は、シェイクスピアなどの重いモノが多かったのだが”喜劇をやろう!”と言う事になり、タイムトラベルも入れたゴチャマゼ演劇をやる事になるのだが、その演劇については余り映されない。が、エンドロールで本物の劇の映像が出てくるのだが、結構受けていたなあ。
・RTA参加者たちが、自分の人生で一番輝いていた時を話すシーンは、彼らの絆を感じたシーンである。小遣いで買ったかき氷の味、芝刈り、妻にプロポーズした時。だが、そんな時は彼らの人生には戻って来ないのである。
・ディバインGは、親切にもクラレンス・マクリンの仮釈放の面接のノウハウを纏めて渡して上げるのだが、ある日盟友と言っても良いマイク・マイクが小さな収監室で脳動脈瘤破裂で突然死して、且つ彼の仮釈放の嘆願も通らずに、彼は劇の練習中に”こんなことをやって何になるんだ!”と暴言を吐き、その場を去ってしまうのである。
驚きつつ、その後姿を見るRTA参加者たち。
だが、刑務所の庭で独り座っているディバインGの所に歩み寄るクラレンス・マクリンが言った言葉が沁みる。”皆で話し合ったんだが、お前を赦すよ。”
<そして、クラレンス・マクリンは一足先に仮出所をし、漸く刑務所を出たディバインGを出迎え”自由は良いな。”と言いながら強く抱き合うのである。
今作は、実在の最も重い警備で有名なNYシンシン刑務所を舞台にした演劇による更生プログラムRTAを受ける"as himself"元収監者出演多数映画であり、そこにこそこの映画の価値があると思った作品である。>
■一応記すが、私の臨席のオバサンは序盤からガックシと頭を下にして熟睡してました。私は優しいので、そのままにしておきました・・。
刑務所であることを忘れ、一人ひとりの尊厳に目がいく
芸術を通じて更生を図るプログラムのRTA (Rehabilitation Through the Arts) は1996年にシンシン刑務所で始まった実在するプログラムで、RTAのサイトによれば、このプログラムを経た者たちの再犯率は、プログラムを受けていない者たちよりずっと低いそうだ。
彼らは演じることを通じで自分の内面と向き合い、他人の立場に身を置くことを通じて自分では気づかなかった新たな一面を発見する。また、決して一人では成り立たない演劇で互いに信頼し合うことを学び、協同して作り上げる喜びを感じ、人としての尊厳を取り戻していく。
鑑賞中、彼らの人間としての悩みや役者・芸術家としてのもがきを見ているうちに、彼らが収監されていることなどつい忘れてしまい、途中に挿入される減刑聴聞などの場面で「そうだ、ここは刑務所の中だった」と思い出さされる。
刑務所だから、犯罪者だから、といった色眼鏡を外して一人ひとりと向き合うことで、それぞれの人の素晴らしさが見えてくるのではないか。逆に言えば、我々は様々なレッテルを人々に貼って偏見で見ることが多すぎるのではないか?
初めから犯罪者として生まれてくる人間などいない。個人の責任がまず問われるのは当然のこととして、一方で、貧困や差別、偏見など社会的・経済的環境、あるいは家庭内での虐待などによって、いつの間にか犯罪手を染めざるを得なくなった人々も少なからずいるであろう。
だからこそ、個人の尊厳を踏み躙ることなく尊重することが大切なのだ。そして、一人ひとりが尊重されることが学べるのであれば、矯正プログラムだけではなく、学校などにおける通常の教育プログラムにおいても演劇はもっと取り入れられても良いのかも知れない。
タイトルなし(ネタバレ)
米国NYのシンシン刑務所。
最重警備施設であり、収監者の多くは重罪で長期収監されている者たちだ。
ただし、同施設では、演劇などの芸術を通じての更生プログラムRTA(リハビリテーション・スルー・ジ・アート)を行っており、同プログラムの受講者は更生率が高い。
演劇プログラムに欠員が出て、新たに受講者を求めることになった。
採用されたのは、クラレンス・“ディヴァイン・アイ“・マクリン(本人)。
麻薬密売地帯で生まれ育ったためか、犯罪・暴力の世界にどっぷり漬かっている。
プログラムを主導するのは、殺人罪で長期収監されているジョン・“ディヴァイン・G“・ホイットフィールド(コールマン・ドミンゴ)とマイク・マイク(ショーン・サン・ホセ)。
しかし、ディヴァインGは、殺人事件は冤罪だと訴えている・・・
といった物語。
ドキュメンタリー的と謳われていたので、RTAプログラムの詳細を伝える映画かと思ったが、意外とドラマ部分のウェイトが大きい。
RTAを通して、ディヴァイン・アイの心が落ち着いていく様などはドラマとしての見どころはあるが、ディヴァインGの冤罪設定などはドラマ的にはやや上滑りしている。
(劇中、殺人は自身が否定し、真犯人の告白もあることから冤罪だが、武器所持の罪は否定していないので収監自体が誤りというわけではないとも思えるので、冤罪部分のドラマが必要だったかどうか疑問符)
ドキュメンタリー的なのは、ディヴァイン・アイ以外のほかRTA受講の元収監者が本人役で出演しており、本プログラムが有効に機能していることはうかがい知れるが、RTAを受けた者と受けていない者との対比が映画の中で薄く、かつ、受講者で釈放された者の更生エピソードもやや薄い(後者は劇中では1名登場するのみ)。
そういう意味では、少し食い足りない。
元収監者が本人役を演じることで、製作意義は達しているとはいえるけれども。
表情が素晴らしい
米ニューヨークで最も厳重なセキュリティが施された
シンシン刑務所で行われている収監者更生プログラムの舞台演劇を題材に、
無実の罪で収監された男‘ディヴァインG’と収監者たち、
そして、途中参加の刑務所で一番の悪人として恐れられている男、
通称ディヴァイン・アイこと‘クラレンス・マクリン’との友情を描いた実話の映画化。
粛々と感動しました。
個々のバックボーンは深追いせずでしたが、
このような刑務所と更生プログラムがあることを知りえましたし、
また演劇に関わることが彼らにとって、とても大切なものであることが伝わってきました。
そして、演じている収監者の表情がとても魅力的。
俳優のコールマン・ドミンゴ(ディヴァインG)や、
ショーン・サン・ホセ(マイク・マイク)はもちろんなのですが、
本人役のディヴァイン・アイも良いのですが⋯
わたしは、個人的にこれまた本人役のショーン・“ディノ”・ジョンソンに惹かれました!
稽古中に後ろを歩かれて、イライラして喧嘩になったところを止めたシーン。
あの話は本当なのかなぁ⋯。涙が本物みたいだったから。
みんな涙がポロッと流れるのが自然で、とてもキレイでした。
「劇中劇」を超え、「劇中劇中劇」という新しいジャンルを確立した作品
NY、<シンシン刑務所>。無実の罪で収監された男ディヴァインGは、刑務所内の収監者更生プログラムである<舞台演劇>グループに所属し、仲間たちと日々演劇に取り組むことで僅かながらに生きる希望を見出していた。そんなある日、刑務所いちの悪党として恐れられている男クラレンス・マクリン、通称“ディヴァイン・アイ“が演劇グループに参加することになる。そして次に控える新たな演目に向けての準備が始まるが――(公式サイトより)。
演劇グループに所属する一義的な意味は、自由が制限され、娯楽が少ない刑務所の中で自由に楽しめるから。しかし本質は二義的な、「何者かを演じることで、自分に返ってくるから」であろう。掛け声にもなっている「RTA」とはRehabilitation Through the Artsの略称。これはどこまでに行っても更生プログラムである。
一方で、過去の罪を、自らではどうしようもなかった出自を、そこから連綿と続く現在の自分を乗り越えるのはなかなか難しい。娑婆に居るわたしたちにだって難しいのに、まわりが自分と似た犯罪者だらけの刑務所であれば、どこか赦される感覚を覚えることや却って居心地が良くなることもあるだろう。全体の出演者の85%が元収監者という本作は、いわばそういう虚無的な堕落を乗り越えた人たちによる、自分次第で何者にでもなれるのだという、静かな賛歌である。
その意味でこの映画は、いわゆる「劇中劇」を超え、「劇中劇中劇」というか、「ハーフドキュメンタリー」というか、何かしら新しいジャンルを確立したと言える。さらに、アカデミー賞にまでノミネートされたことで、「何者にでもなれる」がより強化された。さぞかし本人たちも驚いたであろう。
デジタル撮影が主流の現代において、16ミリフィルムで撮影した意図は、合間に挿入される刑務所での本当の記録映像との地続きを表現するためだろうか、デジタルに比べピクセルがでかい分、色が濃く、鮮やかに映える。
ドラマよりドキュメンタリーの方が良いかもしれない
犯罪者が刑罰でない更生プログラムを受けるという話はそれなりにわかっていたので、期待した。演じる場面より、じっとして口々に言い合う場面が多いので、退屈だった。黒人女性担当者から聴聞を受けることになり、演技ではないかと疑われる場面は、少し可哀想になった。結果が出るまでの待機時間に移り、実物のカーテンコールの場面が続き、少し希望を感じた。釈放で解放された後、エンディングでは、様々な表情や動きをする当事者たちが登場し、そのドキュメンタリーでも良かった気がした。
チームに仲間ができる流れが素晴らしい
刑務所で行われている演劇による更生プログラムを扱った映画と聞くと、不思議とフランス映画をイメージしてしまった。フランス映画をリメイクしたんじゃないかと疑ったくらい。でも、何より驚いたのが本当に元収監者たちが多数出演していたこと。この更生プログラムに参加していた人はほぼリアルな収監者じゃないか。そりゃ知らない俳優だらけだよな。
実際にあった出来事をベースにしているから、それほどドラマティックな事件が起こるわけではない。一からプログラムを作っていく姿を描くのではなく、何回か上映した状態の彼らと新たに参加した収監者を描く手法。でも、皆で何かを作り上げようとするだけでちょっと感動してしまう。一応のトラブルは待ち受けている。最初は壁を作って嫌な奴全開だったディヴァイン・アイが、プログラムの仲間になっていく過程もすごく好きな流れだ。途中から、ラストの感動はもう約束されたようなものだった。
ディヴァインGは無実の罪で収監されているから別の感情になるが、他の収監者たちは基本的に何かしらの罪を背負っている。そんな彼らにどこまで感情移入できるのかが大きなポイントに思える。だから彼らの罪名は基本的にわからないまま。変に知ってしまうとその罪の重さで観ている側に先入観が生まれることを懸念してのものだろう。正しい判断だと思う。
何かしらの罪を犯したとしても人間であることに変わりはない。シャバに戻った人間が訪問し、現在の気持ちを吐露するシーンはそれを象徴するいいシーンだった。つーか、アメリカの刑務所自由すぎないか!?人間的に生活できるよう配慮されている気がする。日本との違いを感じた(日本の刑務所は知らないが)。
出演していた人たちは基本的にいい人に思えたが、他の収監者たちの中には減刑を審査する人に対して平気で嘘をつく人も多いかもしれない。だからこその「今も演技しているのですか」という質問なのだろう。あの発言に対して自分ならどう答えるのか考えてしまった。アンガーマネジメントのいい事例なんじゃないか。自分の成熟さを問われる嫌な質問だ。単純に感動させるだけではない、奥深さを感じる映画だった。
ドキュメンタリーを観ているような・・・
元受刑者だった出演者たちの面構えが、存在感が素晴らしい
ドラマティックな展開があるわけではない。原則として俳優たちが大見得を切ったりもしない。一見、「治療共同体(TC)の車座対話」を淡々と追ったドキュメンタリー作品のようにもみえる。劇映画らしからぬ静かな作品だ。
刑務所の収監者たちが演劇を上演するというコンセプトは、過去にタヴィアーニ兄弟の『塀の中のジュリアス・シーザー』などの作品にもあった。しかし、本作では舞台本番に向けてドラマが収斂していくというより、むしろそのリハーサル過程における人間関係の微妙な変化をじっくり見つめることの方に主眼が置かれている。
言葉にしづらい感情をカタチにする作業を地道に重ねていく行程において、「自分」という殻の奥底に閉じ込めていた心の声に向き合い、ひいては周囲の他者の声にも耳を傾ける——この「RTA(芸術更生プログラム)」への参加経験を有する元受刑者が本作に大勢出演していることもあって、この映画自体が、一種の「ドラマセラピー」ともいえそうな演劇の有効性を証明するものとなっている。
見方を変えると「アマチュア演劇が上演に漕ぎつけるまでの過程を追う」という設定だから、「演劇本来の魅力」や「戯曲の台詞」をしみじみ噛みしめることができるようなシーンはほぼない、とも言える。
それでも、コワモテの収監者がRTAへの参加希望理由を問われ、獄中でたまたま手にした本の一節「人間、生まれてくるとき泣くのはな、この阿呆どもの舞台に引き出されたのが悲しいからだ」(※小田島雄志訳『リア王』より)に激しく共感したから、と答えるシーンなどは、演劇ファンなら大きくうなずくところだろう。
このコワモテの男を演じるのが、元受刑者のクラレンス・“ディヴァイン・アイ”・マクリン本人だ。彼の面構えががイイ。前歯の欠けた口元が実にいい。映画後半ではにかむような表情をのぞかせると人間味があふれ出す。
彼以外に本作に起用された元受刑者たちも一人ひとり、佇まいそのものが存在感を放っている。ちなみに映画前半で、彼らが刑務所内の舞台オーディションを受けるユーモアたっぷりのシーンがあるが、これは本作における実際のキャスティング・オーディション時の映像を使っているのだとか。
そんな彼らに対し、主役のコールマン・ドミンゴらプロの俳優陣も抑え気味の演技で応え、あたかもフレデリック・ワイズマン作品のような日常感を保つことに貢献している。それだけに、コールマン・ドミンゴの仮釈放審査委員会のシーンをはじめ、幾つかの箇所で見られる「典型的な劇映画」的演出には少々違和感を覚えた。また、仮釈放の希望を閉ざされたうえに大切な仲間も喪った彼が周囲に八つ当たりしてしまうあたりの描写も、演技臭が強く出過ぎており、全体の雰囲気を破ってしまって惜しい。
格子のない窓
主役以外はご本人とはいえ、元受刑者で現俳優みたいな人達なのかなぁ。更生プログラムの参加者ではあったみたいだけれど。
普通に見れた。
いや…普通過ぎた。
とても崇高な作品だとは思う。過ちを犯した人間を許せる社会が実現されていて、舞台上には一般の共演者もいて、客席からは笑いと拍手が向けられる。
…複雑だけれど、更生させる資格があるのかと疑問を抱く人もいるとは思うけど、長い目で見たら間違ってはいないんだろう。
参加者にしてみれば別世界なんだと思う。
よくこんなプログラムを思いついたなぁと感心するのだけど、理には適ってるようにも思う。
演出家をかって出た人は肝が据わってんなぁとも思うし、途中途中で挟まれる各人の半生からはバイオレンスしか感じない。
札付きの悪である囚人がプログラムを通して更生し、本人も諦めてた仮釈放を許可されたりする。
その手伝いをしていた主人公は、心の支えでもあった友達を亡くし、仮釈放の面談では「それも演技なの?」と理不尽な質問もされる。立ち上げたプログラムがマイナスに働いた瞬間の表情は…あのまま動かないんじゃないかと思う程に絶望に支配されてた。
主人公のお気に入りの場所として、度々出てくる格子のない窓。
拳が一つ通る程の大きさなのだけど、そこが唯一格子に邪魔されず景色を眺める事が出来るのだとか。
なんかコレが更生プログラムとリンクしてくる。コレを「希望」と呼んでいいのか「泡沫の夢」と呼ぶべきなのか。近づけば格子は見えない。が、引いて見れば格子の存在に気づいてしまう。無くなるわけではないのだ。彼らが収監されてる事に変わりはない。
なんか一気に虚しさが込み上げてくる。
そりゃそういうもんだよなぁ…。
彼らを描くから、彼らに感情移入もするけど、れっきとした犯罪者だもんな。
物語は主人公の出所で幕を閉じる。
不慣れな自由を肌で感じてるかのような主人公は絶品だった。
どんな場所でも状況でも、人って1人じゃいられないんだろうなぁなんて事を思い、人と協力して創る「演劇」ってものには、他者共生の側面なんかもあったんだなぁと、そんな事を漠然と思う。
にしても、どなたもカメラを全く意識してない芸達者ぶりだった。監督はどんな脚本と演出を用意したんだろうか?見事だと思う。
良作ではありますが
全135件中、61~80件目を表示