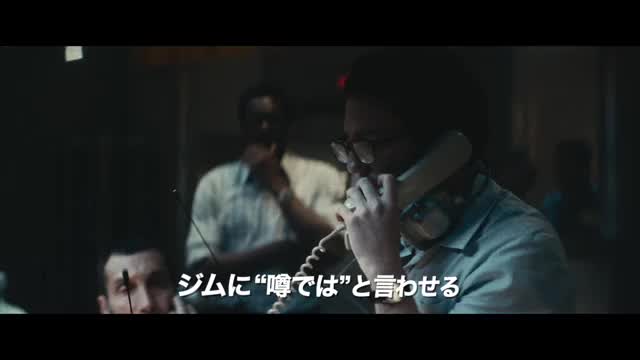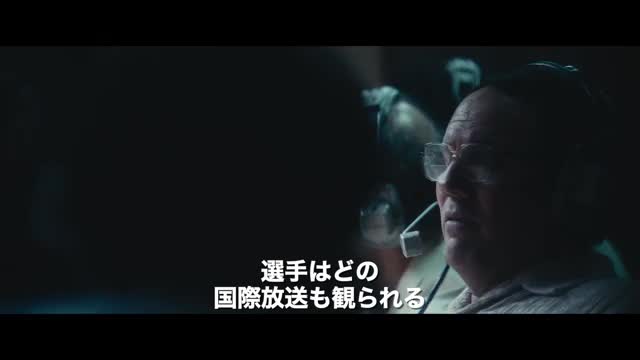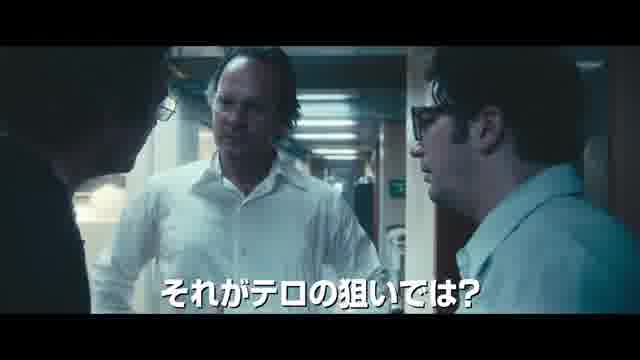セプテンバー5のレビュー・感想・評価
全197件中、101~120件目を表示
題材と視点
今、“敢えて”これ(ミュンヘンオリンピック事件)を題材にするか、と作品に対して若干の複雑な印象を持ちつつも、第97回アカデミー賞「脚本賞」にノミネートされた本作がどんなものか、自分の目で確かめるためにTOHOシネマズ日比谷へ。公開1週目にもかかわらず小さなシアターが割り当てられており、会員サービスデイ10時55分の回は少ない席数に対してなかなかの客入りです。
カラーテレビが(アメリカの)一般家庭にも普及し始めた1970年代前半、72年に開催されたミュンヘンオリンピックは「時差」という壁をものともせずに非常に高い関心を集めていたこともあり、放送局(ABC)の力の入れようがまざまざと伝わってくるオープニング。ただ実際の現場では、24時間体制で対応できる環境を維持するため、疲労やストレスが溜まるスタッフたちと、度重なる機材の不調に融通の利かない(西)ドイツ人との交渉など、そこらじゅうにバッドバイブスが漂っていて皆テンションは低め。そんな中、不意に聞こえてきた「銃声」に急遽スタジオはざわめきだします。ただ、オリンピック中継のために集まった現場スタッフ達は当然「スポーツ班」であって報道のプロではありません。それでも、目の前で展開されるスクープに抑えきれないジャーナリズム。ABC中継のコーディネーション・プロデューサーであるジェフリー・メイソン(ジョン・マガロ)はそんな未知の状況を、手持ちのリソースと少ない情報の中でスタッフを差配しながら、ABCスポーツ社長のルーン・アーレッジ(ピーター・サースガード)を中心に、前代未聞の事態を「生放送」での放映することに踏み切ります。
今作を鑑賞するに当たり、しばらく前に観たきりの『ミュンヘン(06)』を観直してからという考えもあったのですが、今作があくまで報道側を視点にしたアングルに対して「見えてくるもの」を素直に感じるためにも、敢えて(本事件について)曖昧な記憶のまま「疑似的な新鮮さ」で挑むことにしたわけですが、正に報道の舞台裏の緊張感・臨場感がそのままに伝わってきて95分の上映時間はあっという間でした。例えば、今見ればめちゃくちゃアナログな手法の数々はむしろ新鮮で、基の映像素材にテロップを入れる方法や、印刷された写真の引き伸ばし方は正にプリミティブ。また電話の受話器を直結して音声を取り込んだり、ポータブルラジオを改造し周波数帯を変えて警察無線を傍受したりは、昔の「機械いじり」の楽しさを思い出してついついニコニコ。そして、起きている事実を忠実に伝えるべき報道の意義と、どこまであからさまに伝えてよいものなのかを判定する倫理観。更にはタイムリーに伝えるライブ感と、確実に裏付けを取る慎重さなど、現場は常に判断することのせめぎ合いの連続。一方で安全な場所からテレビと言う(当時の)最新メディアを通して観ている「野次馬」達にとって、これ以上ないほどのエンターテインメントだったことでしょうし、或いはこれが(報道部ではなく)スポーツ班が作ったものだからこそのエモみすら感じ、その後の報道番組などに大きな影響を残したことも想像に難くありません。
と言うことで、当初の引っかかりについてはむしろ、現代の「報道の在り方」についてまた考えなおすことも含めて観る価値のある作品でした。そして、本作を観たからこそ改めて『ミュンヘン』を観直したくなりました。堪能です。
もっと観られるべき
スピルバーグの「ミュンヘン」は未見で、事件の顛末は知らないまま鑑賞。
冒頭からテンポ良くずっと緊張感が続く作り。そりゃこのぐらいの尺でないとこっちの身体が保ちませんわ…
実話ベースなのでカタルシスはないが、結果的にどんでん返しはあったり(良くはないけど)して、すっごく『映画を観た』感覚がある。
よく考えるとかなりミニマルな造りでほぼほぼ室内劇なんだけど、当時のフッテージをたっぷり使ってそうと感じさせない上手い造り。
取り扱ってるテーマも、1972年の話ながら報道と正義、テロリズムやデマなど実に現代的なものでまったく古びてない。というか初期だからより純粋に課題が示されているとも言える。
これ、もっと観られるべき映画なんじゃないかな…
お薦めです。
NHKスペシャル風(ただし、ナレーションはなし)
浅薄につき、1972年のオリンピックがミュンへンであったこと、またそこでこのようなテロ事件があったことも知りませんでした。
報道人の野次馬根性と倫理観の狭間で悩みながら、テロの実況の生放送に挑み、右往左往する報道クルーたち。
携帯電話もPCもない時代、トランシーバーやダイヤル式電話、ラジオ等を駆使して情報をやりとりしているのが懐かしくもあり、新鮮。
男性3人は誰が何の役割だか、結局最後まできちんと把握できなかったのですが、それでも全く問題なし。
メンバー内唯一のドイツ人女性、マリアンヌのしごでき()具合が光っていましたね。
一切の無駄もなく最後まで緊迫感を持って、再現ドキュメンタリーとしては楽しく見れる作品ですが、〆に何か考察があるわけではないので自分で深掘りして考えなければなりません。
過去の愚行を繰り返してはならない、というメッセージを含んでいるのでしょうが、今なお熱いイスラエルとパレスチナ問題、地理的に遠いというのと、宗教感の違いからかいまいちピンとこないのです。
多神教の日本人から見ると、聖地を巡って殺し合うとか、何もそこまで?と思ってしまうのですがね。(そんなに単純な話ではないのでしょうが)
彼の地にいつの日か平和が訪れることを願うばかりです。
緊迫の報道戦
テロリスト
常に緊張映画
今を伝えるということ
インターネット環境もない、スマホもない、翻訳機器などもない。そんな環境のなかで、さながらアスリートのように、情報の壁、時間の壁、言葉の壁、国境の壁、様々な障壁をクリアしながら、現実を捉え伝えようと奔走したテレビマンたちの様子を、今そこに立ち会っているかのように錯覚させられるほどリアルにみせられました。それもあって、私がジェフだったとしても、「噂では…」と伝えることを選んでしまっていただろうな等と想像しながら観てしまいました。
「今ここにいる私たちが伝えなければ」という想いは、サウナのアウフグースを想わせるほどの「熱」というかたちでみせられた気がしました。
功と罪の両方をもたらした中継となったわけですが、関わる皆さんが現実に真摯に向き合った結果であったように見えましたし、伝えようという想いとディスカッションに基づく連携がなし得た結果だったのかなと感じました。
便利になり過ぎた今を生きる私たちがあの環境に置かれたとしたら、同じように行動できたのかな?と振り返ってしまいます。53年経った今、良くなったのは届けられる画質だけってことはないですよね。
もちろん作品として何らかの脚色がなされていることとは思いますが、現代の報道に携わる方々にも、この作品に出てきた人たちと同じ「熱」があることと信じたいと思いました。
初めて知った
実際に起こった哀しい事件であるが、捉え方と描写がもひとつに感じた。
今作「セプテンバー5」は1972年9月5日発生した実際の事件、ミュンヘンオリンピック開催中にパレスチナ武装組織”黒い九月”によるイスラエル選手団の選手村襲撃事件の事をメディア報道視点で描いており 初めてテロを世界に向けて実況生中継したとされている。
しかし中継したことで警察の作戦行動がTVを通して晒され作戦変更を余儀なくされた事、後の空港への犯人ヘリ移送と銃撃戦との流れに繋がる。
何にせよ、無実なイスラエル選手団11人と警察官1名、犯人8人中5名が死亡。3人は逃亡図るが逮捕されたとされる。
この事件を受けてイスラエル側(モサド)がパレスチナに対して報復行動に。
この報復作戦映画が2005年「ミュンヘン」である。
こっちの映画は昔観ましたが、なんか電話取ったら爆弾でドカンとホテルの壁に穴が空いて・・・すんごい映画だったのを覚えてます。
確かエリック・バナさん主役でしたね。
今作の方は、ドキュメンタリチックな報道クルーの視点からの展開となってます。
よって 何やってんだか? 凄い慌ただしさは分かるのですがもう一つ重要さや
過激な部分のクロ-ズアップがほぼ無く、音声だけが語っている感じなんですよ。
立て籠もる犯人像と人質の安否とか、ヘリに乗せられた流れとか警察交渉とか、空港での銃撃戦がなぜ起こったとか・・・大事な所がぼやけてて。
何やネンの残念な思いが大きいです。
必死にドイツ語を通訳する女性だけがファインプレ-だった様な思いです。
空港でのヘリ移動後の銃撃戦。一時は人質解放とか?
一斉に喜んだとか思えば それは誤報で。
直ぐに訂正で 全員死亡とか・・・。
メディアの右往左往場面とか 未確認発表(人質安否)の半ば丁半博打的報道とか、誰が責任取るとか、まるで 巷のFテレビとB誌との報道の様相を呈してます。その程度の捉え方と 初めてのテロ中継をどうやって行ったとか、そっちの方が重点となっており ちょっと全体的にがっかりな構成を感じましたですね。
題材はシッカリしたテーマなのにね。
誰が報道側のドタバタに興味あって観るんだと思いましたね。
このミュンヘンオリンピック事件ですが
これも 米国大統領のガザに対しての動向注視しての公開なのでしょうね きっと。私的には、セプテンバー5 + ミュンヘン作品を足してちゃんと大作に再構成し直して公開されたら評価したい所でしょうか。あくまで希望ですがね。
公平でかつ平和な枠組みを持つ事が最優先されるべきだと感じます。
ご興味ある方は
今の内に劇場へどうぞ。
期待度○鑑賞後の満足度◎ 先ず演出と演技が凄い。正に眼前で報道を見ている様な迫真性と緊迫感。テロの世紀の始まりの出来事を描いただけでなく現在進行形でガザで起こっている事とリンクする現代性。
①「ミュンヘンオリンピック」は物心着いて初めて真剣に見たオリンピックだったので(「東京オリンピック」の時は物心着いておらず、「メキシコオリンピック」の時は幼すぎ)、この事件は子供心にも結構ショックだった。勿論、当時はパレスチナ問題なんて分からなかったけれども。今でも、オリンピックは平和の祭典なんて呼ばれているけれども、政治と商業主義に毒されているという密かに心に抱いている疑惑を払拭出来ないのもそのせいかも。
②演技陣のアンサンブルが凄いが特に中心となるルーン役のピーター・サースガード、ジェフ役のジョン・マガロが好演。
紅一点というわけではないが、この前観たばかりの『ありふれた教室』のレオニー・ベネシュが通訳のアリアンヌ役で鮮やかな印象を残す。
緊張感が緩むことなくエンドロールを迎えた
スポーツ局の人間が、テロの生中継をする!!
「真実」という言葉の功罪
例えば、ベトナム戦争は、初めてテレビでリアルタイムで見る戦争だった、という話を聞きます。その時に流れていた、アメリカ側(所謂「西側」)の野蛮で凄惨な行為がブラウン管をとおしてお茶の間に流れた結果、アメリカのみならず世界中で反戦デモが起き、アメリカ国民のベトナム戦争への意欲はみるみるうちに減退していったと言います。それが、結果的にベトナム戦争からアメリカ軍を撤退させたとも言います。わたしは、その時代に生まれてもいないので、実際のところは知りません。
真実というものは、とかく、「真実のようなもの」ほど「真実」と言われるように思います。そしてもう一つ、真実を求めることは「正義」だと思われています。特に、ジャーナリズムにおいて、真実の追求こそが職業倫理の頂点であるかのように信奉されてきたのだろうか、と思うのです。
ですが、果たしてその考えは合っているのだろうか、とこの作品を見て考えました。
1972年9月5日。ミュンヘンオリンピックに湧くドイツは、第2次大戦での苦い傷跡からの復興(精神的な意味でも)を込めて、平和の象徴とされるスポーツの祭典に国の威信をかけていました。その気持ちがどれほどのものか、世界中に見てもらうためにと用意したのは、選手宿舎も見渡せる膨大な数のカメラでした。
一方、世界中の関心が向く平和の祭典で自分たちの気持ちを知らせようとしていた者たちが、その時、暴力という手段でもって命をかけた行為に及んだのでした。
わたしが、この事件を知ったのは、かの有名なスティーブン・スピルバーグ監督作品である「ミュンヘン」を子供の頃に鑑賞した時です。まさか、オリンピックという平和の祭典の真っただ中でテロが起きていたなんて、と思ったことを覚えています。また、その頃は第2次大戦後から今も終わりなく続いている中東情勢(イスラエルとパレスチナを中心とした情勢)のことなど知る由もなかったため、何の話をしているのかまったく分からず、スピルバーグ監督がユダヤの血を引く方ということなど知りもしませんでした。それから十数年の時を経て、再びこの事件について映画をとおして知ることができるという事実は、端的に知的好奇心が擽られました。
ところで、最近まであったイスラエル(というのかネタニヤフ首相の個人的怨嗟なのかは分かりかねますが)の徹底的ともいえるほどのパレスチナ自治区への容赦なき攻撃が、実際にどのようなものだったのか、そもそも今回の攻撃は、ハマスによる強襲に激怒したイスラエルによる報復だったと思っているのですが、それらについて、結局わたしは真実を知りません。わたしは、そこにいないからです。
このように、わたしにとってテレビの見せる所謂「真実」とは、「真実のようなもの」でしかなく、わたしにとっての「真実」を引き寄せるための道具のような感覚があります。それは、「真実」という言葉に危険な中毒的作用が含まれるからだと考えるからです。つまり、「真実」という言葉は時として「正義」の象徴のように祭り上げられるのですが、その実、真実を知ることで傷付くこともあるし、余計にパニックになることもあるという副作用が大きいということ、何よりも危険だなと思うことは、そもそも人間という欲求の権化のような存在である我々にとって、「真実を知る」という行為は、一種の支配欲に通ずる快感を引き起こす麻薬的作用があると考えるからです。そして、その欲求を逆手にとって情報を金に換えた(あくまで個人的見解ですが)のが、メディアという職種だと思っています。時には嘘を振りまきメディア王(「市民ケーン」のモデルになった人のことです。)になった者もいれば、上記の通り真実を振りまくことで戦争を終結に導こうとした者もいました。なので、情報を取り扱う職業人には高い倫理観が必要なのだと思います。
この映画では、その倫理観について考える場面が幾つもあります。テロ事件が勃発した際に、テレビの放映権を巡って幹部が争う場面、嘘を吐いてまで進入禁止区域にカメラを入れようとする場面、その中で、警察の突入をテレビに映してしまい、その後、突入が中止になってしまう場面(テレビに突入作戦の模様が映ってしまったせいなのかどうかは明瞭ではなく、あくまで主人公が自責の念に駆られるだけではありますが。)、空港での銃撃がどうなったのか不明瞭な時に主人公がどう決断したのか、その結果がどのようなものだったのか、など。
確かに、「真実」はその時、その場にしかなかったのだと思います。オリンピックの試合よりも命のやり取りに気持ちが傾くのは、一人の人間として当然の欲求だとも思います。正直、色々書いているわたしも、この映画は単純にテレビのお仕事ものとしてすごく見応えがありましたし、一種のスパイサスペンスのような臨場感すら終始画面の中に感じられて、ホラーでもないのに無意識で座席を握りしめてしまいました。どうして、主人公が「カット」と言うだけでこんなに緊張するのかと思うほどのスリルを感じられ、当時の(というより常に報道の最前線にあるであろう)緊迫感を少しだけ体感することができました。
しかし、一方でそのようなスリルやスパイアクションのような快感こそが、当時の現場に流れていた「真実を知っていち早く伝える」という免罪符(個人的に言えばですが)の裏に隠されていた一種の「罪」のように思えてなりませんでした。
結果的に人質にされたイスラエルのオリンピアンは全員死亡、警官も1名死に、パレスチナ人(恐らくテロリストかと思われますが)も死亡し、事件は「終わり」を迎えます。あまりに悲劇的な終幕に肩を落とす主人公ですが、その翌日には追悼のための番組を仕切るよう上司に言われ、車に乗り込んだところで、この映画は唐突に終わります。まるで、一連の報道番組の終了とも被るような呆気ない幕切れでした。
この映画では、敢えてなのかも知れませんが、当時の中東情勢やPLO(パレスチナ解放機構)、ブラックセプテンバーについて、詳細に語られることはありませんでした。もしかすると、あまりその辺の情報を流さないことで政治的恣意性を排除しようとしたのかも知れません。また、あまりバックミュージックも流れず、現場に流れる音で当時の緊迫感を出していました。だからこそなのか、わたしは上記のような面白さとともに、わたし自身も受け入れていた罪を、最悪な最後でもって罪悪感というかたちで思い知ることになったのです。もしかすると、主人公たち報道陣も、自分たちが行っている行為の裏にある「特ダネをどこよりも最速で流してヒーローになる」というような功名心に対する罪悪感を、人質の救出というかたちでなかったことにしたかったのかも知れませんし、だからこそ、最悪な結果を受け容れられずにいたのかも知れません。つまり、自分たちの行為を正当化できるだけの「奇跡」や「勝利」が欲しかったかも知れないということです。答えは分かりません。そこにいた人たちにしか分からないのです。
現代、上記のとおり中東情勢は変わらず、血で血を洗うような憎しみの連鎖が続いています。家族を殺された子供が、大人になって敵側を殺す悪循環から、抜けられそうにありません。1972年9月5日に起こったことにどのような意味があったのか、当時テレビをとおしてその様子を見ていたおよそ9億人の視聴者たちだけでなく、この映画を観たわたしも、考えなければならないのかも知れません。
メディアの倫理観については、最近の日本でも、事件の被害者に対する対応から始まり、加害者側への悪質で恣意的な報道の仕方、その割に自身の不正を正そうとしない上層部の在り方や誤情報の発信についても取り沙汰されていますが、一方でそれをSNSで無遠慮に叩く市井による、一種数の暴力とも思える動きも多く見受けられ、わたし個人としては、どうにも「真実を追求する」とか「真実こそ正義」という風潮が、そもそも人間の在り方として正しいのか分からなくなってきたため、このような感想を書かせていただきました。
色々書いてきましたが、この映画だけを取り上げてみれば、上記で書いたとおり所謂「お仕事もの」としても十分に面白く、このような大事件を、ほぼスタジオの中だけで完結させているという点でワンシチュエーションものとしても想像力を駆り立てられるエンターテインメントになっていると思います(事件の被害者にとっては何とも言えないとは思いますし、上記したとおり、このような気持ちになること自体が危険なサインなのかも知れませんが)。個人的には、もう少しエモーショナルでも良かったかな、と思ったため、☆一つの半分を除かせていただきました。
ミュンヘンの惨劇
報道する側の視点
全197件中、101~120件目を表示