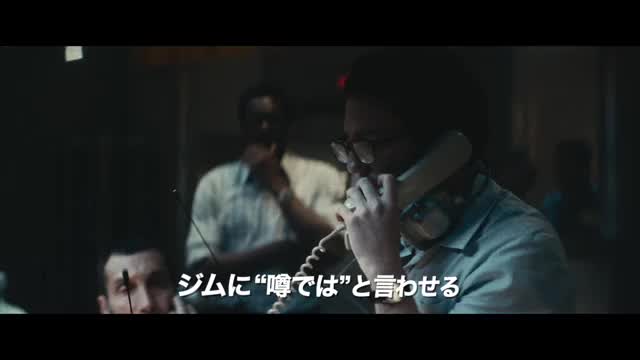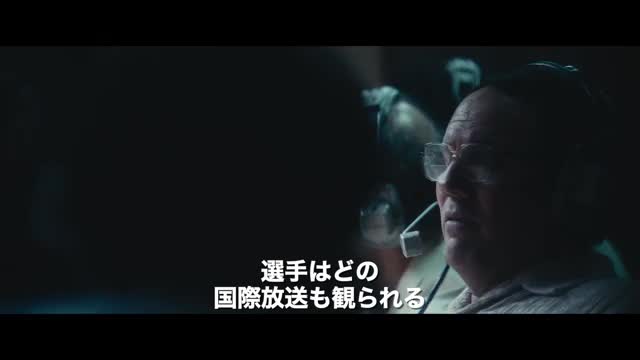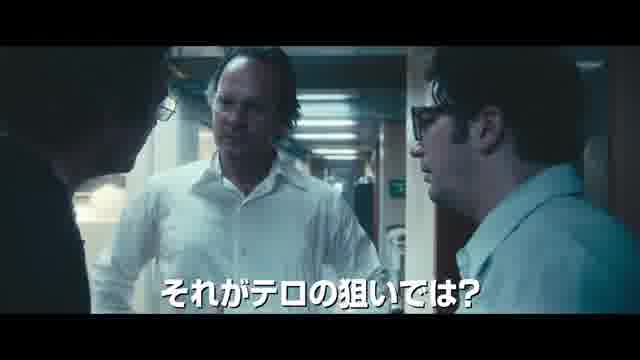セプテンバー5のレビュー・感想・評価
全200件中、21~40件目を表示
緊迫感があって中々面白かったです
全般的に緊迫感があって中々面白かったです。
主要人物の男性が似たような外見なので、区別がちょっと付けづらいけれど、それは何とかなりました。
イスラエル選手とコーチの殺害ということから、ホロコーストの話題が出てくるけれど、物語とは間接的な関係性に止まる。
報道の功罪
表現の自由、報道すること、真実を伝えることは、非常に重要だ。だが、テロリストに警察や特殊部隊の動きを伝えてしまうことは許されるものではない。
報道スタジオで、人質が全員解放されたという「噂」に飛びついたのは、やはり、その前の「自分たちのせいで救出作戦がダメになった」という思いがあったからに他ならない。警察の指揮がダメすぎる、テレビが見れないように電気を切るべきだという主張は責任転嫁でしかない。
そういう部分で、報道陣に感情移入が今ひとつできなかった。
また、イスラエルによるガザの無差別砲撃の最中にこの映画を上映することがアメリカの政治的なものを感じさせる。人質事件やテロが許されないのは当然としても、これらの事件が起きる背景は知る必要がある。
同盟国だからといって、イスラムを悪者にするアメリカの主張と視点にだけ毒されないようにしたい。
なんとも後味の悪さ
これTV局の海外中継派遣チームの話なんだけど、今動画配信とか上げてる人は見てほしいですね。
自分達にとって良かれと思ってやってること、自分達の正義は決して他者にとってもそれではないと言うことを嫌というほど描いてます。
それに後から気付くクルー達だが、その後が何日か経ってではなく数分後だから。
TV報道に携わってる人の職業病なのかも知れないが。
事件や事故に遭われた方へは、無事でいて欲しいとは皆が思ってるのだがそうでなかった時のやるせ無さを感じずには居られないだろう。
世界では戦争が続いてますが、たとえ停戦しても遺恨が残るのが現実で、当事者ではなかったからといって他人事のようにはならないのが今現在生きてる世界だと思い知らされましたね。
ブラウン管、ハンダ、録音テープの温もり、 受話器の重み。
報道とテロ、歴史を伝えるメディアの役割
先日観た『ノー・アザー・ランド』に続き、イスラエル・パレスチナ問題が関わる映画。ただし今回は、50年前のドイツ・ミュンヘンオリンピックで実際に起きた人質テロ事件がテーマになっている。
この映画によると、テロ事件が初めて生放送されたのが、今回のアメリカABCテレビの中継だったという。当時の報道現場を描いた作品であり、物語のほとんどはオリンピック会場近くのビルに設置されたABCの中継スタジオで進む。
事件現場である選手村も目の前にあるが、記者たちは何が起きているのか正確にはわからないまま、手探りで放送を続けようと奮闘する。そこにあるのは、報道の使命感なのか、それとも単なる仕事としての義務なのか。
おそらくこの事件を契機に、報道倫理に関する議論が生まれたのではないだろうか。
映画の中でも、報道が対テロ作戦の進行状況をリアルタイムで映し出してしまい、結果的に警察の作戦がテロリスト側に筒抜けになる可能性が示唆される。
また、SNSもない時代、テロリストが世界にメッセージを発信する手段はなく、「事件そのものを起こすこと」が最大のメッセージだった。
そう考えると、世界中に放映されることでテロリストの目的を果たしてしまったのではないか? という問いは避けられない。
現在では、こうした倫理的問題がより問われるようになり、報道には一定の制約がかかるようになった。しかし、その役割がマスメディアからネットメディアへと移行した今、ネット上では報道倫理がますます厳しく問われるようになっている。
一方で、日本の報道がそれによって大きく変化しているようには見えないのも興味深い点だ。
事件の目撃者でありながら、介入できない報道陣の視点が映画の中心だった。
ABCのスタッフは、「とにかく仕事として報道する」という姿勢だ。ただ一人、現地採用のドイツ人女性スタッフだけが、この事件をドイツの歴史問題と結びつけ、「またドイツは大きな失敗を世界に晒してしまった」とショックを受ける。
彼女のリアクションからは、戦後30年経っても一般市民が「ナチスのユダヤ人虐殺の責任」を意識していることが垣間見えた。
「歴史と個人の感情が交差する瞬間」は、この映画が単なる報道映画ではなく、歴史の記憶を伝える作品であることを強調していと思う。
現代と圧倒的に違うのは、リアルタイムで情報を得られる手段が、テレビとラジオ、そして電話くらいしかないことだ。
スマホもない。ネット検索もしない。SNSで情報が拡散することもない。テレビ映像が「世界の目」として機能していた時代の事件だった。
つまり、この事件は「テレビというメディアが持つ速報性と影響力を証明した」事件でもあった。
現在ならスマホを通じて誰でも動画を発信できるが、当時は「報道機関だけが事件のリアリティを伝えられる」時代だった。
それを象徴するように、映画はまるで記録映像のようであった。事件をドラマチックに描くのではなく、「ただカメラがその場にあった」という感覚を保つことで、リアリティを強調している。
この映画は、歴史的大事件を目撃しながらも、それをただ「伝えるしかなかった」報道陣の姿を描いた作品だ。
何らかの解決を提示するわけでもなく、エンディングもない。ただ、事件は終わり、翌日も仕事は続く。
確かに今日は歴史的大事件に立ち会い、報道した。だが、明日になればまた別のニュースがあり、次の仕事がある。
事件の衝撃や心の揺れ動きも、報道の仕事の中では、過去の1日に過ぎない。
そんな、「報道とは何か?」を静かに問いかける映画でもあったと思う。
よくも悪くも淡々とした作品
封切りから1カ月近くがたつ。上映回数はかなり減ってはいるものの東京都心のシネコンではまだ上映されているのを知り、終わる前に見ておこうと思って平日昼すぎに見た。
50年以上前の事件だが、評者は当時小学生。日本国内でどれだけ注目されたか記憶はほとんどないが、そういう事件があったことは憶えている。
本来、スポーツ取材しかしない(だろう)ABCのスタッフらが、ニュース(報道)の鉄火場に巻き込まれながら、米本土の鼻を明かすように奮闘する部分はなかなかに面白かった。
評者自身も、新聞記者として「現場」取材の経験があるだけに、それなりに感情移入しながら映画を見た。
しかし、全般に描き方が淡白なのである。
緊迫した場面も、あくまで米ABCの五輪中継スタッフの調整室からの視点にほぼフィックスされているだけ。
それはそれで面白くは見ることはできた。敢えて過剰な味付けをしないようにしたのかもしれないが、見る者の感情を揺さぶるような場面もほぼない。
事件の背景を描くでなく、被害者であるイスラエル選手団関係者を描く場面は少しだけで、テロリストたちについては姿がチラチラと映るだけ。
事件を掘り下げるようなことは最初からしないスタンスの作品なのだから仕方がない。
そういう映画なので、時間があった事実の重みがスクリーンから伝わる感じもしないのだ。
出来が悪いわけではないが、どうにもスクリーンから伝わる熱量の少なさが、★2つにした理由である。
わざわざシネコンに足を運んで見に行くほどのものではない。
公開時期と内容にちょっと思うところはあるものの、ミュンヘンオリンピック事件を報道側の視点から捉えるという見方を提示した点は評価したい一作
1972年に起きたミュンヘンオリンピック事件を、現場で取材し続けた報道機関の一つ、ABCのクルーたちの視点で描いた作品です。冒頭のスポーツ中継の流れから、あ、これはクルー動きを見せる映画なんだな、ということがすぐに分かってきます。そのため事件の進展は観客すらもほぼモニター越しにしか把握できず、外界から隔離されたスタジオの密閉感は、たとえ事件の顛末を知っている人であっても、先の見通せない緊張感を強いられます。
取材の不手際を挽回しようとして次のさらなる重大な事態を引き起こしてしまう…、という悪夢の連鎖は報道関係者でなくとも身につまされるものがあります。
この時期にパレスチナゲリラを得体のしれないテロリストとしてだけ描くことが妥当なのか、思うところはありますが、総合的にはテロへの批判だけでなく、メディアの暴走にも警鐘を鳴らしている…、と思いたいところです。
なお同じミュンヘンオリンピック事件を扱った作品として、スピルバーグ監督の『ミュンヘン』(2005)があり、『セプテンバー5』の復習としても、あるいは予習としてでも、併せての鑑賞がおすすめです。特に『ミュンヘン』の前半部では、本作とほぼ同じ状況を描いていおり、本作があえて省略した事件の概要と結末を理解するうえで、とても役立つのでは!
役者の演技とドラマのスピード感、絶品でした。
惜しくも受賞は逃したが、アカデミー賞脚本賞にノミネートされるのは納得。是非受賞してほしかったと思える快作だ。
ミュンヘンオリンピックで起きたイスラエル選手団に対するテロ事件を報道することになった、アメリカABCスポーツ中継スタッフたちの数時間(十数時間?)の人間ドラマ。
この手の映画ではキャラクターの人間味や会話のリアリティがとても重要だけれど、それが実にいい。活き活きとしていて、生々しく、スリル、スピード感に満ちている。
デフォルメされた漫画のようなキャラクターが現実感のないドタバタを繰り広げる、どこかの国の映画とは、人間に対する洞察力が違うなあ…。
主要な登場人物は四人だが、チームの指揮命令系統上それぞれの立場、役割が違う上に、夫々この状況で何を為すべきか、成し遂げたいか、といった動機が異なる。
一大事件を世界に伝えることの重大さに精神を高揚させながら、そのテンションは噛み合うような、噛み合わないような…、微妙な「ズレ」を抱えたまま進行していく。
しかし、ここが肝心なところだけれど、そうした違いを互いに意識しながらも、報道に携わる人間の職業倫理や責任感、人命に対する思い、といった点で、各人は根っこでは信頼で繋がっていて、その重層的で人間臭い関係性と、適切で簡潔なセリフ、鬼気迫る役者たちの演技に、観ていてグイグイ引き込まれてしまった。
加えて、機材や手法など、アナログ時代の撮影現場の様子がとても興味深い。まさにプロフェッショナル、職人集団といった雰囲気で、現場の緊張感がヒリヒリと伝わってくる。
そうした古き良き(?)時代を描きながら、且つ、現代に通じるいくつかのメッセージもしっかり盛り込んであって、ホント、流石。いやはや、ご馳走様でした。
日本酒のコマーシャルだったか、「何も足さない。何も引かない。」なんていうコピーがあった気がするが、この映画の脚本はまさにそんな感じ。
その良質なシナリオを、緩急も鮮やかに、抜群の説得力で演じ切る役者の力量もまた凄い。
欧米の映画人の実力に、改めて感心させられた一作でした。
結末は知っていても
ドキャメンタリータッチの95分ワンシチュエーションサスペンス。史上初のテロリズム生中継となってしまったミュンヘン事件をスタジオ中継室から描いているので悲劇的な結末は知っていても緊張する作品。
今や簡単にスマホでテロや戦争、殺人の映像が見られる世界と違い様々な技術的、倫理的に困難状況で苦悩し焦るTVスタッフの演技に惹き込まれた。
ミュンヘン事件は衝撃的で、いろいろな作品があるので、見比べてみても違いがあり興味深い。
その場にいるような臨場感と緊張感 当時の現場の混乱、世界の状況、何を考えていたのかを追体験することに意義がある
ミュンヘンオリンピックで人質事件が発生。
事件を全世界に発信するために奮闘する現地abcテレビスタッフたちの緊迫の1日!
観客は、まるでその場にいるような臨場感と緊張感を追体験する。
リアルタイムで刻一刻と変わる状況で、様々な問題に対応する現場判断は観ていて面白い。
また、1972年当時の設備、技術が再現されているのも見どころ。
唯一人、ドイツ語が話せる女性局員が、臨機応変に実力を発揮するのがいい。
事件は悲惨な結末を迎え、落胆する局員たちだったが、翌日の特別番組の準備がすでに始まっていて、何事もなかったかのように、また次の日の仕事が続いていく状況に虚無感を感じる主人公。
歴史的な事件の舞台裏を描きつつも、テレビ業界の非人間的な冷酷さを描いて終わる。
ただ、起きたことをドキュメンタリーのように描いただけで、なにがいいたいのかと思う人も要るに違いないが、当時現場で起きた出来事、当時の感情を、再現して改めて問うているに違いない。
それだけに、パンフレットの製作が無いのが残念でした。
過剰な演出を排した創りに共感!!
1972年のミュンヘンオリンピックで実際に起ったパレスチナ武装組織によるイスラエル選手団の人質テロの顛末を描いた作品であるが、これまでにも「ミュンヘン」等この題材をテーマにした作品は幾つかあったが、銃撃シーン等の過剰な演出を避け、淡々とクルーの立場から現場を演出するその創りにはより緊迫感が感じられ共感が持てる。
ニュースクルーではない、スポーツクルーが報道の自由と報道がもたらす結果責任の狭間で悩む術が独特の緊張感の中でより真実味に溢れ、作品としてのクオリティーを保っている。
ドイツとイスラエル、パレスチナと言う対比もこの作品のリアイティーを生むには不可欠!
「ユナイテッド93」もそうだが、実話に基づいた作品は過剰な演出を排除した創りに限る!!
先日見たある映画との差に愕然としてしまった。
ブラック・チューズデー‼️
この作品は、新たなジャーナリズム映画の秀作ですね‼️1972年のミュンヘンのオリンピックにおけるテロリストの襲撃事件を、報道局を主観として事件を描写しているにもかかわらず、観ている側にも事件の緊迫感、恐怖感が直に伝わってくる‼️これは役者さんたちの素晴らしい演技力によるところが大きいですね‼️そしてドキュメンタリータッチの演出で見せてくれるティム・フェールバウム監督の力も大きいです‼️72年当時を思わせるザラついた画面も印象的で、作品の肌触りとしてはポール・グリーングラス監督作を思い出しますね‼️そういえばグリーングラス監督作常連のコリー・ジョンソンも出演してますし‼️そして他局と放送の枠を取り合ったり、自分たちが報道したことで人質の家族への影響などの人権問題、そして警察による人質救出作戦の妨げになったりという、ジャーナリズムの問題点も指摘している‼️今作はテロリズムを初めての生中継した報道の力、その素晴らしさ‼️そして事件の顛末を考えると、ジャーナリズムの虚しさ、無力さを痛感させられる一作‼️ぜひスピルバーグ監督の「ミュンヘン」とセットで観たほうがいいでしょう‼️
全200件中、21~40件目を表示