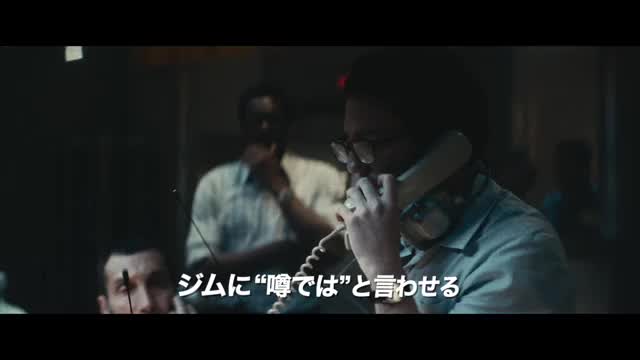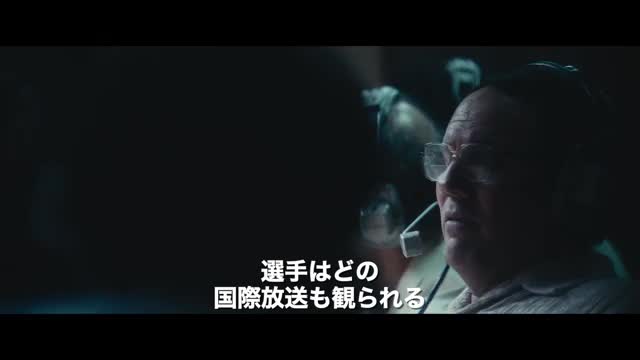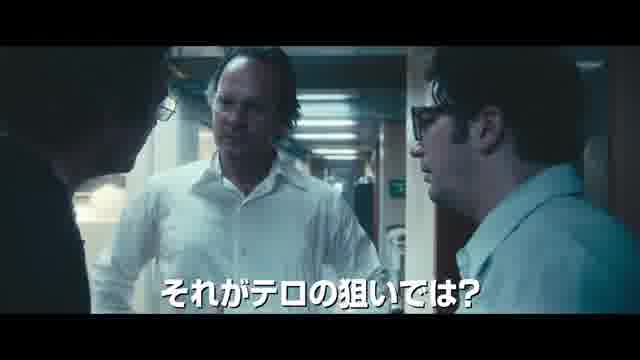「報道とテロ、歴史を伝えるメディアの役割」セプテンバー5 ノンタさんの映画レビュー(感想・評価)
報道とテロ、歴史を伝えるメディアの役割
先日観た『ノー・アザー・ランド』に続き、イスラエル・パレスチナ問題が関わる映画。ただし今回は、50年前のドイツ・ミュンヘンオリンピックで実際に起きた人質テロ事件がテーマになっている。
この映画によると、テロ事件が初めて生放送されたのが、今回のアメリカABCテレビの中継だったという。当時の報道現場を描いた作品であり、物語のほとんどはオリンピック会場近くのビルに設置されたABCの中継スタジオで進む。
事件現場である選手村も目の前にあるが、記者たちは何が起きているのか正確にはわからないまま、手探りで放送を続けようと奮闘する。そこにあるのは、報道の使命感なのか、それとも単なる仕事としての義務なのか。
おそらくこの事件を契機に、報道倫理に関する議論が生まれたのではないだろうか。
映画の中でも、報道が対テロ作戦の進行状況をリアルタイムで映し出してしまい、結果的に警察の作戦がテロリスト側に筒抜けになる可能性が示唆される。
また、SNSもない時代、テロリストが世界にメッセージを発信する手段はなく、「事件そのものを起こすこと」が最大のメッセージだった。
そう考えると、世界中に放映されることでテロリストの目的を果たしてしまったのではないか? という問いは避けられない。
現在では、こうした倫理的問題がより問われるようになり、報道には一定の制約がかかるようになった。しかし、その役割がマスメディアからネットメディアへと移行した今、ネット上では報道倫理がますます厳しく問われるようになっている。
一方で、日本の報道がそれによって大きく変化しているようには見えないのも興味深い点だ。
事件の目撃者でありながら、介入できない報道陣の視点が映画の中心だった。
ABCのスタッフは、「とにかく仕事として報道する」という姿勢だ。ただ一人、現地採用のドイツ人女性スタッフだけが、この事件をドイツの歴史問題と結びつけ、「またドイツは大きな失敗を世界に晒してしまった」とショックを受ける。
彼女のリアクションからは、戦後30年経っても一般市民が「ナチスのユダヤ人虐殺の責任」を意識していることが垣間見えた。
「歴史と個人の感情が交差する瞬間」は、この映画が単なる報道映画ではなく、歴史の記憶を伝える作品であることを強調していと思う。
現代と圧倒的に違うのは、リアルタイムで情報を得られる手段が、テレビとラジオ、そして電話くらいしかないことだ。
スマホもない。ネット検索もしない。SNSで情報が拡散することもない。テレビ映像が「世界の目」として機能していた時代の事件だった。
つまり、この事件は「テレビというメディアが持つ速報性と影響力を証明した」事件でもあった。
現在ならスマホを通じて誰でも動画を発信できるが、当時は「報道機関だけが事件のリアリティを伝えられる」時代だった。
それを象徴するように、映画はまるで記録映像のようであった。事件をドラマチックに描くのではなく、「ただカメラがその場にあった」という感覚を保つことで、リアリティを強調している。
この映画は、歴史的大事件を目撃しながらも、それをただ「伝えるしかなかった」報道陣の姿を描いた作品だ。
何らかの解決を提示するわけでもなく、エンディングもない。ただ、事件は終わり、翌日も仕事は続く。
確かに今日は歴史的大事件に立ち会い、報道した。だが、明日になればまた別のニュースがあり、次の仕事がある。
事件の衝撃や心の揺れ動きも、報道の仕事の中では、過去の1日に過ぎない。
そんな、「報道とは何か?」を静かに問いかける映画でもあったと思う。