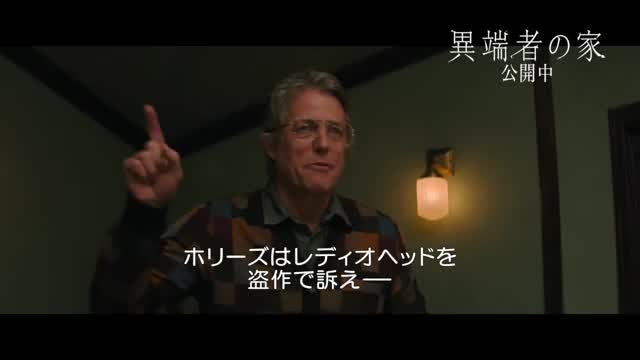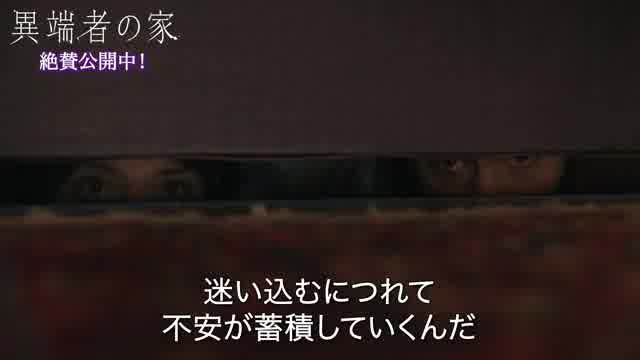「問答によって試される、我々の“信仰心(何を信じるか)”」異端者の家 緋里阿 純さんの映画レビュー(感想・評価)
問答によって試される、我々の“信仰心(何を信じるか)”
【イントロダクション】
宗教勧誘の為、森の中の一軒家を訪れた2人組のシスターが、異端者である家主による恐怖の仕掛けに捉えられ、脱出を試みる様子を描いたスリラー。
シスター達を恐怖に陥れる家主に、『ノッティングヒルの恋人』(1999)や『ブリジット・ジョーンズの日記』(2001)等、「ロマンティック・コメディの帝王」と呼ばれたヒュー・グラント。
監督・脚本は、『クワイエット・プレイス』(2018)のスコット・ベックとブライアン・ウッズ。
【ストーリー】
「モルモン教」のシスターであるパクストン(クロエ・イースト)とバーンズ(ソフィー・サッチャー)は、布教活動として森の中にある一軒家を訪問する。
玄関先にて2人を出迎えた家主のリード(ヒュー・グラント)は、気さくな様子で接するが、嵐が近付いているからと彼女達を家に招き入れようとする。2人は「男性1人の自宅には入れない」と断ろうとするが、彼は「妻が居るから大丈夫。もうじきパイも焼ける」と、彼女達を安心させて招き入れる。
リードは2人を歓迎し、宗教について持論を展開する。しかし、「どの宗教も真実とは言えない」と白熱していくリードを前に、2人は不穏な空気を感じ取る。中々姿を見せない彼の妻に対しても疑問を持ち、彼が「妻を呼んでくる」と席を外した際に、それまで漂っていたブルーベリーパイの匂いはアロマキャンドルによるものだったと知った2人は、いよいよ身の危険を感じ、すぐさま家を後にしようとする。
だが、扉の鍵は開かず、スマホの電波は通じない。この家は、様々な宗教を学習し、その全てに疑問を抱いて“異端者”とされたリードが、自らの信じる「唯一絶対の宗教」を証明する為に用意したカラクリ屋敷だったのだ。
【感想】
まず、何と言ってもかつて「ロマンティック・コメディの帝王」と呼ばれたヒュー・グラントの悪役ぶりが面白い。私自身は恋愛映画が趣味ではないので、彼の過去の出演作は目にした事はないのだが、それでもやはり、彼の放つ「良い人オーラ」からは対極に位置する狂人ぶりには惹きつけられる。
また、彼の展開する独自理論には、共感出来る部分や理解出来る部分も多くあり、そうした理論展開の様子も興味深く鑑賞出来た。
残念なのは、作品を鑑賞するだけでは、リードが“異端者”と呼ばれるに至った詳細な経歴が判然としない事だ。ヒュー・グラントは、役作りにおいて彼の過去について解釈を重ね、信仰心云々よりも、そもそもの人間性への問題を考えたそうだ。女性との関係性(特に性交渉)への問題や、幼少期から周囲の気を引きたいが為にイタズラやマジック、議論を重ねてきたのではないかと想像したそう。
そんなリードの過去は勿論、彼が何故自宅の地下にあれほどの空間を造り上げられたのか含め、作品を構成する様々な要素は「なんとなく」の空気感で流されてしまうのも勿体なくは感じた。
しかし、110分という尺ながら、鑑賞してみるとそれよりもコンパクト(90分くらい)に感じられ、中弛みも一切感じさせなかった点は見事。
但し、予告編から受けた『CUBE』(1997)のような仕掛けだらけの屋敷からの脱出劇、そうしたギミックによる面白さを期待すると、肩透かしを食らう。
驚いたのは、宗教という荘厳なテーマを題材としつつも、物語の幕開けはコンドームやポルノといった下世話な話題から始まる点だ。そして、その冒頭がラストの結末にも繋がっているのだ。
パクストンは、「マグナム・コンドームのサイズは、実は普通サイズのコンドームと一緒で、人はマグナムサイズだと言われたら、そう信じてしまう」と、バーンズに語る。
バーンズは、「姉の夫が巨根だったそうだから、それはないんじゃない?」と、早くも情報に対する疑いの目を向ける。
下らないようでいて、こうした細かな情報に対してまでも、2人の受け止め方の違いが示されている。
そんな対照的な2人を演じた、クロエ・イーストとソフィー・サッチャーの役作りや衣装センスが素晴らしい。
クロエ・イースト演じるパクストンは、いかにも騙されやすそうな雰囲気や、イモっぽさを感じさせる佇まいで、しかし年相応にポルノには興味関心がある様子。対するソフィー・サッチャー演じるバーンズは、洗練されたシックなファッションと、情報を鵜呑みにせずに自身のフィルターを通して判断する知性、腕に施した避妊インプラントは、性生活や生理への対処も心得ている様子で、パクストンより上手の大人の女性感を醸し出している。
R15指定のホラー作品ながら、全体的にグロテスクな表現やジャンプスケアは控えめで、そういったジャンルが苦手な人でも入りやすい作りになっている。
あくまで本作で提示される“恐怖”は、我々が抱く“信仰心”や“理解”に対する問い掛けによって演出されるからだ。そうした硬派で知的な作りは好感が持てるし、身につまされる思いも抱く。
【宗教の本質は、利権を貪る事だろうか?】
リードは、様々な宗教における教義の改正や諸問題を、権力者が自らの利権を行使する為に、自分達にとって都合が良いように組み上げられたものだと語る。
確かに、様々な宗教における解釈は、神の意思ではなく、我々人間にとって“都合の良い事実”と感じられる場面もある。神の名を借りる事で、自らの行為に正当性を見出す自己弁護の様相を呈しているのだ。
私自身は、リードのこの理論に対して異論はない。そもそも、神や悪魔といった超常的な存在自体が、古代の人間が言語化や科学的な知見から証明出来なかった様々な現象を理解する上で用いた「キャラクター化」だと思うからだ。
だからこそ、科学の進歩によって、現代では様々な事柄に説明がつき、若者を中心に信仰心は薄れている。
しかし、忘れてはならないのは、本作で描かれている事は、そうした「神を信じるか?奇跡を信じるか?」という話ではなく、「その情報を信じるか?信じる為にはどうするか?」という非常に現実的・現代的な問い掛けだという事だ。
【人は信じたいものを信じるしかない】
月並みな意見だが、結局、本作の行き着く先はそこだったように思う。しかし、それは決して“諦め”ではなく、自分自身で熟考を重ね、経験を積み、その果てで何を信じるか、どう信じるかを判断すべきという事だ。
また、日本では直近の公開作に当たる『教皇選挙』(2024)にて、レイフ・ファインズ演じる主人公ローレンスはこう語る。
「私が最も恐れる罪は“確信”だ」
「信仰は生き物だ。“疑念”と共に歩むべきだ」
これはそのまま、本作におけるリードの立ち振る舞いに言える事である。
中盤、リードは地下室へと続く2つの扉を前に、どちらに進むべきか決断出来ないパクストンとバーンズを前に、左の扉に“BELIEF(信仰)”、右の扉に“DISBELIEF(不信仰)”と書き殴り、自らの宗教理論を披露して、彼女達に扉の選択をさせる。
リードは、宗教の歴史をボートゲームや音楽を例に挙げ、「宗教の歴史は、“反復”の歴史だ」と説いた。一見すると、彼の意見は的を射ているように感じられ、パクストンも彼の意見に同調し、自らの信仰を容易く覆してみせる。しかし、バーンズは彼の意見は「共通点を指摘しつつも、相違点は無視している」として、素直に受け入れる事はせずに、信仰の扉を選択する。
そう、リードは自らの理論を証明したいがあまりに、自身の理論における“不都合な事実”を排除している。また、どちらの扉を選択しようと、辿り着く先は同じであり、2人は彼の考えたシナリオの実現に向けて動かされていたに過ぎないのだ。
これは、現実社会において“こじつけ”と“屁理屈”を並べて人々を洗脳しようとする政治家やネットの煽動者にも言える。大事なのは、与えられた情報を鵜呑みにせず、常に疑いの目を向けて何が事実かを判断し、容易に惑わされるなという製作側からのメッセージだろう。
リードは、自宅の地下に数々の仕掛けを用意して、パクストンとバーンズに自らが唯一絶対だと信じる宗教である、“支配”について立証しようと試みた。
しかし、バーンズの相手に疑惑の目を向ける姿勢と、そこから来る反論と挑戦。地下に監禁し、支配下に置いていた女性の台本に無い発言(つまり、彼女個人の意思による抵抗)。バーンズの犠牲をキッカケに攻勢に出たパクストンの発想と気付きによって、自らが組み立ててきた理論の整合性が崩され、即興での辻褄合わせを余儀なくされていく。
この時点で、リードが「どのような結末になろうと、その行く末を見届け、受け入れる」という姿勢を見せていれば、結末はまた違ったものになっていただろう。しかし、彼もまた“絶対”という宗教に囚われていたに過ぎず、自らの信じる“支配”を立証する為、辻褄合わせに奔走する。
そして、クライマックスでのパクストンによる「魔法の下着」の反撃を皮切りに、命の危機に瀕したリードは、彼女を殺害しようとする。しかし、最後の力を振り絞ったバーンズの命懸けの一撃によって、リードは自らの宗教を否定されて命を落とす。彼が“絶対”として信じた“支配”という宗教は、若い女性2人が見せた“知恵”と“勇気”、何より、「その行為に意味が無くとも、相手がどんな相手であろうとも、祈りを捧げる事は尊いことだ」と信じたパクストン、「たとえ自分は助からずとも、友人の命だけは守る」と力を振り絞ったバーンズによる、“利他的”行為の果てに敗れ去ったのだ。
ラスト、パクストンは負傷しながらも脱出に成功し、朝日に積もった雪が照らされる森の中で、自らが語った「死んだら蝶になって、皆の指に止まる。頭や肩じゃなく、指に止まる事で私だと気付かせるの」という台詞にある通り、指に止まる蝶を見る。しかし、それは現実ではなく、自らの意思が見せた幻覚だと悟る。
それは正しく、リードが語った「胡蝶の夢」。夢と現実の区別は、その者の認識次第で変わる。パクストンはあの瞬間に、かつてポルノを観た時に出演女優の仕草に感じた「生の感覚」を、より具体的な「人生の儚さ」として知ったのかもしれない。
【総評】
ヒュー・グラントによる怪演にして快演、それに対抗する若手女優2人の演技と、絶えず繰り返される問答は、異色のホラー作品を数多く打ち出してきたA24らしい一作。
しかし、そうした過去作よりも比較的入りやすい入口、誰にも理解しやすいテーマ設定や展開は、万人が鑑賞する事に適している。
個人的には、更にエッジを効かせた尖った一作を期待していたのだが、それでも最後まで興味を持続させられ、実際の上映時間よりも短く感じさせた手腕には拍手を送りたい。