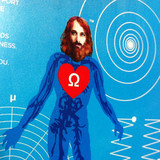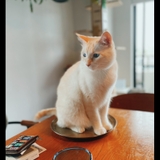ヒプノシス レコードジャケットの美学のレビュー・感想・評価
全32件中、1~20件目を表示
今なお驚きと鮮烈さを与える伝説的デザインの制作秘話にコービンが迫る
アントン・コービンといえば、劇映画の監督のみならず、時代の寵児たるミュージシャンの姿をモノクロームで活写したポートレイト写真でも知られる。以前、インタビューした折、とても物腰柔らかく周囲への目配りや観察眼の秀でた方で、なるほどアーティストたちともこうして心地よく距離を縮めていくのだろうなと感じたものだ。そんな彼の初長編ドキュメンタリーが、パフォーマー側ではなく、太陽と月で言えば月側、ジャケットやポスター制作を担ったアート集団「ヒプノシス」に焦点を当てているのも納得だ。誰もが目にしたことのあるデザインは、時にサイケデリックだったり、強烈に意識に訴えかけてくるものだったり。全ては時代を彩る異才たちの運命的な出会いと化学反応から始まり、そんな伝説を形作った制作秘話の一つ一つが深淵で興味深い。もし彼らのデザインがなかったら70年代の音楽シーンやその影響は多少印象の異なるものになっていたに違いない。
Essential Backstage Rock Story
In the 60's when rock music was cool and revolutionized society, one small London collective was producing the iconic artwork on the face of many records. This DIY story is a must-watch for any aspiring artist or entrepreneur. A start-up launched on the capital from a donated piano in a run-down apartment with only a sink for a toilet, Hipgnosis built its own legacy with crude creativity.
1970年代に英国で、超大御所歌手たちのアルバムのジャケットデザイ...
1970年代に英国で、超大御所歌手たちのアルバムのジャケットデザインを手がけた集団のお話。
ピンクフロイド、レッドツェッペリン、ポールマッカートニー、etc.
驚くようなジャケがたくさんあった頃ですね。
サハラ砂漠にサッカーボール60個、
豚のバルーンを工場の上に飛ばす、
三角のプリズム、
雪山の頂上に銅像、
スーツの背中に火をつけたまま飄々と握手、
etc.
かつてLP盤だった頃は、まずジャケアートに目が行く、中身を聴く前にジャケ買い、そういう心当たりも時々ありました(私的には80年代以降ですが)。
ジャケットの正方形に何を収めるか。
ポップアート、インダストリアルアートとも関連づきそうな作品群でしょうか。
以降のCD,オンラインでは、もう重きを置かれない、添え物のようになってしまい。
音楽との接し方が変わりましたし、やむを得ないとは知りつつも。
当事者の娘さんも "あのiPodの曲の脇の小さい絵?" ぐらいの認識だそうですしね (セリフが多少違うかも? どんな言い方でしたっけ)。
ああいう画期的な絵面の数々、ある意味、贅沢な時でしたね。
そう感じること自体、我ながら古い人だなあとも思いつつ。
よいもの見させていただきました。
50年前の秘話
ちょっと
【1970年代に名を馳せたデザイン・アート集団”ヒプノシス”が作り上げたレコードジャケット製作秘話テンコ盛りドキュメンタリー。】
<Caution!内容に触れています。鑑賞したら、読んでね!>
ー 最初に敢えて記すが、私は年代的に70年代ロックは余り聞いていない。〇坊から聞いていたブリティッシュポップ&ロックから入っているので、デザイナーとしてはピーター・サヴィル製作のジャケットなんだよね。
今作でも一瞬映った、ジョイ・ディビジョンの名盤「アンノウン・プレジャー」のジェケットなんか、クールでムッチャ好きなんだよね。あと、ウルトラヴォックスとかさ。
けれども、このドキュメンタリーでは、特にピンクフロイドのジャケット製作秘話が多数観れて面白かったな。
”原子心母”のジャケの牛の話とか、ムッチャ面白かったのは”アニマルズ”のジャケのピンクブタの巨大風船を飛ばした時のエピソードや、”炎~あなたがここにいて”の炎に包まれた男が握手をしているジャケがホントに火を付けていた事には、ビックリである。
それに、ジャケット製作にとても、お金をかけていた事が随所で分かった事も良かったな。
このドキュメンタリーに出たミュージシャンの中で、多分一番私に年が近いと思われる、ノエルの話も面白かったな。
今は、ストリーミングの時代だからか、レコードジャケットを知らない娘さんとの噛み合わない会話や、マサカノ、オアシスの名盤”モーニング・グローリー”のジャケットを気にいっていなかった事にはビックリである。”誰がこんなジャケットにしたんだ!””お前だ!”は、笑ったなあ。
でもさ、数年前から、定期的にCDを売りに行く中古CD屋の主人と話していたのだけれども、今やLP盤って凄い人気なんだよね。壁に掛かっている名盤LPの値段を見てビックリしたよ。聞いたら、LP盤を愛聴していた年代の方が亡くなった際に、ご家族が持ってくるんだってさ。んで、買取値段を聞いてびっくりして帰るらしいよ。音も当然良いんだってさ。
ノエルも言っていたけれど、ヤッパリ(私はCDだけど)曲順などをアーティストは考えているなんて話を聞くと、ちょっと考えるよなあ。
そういうことを考えると、もう、死語かなあと思っていたジャケ買いという言葉も、復活するかもしれないね。実際、アーティストによってはLP盤も出す様になっているしね。
マア、とにかくこのドキュメンタリーは、知らない事が多数詰まっていて、ロック好きには堪りませんでしたよ。じゃーね。
<2025年4月6日 刈谷日劇にて鑑賞>
レコードジャケットにお金を掛けてた時代
1970年代の洋楽が凄い理由はこれ!
洋楽は今でも1970年代を中心に聴いている。特にピンクフロイド、イエス等のプログレがお気に入りだ。そして、その頃のレコードジャケットにも思い入れがあるのでピンクフロイドの「原子心母」「狂気」などは神棚に飾っておきたい位である。
どうしても観たかった映画なのでパンフも買ったが、嬉しいことに1967年からのアルバムジャケット作品のリストも載っており、あの時代を彩った有名アーティストの作品名を懐かしくたどることができた。その中になんと!松任谷由実の「昨晩お会いしましょう」も入っており、嬉しくなった。このジャケットも飾ってみたくなった。
映画はヒプノシスのストームとポーの2人の出会いや独創的な感性で多くのロックミュージシャンの支持を受け大量の作品を生み出していった過程と時代の変化により衰退していくさまを時系列で語っていく。ポール・マッカートニーの「バンド・オン・ザ・ラン」やレッドツェッペリンの「聖なる館」やピンクフロイド「狂気」「炎」「アニマルズ」等の制作過程がしっかり画像に残っていてその撮影秘話はめちゃくちゃ興味を持って観れた。あと、なんと言っても2人の出会いと初期のイメージ創出のきっかけがあのシド・バレットってのがイけてます。LSDがどれほどのものかはわからないが天才シドとクスリが全ての始まりっなのは1960年後半の退廃的空気と合間ってゾクゾクしました。又昨年公開された「シド・バレット 独りぼっちの狂気」にも逸話として挿入されたピンクフロイド「炎」のレコーディング中に容姿も体型も崩れていたシドが何年かぶりふらりと訪れたエピソードには泣けてきます。そして映画のラストの曲も「Wish You Were Here-あなたがここにいてほしい」、。
私が観たドキュメンタリー史上(そんなに観てないけど)No.1と言える素晴らしい映画でした。
上映してくれたキネ旬シアターさん、ありがとうございました。
まるでhypnotic?
数々の名作アルバムジャケットデザインの立役者ストームさんとポーさんの武勇伝みたいなドキュメンタリー
ツェッペリン、ピンク・フロイドメインだった この間見たピンク・フロイドのシド・バレットさんのドキュメンタリーの続きのようでもあった 例のプリズムのジャケット出てきた時にはおぉ!ってなった 60、70年代はクスリとヒッピーみたいな生活で知り合って意気投合が多い印象
アーティスト達もそれなりにアイデア持ち寄り、天才的に形にしていくのがストームさんで、転機となったサハラ砂漠にボール...のフォトが面白い
レコード最近復権してますが、昔はジャケ買いなんてあったよ、思い出した アルバムに収録曲のイメージ伝えインパクト与える大切なお役目 ただやはり時代に左右されるので、盛者必衰、ビジネスってホント難しいって思った その後は何をされてるんでしょう?
ハッセルブラッドのフォーマット
熱い集団
最近、濃い名作(しかも長い・・・)が続いたので、こういう軽いドキュメンタリー映画もいいかもねとヒプノシスを観ましたが、なかなか見応えのある作品でした。
全編モノクロを基調としたデザイン・アート
集団「ヒプノシス」のオーブリーの語る
制作秘話を中心に今やレジェンドと呼ばれる
ミュージシャンも出てこられるのですが、
皆、結構素直ですね。
特に「ヒプノシス」の天才肌のストームに
関しては皆がアイツ最低だよ!とか言いつつ
才能は認めている。
ポール・マッカートニーにダメ出しできる
人て、この人(ストーム)ぐらいじゃないの・・・
「あぁ分かったよ」とうろたえるポールて!
オアシスのノエル・ギャラガーて、とがった人てイメージがありましたが、この映画では
まともな事言ってるし。
ノエルの言うアルバム・ジャケットは貧乏人のアートて悪い意味でなく、むしろ愛着を感じる発言に思えました。
レッド・ゼッペリンの「プレザンス」の
ジャケットが、なんでこんな平凡な
ファミリー写真にしたのか長らく謎でしたが、
この映画で解けました🙂
時代は80年代に入りMTVというビデオ戦略に上手く乗れなく崩壊してしまった
「ヒプノシス」は、ある意味、彼等らしい
終焉の仕方かもしれません。
私は「新世紀エヴァンゲリオン」を創った頃のガイナックス創世記を思い起こさせました。
現在、素人でもパソコンで簡単に合成できる
時代ですが、「ヒプノシス」を超えるようなジャケット・デザインが生まれたかといえば、
どうなんでしょうか・・・
ただ配信聴き放題でも曲だけでなくスマホの画面にアルバム・ジャケットが映るのは、うれしいですね。
ある意味ジャケット・デザインが身近になったので、また新しいものが生まれる可能性もありますね。
カッコ良いドキュメンタリー
古きよきアナログ
よかったな〜
かっこいいな〜
アナログなクリエイティブの世界
楽しそう
今ならデジタルでなんでもPC上で作れちゃうものを
あほみたいな手間とお金と時間をかかて撮影して
あほみたいだけど最高だよなぁ
それらがあるから
今の時代のクリエイティブにもつながっているわけで
知らないけど
この時代かっこいいよなぁ
狂ってるけど
今よりもっと自由ではちゃめちゃで
わくわくすることを忘れんなよって気持ちにもなった
けどなんとも言えない気持ちにもなるし
まぁとにかく
音楽とアート、デザインが好きな人間としては
楽しく興味深く素敵なものを観たという感想です
登場する作品のジャケも知らないし
音楽も聴き込んでないし
(もちろん存在は知ってるけど、くらいの)
でもとても興味深かった
かっこいい
70年代原風景
作品は最高!人間性は最悪!
【主役はストーム】
ヒプノシスのブレーン、ストームが印象的!
クリエイティブに対する姿勢は本物だけど、人間性は最悪。
でも逆にワガママだったり人の迷惑を気にしない位の人でなければ、平凡なものや優等生的なものしか作れないんじゃないかと思った。
印象的なのは10ccのARE YOU NORMALのジャケット。
莫大な予算をかけてハワイにロケに行って苦労して撮った写真を
ほんの小さくしか使わない。
でもそういうおふざけや、ユーモア、皮肉みたいなものが
突き抜けたものを作るには必要だと思った。
制作を心から楽しんでる感じで、それがアーティスト達にも響いたんだと思う。
自分は割といい子ムーブしまう事が多くて、
ストームみたいな人には憧れちゃう。
だけど結局そういうストームの姿勢がヒプノシスの破滅を招く。
自分を貫くか、周りの意見を聞くかの判断はいつも難しい。
でもバランスをとりながら、その度に自分で考えるしかないと思った。
【豪華なアーティストのインタビュー】
ヒプノシスと仕事をした様々なアーティストのインタビューも見どころ。
ロジャーディーンが喋ってる所を初めて観たのでちょっと感動。
ノエルギャガーは相変わらず面白い。
ジャケットデザインで勝負する時代は終わったのかもしれないけど、どれも今見てもすごくかっこいい!!
当時の熱気も伝わってきてとても楽しかった!
レコードジャケット、最高だぜ。
貧乏人のためのアートだからこその輝き
昔は「ジャケ買い」というレコードの買い方があった。レコードジャケットがカッコよくて、バンドも曲も知らないのに買う手法。聴きながら眺めたり、部屋に飾ったり、レコードジャケットってちょうどいい大きさのアートなんだと思う。「貧乏人のためのアート」とはうまい言いようだ。
デザイン集団ヒプノシスの誕生と終わり、そして彼らが手がけたアルバムジャケットの制作秘話が語られるドキュメンタリー。すべてのアルバムを知っていたわけではないが、結構知っているジャケットが出てきてなぜ嬉しくなる。ピンク・フロイドやレッド・ツェッペリン、ポール・マッカートニーあたりが多めだが、10ccも意外と多いことに驚いた。
意図的にアルバムのタイトルとは関係のない、意味のないアートワークを提案するヒプノシスはすごいが、それに決めるバンド側の勇気もすごい。実際それでロック史に残るジャケットになったのだから。興味深かったのは、ヒプノシスがボツアイデアを使い回していたこと。そりゃそうだ。デザインの世界ではよくあることだと思うがなんか笑ってしまう。個人的にいろんなレコードジャケットが好きなので楽しめる映画だったが、若い人たちにはどうなのだろう。思い入れのないドキュメンタリー映画はひどくつまらなくなる気がする。
レコードからCDにメインのフィジカルが移り変わり、今や配信でしか音楽を聴かないことが当たり前になっている状況。ノエル・ギャラガーが話していた娘とのやり取りが今の世代の感覚なのだろう。とてもさみしく思ってしまうが、それも仕方ない。そういう意味でも貴重な映画だと思う。
全32件中、1~20件目を表示