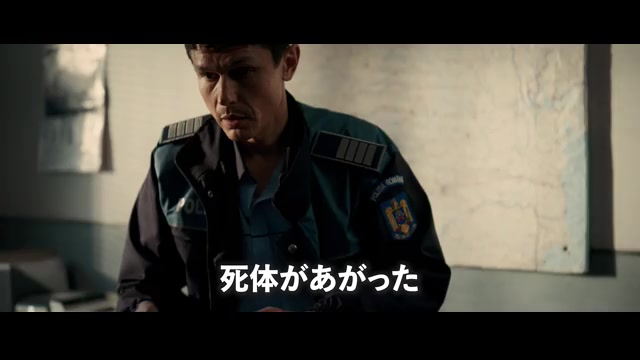おんどりの鳴く前にのレビュー・感想・評価
全54件中、1~20件目を表示
腐敗と人間の醜さを感じ
覚醒した腐敗警官
本作の舞台となったルーマニアがEUに加盟してからというもの、それはそれはひどい汚職が蔓延し、官僚の腐敗たるやウクライナのそれにまさるとも劣らないレベルに達しているという。カンヌのパルムドーラーであるルーマニア人映画監督クリスティアン・ムンジュウが証言しているので、ほぼ間違いないだろう。おそらく自由主義になっても共産主義時代の支配システムをそのまま移行したがために、ソ連というタガがはずれた途端、今まで押さえつけられていた欲望が一気に吹き出してしまったからではないだろうか。
この映画に描かれているルーマニアは、同じ共産主義国家だったC国の現状ととてもよく似ている。GDPの3割を賄賂が占めていたというだけあって、地方政府の腐敗ぶりは目を覆わんばかり。売れもしない電気自動車や太陽光パネル、乗車客の全くいない地下鉄駅に人口よりも数倍多い住居建設。作れば作っただけ中共から補助金がもらえるというのだから、不正が蔓延らないわけがない。しかも、共産主義の最たる悪癖、“競争”という自動チェックシステムが働かない分、バブルがはじけ飛ぶまで突っ走ったつけがここに来て一度に噴出してしまったのだ。
そこへいくと、本作の舞台ルーマニア僻村の村長や神父、その取巻き連中が犯した罪なんて可愛いものだ。煙草や酒の密輸、果物の窃盗、酔っ払いの殺人、被害者の妻や新米警官への暴行…本作の主人公警官のイリエが変な気を起こさないよう、以前から欲しがっていた果樹園の権利を無償提供(つまり賄賂)し、夕食まで振る舞って抱き込もうとするのである。「世の中白黒つかないグレーなことばかり」と公言して憚らない検事も、冤罪だろうがなかろうがはなっから気にもしていない。もともと警官という職務を全うする気などサラサラなかったヘタレのイリエだったが…
しかし、単独で殺人事件の捜査をしていた新任のヴァリが何者かに襲撃され、密かに思いを寄せていた被害者の美人妻に軽蔑の眼差しを向けられた瞬間、イリエの中で何かが変わったのだ。覚醒したのである。果樹園経営で生活基盤さえしっかりすれば、一度は失敗した幸福な家庭をまた築けるかもしれない、という甘い目論見が吹き飛んでしまったのだ。人間の性根が腐っていれば、その手で作られる果実もまた腐敗していることに気づくのである。
ラスト、ダーティ・ハリーと化したイリエは一人で悪党一味と対峙する。はたして、孤立無援のイリエはクリント・イーストウッドになれたのだろうか。はたまた“水上歩行”するイエス・キリストのごとく、イリエはグローバリズムがもたらした腐敗に対して奇跡を起こすことができたのだろうか。ドロドロとしたフォークミステリーかと思いきや最後は古き善き時代の西部劇でしめくくる、意外性抜群のシフトチェンジが“そんなに悪くない”1本だ。
村長こわい
なんかもっとおどろおどろしいの想像してたら意外とシュールな感じだった。
とにかく序盤は全然やる気もない働かないイリエにイライラしてたんだけど、殺人事件が起きてから村長含むヤバすぎ集団がやりたい放題でビックリ。長いものに巻かれていたイリエも堪忍袋の緒が切れて悪を成敗するんだけども、戦い慣れてないからか銃撃戦も鈍臭くてそこがリアルで良かったな〜!イリエは多分元々正義感溢れる警察官だったと思うんだけど、過去に何かあって無気力警察官になっちゃってたんだね。イリエがシャツのボタンしっかり閉めて制帽かぶるあたりは覚悟を感じたし痺れました!面白かったです。
正義も所詮人間の欲
世の中には白黒つかなくていいことがある。
ルールに固執していては仕事は片付かない
映画序盤のこの言葉がやけに記憶に残っている。
何にしても、「どちらが正しいか」「何が正解か」考え始めてしまうけれど、実は「世の中には白黒つかなくていいこと」というか、白黒つかないことの方が多い。よく言う、どちらも正しいくて、どちらも間違っているというやつ。
それでもヒトが何が正かを求めてしまうのは「欲」がヒトに寄生して離れないから。
正義で行動する者と規則に従う者どちらも魅力的に見える作品が多いが、どちらもただ自分の「正しい」と思っているモノに従って行動しているだけ。
正義で行動している者はルールに反して正義という名の欲で動いているだけ、
ルールに従っているモノは自分の利益や「欲」とたまたま利害が一致しているだけ。
主人公は「欲」に従い、他人に自分の正しさをぶつけている。
規則は誰にでも同じように課されるけれど、
「正義」という名の自分勝手な「欲」は人によって姿を変えるし環境や場面で色を変える。
人は規則と欲の間でいつも揺れ動いている。
正義も人間の欲でしかない。ということに気づくと少しだけ悲しくなった。
人は誰しも心の中にヒーローがいるはず。でもそのヒーローも自分勝手な欲の押し付けと思うと胸が痛い。
この映画は、そんな揺らぎを映し出し、観る者に問いを残す作品だった。
退屈なタランティーノ
夜勤明けでの観賞もあって、一瞬寝落ちしてしまいました
それも他殺死体の発見あたりで
焦ったがしかし眠気は治らない
オープニングから1時間近くもルーマニアの田舎の村で働く覇気の無い中年男の警察官の村の権力者に忖度した日常が続くだけ、新人警察官にもあまり仕事を教えると言うよりは村の仕来りを語るだけなのでそりゃ眠くなるよ
ダラダラとした無風状態で生暖かく眠気との戦いでした
若い部下が襲われた辺りから彼の目が覚め始めたと同時に私の眠気もおさまる
それまで村の権力者の言いなりなへタレな中年警察官がヤル気を出し始めることで自分も脱皮しようとする
緊張感のある銃撃戦はショボいがリアル
主要国では無い国の映画の作り方はその場の流れを重要視してる気がする
リアル過ぎて隙があり、穴だらけだが噛み締めれば味が出る類いのモノかも
頻繁にほっつき歩くおんどりが特に意味はないが妙に重要に思う
タランティーノは言い過ぎ
おんどりは2度夜明け前に鳴く
舞台はルーマニアだが、ラストはびっくり。
配信(dmmTV)で視聴。
ルーマニアが舞台のサスペンスはなかなか観られないし観ごたえがあった。
よくあるサスペンスだが、ラストを観るとえ?なんで?と思ってしまった。
ラストが一番残念でドン引きした。せっかく面白いサスペンスと思ったのに。
監督のメッセージが可愛かった
ドラマとしては抑揚がなく、1人のだらしない警察官を中心に物語が展開してしまう為、劇場では安眠している人も出没しちゃっておりましたが、映像にせずとも主人公の裏でどんな出来事が勃発し、どうして悲惨な結果を招いたのかが手に取るように分かるという凄い作品になっておりました。
道端に転がる新人警察官が映し出された瞬間にその前が容易に想像ついてしまうのだから凄いです。
淡々とした会話や映像だけで村の暗部を浮き彫りにしていこうとする監督の明確な意思を感じました。
余談ですが、新宿シネマカリテでは上映前に監督からのメッセージ映像が流れました。
良かったと思う人はSNSで拡散してね。
そうじゃなかった人は嘘ついてね。
というメッセージにちゃめっ気を感じて好感が持てました。
不格好な男の最期
予告の印象とはだいぶ違うよー、
悪くない!
上映館があまりにも少なすぎてはじめての映画館へ。
ミニシアターも雰囲気あってやっぱり好きやなあ〜
田舎でおこる殺人事件。犯人は割と最初の方であっさり判明するんやけどそこからあれやこれやと徐々に歯車が狂っていく。物語的にゆっくりと時が進む感じなので、仕事終わりの私には思わず眠気が襲ってきた😅
主人公がなよなよしていてなんとなーく毎日を過ごしているのかと思いきや、自分の悪口を言っていた新人には強気で接したり(あの叱責は、今考えると巻き込まないように守るという意味もあったのかな?)家庭がほしいから果樹園を作りたいと言っていたりと理想と現実の間でもがいている男性というイメージに変わった。あーでもないこーでもないとそれまでスローペースやった物語がラストに転調するのもいい感じ。ここらへんがタランティーノ風なんかな?
タイトルの意味は、映画に関しての評価も表しているのですが、映画を観た方ならわかると思います!興味があれば観て損はないかも。
主人公が魅力的
冒頭の感じで、主人公が気弱でうだつの上がらない感じかと思ったら
言うことはズバズバと言うし、部下に威張ったりもして結構横柄な人だった笑
そうかと思えば大好きな果樹園を見て変態みたいにニヤニヤしたり、
自分のこれからの生き方について真剣に悩んだりしている辺り、とてもリアルで、人間臭くて、好感が持てる。
物語が進めば進むほど、好きになっていけるタイプの主人公。
だからこそ、ラストの覚悟を決めた眼差しが痺れるくらい本当にカッコイイ。惚れる。
個人的には、主人公に恋する映画と言える作品でした笑
また本作はルーマニア映画ということで、
田舎のルーマニアの風景が沢山見られる。
家の中の作りなんて、ルーマニアが舞台のバイオハザードヴィレッジとそっくりだった。
とにかくお酒を飲む人達なんだな。
人が集まればとにかくまずはお酒を出して乾杯。真剣な話をする時でさえ。
警察や神父も例外ではなく、仕事中でも飲んでいて面白かった。
ミステリー?田舎あるあるでしょう~
おんどりゃー!!
全54件中、1~20件目を表示