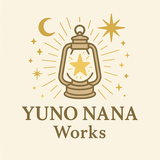ノー・アザー・ランド 故郷は他にないのレビュー・感想・評価
全124件中、1~20件目を表示
カメラは身を守る手段だと知った。
カメラの前でも暴力ははたらかれる。でも撃たれたり危害(殴打など)が加えられるのは、「撮られてない」時なのではないか。
カメラの前の兵士や入植者といった、このドキュメンタリーの加害者側は、言葉や仕草で威嚇する場面が多い。威嚇にしても銃口や実際に殴り倒されたような場面もあるし、確かに映画化段階で凄惨な所は除かれたに違いないとも思う。でも、人が撃たれた瞬間はカメラが壊れてスマホで代替していた時だし、遠くから撮っていた時だった。つまり兵士はカメラの存在に気づいてなかった可能性がある。撮られてない。つまり自分たちの暴力が「バレない」時、酷いことができてしまうんじゃないか。
だから人々は「撮ってるぞ」と連呼していたのかもしれない。「お前たちのやってることは、知れ渡るぞ。」暴力がここだけの、限定されたものではなく、他人が知ることになる可能性があることは、それだけで抑止になるんだと思った。
であれば、映像に残らない、この画面の外ではもっと、考えうる以上に酷い状況なのではないか。
胃のものがせり上がるような鑑賞だった。
学校の授業で、国会で、全映画ファンに、今こそ観ておいてほしい映画です!!
観終わった後の感想は、
「衝撃」のひと言に尽きます。
これは現実なのか?と疑いたくなるような惨劇が、終始フィルムを埋め尽くします。願わくばフィクションであってほしい出来事は、紛れもないノンフィクションで、記録ドキュメンタリーというくくりでこの映画は紹介されています。
撮影者たちが、捨て身の体当たりで伝えたかったこととは?
ただ普通に生活したいだけなのに、それすら許されない。住むところが破壊されるという恐怖は想像するのも恐ろしい。生まれる時や場所を選べない彼らの苦悩と絶望が、この映画を通して痛いほど伝わります。
「対岸の火事」ではなく
まずは、「正しく知ること」が大事。
次に、無力な自分を想う
そして最後に、ただ祈る🙏
理不尽極まりない暴挙にカメラと言葉で戦う2人の青年
今作を見る前日、私は『セプテンバー5』を見た。
ミュンヘンオリンピックでのパレスチナ武装組織が、イスラエル選手たちを人質にし全員死亡という悲劇を取り扱った作品だ。
その作品を見た後、罪もないイスラエルの選手たちに、パレスチナの人たちはなんて酷いことをするんだと憤った。
しかし本日このドキュメンタリーを見て、私は昨日とは全く逆の怒りを感じている。罪もないパレスチナの民間人に、イスラエルの人たちはなんて酷いことをするだろうと。
つまり、こういうことなのだ。どちらが正義で悪とかではなく、これはもう繰り返し行われる復讐の連鎖なのだと。
そして私は、答えの出ないこの長く根が深く、絡まりが簡単には解くことができない現実に打ちひしがれながら映画館を後にした。
命をかけてこの現象を映像や文章で届けようとした、パレスチナ人とイスラエル人の青年ふたり。彼らが突きつけて来る映像は、一方的に暴挙の限りを尽くすイスラエル側の非道さと、理不尽でしかない映像ばかり。何度も目を背けなくなって、誰か早く彼らを救ってくれと願わずにはいられなかった。
ドキュメンタリー映画は、フィクションという逃げ道が無いからこそ、見る側は否応なく受け止めるしか無い。でも受け止めた私たちに一体何が出来るのか、そればかり考えている。
この作品がアカデミー賞に取り上げられたことで、知名度が上がり、世界中の多くの人が見ることで少しでも良いから良い方に動き出してほしい。
パレスチナ人のバーセルとイスラエル人のユヴァル、2人がいつか何のしがらみも制限もなく、これからの未来を明るく楽しく語り合う日が、1日でも早く訪れてほしい。涓滴岩を穿つ日が必ず訪れることを信じるしかない。
土地を奪われるということ
パレスチナ、ヨルダン河西岸のマサーフェル・ヤッタという地域で、イスラエル人入植者たちによる弾圧の実態を捉えたドキュメンタリーだ。ここに射撃場訓練場を建設するという目的で、イスラエルはこの地に暮らす住民を強制的に退去させ、むりやり家を破壊していく。武器を持った軍もこれを支援している様子がカメラに収められており、パレスチナ人に対する理不尽が白日にさらされている。
トランプがガザの住民を強制退去させてリゾート地にすると発言したことが世界中で波紋を広げているが、土地を奪われ、追い出されることがどれだけ辛いことなのか、そのリアルがこの映画にはある。
本作を監督したのは、作品の主人公的な立ち位置でもあるパレスチナ人のバーセルとイスラエル人のユヴァルだ。この2人が立場の違いを超えて友情を築き、この映画を作っているということ自体が、この理不尽に対する微かな希望となっている。今の国際情勢の、数字だけでは見えない地に足の着いたリアルが確実に写されている作品だ。
事実を知ると共に、本作の制作体制にも注目したい
あらかじめ言っておくと、本作内でイスラエルとパレスチナの関係を改めて詳述することはない。よって鑑賞前後には確認の意味を込め、事実関係を頭の中で整理しておくと良いかも。そうやってマクロで知る自分の知識と、本作を通じ突きつけられるミクロ的な現状によって、私自身、これまでTV報道で漠然と聞き流していた場所の空気、人々の悲鳴、息遣いが初めて線と線で繋がったような感覚を覚えた。これはパレスチナ自治区の一つ、ヨルダン川西岸地区のとある村でイスラエルによっていかなる行為が行われてきたかを、パレスチナ 人の若者の視点で描き出したものだ。また彼のみならず、イスラエル人のジャーナリストの若者が支援に加わり、共に活動する。そこで交わされる同世代の何気ない言葉、思いやり、敬意もまた本作の命。彼らを含む計4人体制(イスラエル人ふたり、パレスチナ人ふたり)で対話を重ねて完全合意制で監督を担っている点も深く注目したい。
Timely Document about the State of Palestine
Shot over four years in the Palestinian West Bank, No Other Land puts you right in the eyes of the people pushed out of their homes by Israeli settlers. The filmmakers themselves are attacked by Israeli soldiers in the film. Ironically, the documentary stops just before the October 7th massacre. See for yourself the bizzarre injustice people of the world struggle through in our 21st century.
人が記号に変わるとき
彼らふたりを突き動かすものは、いったい何なのだろうか。
きっとそれは、「記録しなければ、なかったことにされる」という切実な生存本能に近い危機感なのだと思う。
その強さと勇気に、ただ敬意を抱くばかりだ。
人の尊厳や命そのものが「敵」という記号に置き換わってしまう。
そんな環境を生み出す人間の存在が怖い。
何が正しいのかも判断できず、何を信じていいのかもわからない。
そんなふうに、人を変えてしまう環境が怖い。
感覚が麻痺し、正義も倫理も歪む。
信念も通せなくなる。
そのこと自体が怖い。
私たちが現実に目を向けて覚えておかなければ、歴史がきれいに上書きされる可能性だってある。
人間は、環境次第でここまで残酷になれるし、ここまで無力化されるということを知っておかなければ、強い意志を保っていられないかもしれない。
noteでは YouKhy 名義で、もう少し長い感想を書きました。
悔しくて、涙なしには観られない。
タイトルなし(ネタバレ)
イスラエル軍によって強行接収されるヨルダン川西岸パレスチナ人居住地区「マサーフェル・ヤッタ」。
名目は、戦車隊の演習地設営。
イスラエル建国以前からから、もともとパレスチナ人が住んでいた地域。
であるが、イスラエル軍はブルドーザなどで有無も言わさず住宅などを破壊していく・・・
といった映画。
2019年から4年に渡る記録で、パレスチナ人青年バーセル・アドラーがカメラを持って撮り続け、SNSを通じて発信していった。
もともとは素人とはいえ、現在では記者証も所持している。
そんなバーセルの前に現れたのが、ユヴァル・アブラハーム。
ユダヤ人(つまりイスラエル人)のジャーナリストで、軍の非人道的で暴力的な行為を憂いていたのだ。
バーセルの活動を支援し、彼の活動を脇から撮影する。
しかしながら「マサーフェル・ヤッタ」でのユヴァルの立場は、当然にして微妙・・・
で、こういう設定での劇映画だと、バーセルとユヴァルの関係性に焦点をあて、友情譚になるところだ。
が、そんな甘いことには決してならない。
(友情が育まれない、といっているのでない。念のため)
映し出され続けるのは、イスラエル軍の暴力行為。
家屋の破壊、小学校の破壊、抵抗するパレスチナ人への暴力、果ては発砲。
発砲シーンなどは相当ショッキング。
撃たれ、一命を取りとめたバーセルの家族のその後の様子も映し出されるが、あきらかに絶命したと思われる人の姿も映し出されます。
ですので、鑑賞には覚悟が必要。
終わった過去の事象ではなく継続中の事象。
あまりの凄まじさに、観ていて相当疲れました。
できるだけ多くの人に観てほしい
できるだけ多くの人に観てほしい映画。パレスチナとイスラエルの“たった今”。
監督は若干22歳、それでもすでに10年以上の撮影と発信の経験がある。そうか、彼等は生まれた時からすぐそばにスマホやカメラがあったんだな。
マサーフェル・ヤッタにおけるパレスチナ人の状況を実に生々しく伝えるこの映画は、今後のドキュメンタリーの可能性を感じる作品でもあった。
映像は淡々としている。 その淡々とした状況が、この映像が彼等にとって特殊な事ではない、日常なんだという事をまざまざと見せつける。
抑圧されてはいるけれど少しほのぼのした序盤、これまで、長すぎる占領下での生活に、案外住民達には「兵士は実際には撃ってはこないだろう」そんな心持ちがあったのではないだろうか。そして緊張を増す事態。タガが外れるとどうなるか分からない、そんな状況に刻々と進んでいる様が実に辛い。1年、1年と進む毎に、パレスチナ人監督である方のバーセルの疲労と焦燥が見て取れてそれも辛い。
バーセルとユバルはパレスチナ人とイスラエル人という事で、彼の地においては対等ではない。友情というより、理解と共生がテーマな気がする。 そしてイスラエル軍や入植者の横暴が高じると、イスラエル人であるという理由で取材者であるユバルに憎しみを向けてくる人も出てくる。悪循環の縮図。 序盤で父親がかつて運動家だったが今は…と言いつつ逮捕されるし(デモで運動家として復帰した、という事?)、帰って来た後、逮捕中に何があったかは語られないし、?な部分もあるのだけれど、詳細を語ると命とか色々危ないのかも、と思ったり。
こっから、映画で語られた内容ではない事。
なぜこんな事態が起こっているのか。 マサーフェル・ヤッタはヨルダン川西岸部にある集落で、ガザ同様1967年の第三次中東戦争以降イスラエルの占領下にある。実に50年以上もの間である。
元々、アラブ人(パレスチナ)とユダヤ人(イスラエル)がずっといがみ合っていた訳ではない。対立が激化したのには以下のような背景がある。(すごくざっくり)
第一次世界大戦時の英国の二枚舌外交。 オスマン帝国に対抗するため、パレスチナ(アラブ人)とイスラエル(シオニスト:ユダヤ人)それぞれに、同じ地での独立を約束した。そして第一次世界大戦が終結すると、どちらの約束も守らず、敗戦国のオスマン帝国領をイギリスとフランスで都合よく分割し「委任統治」した。 1920年代には委任統治領からイラク王国やヨルダン王国等が独立したが、国境線は元々の居住民の信仰や文化を無視し、英仏の利害で勝手に引かれ、パレスチナの地にはイスラームのスンニ派とシーア派、キリスト教徒など元々対立する人々が居住。さらにはイスラエルの建国を熱望するシオニストは戦時中の約束を論拠に英国に建国を迫り、英国は領地(パレスチナ)へのユダヤ人(イスラエル)の移住を容認したため、さらに混乱。(元々仲良くない人達がひしめき合う事態。さらに言えばパレスチナを委任統治した英国の初代責任者はユダヤ人銀行家を父に持つ熱心なシオニスト。そんなもんアラブ人よりユダヤ人贔屓しまくりである。)
しかしこの頃はまだシオニストの勢力はそこまで大きくはなかった。ちなみにシオニズムとは、ユダヤ人のための故郷をパレスチナに建国しよう!というナショナリズム運動の事ね。(これもすごくざっくり書いてるけどシオニストの中にも主義思想の違う派が存在し、色々複雑。)シオニストはユダヤ教徒をイスラエル人ととらえ、イスラエル国家建国を提唱したが、各国で成功しているユダヤ教徒(ユダヤ人)達は、独立国家に押し込められる事を良しとせず建国には消極的だった。そして第二次世界大戦で事態は変わる。ホロコーストだ。ホロコーストの難を逃れるため、ユダヤ人のパレスチナへの流入は増加し、現地アラブ人との対立が激化。そして戦後、統治者であった英国はパレスチナの混迷を国連に丸投げして撤退。
近代史上最大の迫害と人権蹂躙を受けたユダヤ人達の間で益々シオニズムが高まる。
そして1947年に国連で出された決議案が「パレスチナ分割決議」
パレスチナをアラブ人(パレスチナ)とユダヤ人(イスラエル)で2分割する、という案だが、元々の居住者は圧倒的にアラブ人の方が多かった(すごくざっくり、2/3がアラブ人で1/3がユダヤ人)のに、分割の配分はユダヤ人(イスラエル)が57%という割合であり、アラブ人には受け入れられない不公平な決議だった。
こちらの決議、アラブ系の国は反対したが欧米や日本は賛成で通ってしまう。
そう、日本も賛成しているのである。ワタクシ不勉強なため日本がなぜ賛成したのかは把握していないけれど、日本もいっちょ噛んでいるのである。
こんな不公平がまかり通った背景には、イスラエル側の巧みなロビー活動があった。つまりホロコースト被害への同情や加害に近い国には贖罪を求める…という。(もちろんお金もばらまいたことであろう)
かくしてこんな決議受け入れられないアラブ側と過激さが増すイスラエルとの間で中東戦争が勃発して現在に至るのは、昭和生まれの我々には記憶に新しい所。(中東戦争だって米英仏露が自国の都合で支援する戦争だったでしょ。)
当然、イスラエルの今日のパレスチナに対する侵略や暴力行為を国連は認めていない。
しかしイスラエルは実にしたたかに、自らに都合のいい決議は権利として受け入れ、都合の悪い勧告は全て無視している。欧米がイスラエルに肩入れするのも、各国に散らばった有力ユダヤ人の存在のためだ。つまり自国の利益にならないアラブ人より自国の利益になるユダヤ人を優遇しよう、という意思。(これもキリスト教シオニズムとか福音派とか宗教、思想的にも色々複雑な内部事情がある)ついこの間トランプさん言いましたよね、「ガザは米国が所有する」って。酷い。
そう、バーセル達が闘っている相手は、世界各国の利権により都合よく変化する「正義」でもあるのです。
家族仲良く肩を寄せ合い暮らす人々が軍や怪しげな入植者達に蹂躙される様は、どう見ても「やってはいけない事」です。
それは我々が生きる先進国主導の社会が生み出した歪と暴力。
”正義”って本当になぁ。本当に。(辛)
ちなみにパンフレット欲しかったんだけど売ってなかったな。
それでも見てほしい
この作品をチェックしているような人にはいまさら説明はいらないかもしれません。巷の評判通りの作品です。
あらすじ通り、故郷を不条理に追い立てられるパレスチナの方々の姿を映します。
悲しみに暮れ怒りに震えます。楽しい気分にはなりません。
しかし、やっぱり見たほうがいいと思います。
彼らが間違いなくそこにいることが分かります。彼らの生活が奪われることがいかに理不尽で間違ったことか、知っておかないといけません。
いまの私たちにはどうすることもできないかも知れません。ただただ無力感に襲われ落ち込むことしかできないかも知れません。
でもやっぱり見てほしいです。
いつかこんな理不尽に抵抗できる機会が来た時に間違えて欲しくないからです。
家を壊され土地を奪われること。
この映画では語られない真実が隠れているのでは?
そう見終わって考えました。
これだけでは不十分です。
はっきりしている事実は、
★他人の土地や家を奪ってはならない、
★イスラエル国は、どんな理由をつけようと悪い‼️
この映画がアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したのは
周知のことですが、
帰国した監督のハムダン・バラル氏はイスラエル入植者たちに
暴力を受けて、頭部と腹部に大怪我をしたそうで、全く酷い話である。
この映画は2019年夏にバゼル・アドラがカメラを回しはじめ、
直ぐに家が壊され、仕方なくアドラ一家は大きな電気も水もない
洞窟に避難します。
その後も、マザーフェル・ヤッタの村人100人位は、家を学校を次々と
イスララエル軍のブルドーザーで破壊されて行くのです。
2023年10月に映画は突然終わります。
それはハマスがイスラエルを奇襲して1200人を殺し、人質450人を取って
ガザ地区を占領したから、怒ったイスラエルの報復の、
恐ろしいガザ壊滅作戦が
今もますます過激化しているのです。
★パレスチナは独立国家ではありません。
パレスチナ自治区に過ぎないのです。警察組織もないのです。
そこにハマスというイスラム原理主義者の過激派組織が、大手を奮って
我が物顔に好き勝手をしているのです。
ハマスは1万5000人から4万人位の構成員がいるそうです。
パレスチナ自治区はハマスに乗っ取られているのです。
★パレスチナ人が故郷を愛している(映画の副題の通り)
★パレスチナ人を受け入れる国がない。
★★パレスチナ人には根強いイスラエルへの抵抗意識がある。
などで八方塞がりなのです。
この映画の主役アドラさんの父親もアドラさんの子供の頃から、
抵抗運動家だったと描かれています。
アドラ一家の職業は給油所(ガソリンスタンドかな?)
ここは襲撃されない・・・
そのガソリンはどういうルートで供給されているのだろう?
映画を見た限りでは、アドラさんにしても30代半ばでろくに働いていない。
法科を出たが弁護士の仕事はなく、イスラエルに行って作業員しか仕事に
就けない。
多くの人々が仕事をしていないのです。
また不思議なことに妙齢の女性が殆ど見当たらないのです。
若い女郎性はどこへ行ったのでしょう?
そして産業がない。
せいぜい羊飼いくらいである。
農作をする畑がどこにもないほどの痩せ地なのか?
と、疑問は尽きないのですが、
しかし翻って日本人の現実を思っています。
地震災害や洪水で家を失う人が後をたちません。
それがどれほどに生きる意欲を削ぐことなのか?
それを振り返るとパレスチナ人の苦しみにも
共感してなんとかならないのか?
と切々と思います。
蛇の生殺しみたいな閉塞した現実が、痛ましい。
国が機能していないこと。国際社会からの孤立。
それが一番の問題点で原因かもしれません。
100年前から続く
イスラエルによる占領と破壊の続くパレスチナ自治区ヨルダン川西岸(イスラエルを挟んでガザの反対側)に住み、理不尽な現状を映像で世界に向けて発信するパレスチナ人ジャーナリストの青年と、同じくイスラエルによる占領に反対し、パレスチナ人ジャーナリスト青年と協力してヨルダン川西岸で取材し映像を発信するイスラエル人ジャーナリストの青年。2人が2023年10月までの4年間に渡り、イスラエル軍や入植者の暴力による破壊活動を命がけで記録したドキュメンタリー映画。監督は彼ら2人に加えてパレスチナ人とイスラエル人が1人ずつ、計4人となっているとのこと。
今やテレビでもしょっちゅう流れるようになったパレスチナの映像だが、そのほとんどはガザの惨状だ。一方、映画で映し出されるのはそれ以前のヨルダン川西岸の様子。イスラエル人入植者とイスラエル軍によってパレスチナ人の家屋や小学校までもがブルドーザーで破壊され、井戸がコンクリートで埋められる。住居も土地も奪われ、追い立てられていくパレスチナ人。イスラエル軍や入植者に銃で撃たれて死んだり半身不随になる者もいる。そのような理不尽で非道なイスラエル軍と入植者の行為を、2人はスマホやハンディカメラで接写して臨場感あふれる命がけの映像を撮っていく。そのようなひどいことの連続がパレスチナの日常であり、イスラエル建国と数度の中東戦争以来数十年、いや建国以前からユダヤ人の移住はあったんだから100年近くに渡って続いてきたとも言える。もっとも迫害が激しくなったのは60年代から80年代らしいんで、そこからは40年から60年でやっぱり数十年だ。思えば90年代にはPLOのアラファト議長とイスラエルのラビン首相の間で和平の動きがあり、ほのかに希望の見えた時期もあったが、今となっては遥か夢の彼方となってしまった。それにしてもパレスチナ自治区ヨルダン川西岸でのイスラエル軍およびイスラエル人入植者の行為を見ていると、満洲国における関東軍と満洲開拓移民もおそらくはこうだったんだろうなあと連想させられた。そういう意味では日本人にとっても決して他人事ではないと思わされる。
そして、この映画で意外にもそれ以上に印象深いのは、そのような過酷な映像の合間に映し出される2人の青年の会話と交流のシーンだ。共に撮影を続ける2人が語り合うパレスチナとイスラエルの未来についての対話や、2人の若者の間に生まれる友情が静かに胸を打つ。パレスチナとかイスラエルとかではなく同年代の若者の、1人の人間と1人の人間の関係こそが未来を形作っていくのではないか? そういうほのかな希望が宿る。そんな映画でした。
撮影は2023年10月で終わったことが示されるが、エピローグとしてガザとイスラエルの紛争が再び勃発したこと、ヨルダン川西岸でも事態はますますひどくなっていることが触れられる。この映画のパレスチナ人監督の1人がイスラエル軍に拘束されたというニュースが今年流れたことも記憶に新しい(後に解放)。映画の中でパレスチナ人ジャーナリストの青年がイスラエル人ジャーナリストの青年に「焦りすぎだ。数十年の問題が1日で解決はしない」と言うシーンがあるが、解決にはまだ多くの歳月が必要なのかもしれない。
引用させてください
映画鑑賞後、パンフレットを購入して読んで見ました。意外にもこの映画についての辛辣とも言えるコメントがあったので引用させてください。
「(前略)パレスチナとイスラエルの両当事者による共働は、パレスチナ問題の現実が厳しいとものであるほどに、救いに近い感情を与える。一方で、映画としてはある種のパターン化に陥っている印象が否めない。平和主義者のパレスチナ人とリベラルなイスラエル人が登場し、勇気ある共働に国外から高い評価が送られるという一連の流れである。(後略)」(鈴木啓之東大特任准教授)
この映画の制作国にはノルウェーが名を連ねている。「オスロ合意」のノルウェーである。「オスロ合意」を無視するイスラエルへのノルウェーの人たちの憤りが映画制作の原動力になったのかも知れない。
現実は映画よりも絶望的な状況になっているのは言うまでもない。再び光が差し込む日は来るのだろうか。
言葉が出ないシーンばかりだが、希望も感じた作品
話題のドキュメントで、アカデミー賞国際長編ドキュメント賞受賞作品。
やっと観ることができたが、文句なし素晴らしかった。
中東情勢は現在進行形だが、とにかく今回の作品は言葉が出ないシーンばかり。
イスラエル人入植者がまさか武装してパレスチナ居住区に来るとは思わなかった。
今回の作品も含めて日本のニュース以上に深刻な中東情勢であることは間違いない。
そんな中でも、この作品のメインテーマでもあるパレスチナ人青年とイスラエル人青年ジャーナリストの命がけの交流、対話は印象に残った。
二人のセリフは胸に響くし色々考えさせられた。
今年のベストドキュメント有力作品といえる。
中東情勢に関心がある方は必見のドキュメント作品です。
まだなにも終わっていない
日本では報道されないパレスチナの現実
日本に暮らしていると、忘れている現実を映し出す。
必要十分な食事が毎日摂れること。
義務教育を受けること。
男女平等であること。
尊厳が保障されていること。
病気になったら医者にかかること。
清潔なトイレをいつでも利用できること。
安全で安心な我が家に住めること。
命の危険にさらされないこと。
日本では普通のことが、普通ではない世界があることを思い知る。
イスラエルとその為政者を理解しようとしなくていいし、パレスチナの人たちに同情するのも違うと思った。
日本も、一見平和な今の状態が続くとは限らない。
なんせ、大荒れの東アジアの一員で、隣国はロシアなのだ。
世界は繋がっているから、知り、考え、行動していかなくちゃ。
エンタメ要素もなく、楽しい気分になる映画では全くない。
でも、観る価値のある映画だった。
ドイツとアメリカでドキュメンタリー賞を受賞したこと、そしてなによりバーセルとユバルの友情に心から拍手を送りたい。
全124件中、1~20件目を表示