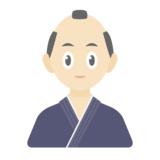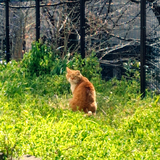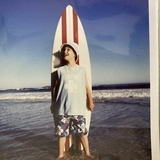I Like Movies アイ・ライク・ムービーズのレビュー・感想・評価
全106件中、21~40件目を表示
自分ではなく環境が変われば、、みたいな!?
俺は、お前みたいのは嫌いだ!!
でも、ポール・トーマス・アンダーソンの『パンチドランク・ラブ』は俺も大好きだぁ!!!
周りに甘やかされて何も気付かない、置いてけぼりかのように一人だけ成長していない、自意識過剰、何を根拠に自信ありげな感じ?
やっと気付いて少しだけ成長して改心した、いや、全ては周りの変化と周りの優しさ、何も変わらないで生きて行くんだろう??
御涙頂戴、過剰に煽るような演出はなかったようで主人公に寄り添う訳でも、冷たく突き放したり甘やかしたりなオチも、ただ現実を打ち付ける、そんな物語には好感が持てる。
主人のその後の成長が伺える映画です。
「お坊さまと鉄砲」鑑賞して、15分後に同じSCREEN3で「アイ・ライク・ムービーズ」を観ました。
カナダの⽥舎町で暮らす主人公は映画が⽣きがいのニューヨーク大学で映画を学ぶことを夢見ている⾼校⽣。社交性がなく、自己中心的で周囲の⼈々とうまく付き合えず、友人たちをそんなつもりもなく傷つけてしまう。しかし、アルバイト先の店長さんがとてもイイ人で、彼女の「人の話を聞けるようになる」の教えを受けて、高校とは違い大学生活が、青春が、花開くであろうと思わせる内容でした。
何十年ぶりで1日で2本の映画(合計224分)をハシゴしたのは••• 。まだまだ映画を観る体力と気力は残っていました。
【”映画は僕の全てだった。けれどそれ以外にも大事な事が沢山ある事を知ったんだ。”今作は、性格にやや難ある愛すべき映画少年が、バイトや学校生活の中で徐々に成長するコミカル物語である。】
ー 序盤のローレンス(アイザイア・レティネン)は、同じく映画好きのマットとつるんで、映画を観たり映画を撮ったりしている。
彼は4年前に父親を首吊り自殺で亡くした事が原因なのか、どこか情緒不安定で我儘で、傲慢だ。だが、今作での彼は観ていて何故か愛らしい青年に見えるのである。-
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・ローレンスはマットに何気なく、”君とは映画愛のレベルが違うよね。”みたいなことを平気で言ってしまうし、高額な学費のNYU(ニューヨーク大学)に進学するためにレンタルビデオ屋でバイトを始めるが、夜中の二時でも母親に迎えに来て貰う事が当然と考えている、ちょっと世間知らずで傲慢な高校生である。
・又、レンタルビデオ店の店主アラナ(ロミーナ・ドゥーゴ)から指示された仕事は何となくこなすが、遅刻は多いしナカナカ問題児でもある。
・映画の知識は凄く、キューブリックが好きみたいである。TVで「フルメタルジャケット」を見ながら、微笑みデブが鬼軍曹から叩きのめされているシーンを観て笑っているが、彼はその後、自分も同じような目に遭って行くのである。
・彼は自分の言動が元で、マットに愛想を尽かされ映画作りはストップする。更にはバイト先で勝手に夜中に寝てしまい、セキュリティシステムを掛けろと言われていたのに、正面玄関から朝、帰ってしまい泥棒に入られ、レンタルビデオ店に損害を与え、アラナを傷つけてしまうのである。
流石にローレンスもしょげ返る。そして、NYU(ニューヨーク大学)の不合格通知が来て、彼は更にどん底に落ちるのである。ちょっと可哀想。
・けれども、彼はダイナーで独り昼食を摂っていると、アラナがやって来る。彼女は店で話してくれた女優時代の悲惨な経験を乗り越えて、もう一度演技を勉強するために安定したレンタルビデオ店を辞めると、彼に微笑んで告げるのである。
それを聞いたローレンスは、マットが映画プロデューサー志望の女の子と作った映画を観て”良かったよ。”と言い、仲違いを解消し、頭をサッパリと母親に刈って貰い、カナダの大学に進学するのである。
そして、大学の寮で、初めて会った同級生達の会話に自分から入って行くのである。
<今作は、性格にやや難ある愛すべき映画少年が、バイトや学校生活の中で徐々に成長する物語なのである。
<2025年2月9日 刈谷日劇にて観賞>
この設定には弱い
もっとマニアックな話かと思ったら(主人公のルックからの勝手な想像)、割と普通の映画好きな地方の男の子の青春もの。というか、男の子版『レディバード』風。決して『ニューシネマパラダイス』みたいなことでもない。それと後半、学校記念の映画(卒アルみたいなの)のエピソードが出てくるのでスピルバーグの『フェイブルマンズ』風でもある。だから、というか、それらの先行する作品に比べてしまうと厚みがまったくないし、笑いや、さすが!みたいな切れもまったくないのだけど、田舎町を出るぞ、とイキがってる男の子が映画エリートの向かう憧れのニューヨークに行けなくなって、別の場所に向かうあたりがとてもよく、涙が出てくる。ことにラストの学生寮あたりはとても美しく、もうこのシチュエーションは自分的に鉄板なんだな、と思った。
もっとあの当時のレンタルビデオ店や自主映画界隈っぽいマニア度や、店長の過去エピソードももう少しハマればな、とは思った。
ただのオタク話ではない…
忘れられない一本
I hate movies!
2003年のカナダを舞台に、人間関係がうまくいかず、行く先々でトラブルを引き起こす映画好きな高校生を描いた青春コメディ『I Like Movies アイ・ライク・ムービーズ』
トロント国際映画祭を皮切りに熱狂的な評判を呼び、バンクーバー映画批評家協会賞で最優秀カナダ映画賞など4部門を受賞した。(公式HPより)
フライヤーに惹かれ、近くの気になっていた単館系シネマで上映されているとのことで鑑賞。
ラスト数分前まで、ただの映画好きなどうしようもない男子高校生(ローレンス)にモヤモヤ通り越して怒りを覚え、なんなんこいつ、高校生と言えどまじ最悪、胸糞悪い、などとイライラし続ける。
確かにいるいるこういう高校生。自分の好きなものを語りすぎて周りに疎まれちゃったり、こだわりが強かったりで、「好き」のエネルギーを昇華できずにふてくされてる子。高校卒業して、大学とかである程度自由ができて、「好き」の発散方法を見つけられたら花開くタイプ。でも周りはたまったもんじゃない。
ローレンスの周囲の人たちは心優しく、穏やかなぶん、主人公の子供っぽくてどうしようもない言動が目立つ。
その言動に振り回される家族、アラナ(バイト先であるビデオ屋の店長)、クラスメイト。
特にローレンスの母やアラナ、クラスメイトの才能ある女の子など、女性の傷つく姿にシンパシーを感じ、またイライラ。
彼女らはローレンスにきつく言い返したり悲しみながらも、なぜかローレンスを見る眼差しは少し穏やかだ。それはそれぞれ過去の痛みがあるから?もしくは"I like movies!"と訴える彼のまっすぐな瞳があるから?
確かに、人が好きなものを語る顔は非常に眩しい。なんかキラキラ、というかテカテカしている。お金もない、知識もない、技術もない、でも好きなんだ!!!という強い情熱は、なんというか、たくましい生命力を感じて、すごく、いい。
わたしにはそういうのあるっけなあ。
そんなふうに考えだした時からローレンスの魅力になんとなく惹きつけられている。
そして最後、爽やかなラストに繋がる。
わたしは、アラナの語る、「友達を作る方法」がグッと来た。
アラナはめっちゃかっこいい。ビデオ屋の仕事中に叫ぶ"I hate movies!"も、レジに方杖ついて放つ"××××"もめちゃくちゃ爽やかでかっこいい。
いいもん見た気がする。それはローレンスに対して溜まったヘイトから一気に解放されたからだろうか。夢も希望も詰まった若人のエネルギーがまぶしいからだろうか。
年齢は関係ない。だってアラナも辛くても立ち上がって、自分のやりたいことと向き合ってるから。
ちなみに、単館シネマを出た瞬間、同じ映画を見ていた見ず知らずの年配の女性に「いまの映画どう思った?」「あなた、映画お好きですか?」と聞かれ、なぜか彼女のおすすめの映画をいくつか教えてもらった。またこの映画館で会いましょうという約束をして。
なぜ私に?ありがとうだけどさ。
やっぱ映画の力ってすごい。
映画好きなら涙すること必至のマグノリア
最高だった
前半は共感性羞恥が凄くて、
もうほんとにやめなやめなって感じなんだけど、
後半から各々の心の内が見え始めてよかった。
アラナがいいのよな、この映画は
二人の喧嘩なんて最高だったじゃないですか。
いやー、それにしても「マグノリアの花たち」か。
あんな溜められると、ん?ってなっちゃうけど、
終わってみると、最高の解だったとわかる。
めっちゃ考えたろうな。
もうね、アラナが主役と思うよ、この映画は
クソみたいな映画界に入って行く小僧のメンターだもんね
なんで被害を受けた女性が教える立場に回らないとあかんねんってのはあるけれど、なんせ相手は17歳だもんな、、
「あんたみたいな奴が大学入って、女をゴミ扱いするの」とかもうめちゃくちゃ良かったよ、マジで納得した。あいつが女をゴミ扱いするんだよ、
そんでさ、アラナ本当に偉くてさ、今後の業界のために
あいつに教えてやるんよな、人と関わる簡単な方法をさ…。
いやー、心にアラナを…。
なんかいつか、二人が仕事で会えたらいいなとか思うよね。
あのビデオショップの店員もみんな好きになる。
あとお母ちゃんもね、、あの人もキーパーソン。
「キャスト・アウェイ」の海を思い出させるシーンは泣いた。
「お前と一緒にいると、ママも自殺したくなるわ」も泣いた。
いいキャラクターだったな…。家族なんてあんなもん。
ああやって、ずっと続けて、生きて行くしかないのよ、
役者、全員お見事! ただし脚本の一点だけに疑問・・・
主役ローレンス(演:アイザイア・レティネン)もそのお母さんテリ(演:クリスタ・ブリッジス)もバイト先店長アラナ(演:ロミーナ・ドゥーゴ)も、もっと言えば親友も学校の先生もバイト先の他の店員もみんなキャラが立っていてクォリティ高い演技を見せてくれました。
他のレビュワーさんも言及していますが、ローレンスの極端な言動はやっぱりある種の発達凸凹で、その知識がなく背景もわからない人には「しばいたろか、このガキ」とか「青春の一時期にありがちな傲慢さが痛い」と捉えられるかも知れません。
でもしかたない、病気なんですよね。
というかパニック障害で更衣室に立てこもってしまうところも含めて、すべての言動がローレンスの生きづらさを表していますね。
だからお母さんのテリが「Cast Away」を思い出して」って誘導してドア越しに落ち着かせるのが妙にリアリティがあった。
ただ、ちょっとわからない展開が、アラナの「ルームメイトが自殺した」のは嘘だった、と、それに続いて言わなかった俳優キャリアで性被害に遭った、という告白。
つまり性被害に遭って仕事も学業も一旦挫折した過去を言いたくないがために、それと同等くらいショッキングな「ルームメイトの自殺」というエピソードをフィクションとして言ってしまいました・・・という建付け?
・・・うーん・・・
性被害について告白するドゥーゴの演技は素晴らしかったし、そのあと夜の駐車場で自分の父親の自殺を告白するローレンスに共感し黙って抱き締めるシーンもぐっと来たのですが、えええええ? あのルームメイトの自殺が嘘だったの? それならあの駐車場の共感シーンは何? 身近に自殺者が居たという共通体験からの「共感」に嘘があるということになる。
その割には、ローレンスが店内に泊まって翌日問題になって、従業員控室みたいなところで本社筋?の男性の前でローレンスと罵り合いになった末、確かにそこで言うことじゃないだろうが自分の父親が自殺したことを口走ったローレンスに「あんたはいつもそうやって父親の自殺を引き合いに出して同情を引くのよ!」って、それはそれでちょっと言いすぎでしょう。
いやーこの女優いいなぁ、とずっと思いながら観ていたので、そこのところからちょっと興醒めしてしまいました。
そこだけ惜しいなぁ。ので星を半分減らして3.5にしました。
I like "I Like Movies”
映画好きさん?と興味を惹かれて鑑賞。
詳細はあまり事前にチェックせず、コメディかと思っていたけど違ったが、なかなか面白かった。
2003年のカナダ。映画が大好きで仕方ない高校生のローレンス。フィルムメーカーになりたくてNYUを目指すけど、そんなに物事上手くいかないよ... というお話。
題材が映画でなくて音楽でも野球でもサッカーでも同じ。好きな事だけしか見ないで人の事は全く考えずにいたら、そりゃぁ人は離れていく。
でもまだ彼は若く、それに気づけたのも周りの人のおかげ。
そうして社会を学んでいく、青年の成長物語である。
新たな地で、新たな出会い。未来に期待、上手くいくと良いな。
ちょっと岡山天音君の「笑いのカイブツ」を思い出した。
映画作品名がセリフでいっぱい出てくるので、映画好きな方はそれも楽しめる。
最後に出てくる「マグノリアの花たち」を、レンタルかスカパーかで昔見たけど、泣いた記憶あります。いつの間にか配信で映画見られる時代になって、ローレンスのバイトするレンタル店も懐かしく感じた。
*****
字幕の「○○じゃ?」 (知ってるんじゃ?とか、見たんじゃ? など)という訳が、現代風だなあと変なところに感心してしまった。
「おい おい 友達失くすぞ!」と突っ込みを入れたくなる映画監督志望...
バイトリーダーさんがちょっと可哀想💧
夫は自死…息子は発達障害(?)な自己中オタク
1番やりたい仕事にもつけなかった母親を抱きしめ労ってあげたい
あんな💧息子に振り回されても振り回されても
どんな態度であろうがキチンと愛情を注いでいる姿に頭が下がるばかりでした
大学に入学し身近に居なくなった息子を変わらず愛想いながら暮らして行く彼女自身のこれからの幸せを願わずにいられません
バイト先の店長アラナもローレンスと接する中で
共に前に進めた事…頭を多少傾げながらも
もしかしたら良き流れだったと思えるし
彼が振りまいた微妙にイタい行動や言動が
アラナの踏み出しへのきっかけになったのかもしれません
そしてローレンス!大学デビューはまずまずの様かな?
君が少し大人になった時
ママに映画以上…いや同じ位でも構わないから惜しみなく愛を降り注いで欲しいな
君の健闘を祈ります!
全106件中、21~40件目を表示