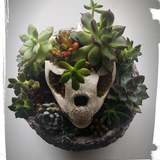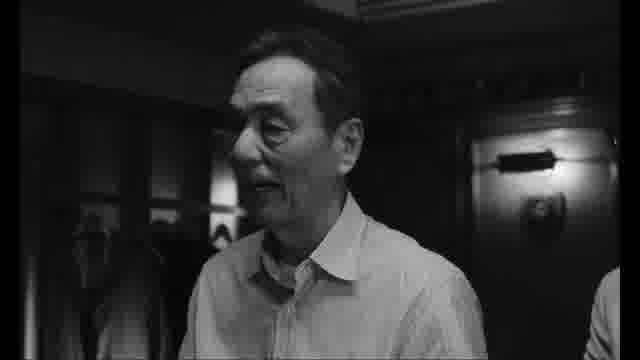敵のレビュー・感想・評価
全102件中、61~80件目を表示
良い映画、でも楽しい気持ちにはならなかった
この映画の“敵”とは
・大学教授としてのプライド
・プライドゆえに素直に振る舞えないストレス
・ちゃんとした生活を送らなきゃという自分へのプレッシャー
・本当はどう思ってるか分からない他者の気持ち
・出来なかった事への罪悪感(妻とパリに行く)
・管理が難しかったり手に負えない家
・若い女たちへの下心、教え子が尋ねてくる妄想への罪悪感、
それを隠したいけど隠すのは苦しい気持ち
・老いへの不安と、それに重なる連載打ち切り、新しい編集者(若者)への恐怖心
・詐欺メールが来る屈辱感
・健康への不安
・世の中からの孤立、寂しさ
などなど
妻の死後20年かけてジワジワと主人公のなかに溜め込まれた“敵”に
最後は自らが潰されてしまったように見えた。
ただ主人公が“敵”と思っているものは実際に悪い事をする者でなく、
主人公の内面の中で“敵”と認識してしまっているだけに見える所が気になった。
人間は、考え方や向き合い方次第で、敵でないものも敵と認識して心をすり減らして肉体的にもダメージを負ってしまう。
それはとても怖い事だけど、考え方次第ではその逆もあり得るというのは救いでもある。
舞台となる家に主人公が閉じ込められている感じも、主人公が“自分の認識”から身動きが取れなくなっているのを象徴している様にも感じた。
最後の主人公の幽霊のようなものはよく分からなかったけど、
最後まであの家=自分の頭の中に閉じ込められたままだった主人公の様になるなよ、
というこれからあの家に住む者と、観客へのへの警告の様にも感じた。
この映画から学ぶなら
気楽さやテキトーさも大事!という事なのかな。
ダブル松尾😁
寝落ちした😂
目覚めたら、自宅に訪ねてきた編集者の不躾な男と女の子が、黒沢あすか扮する奥さんが振る舞う鍋を囲んでいたら、主人公が奥さんとケンカになったと思ったら、不躾な男が女の子に殺されて、井戸に落とそうと引きずっているのを、松尾諭が手伝って井戸に死体を落とすカオス…🤯
何だ、夢オチかいなと思ったら、今度は爆撃始まって、また夢オチかいなと思ったら、ホントに死んだのか🤣
結局、演技派女優の河合優実の出演シーンを見逃すという😌
それにしても、昔、あっち系でお世話になった黒沢あすかは、この系の役柄をやらせたら、右に出るものはいないよなってくらい、安定感抜群ですわい😆
ホラー?
一昔前のアートシアター系っぽい映画。つまり、芸術性が高いのか、製作者の自己満足なのか、いずれにしても難解で私のような凡人には理解不能!最後の双眼鏡を覗いたあとのシーンも意味不明!
それはともかく、映画の中の河合優実に頼まれたら私も騙されてかもしれません。
長塚京三さんだからこそ。
一歩間違えたらイライラする主人公像が、
表面が知的、紳士的でありながらみっともない、俗的、けどどこか人間味があり憎めない魅力的な
キャラクターになっている。
長塚京三さんの演技が変わらず素晴らしく魅力的で
感動してしまった。
あれだけ、みっともない姿はみせたけど
そんな中で後半の夢のような世界で亡くなった奥さんを追って『行こうよ!フランス』と、叶えられなかったことを叫ぶシーンは胸に来た。
どんなに若い女性に夢想しても奥さんが
忘れられないしコートを抱きしめてるシーンも
なんともせつない気持ちになった、
更に主人公の一番最後の台詞もよかった。
あの一言は涙がでそうになるね、自分も死ぬ時は
意識が遠のく中で『皆に会いたいな』と
親しい人を思い呟くんだろうか。と
しかしながら後半は筒井先生ワールド全開なので
好き嫌いわかれる表現は満載。
私は好きですが、あの世界観は教授の自己嫌悪や後悔が見せた夢、精神世界だったのかな。
まだ、教授の魂は生前の後悔と思い出の中で終わらない時間を過ごしているんだろうか。
良い映画体験でした。
鑑賞動機:筒井康隆9割、長塚京三1割
原作は未読だけどあらすじは把握。筒井さんなので、夢/妄想か擬似イベント物…は今更ないか。実はメタフィクションなら映画化難しいのわかるけど。加えて吉田大八監督なら何をやってくるか?
結構手をかけた自炊で、ちょっと美味しそう。
ずっとモノクロでほぼ固定カメラを切り替える映像。一人暮らしの高齢男性にしては、充実した生活をされている方でしょうか。
徐々に夢/妄想の比率が増えていき、いつしか現実にまで侵食…かどうかは判然としないけど。願望充足ともちょっと違う。そして敵。何となくアレかなというのはあるが…。むしろエンディングに困惑。
たまたまつけたテレビで「100分de 名著 筒井康隆」に遭遇。短時間ではあるが吉田監督のインタビューもあって満足。星増やそ。
下心な出費も計算済?
残りの人生と貯金残高を計算しバランスを考え生活する渡辺儀助の話。
妻に先立たれ祖父の代から続く家に独り住む儀助だったが、ある日PCにメールが届き開いてみると「敵がやってくる」というメッセージが届き…。
原作未読、モノクロ映像の中で進むストーリーで見せるけど、ただただ印象的に残ってるのは基本主食は麺類と焼鮭を焼いてるシーンが美味そう!と鷹司演じた瀧内公美がセクシー&セクシーって感じで!
独り孤独に住みながらも日々の生活の不安や下心、生前妻とは出来なかったことの後悔がちょっと分かりにくい世界観ではあったけれど、夢として見せていたって感じなのでしょうかね!?
とりあえず終盤の鍋の件、図々しい編集者に笑えた!「敵」って結局、“不安”に追いつめられるとかの意味?よく解らなかった。
原作世界の現代的再現を楽しむ
1998年に上梓された筒井康隆原作の同名小説の映画化作品でした。1993年に断筆宣言をし、1996年に断筆解除した筒井が、解除後初めて発表した長編小説でしたが、当時は老人が主人公の地味な作品という印象で、従来の派手な作品を心待ちにしていた筒井ファンとしては、何となくガッカリした記憶がありました。
あれから四半世紀余りが経過し、今回映画化されるにあたって改めて原作を見直してみると、自分が主人公・渡辺儀助の年齢に近づいてきたこともあるのか、かなり違った印象を持ちました。特に前半部に書かれた一人暮らしの老人の生活にまつわる微に入り細を穿った表現は、リアリティがあり過ぎて文面から匂いが感じられるほどでした。また、自分にも迫った「老い」というものを、どう捉えるべきなのかも突き付けられた感があり、私自身も”終活”をせねばと思ったところでした。
肝心の映画の方ですが、原作の微細な「老い」にまつわる表現を、如何に映像化するかに注目して観ました。その結果、まずは主演の長塚京三が完全に嵌り役でした。年齢的な部分もそうですが、フランス近代演劇史を教えていた元大学教授の儀助という役柄は、パリ大学への留学経験がある長塚にはピッタリ。フランス語を喋るのはワンフレーズでしたが、充分に重みを感じられました。
一方で、女性の登場人物たちは、キャラ設定とか雰囲気は原作通りだったものの、その行動が原作と異なる部分もあり、そこが興味深いところでした。瀧内公美演ずる鷹司靖子は、色気が溢れていて実に魅力的な女性であり、その辺りは原作路線を寸分違えていなかったものの、最終的に人を殺してしまうことに。この部分は映画オリジナルの展開でした。また河合優実演ずる菅井歩美も、鷹司靖子同様に原作通りのキャラ設定や雰囲気を醸し出していたものの、最終的に儀助から学費の援助を受けた直後に姿を消すという映画オリジナルの展開になっていました。
鷹司靖子と河合優実は、儀助とは親子、ないしは祖父と孫ほどの年齢差があるものの、早くに妻を失った儀助にとっては恋愛対象になり得る存在であり、儀助に感情移入している当方にしてみれば、彼女たちの犯罪行為は極めて衝撃的なものでした。さらに、儀助が内視鏡で大腸検査をする際に、女医に意味不明に屈辱的な格好をさせられ、加えて内視鏡が肛門に超スピードで吸い込まれていくシーンも映画オリジナル。(因みに女医を演じたのが役者さんが、”唯野未歩子”さんというお名前だったので、これって名字でキャスティングしたんじゃないのと思ってしまいました。)
これら女性から酷い仕打ちを受ける儀助というのが、映画オリジナルの展開でしたが、概ね原作通りに描かれた本作が、ここだけオリジナルだったのは一体どういうことなのか?愚考するに、原作にしても映画にしても、この物語世界における「敵」というのは、老いを拒否する自分を罰するもう一人の理性的な自分なのではないかと思うのです。老いを拒否するからこそ、亡き妻を忘れて若い女性に恋心を抱く儀助な訳ですが、そんな自らを弁えぬ身勝手な自分を、理性的な自分が罰を与えている物語を、昨今の時代背景を加味して映画では強調したのかなと思ったところでした。
以上、原作を読んだ直後に映画を観たので、非常に楽しめました。そんな訳で、本作の評価は★4.6とします。
タイトルなし(ネタバレ)
妻に先立たれ、ひとり暮らしをしているフランス文学元大学教授・渡辺儀助(長塚京三)。
祖父の代からの東京郊外の一軒家暮らしで、ひとり暮らしは20年になる。
教授を辞めたあとは、年金とちょっとした原稿書き、時折舞い込む講演が収入で、貯金がゼロになる日を「Xデー」と自ら定めている・・・
といったところからはじまる物語。
全編モノクロ(色調が良い)で、前半は『PERFECT DAYS』さながら、淡々とした儀助の日常生活を描く。
この前半が素晴らしい。
儀助にとってはかなり低い位置にある流し台、米を研ぐ、魚を焼く、麵を茹でるなどの動作・所作がリズムよく描かれている。
が、枯れているようで枯れていない。
教え子で編集者の三十路女性・鷹司(瀧内公美)が訪問すると、やはり心が浮き立つ(表面に出ないようにしているが)。
小洒落たバーのマスターの姪で仏文専攻の学生・歩美(河合優実)には、何か手助けしてやれないかと思う(スケベ心が底にある)。
夢で死んだ妻の信子(黒沢あすか)が現れ、そんな枯れていない心を咎めるが、それはなんだか夢ではないような・・・
と、幻想怪奇譚めいてくる。
この途中の展開も、やや常識的な感じがしないでもないが悪くない。
が、ある日パソコンの画面に「敵」がやって来るというメッセージが流れ・・・の後が、どうもいただけない。
いや、面白いといえば面白いが、それまでに、眠って起きて・・・と繰り返し描かれたことで、唐突感が失せてしまった。
個人的には、この終盤、銃撃戦がはじまったところからカラーで、パーンと世界が変わるようなのがよかったかなぁ。
血は毒々しい赤で。
モノクロに赤の血が飛び、カラーに転調。
あっという間に儀助の目の前が真っ白に・・・(死)
飛び散る白は夢精のそれか・・・
で、「敵」が攻めて来たのが現実、かつて淡々とした生活での少々の欲情が夢だった・・・
あ、それだと別の映画になっちゃうか。
(ジョゼフ・ルーベン監督『フォーガットン』とか、別の映画ね)
四季ならぬ三季のぶった切った場面転換は印象的。
長塚京三の端正でありながら、少々のスケベ心を感じさせる演技、素晴らしい。
瀧内公美、相変わらず、清楚なのにイヤらしい。
河合優実は、フツー。
カトウシンスケの編集者が生理的に受け付けなかった(そういう演出なんだけど、やや過剰かな)。
松尾諭と松尾貴史も滋味に好演(クレジットのトメでふたり並んでいるあたりは遊び心を感じる)。
観終わった後、「ちょっと食い足りない」と感じたが、レビュー書いているうちに面白くなってきました。
面白かったのかなぁ、面白かったのかも。
「敵」が現れると???
フリーの元大学教授が過ごす日常を丁寧に描いて、
PERFECT DAYSとは違う切り口で老い方の描き方を好感をもって観てました。出てる方全員が自然で、見入る事が出来ました。ただ。。「敵」が現れだすと様相が変わってきます。内なる敵だと思わせたものが具体的になってきて。。。本当の敵を出してどうするの。。と私は感じました。後半の展開が好き、斬新と思われる方もいるかとは思いますが私には合わないと思いました。
文学より書院
原作未読のため、粗筋から不穏な話か多重人格か、呆け老人の妄想なのか、判別がつかぬまま鑑賞。
結果から言うと最後が一番近かった。
劇中では儀助の平穏な日常が淡々と描かれるが、所々がファンタジー。
特に元教え子(しかも人妻)が自宅に来て、酒に酔って終電近くまで無防備に寝こけるとか、有り得ないわ。
後半にいくにつれて妄想パートが増えたように感じていたが、このへんからするとすべてが夢オチか。
最後の独白や遺書の内容からしても、教え子たちとの交流も絶えてそうだし。
それ以前に、妄想内でしか描かれてない出来事も多い。
特に歩美へお金を渡した件や夜間飛行の閉店、松尾貴史の手術などはその後も触れられず曖昧なまま。
個人的には独居老人の侘しさが108分かけて表現されていたような解釈に落ち着いた。
出ずっぱりで画面をもたせる長塚京三もサスガだが、出色は瀧内公美。
清純な妖しさとでも言おうか、とにかく魅力的だった。
画作りとしては、終盤に中島歩が庭を横切った際に、“敵”が侵入した場面がすぐ想起されるのが見事。
ただ、クライマックスのドタバタは中途半端さを感じたし、締め方もよく分からない。
不思議と嫌いではないし、原作があるので難しいかもしれないが、もう少しオチに工夫がほしかったかなぁ。
現実か妄想か
こんな令和にモノクロ映画!?と思い、気になって川崎まで向かい視聴。
70代になった主人公が丁寧に生活している描写が続き、徐々に周りの人が離れ仕事もなくなり金も盗まれ、夢の世界(認知症や妄想、せん妄?)に引きづり込まれていくストーリー。
70過ぎて若い子をセクハラするなんてと20前半の頃飲み屋でセクハラされる度よく思ってましたが、歳取ってからこんな真面目な生活をしてる健気な男性にも性欲はあって若い教え子に妄想して亡き奥さんに怒られる妄想もして、その欲が書かれてて面白かった。ちょいちょい挟まる犬とうんちのシーンは何が書きたいのかちょっとよく分からなかった。すごい音がしたとおじさんが言ってたのでその妄想が少し現実味帯させるためのフラグだったのかな、、??
ぐっときたのは最後死ぬ前のシーン。
雪の降る外を見ながら「みんなに会いたいなぁ」とぼやく。こんなに妄想か認知症か分からないけど歳取って誰もいなくなって苦しい思いをして普通の生活も出来なくなったけど、今まで一緒にいた人たちをずっと思ってるんだと思ってこの主人公の清い心に胸を打たれました。認知症になっても周りにいた人達を思える人間になりたいなぁ。
こんなに丁寧に生活して元奥さん以外結婚することもなく素敵な主人公でしたが、老いて苦しい思いするなんて人生不平等過ぎて、年老いてから騙すなんて嫌な話だなぁ
そういえば妄想とは別に謎の敵が出てくるのが面白いですね、最後のシーン家の上にいた男や井戸を修理する男が若い人を見たというシーン。実際変な人がいたようにも見えて不気味でした。
人生の客たち
丁寧で手際よい調理
それに合わせた器選び
きれいな盛り付け
そして
実においしそうな食べっぷり
儀助は健康そうである
きちんと片付いた古い日本家屋も風情があり、自分のリズムで快適そうに過ごし羨ましい老人の独り暮らしにもみえる
そんな彼の人生にも客はたびたび訪れる
細々と続けていた仕事相手、美しいかつての教え子、バーで知り合うひとなつこい女子大生
プライドを保ち、ある時は品よく潔く礼儀正しく、ある時はほんのりときめき、ある時はこっそり自信を蘇らせ
家に戻れば長い人生の〝伴〟亡き妻の残り香を抱きしめる
そこまでは私もほんのりした幸せを感じながら居た
だが、招かざる客が現れ始める
それはこれまでの儀助を揺るがす不意の〝敵〟だった
敵に誘い出されるたび儀助は抗おうとする
不安は不可解な行動や悪夢となり目覚めの悪さは可哀想になるくらいだ
日増しに過去と現在の入り乱れ、おざなりになっていく食事に傍目にはどうしようもない影響があらわれているのがわかる
しかし彼の自覚はもはやそこにはないかもしれないし、
そもそも他の客とのエピソードも完全には不明だ
そんな儀助に余韻ある息を見事に吹き込む長塚さん
モノクロの世界に色も香りもぷんぷん漂わせ、時にユーモラスに、シビアに、おまけに人間の愛おしさまで匂わせながら栄枯ある人生の景色にシナリオにない部分の彼や彼の人生をも想像させてくれる
免れない老いに触れ、人の心の奥をしみじみとじんとさせる作品だった
訂正済み
意識するとそれは敵になるのか
老いからくるのか、孤独からくるのか。現実と妄想と夢の区別もつかないモノクロの世界の中、それは地味に確実に近づいてくる。それは孤独なのか、死なのか。変わらぬ日常に少しでも色付けするが、それでもモノクロから抜け出ない。
不思議な世界観を味わった。
歳とってから騙されたくないなぁ、、、
「敵」とは生存権を侵害するもの
殺傷武器を持って命を奪いに向かって来られたらそれが誰だろうと敵と認定せざるを得ませんし、スポーツの勝敗も生き残りを賭けた疑似の戦いとすれば相手を敵と表現することも多々ありますし、昨今じゃ税金の負担度が上がりすぎて国民の生存権が侵されている、国民の敵は政府?政治家?いや財務省だ!などと云われる始末、現代の本能寺は一体何処にあるのやら。
命の権利を侵す最多最強の敵"老い"は決して逃れられない負け確定のラスボス、劇中で「敵はゆっくりやって来ない、いきなりやって来る」ということでしたが近づいてくる予兆は感じられる、それは"不安"という感情になって心に現れるのでしょう。
講演執筆の仕事も少なくなって収入が減った、貯金の底が見えて残高ゼロになる日が計算出来るようになった、20年健康診断をしておらず身体の状態がわからない、辛いものを食べただけで身体を壊した、後を頼める親族もいないなどなど経済的な不安、健康の不安、孤独の不安が人生終盤となるとどんどん募って来るわけです。
不安は眠りを浅くし余計な夢を見ることになって感情を乱し、不安を取り除くためか夢や妄想の中で告白や言い訳、懺悔をし始め、儀助は現実と夢と妄想での不安との戦いに疲弊し急速に老いて抵抗する力を失ってしまい、ある日何でもない事をきっかけに"老い"は「不安」という弾をマシンガンのごとくダダダダダッと心に撃ち込む「敵」となりパニックになる、という映画だと思いました。
「不安が募っていつか"老い"が敵になるぞ、準備と覚悟をしとけ」なのか「準備を怠らず不安に支配されるな"老い"は敵じゃない抗うな」という話だったのか今はよくわかりません。
私もご多分に漏れずン十年前の中高生時代にショートショート文庫本はほぼ揃えたツツイストでした。筒井先生のような先達がこのような心理分析を作品にして残して頂けるのは非常に有り難いですね。準備と覚悟に繋がります。
いつか爺さんになって老いと不安に対峙した時、「嗚呼、これが筒井先生の言っていた敵かー、どれどれ、"老い"と友達になれるか試してみよう」と言えたら幸せな人生だったと言えるかも知れませんね。
老人は夢見る、もうひとつの人生を
長塚京三さん演じる主人公の日常を見ているだけで満たされる映画。皆さんも名前を挙げる映画、「PERFECT DAYS」を思わせる丁寧な暮らしだ。あの映画はあつらえた感じで好きでなかったが、こちらの長塚さんが包丁を握り、コーヒーミルを回す様子は知的で芯が通っていて、しかし高齢者のもろさをちゃんと感じさせる。
主人公は退職して10年以上の大学教授で、今でも講演をしたり美人の教え子が訪ねてきたり、「俺もまだまだやれるな」と思えるうらやましい老後だ。資金が尽きたら潔く死ぬと言いながら、教え子との情事を夢見たり、バーで出会ったフランス文学専攻の女子大生にときめいたりする。
甘い夢もあれば、病気、亡き妻をめぐる後悔などの苦い夢もある。そのたびに主人公は夢から覚め、ベッドに横たわる痩せた姿をさらす。このように、達観しているようで「もしも、こうだったら」を夢見てしまうのが老境ということだろうか。
映画の後半では、主人公の妄想が深刻化し、いよいよ夢か現実なのかわからないシーンが続く。認知症や、ネットの陰謀論と現実を混同するような描写。でも果たして必要だったのか。私は途中で冷めてしまった。
認知症を描くなら、周囲の反応の冷たさや生活スキルの破綻などの描写があればリアルだと思うのだが。長塚さん演じる主人公は、どうしても最後まで健全に見えてしまった。またネットの陰謀論は時代を描こうとして古くなってしまう要素だと思う。
個人的には、この映画はあくまで長塚さんの日常の連続で描いて欲しかった。あるいは、ホン・サンス監督の「WALK UP」のように、主人公の言動や人間関係がチャプターごとにしれっと変わってしまうような形も面白かったと思う。
3人の美しい女性が出てきて、河合優実さんにはもちろんドキドキしたが、亡き妻(黒沢あすかさん)と一緒にお風呂に入る夢のシーンが一番好きだった。「生きているときは恥ずかしくてできなかった」だって。
老い 孤独 尽きる 危害 時間 狂気 過去 敵!!!!!!!!!!
だいぶ静かめな映画。
劇場で観に行った際はけっこう席が埋まっており、ときどきイビキも聞こえてきた。鑑賞層は主役と同じくらいの方々が見受けられた。
主人公の爺さんは独り身でありながら立派な屋敷、立派な経歴、立派な人脈と立派に毎日料理洗濯家事掃除もこなすし種も枯れてない強さを持った魅力的な人物。
しかし彼にも社会的・生物的に人間として避けられない悩みがあり、その恐怖や困惑から幻覚・悪夢、「敵」として彼を苛む様子が描かれる。
最初はクスっとくる悪夢がだんだん冗談じゃないような内容にエスカレートしていく様に彼の焦りや混乱が乗っかってこちらにリアルに伝わってくる。幻覚と悪夢で混沌とする精神に脳が酔う感覚を味わう作品。
白黒映画で画面の情報量がだいぶ削減されているが、セットがバッチリしており、物が多いけど綺麗に整っている部屋部屋がリアルで没入感があり、会話の内容に集中できる分、より幻覚・悪夢の混沌としている感じが強調されていた。
見ていて気分が明るくなる作品ではないが、とても完成度の高い作品だった。
その後に上映されていたトワイライト・ウォリアーズを見たおかげでまるでサウナの過激な寒暖差を味わえたので、前座としてとても良い映画だった。
うだつ
原作は未読です。
敵は体の衰えや病気なのかなと推測しながらの鑑賞でしたが、前半で混乱したのに後半で更に混乱する大変な作りでこれは自分には早かったのかな〜と思ってしまいました。
自分の貯金残高に見合った死に方をしたいという、将来的にそういうことを考えるのかなと思ってしまうシーンがあったり、生活へのこだわりだったり、徹底したマイルールが良い意味で居心地の悪さを体現していたのが良かったです。
日常生活での変化に一喜一憂している主人公が人間臭くて良いところだなと思いました。
後半は登場人物のテンションも映像も激しいものになっていき、死ぬ前ってこんくらい目まぐるしくなるのかなと思いつつも完全に振り落とされてしまいました。
単純に自分の健康周りだけでなく、過去の経験なんかも敵となって襲ってくるというところにはいたく心揺さぶられましたが、映像がどうにもホラーチックになってしまったせいで集中力が削がれてしまいました。
終盤の展開で潔く終わっていくところと中島歩さんの表情でゾワっとさせられましたがもう少し早く欲しかった〜となりました。
モノクロでしたが飯の美味そうさは抜群に伝わってきました。
シンプルな料理だけど一手間加えるだけで美味しさが爆増しましたし、先生の料理食ってみたいなーとなるのも良かったです。
女性陣は皆々様それぞれのオーラが放たれており、瀧内さんの色気は凄まじかったです。
劇場内には年配の方が多く、自分の心境に重ねる部分も多いのかなと思いました。
30年後くらいにこれを見たらどうなるのか、だいぶ先の自分にぶん投げておきます。
鑑賞日 1/20
鑑賞時間 15:50〜17:45
座席 D-12
振りと回収のお手本
トランクケース一杯の石鹸等、老人が使える数などそれ程多くないのにという前段での、家の前でプレゼントとか、高等なジョークが続く本作 それにしても年齢を感じさせない長塚京三の俳優魂を改めて噛みしめた演技力である
全102件中、61~80件目を表示