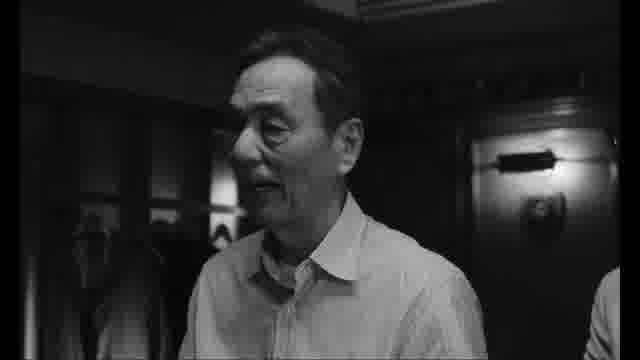敵のレビュー・感想・評価
全102件中、21~40件目を表示
還暦目前の鑑賞者の感想
自身還暦を前にして老いの問題が自分事になっているところで本作を観れば、孤独や痴呆やこれからの過ごし方につき考えさせられるところは少なくなかった。 感受性は老いても衰えさせたくないと思ってはいるものの、環境や病がコントロールしたくてもできないのであるから、衰えをどれぐらい許容すれば苦しまなくて済むのだろうか、などとと自問したくもなる。
映画としては、モノクロの選択は良かったと思ったがそれこそ老いが理由なのか、画面が少し眩しく感じられてキツかった。一緒に観ていた同年代の妻も同じ感想だった。劇場には自分と同年代、そして少し年配の方が多かった。老いをテーマにした作品への世の中の関心の高さがうかがえた。
これも老いのせいなのか、最後のシーンが捉えられなかった。最後に映ったのはだれ(何)で、そのカットに含ませたかった意味は? 私を含め結構な老いた鑑賞者は動体視力の衰えゆえ捉えられなかったかも知れません。
でも興味深く観ることはできました。
敵とは…
77歳の方に世界がどう見えるかにスポットを当て、白黒の情景にしたり、極力BGMを抑えているようでした。
敵=死に対して怯えたり、先に生き別れた方のことを考えたり、過去へ後悔したり…
そして、敵が近づいてきた時には逃げ、向き合う決心をして、受け入れる…そんなことを感じました。
どんなに年齢を重ねても、死というのは近づいてくるまで怖いものなんですね…
私も年齢を重ねること、死ぬこと、怖いです…
敵は何処に?
原作を読んだのは大昔だったがあらすじはある程度覚えている。当時は30代だったので普通に娯楽小説として楽しめたが、正直70を過ぎてこの映画を観るのは辛いかも?僕の記憶では主人公は長塚京三のような紳士的な大学教授ではなくもっと尊大な(筒井康隆のような?)イメージだったが。瀧内公美は笑っていても怖く、河合優実は笑っていなくても、父親が破産して寸借詐欺を働こうとする時でも、幸せそうに見える(少なくとも僕には)のが対照的。パーフェクトデイズを思わせる歯磨きのシーンが多いが、ここまで何度も観客に見せる必要があるのかは疑問。モノクロにしたのはよかった様な気がする、下血シーンはカラーでは観られなかっただろうから。一人の食事でもきちんと材料から手作り(一人焼き鳥は初めて見た)する几帳面な主人公が途中からカップヌードルを食べる(僕と同じ)ように変化していくのは象徴的。敵は老いであり、そして着々と進行する認知症。僕もそろそろ老後の準備をしなくてはいけないのかもしれない。
敵の正体は
自分自身の老後が気になり、「敵」を鑑賞しました。
去年は「九十歳、何がめでたい」も鑑賞しましたが。
「敵」とは何か、劇中では直接的な説明が無かったのですが、主人公が飲み込まれた「悪夢」、それを引き起こした「老い」、となるでしょうか。
知的な主人公は自分を安売りすること無く、自尊心を持って規則正しい日々を過ごしていましたが、そんな人でも敵から逃れられなかったのですね。
準備を怠ることが無いようにしたいです。
まずは掃除をして身綺麗にしておかないと、と反省しておきます。
自分とは違うけれど、気をつけたい
同じ元大学教授だが、主人公ほど研究面での仕事の依頼や教え子との交情が全くないところは違うので、性的誘惑にかられる心配は少ない。詐欺に遭う可能性はあるだろう。コンピュータウイルス感染のようなことはつい最近経験したばかりで、情報面で致命的で、良い助言者に恵まれることが大事だと痛感しているところだ。近隣の揉め事に巻き込まれることもまさに直面している。本作のように、妄想に呑み込まれないように気をつけたい。
パソコンが壊れ、デジタル文書に著していた遺書と、アナログ文書に遺した遺書の内容は違っていたということだろうか。最後の場面は原作にはなかったらしいが、主人公が既に、死んだはずの祖父の幻をみたように、相続人も死んだばかりの主人公の幻をみてショックを受けたというのが当然のところだろう。
タイトルなし(ネタバレ)
こちらも安楽死の参考になりました。自分の死に方を決めていた主人公の生き方が。
(300万騙し取られて)不思議と怒りはないんだ。むしろなるべくしてなったような気っがする。世間知らずの大学教授への罰だよ。
という言葉が印象的でした。
モノクロでこそ際立ちます
妻に先立たれ、古い日本家屋に1人で住む渡辺儀助
設定は77歳でフランス文学の大学教授だった
独居老人と言っても、自炊して美味しいものもしっかり食し、公演や教え子から依頼される記事を書いたりして生活に張りがあるように見える
かつての教え子たちからも慕われ、時々は料理を振舞ったり、身の回りの雑用を請け負ってくれる教え子もいたり、たまには友人と酒を嗜んだりで、良い老後を満喫しているようにも見える
自分のお金の残高を計算しながら生活しているが、それはそれでしっかり見据えていてさすが元大学教授
かと思えば、行きつけのバーで働くバーのオーナーの姪っ子に大金を騙し取られたりして気弱な老人なところも
途中までこの映画のタイトルは「敵」であったことを忘れるほどだったが、パソコンに「敵」についてのメールが届き出したところで思い出した
そこから映画の雰囲気が変わりだし
儀助が悪夢を見るようになった
どれが夢でどれが現実か
覚めても覚めても夢なのか
そして敵とは
夢は全て儀助の妄想で、
その妄想が「敵」で
義助を追い詰めていたということなのだろうか
最後 儀助の遺言で槙男に家屋を託していたが、納屋の品物や、家の中の書物についても教え子に託したはずなのにそこには触れてなかったのは、教え子達も妄想?夢?だったのか
実はどこからが夢だったのか
モノクロなのも心理的に見入る要素になっていたし、最後まで不思議な感覚で鑑賞することが出来た
ある高齢者の心情を見事に描いた秀作
(完全ネタバレなので必ず鑑賞後にお読み下さい!)
結論から言うと今作の映画『敵』を大変面白く観ました。
ある高齢者の心情を見事に描き切った秀作だと思われました。
主人公・渡辺儀助(長塚京三さん)はかつてのフランス文学者の権威であり、おそらくかつては時代の中心のフランス文学評論家として活躍した人物だと思われます。
しかし、フランス文学評論家として重宝された時代は過ぎ去り、主人公・渡辺儀助の社会的な権威は薄まっている事が、雑誌の連載掲載の先細りとしても示されます。
この、かつては時代に上げ底にされ、というより時代の価値観の中で必死に研鑽を積んだ足場が、時代が過ぎ去ることによって空洞になり、自身のプライドだけが宙をさまよっている状態は、大小はあっても高齢者の(特に男性の)誰しもに訪れる普遍性ある場所だと思われました。
今作はその意味で、主人公と同世代やそれに近い人なら当事者として、あるいは自身の父親として、あるいは自身の祖父として、多くの世代にも思い当たる関係深い映画になっていたと思われます。
主人公・渡辺儀助はこれまでと同様に(妻・渡辺信子(黒沢あすかさん)が亡くなった後からと思われますが)朝起きて自炊をし、日常生活を淡々と過ごしています。
しかし現実は、自身の足場は時代が過ぎ去った後に空洞になっており、自身のプライドだけが宙をさまよっています。
そして次第に自身の内面に、妻・信子の幻影や周囲の女性に向けられた性欲の妄想や悪夢や陰謀論が忍び込んでくるのです。
(今作はもしかしたら高齢者の女性とは違った感覚があるのかもしれませんが)
男性にとっては誰しもが避けられないある一つの高齢者の心情の過程を見事に描いた秀作だったと思われます。
(なぜ傑作とまで個人的には思えなかったかというと、とはいえ一方で私的には本質的なところで高齢者の感情がそこまで理解出来ているとは思えず、その点では私は今作の描写からは切実さの点で外部の人間ではあるからだろうとは思われています。)
私達は高齢者になって、
1.かつてあったがもうすでに無くなっている時代の足場を、今でもあったことにしてしがみつき「老害」として振舞い続けるか
2.時代によって簡単に自身の足場は無くなることを受け入れ、自身の価値観を常に捨てて辛うじて現在でも残った自身の価値観のみを残したままで新しい価値観を受け入れ続けるか
3.どちらもかなわず、最後には幻影と妄想と悪夢と陰謀に侵食され自身を消滅させていくか
それらに備えろと伝えている映画にも思われました。
そのことを全く理解する頭の無い”老害”と言っていれば時代を断罪し切った気になっている自身の表現の稚拙さ浅はかさを自らは理解していない、ごくごく一部の芸人やそれを持ち上げているさらに馬鹿な周囲などが存在はしてはいます。
今作の映画『敵』はそれらとは真逆な、遥かに深く現在への1つの解答を示し切った秀作だったと、僭越思われました。
生と死を行きつ戻りつ
原作未読で映画だけ、感想を記載させていただきます。
長塚さん演じる元教授(今後は「先生」と書きます。)が送る、最後の一年ということが、物語の表面的な時間経過となっている本作ですが、そこに先生のたくましい妄想力が加わることにより、時間は意味を成さず、むしろ逆行することすたあるかのような状態になっていくのが、個人的にとても魅力的な作品であると感じ、たった一人の老人の、人生の最後をひっそりと描くだけにも関わらず、強烈なインパクトを残していると思いました。
恐らく、表題である「敵」とは、己のうちに潜むものであることが、予告編など様々な媒体で、ぼんやりとですが予想できていました。それでも、ここまでしっかりと描写するのは色々な意味で挑戦的で勇敢であり、素晴らしい試みであると考えます。
まず書いておきたいこととしては、冒頭も書かせていただいた「時間」や「夢か現実か」など、そういうものはまず取っ払って観た方が分かりやすい作品なのかな、と個人的には思いました。どの作品でも、感想は十人十色でありますが、その感想に物語上のギミックを混ぜすぎると、時として本当に思っていることが沈んで行ってしまうと思うからです。なので、わたしは、上記の「時間」や「夢と現実」、「空間」なども含めて、敢えて考えずに思ったことを書こうと思います。もちろん、「敵」について送られてくる正体不明のメールについても、夢か現実か分からない舞台装置に過ぎないと思っていますし、分かったところで個人的にあまり意味を持たないため、あまり考えないことにします。
この物語のほとんどは、先生が日々を淡々と生きる描写で構成されており、先生が朝起きて、コーヒーを豆をゴリゴリ潰すことから始めて、朝食を作り~というような流れを淡々と音楽なしで表現します。この淡々としていつつも「生命活動」をしっかり描くところも魅力的だな、と思っています。そんな先生は、その中で出会う友人や井戸を掘ってくれる元教え子に、自身の死を予期したかのような発言もします。そういう時の先生はとても理知的で、所謂「理想の老後」を悠々自適に送っているのようにも、わたしには見えました。つまり、人間は老いて死を待つだけになる、つまり「必要とされなくなる」存在であると言外に示しているのだと思います。先生も割と自虐的に「わたしの話に10万円の価値があるという根拠はない。」などと、達観したかのような発言をしていますので、多分、そういうことなのかな、と思いました。
そのような中で、先生は3人の女性と主に関わります。3人は様々なかたちで先生と出会いますし、年齢も境遇も、関わり方もそれぞれです。しかし、唯一同じであることは「必ず先生から離れていく」ということだと考えます。
率直に言って、わたしはこの物語における「女性」とは、「生命エネルギー」のメタファーのような存在なのかな、と思いました。そして、反対にこの物語における「男性」とは「死」を連想させるメタファーとなっているようにも思えたのでした。それが、タイトルにもある「生と死を行きつ戻りつ」にも繋がっています。
物語は先生の人生の終わりを分かりやすく表現しているのか、蝉の生命ほとばしる鳴き声で埋め尽くされる「夏」を始まりとして、段々と静寂が忍び寄って来る「秋」、そして遂に「敵」が襲い掛かる「冬」と経過していきます。その中で、先生の友人は検査入院のはずが危篤状態に陥るほどの大事を患ってしまい、先生が寄稿していた雑誌への連載は打ち切りとなるなど、ネガティブな事件が立て続けに起きます。その辺から、先生の所謂「夢」は急激に肥大化していくように思えます。わたしは、上記で「男性=死」という考えを書きましたが、もう一つ加えると、それは「現実」という要素だと思います。ちなみにもう一人、元教え子の編集者についてきた若手編集者も男性であり、ある場面で殺されてしまう描写があるのですが、ここでも先生の周囲にいる男性は「死」を想起させますし、元教え子が掘っている井戸は、やはり「下の世界=黄泉の国」を想起させるものとも思えてしまい、同様に「死」のメタファーのように感じられました。
つまりわたしが言いたいのは、この映画においては「男性=死=現実」という方程式が成り立っているのではないかということです。先生の世界において、男性の登場は現実世界との接触であるとともに、自分の死を連想させる装置になっているのではないかということですね。
では、反対にわたしが上記で生命エネルギーのメタファーとして考えていると書いた「女性」はどうかを書かせていただきます。その前に、この「女性」にも、もう一つ「男性」と対となる言葉があると思いますので、先に書くと、それは「夢」です。これは「幻想」とも言えるように思います。これは物語のギミックとして先生が彷徨う「妄想」ではなく、あくまで象徴としての「夢」だと思っていただけると幸いです。
そんな女性の中で、一番象徴的なのは、瀧内さん演じる元教え子であり、先生が最も性的に見ている女性でもあると思います。この元教え子が実在するのか否かは置いておいて、少なくとも過去に自分が教えた生徒であったことは確かなのだと思います。その教え子が「来てくれる」ことで、先生は分かりやすく明るくなり、教え子が「誘ってくれる」からセックスに及ぼうとする、という夢を観ます。つまり、先生にとってこの教え子は、自分の男性性を優越してくれる、とても都合の良い存在のようにも思えるのです。
次に、「夜間飛行」(フランス人作家で飛行機乗りだったサンテグジュペリの作品ですね。)というバーで出会う河合さん演じる女学生ですが、この女性にも先生は知的マウントから男性的な優越を図ろうとします。しかしその実、女学生の言葉にすっかり舞い上がっていることには気づいていない様子です。
結果、この二人の女性は先生から離れていきます。女学生は、先生から300万円をだまし取るようなかたちで消え失せ、教え子はかつての自分への対応をコンプライアンスに抵触すると非難し、気持ち悪いものを見るような目で蔑みます(恐らく幻想だったのですが。)。何かを期待していた女性たちからの手痛いしっぺ返し(というか、これも先生が勝手に舞い上がっていただけなのですが。)を受けた先生は、上記友人の入院や連載ストップなども重なり徐々に死へと向かっていきます。周囲から「女性」――つまり生命エネルギーがなくなっていき、代わりに残るのは死を待つ自分だけだからです。
しかし、ここで注目すべきなのは、「生」の象徴でありながら「死」そのものでもある存在としての奥様です。奥様は、ある場面からふと先生の前に至極当然のように現れ、先生の心をかき乱します。ある種のクライマックスである鍋を囲んだ食事シーンでは、先生の性生活を暴露し、教え子の性根の悪さも暴露するなど、物語を動かしていく役割を担っているのですが、これは端的に先生にとって奥様が「罪悪感」そのものだからかな、と思いました。フランス旅行にも行かせてやらなかった奥様、マンションに住まわせてやらなかった奥様、早くに死なせてしまった奥様、そんな奥様の愛を裏切るように若い女性に現を抜かす先生。そういった様々な後ろめたさが、常に奥様に対しては言い訳がましい先生の台詞によって感じ取れました。なので、この奥様が出て来るシーンは少し複雑で、奥様を追い掛ける先生と冷たくあしらう奥様というような「死」を連想させるものと、一方で一緒にお風呂に向かい合って入り、笑顔で話す「生(性)」を連想させるものとが同居しているように思えます。ただ、ここで注意しなければならないのは、この先生にとっての奥様は「生」であるとともに「死=現実」の象徴でもあるので、他の女性(つまり「夢」)と食い合わせが悪い様子で、だからこそ上記の鍋シーンのような修羅場が描かれることになるのではないでしょうか。夢ばかり見ている先生が、フッと現実に引き戻される象徴として奥様が現れる。こうしてみると、先生が如何にして夢と現実を行っては戻っているのか――もっと言えば、生と死の境界を行きつ戻りつしているのかが分かりやすいと考えました。
あまり関係はありませんが、夢の一つとして、病院の女性医師(?)に下半身を露出させられる夢を見たり、奥様と一緒にお風呂に入りたかったりと、先生は本当のところでは女性に自分の恥部を曝け出したい人だったのではないかと思いました。一方で、夢の中の教え子は自分にセックスを誘っておきながら時間制限を持ち出してある種の管理をしようとしたり、「服は着たまま」と命令したりと徹底しています。服を「理性」や「壁」とメタファーを考えると、反対に裸や恥部の露出は「欲求」や「解放」とも考えられ、最も性的に見ていたであろう教え子の夢が理性によって固くガードされているところは、興味深いところかな、と個人的には思いました。
と、ここまで書いてみて、わたしが思うのは、やはりというべきか先生は本当は全然死を受け入れてはいないのだろうな、ということでした。教え子や友人には見栄を張って達観している風情を出していますが、その実、いつやってきてもおかしくない死を恐れ、それが先生の妄想力によって肥大化し、最終的には「敵」という茫漠だったはずの存在として顕現した。そういうことなのかな、と思いました。
物語のラストになると、突如として「敵」は先生に襲い掛かります。先生は必死に逃げて庭の納屋に逃げ込むのですが、これは恐らく「母親の胎内で大空襲を経験した」と語っていた先生の胎内回帰願望が見せる妄想なのだろうと思います。それでも、ふと棒を持って納屋から出て来て「敵」に立ち向かう先生の姿は、母親の中から生まれた赤ん坊とも取れると思いました。結局は撃たれてしまうのは、「敵」が先生にとっての「死=現実」だからなのでしょうか。母親は女性の象徴ともいえるので、この時ようやく先生は「女性=夢」から飛び出して「敵=現実」と向かい合ったとも取れる、とてもテクニカルなクライマックスだと思います。
その後は、とても切なく、夢から覚めた先生は縁側で春の前ぶりともいえる雨を眺めながら「春になればみんなに会える。」と、ようやく本当の願いを言葉にするのでした。要するに、これまでのすべては、忘れられて不必要だと言われていく自分の存在を少しでも世界につなぎ留めたいと願う一人の孤独な老人の話であった、というように思える構造なのですね。
ただ、最後の最後にとても個人的なわたしの「妄想」を書かせていただくと、これらすべては最後にやってきた「春」の章までの「夢」だったのではないかと考えてしまいました。春という季節は、生命が再び活気を取り戻す訳ですが、そこで思い浮かんだ生き物に「蝶」がいます。「蝶」と「夢」で思い浮かぶのは「胡蝶の夢」という、それだけの話なのですが、最後に(恐らく)甥っ子(先生のおじい様(お父様?)にソックリ)と思われる方が納屋にあった望遠鏡を覗きこむと、家の二階に先生の姿を捉えるのですが、そこでふと甥っ子は消えてしまいます。わたしは何となく、これまでのすべては「胡蝶」(あるいは「敵」という名の「何か」)が先生に見せていた夢に過ぎず、甥っ子は先生を「見て」しまったことにより「胡蝶」の夢に取り込まれてしまったのではないか。
そんなことまで、考えてしまいました。そういえば、映画の途中で夜に何者かが庭をうろつき、先生が追い掛けるとそれは自分のお爺様(それかお父様)だったと奥様に嬉しそうに報告(という名の言い訳)をする場面がありましたが、あれは単純に夢と現実が曖昧になっていたことを表していたのかな、とも思いました。「パプリカ」を書いた筒井先生だし、それをやってもおかしくないな、などと。
上記のように、色々と自分なりに考えて楽しむ余地の非常に多い作品ではありますし、男性という存在の脆弱さを心身ともに表してみせた表現力はものすごいのですが、もう少し明瞭でも良いのかな、と個人的には思ったので、☆を一つ覗かせていただきました。
一人暮らし男の淡々とした日常
休日にいつもの映画館で
会員価格1,500円と駐車場代200円ナリ
チラシを見て気になっていた一作
長塚京三は好きな俳優だ
なんか学園ドラマとかお仕事ドラマで
嫌味な教頭とか上司を演じていたような記憶
色の付いた眼鏡をかけていた
そのうちいい役が増えて
恋は何とかの花火ではないとかサントリーのCMに出ていた
あとNHKで頼朝役をやったと思う
この後改めて確認したい
この監督も一筋縄でいかない人
原作は読んでいないのだが
きっと独自の解釈をしているのだと思う
霧島…もおそらくそうでは
白黒にした意図は何なんだろう
トイレとか犬の排泄物の描写もあったからなぁ
出だしは去年観たPERFECT DAYS的
一人暮らし男の淡々とした日常が進む
オラははこういうのが好物なのだ
でも後半かなり動く
虚実ないまぜ
どれが虚でどれが実なのかよくわからなかった
全てが忌の際で観た幻という解釈もあると思うし
友だちが入院したり女の子に騙されたり
あと井戸の中に若手の編集者が放り込まれたのも事実なのかも
そのあたりをあえて整理していない
ラストシーンもよくわからない
はっきり言って嫌いなタイプなのだけど
まぁこういうのもありと思えるようになって嬉しい
妻役の黒沢あすかは30年くらい前に六月の蛇という映画の主役だと思う
当時なぜか観た 塚本晋也だったかな 当時も妖艶だった
内容は覚えていない
教え子役も似た雰囲気の女優だと思った
最初は長塚京三に惹かれて
原作読んでませんがテーマとしては2001年のニコールキッドマン主演『Others』に近しいかなと。
但し『敵』は相当コミカルに描いた分、身近な問題提起作と捉えました。
上映後の監督のトークセッションでは、ラストカットの尺に対する質問に悩んでた様子。
確かに尺を延ばすと『Others』と同じになってしまう。泣かせる作品では無いから現状が最適解かと。白黒映像なので人が風景に溶け込んでしまった(特に止め絵)のは設計の問題ですね!
長塚京三さんの仕草が満喫できる日常芝居が見られます。
長塚京三の代表作になった
老いと死という敵は、誰にでも必ずやってくる。制御出来ない敵。また、食べることは生きること。敵に抗うこと。儀助が今までの人生を振り返るとき、亡くなった妻への悔恨の念や元教え子や若い女性への性的欲望が、現実か妄想かわからない映像となって観客に提示される。観ていて、とても苦しくなりました。
儀助(長塚京三)の顔の皺の印影から現在までの人生の積み重ねの時間を感じ、モノクロの画面に美しくもあり恐怖でもありました。
『春になれば花も咲いてみんなに会える』
夢と現実が激しく混線する、しかしそれこそが極めてリアリティ
ひとりの人生の終末をここまでの高解像度で表現したことに強く感銘を受けた。
自身に確実に迫ってくる「終わり」にしっかりと向かい合っているように見える、いわゆるしっかりとした立派な大人でも、ちょっとしたことでバランスを崩すと見事に崩れ落ちていく。ということを見せつけられ、人生の終わりの残酷さを感じさせられた。
夢と現実が混線する作品であるが、極めて現実を映している作品であると感じた。
反面教師ならぬ反面教授?
原作未読ですが、【由宇子の天秤】の瀧内公美さんと河合優実さんの再共演ということで公開日に早速観てきました。
引退後の人生の過ごし方という逃げられない未来を、自分はどう生きるべきかと色々考えさせられる作品でした。鑑賞後も自らへの問いがしばらく頭の中を巡りました。
主人公は、一般的に立派な方と言われるのかも知れませんが、私はこういう方にはならないように気をつけたいと思う部分がありました。欲が自制できずうたた寝中に果てるとか、教え子を片付けに駆り出すとか、お金の使い方とか。
飯テロ映画でもあります。朝からご飯を炊いて魚を焼いて等、よくある献立でも白黒映像な所が逆に美味しそうに見えました。
何食かでてきてどれも美味しそうなのですが、汁物が全然ないのが気になったのは、劇映画孤独のグルメを観た後だからでしょうか。
主人公の偏屈な性格を描写したもの、とも思いました。
老いへの恐怖
妻を亡くし毎日を平々凡々と生きる元フランス文学大学教授の日常を描く。日常を侵食する妄想、老いという悪夢、それこそが敵なのか。
長塚京三好きで吉田大八監督の作品か好きなので飽きずに観られたが楽しいかどうかと言われたら…。
自分も50歳半ばで無理の効かない年になり、恐怖を強く感じた。
第三種石鹸遭遇
筒井康隆の大ファンだ(った)が、この原作は未読。特に初期の短編(「トラブル」「マグロマル」など)が好きだった。この作品は著者64歳の時の作品だが、既に“老い”への恐怖というテーマが色濃い。
いたって普通の日常生活も、モノクロだと枯淡の風情を帯びてくる。主人公はひとり暮らしなのに随分手間ひまかけて料理をする。後半に入るとカップ麺にお湯を注ぐだけになったりするのが悲しすぎる。夢落ちの連鎖という構造が見えてしまうと、途中からもう話がどうでもよくなってくる。
長塚京三はかつての「ザ・中学教師」の印象が強烈だった。久々に見るとすっかり枯れてしまっていて驚いたけれど、傘寿真近と知ればいたしかたないところ。
私はあんなにわんさか石鹸をもらったことはないなあ。
単細胞的に考えました。
はい、長塚京三の日常が淡々と描かれます。
ご多分に漏れず「PERFECT DAYS」を連想
「PERFECT DAYS」同様、最後まで淡々としていて欲しいなあ・・・と思わせてくれます。
役所広司とか長塚京三は眺めてるだけで楽しいので
ひたすらボーッと眺めるのも至福のときでした。
しかし、ネジは外れ出します。
この「敵」
様々な解釈が出ていますが
僕は単細胞的に「夢」と捉えました。
つまりね
異常事態の後に「目覚める」シーンが多用
気分は「特急シリーズ」のフランキー堺です。
が、起きたあとも異常事態やん
となりますが
ここから僕の実体験の話をします。
一時期、悪夢ばかり見ている時期があり
「夢」の中で「夢」見ていて、それがまた「夢」という多重構造だったり(「ドクラマグラ」みたいね)
「夢」の中で「夢」と気づいて起きようとするんだけど、また「夢」中に引っ張り込まれる
とか怖くて疲れる日々をおくってました。
人に話したら
「エルム街の悪夢」の見過ぎなんですよ
と言われたりしましたが
これ順番が逆で
僕のような恐怖体験をしている人が世界中に沢山いたから「エルム街の悪夢(1作目)は大ヒットしたんだと思ってます。
で、本気で怖かった。
2作目以降に関して言うと、僕は「ホラーキャラのアイドル化」推進派なので、楽しく見守らせて貰いました。
(したがって「貞子」シリーズも楽しく見守ってます)
親しくしている女性から「セクハラ」を指摘されて、ありていで説得力のない弁解をするなんて京三には本気で悪夢でしょう。
また「夢精する京三すげえなあ」と思いましたが、それもまた夢かもしれません。
もしエンドロールの後で、夢から目覚めて起きるシーンがあったら
僕はスッキリだけど
皆さん嫌な気持ちになったでしょう。
観る人によって合うか合わないか(もしくは好きか嫌いか)がはっきり分かれそうな作品です。白黒作品である理由は何となくですが理解できた気がします。
出演者の中に気になる人が複数名おりチェックしてました。
長塚京三さん、瀧内公美さん、河合優実さん等々です。・_・
白黒映像にもどんな理由があっての事なのか気になります。
そんな訳で、さあ鑑賞。
した訳なのですが…。
この作品の感想をどう表現したら良いものか困ってます。*_*ン
鑑賞後1週間経過しても感想がまとまりません。
# 楽しかったですかというと いいえです(すいません)
# つまらなかったかというと 前半寝てしまいそうでした
# 気持ち悪かったかというと 否定できません (すいません)
# 観どころは無いかというと そうとばかりも言えない気も
うーん。
もしかすると、この作品をそんじょそこらの作品(どんなだ)と
思って鑑賞してしまったのが間違いだったかも。うん、きっとそう。
良くみれば、原作が筒井康隆の小説 だし。 @_@;;
というわけで…
以下、この作品が自分に合うか事前チェック~
…って 観てからやってもなぁ…と自分に突っ込みつつ
【設問その1】
筒井康隆を読んだことかありますか?
はい (次の設問へ) ★
いいえ (考え直すなら今のうちですよ)
【設問その2】
「時をかける少女」くらいでしょうか?
はい (引き返すなら今のうちですよ)
いいえ (次の設問へ) ★
【設問その3】
筒井康隆の作風を何となくでも理解していますか?
はい (この作品をお楽しみ下さい)
いいえ (選び直すなら今のうちですよ)
たぶん (何があっても自己責任ですよ) ★
★は私の選択です。
筒井康隆の小説で読んだことがあるのは、
「時をかける少女」
「家族八景」
「七瀬ふたたび」
「エディプスの恋人」 (←もしかしたら読んでないかも)
正直に書くとこの程度しかありません。@-@ ; ウン
そして、いわゆる七瀬三部作(の中のどれだったか)を読んだ
際に、トラウマになりそうなキツイ場面があった事も思い出し
てしまいました。・-・;; オッ
※「火葬場」「蘇生」「テレパス」このキーワードで ” あれか ”
と分かって頂ける方もいらっしゃるかも。
要するに、安心して鑑賞できる作品と思って鑑賞した自分が
悪かったのです。という事をお伝えしたいだけテス…。@_@;;;
そんな訳で、以下レビュー本文です。
◇
作品の概要を挙げてみると…
年老いた一人の老教授(長塚京三)が主役。仏文学の先生。
彼の日常生活のシーンが淡々と続く。
人生の残り時間を、収入見込みから逆算しているヘンなヒト。
その自説を、尋ねてくる人(多くは無い)に説き聴かせている。
住んでいる自宅は庭付きの、年季の入った屋敷。
奥様を無くして以来、一人で暮らしている。
家の手入れも大変だろうが、売って身軽になろうとかの考えは
全く持ち合わせていないようだ。
そんな彼を尋ねてくる内の一人が、過去の教え子(瀧内久美)。
教授と女子大生だった頃、カンケイがあったのかどうか不明。
自分を尋ねてくれるこの元教え子に対して抱く感情は…。
たまには、仏文学の評論記事の依頼がやってくる。
仏文学の研究は格調高い世界と思われているようだが、卒業後に
それで食べていくのが困難な分野でもある。
元教授が良く利用しているパブ(?)がある。
そこに行けば、新しいアルバイトの女子大生(河合優実)。
どうやらこの娘も仏文学をやっているらしく、久しぶりに文学の話
を交わすことで、精神が若返った気分を味わっている。
庭では使われなくなった古井戸を堀り直そうという話になり、
知り合いから紹介された業者が作業に来ている。
と、こんな感じに
淡白で静かな出だしから始まり、とても静かな展開を見せているの
ですが、ある時点を境に話の内容に変化が見られるようになっていき
ます。どちらかというと、不穏な変化が…。
◇
ある夜。トイレの水面を見て呆然とする教授。
白黒作品なので色が分かりませんが、恐らくは真っ赤な出血。きゃー。
辛いキムチを買って夕食に食べたのだが、食べすぎたせいか…。
医者に行く。ベッドの上に四つんばい。
手首も縛られ身動き出来ないように拘束され、下着を下ろされて尻に
検査器具をズブズブと。…うおぅ
その器具のホースが暴れ出し、悶絶する教授…。
という所で場面が変わり、…夢?
このあたりから後次第に、不安な現実と不穏な妄想の入り混じった展開に
なっていく訳で…。うーん。
鑑賞後に残ったのは、
” もやもや”
” 不条理 ”
” 不快感 ”
ほぼ、そういったプラスの感情ではないものが殆どでした。
最後の方では、やはり筒井康隆の世界だったと思うしかないのかと、
半分悟りを開いたかのような心境の中、更に悶々とすること数日。。
◇
突然、頭の中に閃いたものがありました。☆△☆
” 訳の分からないストーリーに変わっていくのは 主人公の ”
” 脳内の認知能力低下の進行を表現しているからではないか? ”
奥さんを亡くし、単調な一人暮らしの毎日の連続。
それによる、認知症の悪化。ワケ分からなくなった認識の表現。
と、アンソニー・ホプキンスの「ファーザー」を思い出しました。
徐々に認知機能が壊れていく老人の世界を、老人の側から描いた強烈な
作品でした。
この作品をそうなのかも、と考えていったら
「理解は出来なくとも納得はできる」 ようになりました。
理由のわからない不条理な展開も納得できます。
※ 本当は違うのかもしれませんが…、そう思うコトにしました。。
◇あれこれ
■長塚京三さん
ひきしまった肉体でしたねー。すごい。
何か特別な運動でもされているものやら。弛みが全く無いです。
とても80歳間近とは思えません。
■河合優実さん
色々な役を演じられる役者さんだなぁ と感心するばかりなのです
が、この作品では「水商売のお手伝いをする女子大生」でした。
一歩引いた感じの「目立たない存在感(ん?)」で好演。
■遺産相続
この作品に出てくるような、庭付きの一戸建て。
なるべくこのままの状態を保全してね との条件で譲られたら…。
うーん。相当の思い入れが無いと、かなりお荷物に感じるかも。
■相続したヒト
” 従兄弟の息子 ” に、その財産が相続されて終わったようですが
あのラストシーンって…。
あの家そのものにも、何かがある(いる)のでしょうか…。こわ。
◇最後に
この原作を書いた時、筒井康隆さんは60代半ば。
これから先の人生に立ちはだかると思われる「老」の世界に
色々な想いを込めて書いた小説なのかなぁ と、
勝手に思っています。(違ってたらすいません)
☆映画の感想は人さまざまかとは思いますが、このように感じた映画ファンもいるということで。
虚しい
原作知らないです。読んでいないです。
正直楽しい映画では無かった。
文学としてはいい作品なのかもしれない。
敵って何?何が来るのか?と楽しみに見ていたが
結局まもなく来る自分の終わりじゃん。
現実と過去と妄想がごちゃ混ぜになりながら
人生を終わる、そんな現実を見せられただけ・・・。
むなしくなった・・・。
全102件中、21~40件目を表示