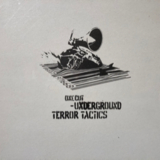リアル・ペイン 心の旅のレビュー・感想・評価
全218件中、101~120件目を表示
良い映画でした。この映画が比較的高評価で良かった。この何とも言い難...
A REAL PAIN
本当の痛み→困った奴、だなんて!
彼らと共に巡る心の旅
痛みや弱さと共に生きる
祖母の死をキッカケに、疎遠になっていた正反対の性格の従兄弟がユダヤ人の歴史を巡るポーランドツアーに参加する数日間を描いた本作。
几帳面で真面目でちょっとコミュ障なところもあるけど家庭も仕事もある“普通の40代男性”のデヴィッドと、空気を読まず破天荒で明るく誰とでもすぐ打ち解けてしまう自由人ベンジー。ホテルや空港、ツアー客とのやり取りから、2人の性格が全く違うことで、お互いにストレスフルなことがビシバシ伝わります。デヴィットの気持ちがよく分かるので、うわー大変そうだ〜と思いながら観ていました。笑
強制収容所を含むユダヤ人の歴史探索ツアーなので、明るく楽しい観光というわけにはいかず。そんな道中で明らかになっていくデヴィットとベンジーの気持ちが胸に響きました。
大嫌いで大好きで、理解できなくて一番分かり合っていて、憧れで。そんな相反する気持ちを抱えている2人は、やっぱりとても互いを思い合っているように見えました。
痛みを抱えながらも、人生は続くし、生きていかなきゃいけない。前向きにならなくちゃいけない。それはとても難しくて、心が折れる時もある。
ラストシーンも、対照的でした。あれからどうなったのかな。安らぎと幸せが訪れていることを願います。
まさにリアル・ペイン
タイトルの通り、人間の心の痛みを描いたような作品。 本年度ベスト級。
思っていたのとちょっと違ったけど、実際にポーランドのホロコースト・ツアーに参加したような気分になる作品だった。
本作はコメディー映画のジャンルだけど笑えるシーンは皆無。
従兄弟の2人の相反する性格を皮肉って「コメディー」としたジャンルに思えた。
他界した叔母の家を、久し振りに再会した従兄弟のデビッドとベンジーが訪ねるストーリー。
叔母の家に行く前、数日間のホロコースト・ツアーに参加。
ガイドを含め7人のメンバーで観光する物語がメイン。
そのツアー中、少しずつデビッドとベンジーの人間性が分かっていく感じだった。
ベンジーとデビットの相反する性格が本作のポイントとなっていた印象。
観光ツアーのガイドの案内するトークが訪れる場所によって変わるのが良かった。
ワルシャワ蜂起博物館の反乱軍の銅像の前で子供の様にはしゃぐメンバー達。
反面、ユダヤ人収容所のガス室では皆、声が出なくなるシーンが印象に残る。
ガス室の壁の色が恐ろしい。
BGMは美しいショパンのピアノ。
美しい風景などにマッチしていて、睡魔を誘うことなく心地よかった。
ラストで2人が別れた後。
帰宅して娘や妻とハグするデビッドの姿に反し、空港に残りベンチに1人で座るベンジーの相反する姿が印象に残る。
外国の方って、初対面なのに何故フレンドリーになれるんだろう(笑)
羨ましいです( ´∀`)
ストレートに感動できる作品ではない
真面目で余裕がなさそうに生きている主人公と空気など読まずに好き勝手に生きる従兄弟が、彼らのルーツであるポーランドのツアーに参加する様子を描いた映画。
タイトルが「リアル・ペイン」であることから、これこそが制作陣の狙いかもしれないが、主人公と従兄弟に対する共感性羞恥に似た苦い感情を強く覚え、観ていてやや苦痛を感じる作品だった。
そこで何が行われたのかを知ることも大事だが、その空気から何を感じるのかも大事なのことだと思う
2025.2.5 字幕 TOHOシネマズくずはモール
2024年のアメリカ映画(90分、G)
祖母の生家に向かうユダヤ人のいとこ二人を描いたロードムービー
監督&脚本はジェシー・アイゼンバーグ
原題は『A Real Pain』で、直訳は「本当の痛み」、スラングは「困った奴、面倒くさい奴」という意味
物語は、NYからポーランドに向かうユダヤ人のベンジー(キーラン・カルキン)と、そのいとこ・デヴィッド(ジェシー・アイゼンバーグ)が描かれて始まる
出発の2時間前にチェックインをしたベンジーは、ずっと変人観察を続けていて、デヴィッドの電話には一切出なかった
その後、なんとかワルシャワに着いた二人は、そこでツアーガイドのジェームズ(ウィル・シャープ)たちと合流することになった
二人が参加するのは「ホロコースト歴史訪問ツアー」で、参加者はユダヤ人老夫婦のマーク(ダニエル・オレスケス)とダイアン(ライザ・ザトビ)、離婚直後のルーツ探しをするマーシャ(ジェニファー・グレイ)、ボスニアの大虐殺を生き抜いてユダヤ教に改宗したエロージュ(カート・エジアイアワン)たちだった
ジェームズもホロコーストの経験者でもユダヤ人でもなかったが、彼らの生き方に興味を持っている存在だった
彼らは、ワルシャワを皮切りに、最終的にはマイダネク強制収容所に向かうことになっていた
そんな道中にて、いろんな歴史の爪痕を見学していくことになるのだが、ベンジーだけは「ツアー」に違和感を感じていた
それは、歴史と統計を強調し過ぎているというもので、現在のポーランドとの関わりがほとんどないというものだった
ジェームズにもツアーを初めて5年のキャリアがあり反論するものの、とりあえずはベンジーのアドバイスに従って、説明を少なくすることに努めていった
物語は、レンジーの自殺未遂半年後という時期で、ツアーに申し込んだのはデヴィッドの方だった
彼は、レンジーを元気づけるためにツアーへの参加を促し、祖母の生家と対面することで何かが変わるのではと思っていた
実際に何が変わったのかはわからないものの、レンジーの存在は参加者のマインドを少しずつ変えていた
別れる前夜のレストランでの出来事はそれぞれの心に深く刻まれていて、ベンジーとデヴィッドの本当の痛みとは何なのかを追体験するようでもあった
ベンジーはかなり多感な人間で、収容所に立ち寄った後のバンの中では、他の人が普通に談笑しているのにも関わらず、一人で何かに祈りを捧げていた
デヴィッドはここまで命に寄り添えるのに、どうして自殺騒動を起こしたかが不思議に思えていた
だが、ベンジーとデヴィッドが感じる「痛み」には違いがあって、種類も違えば、受け止め方も違っていたのである
ユダヤ人の慣習として、お墓参りに行った際に石を置くというのがあって、ラストでは祖母の生家の玄関先に石を置くことになった
近隣住民からの苦言でそれをどけることになったのだが、デヴィッドはそれを持ち帰って家の中に置いていた
それは「来ましたよ」という合図から、「行ってきたよ」という合図に変わっていて、その石には祖母の記憶とベンジーとの思い出も刻まれているのではないだろうか
いずれにせよ、自分のルーツを探る時、多くの人が「自分の命が繋がっているという奇跡」を目の当たりにすると思う
もし、ホロコーストがなければ、ベンジーもデヴィッドもポーランドにいたかもしれないが、同時にこの世に存在していなかったかもしれない
自分の人生を生きているようでも、実際には長く受け継がれてきたものを次世代にバトンタッチをする役割を担っている
それでも、戦争などがなくても途絶えるものは途絶え、続くものは続いていく
そう言った生命の因果を鮮明に映し出しているのが、あのガス室の空気で、あの場所の生命を敏感に感じ取れるのがベンジーという人間なのかな、と感じた
二人の掛け合いが最高
観てよかった、じつに染みる佳作。
ナチスドイツによって親や祖父母が強制収容所へ送られ、戦後アメリカに移民したユダヤ人の子孫たちが、ポーランドのユダヤ人ゆかりの地を巡る「ホロコースト・ツアー」に参加し、参加者視点でそれぞれの胸の内を語っていく。
かつてのユダヤ人街(ゲットー)、墓地、反ナチスのレジスタンス運動を行った人々の銅像、そして強制収容所跡……
観光地となった土地を巡る中で、W主人公である従兄弟二人によって、現代40代アメリカ移民の生きづらさや、直面する悩みが露になっていく。
監督・脚本のアイゼンバーグが論理的で真面目だけど人見知りのデヴィッド、兄のマコーレー・カルキン主演『ホーム・アローン』で主人公のいとこ役を演じたキーラン・カルキンが奔放で自由な従兄弟ベンジーをそれぞれ熱演。
実際に真横にいたら迷惑極まりないベンジーですが、創作物の中なら面白いキャラ(そして実際にあちこちにいそうな人でもある)。
二人の掛け合いが最高で、これだけもう少し長く観ていたかった。
(ハッパ=マ〇ファナだけはいただけないけど)
万人向けではないけれども、40代以上、で肉親を亡くした経験のある人には薦めたくなった。
キーラン
劇的な変化が起きるわけではありません。人々が抱える苦悩が明らかになったりもしないのです。それでも巧みな脚本と2人の達者な演技で見せるロードムービー
20世紀の初めにユダヤ人移民が礎を築いたハリウッドにとって、ホロコーストは特別な意味を持つようです。「シンドラーのリスト」を筆頭に、この歴史的虐殺を題材とした多くの映画が作られてきました。本作で監督、主演を務めたジェシー・アイゼンバーグもユダヤ系米国人。ポーランドを旅した自身の体験を基に構想したといいます。才人アイゼンバーグは、歴史劇として惨事を再現するのではなく、ままならぬ人生を生きる現代の人間関係を横糸にして、歴史の縦糸と織り合わせました。
誰かの苦しみや悲惨な過去の記憶に触れた時、人は何かできるのでしょうか。「リアル・ペイン(本当の痛み)」を分かち合う大切な過程が描かれていきます。
米第97回アカデミー賞では助演男優賞、脚本賞にノミネートされた、祖母を亡くしたいとこ同士の2人の旅路を描くロードムービー作品です。
●ストーリー
ニューヨークに住むユダヤ人のデビッド(ジェシー・アイゼンバーグ)は、長年疎遠だったけれど兄弟同然に育ったいとこ同士のベンジー・カプラン(キーラン・カルキン)と最愛の祖母の遺言により再会します。遺言どおりに祖母の故郷ポーランドのホロコースト遺跡を巡るツアーに参加することになるのです。祖母はそのために遺産を残してくれていました。
参加した史跡ツアーでの新たなる出会い。旅の先々で揺れ動く感情。デヴィッドとベンジーは、時に騒動を起こしながらも、同じツアーに参加した個性的な人たちとも親睦を深めながら戦争の歴史を体感していくのです。正反対な性格の二人でありながらも、家族のルーツであるポーランドの地を巡る中で、互いに求める“境地”は重なり合って行くのでした。最終日にはツアーを離れ、ユダヤ系の祖母がナチス・ドイツに迫害を受けるまで住んでいた家を訪れることに。
そんな2人がこの旅で得たものとは?“リアル・ペイン”(本当の痛み)に向き合う力をどう見出だしていくのでしょうか。
●解説
映画の前半、観客はデビッドとベンジー、それにツアーの参加者とともにポーランドを旅します。博物館や収容所跡などのホロコースト遺跡をガイドの説明を聞きながら見物し、非人道的な所業に改めて粛然とさせられます。それだけなら歴史探訪ですが、そこで終わらないところが興趣といえるでしょう。
神経質なデビッドと、自由奔放で繊細なベンシーは対照的。ネット広告業界で働き、家族を持ったデビッドと、定職もなく母親の家に寄生したままのベンジー。デビッドは真面目できちょうめんですが、心配性で社交性に欠けます。ベンジーは持ち前の陽気さと人の懐にやすやすと入り込こみツアー客たちの心をつかむ一方、感情の起伏が激しし、思ったことをズバズバ吐露し、協調性や思慮深さのかけらすら持たない人物でした。またベンジーは、最愛の祖母も経験した暗い歴史に平静を保てず、激しい感情をあらわにすることも。デヴィッドはベンシーに振り回されていらだちつつ、心のどこかではうらやましさを感じているのでした。
ベンジーの身勝手さには、わたしも嫌悪感を持ちました。でもベンシーが巻き起こすトラブルや不和が必ずしもネガティブに描かれていないところが本作の良さというべきでしょう。多少の欠点やもめ事なら大目に見る懐の広さが、作品を包み込んでいるのです。
対照的な2人の肖像を、ささやかなエピソードと会話を積み重ねて浮き彫りにしていく手際が鮮やかです。仲の良い2人の間の小さなわだかまりと確執が、次第に示されてゆくのもスリリングです。
軽快でユーモラスなせりふの応酬に、それぞれの背景や人間性がにじみ出ています。周囲の人に対する好意が空回りしてしまう母と息子が、分断を乗り越えて歩み寄る姿を描いた前作「僕らの世界が交わるまで」(2022年)と同様、欠点のあるキャラクターにも憎めない魅力を持たせるアイゼンバーグ監督の脚本が秀逸です。不器用な人々の微妙な関係の変化を描くのが本当にうまい作家だと思います。
ただしタイトルから連想させるような、劇的な変化が起きるわけではありません。人々が抱える苦悩が明らかになったりもしないのです。けれど漫然と進んでいく現実のなかでふいに立ち止まり、自分の発した言葉をもう一度考え直すとき、そこから生まれる微細な変化を捉えようとするアイゼンバーク監督の試みは、映画にたしかな光を与えてくれるのです。
ポーランドの歴史を語るなら避けて通れないホロコーストの描き方には、自身もユダヤ系アメリカ人である監督の誠実な姿勢が垣間見えます。特にマイダネク(ルブリン強制収容所)跡地を見学するシーンは鮮烈。終始軽やかに交わされていた会話はぱたりと止み、静寂が訪れるのです。よく晴れた空と無機質な建物のコントラストが利いた映像から、ホロコーストのむごさを肌で感じるツアー客たちの、感情の乱れが伝わってくるのです。
悲惨な事実をただ伝えるのではなく、今を生きる人がどう受け止めて歩んでいくのか。それはきっと、同じ時代を生きる誰かの痛みを想像して分かち合うことにもつながることでしょう。ベンジーの暗い過去に踏み込めず葛藤していたデビッドも、旅を通じて理解と連帯を深めていくことになるのです。
映画の後半、2人はツアーを離れ、祖母の生家を尋ね当てます。2人は民族と個人とふたつの葛藤を経て、安易な和解や調和ではない境地へとたどり着くのです。
ユダヤ人の悲劇を強調するところはいささか押しつけがましくもありますが、巧みな脚本と2人の達者な演技で見せるロードムービーでした。、
●特筆すべき音楽面
旅を彩る全編の音楽は、ポーランドが生んだ偉大なピアノの詩人ショパンの名曲たちです。時に軽やかに、時には荘厳に。美しい景観が内包する影の歴史、人の笑顔の裏側にある“リアル・ペイン(本当の痛み)に至るまで、美しいピアノの旋律が包み込んでくれるのです。この心のロードムービーは、曲とともに見る者の中できっといつまでも、リフレインを続けることでしょう。
●感想
歴史的な痛みを背景にしながら、対照的な性格のいとこが抱える違う種類の痛みを描き出したアイゼンバーグ。辛辣(しんらつ)なユーモアの中に温かさをしのばせる手腕に、監督、脚本家としての伸び代を感じました。
何といってもポーランドのホロコーストの跡地に現代の視点を加味させ、ベンジーとデビッドの丁々発止の掛け合いで見せる脚本が巧みなのです。
そうはいっても、ベンジーは近くにいたら本当にうんざりさせられそうな面倒なキャラクターなのです。けれども自分もこんなふうに生きられたらと、つい嫉妬してしまうような正直な人でもあります。
温厚で勉強家のツアーガイド、ジェームズ(ウィル・シャープ)を、素直だが思ったことをすぐ口にしてしまうベンジーの引き立て役にした構成も効果的だと感じました。深刻さと軽妙さを違和感なく同居させ、じんわりと心にしみるシーンがあるかと思えば、クスッとほほ笑ませるバランスも絶妙です。2人の生きづらさやホロコーストという重たいテーマを、ツアーという形で実感させ心揺さぶる重厚な映画に仕上げたのです。
アカデミー賞間違いなしのベンジー役のカルキンはもちろん、羨望と疎ましさの両方を細やかに表現したアイゼンバーグの演技にも心を動かされました。
けっこう泣いてしまった
厄介者のピエロの涙
監督・脚本・主演を果たしているのは『ソーシャル・ネットワーク』(2010年)でザッカーバーグを演じたジェシー・アイゼンバーグ。そんないろいろな才能の持ち主だったなんて知らなかった。
さほど大きな事件が起きるわけでもなく、40代のおっさん2人旅の様子が淡々と描かれるロードムービーで、ポーランドの美しい街並みを一緒に旅しているような気分にさせてくれる。ただ、強制収容所を訪れる場面では、ポーランドには行ったことがないが、代わりにポルポト時代の虐殺の様子を残しているプノンペンのトゥールスレン博物館を初めて訪れたとこのことを思い出して胸が締め付けられた。
ちなみに、劇盤は基本的にショパンのピアノ曲。そのピアノ曲が場面や登場人物の心情にマッチして、ときに楽しく、ときに物悲しく響く。
普段の日常生活から離れてみることで、自分では意識していなかった仕事や家族その他のことに起因するストレスや残りの人生に対する不安感など、いわゆる「ミッド・ライフ・クライシス」を抱えていたことに気付かされるデイヴィッド。一方、ピエロの顔に必ず涙が描かれているように、自分の唯一の理解者だった祖母の喪失以来、大きな苦しみと悲しみを心の中で抱えているからこそ、人前では過度におどけてしまうペンジー。その2人が本当に素直になれるのは、祖母が奇跡的に生き抜いた強制収容所を見学し、昔住んでいた何の変哲もない家を見てから。自分が今ここにあるのは祖先たちの存在があるからこそと感じる二人。我々アジア人のような先祖信仰を持たない欧米人でも、歴史の積み重ねで現在があるという事実の重みをやはり感じるのではないだろうか。
移民の歴史を軽んじる人物が楕円形の執務室にいる時代にこんな作品が作られたのはただの偶然なのだろうか?
なお、タイトルの「リアル・ペイン」は文字通り主人公たちが抱える心の「本当の痛み」であるのと同時に、英語で He is a real pain in the neck/ass. と言うと「アイツは本当に面倒くさい、厄介なヤツだ」という意味になるので、〈厄介者のペンジー〉をも指してもいるのだろう。
各々が抱える痛みと各々が持っているもの。しっかりとした芯が有りなが...
全218件中、101~120件目を表示