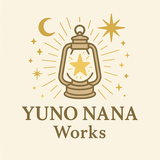花まんまのレビュー・感想・評価
全440件中、1~20件目を表示
パァッと花を咲かせましょう
原作は未読、公開前になにかの記事を読んで、本作を知りました。
実際にお子さんを刺されて亡くされたお父さんのお話「子供が刺されて痛い思いをしてる時に、自分はご飯を食べていた。そんな自分を責める」という話を聴いて、この作品が生まれたとか。
どんなふうに、遺族の傷みに寄り添うのか、気になり観賞です。見事でした。
花は、目を楽しませてくれるのと同時に、心に灯りや光を差し込んでくれるように、気持ちを晴れやかにさせてくれる効果があります。
本作では、やさしく癒やしになっていました。
観賞後の気持ちは、決して悪くないし むしろ良いものだと思うのですが、なにかモヤモヤするというか感想を難しく感じました。無念の中亡くなる人が多いので、人に勧めるときに「よかった」という感想を言うにはどこか躊躇を感じます。だけど、深く考えずになんとなく観れるのに、人は自分一人で生きてるわけではない、という深いメッセージを、嫌味なく伝えてくれています。
生を、周りを、大事にしていこうとやさしくおしえてくれる作品です(*^^*)
〜 以下、個人的な感想 〜
病院前でのバンザイだけ、頂けませんでした。色んな想いや病を抱えた人がいるのですから( '꒳' ;)
バンザイしたくなる気持ちはすごくわかるし、嬉しさの表現方法の1つとは思いますが、、、ほかの表現で観たかったなぁ。まぁ仕方ないですね。
あと、見ず知らずの人の記憶が入ってくるというファンタジーっぽい設定(?)ですが、あながち、ファンタジーではないのかもしれません。いや、ファンタジーかもしれません。どっち!ꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*)ァ,、'`
「戦艦大和の記憶を持つ少年」の話をTVで観たことがあります。すぐ出てくるので検索してみてください…!
自分の身に起これば、否が応でも考えることをすると思うけど、自分に親しい人に起きた場合なかなか受け入れ難い事のようにも思います。ですが、自分の身近な所には無いだけで、実は、こういうことは現実に起きているのかも…。そう思うと、やはり周りの人にやさしくありたいなぁと思ったりしました
いま大切な人に贈る小さな花のお弁当
予告編から絶対に観ようと楽しみにしていた本作品。原作は2005年第133回直木賞を受賞した朱川湊人さんの短編小説だということですが、なんの下調べもなしで鑑賞しました。思ったのと少し違う展開でしたが、タイトル「花まんま」の意味もしっかり回収、ラストはこれでもかと涙腺を刺激してくる展開に思わずホロリでした🥲ファンタジー要素をよくもこれほどすんなりと現実に落とし込んだものだと感心しました。前世の記憶とか自分の中に他の誰かを感じるとかそういう世界仰天ニュース的な非科学的なこともあながち全くなしではないのかもしれません🤫
フミ子の婚約者で動物行動学者の中沢太郎役の鈴鹿央士くんいい味出してました。カラスと会話できるとか、オモロ過ぎるでしょ🤫爆発した髪型で助教授感だしてましたが、ラストの結婚式のシーンで男前まるバレでしたね。また俊樹の幼なじみでお好み焼き屋「みよし」の看板娘を演じたファーストサマーウイカさんもいいですね〜。そのへんにいる大阪のお節介姉ちゃんやらせたらピカイチですね👏兄鈴木亮平さんとの明るいハッピーエンドが予想される流れで安心できました。鈴木亮平さんの熱い演技も予想通り。妹役の有村架純さんも奇妙な記憶と秘密を抱えた難しい役どころをナチュラルに演じ切りました。最後の透明感ある花嫁姿は眼福以外のなにものでもありません!ほんとに綺麗すぎました😍
観て損はない良作な映画だど思いますので、感動作がお好きな方はぜひ映画館へ足をお運び下さい♪
優しくて愛に溢れた世界に心が洗われた
華金の夜、仕事終わりに鑑賞。感動で泣き腫らした目を、心地よい風で冷やしながら帰る幸福感たるや!
今週も頑張った!と週の終わりに見るにはぴったりな、多幸感溢れる作品だった。
ファンタジー要素は強めで、泣かせにくる演出に冷めてしまう人は向かないかもしれないけれど、細かいことなんてどうでもよくなるぐらい、出演されている皆さんの演技がすごく良かった!
そして出てくる登場人物たちがみんな良い人しかいなくて、心があたたかくなる。
何をやらせてもその役にしか見えない鈴木亮平さんは、今回も真っ直ぐすぎて感情的だけど憎めない兄やん役にぴったりハマっていて最高。
有村架純さんも、芯が強くただ複雑な状況にいる妹役がお見事で、この2人の演技のぶつかり合いで見えてくる兄妹の歴史が、物語に深みを増していた。違う方ならあっさりしたものになってしまっていたかもしれない…。
またこの2人の幼少期を演じられた子役の2人が、これまたすごくて、可愛いのと演技のうまさに衝撃を受けた…すごすぎた。
見る側によって感情移入をしてしまうキャラクターが変わってくる作品だけど、誰に感情移入しても感動してしまうと思う。
私も妹がいるので、兄やんの悔しい気持ちがわかりすぎて泣けた。私も同じ立場なら同じように思うと思う。かと言って繁田一家の気持ちもすごくわかる。誰も悪いことはしていなくて、愛で動いていることがわかるからこそ切なかった。
喪失からの再生、愛のバトン、支え合うことの素晴らしさ、優しい世界の物語に心が洗われる作品だった。
記憶に関する設定に思うことなど
本作については当サイトの新作評論枠に寄稿した。そこでの切り口や字数の都合上、言及できなかったことをこちらで書いてみる。ラスト近くの感情を揺さぶる部分、涙を誘うシーンについての言及もあるので、未見の方はできれば鑑賞後に再訪していただけるとありがたい。
物語をごく短く紹介するなら、幼少期によみがえった前世の記憶を抱えたまま成人し近く結婚する妹と、早くに他界した両親の代わりに妹を養い見守ってきた兄の話。現在進行形で語られるパートはほぼ映画のオリジナル、回想される幼少期のエピソードは朱川湊人の原作小説に基づく(より詳しい作品成立過程は評論のほうで解説した)。
前世の記憶という、既存の科学では説明できないものの、古今東西いくつもの実例が報告されてきた、ファンタジーとリアルの中間に位置するような事象を扱っている。ファンタジックな大人のおとぎ話と割り切るなら合理性や納得感を論じるのは野暮だが、現実に起こりうるかもしれない話だと考えると、映画で創作されたストーリーで気になる点がある。
気になるのは、記憶と人格をめぐる設定のあいまいさだ。妹・フミ子は小学校に上がる前の頃、事件で犠牲になった20代女性・繁田喜代美の記憶を取り戻した。映画のワンシーンで、危篤の喜代美と母胎内のフミ子が病院ですれ違った瞬間、成仏するはずの喜代美の魂が(手違いで)フミ子の中に移ってしまったと説明される。ただし、喜代美の記憶がよみがえってからも、それまでのフミ子としての記憶を保ったままなので、フミ子の人格のなかに自身の記憶と喜代美の記憶が並存していると考えるのが自然だろう。
比較対象として、村田椰融の漫画でドラマ化・アニメ化もされた「妻、小学生になる。」が参考になる(次の段落以降で結末に触れるのでご注意)。10年前に妻・貴恵を亡くした主人公・新島圭介の前に、貴恵の生まれ変わりだという小学生の白石万理華が現れる話。万理華のなかで自身の人格・記憶と貴恵の人格・記憶が切り替わる設定で描かれていて、万理華が自分の人格を取り戻すと、目の前にいる圭介が見知らぬ大人に映っておびえてしまう。旧呼称の多重人格障害、現行の用語で解離性同一性障害に近い状態と考えるとわかりやすい。
これら2つのストーリーは、エンディングに向けて似た経過をたどる。映画「花まんま」では、結婚を控えたフミ子のなかで喜代美としての記憶が薄れていく。「妻、小学生~」では、万理華のなかで貴恵の人格でいる時間が次第に減っていく。
どちらのストーリーでも、ラスト近くで前世の魂は現世の肉体を離れ、それとともに前世の家族との記憶も失われる。「妻、小学生~」の場合、人格・記憶が切り替わる設定であり、貴恵の人格のときに経験した記憶を万理華は知らないため、この結末はより合理的で、納得感がある。だが一方、「花まんま」ではフミ子の人格のなかに自身の記憶と喜代美の記憶が並存している、つまり成人してから繁田家の家族に会いに行ったことなどもフミ子の人格が記憶しているはずなので、喜代美の魂が失われたからといって繁田家に関するすべてを覚えていないのは整合性の点で難がある。おそらく映画の作り手は花嫁のフミ子が喜代美の父を見知らぬ来賓として接するくだりを、涙を誘うシーンとして描いたはずだが、記憶と人格をめぐる設定のあいまいさが引っかかってしまうのだ。
これは私見で、好みの問題でもあるが、映画オリジナルの創作パートで、フミ子のフィアンセがカラスと会話できるというジャンル違いのファンタジー要素を足したりせず、魂の転生と前世の記憶という原作小説から引き継いだ主題をもっと深掘りするべきだったと思う。朱川湊人の短編集「花まんま」に収められた各話はおおむね、身近な人を亡くした登場人物らが不思議な経験をする話、死者の霊や魂の存在を示唆する奇譚だ。原作で示された死生観を映画がさらにつきつめ、観客に命や人生について新たな視点で向き合うことを促すような展開になっていたらと惜しまれる。
とはいえ、そこらあたりを深掘りしすぎると、観念的で難解になり、大衆受けせず興行的に振るわないリスクも出てくる。多額の資金を投じて製作する以上、より幅広い層が感動しやすい話に仕立てることが優先されたのだとしても、それはそれで理解できる。長々と書き連ねたが、つまるところ、好みは人それぞれなのだ。
曖昧なままで視聴した方が良い作品
フミ子に入った喜代美の魂が…と表現されており、5歳のフミ子が急に大人びて、態度が変わったのは喜代美になったのか?と思ったが、フミ子の感覚と喜代美の記憶が並列処理されている感じで、フミ子が大人なみに賢くなる訳でもなく、フミ子に混ざり込んだ喜代美の魂は宿主のフミ子とどう折り合いを付けたのか…作中見える部分だけでもどうなんやろ?と思う所もあった。病院ですれ違ったタイミングで神様が魂を入れ損ねたとしたら、そのせいで喜代美が亡くなってしまったのか?(神様がミスっとるやん)5歳になるまでフミ子の中で目覚めなかった喜代美が怨霊宜しくフミ子を乗っ取る事も出来たのではないかとか色々想像したがそれではホラーなのであきまへんわな。自分の善なる解釈では、イマジナリーフレンドの様に適宜、フミ子に語りかける程度の記憶の共有だったのではないか?と想像している。花まんま1つで喜代美(フミ子)を信じ尽くす繁田家の面々には驚くがここはファンタジーの要になる人々だから…。作中の大阪弁行き交う中、目立ったのはファーストサマーウイカ演じる駒子。浪花節を彩る俳優陣で同級生俊樹を力強くサポートとしている姿は好感持てた。
急なファンタジー展開に馴染めれば泣ける作品だし、俊樹の親族代表挨拶はグッとくる人も多いと思う。ラストの「どちらから来られたんですか?」のセリフから来るあの喪失感にこっちの心がやられてしまう。ただフミ子の人生に入り込んだ事の清算せねば1つの脳に2つの心は危ないからラストあれで良い。
支えられて生きる、ということ
舞台が大阪であることは単なる設定ではなく、この作品の“血統”そのもの。
前田哲監督の『花まんま』を機内のモニターで鑑賞した。
原作の源流には、金子みすゞの詩「花のたましい」がある。小説家・朱川湊人はこの詩にあった“転生”と“花びらで作ったままごとの御飯”というモチーフに着想を得て、自身が幼少期を過ごした昭和40年代の大阪の下町を舞台に、幼い兄と妹が体験する不思議な出来事を描いた短編「花まんま」を執筆した。2005年には、この短編を表題作とする短編集が刊行され、直木賞を受賞している。
大阪出身の原作者が大阪の下町を描いていることもあり、登場人物や風景には確かな手触りがある。舞台が大阪であることには、単なる設定以上の“血統としての必然性”があると感じた。朱川の短編を土台に、前田監督とスタッフ、キャストが新たな映画として生まれ変わらせたことで、金子みすゞの詩から始まる三世代の表現者たちのリレーが、映画という総合芸術へと昇華しているように思う。
観始めてまず驚かされたのは、鈴木亮平の関西弁の自然さだ。鑑賞後に彼が関西出身だと知り、「なるほど」と深く納得した。
さらに、メガホンを取った前田哲監督が関西出身であり、妹を演じる有村架純も兵庫県出身。ほかにも鈴鹿央士(岡山)、ファーストサマーウイカ(大阪)、キムラ緑子(兵庫)、六角精児(兵庫)、オール阪神・巨人(大阪)と、関西ゆかりのキャストが揃う。いわゆる“ネイティブスピーカー”が醸し出す会話の間や空気感にまったく違和感がなく、この作品にリアリティと厚みを与えている。
物語の中で鈴木亮平が演じる兄は、幼くして両親を亡くし、厳しい生活の中でも工場員として懸命に働き、妹を守ろうとする。その「守る」「守りたい」という本能が、関西弁の親しみや、土地に根ざした身体性とともに、いとおしいほど伝わってくる。これは、セリフの巧さを超え、生まれ育った場所を背負った役者だからこそ出せるリアリティだと強く感じた。
脚本では、原作には明確に描かれていなかった両親の亡くなった経緯が加えられており、その設定が物語の進行とともにじわじわと効いてくる。妹の婚約者がカラスと会話できることや、六角精児演じる教授が以前からの知り合いであることなど、現実には起こり得ない要素も盛り込まれているが、それらは“生まれ変わり”という非現実的な核を和らげ、物語に軽やかさと遊び心を与える役割を担っているように思えた。鈴鹿央士と六角精児は、ある意味でこの作品におけるトリックスター的な存在であり、オール阪神・巨人は大阪という舞台に確かなリアリティを与えつつ、虚構と現実の交差点を作り出している。
物語が進むにつれ、涙腺が徐々に緩み、ラストでは機内の客室という場所を忘れるほど、涙をこらえるのに苦労した。
映画を観るときには、物語やセリフだけでなく、その奥にある──詩人、作家、映画人たち、そして関わった多くの人々の想いが折り重なっていることも含めて、じっくり味わってほしいと強く感じた。
ツッコミどころの設定はさて置き、ほっこりの物語
前世の記憶系の映画が苦手
小説は知らず、アマプラでおすすめにでてきたので視聴。
幼い子が前世の記憶があって、それを知りたいという気持ちはわかる。
でもその子との関係を続けようと思う遺族の3人は本当に気持ち悪い。
結婚式まで来て当たり前に親族席に座って、バージンロードまで歩いて、ぞわぞわした。
花まんまを涙ながらに食べているシーンは泣いたけど、この展開になるとは思わなかった。
最後は忘れられる展開ホラーすぎる。。
別の映画の前世の記憶があるやつも嫌いだった。
もう前世の記憶がある系の映画を観るのはやめよう。
お父さん役者さんの、ほんと死ぬ間際のガリガリ骸骨姿と、結婚式当日の姿の変化に一番の賞賛。
全体よりは、終盤のスピーチを観る為の映画に感じた💒
妹の嫁入りで過去を思い返す出だしは、氷河期で脱落した私には、しんどかったです。途中からファンタジー?オカルト?要素が入り、しんどさは少し和らいだものの、この映画面白いかな?と好きにはなれませんでした。このシナリオと分かった上で、キャストさんの演技を観たい人用の映画、終盤のスピーチを観る為の映画に感じました。きょうだいは、ぶつかり合う事も度々あると思いますが、演者含め美しくし過ぎでは無いでしょうか。
事件に巻き込まれて亡くなった女性の記憶が妹に入り込む。 突飛な展開...
ふたりの関西弁に違和感はなく、気持ちよく見れました
故郷、わが綾部市には映画館がない。ただ、見逃した映画を上映から半年くらいして、京都府中丹文化会館で上映してくれる。
過去に何度か見に行ったが、今日は「花まんま」。本作は第133回直木賞を受賞した朱川湊人の小説を、鈴木亮平と有村架純の初共演で映画化したもの。今年4月末の公開だったが見逃した。映画ってたとえば「国宝」とか「鬼滅の刃」とか、よほどの大ヒットでないと、ロングランにはならないので、すぐ上映が終わったしまいますからねえ。
面白かったですよ。主演の鈴木亮平さんは西宮出身、有村架純さんは伊丹出身。舞台が東大阪なので、ふたりの関西弁に違和感はなく、気持ちよく見れました。まあ鈴木亮平は相変わらず大根役者でしたけどね(笑)
近くの席のおばさんはめちゃ泣いてましたね。私も3回くらい泣きました。ギャクもなかなかウエットもきいてるし、関西のノリで、面白かったです。4回くらいは笑いました。
設定がはまんなかった
最後の最後でやられた
結婚式までは、わりと予想通りの展開で、
鈴木亮平さんの名演技もあり、
それでも十分感動ものなのですが、
最後の最後、お見送りのシーンでやられました。
せつなすぎて号泣です。
いい映画でした。ウイカやっぱ演技上手い。
💐ブリザードフラワー💐💐🌺🌸🌼
話のテーマはいいと思う。
ツツジ🌺の園も美しい。
花まんまのお弁当も上手く作ってる、プロの仕業やな。
カラス🐦⬛との日常会話もおもしろい。
近江牛のもてなし羨ましい。
吉本大集合。
兄トシキ役子役は上手いと思うけど、
妹フミ子役の子役がパッとしないな。
鈴木亮平さん、
妹思いな兄をテンション高めに必死に
出してられるけど、
大阪弁やったら新喜劇のノリでいかなあかんって
思ってられるんかな。
いくら母親が仕事し過ぎでも小5の子供に委ねて
動物園に行かさへんやろ。
繁田家と大人の俊也との話で
俊樹が昔=子供の頃、の約束って
大人と対等にというところも腑に落ちなかった。
やっと父と娘でバージンロード‼️で拍手👏、
と思ったけど、
繁田父娘となる。
やはり加藤フミ子はどこ行った、となる。
しかし俊樹がそう仕向けた。
なんか感動せい、感動せい❗️と
終始圧をかけられているような気がして仕方ない。
式後、フミ子が繁田家族をすっかり忘れてしまい、
愕然とする繁田家族と俊樹。
繁田父の酒向芳さんが良かったな。
涙で心の中の汚い物が流れていきました
全440件中、1~20件目を表示