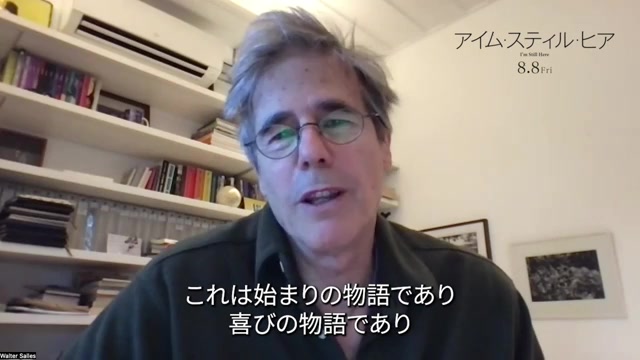「クーデターで政権が代わる国の恐ろしさ」アイム・スティル・ヒア kazzさんの映画レビュー(感想・評価)
クーデターで政権が代わる国の恐ろしさ
まず余談から………✒️
客席の傾斜が緩い劇場では、しばしば前の席の人の頭が邪魔になる。そういう劇場だと分かっていれば、中央よりも少し端に寄った席を選ぶ。
本作を鑑賞した劇場もそうだった。
が、2列前の席の、しかも私の真ん前ではなく3席ほど横にずれた斜め前の席の人が邪魔になるという初めての経験をした。
座高が高く頭が大きい方に限って、背筋を伸ばしてお座りになる傾向がある(いや、確かではない。勝手な思い込み)ので、是非ともご自身の座高を意識して席を選んでいただきたい。
洋画は画面下に字幕が出るのがほとんどなので、運が悪いと字幕が全く読めないという不利益を被る。
今回は割と空いていたので、私はさらに端の席に横移動して難を逃れたが、その御仁の真っ直ぐ後ろの(といっても私と同じ列なので、1列前に空席を挟んだ)席にいた女性は、終始体を右に左にくねらせながら字幕を読んでおられた。お気の毒に。
それにしても、座席の背もたれから両肩が完全に飛び出して、なんなら肩甲骨まで見えたかというほどの座高の高いお姿には驚いたが、2時間強の上映中微動だにされない姿勢の良さにも驚いた…。
以上、余談終了…………✒️
🎬️…………
ブラジルは植民地支配を受けた国の典型で、数奇な運命をたどった国だ。独裁政治、民主左派政権など政情は安定せず、第二次世界大戦を経て軍事クーデターの兆しが芽を出したのは1960年代の初頭のこと。政権を奪取した軍事独裁体制は20年余り続いたというから、ある意味では長期安定政権だったのかもしれない。
この映画は1970年のリオデジャネイロを舞台に幕を開けるので、独裁政権はその歴史の半ばに差しかかろうとしていた時期だろうか。
裸足の子どもたちが路上でサッカー遊びをしていて、独裁国にありがちな国民の貧しさが見て取れるが、主人公の家族は決して貧困家庭ではない。
政権軍部によって拉致、殺害されたルーベンス・パイヴァ。その妻エウニセが独裁政権を相手に戦う姿を息子マルセロが著した回顧録をベースとして描いた物語。
ルーベンス・パイヴァという人は、クーデター前の政権時代に下院議員だったが、政権が倒れて議員の職を追われたらしい。
劇中の会話では、いったん国外に避難していたが、帰国して土木工事業を営んでいたという。
政権当局に監視されるような活動をしていることは、家族は知らされていなかったようだ。
なぜ独裁国家となったブラジルにわざわざ戻ったのかと気になったが、その活動が帰国の目的にあったのかもしれない。
妻エウニセが、夫を取り戻すため、あるいは夫の死を知らされた後も家族を守りながら独裁政権の国家的犯罪を追及するため、飽くなき活動を続ける強さには本当に頭が下がる。
万が一自分が同じ状況に置かれたら、早々に挫けてしまうだろう。
取材の家族写真撮影で「悲しい顔をしたほうがいい」と言われても、みんなが笑顔でカメラに向かう場面に、あの母の強さが子どもたちを明るくさせているのだと感じた。印象深いシーンであり、その本物の写真がエンドロールで映し出されるからより感動的だ。
エウニセ役のフェルナンダ・トーレスの演技は、ヴェネツィア国際映画祭でも、アメリカでも、高く評価された。
エウニセの老年期を演じたフェルナンダ・モンテネグロは彼女の母親だとのこと。母娘で一人の女性を演じたとは…。
蛇足…………
ブラジル映画の邦題を、なぜ英題のカタカナ表記にしたのか。日本語のほうがよかったのでは?