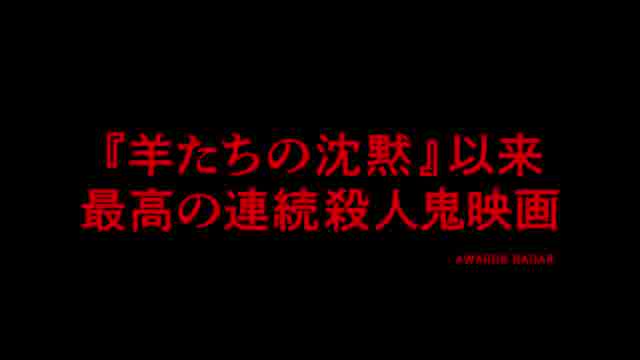「日本では賛否両論の問題作。その理由は…?」ロングレッグス 緋里阿 純さんの映画レビュー(感想・評価)
日本では賛否両論の問題作。その理由は…?
【イントロダクション】
1990年代を舞台に、オレゴン州で起きた複数の殺人事件に関わる犯人を女性FBI捜査官が追う。事件を追うFBI捜査官リー・ハーカーをマイカ・モンローが、事件の犯人“ロングレッグス”をニコラス・ケイジが演じる。監督・脚本はオズ・パーキンス(オズグッド・パーキンス)。
アメリカでは《過去10年全米最高興収ホラー映画》と評され、《(独立系作品として)過去10年全米最高興収ホラー映画》としてスマッシュヒットを記録。
【ストーリー】
1974年、とある白い家に住む幼い少女は、庭に停車された謎の車を確認しに外に出る。ポラロイドカメラを持った少女の前に、白塗り化粧をした不気味な男が現れる。
時は経ち、1990年代(恐らく1994年)。FBI捜査官リー・ハーカーは、とある凶悪犯の確保に乗り出す。リーは持ち前の霊感によって、事前に知らされていた情報とは異なる場所に潜伏していた犯人の居場所を突き止め確保する。
リーのスピリチュアルな能力に疑問を抱きつつ、上司であるカーターは、彼女をオレゴン州で起きた未解決連続殺人事件“ロングレッグス”の捜査官に任命する。
事件に共通するのは、父親が家族を惨殺した後に自殺を図ること。現場には謎の記号を用いた文章が残され、最後に必ず“LONGLEGS(ロングレッグス)”と記されていることだった。
捜査を進める中で、リーは惨殺された家族には、必ず14日が誕生日の9歳の娘が居たことを突き止める。
やがて、一連の事件の裏に隠された犯人の狙いに辿り着いた時、リーの過去に纏わる衝撃の真実が明かされる。
【賛否両論の問題作⁉︎】
オズ・パーキンス監督の、過去の名作群や巨匠に対する敬意と愛情が感じられる点には好感が持てる。また、ジャンルミックス具合の上手さも相まって、かなり楽しめた。賛否で言うならば、明確に“賛”側である。
しかし、日本ではXをはじめ、ここFilmarksでも賛否両論の様子な本作。何故、本作が賛否両論になるのか?理由は、大きく分けて2つあると思う。
1つ目の理由は、“本作にどのような要素を求めるか?”だ。
私は、事前にXで試写会組の反応を目にしていたのだが、概ね一致していたのは、{本作は「ホラー」というより「サスペンス」。また、「オカルト」の要素も含んでいる為、純粋な「サスペンス」を期待しても肩透かしを食らう}というものだった。なので、私は事前に本作がどちらかと言えば「サスペンス」調の作品である点や、「オカルト」の要素も含む作品である点を留意して鑑賞に臨んだ。
実際に鑑賞してみると、なるほど、確かに本作は様々な要素を兼ね備えた作品であり、観る人によってジャンル定義が異なるだろうなと言える。
私としては、本作を強いてジャンル分けするならば、「ホラー・サスペンス」と定義したい。
というのも、本作を過去の名作タイトルを挙げ連ねて表現するならば、『セブン』(1995)と『羊たちの沈黙』(1990)に、『シャイニング』(1980)と『ヘレディタリー/継承』(2018)を足した印象だからだ。そこに、キューブリックの『時計じかけのオレンジ』(1971)を彷彿とさせる赤い画面や、彼が好んだ左右対称の画面構成(厳密に言えば、本作は人物を画面中央に配置して捉える事による、左右対称“風”の絵作り)によって構成されている。
早い話、複数のジャンルに跨った作品であるのだ。
本作に「ホラー」を求めた人は、恐らく本国での評判にある《この10年でいちばん怖い映画》という部分から、ホラー映画としての期待を膨らませた人だろう。また、独立系作品として《過去10年全米最高興収ホラー映画》という謳い文句が、本作のジャンルをホラーとして大雑把に定義してしまった弊害もあると思う。
なので、そうした要素を期待して鑑賞すると、意外にもホラー的側面は弱く(ジャンプスケアはあり)、サスペンスと定義したくなるのだと思う。
2つ目の理由は、“霊感や悪魔崇拝という「オカルト」要素が、一連の殺人事件と密接に関わっているという種明かしを受け入れられるかどうか?”だ。
私自身は、本作を「ホラー・サスペンス」と定義したが、その「サスペンス」の部分に「オカルト」の要素が密接に関わってくるという点を、どの程度まで許容出来るかで、本作の受け止め方が変わってくるように思う。
本作の犯人“ロングレッグス”ことダル・コブルは、悪魔崇拝者の人形技師という設定。「階下の男」ことサタンを盲信するあまり、人形に自らの一部を宿した“黒魔術”を用い、悪魔憑きの人形を作成する。それを共犯者であるルスがシスターのフリをしてターゲットの自宅へ届け、人形に宿った悪魔が家の主人を操って凶行に走らせるというものだった。
殺人事件の動機やトリックに、論理的・現実的な仕掛けではない超常的な力が関与しているという点が、観る人によっては納得がいかず、拒否反応を示させるのだと思う。
また、真相が“悪魔崇拝”という日本人に馴染みの薄いものなのも、作品との距離感を生む要因だろう。日本では無宗教が大多数を占める為、神や悪魔という存在に対して関心が薄い(神頼みは頻繁にするが)し、悪魔崇拝なんてしようものなら“中二病”と嘲笑われるくらいだ。だから、それに対して恐怖感を抱くというのは難しい。
しかし、何故本作が本国アメリカで「ホラー映画」として評価されたのかは、納得する部分がある。それは、先に挙げた『ヘレディタリー』に対する評価にも関係している。『ヘレディタリー』もまた、悪魔崇拝を取り扱った作品であり、それに対する評価は《直近50年のホラー映画の中の最高傑作》《21世紀最高のホラー映画》という大絶賛ぶりだった。近年は若者を中心に信仰心が薄れているそうだが、それでもキリスト教が人々に深く根付いているアメリカにおいては、悪魔崇拝やそれに関連した殺人事件は、リアルな恐怖に他ならないのだろう。
そういった意味では、本作は間違いなく「ホラー」なのだ。
【感想】
演じたニコラス・ケイジ自身が、「このような役を演じる事は2度とないだろう」と語るほど、ロングレッグスのキャラクターは強烈。
長い白髪に白化粧という不気味な風貌、悪魔崇拝者の人形技師で、精巧な人形に悪魔を取り憑かせるという設定は非常に魅力的だった。「クー、クー」や「ようやく会えたね。天使ちゃん」という台詞含めて、ニコラス・ケイジ史上最も“気持ち悪い(キモキモ気持ち悪い!)”キャラクターだった。あんな邪悪な「ハッピーバースデー トゥー ユー」があるだろうか?
とはいえ、演技自体は割とニコラス・ケイジまんまだし、どう見ても演じるのを楽しんでいたように見える(製作も務めている)ので、これからもこういったピーキーな役は積極的にやっていただきたい。
余談だが、そのビジュアルが何処となく『ルパンVS複製人間』(1978)のマモーを彷彿としたのは私だけだろうか?(笑)
リー役のマイカ・モンローは、私としてはNetflixの『TAU/タウ』(2018)で主演を務めていた点から、スリラーやサスペンス系作品と親和性の高い女優なのかと思った。
本作ではポニーテールに白のブラウス姿が印象的で、自身を取り巻く事件に翻弄されつつ真相に迫っていく姿が美しいと同時にキュートだった。ホラーにおける“最悪の事態に巻き込まれる美女”を体現しておりグッド。
また、彼女はロングレッグスとの取り調べ室のシーンで、ニコラス・ケイジのメイク姿を知らされていなかったそうで、あのシーンにおける彼女の怯えっぷりはガチなのだそう。
リーの霊感の方について、どう説明を付けるべきか。長らく自身を模した人形に悪魔が宿っていたのならば、それにより悪魔と霊的なパスが繋がって、透視や超直感を獲得もしくは目覚めたと捉える事が出来そうではあるが。
暗号解読のシーンは、自身の超直感による解読なのは分かるが、どういうロジックで組まれた暗号なのか程度は、我々観客にも示してほしかった。
クライマックスで事件を終わらせる為に母親を射殺するというのは、悪魔からしてみれば最大の堕落行為に他ならないのだろう。だとすると、本作のラストはバッドエンドとも言える。
ルスが人形を破壊したにも拘らず、ルビーを連れて逃げる際に悪魔の囁き声が聞こえた点を考えると、彼女はまだ悪魔の掌の上なのかもしれない。
ロングレッグスの共犯者として描かれたルスについては、子供を守りたいが故に悪魔に魂を売るという背景には納得が行くし、犯行を重ねる中で次第に箍が外れ、返り血を浴びて狂気に飲まれていく姿も良かった。父親不在のシングルマザーがシスターに扮して犯行に加担するという点は、父の影が全くないという点で処女懐妊を成した(一説には、翻訳の際の誤訳だとも言われている)という聖母マリアが悪魔の手によって堕落させられたかのようにも見える。しかし、そう見せる意味でも、またラストで母を射殺する悲痛さを出す意味でも、ルスとリーの親子関係にはもっとドラマ性が必要であったはずだ。
本作を語る上で外せないのが、画面構成の素晴らしさだ。
スタンリー・キューブリックを彷彿とさせるオープニングの赤い画面や左右対称風のショットは勿論、基本的に全編薄暗い画面、リーの一人暮らしの自宅でのオレンジ掛かった色調やオープニングでのサブリミナル演出まで、とにかく画作りに対する拘りが随所に感じられる。また、正方形の画面で描かれる過去回想もオシャレ。
リーが事件を捜査するため赤いカーペットの上で資料を広げる姿、ロングレッグスとの対面で怯える姿。ルスが幼いリーを模した人形をショットガンで破壊した際に人形の頭部から立ち込める黒いもや。グラフィックデザイナーの大島依提亜氏によるオルタナティヴ・ポスターのデザインにも採用されている血塗れのマリア像かのようなルスの姿。作中のあらゆるショットもバチバチにキマっている。
wikiによると、本作の製作費は約1,000万ドルと低予算らしいが、こうした画面構成や印象的なショットを用いるといった演出面の創意工夫は、安っぽさを一切感じさせない重厚感と不気味な威圧感があり見事。
全編に漂う不穏な空気と、それを盛り上げる音楽も高評価。「雰囲気だけ」と言ってしまえばそれまでなのだが、その雰囲気が個人的に抜群に好みだった。
事件の真相に関しては、事前にオカルトの要素があると知っていたので、特別拒否感を抱く事は無かった。また、私自身が悪魔崇拝はともかくオカルトという分野に興味関心が深い(あまり信じてはいない)事も、本作を好意的に受け止められた要因だろう。人形を用いるという不気味さは非常に好みだし、読んで字の如く「人の形をしているもの」には色々な“念”が宿ると言うので、それが悪魔であっても「まぁ、宿るかもね」と不思議と納得は行った。また、“追ってきた犯人が、実は実家の地下室でずっと共同生活を送っていた”という種明かしは実に恐ろしい。ただ、それ自体を割と軽く処理されてしまったのは残念だった。あの空間だけでも、リーの霊感を通して色々な過去が見えそうなものだろうに。
エンディングでT.Rexの『Bang A Gong(Get It On)』に乗せて、真っ赤な文字のスタッフロールが上から下へと流れて行く演出も粋。ラストのロングレッグスの「サタン万歳」という台詞を思うと、「全員地獄に堕としてやる」という邪悪さが感じられる。まさか、T.Rexのこの曲にこんな邪悪さを感じる日が来るとは。
【総評】
過去の名作の要素や巨匠の手法を貪欲に取り入れつつ、何処か懐かしさも感じさせる。不足している部分はありつつも、1級のサスペンスに仕上がっていた。キャスト陣の熱演や演出の工夫にも拍手を送りたい。
9月に公開が決定した、同監督によるスティーヴン・キング原作の『ザ・モンキー』を心待ちにしたい。
余談だが、本作の趣向を凝らした捜査資料風パンフレット(1,300円)が売り切れにより手に入らなかったのが残念でならない…。