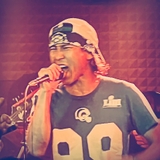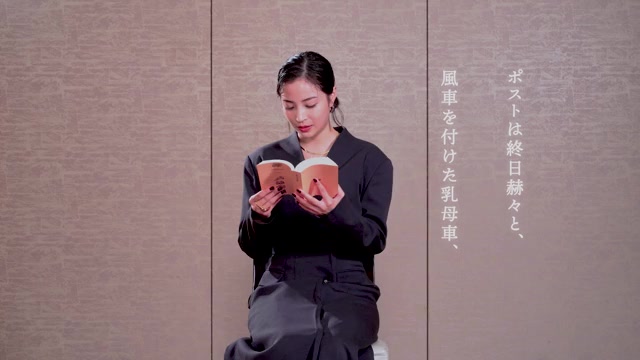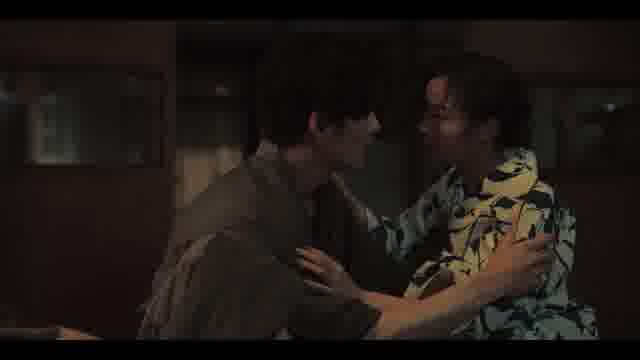ゆきてかへらぬのレビュー・感想・評価
全30件中、1~20件目を表示
天才・中原中也を捨てた女。
大正時代の京都と東京を舞台に、実在した女優・長谷川泰子と詩人・中原中也、文芸評論家・小林秀雄という男女3人の愛と青春を描いたドラマ。
端役の女優をしていた長谷川泰子が出会ったのが年下の学生詩人・中原中也。
後の世では「天才詩人」とも称される青年と出会い、恋仲になる。
やがて二人は京都から東京へ。
二人で同棲する生活を始めるも、やがて中也の強烈な個性は泰子の精神を蝕んでいく。
そんな中で泰子が知り合ったのが、中也の友人の評論家の小林秀雄。
この女一人を挟んだ男二人との奇妙な関係が幕を開ける。
やがて泰子は中也への腹いせか、もしくは逃避か、家を出て今度は小林と同棲を始める。
しかも、小林の家と中也の家は近所で三人はそれ以降も度々逢瀬を重ねることになる。
不可思議な「三角関係」だったのだ。
泰子は小林と同棲しても心休まらず、却って精神に異常をきたしていく。
小林との蜜月も共倒れを恐れた小林が逃避して終わりを告げた。
しかし、そこで三者の縁が切れたのではなく、その後も連絡は取りあうなどしていた模様。
やがて中也には結婚話が持ち上がる。お相手は実家の紹介らしいが、お嬢様で自分とは全然違う。
後に中也と再会した際に彼は子供が夫人との間に生まれていたが、既に病重篤で余命いくばくも無かった。
小林から中也の死を知らされたのはそれから程ない頃。
葬儀にも参列した。やはり彼には何かしらの想いが残っていたのだろう。
その後の彼女は史実では金持ちと結婚して戦前までは贅沢な暮らしをしたものの、戦後は一転して夫の事業が傾いて、晩年は職を転々として神奈川や東京に住んでいた模様。
亡くなったのは何と平成5年で88歳であった。
職業は本来は「女優」のはずで、残された写真からも美人であることは間違いなかったのだが、主演映画は生涯を通して1本しかない。むしろ「中原中也を捨てた女」として世に名を遺した。
晩年、自ら中也との関係を回想して本も出されている。中也ファンには重要な人物であることは間違いないようである。
女と男と男、分からぬ関係
この令和の時代にまで根岸吉太郎監督&田中陽造脚本コンビの新作が見られるとは…!
田中陽造は『最後の忠臣蔵』以来15年ぶり、根岸監督は『ヴィヨンの妻 桜桃とタンポポ』以来16年ぶり。それだけでめっけもんである。
田中陽造が40年以上も前に書いたというオリジナル脚本。何度も映像化の企画はあったらしいが、実現に至らず。やり残した事を名タッグでやっと日の目を見る事が出来、安堵と本望だろう。
年齢的に見ても最後になるかもしれない本作は…
大正時代。駆け出しの女優・長谷川泰子、詩人・中原中也、文芸評論家・小林秀雄。実在した3人の実際にあった奇妙な三角関係の模様を描く。
久々とも言える文芸映画の香り。
映像美は特筆もの。登場人物たちの心情に寄り添ったようなカメラワークも流麗。
こだわりの大正美術や衣装。
泰子と中也が東京に来た時の街並みや路面電車の再現には感嘆させられた。
旧きと近代が入り交じった大正特有の雰囲気に酔う。
映像美、様式美は今年の日本映画屈指だろう。
大正時代に影も形も無かった今の時代の若い3人が、大正時代に生きる若者たちの愛や息遣いを体現。
今年映画やドラマに出演作が相次いだ広瀬すずはつまり、昭和・平成・令和に生きる女性をそれぞれ演じた訳だが、もう一昔遡って大正女性まで。一年の内に4つの時代の女性を演じるのもなかなか無い体験だろうが、さすがの巧みの演じ分け。今年演じた中で最も洗練された大人の女性役だが、同時に女優としての気品、気の強さ、一人の女としてのわがままさ、愛を欲する儚さ、哀しさ、脆さ…。ほんのり色気も滲ませ、難しい役所を演じ切っている。単体でもいいが、今年見せた様々な演技、魅力、顔…。年末、何か一つでも主演女優賞を!
アニメ映画『きみの色』はあったが、木戸大聖の映画やドラマを含めて演技を見るのは個人的に初めてかもしれない。ちと拙さはあるが、その時によって見せる子供っぽさ、大人になったばかりの男、詩人としての顔…。フレッシュに魅せてくれている。
それに対し、岡田将生は落ち着いた大人の男の魅力を魅せる。
ほとんど3人芝居。大正人間と令和時代の役者、若さと演技と魅力のケミストリー。
名匠と名脚本家の久しいタッグ、演者の好演、大正文芸やこの題材…。キネ旬ではベストテン入りする事だろう。
しかしそれは、あくまで批評家目線。興行収入の結果を例に出したくはないが、一般観客から見れば…。
見るべきものは多いが、なかなかに取っ付き難い…。
大正時代に造詣があるとか、3人の関係を知っているとか、中原中也信奉者でもない限り、興味や関心は引かれないだろう。私も中原中也は名前を聞いた事があるくらい。
話や登場人物たちの心情も分かり難い。
惹かれ合う泰子と中也。ここに秀雄が加わり、友人関係の中也と秀雄に泰子は疎外感を感じる。
秀雄は泰子に想いを。衝突多くなった中也に見切りを付け、安らぎを求めて泰子は秀雄の元へ。
未練引き摺る中也。尽くす秀雄。秀雄の元に身を寄せながらも、中也の事を引き摺る泰子。
好いて、別れて。新しい相手と共にしながらも、まだ前の男を引き摺る。
お互い不満や嫌な所を口にし、会えばまた衝突しながら、2人で時には3人で会う。
苦悩や発狂するほど相手を愛しているのだろうが、それが自身の求める安らぎや愛なのか、激情に身を任せたいのか。
恋人?愛人?浮気?三位一体? この3人にしか分からない関係性。
どうしようもなく3人各々、心と心で繋がっている。
3人各々、つっかえ棒のように支え合っているが、ちょっとした事で崩れる危うさ。
あまりにも特異な関係性。そもそも理解するのが無理な話。
中也の置時計の鐘の音に発狂する泰子。中也の異常な執着心。これって、メンヘラ男女の話?…とも思う。
タイトルは色々推測出来るが、3人各々の自分の気持ち、相手への思いと読み取ったつもり。
あなた/君は私/僕の元へ来た。そして去り、帰って来なかった。
男女の関係は単純なものばかりではない。
時には交錯し、歪み、それでいて激しい。忘れられぬ一生のもの。
でもやっぱり分からない。
そんな大人の男女の世界を覗いた気がする。
とにかく絡みのシーンはいらない
誰が何を期待しているのか、よくわからないが、絡みのシーンは特に必要ないように思われる。無駄な絡みのシーンがある映画は、もうそれだけで、本編に入り込めない。なので、基本的に評価を下げる。最近の作品ならなおさら。
愛と孤独
傑作です。映画館で鑑賞できなかったのが惜しいです。広瀬すずさんのお芝居を見るといつも感じるのは、向かってくる時は鋭利なのに、こちらに届く頃にはなぜか痛くない。不思議なものでしっくりきます。
広瀬さんが近年演じる作品のキャラクターは、どれも同じではないけど、近しいものを感じます。
気高いようでいて、その芯は脆い。何も抱えていない人などいないけれど、目に見えないだけで抱えているものの重さに心が負けてしまう。
強く見せようと見栄をはるが、外側に貼り付けたそれが剥がれ落ちるのは早い。
この作品で演じた役柄は実在の人物ですが、おそらく広瀬さんでなくては、長谷川泰子という女性を演じられなかったでしょう。
みんな不格好ですね。欲しいと思う時は金銀財宝のように光り輝いて見えていて、手に入ったものが「がらくた」だと感じた瞬間、唇から零れるのは「がらくた」に対する愚痴。
三者三様、本音と建前の建前が崩れる瞬間が何度も垣間見えました。
結局小林は泰子を愛しているというよりも、泰子というフィルターを通して中原を見ようとしていたし、泰子は小林のところに行くと決めたのは自分だと口では言いながら、その言葉の奥には中原への執着とも呼べる未練が見える。
中原も泰子に見せつけるようにわざと彼女をヒステリーに陥らせるような言動をとる。
誰しもはじめから罅があって、各々の境遇によっていずれ来たる形あるものの終わりを待っている。彼女の場合特に、思っていたより呆気なくその時を迎えたということなのかもしれません。
滑稽にも見えるが、なぜかそれを美しく思わせてしまう女性と、それに翻弄される男性達の姿は、欲望に忠実で生々しく、そして人間味に溢れている。
愛に飢え、それによって生み出された歪みに飲み込まれ、人間をこんなにも狂わせてしまう。
僕の目には、この人を愛している、という彼女自身が起こす錯覚と、本当は誰かに止めどない乾きを癒してほしくて縋るしかない彼女の孤独が映った。
作品に投影された彼女のラストは、中原の死と共に、漸くの決別と、本当の愛に辿り着いたような気がした。
彼女の「さよなら」はどこまでも美しかった。
この映画の硬質さに関して‥
(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)
(レビューが溜まっていたので短く)
基本的には、今作の映画『ゆきてかへらぬ』を面白く観ました。
特に美術をはじめ、画面の美しさは観るべき素晴らしさがあったと思われます。
しかしながら、映画全体を覆う硬質さに関して、個人的には人物の本心に迫り切っていないのが理由のように、一方では思われました。
主人公・長谷川泰子(広瀬すずさん)は、母が父に裏切られ、自身ともども母が入水自殺しようとしたとの話をします。
中原中也(木戸大聖さん)は、風車をつけた乳母車の赤ん坊は自分自身だとの話をします。
それぞれ主人公・長谷川泰子も、中原中也も、幼少期に負った心の傷によって、互いに内面の空虚さを持っている事が伝わる場面でもありました。
しかしながら一方で、今作はそれ以上に踏み込んで、主人公・長谷川泰子や中原中也の心情の理由が解明されて描かれていないように思われました。
主人公・長谷川泰子と中原中也は、内面の本心を吐露する代わりに、表面で強がっていて、主人公・長谷川泰子は精神的におかしくなり、中原中也は若くして病気で亡くなることになります。
しかし長谷川泰子も中原中也も、内面を解明的に映画で描かれていないので、観客は本当の意味で2人の心情を理解出来ず、感情移入し辛い描き方になっていると思われました。
これが映画が硬質に感じた要因だと思われました。
おそらく今作の根岸吉太郎 監督は、主人公・長谷川泰子と中原中也が、なぜこのような振る舞いをしていたのか、深く捕まえることなく今作を描いてしまったのではないかと、僭越思われました。
初めに触れた美術や画面の充実した素晴らしさ、そして主人公・長谷川泰子を演じた広瀬すずさん、中原中也を演じた木戸大聖さん、小林秀雄を演じた岡田将生さんを含めて俳優陣の素晴らしさはあったと思われます。
それだけに、惜しい作品になっていると僭越思われ、今回の点数となりました。
歪な愛情
大正時代に出逢う女性と2人の男性。
それぞれの想いが交錯し歪な愛情の中で、愛することを模索する。
出逢いなく始まり、それぞれが本心を隠したまま進む恋愛模様が淡々と進む。
盛り上がりも薄く感じられ、それぞれが愛してたことは解るのだが今ひとつ心に届くものを感じられなかった。
好みもあるのだろうけど。
根岸吉太郎の前作より面白かったし、好きな作品だけど…
久々の根岸吉太郎監督作品。
シナリオが田中陽造で、「知る人ぞ知る」幻の傑作だったとか。確かに短編小説ようなキレがあり面白い。
時代は、大正〜昭和の初期までを描いている。美術セットもかなり凝っている。CGなどVFXを駆使して大正〜昭和の時代の風景を情感豊かに作り出している。(新宿駅から屋外に出てくるシーンはワンカットで撮っているし、京都の下宿先の建物群のセットも目を見張る!)
今回、カメラがよかった。特に異常に被写界深度を浅くして人物にフォーカスを合わせ、周囲がボケる撮り方が今回の濃密な人間関係に合っていたし、さまざまな場面での色調の変化も美しく暗示的。
などなど映像は素晴らしく、飽きない。
広瀬すずが長谷川泰子、木戸大聖が中原中也、岡田将生が小林秀雄で、この三角関係の演技陣の絡みも見応えがあるが…。
全体的にとても上手く上品で、楽しませてくれるしセンスもある。見ながら飽きない。でも…。何か物足りない。
多分、突き抜けたものがない。
広瀬すずは熱演で、申し分ないけど、やはり男女の絡みのシーンでは、演出に遠慮がある。何も広瀬すずの裸体を見たいわけではないけど(見たいけど)、ちょっと踏み込みが足りなかった。その分嘘くさく見えた。いくら神経がやられている芝居を見せても…
最初の下宿屋のシーンやローラスケート場、ダンスホールのシーン。母娘で入水するシーンなど見応えのあるシーンが数多くあり、見ている分にはとても楽しめる。でも見終わった後、思ったより残らない。
何かが足りない…。真剣さ?リアルさ??
根岸吉太郎の前作より面白かったし、好きな作品だけど…。
<3月29日追記>
エンドロールの「主題歌」はこの映画に合わなかった。なぜ岩城太郎の音楽だけで終わらせなかったのだろう。大人の事情?
疲れた身体に悪い意味で効く映画
期待半分不安半分で観に行きました。
予告編でかなりヤバそうと考えていたけれど、結局、悪い予感が当たりました。
中原中也を演じた木戸大聖さんが酷過ぎたかも。
主役の広瀬すずさんはいつもの感じだけど、やっぱり同じような演技しか出来ないのね、という印象。
岡田将生さんの演技は、悪くなかった。
中原中也の作風についてはよく知らないです。
映画は、大正浪漫的な雰囲気を何かそれっぽく映画で見せようとしていることで、結果として、ものスゴく安っぽい映画になっている感じがしました。
おカネ返して!と叫んで立ち上がるほどの怒りはないけれど、疲れた身体に悪い意味で効く映画でした。
大正ロマネスク‼️
大正時代の京都と東京を舞台にした、女優と詩人、文芸評論家の三人の男女の三角関係を描いた大正ロマネスク作品‼️作品としては、森田芳光監督の「それから」みたいな作品かなと思ったら、大正時代を舞台にした、トリュフォー監督の「突然炎のごとく」だと感じました‼️16年ぶりにメガホンを取った根岸監督が、男女三人のまるでつっかえ棒で支え合っているかのようなもろい恋愛関係を、レトロに描いてます‼️大正時代の京都や東京の街並みの再現も完璧だし、衣装や風俗も同じく、色を抑えた映像も大正時代っぽいし、そしてすずちゃんや岡田将生の演技もちゃんと大正してる‼️ただ中原中也役の木戸大聖の演技が思いっきり令和で、違和感ありまくりでした‼️
入り込めるか、込めないか。評価は変わる。
美術、照明、衣装、メイクアップ、全てのスタッフを絶賛したい。
全編美しい❗
中也と泰子が暮らし始めた京都の路地、
雨に濡れる黒瓦、俯瞰に流れる朱の傘、白く積りゆく雪、風に流れる桜。
部屋の調度品、窓ガラス、食器に至るまで
細部にまで神経を研ぎ澄ませた根岸監督の作品に魅せられた。
星5はこの映像美に捧げたい。
物語にはなぜか入り込めなかった。
恐れなく言ってしまえば、現実味のない芝居に退屈してしまった。
広瀬すずの全力演技をしても、ヒリヒリとした軋みが伝わってこない。
中原中也という詩人の魂も、小林秀雄の裏切りの痛みも。
ふと、気がついた。
コレはこの映画は、原作ゆきてかえらぬは、2人の男に揺れた長谷川泰子の口述筆記による著作を原作にした、長谷川泰子の視点で描かれた映画であると。
彼女にとっては、後の天才詩人も(17才の傲慢と繊細にゆれるセンチメンタルで世間知らずな)一人の若者であり、後の大評論家も(頭でっかちで理性を重んじる)窮屈な大人であるのかもしれない。
広瀬すずの渾身演技に胸打たれたのは映画後半、中也が亡くなったと知った後に、その死に慟哭し、中也のくるりと折り畳んだ赤い手袋を(彼の心臓として)唇に寄せ食べようとする無言の数分のシ−ンだった。
求めるものによって、この映画の評価は変わるのかもしれない。
3人の演技がよかったです!
出演者でちょっと気になってたので鑑賞!
京都。
まだ芽の出ない女優、長谷川泰子は、まだ学生だった中原中也と出逢った。20歳の泰子と17歳の中也。どこか虚勢を張るふたりは、互いに惹かれ、一緒に暮らしはじめる。価値観は違う。けれども、相手を尊重できる気っ風のよさが共通していた。
東京。
泰子と中也が引っ越した家を、小林秀雄がふいに訪れる。中也の詩人としての才能を誰よりも知る男。そして、中也も評論の達人である小林に一目置かれることを誇りに思っていた。男たちの仲睦まじい様子を目の当たりにして、泰子は複雑な気持ちになる。才気あふれるクリエイターたちにどこか置いてけぼりにされたようなさみしさ。
しかし、泰子と出逢ってしまった小林もまた彼女の魅力に気づく。本物を求める評論家は新進女優にも本物を見出した。そうして、複雑でシンプルな関係がはじまる。重ならないベクトル、刹那のすれ違い。ひとりの女が、ふたりの男に愛されること。それはアーティストたちの青春でもあった。
というのがあらすじ!
個人的にはちょっとよくわからない難しい印象でした…
最初は見逃した?って思うぐらい一気に同棲までいってそして東京に出た感じ…笑
そして中原中也と長谷川泰子と小林秀雄の三角関係は理解しにくい…
途中は掴み合いの喧嘩とかしてたけど迫力がすごかったですね!
ナミビアの砂漠をちょっと思い出しました笑
3人ともちょっとめんどくさい人たちだなーという感じ笑
有名な3人の実話の話を元にした話らしくそこを知ってる人はかなり楽しめる作品なんだろうなと思います
私は全く知らない人たちだったので調べていればもう少し楽しめたかなと思います…
でも3人の演技が素晴らしかったですし大正や昭和初期が好きなので楽しめました!
あと広瀬すずさんが美しかったですし衣装もお綺麗でしたね!
いい映画をありがとうございました😊
岡田将生はさすが!広瀬すずも頑張っていた、中原役の演技が
岡田将生さんが好きなので広瀬すずだし、これはなかなか良い作品なんじゃないかと思って見てみましたが中原役の人の演技があまりに学芸会すぎて「これは見て失敗した〜」と序盤からだいぶ萎えました。はっきりいって主演を張るにはこの人ではだいぶ力不足です。
事務所がゴリ押しで金積んだのでしょうか?笑
ま、見ていくうちにこの人の演技も見るのに慣れてはいきましたが。しかもアイドルかと思いきや肩書きが俳優のトライストーンの方みたいなので事務所の先輩である綾野剛を見習ってもっと演技力を頑張ってほしいです。
広瀬すずは頑張っていたなと思います。広瀬すずはただのアイドル女優かと思いきや最近の彼女は良い演技する女優になってきたと感じます。
今作では特に神経症でイカれてきたとこや、中原との取っ組み合いのシーン、時計を聞いて泣くとことその後に破壊するとこは大爆笑しちゃいました!
ただ、この作品でのこの女性像は何というかエロティックで色気あるような女性として映したいように私は解釈しましたが、広瀬すずではその女性像を映し出すための色気が足りないなーと思います。
これは年齢的にもまだ若いしこれから歳を重ねてそういった色気的な魅力をつけていくのかなとは思いますが、この点で言うと広瀬すずに合ってない役柄だな〜と思いました。なんていうか演技はうまいが幼すぎるように見えました。
倉科カナとかがやったらめっちゃ色気ムンムンにやれたのかな?と、最近のブレイクしてる人でなら松本若菜あたりでもいいかなとか思ったり。
岡田将生さんはさすがでした、途中一瞬だけ金を貸してくれってとこのシーンで出てくるおじさん、あの人と岡田さんとの掛け合いのシーンが一番見ててしっくりきて安心して見れるシーンだったなと思いました。
内容的には奇妙な三角関係を描いた、なんというかぶっとんだ作品です。
昨年公開された「雨の中の慾情」に少し通じる世界観もありました。
こういう作品は演技力の爆発さをいかに魅せれるかが大事かと思うのですが、やはりその点でいうと中原役がとんでもない素人演技なので見てて恥ずかしくなりました。
せっかく岡田将生さんが出てるのにだいぶ駄作で岡田将生の無駄遣いだなと思いました。
ユーモア
キャストは豪華なのに全然話題になってないな…と不思議になりながらの鑑賞でしたが、あーこれはヒット難しいわと納得させられる感じのマニアックな作品でした。
モデル元の登場人物は名前聞いた事あるかな?くらいの認識なのでほぼほぼ初見です。
ほぼほぼ登場人物3人でのやっかみ合いがメインですが、そのやり取りが中々に狂気に満ちていて本来なら大好物なはずなんですが、現代でいう厨二病チックなところが強すぎて引きながらの鑑賞になりました。
ちょい捻くれ文学学生な中原中也と転がり込んできた役者見習いお姉さんの長谷川泰子、数年後に編集者として2人と携わる小林秀雄の3人芝居ですが、これだけで2時間オーバーの時間を持たせてる、なんならもっと尺伸ばして深掘りすればより良かったのでは?となるのが惜しいところでした。
序盤のちょい粗いお姉さんだったのがマシだったのかと思うぐらい泰子のメンヘラっぷりが加速していくんですが、それまでの背景が濃く描かれていないために、精神病でおかしくなってると言われても、事細かいところまで他人に指示させるところからの大女優への昇格までの繋がりがうまいこと見出せずで頭の中クエスチョンマークだらけでした。
終盤の哀愁漂う感じは好みだったので、良い部分悪い部分が観る人によって分かれるんだろうなぁとはなりました。
多分敢えてだとは思うんですが、台詞回しがわざとらしいのが序盤から中盤にかけてくどくなってしまっており、一瞬持ち直したと思ったらやっぱりくどくなったりと胃もたれしてしまいました。
大正時代のリアルと演劇っぽさが噛み合わさった結果、イマイチ世界観にのめり込めないのがずっとノイズになっていました。
濡れ場らしい濡れ場が2回あるんですが、全年齢対象の時点で期待せずでしたが脱いでも映るのは背中のみだったり、後ろ姿が多くて本当にすずちゃんがやってるのか?と疑って観てしまうところが多く、そこがエロティックならもっと時代とか関係性とかにハマれたのかなと思うとキャスティングからミスってたのでは?となってしまうのが残念でした。
木戸くんは「先生!口裂け女です!」で初めて出会って、去年の「きみの色」でドカンと興味を持っていたので、木戸くん目当てで今作を観たといっても過言ではないんですが、その2作に比べて演技が拙い…?となってしまいました。
台詞回しが独特なのはあるんですが、すずちゃんと岡田くんと並ぶとどうしても幼さが出てしまってバランスが悪くなってしまっていてモヤモヤしっぱなしでした。
ただ晩年の中也の燻っている感じはとても好きでした。
岡田くんが出ると画面がキュッと引き締まるのもあり、安心安全安定してくれて肩の荷が降りたのもこれまた事実です。
大正時代を感じさせるセットや背景だったりはとても良かったですし、止まったところを切り取ったようなカットは綺麗でした。
地味に気になったのが上から下へ、下から上へ動くカメラワークの時にプルプル震えていたところだけは固定じゃないんだ…となりました。
今年に入ってから気になってる事なんですが、大作で主演を張ってる役者陣が大衆ウケではない作品に出た時にガクッと興行収入が下がる現象が2ヶ月で連発してるんですけど、洋画離れに近いものがあるのかな?と勘繰ってしまったり。
2時間タイムスリップした感覚は確かにあったので、それだけは儲けもんかなと思いました。
鑑賞日 2/25
鑑賞時間 16:05〜18:25
座席 L-13
三人三様に切なく、美しい
中学生の頃に中原中也、長谷川泰子、小林秀雄の関係を知り、興味津々。逗子に住んでいたので、隣の鎌倉にいたことに親しみを感じ、映画になったのが意外に遅かったと思いました。
レビュー評価はそんなに高くなかったので様子見でしたが、良かったです。特に中原中也。木戸大聖の清潔感が、退廃的、暗くなりがちな話を救っていました。
文人たちよりも泰子の方が神経症で世話を焼かせていたなんて面白い。確かにそうだったかもしれない。
自分の元を去る彼女の身の周り品を運んであげて。小林と泰子の部屋に柱時計を贈り、自分も同じ柱時計の音を部屋で聞く中也。それに泰子は錯乱するのだが、何だかかわいい。今だったらお揃いのスマホか。
17歳の学生の身分で泰子をフランス料理のレストランに誘い、贅沢ねと言われた中也は、自分にとっての贅沢は詩なのだと語る。印象的なシーンでした。
大正時代の家、TOBACOOSの看板、ダンスホール、メリーゴーランド、無声映画、舟遊び。美しい映像と恐ろしい結核の対比。宮沢賢治や石川啄木も同じ死因だったと思うと、なんてもったいないことか。
彼らの青春の時の流れが切なく、生きた時代も切ない。でも中原中也は有言実行。短い人生でちゃんと後世に残る詩を書き、親孝行した。残され、長生きした2人には死ぬまで忘れえぬ人だったろう。まさに天使のような詩人だ。
シナプス
泰子を中心とした3人の、独特な愛憎を描いた作品。
彼らの職業もあってか理解も共感もできないが、それを求める作品でもないとは思う。
中原中也が出る割に創作の方には話がいかず、惚れた腫れたに終始している。
それで成り立つのは、恋愛や友情だけでは語りきれない、言葉にできぬほど複雑な内面が描かれているから。
神経症になった泰子は傍から見るとちょっとコミカルで、白磁の壺を投げたシーンなどで少し笑った。
役柄的に広瀬すずは色気が足りないのだけど、低く掠れた声音や重くした瞼で標準以上に仕上げていてサスガ。
20歳から始まることも考えれば、最終的にあれで正解にも感じられたほど。
岡田将生の落ち着いた芝居は全体を下支えしていた。
気になるのは役者ごとに醸す“時代感”がバラバラな点。
特に木戸大聖は突出して今っぽすぎて、マントやハットもコスプレにしか見えないのは残念。
その代わり、建物や調度品の雰囲気はバッチリだった。
正直観終わって残るものがあるわけではないけど、いくつかの価値観を覗く意味では興味深い。
それは上で少し下げた木戸大聖含め、実在感を持たせた役者の力だろう。
ただ、重さや厚みを出すまでには未だ及ばず。
『敵』で「フランス文学よりフランス書院」と宣ってたカトウシンスケが仏文学者の辰野隆役で、偶然ながら爆笑。
ボールルームでのダンスシーンも素敵でした。
愛は平和のなかになかった
17歳の少年が煙草を吸い、酒を飲み、女郎を買い、年上の女性と同棲する。
およそ現在では考えれない、ポリティカルコレクトネスから外れた物語だ。
中原中也は医者の息子で親の金で放蕩するのだが、そのような文学史など知らなくても中原自身の金でなく生活しているのは明らかだ。
中原に、そのことに対する後ろめたさなどない。
泰子の女優業で稼いだなけなしの金をその場で借り、「今からこの金で女郎を買いにいく」とうそぶく。
泰子は、世間の側にいる小林の経済と「まともさ」に寄りかかりながら、ダメンズの中原を小林よりも、より深い部分で愛さずにいられない。
小林は小林で本当に愛しているのは中原の天才性であり、泰子は中原に至る媒介に過ぎない。
泰子をただ肉欲のままに愛することができずにいることの倒錯がもどかしく美しい。
盗られた女と盗った男のもとに足しげく通う中原。
時計を贈って、その時計の時報を同じ時刻に中原が聞いているとわかりながら、泰子は、その時計を自分では壊すことが出来ない。
泰子は小林に時計を壊させるが、その壊した時計の上に、泰子は、小林の審美眼の象徴である朝鮮白磁を叩きつける。
全編、美しい画像と台詞に余計なことを考えずに浸っていられる最近では珍しい映画かもしれない。
中原中也の天才性に恥ずかしくない台詞を生み出すのは大変だったろうと推察する。
広瀬すずのすこし時代がかった大仰なセリフ回しが心地よかった。
まるきり、不幸の物語であるにも関わらず、大正の耽美に私たちは酔いしれてしまう。
「二人の不幸は終わったのよ」
の台詞が間をあけて二回繰り返される。
まるで不幸をいとおしむように。
もう病気だ。
よい!
トータス松本、柄本佑、草刈民代はワンカットのみの出演。
それでも画面に残りたいと思ったのだろう。
その価値はあったと思う。
中原中也に興味があるかどうか
中原中也に全く興味ないけど、なんとなく良さそうなので視聴。
まず、自分はサイコパスな主要登場人物が苦手なので、中原も長谷川も苦手でした。なので☆2です。
中原と長谷川の出会いのシーンだけが謎過ぎましたが、あとは三角関係としてはありかなと。ただし、中原中也に興味がない人がこの三角関係に興味が持てるかどうかは微妙です。正直、中原中也に興味が無かったので、あまり興味持てませんでした。(なぜ観に行ったんだ、というのはさておき)
最後に、広瀬すずが「きれいではない役」をしっかりと演じていました。これは良かったです。それだけでも観る価値はあると思います。
映像が良い
キノフィルム、映像が良い
良いが、良すぎてしまって、
必要以上に鮮やかなのが気になる。
夜のシーンはちょうど良く感じるので、
昼だと作り物感が出てしまうか。
キャストも誰も良かった。
中原中也が何も説明されなくても
中原中也だと分かる絵の力は、とんでもないと思う。
性的なシーンはもっと描くか、
もっと描かない方がバランスが良いと思う。
個人的には、もっと描かない方が良いと思う。
対比がよかった
中原→泰子→小林→中原で、見事なまでに三角関係でした。
中原が泰子と喧嘩をして負けるのは、途中まで気づかず劇中の会話で言われてから気づきました。
泰子が中原の客である小林に失礼な態度を取れるのも、中原の泰子への愛が大きいからですね。
泰子が小林を好きになりすぎて病気になったのを見て、少し分かるような気もします。
中原に対しては傍若無人だった泰子ですが、小林に対しては髪を整えたり身なりを気をつけてたのがこれも愛の大きさがわかる。
“小林の客”である中原にはしっかりもてなして、ティーカップも持ち手が右側“でないといけない”。
病気になったのも“でないといけない”ことが多かったからでは。
本当に小林の事が好きなのが伝わってきました。
『神経と神経で繋がろうとしましたの。それが1番深い愛、潔い愛だと思ったから』
小林と泰子のセックスシーンがありましたが、上記の台詞から察するに、結局最後まで出来なかったんですね。
時計のシーンで泰子がおかしくなったの何となく気持ちわかったような。小林と中原が神経で繋がりそうで気持ち悪いと見た時は思いました。
最初に小林は傍若無人な自由そうな泰子に惚れたのかと思ったら終盤の中原の奥さんを褒めてるの見て、お前もそういう人がいいんかい!って気持ちと同時にまた手を出そうとしたんじゃないのかと思いました。結局、中原の泰子だからよかったんですね。
泰子と叩き合いして、でも結局は負けちゃう中原と、優しく寄り添うのに最後は叩いて払っちゃう小林。その対比もすばらいですね。
岡田将生さん出てきてからのワクワク感、さすがだなと感じました。ほんと空気が違うというか物語が動き出した感じが、より一層泰子の気持ちがわかった。
広瀬すずさんは今まで作品を見た事無かったんですが、演技が上手でよかったです。
目で語る演技や、違和感のない喋り方とか。
全30件中、1~20件目を表示