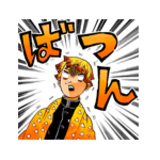ゆきてかへらぬのレビュー・感想・評価
全187件中、61~80件目を表示
地味な内容のストーリーでした。 女優・長谷川泰子と詩人・中原中也と...
地味な内容のストーリーでした。
女優・長谷川泰子と詩人・中原中也と評論家・小林秀雄の三角関係が
時間を追ってそのまま描かれているような感じ。
事実に沿って作られた映画なんでしょうね。
冗長な感が否めないお話しでした。
レトロ好き
秀雄にメロメロパンチ
詩人と評論家と女優、もうこれだけですごいドラマが生まれそう。
それぞれがパワーワード過ぎて、一人だけでも充分なエピソードが出てきそうな所、かける3なのでとにかくなんか濃い。
色々濃い。笑。
実際の彼がどうだったのかはわからないけど、映画の中に限って言えば小林秀雄がカッコ良すぎる。
私は岡田将生氏が大好きなので、9割り増しなこともあったかもしれないが、かなりのメロメロパンチを喰らったわっ!
クールで知的なイメージが岡田将生氏本人と被ってるのもあるけど、小林秀雄氏が輝いてみえたわよ。病み散らかす泰子にも穏やかで優しく対応できる猛獣使いっぷりも、ライバルでありつ天才だと認めてもいる中原中也との関係の変化諸々後にも彼を大切に扱う紳士な対応も。
そりゃ好きになるよ。
仕方ないじゃん、カッコいいんだから。
すずちゃんは和装でも洋装でも女をやっていても女優をやっていても歌っても踊っても叫んでても美しくて、本当に美✨
美しさに目が行くけど、喋る?セリフの?なんて言ったらいいんだろう、感情の表現を言葉を通して表現するの上手いなーと思う。
あと今まで観た作品の中で、一番私の中でのイメージに近かったかも。
あと再現度の高さに度肝を抜かれた中原中也役の木戸大聖君。
なかなかあの帽子が似合う人はいないわよ。
繊細で死にたがりな坊ちゃん。
ついつい仕方ないなあと思ってしまう、お姉さん心をくすぐるかわゆい年下男子を上手く演じてたと思う。
それから世界観がとても素敵だったわ。
泰子の衣装はどれもこれも可愛かったし、秀雄の家の窓が素敵で出てくるたびに見惚れてしまった。
携帯電話もPCもなかった時代は、なんか相手との距離感も、距離の取り方も違う気がする。泰子の激しさも、中也の坊ちゃまが許される生き方も、秀雄のスマートなふるまいも、現代でやったらまた違う感じになるんだろな。
面白かったし、何よりこの時代そのものにちょっと憧れてしまった。
木戸大聖を観る作品
大正時代の京都で、20歳の女優・長谷川泰子は、17歳の学生・中原中也と出会った。2人は互いにひかれあい、一緒に暮らしはじめた。その後、京都で唯一の友人だった富永が治療のため東京に戻ったため、中也達も東京に引越し、2人の家を小林秀雄が訪れた。小林は詩人として中也の才能を認めていて、中也も小林の適切なコメントに敬意を払っていた。2人の仲の良い様を目の当たりにした泰子は、彼ら2人の世界に入れない寂しさを感じていた。その後、小林は泰子の魅力と女優としての才能に惚れて、中也から泰子を奪い・・・さてどうなる、という話。
長谷川泰子役の広瀬すずは美しかったし、魔性の女としてエロさもあり良かった。
だが、なんといっても、中原中也を演じた木戸大聖が素晴らしかった。彼のことを今まで知らなかったが、小林秀雄役の岡田将生より光ってたと思う。
天才詩人・中原中也とはこんな人だったのだろう、と思わせる、引き込まれるような木戸大聖の演技が素晴らしかった。
彼を観るための作品と感じた。
セリフ回しが鼻につくが中盤の広瀬すずの演技は必見
久しぶりに映画に引き込まれた
出だしこそ芝居臭さが感じられたが、テンポが良いので、それも演出のうちのように自然に物語の中に引き込まれた。登場人物たちの危うさと潔さが若さからなのか大正~昭和初期という時代だからなのか、それともそれぞれの才能と自負によるものなのか、観ていてとても面白かった。演者も良い。たかだか百年なのに暮らしの変化には驚かされる。このような丁寧な作りこみをされた映画を観る楽しみを思い出した。観ている途中で「良い映画だなぁ!」なんて思ったのは本当に久しぶりのことだった。鑑賞後の感情とテーマ曲が切なくなるくらいマッチしていた。
原作には忠実
内容は盛っておらず、長谷川泰子の口述筆記による原作「ゆきてかへらぬ 中原中也との愛」の内容を壊さぬ様に、結構忠実に作られた映画と思われました。逆に言うと盛っていない分、エンタメ性はかなり低めで、エンタメを期待して観にいく人に向いていないでしょう。
長谷川泰子、中原中也、小林秀雄の奇妙な三角関係を、長谷川泰子を通して見る世界観で紡がれています。
一人の天才詩人と一人の稀代の評論家の間を生きる大部屋女優の半生が描かれており、中也や小林秀雄が好きな人間には楽しめる内容と言って良いでしょう。とはいえ目新しいエピソードは全く含んでいないので、詳しい人にとっては、改めて3人のエピソードを懐古する程度の内容です。
3人の演技がよかったです!
出演者でちょっと気になってたので鑑賞!
京都。
まだ芽の出ない女優、長谷川泰子は、まだ学生だった中原中也と出逢った。20歳の泰子と17歳の中也。どこか虚勢を張るふたりは、互いに惹かれ、一緒に暮らしはじめる。価値観は違う。けれども、相手を尊重できる気っ風のよさが共通していた。
東京。
泰子と中也が引っ越した家を、小林秀雄がふいに訪れる。中也の詩人としての才能を誰よりも知る男。そして、中也も評論の達人である小林に一目置かれることを誇りに思っていた。男たちの仲睦まじい様子を目の当たりにして、泰子は複雑な気持ちになる。才気あふれるクリエイターたちにどこか置いてけぼりにされたようなさみしさ。
しかし、泰子と出逢ってしまった小林もまた彼女の魅力に気づく。本物を求める評論家は新進女優にも本物を見出した。そうして、複雑でシンプルな関係がはじまる。重ならないベクトル、刹那のすれ違い。ひとりの女が、ふたりの男に愛されること。それはアーティストたちの青春でもあった。
というのがあらすじ!
個人的にはちょっとよくわからない難しい印象でした…
最初は見逃した?って思うぐらい一気に同棲までいってそして東京に出た感じ…笑
そして中原中也と長谷川泰子と小林秀雄の三角関係は理解しにくい…
途中は掴み合いの喧嘩とかしてたけど迫力がすごかったですね!
ナミビアの砂漠をちょっと思い出しました笑
3人ともちょっとめんどくさい人たちだなーという感じ笑
有名な3人の実話の話を元にした話らしくそこを知ってる人はかなり楽しめる作品なんだろうなと思います
私は全く知らない人たちだったので調べていればもう少し楽しめたかなと思います…
でも3人の演技が素晴らしかったですし大正や昭和初期が好きなので楽しめました!
あと広瀬すずさんが美しかったですし衣装もお綺麗でしたね!
いい映画をありがとうございました😊
タバコとマントが恋をした。
かつて、山口市にある中原中也記念館を訪れた時、中也の泰子にたいする愛に涙した。小林との三角関係をどう受け入れていたのか、中也なりの瘦せ我慢を感じたからだった。同時に、中也と小林の心を弄んだ(が正しいのか?)泰子の実像は、ファムファタルなのかむしろ犠牲者なのか興味を持っていた。
広瀬すずの危うさが泰子とシンクロしてた。岡田将生は安定。中也役の若手木戸大聖、青臭さがよくでていてよかった。
過日の記念館訪問時のメモを探してみた。″彼の言葉を我が身の内に落とし込んでじっくり噛み締めると、とてつもなく胸が苦しくなってくる"と書いていた。そしてさらに"泰子を奪った小林秀雄との、終生変わらぬ関係は、まるでJ・ハリスンとE・クラプトンのようだよ。 悲しみからしか文学が生まれないのだとしたら、不幸ではないか?"とも。中也が後世の我々に残したものは大きいが、中也自身、自分の人生をあれで良しと思えたのか。幸せと思えたのか。
これぞ『大正浪漫』『一流文芸』
重い物質感
うーん...
男優たちは青いが、全カット美しい
全187件中、61~80件目を表示