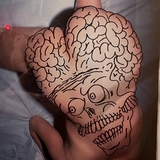本心のレビュー・感想・評価
全151件中、81~100件目を表示
本心と分人
全体にテクノロジーの進歩によるネガティブな側面にフォーカスされていて
要素として提示される様々な社会問題も回収(解決)されないので
主人公同様にちょっと混乱しつつ、複雑な気持ちで観ました。
亡くなった母の本心を追い求める過程で、
逆に自分自身の本心を見失っていく様を繊細に演じた池松さんや
その近しい登場人物の表情をクローズアップ気味に捉えた映像が印象的でした。
暗い調子の映画ですが、
ピアノのワルツが流れるレストランのシーン、
そして光を掴もうとするが如きシーンは、
変貌した近未来の世界において、接する肉体がなくなっても、
心を通わせることができる、という一縷の希望を表現しているようで救われました。
凄く希望が持てて、さりげないラストシーンで、とても感動しました。見事ヒューマンドラマに着地した石井監督の新境地と言えるでしょう。
AI(人工知能)の普及で、増え続ける電力需要に応じるため、あの米スリーマイル島の原発を再稼働させるニュースが話題になっています。今この時を表現する映画でも、AIの影響は避けて通れない題材の一つ。母の死に向き合おうと、AIに頼る青年を描いた平野啓一郎の同名小説を、「月」「舟を編む」の石井裕也監督が池松壮亮を主演に迎え映画化しました。テクノロジーで人の心は作れるのか。人類の課題を鮮やかに先取りし、鋭く問いかけてきます。
●ストーリー
ヒグラシが鳴き、風にカーテンが揺れる無人の教室の窓際に制服姿の女子高校生がポツンと座る。廊下から彼女を見つめる男子の瞳が一瞬陽光にくらむ。再び彼が目を開けても彼女はもうそこにいません…。それは主人公石川朔也(池松壮亮)の(おそらく何度も見てきた)回想混じりの夢でした。そこにいたはずの人がいきなり消えても不思議はないとも思うが、同じことが立て続けに起こるのです。
工場で働くの朔也は、同居する母・秋子(田中裕子)から「大切な話をしたい」という電話を受けて帰宅を急ぎます、豪雨で氾濫する川べりに立つ母を助けようとしたものの
通りかかった自動車のライトに目がくらみ、川に落ちて昏睡状態に陥ってしまいます。
1年後に目を覚ました彼は、母が“自由死”を選択して他界したことを知ります。勤務先の工場はロボット化の影響で閉鎖しており、朔也は激変した世界に戸惑いながらも、カメラを搭載したゴーグルを装着して遠く離れた依頼主の指示通りに動く「リアル・アバター」の仕事に就くのです。
ある日、仮想空間上に任意の“人間”を再現する技術「VF(バーチャル・フィギュア)」の存在を知った朔也は、開発者の野崎將人(妻夫木聡)に母を作ってほしいと依頼します。生前、合法的な自死を選んだ母の選択に納得できないでいた朔也は、母の本心を探るためVFに頼ろうとしたのでした。けれども野崎が告げた「本物以上のお母様を作れます」という言葉に一抹の不安を覚えつつ、VF製作に欠かせないデータ収集のため、母の同僚で親友だった三好彩花(三吉彩花)に接触。こうして“母”は完成、朔也はVFゴーグルを装着すれば母親にいつでも会えるようになります。一方、三好が台風被害で避難所生活を送っていると知り、VFの母と三好の3人で奇妙な共同生活を始めるのです。他愛もない日常を取り戻していきます、VFは徐々に“知らない母の一面”をさらけ出していくのです…。
●解説
原作では2040年頃から始まる物語の時代背景を、現代により近づけました。本作のAI監修者によると、次世代サービスとして登場するVFに似た技術はすでに実装されているといいます。物語の未来像に現実が猛追する中、仮想とリアルの境界がますます曖昧になった世界を視覚的に表しました。また、私たちが生きる今と時間軸を接続させたことで、朔也の孤独や焦燥感が真に迫ってきます。
朔也は依頼主の分身となって行動する「リアル・アバター」を仕事としています。横文字で聞こえはよくても、実態は使い走りです。モラルを欠いた依頼主に振り回され、心身を消耗させるのです。貧富の格差が広がり、固定化された社会。癒やしと安らぎの仮想世界と、肉体を酷使する持たざる者の現実を対比的に描がれました。
原作小説のテーマの一つは「最愛の人の他者性」だった。ある一面を照らし出そうとすればするほど、自分とは切り離された他者である事実が浮かび上がる。よりどころをいちずに求める息子役の池松、そんな息子を見守りつつ、同時にどこか突き放したようなVFの母役の田中が、最も身近な他人である親子の機微を繊細に演じました。
亡き母を復活させるという一見後ろ向きな朔也の行動は結果的に、三好やアバターデザイナーのイフィー(仲野太賀)など新たな人間関係につながっていきます。世の実相に背を向けて、母が待つ仮想世界に生き続けるのか。悲しみを克服し、現実に戻るのか。母の似姿であるVFは容易に 「答え」を出してくれません。だからこそ、悩み抜いた末、朔也が下した決断に希望を感じるのです。
また本作は人の存在の「不確かさ」を冒頭から強調します。確かにその人を捉えていたはずの画面が、別のショットを短く挟むだけですぐさま無人になるのです。映画はこんなに簡単に人を消せるのです、と言わんばかりです。母親の場合、事態は深刻で、大切な話がある、と工場で働く息子に電話をかけていたことが、その後ずっと朔也の気持ちを揺り動かします。母は「自由死」~本作では自分の意思で「自由に」死を選択できると設定される~を選んだのか?と。その本心を知りたくて、朔也は母親をVFとして再生させるのです。今度は構図が逆転し、死んだはずの人がいともたやすく画面に姿を現すことに。しかし、それはむしろ朔也の本心をあらわにするための装置であったのです。私たちの予想はいい意味で裏切られ、映画はテクノロジーの進展で変貌する母子関係といったSF的主題から離れます。
朔也がある女性に愛を告白する場面が痛切です。「私はあなたを愛していません。」そんなストレートな言葉でさえも本心なのかわからないのです。それはSFでもなんでもないだろう。ロボットの導入で工場から人影が消え、人が人として働く機会を奪われる。そんな世界において、今ここに生きる私たち一人ひとりの「(本)心」の 「不確かさ」があらためて浮き彫りになります。
●感想
一見するとVFが日常生活で当たり前となる未来社会を描いたSF作品に見えるでしょうが、実は主人公と同居人のヒロインとの恋を描いた恋愛映画なのです。
けれども朔也のじれったさには、見ていて腹が立ちました。生まれた時から父親を失っていた朔也は、人を愛することも愛されることにも自信がありませんでした。だから彩花に自分の本心を明かせないばかりか、自分自身の本心までも奥へ引っ込めてしまったのです。けれども彩花と同居する朔也の気持ちはバレバレでした。
そんな朔也に雇い主のイフィーは、あえて彩花との仲を取り持つように懇願するのです。なんと朔也は快諾してしまいます。というのもイフィーの晩餐に招かれた朔也に付き添った彩花は、イフィーから握手の求めに応じたことで嫉妬心を募らせて、自棄になってしまったのです。セックスワーカーだった彩花は何度も怖い体験と遭遇し、すっかり人と接触することに恐怖感を抱くようになっていたのです。なのにイフィーには普通に握手してしまったのでした。
彩花へプロポーズするつもりのイフィーのところへ、朔也は彩花に行くように勧めます。その言葉に急に不機嫌になる彩花。朔也への怒りから、彩花はイフィーのところへ向かってしまうのです。ふたりの気持ちがわかるだけに、本当にじれったいシーンでした。
これまでの石井作品なら、ここでバッドエンドとなったことでしょう。どう違ったのか、それは内緒です。でも何というか、凄く希望が持てて、さりげないラストシーンで、とても感動しました。見事ヒューマンドラマに着地した石井監督の新境地と言えるでしょう。
若手俳優陣がいい
toho日比谷で鑑賞
平日ですが混んでました
石井裕也監督×池松壮亮なら
必見だろうと
最後まで楽しく見られました
原作は未読
ある男、空白を満たしなさい、の著者と知って
なるほどねと。作家性あると思います
池松壮亮はもう言わずもがな
危うい繊細な人物を演じさせたら間違いなし
水上恒司のベタベタした感じや、
仲野太賀のうさんくささもいい!
そして三吉彩花(役名がややこしい)
ほぼすっぴんのほうが美人に見えるという
メイク泣かせ
上映時間122分ですが、テンポがよくないのか
たっぷり演出なのか長く感じました
ストーリーは非常に意地悪
ラストの解釈もタイトル本心だしな…となって
最近の邦画には珍しくおっぱいが出てくるぞ
映画館で見たほうがいいよ
追加。朔也のショルダーバッグのダサさが絶妙。
あの秋葉原感。
とにかくつまらなかった。AIストーリーに入れてるのも、途中アニメみ...
依頼主(カスタマー)の人間性に戦慄を感じ、ギグワークの残酷さに寒気を覚える
リアルアバターを雇用した依頼主が、ギグワーカーがどこまで要求に従うかを試すかのように下劣な指示をくだすシーンに戦慄を感じました。
評価を下げられると職を失うため、一線を越えて依頼主の指示に従おうとするギグワーカーと、そんな彼らをあざ笑うかのように低い評価を行う依頼主。
ギグワーカーの評価は依頼主からの一方通行で、映画で示されたシステムではワーカー側から顧客の評価を行うことはできないようでした。ウーバーなどのリアルシステムも同じなのかもしれませんが。
本来であれば双方向から評価を行い、契約するに値しない顧客は出禁にすべきと思うのですが…。
効率のみが支配する近未来の現実にゾッとしました。
映画のテーマである亡き母の「本心」については少々消化不足感が残りました。
石井裕也作品は面白いけど苦手で好きになれない
ダメな作品とは思わないんですよ。
現代のさまざまな社会問題をうまく取り込んでるし、全体として見れば興味深い作品ではあるんです。
予告を見て、本作を見る気になったから見たのも事実です。ただし、これは原作のよさだけかもしれません。
石井裕也作品特有の最初から終わりまで「善」と「悪」の判断がキッチリ決まって、それが押し付けられる感覚はやはり気持ちよくないです。映像やストーリー的な余白はあっても価値観の余白がないんです。
加えて、これも同監督の作品でよくあるストーリー的には脈絡のない脇役として「醜悪なもの」を登場させ、それをことさら酷く描くことで、作品の主題を強化しようという独特の「手癖」は見ていて本当に不愉快なものがあります。
原作の平野啓一郎さんの政治的スタンスは好きではない部分もありますが、作家として作品にするときには、絶妙な匙加減である種の「党派性」を消して、打ち出したいテーマを表現しているので、その意味では非常に信頼できます。しかし、本作は石井裕也監督がその消したはずの党派性を、再度わかりやすく浮かび上がらせているため、ひとつの作品ではなく、ある種の単調でプロパガンダとして成立してしまっています。
現在の日本社会に多くの問題点があるのは事実ですし、テクノロジーがそれを加速させている側面は否定し難いです。ただ、それをそのまま作品として表現したものが一本の「映画」作品として素晴らしいかは完全に別物です。
このような理由から面白くなかったわけではないですが、まったくといっていいほど、満足できる作品ではありませんでした。
P.S. テクノロジー的な考察の面や社会的な問題の切り取り方でも雑な作品なので、石井裕也監督は脚本を第三者に任せるか、監修を付けた方がいいと思います。
生きることが目的となり
原作とはまったく別物でしたぁ
芸達者な池松くん、ミヨッシー(三吉彩花)の好演には救われましたし、原作をまったく読んでいない方には、個々のテーマの軽重は気にならなかったやもですが… 何が主題か、とても分かりにくかったのでは? 映画にするための脚色は自由なれど、一部設定が無理筋で、原作の大事な設定が無くなってしまっていたのは…
もはや実現可能な状況となっているヴァーチャルフィギュア、リアルアバターを利用する近未来でのAIやメタバースというテクノロジーの功罪。一方、深刻な社会問題としての、政治の無能、貧富の差や差別の拡大、自然死という名を与えられた自殺(尊厳死?)などなど。平野啓一郎の原作は、それらを巡って、人間の右往左往や受容と絶望・希望・愛を描いたスゴイ野心作です。
やはり2時間での映像化、その為の改変が多すぎて、石井監督をしても作品に纏める無理だったか、と言うのが一番正直な感想かなぁ⁈
個人的には「ガタカ」のような、もっともっとドライ、無機質、淡々とした映像の中での人間性の苦闘、抵抗みたいな描き方を勝手に期待してました。
気になる方は、やはり原作を読んでください!
早く終わらんかな。。
石井裕也監督、毎回オリジナリティを感じる作品を送り出し、また死生観をテーマにすることが多く時に挑戦的な作品も。と言うことで、新作が公開されれば無視は出来ない監督です。ただ正直なところ、私の好みとは違った作品もあり「今回はどっちだ?」と思いながらTOHOシネマズ日比谷へ。サービスデイ(キャンペーン)の10時50分からの回、平日の割にはまあまあの客入りです。
で、観た感想は、、、ちょっと戸惑うくらい想像と違いましたし、肝心な出来としてもイマイチな感じ。ちなみに原作未読なのですが、どれくらい忠実な脚色なのか?逆に興味が湧くほどでした。(読まないですけど。)
それにしても、邦画で取り扱われる「近未来とテクノロジー」ってどうしてこう現実感がないのか?勿論、予算がないのも大きな理由の一つだと思いますが、語られている世界観がルック的に伝わってこないため、それっぽい言葉で説明されてもピンとこないし入り込めない。そもそも、それだけの技術力があれば日本に留まるはずもないと思うのですが、そういう様子は皆無で、むしろガラパゴス化しているように見えます。だからこそなのか?セキュリティや倫理観は劇下がりしており、格差によって恵まれない人間に大きくしわ寄せが行っており、奴隷のような扱いを受けていてディストピア。だったら街ももっと荒廃してそうなのですが、勿論、そんなの表現する予算はないですからね。。
そして、演出的にも気になる点あり。朔也(池松壮亮)以外のキャラクターのほぼ全員、謎めいていてどこか怪しさを感じさせるためか、皆やや過剰に感じる「演技」なのですが、反ってその演出に役者の力量判りやすく現れいるため、人によっては悪目立ちしていることもあってノイズです。敢えて言いませんが、大袈裟ではなく観ていてしんどく感じるくらいの役も。。
内容的にも「これ要らないんじゃないか?」と思うシーンもありますし、上映時間122分はとても長く感じて、中盤以降は「早く終わらんかな。。」と思って観てました。取り敢えず、「終わり方」だけは悪くないかな。
と言うことで、田中裕子さん、池松壮亮さんは今回も素晴らしかったことが救いの一作。石井監督、、次作も待ってますので何卒宜しくお願い致します。
トイレ行くときどうするんだろ?
全くハマらなかった作品だった。
いろんなことを考えさせてくれる作品
本心と実際口からでる言葉は必ずしも同じではないのでしょう
石井裕也監督と言えば、大渡海と言う国語辞典作りに奮闘する編集者を描いた「舟を編む」や重度障害者施設で起きた大量殺害事件を映画化した「月」が代表作です。
舟を編むの松田龍平、月の宮座りえと礒村勇斗の演技に唸りましたが、本心の池松壮亮と三吉彩花の演技にも引き込まれました。
ストーリーは、
仕事からの帰宅中に偶然母親の投身自殺の現場を遭遇し、助けようとして川に転落した男は昏睡状態に陥ってしまう。
そして、意識を失ってから1年後に目覚めるが、男が出勤する時に母親から「大事な話があるの」と言われたことが気になり、母親のアバターを作ろうと思いたち、バーチャルフィギュアを作る会社に依頼する。
母親のデータをインプットされたアバターはAIにより学習する。更に、唯一の友達で棲むところを災害で失った若い女性からも、暮らす部屋を提供する代わりに母親のデータを提供して貰うが、それでも何故自殺したのか、何を言いたかったのかアバターは話してくれない。
また、この女性も母親から本心を聞いている素振りをみせるが話してくれない。
そして、仮想世界で母親と旅行した場所に行くと突然母親のアバターから死ぬ前に「あなたを産んで良かった」「愛している」と言いたかったと男に伝えた。
母親の本心とは、母親の友人の女性の本心は、そして母親の友人の女性に対する本心は、、。
とても面白い映画でした。
目は口ほどに物を言う
工場で働く『石川朔也(池松壮亮)』は
豪雨の帰り道、増水した川の畔に立つ母『秋子(田中裕子)』の姿を見つける。
次の瞬間に彼女の姿は消えており、
『朔也』は母を助けようと濁流に身を躍らせる。
彼が正気付いたのは、
それから一年近く経った病院のベッドの上。
母は亡くなっており、しかし
彼女が生前に電話で告げた
「帰ったら大切な話をしたい」との言葉が脳裏から離れない。
故人の膨大なライフログをAIに学習させ、
仮想空間上に再現させる「VF(ヴァーチャル・フィギュア)」の技術は実用化されている。
母が伝えたかったことを知るために、
『朔也』はその技術を頼るが、
更なるデータをインプットし、より本物に近づけるため、
母の親友だったという『三好(三吉彩花)』にコンタクトする。
そこから、『朔也』と『三好』と『VF秋子』の
奇妙な三人の生活が始まる。
物語りの舞台はそう遠くない未来の日本。
「安楽死」や「尊厳死」よりも一歩進んだ「自由死」が合法化され、
まだ元気な人間でも「自死」を選択でき、
その死に対しては国から金銭的な補填すらある。
AIやロボットによる人間の仕事の代替は更に進んでいる。
それにより多くの失業者が巷に溢れ、
職を求めている。
その一部は、良い収入との言葉に惑わされ、
内容を吟味しないまま非合法な仕事に手を染める。
「リアル・アバター」との仕事が始まっている。
ゴーグルを装着し360°カメラを持ち、
依頼主の代わりに目的を遂行し、
一部始終はHMDを通して配信されるが
報酬は微々たるもの。
代行業務で感謝されることがある一方、
中には些細な理由で低い評価を付ける者、或いは、
雇用・被雇用の関係を嵩に懸け、理不尽な要求をする者も。
社会は富裕層と貧困層に、完全に分断されている。
2019年~20年に新聞連載された『平野啓一郎』が原作。
今のこの国での問題が
既にして多く盛り込まれていることに驚く。
もっとも、「ぬいぐるみの旅行代理店」などは2010年代前半からあり、
「リアル・アバター」は、
これと「ウーバーイーツ」の掛け合わせ且つ発展形かもしれぬが。
『朔也』は過去に犯した罪を引きずる。
『三好』も、昔の仕事がトラウマとなり、
他人との接触を極端に恐れる。
『秋子』は息子には伝えていない秘密を抱えている。
いくら科学が進歩し、連絡を密に取れるようになっても、
互いの心を理解することは難しい現実。
しかし面と向き合うことで見えて来るものもある。
それが如実に示されるのは
掲げた手の先には太陽が、
そして光明が見える印象的な最後のシークエンス。
主役の三人の演技は皆々秀逸。
『田中裕子』は掴み処のないとぼけた感じが、
『三吉彩花』は引きずっている翳が払拭されていく変容が。
が、とりわけ『池松壮亮』が出色で、
口から出た言葉が真実ではないことを、
眼差しで分からせてしまう、
ラストシーンに向けての
裏腹な一コマの表現の素晴らしさ。
本心とは・・・
近未来に起こりそうな問題を予感させる予告に惹かれ、期待していた本作。レビュー評価が芳しくないことに不安を覚えながら、公開2日目に鑑賞してきました。
ストーリーは、「大切な話がある」という言葉を残して”自由死”を選んで亡くなった母・秋子の本心が知りたくて、仮想空間に任意の人間を再現する「VF(ヴァーチャル・フィギュア)」として”母”の作成を依頼した石川朔也が、リアルとヴァーチャルの世界でさまざまな人と関わる姿を通して、人間の本心について描いていくというもの。母の死の真相をめぐるヒューマンミステリーを装いながら、実際には人の本心はどこにあるのかということをあぶり出すような印象の作品です。思っていたのと少々テイストの異なる作品でしたが、なかなかおもしろかったです。
VFにしてもリアル・アバターにしても、VRとAIの進歩と融合により、あるいはこんな技術革新やサービスも登場するのではないかという現実味を帯びた設定がおもしろいです。倫理や常識に照らしてアウトと感じるシーンもありますが、世の中に初めて登場したものが一般に定着していく過程では、十分に起こり得る問題であり、かえってリアルに感じます。
そして、その中で振り回される人間の愚かさや滑稽さや悲しみを通して、人の心の機微を繊細に描いているように感じます。SNS全盛の現代の風潮をみると、そのうち人の本心はVRやアバターやネットを介してしか語れなくなってしまうのではないかと感じます。それは利便性の問題というより、相手から返される好ましくない言動から自分の心を守る自己防衛手段として、何かを媒介としているような気がします。その心理には共感しますが、果たしてそれは本心として相手に伝わるのでしょうか。
一方で、本心は面と向かって伝えなければ本当に伝わらないのかとの疑問もあります。手紙や電話なら伝わるような気がするのに、なぜネットを介するとダメなんでしょうか。しかし、いま抱いているそんな違和感も、将来的には払拭され、コミュニーションの主流は完全にネットに移っているかもしれません。
結局のところ、伝わるかどうかは対面かネットかといった形式の違いではなく、その人のもつ人柄に由来しているのでないかと感じます。目の動き、話す速さ、声の大きさ、額の汗、声の震え、文字の美しさ、紡いだ言葉、会話の間、日頃の言動など、それこそ膨大な情報を処理して相手の心を見極めているのではないでしょうか。人の本心なんてさまざまな思いが混ざり合って形成されており、当の本人ですら端的に言い表せない代物であり、いくら優秀なAIが導き出したとしても、それは数ある正解のうちの一つに過ぎないのではないかと思います。
ラストで朔也が伸ばした手に重なるもう一人の手。あの手を伸ばした人物は、朔也が語らなくても、AIに頼らなくても、きっと朔也の本心をしっかり受け取ったのだろうと思います。
こんな感じで、人の本心について考えさせられる作品ではありましたが、さまざまな人物を登場させたことで、やや焦点が定まりきらなかったような気がします。特に、予告で釣った”母の本心”が中盤で放置され、オチも肩透かしなのはいかがなものかと思います。低評価の理由は、おそらくこのあたりにあるのではないでしょうか。
主演は池松壮亮さんで、誠実さが滲み出るような演技が秀逸です。脇を固めるのは、三吉彩花さん、水上恒司さん、田中泯さん、仲野太賀さん、妻夫木聡さん、田中裕子さんら。
人の本心は推して量るもの、人の心の底なんて分からないのが当り前だと...
人の本心は推して量るもの、人の心の底なんて分からないのが当り前だと思う
それにしてもあのウーバー地蔵みたいなのは闇バイトなんですかね、なんか幾らでも危いこと依頼されそう...
母は結局ネコを庇って?
キャストも無駄使い感漂ってるし
何か1つでもはっきり答えを提示して欲しかった、仕事とかAIとか倫理観というかガイドラインがなっとらんだろ!と思ってしまいました
あっち側とこっち側とか…
平野啓一郎原作で楽しみにしていた反面、監督が石井裕也ということでイヤな予感はあったわけだが、案の定、小説の表面だけを雑につまんで話を組み立てていて、設定や人物造形、テーマなどすべてがペラくてまとまっていない印象。これ、原作知らない人は理解できるのだろうか?
原作は、自由死(尊厳死)だけでなく、社会格差や労働問題、仮想空間、LGBTQ、在留外国人、コミュニケーションなどなど、平野らしい数々の社会問題の提起と視点を多層的に描きつつ、それに対する別方向からの考えも丁寧に提示している。また、タイトルの人の本心というテーマについては、主人公の一人称で語られる小説だからこそ成立しているともいえる。そんなわけで映画にするには繊細な演出が要求されるし、映画化の難度が高い文学作品だと思う。
本作は、本心と言いながら登場人物に自分のことや秘密をペラペラしゃべらせるし、エピソードやキャラを単純化したことで結局、朔也と三好の安易な恋愛オチにもっていってしまう。意味不明な部分も多々あって、小説と映画は別物とはいえ、映画化して何がやりたいのかよくわからない。せめて映画的演出が期待できればと思うのだが、各シーンに魅力がないのが致命的。妻夫木の会社もヘッドセットもVR世界も貧乏くさいし、リアルアバターはウーバーイーツだし、印象に残る画作りがまるでなくてツラい…。
唯一よかったのは三吉彩花! こっちの方がVF感あるパーフェクトな美人ぶりは彼女を主人公にしてほしかったぐらいなのだが、そもそも役名の時点で三吉が演じるのは当然という気も…。いろいろめちゃくちゃ言ったけど、石井監督の過去作を振り返れば社会問題を意識したいという意欲はあれど、正直それをまとめて訴えかけるだけの技量が監督には不足してるとあらためて思ってしまった(かなり上から)。
良い意味で予告と期待を上回る
全151件中、81~100件目を表示