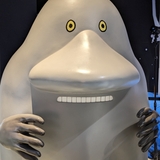十一人の賊軍のレビュー・感想・評価
全456件中、61~80件目を表示
新発田より愛を込めて
新発田市出身者です。
この作品はいち娯楽映画であるが、新発田にとってとても重要な作品となりました。
それは新発田は越後の外様大名の小さな藩で、しかもお隣には親藩大名の会津藩があり、とても弱い立場であったことを忠実に表現している。また勤王派にもかかわらず奥羽越列藩同盟に周辺大藩たちの圧力によって加盟させられた苦悩を見事に描いているからです。
今までは会津、長岡側から見た戊辰戦争の作品しかなく、新発田藩は一方的に卑怯な裏切り者扱いでしたが、この作品のおかげでこの戦での振舞いを理解して頂けると思います。この映画の製作に携わった関係者全員に感謝致します。
また新発田の人を演じた出演者の方々は訛りがお見事でした!
彼らは全員新発田市の名誉市民にしたいです!
仲野太賀の一人勝ち
戊辰戦争において新発田藩が奥羽越列藩同盟から新政府へ寝返った史実(※)を背景に、新発田城下で同盟軍と新政府軍が衝突することを避けるために、処刑を待つ罪人たちを新政府軍足止め要員として送り込んだというフィクション。
※新発田藩はそもそも勤王が藩論だったから、錦旗を掲げた新政府に反抗する同盟に加入したことが城下の民意に対しては裏切りだったかもしれない。
もっとも、同盟の各藩も新政府と戦をしたかったわけではないのだが…。
この映画はすこぶる評判が良く、そろそろロードショーが終わりそうだったので慌てて劇場へ駆け込んだ。
だが、私は物足りなさを感じた。
多くの登場人物たちを一見丁寧に描いているようで、それぞれバラバラの断面を見せているだけで中途半端なのだ。
アクションにそれなりに尺を割かなければならないうえに、中途半端な人物描写にも尺を使っているから全体が長くなっている。もっとダイエットできたはずだし、面白い設定が活かされていない気がした。
主人公は罪人の政(山田孝之)と足軽の鷲尾兵士郎(仲野太賀)の二人だ。
この二人の間に対立や友情のような物語はない。だが、最後に共通の敵と戦うというドラマ構成が秀逸なのだが、兵士郎の道場仲間だった藩士入江数馬(野村周平)にも花を持たせたりするから、ボヤケてしまっている。
罪人たちを最後は口封じしろというのは藩命だ。なのに数馬は罪人たちに謝り、家老に放免をかけ合うと約束する。それほど罪人たちと心が通った訳でも、罪の意識を持っていた訳でもないのに、唐突なのだ。藩命に背く数馬の藩士としての矜持は何なのか。
家老溝口内匠(阿部サダヲ)の娘(木竜麻生)が数馬の許婚者だというのも布石がなく、一人で砦にやってきて数馬の死を看取るお涙には無理やり感が否めない。
家老を悪役にするのは良いとして、幼君溝口直正(柴崎楓雅)をわがままなバカ殿のように描いていながら、結局それに翻弄されるでもなく、家老の独断で事が進んでいく。
家老の妻(西田尚美)に至っては、存在感が薄かったのに自決するに及び、家老に何を訴えたのか。
笠原和夫の幻のプロットを評価する専門家筋のコメントを目にするが、脚色と演出への評価ではないのでは…。
とはいえ、上記のような不完全な人物描写を除けば、スケールも大きくて面白い面はある。
砦の攻防アクションは、確かに見どころだ。
あんなロケ場所をよく見つけたなと、そこによくオープンセットを作ったなと、感心する。
官軍が大砲をあんな場所まで運ぶのは大変だったろうと思うが、大砲攻撃がないとあの攻防は盛り上がらない。やはり、今の映画ならではの演出だ。
吊り橋を爆破するメインイベントは、特に面白い。
油を使っての奇襲はリアリティに欠けるものの、その後チャンバラまで展開して盛り上がる。
そして、最後に家老と兵士郎の直接対決だ。
この映画は、阿部サダヲvs.仲野太賀だったのだとハッキリ示している。
芸達者な二人の役者による渾身の演技合戦は見応えがあった。
特に、全身で見栄を切る仲野太賀のエネルギッシュなパフォーマンスに魅せられた。
さて、10人の罪人たちの中で2人を生き残らせたのは、そこだけ切り取れば悪くはないのだが、そもそも笠原和夫が製作と対立した理由が「全員死ぬ」結末だったのなら、笠原和夫の無念はこれで晴らされたと言えるのだろうか…?
白石監督史上、最高傑作
久しぶりにこちらにレビュー投稿。
というのも、今作の素晴らしさをもっと世に伝えたい。
東映と白石監督はこれまでも『孤狼の血』があったが、やはりかねてから監督は時代劇制作を熱望していただけあって、東映との相性は抜群。おそらく制作費もこれまで監督が作った長編の中で一番あったのかな、と推測。
内容も戊辰戦争に着想を得て、そこにさまざまな人間模様が入り乱れ、それは決して受け入れられないような人間もいるが、それも生きる為の手段だったり、と面白くも切ない人間ばかりだった。
これまでの白石監督作品に出てきたようなキャラクターが多く、監督を線で追っている自分としてはそういうキャラクターが愛おしく、また圧倒的な殺陣技術や、かなりハイレベルな撮影技術に感動。最後は自然と涙が流れた。
もっと世界に売り出してほしい。
斬り合い闘いに凄く迫力があって予想以上に良かった。前作イマイチも、白石監督凄いジャンと唸らされた
白石和彌 監督による2024年製作(155分/PG12)の日本映画。
配給:東映、劇場公開日:2024年11月1日。
戊辰戦争で奥羽越列藩同盟の一員ながら新政府軍に寝返った新発田藩を舞台に、虫ケラの様にあつかわれる罪人等庶民たちによる権力者との死闘を描いていて、物語のつくりがお見事。流石、笠原和夫の原案、そして今の時代にしっかりとフィットしていると思わされた。
戦い・斬り合いの迫力もすごく感じられ、刀がぶつかりあう音響もバッチリ。貴重な兵器となった手作り爆弾も、随分と派手な爆発で、絵的にも効果抜群に思えた。ただ、真っ暗でとても見にくいシーンが存在することには、剣捌きの拙さのカバーの様にも思え、少し抵抗感を覚えた。
ダブル主演の罪人役山田孝之も、剣術道場主で藩士ながら共闘した仲野太賀も共にとても良かった。演出も含めてだが、二人の超絶的戦いのアクションそして壮絶な最後も素晴らしく、俳優として大きな魅力を感じた。
新発田藩の重臣溝口内匠(阿部サダヲ)の描かれ方も、とても気に入った。主人公たちを無罪にすると騙して新政府軍と戦わせた悪役なのだが、かたや相手の強大さを認識し家臣や領民たちの命を守った恩人でもあり、藩の政治を司った人間としては評価もできる両面を示した脚本(池上純哉)は、最愛の娘を無くしてしまう展開も含めて、とても秀逸に思えた。
また主人公以外の罪人たちも個性的で良かった。特に紅一点のなつ役鞘師里保は、お姐さん的存在感も有り、印象に残った。元モーニング娘(9期)とは知らなかったが、今後も映画女優として期待できそう。
監督白石和彌、原案笠原和夫、脚本池上純哉、企画紀伊宗之、プロデュース紀伊宗之、プロデューサー高橋大典、ラインプロデューサー鈴木嘉弘、キャスティングプロデューサー田端利江、音楽プロデューサー津島玄一、撮影池田直矢、照明舘野秀樹、録音浦田和治、音響効果柴崎憲治、美術沖原正純、装飾郷原慶太、小道具松永一太、衣装大塚満、メイク床山
山下みどり、特殊メイク中田彰輝、編集加藤ひとみ、音楽松隈ケンタ、アクションコーディネーター吉田浩之、操演宇田川幸夫、ガンエフェクト早川光、シニアVFXスーパーバイザー
尾上克郎、特撮VFXスーパーバイザー神谷誠、監督補松尾浩道、助監督藤江儀全、制作担当
松村隆司。
出演
政山田孝之、鷲尾兵士郎仲野太賀、赤丹尾上右近、なつ鞘師里保、ノロ佐久本宝、引導千原せいじ、おろしや岡山天音、三途松浦祐也、二枚目一ノ瀬颯、辻斬小柳亮太、爺っつぁん本山力、入江数馬野村周平、田中俊介、松尾諭、仙石善右エ門音尾琢真、柴崎楓雅、佐藤五郎
吉沢悠、駿河太郎、松角洋平、浅香航大、佐野和真、安藤ヒロキオ、佐野岳、ナダル、木竜麻生、長井恵里、西田尚美、山縣狂介玉木宏、溝口内匠阿部サダヲ、村娘ゆりやんレトリィバァ。
わが町でも
幕末、旧幕府側に立つ奥羽越列藩同盟と新政府軍(官軍)の間で右往左往した新発田藩。若き藩主は列藩同盟に参加せず新政府側につきたいと。しかしまわりをぐるりと同盟側に囲まれた新発田にはそれを選択することが難しい…
そんなことから身内をも欺く非道な作戦が実行される。
これは歴史に名の残らない作戦、名の残らない人々の物語。
私の住む町(新政府側についた)にも戊辰戦争の大きな爪痕がある。辻には石碑が、寺々には墓地や供養塔が、土方歳三や大鳥圭介に関する逸話も残っている。
京都から函館に至るあちこちでこのように名も残らぬ人々が無残に散ったのだ。身近に起きたことのようにじっくりと受け止めた。
仲野太賀さんの時代劇は初めてだったが剣術家らしく猛々しく戦う姿が良き、さらに「ちはやふる」以来の野村周平さんのイケメンぶりも良き、若き藩主の意向に悪事をおかしてでも応えようとする家老、阿部サダヲさんの奮闘ぶりも見事だった。
キャラの魅力がもっと欲しい!
令和の娯楽時代劇
圧巻の演技とカメラワーク
幕末好き、山田孝之好き、仲野太賀好き、玉木宏好きとしては観ないといけない映画だとおもってみました。
期待を超える内容でした。
仲野太賀の殺陣とそのカメラワーク超かっこいい!
山田孝之の演技かっこいい!
今までよく知らなかったんですが、尾上右近、鞘師里保、岡山天音、本山力がすごく良かったです。
ナダル!、お前いたんかナダル!wwというくらい、芸人のナダルさんが出ていることに全然気づかなかったです。
すごく目力のあるいい役者だな~と思ったらあのクズキャラで売っているナダルさんとは。
鑑賞後に調べてひっくり返りました。
演出もとっても良かったです。
ストーリーは、まぁ及第点かなと正直思いました。
とっても楽しめました。良かった。
わしは賊軍だ、十一人目のな。
まず、幕末、そして官軍と奥羽越列藩同盟の対立の経緯を予備知識として知っているかどうか、そして越後の地理と各藩の力関係がわかっているかどうかで、この映画の楽しめ度が違うだろうなと思う。だからと言って、その説明をしていては凡長になるし。そして、観ている個人個人が、どの勢力に肩入れして観るかでまた大きく見方が異なる。
で、自分はというと会津びいきなので、当然、長岡も新発田も嫌いである。冒頭、「そこから長岡を中心とする奥羽越列藩同盟、云々」とナレーションが入るが、新発田も日和見だけど長岡こそ天秤外交のような日和見交渉の末に城下を焼野原にしたんだろうが、という反発しかない。むしろ、最後まで城下を守った新発田は、憎いながらも褒めてやりたい気分。だから、阿部サダヲ演じる内匠を悪人だとは思いきれない。むしろ潔く悪役を買って出ている覚悟が見えて、組織人としての矜持を感じた。
さておき、白石監督なので、おそらく必要以上にドッカンドッカンとやってくると思ったら案の定だった。しかも城下に入るのにそんな谷底の深い川に架けた橋しかないんかよ、と突っ込みも入れたくなる。べつに、ひと山向こうに迂回すればいいだけの話だがそれを言っちゃ野暮。
エンタメとしては、殺陣が存分に楽しめた。当然、この監督なので首は転がすわ、腕もぶった切るわ、指も飛び散る。仲野太賀の迫真の演技には目を見張った。が、それにも増して、おや?このおっさんいい声してるな?と気にかけた白髪頭が、見事な太刀裁きを見せた。あとで調べると、なるほど時代劇でさんざん切られ役をしてきた東映剣会の凄腕のようだ。伏せてきた正体(名乗ったときに、ああそれなら!と膝を打った)さえも存分に納得できる腕前。
史実にのっとったとはいえ、エンタメ寄りだと思えばいいかな。
伝統の時代劇
七人の侍から伝統の、少数で多勢の悪と戦うという時代劇。
10人の罪人が時間稼ぎするために砦を守るという流れ。
よくある展開。
色んな罪で囚われているが罪人は思ったより悪い奴らではない。
山田孝之のやさぐれ感がなかなかいい。
今回の罪人達は個性があるようでその辺りの話は割愛されており、感情移入も特に出来ず、11人全員の見せ場もある訳ではない。
活躍する者しない者の差が激しくアクションシーンも悪くなかったがその点はずっと気になる。
せっかくの150分超えの上映時間なのに勿体無い。
それぞれ強みを活かした個性ある戦いを見せてくれたら尚よかった。
今回は悪役という悪役はいないが阿部サダヲがその役回り。
全編通して役者陣が素晴らしいが言うまでもなくMVPは仲野太賀。
最後の殺陣の迫力がすごかった。
時代は幕末だが現代に通ずるもの有り。
賊の意地
戊辰戦争の最中、勢いを強める新政府軍との闘いで劣勢に立たされた幕府軍。闘いの前線にされそうな新発田藩の溝口がある作戦を企て…。その駒として砦を死守することとなった罪人達の物語。
それぞれに重罪を犯した死刑囚達。しかし、ある作戦に身を投じれば無罪放免を言い渡され…といった所から本筋が始まっていく。
登場人物は多いものの、皆キャラが立っていてわかりやすく良い感じ。
何物でもない一般人(重罪人なのでそうは言えないか…)達が、官軍を相手に見事な作戦で闘う様は、唸らされると同時に大迫力。
ここでの敵は官軍でありながら、こちら側は罪人と藩という構図で、中々一枚岩とならない描写も見応えアリ。…そうそう、無罪放免といってもやっぱりね。。
そんなこんなありながら、アクションシーンは大迫力‼…の合間に見せられるドラマパートはちょっとテンポがよくなかったりしたり、やはり2時間半超えの尺はどうにも長く感じてしまったり。
あとは、賊の意地だなんだとカッコ良い言葉を並べても、アンタ何度も皆を…。
感情移入するにはちょっとアレな主人公だったのが少し残念。でもまぁ罪人なわけだし、キレイに描かれていてもそれはそれででしょうかね。また、最後の殺陣は流石にちょっとやり過ぎなような…。
と思う所はちょくちょくあれど、圧倒的に不利な状況を知恵と腕っぷしで戦い抜く決死隊の姿には熱くなったし、誰もが生き残って欲しいと思える程良キャラ揃いだったのはとても良かった。
総じて、とても面白い作品でした。
単純な物語ではないところがいい
長丁場に耐えうる各役者の演技
そのリアリティに感心
リアルでしたね。主人公が全然被弾しないどこぞの国のヒーローものと違って、ちゃんと死亡•負傷します。十一人で軍隊に対抗できるわけが無いとも思いましたが、そこは地の利を活かした説得力のある戦略で乗り切るところも面白かった。その戦略により自軍もダメージを負うところもフェアに感じました。
勧善懲悪でないところも良かったですね。この映画に完全な悪は登場しません。皆それぞれの立場において良かれと思える事を全力で成し遂げようとします。たまたまその事が他者の犠牲を伴うだけの話であって、この時代ではよくある話であったと思われます。
とにかくリアリティに富んだお話で、よく練れていると感心しました。
最後に仲野太賀さんの殺陣、凄く頑張ってましたね!
重いですね…
生々しい戦いのシーンが多く、「ずっとこんなシーンが続くのか…?」と少し心配になりましたが
ラストに向け、怒涛のような、ありとあらゆる感情の波が押し寄せてきて、大変なことになりました。思い出しても、目頭が熱くなります…
そして阿部サダヲを、本気で恨みました…笑
そのくらい入り込んでしまいました。
そういう時代もあったんだよね…とか
生まれる時代が違ったら…とか
貧富のさとか、生きるとはとか いろいろ考えさせられました。
罪人たちの背景をもっと知りたくなりました。
ザッツ・ジャパニーズ・エンターテイメント‼︎
全456件中、61~80件目を表示