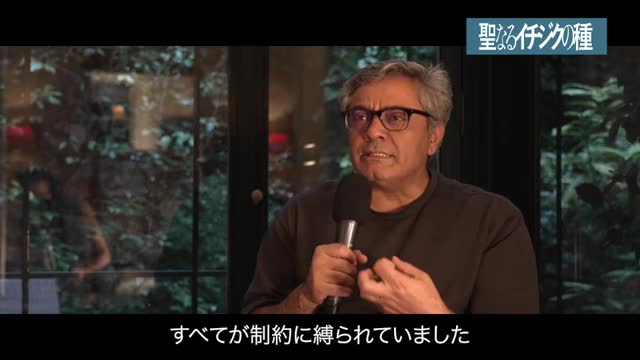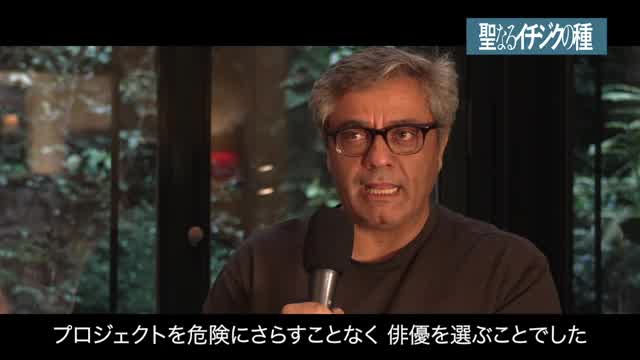聖なるイチジクの種のレビュー・感想・評価
全122件中、81~100件目を表示
決死の覚悟で作られた映画
アカデミー賞の国際長編映画賞にノミネートされ、日本でも先週から公開され(上映館がかなり少ないが)ジワジワと評判高まってるようなので鑑賞。かなりの長編でしたが前半はイランのちょっと豊かな家庭の情景とスマホ画面で差し込まれる実際のデモや暴動のシーンに引き込まれ、後半は拳銃紛失後の捻れた家族の関係が崩壊に向かうサスペンスに打ちのめされ、衝撃のラストで息が止まってしまいました。
夫のイマンは20年真面目に仕事し判事手前の調査官になり家族にも広い官舎に住まわせる事が出来たが、機械的に死刑を宣告するような仕事に神経をすり減らしてしまい、拳銃がなくなってからは家族の信頼を裏切る行為(友人に尋問させる等)がエスカレートする。妻のナジメは夫の体を心配し立場も尊重し娘たちに厳しくあたるが同時に母として彼女たちを守らなければいけないので葛藤に揺れる。長女レズワンは今起きていることに対し正しい意見が言える新しい考えの女性だ。次女のサナは子供だと思っていたが実は冷静に社会と両親を見ていた。彼女が拳銃を隠した理由は不明だがイマンが家族を疑い卑劣な行為を繰り返す中で自分自身の正義が芽生えてきたのだろう。結果、どうしようもない悲劇となるが、モハマド・ラスロフ監督が伝えたいイランの今の真実なのだと思う。
監督は国家安全保障関連の罪で実刑判決となるも命がけでイランを脱出し遠隔で映画を完成させたとのこと。又室内以外の街や車の中での撮影はロケなど組めないので全て盗み撮りとのこと。映画のスタッフや俳優も撮影終了後は逮捕リスクがあるのでイランから出たがナジメ役の女優は捕まってしまったらしいです(町山智浩氏のコラムより)。
決死の覚悟で作られた映画です。アカデミー賞獲って欲しいです。
脚本が凄い
ドイツ代表作品
第97回アカデミー賞では“ドイツ代表作品”として国際長編映画賞にノミネートされた本作。監督の来歴をWikipediaなどで確認すれば判る通り、大変厳しい状況下でも諦めることなく「表現」し続け、いよいよ祖国を離れドイツへの亡命したニュースなどを聞いていたこともあり、非常に興味深く待っていた作品です。TOHOシネマズシャンテ、サービスデイ10時15分からの回はそこそこの客入り。
2022年にイランで起きたマフサ・アミニさんの不審死が発端となり、その後イラン全土に発展したイラン反政府デモが背景となる本作。作品内でも時より、当時SNS等で発信・拡散された動画を織り込みながらの映像は非常に生々しく、目を覆いたくなるシーンもありますが、作品を観終わればむしろ同国に対する「興味」がより深まること必然です。
良く練られた脚本はドラマ性が高い上に、当時のイランの状況や問題がよく解る内容で、リアリティーを強く感じさせるフィクションに仕上がっています。そして、作品内における女性、特に若い世代のセリフの一つ一つが芯を喰っているからこそ、旧態依然としたままのさばり続ける男性、権力、ひいてはイラン政府に対して「NO」を突きつける強い意志が感じられます。勿論、メッセージ性だけでなく物語りとしても非常に面白く、特に作品の中心となる一家それぞれのパーソナリティと、夫の「職業設定」が絶妙です。そして、夫・妻・娘たちそれぞれの群像劇で動き出すストーリーは、ある「事件」をきっかけに全方向に対して疑心暗鬼。中盤以降は「一体どこへ向かうのかと」とくらくらするほど予測不能な展開はスリル満点で、上映時間167分とやや長めの尺ですが、ダレることなく最後まで目が離せません。
勿論、イスラム教やヘジャーブ(ヒジャブ)のことなど、Wikipediaを斜めに読んだ程度のにわか仕込みで物は言えませんが、抗議デモにおけるスローガン「女性、命、自由」が強く印象に残る一方、どの世界にも共通する「ダメな男達」の存在に改めて、他山の石としなければ思う私は、モハマド・ラスロフ監督と同世代(正確には一つ年上)。。実に素晴らしい作品だと思います。
聖戦
期待していた作品だが、ちょっと散らかった印象。
冒頭、ナジメに銃を見せるイマンの指が引鉄にかかっているのが凄く嫌…
序盤は主人公家族に加え、過熱する抗議運動とそれに対する弾圧の様子が、実際の映像を交えて描かれる。
しかしこれが、あくまで背景にしかなっていない。
家族の誰かが関わることもないし、サダフの件も途中から忘れられるのに、力を入れ過ぎでは。
職務に対するイマンの葛藤もあまり伝わってこない。
中盤を過ぎてようやく銃の紛失が起こる。
家族のために出世や保身を望んでいたかに思えたイマンの、ナジメ曰く“本性”がここから顕在化していく。
その目的は銃からウソへ、そして罪へと移り変わり、行動はエスカレート。
家族へのそれもだが、故郷への道程で出くわす夫婦に対する蛮行はイカレてます。
最も印象的だったのは、ナジメの母性。
家族第一主義でありつつサダフを冷酷に扱いきれないのは、“娘の友達”だからではなく“誰かの娘”だからだろう。
夫への「服従と信仰」を捨て、最後まで“母”であった彼女が主人公では。
銃を盗んだ動機はぼんやり想像できなくもないが、いつ存在を知って、どう盗んだかは不明。
(主題でないのは分かるが…)
最後の鬼ごっこや落下はコメディに見えてしまった。
あそこで終わりというのも半端だし、ここまで長尺にする必要があったかも疑問です。
とはいえ動きのない話で緊張感を途切れさせない演出や演技は見事。
もう少し重心を明確に短く纏まってれば秀作だった。
167分は長い
原題のdāne-ye anjīr-e ma'ābedのうち、anjīr-e ma'ābedとはインドボダイジュのことで、学名または英語ではFicus religiosaまたはsacred fig と言うそうですが、これを「印度菩提樹の種」と訳さず、あえて英単語を単語レベルで翻訳するに留めて、「聖なるイチジク」と訳したのは素晴らしいと思います。「印度菩提樹の種」というタイトルだと、どうしても仏陀が悟りを開くイメージを持ってしまい、父親が狂気をおびるようになる、この物語とは真逆のイメージを持ってしまいますから。また、anjīr-e ma'ābedを単語レベルで直訳したところで「寺院のイチジクの種」となり、あまりキャッチーではない気がします。「聖なるイチジク」とのタイトルは神秘的で実に秀逸です。
なんでもこの印度菩提樹は、他のイチジク属と同様に絞殺しの木になることがあるそうで、本物語も冒頭にその旨のメッセージが流れ、物語が始まります。あたかも鳥によって宿主の樹上に落とされた種子が発芽し、根を伸ばし、宿主の表面を覆い、宿主が枯死し、木の中心部に円筒形の空間を残すかのように、父親に支給された拳銃、あるいはその弾丸が彼あるいは彼の家庭に根を伸ばし、彼が理想としていた伝統的な家庭を失わせしめ、最後には……という物語ですが、まさに絞め殺しの木の物語だと思いました。最後にはご丁寧に穴まであきましたし。
物語に登場する人物は、中流以上の家庭に属する、裕福ではあるがごく普通の人たちばかりでした。そのような家庭の父が最後には狂気に走ることになり、ボタンを掛け違えると誰もがそのようなことになることを痛感します。日本でも、テレビのニュースで重大事件を扱った際に、「あんなことをする人には思わなかったんだけどねぇ」などと近所の人たちが話していることが思い起こされます。劇中で彼や彼の奥さんがイスラム的価値観を大切にする様子や、彼がイスラム体制側の人間として描かれていることから、だから宗教は危険なのだとのイメージを持ちがちですが、彼があのような狂気に走ったのは、上司からの無理な指示に従わされることで次第に心がすり減っていき、貸与された銃が盗まれたことから出世の道を断たれ、収監される恐れを感じたという非常に世俗的なことから狂気に走っています。まさに私たち日本人にも同じように起こりうることだと思います。
物語の冒頭で取調官(字幕では調査官となっていますが、bāzporsは検察官の指示のもとに取り調べや証拠の収集に従事し、必要であれば起訴状を書いたりする役職ですので、取調官のほうが適切な気がします。実際、終盤で彼が娘を取り調べる際にはbāzporsから派生したbāzporsīの語が使われているのですが、字幕でも「尋問」となっています。「調査」ではありません。また職場についても全てのセリフが字幕では「裁判所」となっていますが、dādgāh-e enqelābの時は革命裁判所でよいとして、dādsarāと話している時は常識的に考えて検察庁としてほしかったです)に昇進したイーマーンが、検察官が死刑の求刑を求めている案件で、ろくに記録の検討もしないまま起訴状にサインなどできないと言っていたのに、最後は娘たちに対する尋問をするのですから、その変化に恐怖を覚えます。
母親のナジュメについても自分たちの今の生活を守るために精一杯という姿が伝わってきます。夫のキャリアに傷がつきそうなときは、娘たちを叱り、たしなめる一方で、娘の友達が抗議デモに巻き込まれて顔に散弾を浴びた際には、その散弾を取り除いてやるという母性にあふれた行動にでますが、散弾を取り除いた後は、やはり今後の自分たちの暮らしを考え、娘の友達を家から追い出します。その際には散弾を受けた顔が見えないよう、顔にスカーフをかけて隠すようにしますが、それとて彼女をいたわってのことではなく、近所の人たちに見とがめられ、夫のキャリアに傷がつくのを避けるためだったりします。もっとも、自分も同様の立場に立たされた場合に、はたして人道主義的な行動に出られるかと考えると、ナジュメと同じような行動に出る恐れがあるので、彼女を責める気持ちにはなれません。
イーマーンにしろナジュメにしろ宗教的な価値観を大切にし、自分たちの生活を平穏無事に送るために努力するという、本当にごく普通の人たちで、私たちと異なる別世界の人間などではないと思います。
娘たちについても、抗議デモに好意的なごく普通の、ありふれた若い世代の人たちとして描かれています。マハサー・アミーニーさんがお亡くなりになった際にBBC等の番組を見ていた時に、若い世代の女性たちが頭からスカーフを外して町中を練り歩いたり、スカーフやホメイニーさんの写真の印刷された教科書のページを燃やしたりしている姿を目にし、若い世代の人たちはすごいなあと感じたことが思い出されます。
この世代間のギャップといったものも映画では見事に表現されていました。インターネットの発達でより簡単に外国からの情報にアクセスできるようになった世代からの「なぜイスラムでは~」という問いに、論理的な回答をできない親世代。個人的にはヘジャーブについては、守りたい人は守る、守りたくない人はなしでかまわないという制度になるのが一番だと思いますが、イラン政府にとっては難しいことなのでしょう。
全部で3時間足らずある本作の約3分の2が、物語の舞台設定説明、つまり当時のイランの雰囲気の再現に充てられています。消えた拳銃に関する物語は、実質最後の1時間ほどのみです。恐らくこれは、イラン人ではない私たち外国人が当時のイランの状況をより身近に、具体的に理解できるようにとの配慮なのでしょうが、少々冗長に感じました。もっとも、拳銃が盗まれたことをイーマーンが上司に報告した後の帰宅途中、彼の車の隣に信号で停車した車のステレオからシェルヴィーンのbarāyeが聞こえてきた時には、「あの時期流行ったよね」などとニヤリとさせられましたが。
ドキュメンタリーあるいはzan zendegī āzādī運動(字幕や新聞記事等ではzan zendegī āzādīを「女 命 自由」と訳していますが、zendegī を「命」と訳すのは何とかならないものでしょうか。zendegī というのは、これに「~する」という意味の動詞kardanをつけ加えると「生きる」や「住む」、「暮らす」という意味になる通り、「生きること」を指しているはずです。例えば、lifestyleという英単語は、lifeという単語を含んでいますが、命の形という意味ではなくて、「生き方」や「生活スタイル」という意味ですよね。できれば「女 生きる 自由」などとしてほしかったです。この運動は女が女として自由に生きることを求める運動であって、命を大切にしましょうという運動ではないはずです)に関するラスーロフ監督の政治的な声明や表明ということであれば、評価できるのですが、サスペンスの映画としては正直、少々物足りない気がします。
映画をきちんと見ていない、あるいは理解できていないだけなのかもしれませんが、下の娘が銃を盗んだ動機や方法が分からないまま映画が終わってしまいましたし、また、最後に母と娘たちがイーマーンから逃げようとする際にも車を使って逃げなかったことや、廃墟の中のおっかけっこも、少しコミカルな感じに思えたのが残念です。
最後に登場人物の名前等についてですが、引く音や小さな字を徹底的に避けようとする翻訳者の方の態度が少し気になりました。確かに字幕翻訳の世界では、使える文字数に制限があり、可能な限り引く音等を使いたくないというのもわかりますが、イーマーンをイマン、ナジュメをナジメ、ヘジャーブをヒジャブとされると、その表記が気になって物語に集中できなくなってしまいます。確かに英語至上主義の翻訳者の方からすると、たかがペルシア語風情が英語様に逆らうんじゃない、ビシビシ短くすればばいいんだという判断なのでしょうが、できればもう少し元の言語を尊重してほしいものです。また、監督の名前もラスーロフでなくラスロフと引く音を省くのは失礼極まりないことだと思います。例えば、私たちが日本人として、「タロウ」という名前を「タロ」とされると正直あまり気分の良いことではないのと同様に、ちょっとしたことですが、他の国の人たちの名前に関して、最低限の礼儀を払ってほしいものです。
「女性・命・自由」 2022年のマフサ・アミニの死(ヘジャブの着け...
「女性・命・自由」
2022年のマフサ・アミニの死(ヘジャブの着け方を理由に道徳警察に拘束されて3日後に死亡した事件)をリアルに扱っているので「本物感」が強い。
公式の解説や予告編に「家の中で消えた銃をめぐって家庭内に疑心暗鬼が広がっていく様子をスリリングに描いたサスペンススリラー」とあるが、銃が紛失するのは伏せてた方が緊張感があって良かったような。
でも緊張感はしっかりあって終盤に向けて盛り上がる。
縦長のスマホ映像は本物だろうし、神が頂点の国イランだと私は死刑だろうから想像すると怖い。女性はさらに窮屈だろう。
この映画は、町山智浩さんの解説が参考になる。鑑賞前よりは鑑賞後に見るのが良いかも。"町山智浩 映画『聖なるイチジクの種』『TATAMI』2025.02.11"
娘よりも母親の姿に抑圧の根深さを感じる
この映画の中で、母ナジメはずっと揺れている。
絶対的な家父長制のシステムの中で夫に服従する妻としての自分、娘の身を案じつつ娘の気持ちに寄り添いたいと思っている母親としての自分。その間でずっと揺れ動いている。
娘が自由を欲しがる気持ちを本当は理解しているが、自由を求める代償がいかに大きいものなのか身を持って知っているためにその気持ちに蓋をして、娘たちに旧来の生き方を勧めている。そしてそれは他ならぬ自分に言い聞かせるためでもある。これはある種の諦めであり、徹底した現実主義でもある。
抑圧下でそのシステムに迎合して生きようとするのは自然な防衛反応であり、決して悪いことではない。しかし、そのような人ばかりではいつまで経ってもそのシステムが変わらないのも事実である。
いつかはイチジクの木のように、古いシステムを絞め殺さなければいけない日がやってくる。しかしその代償はほとんどの場合、市民の血である。
イチジクの種が果実を生み出すための犠牲はあまりにも大きい。
現代に生きる、中東の人々の価値観
一昨年「聖地には蜘蛛が巣を張る」というイラン舞台の娼婦連続殺人をモチーフとする映画を見て以来、イスラム社会に興味が尽きないので、今回鑑賞
「蜘蛛が…」で違和感を感じたのは、イスラム社会での女性への圧倒的差別。職場でも家庭でも、女性は男性に従属することを求められる。どんなに能力がある女性であっても、である
そして「聖なる…」でも妻は夫に傅かんばかりに尽くす(途中、親父の身だしなみ&毛染め&シャワーシーンがあったけど、アレいる?)。大学生の長女と、高校生(?)の次女も、家庭では現代っ子らしく親に口ごたえするが、結局母親には逆らわない
ヒジャブをまとった姿は取っつきにくい感じがあるが、家で床に寝転び、喋りながら毛抜きで娘の眉を整える母の姿は何処の国も同じようで微笑ましい
ヒジャブを着用しなかったことで拘置所に連行直後に亡くなった女性(アフサ・アミニさん)に対する抗議デモが頻発し、国中が混乱しつつあるイラン
そんな時、裁判所の予審判事として昇進したイマン。その職務はでっち上げの起訴状を認めるだけの、警察組織の傀儡ともいえる仕事で、それへの不満を隠さない彼は上司には嫌われていて、ようやく認められた昇進であった
裁判所の廊下が画面の端によく映るのだが、引きずられていく収監者、警官に連行される人々、廊下のドアの前にじっと亡霊のように佇む女性(そこで待ってろ!とか言われたのか…?)、裁判所がちょっとしたホラー
裁判所のドアごとに謎の等身大の男性が佇むパネルがズラリと並んでいて、あれ何なの?中東の濃い顔がにこやかに笑っているが、お化け屋敷のよう…
昇進し広い官舎に移れると、妻(ナジメ)は素直に喜びを示すが、夫はこれからもっと意にそまない仕事をせねばならないストレスから逃れられない
反政府組織に狙われることを懸念し、親しい上司に護身用の銃を与えられるが、それを紛失してしまい…というのがメインの筋立て
そこに至るまでが意外と長い。長女(レズワン)が友だちを家に招く、和やかな談笑の居間で娘は密かにスマホで抗議デモをチェック、次女(サナ)学校の制服の注文に行く…日常のシーンが多くて、肝心の銃が出てくるまで1時間はかかったかな?
私達があまり見たことのない中東の人々の普通の生活なので飽きずに見られるが、さすがにちょっと尺長めかなぁ。途中少し眠気が…
銃の紛失が出世の汚点になりかねないので、夫は家族を問い詰め、妻は子ども達の持物を総ざらいさせてまで探す。そこから何故だか、親戚の尋問のプロの男性との面談させられ、それでも銃は出てこない……
作中のデモのシーンは全て本物だそうで、演出ではない民衆の怒りが空気感で伝わる。がんじがらめに縛る神権政治(神のご意思だ、で全て決められる政治体制)への抵抗運動と、アメリカのトランプ政権に象徴されるような大衆的民主主義が、この現代世界にそれぞれ同時に存在していることがまさしく驚異と感じる
それぞれの言い分
77点ぐらい。良かった。
緊張感が続いて引き込まれて観てたけど、少ーしだけダレた167分。
体感的には、そこまで長さは感じなかったけど。
終わったあと調べて分かったのが、実際の事件がベースになっていること。
2022年イランにて、マフサ・アミニさんがヒジャブの付け方が悪いと逮捕されたあと死亡し、イラン政府へのデモに発展、このデモは海外にまで広がった。
全然、知らなかったです。
実際のデモの映像やマフサ・アミニさん本人の写真も使われてます。
イラン政府とデモ隊の衝突は、韓国の光州事件や中国の天安門事件を思い出しました。
監督はイラン政府を批判したとして実刑判決を受け、他国へ亡命し、カンヌ国際映画祭では12分間に及ぶスタンディングオベーションを受けたらしい。
評価は厳しめで、75~80点の間で77点ぐらい、星だと3.5~4の間で3.5で。
もう1回観ようかな…
政治的映画とみるかサスペンス映画とみるか。
衝撃作
信仰と国家への忠誠を重んじる父、家族の絆を重んじる母、正しさを追い求める姉妹を通して、イランの政治体制に対する批判を克明に描いた良作ではあった。
イラン政府の目に余る政治体制の独裁っぷりには驚嘆と怒りを感じた。あんな暴力がまかり通って良いはずがないし、それに準ずる父の仕事も全くもって褒められたものじゃない。神への信仰から善悪の区別がつかず、次第に過激になっていく父の行動に、政教一致の怖さが表されていて感心させられた。
妹の行動は流石に訳がわからないし、父が憤怒する気持ちも理解できる。本人曰く、母が常に父に従わされているという構図を覆すことが動機だとしていた。これは、父をイラン政府、母を国民に置き換えて、国民を暴力で(父は母に対して暴力を振るっていないが)支配する政府からその手段を取り上げることを比喩として示したかったんだと感じた。それを踏まえて考えると、どうしても個人の間でのやり取りに置き換えてしまっては不自然だと思う。父は銃を、母を従わせるための手段としては使っていないし、銃を隠したところで何の問題も解決しない。それどころか、銃の紛失によって立場が危ぶまれる父が怒るのも無理ない。その後の父の行動はどう考えても擁護できたものじゃないが、自身の行動のせいで母や姉が酷い目にあっていることを妹はもっと自覚したほうがいいと思った。
身近な場所からの権威主義の崩壊
預言者『ムハンマド』が、
その下で啓示を受けたと伝えられていることから、
イスラム教では、無花果は聖なる木とされているらしい。
とは言え、本作の冒頭で示される一節は、
聖なる無花果の種が発芽し、
主となる木を巻き込んで成長
やがては主木を滅すというもの。
これはなんの寓意を示しているのだろうか。
2022年9月にクルド人女性の『マフサ・アミニ』が
へジャブの着け方を理由にテヘランで道徳警察に逮捕され、
まもなく勾留施設で意識不明に陥り、
三日後に病院で死亡した事件がコトの発端。
その後、イラン全土で、主に女性による
大規模な反政府デモが発生。
彼女たちはスカーフに火をつけて抗議の意を示した。
この一連の抗議と政府による弾圧の映像は
SNSにアップされ拡散、
本作でも使われている。
そこに映っているのは、
市民に対し散弾銃を水平射する治安部隊。
たとえ暴徒相手でも、
同胞に銃口を向けるのは躊躇いがあるものではないか。
それを何の迷いも無く行うことに戦慄を覚える。
テヘランで妻娘と暮らす『イマン』は長年の貢献が認められ
裁判所の調査官へ昇進。
給与も増え官舎も与えられ、
ゆくゆくは判事への昇格も見えて来た。
その一方、官に属することで
市民からは怨嗟の目を向けられ、
いつ報復を受けてもおかしくはない。
護身用にと支給された拳銃が、
ある日家の中で消えてしまう。
家探しをしても見つからず、
彼は妻と二人の娘に疑いの目を向ける。
貞淑な妻は二十年以上も献身的に夫に尽くしている。
一方の娘たちは女性が抑圧される国の情勢を不満に思っている。
三人とも、銃の行方は知らないと頑なに否定する。
そんな中、『イマン』の個人情報がネット上にアップされたことで、
彼は家族ともども身を隠す決断をするのだが、
次第に精神的に追い詰められていく。
〔シャイニング(1980年)〕を思わせる
「狂気に囚われた夫/父親」の構図がここでも現出する。
霊に取り憑かれた訳でもないに、
家族に対しての執拗な行為は
傍目でも異常な上に、目的すら判然としない。
やがて悲劇的な結末を迎えるも、
これは最小単位である家族に仮託し、
国の行く末を描いて見せたのではないか。
身内に刃を向けることの
普遍的な帰結を提示したものと受け取る。
三時間近い長尺も、序破急の流れが巧みで
冗長さは感じない。
制作上の制約もあろう、
登場人物も過少、
舞台となる場所も少ないことが
却って濃密な空気を生み、
観ていて息苦しくなるほど。
銃が消えた理由付けは
やや弱い気もするが、
この国に住まう女性の代弁としては成立する。
三界に家無しの状態を目の当たりにし、
国家とは宗教とはを
改めて考えずにはいられない。
抑圧
家族で何しとんの!?
体制側についた家族の苦悩であるなら、サスペンス入れずそれを中心で描けばよかったのに。
●友達じゃなくて、娘がはっきりと反体制側についていた方がわかりやすかったと思う。
家族のためにやっていることが父の苦悩になり、犯罪者となった娘をそれでも守りたい…など?
●銃は雑音でしかない。そもそもなんで銃を盗んだかもいまいちわからない。
そんな親子で銃を突きつけ合うようなことか?変なサスペンスが始まったあたりで
うんざり…。
●実際のスマホ画像を半端に挿入するくらいなら、前編ドキュメンタリーでいい。すごくダサく感じる。
ドラマの方法論を間違ったと思う。
タイトルなし(ネタバレ)
前半の社会派の展開から後半一転してカーチェイスからの『シャイニング』的展開になるのは驚いた。監督はキューブリック好きだとみた。前半パートがちょっと長く感じたが今思うと後半への振りだったんだろうな。
途中出てくる男女2人組が以前あおり運転で話題になった人達みたいで笑いそうになってしまった。
25-026
父親
が悪いみたいになってるけど、そうなんでしょうか?確かに子供や母親を監禁したりするのは行き過ぎだけど、判事を目指して邁進して、管理が悪かったとは言え貸与された銃を隠せれて、あれだけ困っているのに出さない娘もどうかと思う。世相や時代もあるでしょうけど、親子でキチンと話せればこんな問題も起こらなかったかも。もちろん死ぬことも。
全122件中、81~100件目を表示