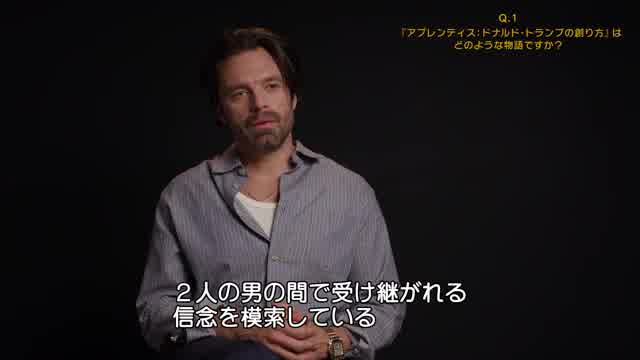アプレンティス ドナルド・トランプの創り方のレビュー・感想・評価
全49件中、21~40件目を表示
若き日のトランプを描いた作品ですが……
大統領であるドナルド・トランプの若き日を描いた作品……なのですが、トランプ自身というよりは彼に絶大な影響を与えたロイ・コーンの評伝になっていますね。
ロイ・コーン自身の強烈な考え方や行動様式を身に着けたトランプが財力を蓄え力をつけていくとともに、老いと病で影響力を失っていくロイ・コーンの対比は素晴らしかったです。
ある種のピカレスクコメディとしても楽しめる映画になってはいるものの、本作がコメディたりえないのは、そのエンディング後が実社会と地続きで、笑えない結果をもたらしているからでしょう。
けっこうよかった
トランプがぺーぺーだったころから大物になり上がるまでを描く。先輩の弁護士が全部仕込んで抜かれていくのが悲しい。お兄ちゃんがかわいそう。奥さんもかわいそうだった。我欲しかないゲス野郎で、近づいちゃいけない人物だ。そんな感じを容赦なく描いていて素晴らしい。
全てはアメリカの為に 〜 3つのルール
70年代のニューヨーク、青年ドナルド•トランプ( セバスチャン•スタン )は、マンハッタンの会員制高級クラブで弁護士ロイ•コーン( ジェレミー•ストロング )と知り合いになり、圧倒的勝者となる為の3つのルールを叩き込まれる。
未だ何者でもない青年ドナルド•トランプが、弁護士ロイ•コーンとの関わりの中で、日々何を思い、より高みを目指し時代の寵児となっていったのか。
ドナルド•トランプを演じたセバスチャン•スタン。まるで若きドナルド•トランプの私生活を覗き見しているかのようでした。
また、ロイ•コーンを演じたジェレミー•ストロングの冷徹な眼差しや言動は、ロイ•コーンという人物が持っていたのであろうカリスマ性を十分に感じさせる名演でした。
セバスチャン•スタン、アカデミー賞主演男優賞受賞🏆、ジェレミー•ストロング、アカデミー賞助演男優賞受賞🏆でしょうか。
想定以上に赤裸々な内容でしたが、演技は勿論の事、作品としても見応えがありました。
ドナルド•トランプが目指すアメリカの未来像とは 🇺🇸
-感覚が鈍るのは嫌いだ
映画館での鑑賞
大統領トランプ Episode0
まず、この映画を製作し、公開できた自由の国である、偉大なアメリカに敬意を表したいと思います。
素直に、彼我の差を感じてしまいました。
また、大統領選挙の時には日本公開が難しかったのでしょうが、
トランプの当選の方に賭けた日本の配給社に、感謝を示すために映画館で観ました。
ただし、最前列で見たのですが、残念ながら音響があまり良くなかったと感じながら観ました。
どこまで真実なのかはともかくとして、
ラスト前のコーンの葬式と、トランプの美容手術のカットバック、および、
ラストのライターに、「勝つための3つのルール」を自説として披露するのには、物語としてしびれました。
でも、トランプが妻と不仲になる過程は、唐突に感じました。
(「市民ケーン」の不仲になる描き方は納得できました。)
また、コーンに送ったカフスボタンが安物だとわかるのは、コーンはそれを知らず、映画鑑賞者のみに安物であることを知らしめる方が私の好みでした。
最後に、さすがに作品賞にはノミネートされなかったものの、
主演のセバスチャン・スタンと助演のジェレミー・ストロングがアカデミー賞で各々の最優秀賞に当選しますように。
第47代アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプは悪魔か天使か“人間”か?
脚本家のガブリエル・シャーマン曰く、
「ドナルド・トランプとロイ・コーンが密室で交わした会話は私が創作したもの。しかし、この映画はドキュメンタリーではありませんが、本人を知る方々にはリアリティを感じてもらいたかった。」
と語る様に、非常にリアリティを感じられる脚本に仕上がっている。
セバスチャン・スタン演じるトランプは非常にリアルだ、そして“人間”トランプが作り上げられていく姿を見事に演じている。途中からは本当に若き頃のトランプはこんな“人間”だったのではないかと思えてしまうほど。日本人が報道で接し見聞きしているトランプそのものに見える。
そして、そんな“人間”トランプにも若造だった頃があり、今のトランプが出来上がった全てが語られている・・・様に感じてしまう。
しかし、この作品を見たからと言って、決して「トランプの事がわかった」などと思ってはいけない。
大統領選挙に勝利はしたかもしれないが、トランプが思っているほど世の中が思い通りになろうはずは無い、もし思い通りになるなら一次政権の時にもっとマシな政策が実行できたはずだ。
ドナルド・トランプが悪魔か天使かそれとも人間か、これからその本性が現れる事になるが、一つだけ言えることがある。それは、第二次大戦後アメリカを中心として長い年月をかけて築かれてきた民主主義の良識が崩壊させられたという事だ。中国やロシアに多大な関税や制裁が課されたとしても先制主義国家の独裁者達にとって、これほど喜ばしい事は無い。
そして、あまりにも罪深い男・・・。
ヤフーの「みんなの意見」現在7万人余りが投票しているが、40%近くの人がどちらかというと期待しているという意見に正直驚きを感じている。
あれだけ、トランプ政権を望ましく無いと報道していた日本でも、こんなにも多くの人達が少なからずの期待をもっていたという事実。日本が分断されない事だけは祈りたい。
そして、トランプ強権政権に尻尾をふりふりしている、企業や政治家達の4年後は注視したい。少なくとも4年後にはトランプ政権は終わる。
その時に総括する為にも、この作品を視聴する事をすすめる。
奴を救ってやれ
こないだ鑑賞してきました🎬
トランプの伝記映画ということで、どんなものかと思いましたが…なかなか良かったです😀
トランプを演じたセバスチャン・スタンは、髪型から雰囲気まで忠実な再現度😳
最初は苦境に立たされた青年だったはずが、やがて大物実業家に変貌。
ナイーブさはどこへやら、後半は横柄な感じになりつつ、実績も重ねた男を巧みに表現🤔
悪名高いロイ・コーンを演じるのは、ジェレミー・ストロング🙂
まだ青年だったトランプに目をつけ、3つのルールを伝授。
彼の相談役として、行動を共にしますが…段々と手に負えなくなります。
更に新たな問題も浮上し、ロイ自身も追い詰められ…。
前半と後半の演じ分けは見事でした😀
イヴァナ・トランプを演じるのはマリア・バカローヴァ🙂
彼女は特別美人ではありませんが、なぜか惹かれる魅力がありますね😀
トランプの猛アタックに根負けした彼女ですが、時とともに距離が開いていきもどかしさを抱える羽目に。
こういう状況ではありがちなのでしょうか🤔
知っての通りトランプは大統領に返り咲いたわけですが、彼の存命中にこの映画を公開できたのは興味深いですね😀
実際に襲撃されたりしてる彼ですが、直後のパフォーマンスを見るにタフなのでしょう。
プロモーションが大変だったという話がありますが、公開禁止にならなくて良かったです🎬
セバスチャンのなりきり具合だけでも、見る価値はありますよ👍
意外や意外、おもしろかった。ぜひお勧め
トランプが米国内での公開差し止めを求めたいわくつきの作品。
オリジナル脚本は、ニューヨーク・オブザーバー紙で不動産担当の駆け出し記者だった頃からトランプを取材してきた、脚本家で作家のガブリエル・シャーマン。
監督は、事前に知らなかったがあの怪作『ボーダー 二つの世界』を撮ったイラン出身のアリ・アッバシだった!
こちらは製作の意向だろうか、米国政治とは関係のない人物をと幼少期をイランで過ごしヨーロッパに移住したイラン系デンマーク人のアッバシに白羽の矢が立ったようだ(以上、脚本と監督の項はjiji.comの豊田百合枝氏の記事より構成)。
アプレンティスとは、見習い、実習生のこと。
小生は観たことはないが、トランプが「お前はクビだ!」と叫ぶのが人気を博したリアリティ・ショー番組のタイトルが『アプレンティス』だったらしい。
つまりは、若き日のトランプ"実習生"を「ああいう悪党」に創り上げた先輩悪党との半生、という物語だ。登場人物のほとんどと、公知のエピソードは実在であり事実であります。
先輩悪党とは、悪辣な手口で裁判を闘う弁護士、ロイ・コーン。トランプの後ろ盾、あるいは「教師」として彼をレッスンしていくが、最期は不法行為で弁護士資格を剥奪され、その直後にエイズを原因とした複合疾患で命を落とす。
公式サイトのインタビュー映像でロイ・コーン役のジェレミー・ストロングが語ったことがこの作品の本質を見事に言い当てている。
「モンスター(コーン)が別のモンスター(トランプ)を生み出した、フランケンシュタインの物語なのだ」
そう、フランケンシュタインとは怪物のほうじゃなくて、それを生み出した博士のほうだ。そして自分が生み出したモンスターを制御できなくなって復讐されてしまうんだっけ。
---------------------------------------------
さて、選挙戦の結果でただでさえ胸糞悪い小生としては、He'll make America stupid again.などと呪詛を吐いているのに、何をわざわざ映画館に足を運んで最悪な気分になろうとするのだ、と思いつつ、なぜかチケットを取ってしまった。
うーむ 意外や意外、かなりおもしろかったw
まずトランプ役のセバスチャン・スタンが見事である。
これは特殊メイクではない。そもそも横顔が似すぎていることもあるけれど、外見だけの話ではなく、あの喋り方や間の取り方まで徹底的に研究して演じている。
後半になって肥満し、顔も丸くなっていくのも、役者として体重を増やしたとのこと。
ただ、このやり方はトム・ハンクスも鈴木亮平もいろいろな役者がやっているけれど、後年に糖尿病発症のリスクが非常に高くなるらしいので、特殊メイクでもいいよ、もう、と言いたくなる。
また、ロイ・コーン役のジェレミー・ストロング。
すでに何年も前に故人となったこのロイ・コーンという人物の振る舞いを映画が公開されたこの2025年時点で実際に見たことのある人はほとんど居ないだろうが、これまたジェレミー・ストロングの鬼気迫るクールな演技には脱帽である。
妻イヴァンカ役のマリア・バカローヴァも併せ、この3人の存在感はこの作品を「政治&セレブ・ゴシップ作品」に堕すことなく、かつ、すでに周知のネタバレエピソードをなぞるだけにもせず、見事なドラマに仕立て上げている。
役者、脚本、監督。三拍子揃えて最高のモノを引き出した製作。
もう一回、観に行こうかな。
---------------------------------------------
トランプはなぜ公開されたくなかったのか?
そりゃあ彼をのし上がらせた悪徳弁護士ロイ・コーンとの関係や、夫人との不仲説や、父親との確執や、兄を見放した件など、いろいろ白日のもとに曝されたくはないだろう。
よくよく考えてみりゃ、誰だって家族の恥部は曝されたくない。ダーティな野郎だというイメージを拡散されたくない。
でも、小生にとって非常に印象的なシーンはそこではない。
まず、駆け出しヒヨッコのドナルドは、最初は自信なさげで、父フレッド(こちら悪徳不動産業者)の会社で生活困窮者から家賃を取り立てる汚れ仕事に辟易し、法廷闘争で綱渡りになると狼狽しながらコーンの助けを懇願する。それも一度ならず二度三度と。
そして行政であろと司法であろうと相手の弱みを握った脅迫を奥の手として使うコーンに「これは違法だろう。こんなことをしていいのか?」と心配そうに言う。
そう。あいつも良心があったのだ、かつて。
もう一つ。
旅客機パイロットになったことで父とともにトランプが侮蔑し、避けていた兄のフレッド・ジュニアがアルコール依存症の影響で急死したあと、豪華な自宅のベッドで妻イヴァンカと並んでぼんやりとテレビを見ているシーン。
隣で慰めようとするイヴァンカを
「俺を見るな。俺に触るな」
と嗚咽しながら拒否する。
これはどちらも、これまでの人生でずっと「天性の勝負勘がある」「頭が良い」「何事にも動じない最強のマッチョマン」を自認してきたドナルド・トランプにとっては「弱々しいドナルド・J・トランプ」であり、受け容れ難いシーンだろう。
---------------------------------------------
そして小生がもっとも衝撃を受け、かつ、答が出せないシーンは次の2つだ。
最初は、死期が近づくコーンのために一度は決別したトランプがコーンの誕生会のディナーを催す。トランプからコーンに贈られたダイヤを散りばめたカフスボタン(しかしそこに「Trump」と彫刻が入っているのが笑えた)。
孤独感と死の恐怖で弱っていたコーンが感極まったようにそれを眺めていると、隣席のイヴァンカが周囲に聴かれないように
「偽物よ。ダイヤじゃなくてジルコニア。ドナルドはそういう恥知らずなの」
と残酷にも囁く。ショックを受けるコーン。
まず、それは本当なのか?
小生には、かつてトランプと結婚する直前にエグい「結婚契約書」を持ってトランプとの席に同行してきたコーンに対する意趣返しとして(しかも何十年も前からの執念として。おおこわ)、そして夫を自分と同じモンスターに育て上げたかつてのモンスターである彼を、肉体的な死の淵からさらに精神的な死の淵の絶望に叩き落とすためのウソであって、実は本物のダイヤだったのではないか。
あるいは、全く逆に、つまりまさに偽物である可能性もある。
トランプが自分でそういうプレゼントを手配するわけはなく、恐らくイヴァンカに丸投げしていたと思えるが、イヴァンカが手配するなら、どうせトランプなんかには見抜けまい、と、そういう手の込んだ偽物を発注して、コーンにだけ囁いて辱めることに陶酔したのではないか。
このシーンはトランプ本人ではなく実際のイヴァンカ本人から訴えられそうなくらい問題のシーンだと思う。
そして2つ目のシーンは、そんなショックを受けたあとにコーンのもとに色付きのクリームで星条旗がデザインされたバースデイケーキが運ばれてきて、ケーキを見下ろしながらあの悪党、モンスターが嗚咽する場面だ。
彼はなぜ泣いたのか。
自分が育てたトランプとその妻が、ここまで自分を辱めるのか、という屈辱に泣いたのか。
あるいは、ケーキに描かれた星条旗に「アメリカのため」と言いながら生きてきた自分の半生を重ねて、死を前にした無常観に泣いたのか。
---------------------------------------------
よく出来た映画というのは、すっきりとしたカタルシスだけでは成り立たない。
こうした「答の出ない問い」、それも本質的な問いが放り込まれていて、観た者に「むぅ」と考えさせるから良い映画なのだ。
---------------------------------------------
余談だが、トランプ家の長男として期待されながら別の道を選んだため、父フレッド・シニアとドナルドから辱められ続けた末に亡くなったフレッド・ジュニアの娘、メアリーは、長じて臨床心理学者となり『世界で最も危険な男 「トランプ家の暗部」を姪が告発』という暴露本を書いた。2020年に日米で発売され、日本では小学館が刊行した。
Beginner's luck
演説で過激なスピーチを続けまくっているドナルド・トランプが少し前にアメリカ大統領に就任する前のお話で、今あるトランプ像を作り上げた人物をどう見せるのかなと思っていましたが、その人物すらも喰ってしまっていました。トランプ恐ろしや。
弁護士のロイ・コーンの猪突猛進な感じで自分が正義を貫き通す姿に強く感銘を受けて自分自身も近い感じで立ち振る舞っている姿が現在のトランプの原型だったんだろうなと思いましたし、演説の一つにあった「性別は男と女しかない」発言は若い頃一貫していましたし、コーンがゲイだと発覚してからは煽りまくり罵りまくり騙しまくりと恩人を仇で返しまくってて笑っちゃいけないんですが笑ってしまいました。
自分の欲に素直でやりたいことは全部やってのけるの精神で行動しているので、その直向きさは見習いたいものですが、こうはなりたくないと本能で思わせてもくれるので本当不思議な人物だなと思いましたし、この人に惹かれる人がいるのも分かるなとなりました。
映像が古き良きな感じでタッチとしてはドキュメンタリーに近い形なんですが、当時の様子を違和感なく味わえるという点で長所になっていたなと思いました。
音楽もアッパーチューンなものからしんみりしたものまで幅広く揃えられており、聴きごたえのあるものに仕上がっていました。
ジェレミー・ストロングとセバスチャン・スタンの演技合戦は見応えしかなかったです。
トランプの生き写しでは?と思うぐらいセバスチャン・スタンのトランプ感が凄まじかったです。
そりゃトランプも激おこなわけです。
脂肪をとったり、毛を増やす手術の違和感だったりはありましたが絵面の痛さとそれを臆することなくやるので、実際にやったんだろうな…という気分にさせられるのが不思議でした。
自伝を書いてくれと頼んだ作家に書くことがあんまないと困らせるところは最高に笑いました。
こんだけ波瀾万丈の人生を渡り歩いているのに書くことないんだ…と当人も困惑したはずです。
今後アメリカがどんな国になっていくのか、日本とアメリカの関係性はどうなっていくのか、パナマ運河はどうなるのか、これからもトランプからは目が離せません。
130歳くらいまで元気に生きそうだなこの人。
鑑賞日 1/22
鑑賞時間 16:05〜18:25
座席 Z-1
ただ最後に勝つために
ドナルド・トランプ
第45代・47代アメリカ合衆国大統領
ニューヨーク・クイーンズ生まれの
自らの名を冠した不動産グループの王
お騒がせスキャンダルやテレビ露出を経て
アメリカではどの層も知らない人は
いない程の有名人
共和党も咬ませ犬的に候補選挙に
挙げたら16人の候補を勝ち抜き
あれよあれよと政治家も従軍経験も
ないながら大統領になってしまった
2025年2期目に再就任
トランプアレルギーの日本のマスコミは
絶賛発狂中である
ざまあみろ
そんなトランプの若いころから
5番街に今でもそびえ立つトランプタワー
を構えアメリカを強くする野望を持ち
成りあがるまでの自伝的映画
どうだったか
常にノイズの乗った70~80年代の
ニューヨークの世界観に
セバスチャン・スタンの
仕草まで完璧に再現した演技
まさに赤裸々に
現職大統領の過去としてここまで
やっていいのか!?とつい
引いてしまうほどの遠慮のない描写
最後まで面白かったです
転がってる〇体を跨いで歩くほどの
治安の悪い1970年代半ばの
ニューヨーク
不動産王の父フレディの会社は
そこに建設したアパート群に
黒人の入居を断ったとして
政府から訴えられていた
そんなフレディの四男に生まれ
兄フレディJr.はTWAのパイロット
ドナルドは父の会社でアパート群の
家賃回収をする毎日
ドナルドはその貧困層の
支払いの悪さに
訴訟に負け入居を許したら
会社が破綻するのは目に見えており
有数の財界人がいる高級クラブに
入り込みロイ・コーンに出会います
ロイはウォーターゲート事件で
辞任したニクソン大統領ともパイプが
あるほどの辣腕弁護士
ソ連のスパイ活動を行っていた容疑で
死刑判決が下っていたローゼンバーグ
夫妻をほぼ自白だけの証拠で
死刑に送ったとも豪語する
コテコテの反共保守派の性格はアレ
そんなロイにドナルドは状況を
相談すると政府だろうと人権屋の
ふざけた訴訟など楽勝だと言い放ちます
そんな頃からドナルドは5番街の
「コモドア・ホテル」というボロホテルを
買い取り世界一のホテルを建てる
野望をあたためていきますが
銀行にも父にもこんな貧民街にそんな
ものを建ててどうすると相手にされません
ドナルドはそれでもロイにともかく
訴訟の対応を頼み込むと了承され
100%俺の言うとおりにしろと
言われます
そしてロイは「3つの鉄則」
1.「攻撃 攻撃 攻撃」
2.「非は絶対に認めず否認し続けろ」
3.「最後まで勝つと言い続けろ(最重要)」
をドナルドに教授していきます
1.「攻撃 攻撃 攻撃」
政府側のベテラン判事に電話で
さっさと訴訟を取り下げないと1億ドル規模の
訴訟を起こすぞと怒鳴り込みます
2.「非は絶対に認めず否認し続けろ」
裁判に臨み平然と退廷したロイはドナルドに
「これは勝てない」と言います
入居を断った黒人の名前の頭に
「C(Colored)」と書いてあり
人種で分けた証拠が明白だったからです
じゃあどうするんだとドナルドが聞くと・・
3.「最後まで勝つと言い続けろ(最重要)」
ロイは政府側の高官を呼び出し
愛人(同性)とまぐわっている写真を見せ
訴訟を取り下げないとこれがポスト紙に
出回って嫁が知るぞと要求します
ドナルドはドン引きしつつ
ロイが3度自身が訴訟されても
勝ってきたやり口を理解します
あとひとつロイは
「人と論ならば人の方が重要」
「人を押さえれば理屈などどうでもいい」
という「現実」をドナルドに伝授します
ドナルドはロイと訴訟の依頼を
する際に小切手を渡していましたが
ロイはそれをそっくり返してきて
「報酬には友情で応えてくれ」と
ここからタッグを組むことになります
その後ドナルドはぐんぐん
ニューヨークの街を再開発していき
妻イヴァンとも結ばれ成功者の道を
歩んでいきますが
ロイの秘書ラッセルとのあっ…(察し)
な関係なども知るようになって
いきます
そして5番街のトランプタワーの夢
トランプは市の有力者にプレゼンを
行いますがハイアットの支配人に
5番街の発展のためなら
ハイアットの莫大な納税を
チャラにさせるとつい言ってしまいます
困ったドナルドはロイに頼み込むと
秘密の部屋膨大な盗聴テープを
取り出してきて5番街再開発にあたり
ハイアットの税金をチャラにする
議決を勝ち取ります
…ひょっとしてニクソンに
ウォーターゲート事件とか
盗聴しまくる癖を植え付けたのは
…いやなんでもない
1980年代半ばに入り
アメリカは減税や規制緩和の
レーガノミクス全開
そしてトランプ・タワー完成も
まだ終わらぬうちにドナルドは
ニュージャージーの観光都市
アトランティック・シティの
カジノなど急速な開発は借金を膨らまし
ロイはやめるべきだと忠告しますが
トランプは徐々に聞く耳を持たず
他の弁護士にも頼むからと言います
ロイはついにじゃあ俺も報酬制に
してくれと言い友情は終わりを
迎え始めていきます
しかしとりあえず完成したトランプタワー
落成式に現れたロイ
そして秘書ラッセルが肺炎になったので
ハイアットで療養させるよう頼んできました
ドナルドは一応了承しますが
ロイも体調が悪そう
その後調べさせると
ラッセルはHIVウイルスに感染していた
事が判明しドナルドはラッセルの退去を
こっそり指示するとロイが怒鳴り込んで
きましたがここで決別は決定的と
なってしまいます
実際トランプは何度も負債が膨らんで
資産を売却したりしていますから
ロイの指摘は間違っていませんが
そのたび蘇ってくるのがドナルド
その後トランプも酒におぼれて
死んでしまった兄から酒はやめたが
多忙から服用していた興奮剤
アンフェタミンによる副作用
過食・インポテンツ・脱毛により
身体はボロボロになっていきます
そもそも医学的な知識はデタラメ
(このへんがCOVID-19の際の
対応も遅れてしまった事にも
影響しているかもしれない)
夫婦仲も最悪になっていき
結局ドナルドは自分の理解者は
ロイしかいなかったことを痛感し
フロリダでロイの誕生日祝いを
しようと連絡しますが
ロイは案の定HIVに感染しており
立てもしない状態でした
ドナルドは接触感染は
ないことを確認しつつ
それでもロイを呼び誕生日を
祝います
その後ロイは程なく亡くなり
ロイが余生を過ごしたフロリダの
大邸宅は徹底して「消毒」されます
その後ドナルドは自身の取材に対し
過去は語る気はないと言いつつ
生きていくのに必要なのは・・
1.「攻撃 攻撃 攻撃」
2.「非は絶対に認めず否認し続けろ」
3.「最後まで勝つと言い続けろ(最重要)」
だと語り話は終わっていきます
最後までドナルド・トランプという人物を
どこか感情移入させるようでさせない
不穏さが逆に画面から目を離させない感じ
批判でも肯定でもないライン
アリ・アッバシ監督の手腕が光っていると
思いました
ヤなやつ
さすがにロッキーとミッキー、ダニエルさんとミスターミヤギ、酔拳のジャッキーと赤鼻の蘇みたいな関係にはいかないよな。
お互いの私欲で出来上がってしまった師弟関係?が大変面白かったです。
ロイが弁護料を受け取らず人間関係の構築に比重を置く所など、マフィアみたいで思わずうなってしまう白眉な場面でした。
詳しくはないまでも、報道で大よそ主人公の完成形がどんなか分かってるだけに、
最後は期待通りしっかりやーな奴になってて、つくりものとして興味ぶかい作品でした。
トランプが成り上がってからの、諸々の裏切りなんか ・・でしょうねと、いちいち納得して見てました。
オーラスの頭皮移植と脂肪吸引オペは醜悪でありながらも、まるでアナキンがベイダー卿なっていくような変な清々しさを感じました。
本当の意図は分かりませんが、アナログTV画像風な画面演出も当時の80年代の雰囲気を醸し出してて興味深いところでした。
コレを制作できるアメリカの土壌って改めて凄い。
楽しめたので及第点。
マスターは誰なのか
すごく気になって観てました〜、ロイコーンの。
以前TVでドキュメンタリーを観たの思い出しても、
その辺の記憶が曖昧で。
ロイの映画もあったら鑑賞したくなる映画でした♪
スターウォーズ風に云うとドナルドさんはパダワンですよね。
思いっきりマスター=師匠をコケにして、闇落ちしてました。
ビデオっぽかったり、フィルムぽかったり、映像効果の色褪せやノイズ、
昔むかしのポップの楽曲も相俟って、ドキュメンタリーに寄せてますが
だまされそうなくらいです。
セバスチャン・スタンさんは名演技です!
2月、5月までバッキーが待てなくて、ノーマークだった本作みちゃいましたが
逆に見逃さなくてよかった、よかった
1970〜90年代のアメリカを知らないと意味不明だと思うので、事前に予習はしておいた方が良いと思います
2025.1.22 字幕 TOHOくずはモール
2024年のアメリカ映画(123分、R15+)
実在の人物ドナルド・トランプの若き実業家時代を描いた伝記映画
監督はアリ・アッバシ
脚本はガブリエル・シャーマン
原題の『The Apprentice』は「見習い」という意味
物語の舞台は、1973年のアメリカ・ニューヨーク
父フレッド(マーティン・ドノヴァン)の会社「トランプ・オーガニゼーション」の副社長を務めているドナルド(セバスチャン・スタン)は、ニューヨークの再開発に興味を持っていたが、父と意見が対立していて思うように動けなかった
彼は、父が作ったトランプ・ビレッジの管理を任されていて、家賃の回収に向かうものの、住人からは冷たい目で見られていた
トランプ・ビレッジは貧困層にも貸し出していたが、人種差別を行っているとして、公民権局から訴訟を起こされていた
理不尽な訴訟だと反論するものの、世間体は厳しく、勝ち目のない裁判となっていた
ある日のこと、会員制クラブを訪れたドナルドは、そこでラッセル(ベン・サリヴァン)という若い男から声をかけられた
彼は「友人が話したいと言っている」と言い、ロイ・コーン(ジェレミー・ストロング)のいるテーブルへと案内した
そこには、マフィアのトニー・サレルノ(Joe Pingue)、実業家のスタインブレナー(ジェイソン・ブリッカー)などもいて、ドナルドは彼らと一緒に飲むことになった
ロイはフレッドが訴訟を抱えていることを知っていて、ドナルドは「いじめだ」と訴える
ロイの友人たちは「彼に頼めば良い」とふざけるものの、ドナルドは本気で彼を頼ろうと考えていた
父はロイのことを快く思っていなかったが、家族会議の末にロイの話を聞くことになり、彼はトランプ家の代理人として、公民権局と戦うことになった
映画は、この出来事をきっかけに、ドナルドとロイがクライアント以上の関係になっていく様子が描かれていく
ロイは「勝つための3つのルール」というものを持っていて、それをドナルドに教え込んでいく
「攻撃、攻撃、攻撃(Attack, Attack, Attack)」
「何一つ認めず、全否定せよ(Admit nothing, Deny everything)」
「勝利を宣言し、負けを認めるな(Claim victory and never admit defeat)」
ドナルドはその教えを忠実に守り、やがてはロイの制御が届かないところまで上り詰めていくことになったのである
物語は、ロイの他にのちに妻となるチェコ人モデルのイヴァナ(マリア・バカローバ)との出会いも描かれていく
会員制クラブに入れなかったイヴァナを助けたことがきっかけで、この恋愛にもルールを押し通していく
だが、結婚制度に異議を持つロイは自殺好意だと激怒する
やむを得ずに「婚前契約書」を交わすハメになるのだが、そんな結婚がうまくいくはずもなかった
やがて、ドナルドの成功とともに表舞台に出ざるを得なくなるイヴァナは派手に着飾ったり、夫の意見を取り入れて豊胸手術をしたりしていく
だが、夫婦の倦怠期はあっさりと訪れ、「もう魅力を感じない」とまで断言されてしまった
ロイとの関係は、仕事というよりもロイの健康面のが原因で、それが全米を襲ったエイズの流行だった
ドナルドはロイとラッセルがそのような関係であることを知っていて、ラッセルの病気がエイズであることに気づいていた
当初、ドナルドはハイアットホテルにラッセルを泊めていたが、偏見はやがて衝突を生み、彼をホテルから出さざるを得なくなった
この行為によってロイとの間に亀裂が生じ、さらにロイ自身もエイズに感染してしまう
ドナルドは距離を置かざるを得なくなり、美容外科医ホフリン(マット・バラム)にも、それとなくエイズのことを聞いていた
やがて、ロイは車椅子生活を余儀なくされ、ドナルドの知らないところでラッセルは亡くなってしまう
ロイは新しい恋人ピーター(Aidan Gouveia)の介助を受けるものの、ドナルドに抱いていた想いも捨てきれずにいた
ある日のこと、ピーターとともに避暑地に出向いたロイは、そこで盛大な誕生日会を催してもらう
ドナルドから高価なカフスボタンをプレゼントしてもらうのだが、イヴァナはそれを「安物だ」とバラしてしまう
ロイは落胆するものの、アメリカの国旗を施したバースデーケーキを前にして、最後の意地を通して、ドナルドと切れることを決意するのである
一般的にカフスボタンは女性が気になる男性に贈るもので、「私を抱きしめてほしい」という意味合いが込められていると言う
受け取ったロイとすれば、ドナルドの計らいに感動するものの、イヴァナの言葉でその意味が逆転してしまう
また、国旗を施したケーキを見て、ロイは「ドナルドの決意」と言うものを感じ取る
それは、これまでにロイが掲げてきたアメリカ・ファーストの考え方を、今度はドナルドが受け継ぐと言う意味合いになっている
それゆえに、ロイは私情を挟むことなく、ドナルドの前から姿を消すことを厭わなかったのではないだろうか
いずれにせよ、実在の人物が大統領選に出ると言う段階で制作されているので、ある種のネガキャンの一歩手前のような映画になっていた
公開差し止め請求が来るのも当然で、かなりプライベートな部分を掘り下げすぎているように思える
ドナルド自身が良くても、故人の名誉を蔑ろにしたり、さらに家族に与える影響というものも大きいだろう
ただし、思ったよりもネガキャン要素は感じられず、ドナルドの人間的な部分と彼の政策に関する思想を尊重しているので、その点は悪くないのかなと思った
この映画はドナルドの伝記であると同時に、これから変わっていくアメリカの方向性というものを表している
なので、賛同者は「USA!」な政策に鼓舞し、その思想にそぐわないと感じるものは反発をするのだろう
ある種の分断が起こっているのだが、民主主義は分断を起こすことが前提になっているイデオロギーでもあるので、今後はマイノリティには住みづらい世の中になっていくのかなと思った
トランプという人間性の難しさ
序盤は若い青年がコーン達から影響を受けて、途中からトランプのキャラクターは性欲、顕示欲、投資の3つしか価値観がないという趣旨の内容が途中から繰り返されていく。そして、そのまま映画は簡単に終わってしまった。おそらく、アメリカの陰謀論や権力闘争の歴史に興味がなければ後半のシーンは全く魅力を感じない人もいるだろう。
私もあまりにアッサリとした終わり方に疑問が出たが……。
トランプが出演しているテレビの関係者と番組の決め台詞を考えたり、経済的な失敗もかなりしている部分は殆ど描かれてなかった。しかし、映画のラストも「投資の芸術家」と言わせたり、そういうビジネスマンという印象が強い通り、トランプとはイメージ戦略に特化した人間であり、それを巧みに扱いアメリカンドリームを掴んだ数少ない人間の一人なのは確か。その意味では正しい映画の締めだったのかもしれない。どこまでが虚構で、どこまでが真実なのか見極められる人はいない。それが分かる映画だった。
ちなみに海外のレビューサイトでは、やっぱり陰謀論について議論されたものが多かったように私は感じた……。
トランプ大統領就任の日に
急に思い立ち、キノシネマみなとみらいで鑑賞。
他人の助言を求めていた青年時代からの変貌ぶりに
観終わった直後はショック状態になったが、
1日経つと「だから大統領まで上り詰めたのか」と妙に腑に落ちてきた。
トランプとロイ•コーンの師弟関係はこれまで知らなかった。
知らなかった世界を知れる、だから映画は面白い。
ラスト、ロイ•コーンの3つの教えを自分は勘が良いからと、
元から自分の考えのように記者に語るトランプ。
セバスチャン•スタンが、作品が進むにつれ、
どんどんトランプに見えてくる…とくに横顔!
ジェレミー•ストロングが演じるロイ•コーンは、
鬼気迫る迫真の演技で序盤から引き込まれた。
これは私自身の願望かもしれないが、
ロイにプレゼントしたティファニーは、
本当に偽物だったのだろうか?
イヴァナからロイへの仕返しでそんな事を言ったのでは…?
トランプ氏に少しでも人間らしさが残っていて、
死期が近づくロイに最後は恩返しをしたと思いたい。
彼の素が垣間見れて楽しめた! 見事な表情ジェレミー・ストロング氏に賞を!
ドナルド・トランプ殿へ
二度目の米国大統領就任おめでとうございます。
この映画を観るまでは そんな気には全く成れなかったでしょうね。
人と言う者は、本性を包み隠さす曝け出して語って
それで評価を受ける物でしょうかね。
中々それは誰しも出来かねる事ですが
大統領に成る人物はそれが成し得てこそかもです。
この映画を観て少しはトランプ氏の人となりを感じ得た次第です。
厳しい試練を日本に投げかけて来るかもですが
それもまた 運命なのでしょう。そんな気がします。
この映画で出ていた
ロイ・コーン(弁護士):演じた ジェレミー・ストロングさんが良かったです。
この表情、この変化。お見事ですね。とっても好演でした。
なんか助演賞をと感じましたです。
そして トランプ氏を演じた セバスチャン・スタンさんですね。
出だしから中々のアメリカの好青年を演じてますね。
とっても良かったです。
最初の奥様との求愛もそこだけは 想いは素敵な感じでした。
一見、中々周囲から理解されない殿方トランプ氏。
でも元々は普通のアメリカの好青年であって
今も彼の中にはそれが存在しているのではと 私は思いたい所でしょうか。
興味ある方は
是非 劇場へ!
ロイ・コーンの怪演がすごい
ドナルド・トランプを、並外れて功名心と成功欲が強いが、利己的で傲慢で、自身に甘く、他者に厳しく、人情が無い、単純で愚かな人物として描いている。人並み以上の成功を求めたために、人並みの幸せを手に入れることができなかった哀れな男としても描いている。
かなりの部分を推測で脚本化している映画とわかるので、この映画を観たからといって、「トランプけしからん」、とはならない。
でも普通にドラマとして面白い。ナイーブな成功欲の高い若者が、ロイ・コーンという怪物に出会い、変貌していく物語。ロイ・コーンの怪人物っぷりの演技は素晴らしい。
ロイ・コーンを、同性愛者でありながら、同性愛に対して蔑視的発言をする、自身が同性愛者であることを認めなかった、複雑な人物として描いているのも面白い。
この映画の核心は、ロイ・コーンの語る「勝利への3つのルール」。どんな汚い、非合法な手段を使ってでも、目的を達成する、というロイのやり方をトランプは目の当たりにしていく。
そして成功者となったトランプは、インタビューで、この3つのルールをロイから聞いたとは言わずに、自分が考えたことかのように語る。ロイから聞いたと言いたくなかったともとらえられるが、むしろ、ロイから聞いたということすら忘れてしまうくらいに自分自身の考えとして一体化してしまった、とも解釈できる。
この映画のトランプは、(もちろん実際のトランプの実像とは大なり小なり違うだろうということは承知で、)利己的な愚かな人間ではあるが、どこか憎めない、共感できる要素もあるように思う。
道徳や良識のごまかしで覆われて見えにくい本音を言ってくれる人物でもあるように思う。兄からもらった子供へのおもちゃをゴミのようにぞんざいに放り投げるシーンは、まるでコントのようで笑えた。
あたりさわりのない言葉ばかりで何を考えているか分からない政治家よりは、悪人でも本音で語ることができる政治家の方がましなのかもしれない。
兄ちゃん
TWAのパイロットという立派な仕事に就きながら、父から蔑まれ息子のうちに数えてもらえなかった、トランプの兄ちゃんにいちばん感情移入してしまった。ロイ・コーンというトランプの人格を作り上げるに影響大であった人物との付き合いも、兄ちゃんの後押しあってのことだったんである。どこか兄ちゃんに支えられながら、父に勝ちロイ・コーンに勝つためには、兄ちゃんの情緒的で優しい部分は切り捨てられなければならなかった。/killerとしてのトランプも父もロイ・コーンも、肉体に裏切られるというところも面白かった。/アメリカ的男性性の毒を描いた作品として、『アイアンクロー』と合わせて見たい作品だと思った。/セバスチャン・スタンの“トランプになっていく”演技がうまかった。
「トランプ圧勝」「レッドシフト」と言われる事の事実関係
・2024年大統領選でトランプは初めて民主党より得票数で上に立った(7800万票近く得票)。ハリスに対して280万票程度上回った。
・なお民主党は2020年8120万票に対して7500万票まで減った。トランプは激戦州で80万票超の新規投票者獲得をした上で200万票超を民主党から鞍替えさせた。残り400万票近くは投票放棄という形で減った(なお第3政党・独立系立候補者が260万票ほどとっているがここも50万票近く減っている)。
・選挙人団の州人数配分は連邦上下院定数を合計したものになっている。この関係で人口の少ない州は最低3人の枠を持っており人口の多い州の意思が通りにくくできている(ワイオミング州だと人口58万人で選挙人団3人。カリフォルニア州は人口4000万人近くで選挙人団54人)。人口の少ない州は大抵共和党支持なのでトランプは16年選挙でクリントンより280万票少ないにもかかわらず「圧勝」した。ゲームのルール、勝者を決める仕組みとしてはわかっている話なのでいいんですが、ただこれを「圧勝」と呼ぶのはデータ見てないだろというしかない。ちなみに2016年と2024年の得票差は近い数字です。
・2024年選挙は投票数が大きく減っていて、それは民主党側の支持層が起こした反応だと見られる。「レッドシフト」と言われるが実態は投票数の減少=民主党支持指標の減少が大きくて得票率の変動はこれに影響されている。ハリスも嫌だがトランプも嫌だという人が400万人近く出た事が「レッドシフト」を大きく見せている。
・『アプレンティス』いうまでもなくトランプが「お前は首だ」で有名になったリアリティショー番組のタイトルでもある。
・トランプの調査報道をまとめた本が訳されている。文芸春秋社『トランプ』(2016)。ロイコーンの話を含めて詳しいのでおすすめです。
むしろトランプ支持者が増えそう
ピカレスクロマン(悪漢物語)としてそれなりにつくられているので、むしろトランプに感情移入する人も多そうな出来上がり。
トランプが嫌いな人は批判的に見られるだろうけど、そうでない人や元からの支持者には、困難を乗り越え、父や恩人さえ蹴落としてのし上がっていくヒーローに見えるでしょうね。
演技陣はいいです。とくに主役は、あのトランプがちゃんと映画の中にいる感じがします。風貌や喋り方までよくコピーしています。
トランプがロイ・コーンの戦術を学んでつくられていったというあたりがストーリーの中心なんでしょうけど、こういう人であることは知ってるし、過去に悪どいことをやってきたのもだいたいわかるので、これならドキュメンタリー映画にした方がよかったのではという気もしました。
ただ、ロイ・コーンが落ちぶれ、信頼できる人が周りに誰もいない状態の末路をたどったのが、将来のトランプの末路だといいたいのかもしれません。
全49件中、21~40件目を表示