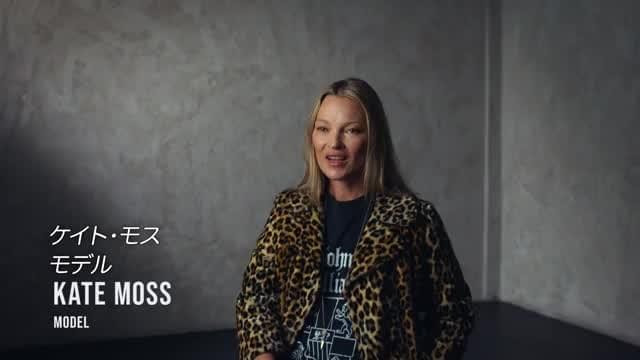ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナーのレビュー・感想・評価
全2件を表示
「気分」で生きることの運命
映画「ジョン・ガリアーノ 世界一愚かな天才デザイナー」を観た時、久石譲さんの本の中の一節を思い出した。
優れたプロとは、継続して自分の表現をしていける人のことである。
さらに言えば、プロとして一流か二流かの差も、力量を維持継続していけるか否かにかかっている。
二流のオーケストラが一流の指揮者のおかげで素晴らしい演奏をできたとしても、その指揮者がいなくなればまた元通りになるのなら所詮二流止まり。
ラーメン屋でも寿司屋でも、客を満足させる味を維持継続し続けられる店だけが、一流店として認められる。
コンスタントに一定レベル以上の曲をたくさん創作し続けていくためには、その時々の自分の気持ちに依存しないこと。
確実にたくさんの曲を作り続けていくには、気分の波に流されてはいけない。
何かを表現していく人間にとって、自分の拠り所を「気分」に置いてしまうのは危ういことだ。
(久石譲「感動をつくれますか?」)
その後、久石譲さんは、アーティストが自分の「気分」に依存する危険性として、わかりやすい例を挙げている。
「気分」を拠り所とするミュージシャンが、壁にぶつかった時、「気分」を上げるためにドラッグの世話になってしまう。
27CLUBというフレーズを出すまでもなく、60年代以降、若くして時代の寵児となるも夭逝し、伝説となったミュージシャンたちは数えきれない。
(久石譲「感動をつくれますか?」)
アーティストにとって「平常心」でいることの恐怖
ジョン・ガリアーノは、誰が見ても120%の天才デザイナーだった。
ファッションの世界の住人はもちろん、一般層でも、彼が他のトップ・デザイナーと比較しても一目瞭然で違いがわかるレベルの圧倒的な才能の持ち主だった。
映画の中で、ガリアーノは当時の自身が担っていた仕事量が半端ないことを語っていた。
年2回の大きなファッションショーのデザインを中心に、サブブランドやバッグ、シューズライン、アクセサリーやサングラスなども同じペースで新作デザイン発表のための準備を要する。
それだけの膨大な量の新作デザインを、しかも「天才」と呼ばれるトップ・デザイナーとして世界中を熱狂させるハイレベルのデザインを生み出し続けることは、どんな天才でもキャパオーバーなのは明白だった。
ガリアーノは、周囲の期待、そして何より自身の期待に応えるため、研ぎ澄ました精神を維持するための「刺激」を外に求め続けた。
夜通しパーティーに明け暮れ、アルコールに溺れ、ホテルで暴れて室内を破壊し、エキセントリックな瞬間に浸り続けた。
何より平常心でいることを恐れた。
きっと平常心を取り戻した瞬間、きっと自分に課せられている仕事量が異常であることに心が折れてしまうだろうから。
キャパオーバーが人を、人生を一変させる
経験がある人もいるかもしれないが、若い頃に自分が一気に成長したと感じる時期は、仕事に忙殺された時期と重なっている。
不眠不休でのめり込んだ時間が濃いほど、その経験は人を階段飛ばしで成長させてくれる。
じっくり考える暇も与えられず、即断即決でアウトプットを出し続けたことで、引き出しが増え、懐が深くなり、こなせる仕事の許容範囲が格段に広がる。
加えて、関わる仕事が多岐にわたるほど、出会う人が増え、新たな人間関係からたくさんの刺激を得ることができる。
そんな過去を振り返る時、2023年公開の映画にもなったフランスの文豪オノレ・ド・バルザックの小説「幻滅」を思い出す。
上昇曲線が急であるほど、下降速度は悲劇的となる
地方出身の無名の詩人が、ゴシップ新聞の芸能記者職を得たことで一躍パリ演劇界に大きな影響を与える評論家となるも、自分の能力を過信し、欲に溺れて結局は転落して地方に戻る若者の物語。
ガリアーノ的な現代のアート業界は、まるで19世紀前半が舞台のこの物語の焼き回しのように思えて仕方がない。
アーティストというポジションが成立して以降、ゼロから頂点へ、そして一直線にゼロに落ちていく曲線は、アーティストの逃れられない運命なのかも知れない。
だからこそ、久石譲さんはそんなアーティストの運命に陥らないための処世術を自ら編み出したのだろう。
若き天才の60代での再出発
2011年、有罪となって「クリスチャン・ディオール」のデザイナーや自身のブランド「ジョン・ガリアーノ」のデザイナーを解雇されたガリアーノ。
この映画で13年ぶりに姿を見せた彼は、過去の自身の過ちを素直に認め、もう一度デザイナーとして復帰するための地道な活動を始めていた。
自分の「気分」に依存しない現在のガリアーノのデザインが、ファッション業界にとってどのような価値を生み出すのだろうか。
27 CLUBのミュージシャンたちは、やり直すチャンスを手にしないまま、永遠の伝説となった。
ファッション界の寵児だった頃のガリアーノも彼らと同じく「伝説」となってしまっている。
生気ほとばしるエキセントリックな「気分」の爆発は、若い時期、ほんの短い期間にだけ与えられた「スポットライトを浴びる瞬間」として人生を大きく変えてしまう力を秘めている。
しかし、それは、あくまでその時期にだけ与えられる期間限定の力なのだ。
天才と呼ばれた男が過去を捨て、60代で平身低頭の姿勢で勝負の舞台にもう一度立とうとしている。
それは微笑ましくもあり、悲しくもあるのはなぜだろう。
ヘイト発言の真の理由。。。
クリスチャン・ディオールのデザイナーに抜てきされ、「ファッション界の革命児」の名声を得ていたジョン・ガリアーノ。そんな彼のコレクションが実はあまり売れず、収益性は良くなかった内幕等が前半であかされます。そんな彼の、収益面をカバーしてきたパートナーが過労により自殺したことで、彼はそうした仕事にも直接携わるようになり、やがてヘイト発言へ。その真意が気になるところです。
映画を観る限り、彼がユダヤ人に対して固有の感情を抱く理由は明かされず、発言の相手はアジア人だったりしているので、ユダヤ人に対する恨みというよりは、その言葉に象徴される何かに強いストレスを感じていたのでしないかと思います。作中からはディオールが属する世界一のファッションコングロマリットLVMHの経営トップもユダヤ人であったことがわかりますが、経営者からデザイナーに直接強い圧力がかかっていたとも思えません。私としては、ユダヤ系の優良企業に幅広く観られる超合理主義(徹底した効率・収益の追及)とガリアーノが直接対峙する中で、彼の(まつ毛にまで細かくこだわる)アーティストとしての気質が蝕まれていったのではないかと思いました。
それならば「合理主義の馬鹿野郎」とか「ビジネスなんかクソ喰らえ」とでもいっていれば、何でもない戯言だったわけですが、これを少数者へのヘイト発言にすり替えたものは何なのか。ここは、ショーの中でもマタドールに扮してポーズを決めるような、ガリアーノの強い自意識が、自らの弱さを認める事を拒んだためかと認識しています。
私の見方が正しいのかはともかくとしても、発言の過激さからストレスもそれを押し込めようとする力も半端でなく強かったことがうかがえます。
さらに、興味深かったのはオスカー・デ・ラ・レンタのデザイナー時代にニューヨークでオーソドックス(厳格派ユダヤ教徒)の恰好をして外出するあたりでしょうか。ガリアーノにしてみれば「和服を着た親日家」くらいの軽いラブコールだったのかもしれませんが、オーソドックスの人たちにしてみればファッションは宗教的生活(禁欲)の一環。例え天才デザイナーがあの服装にユダヤ教全体を総括したインスピレーションを感じたとしても、相手からは「ユダヤ教を勉強した」ことが、変幻自在の「ファッション」の1つとして揶揄された、と受け取られても仕方がないかと思います。
今回の映画を観た限り、ヘイト発言の真の動機(ストレスの原因やそれを封じ込めようとするもの)にガリアーノ自身が向きあって、問題を克服している印象は、あまり感じられませんでした。確かに、ジャポニズム、近世フランスから古代エジプトまで、各ストーリーを独自の感性で創造する彼の素晴らしいショーを観れば、客観性・論理性など無用にも思えますし、そのあたりはアナ・ウィンターのような敏腕のプロがついているわけですからなんの心配もないのかもしれません。ただ、1人の人間として彼を観た場合、特異な感性の優位性にスポットが当たりすぎ、その他の自分とバランスをとる機会が失われていたことが彼の人生を無用に生きずらくしていたようにも感じます。これからデザイナーとしても集大成の時期に入るガリアーノがどんな活躍を見せてくれるのか、今後を見守っていきたいと思います。
全2件を表示