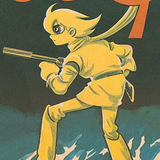ディア・ファミリーのレビュー・感想・評価
全411件中、21~40件目を表示
月川翔という監督は「君の膵臓をたべたい」(2017)を見たことがある。原作は清武英利の『アトムの心臓「ディア・ファミリー」23年間の記録』らしい。
動画配信で映画「ディア・ファミリー」を見た。
2024年製作/116分/G/日本
配給:東宝
劇場公開日:2024年6月14日
大泉洋(坪井宣政)
菅野美穂(坪井陽子)
福本莉子(坪井佳美)
川栄李奈(坪井奈美)
新井美羽(坪井寿美
松村北斗(富岡進)
有村架純(山本結子)
光石研(石黒英二)
上杉柊平(佐々木肇)
徳永えり(柳玲子)
満島真之介(桜田純)
戸田菜穂(川野由希)
月川翔という監督は「君の膵臓をたべたい」(2017)を見たことがある。
脚本の林民夫といえば、「チア☆ダン 女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話」、
「ラストレシピ 麒麟の舌の記憶」、「空飛ぶタイヤ」、「護られなかった者たちへ」など多くの作品を手掛けている。
原作は清武英利の『アトムの心臓「ディア・ファミリー」23年間の記録』らしい。
モデルとなったのは東海メディカルプロダクツの会長筒井宣政とその家族であるらしい。
株式会社東海メディカルプロダクツは、愛知県春日井市に本社を置く医療機器メーカー。日本初のIABPバルーンカテーテルを開発、医療用カテーテルを中心に製造している。心筋梗塞や狭心症などの患者の心臓の動きをサポートするIABPバルーンカテーテルで国産シェアナンバーワン。
実話がベースであるようだ。
小さな町工場を経営する坪井宣政は、
生まれつき心臓疾患のある幼い娘・佳美の余命が10年と宣告されてしまう。
理不尽な現実に絶望した彼は、
誰にも頼れないならと自分の手で人工心臓を作ることを決意する。
娘を救うために医療知識がないながらも諦めずに挑戦し続ける父親と、
それを支える家族の姿が素晴らしい。
家族は医者から、たとえ明日人工心臓が完成しても佳美ちゃんは治せないと宣告される。
佳美ちゃんのための人工心臓の開発は間に合わない。
そんな時に佳美ちゃんは、
自分の命はもういいから、
他の心臓疾患の人を救ってほしいと父に言った。
今を懸命に生きる姿と家族の絆、生きる証を感じた。
泣けるシーンはたくさんあるが、
終盤、有村架純の登場するシーンが俺にはジーンときた。
満足度は5点満点で5点☆☆☆☆☆です。
わかっていても感動できる
大事な事を教えてくれた映画
医療の知識など全くない技術者である父親の執念に感動した。娘の命を助けたい一心で始めた人工心臓の開発。諦めの悪い性格と粘り強さポジティブ思考、持ち前のタフさだけでなく1番の理解者である奥さんの支えと家族の存在がこの結果に繋がったと思う。この頃のクソみたいな医療会に腹が立ったが、バカにされてた教授を見返せてざまあみろだった。有村架純は脇役?と思っていたが、ラストで回収され感動の波が押し寄せてくる彼女の使い方がうまい
物凄い執念
すばらしいお父さんです。
まさに、感動、驚きの実話
心臓病の幼い娘、余命10年と聞いて落胆する夫婦、他の病院に当たってみる位のことはどの親でもするだろうが自身で人工心臓を作ろうとするあたりは想像を超える。実話とあるので調べてみたらまさに映画どおり、愛知県春日井市でビニール製品の町工場「東海高分子化学」を父から引き継いだ筒井宣政さん家族がモデルでした。「娘の命を救いたい」その一心で、関西学院大学経済学部卒業で医学知識ゼロだが、高分子化学は仕事上得意分野、全財産を投入し多くの医師や研究生と共に人工心臓やカテーテル開発に挑み、世界中の17万人の命を救ったという。ドラマだったら出来過ぎと思ってしまうだろうが実話というのは人知を超えた奇跡の挑戦。
硬直した医学界の側面は誠に遺憾、人工心臓が無理なら諦めるところ、同じ心臓病を病む子供たちを救って欲しいと言う娘の願いに救命措置に必要な患者の年齢、体形に合わせた国産バルーンカテーテル製作に方向転換、娘を救えなくとも病の子供たちは救いたいという博愛精神も立派ですね。
感動の実話を大泉洋さん、菅野美穂さんが大熱演でした。
有村架純が美味しいところを・・・
IABP(大動脈バルーンパンピング)の誕生秘話。ほぼ事実を元にした作品であるため興味深く鑑賞させていただきました。まずは人工心臓を作るために奔走する坪井宣政と妻・陽子の物語であり、余命10年の次女・佳美(福本莉子)の演技が霞んで見えてしまうほど。徐々に医師と対等に渡り合うほどまでになった町工場の社長宣政。また、人工心臓を諦めて辞めてしまう医師や未来が無いと退職する工員たちの姿が絶妙だった。熱意だけではダメなのね・・・
「in vivo」と「in vitro」。ちょっと懐かしい。工場経営者がいきなり医学を学び始めるところから、あちこちの大学病院を探し、人工心臓を作るめどがたった。しかし、結局は成功しなかったものの佳美の言葉によって他の人の命を救うため、バルーンカテーテルの製作に力を注ぎ込む。
泣かせようとするシーンもあるけど、佳美が亡くなるシーンをカットするという潔さ。この大胆な構成によって有村架純が目立ってしまったんですね。日記を読むシーンより泣けた・・・
自然光を取り入れたり、70、80年代の雰囲気を出すための凝ったCGのさりげなさも良かった。特に時代に合わせた車たちがリアルでした。
実話なんですね、尊い内容でした
あきらめが悪い
長編映画にしても良かった
かつて病気関連でここまで前向きな作品あっただろうか、、と思うほど、...
かつて病気関連でここまで前向きな作品あっただろうか、、と思うほど、とても悲しく切ない物語なはずなのに観終わった後どこか前向きになれるような不思議な作品だった。
これまで観てきた病気ものの作品は見終わった後悲しい余韻が広がる作品が多かったけど、この作品は前向きな生き方、諦めないことのかっこよさ、夢は変化していくものだということ、などいろんなことを学べた。
ただ切なく悲しい病気ものの作品も好きだけど、こういう前向きな気持ちになれてどこか背中を押されるような作品もとても好きだなと感じた。おかげで良い休日になった、、
そして何よりキャストの方々豪華かつ、贅沢な使い方すぎてびっくり。流石の演技力ですっかり世界観にのめり込んでしまってあっという間の117分でした。
諦めないこと
ディア・ファミリー
世界で17万人の命を救ったIABPバルーンカテーテルの誕生にまつわる実話を映画化したヒューマンドラマとのこと
医療従事者でなくても、こんなこと実現できるのだと驚愕しました
人工心臓をつくるために莫大な費用を費やし
それに向かって周りの人をも突き動かし
確実に進歩していく
結果的に娘の佳美の心臓は助けることは出来なかったが
『もっとたくさんの人を助けて欲しい』という佳美の願いが、家族の願いとなったこと
絶対に諦めないこと
それが世界の17万人の命を救った
自分だったら何度も諦めそうになったと思います
でもそんな坪井さんの姿が
家族を強くして
そして強い絆が生まれたのだと思います
お涙頂戴映画だけどマ王は知っている
珍しく枕話は割愛で本編のレビューに進みたい。
本作の内容を耳にした時からマ王は決めていた事がある。
①映画館では絶対に観ない
②気持ちの落ち着いてる時に鑑賞する
の2点であった。
①に関しては完全に号泣必至の物語なのがバレバレだったので単純に映画館で泣きたく無かっただけだ。
マ王は泣く為に映画館へと赴きたくない(洋画で例外アリ)
②の方だけど精神的にも肉体的にも穏やかな時に鑑賞したいと望んだからである。
またもう一つ、コレは①②に共通する次項にもなるけど実はマ王、本作に出て来るIABP(大動脈内バルーンパンピング=Intra-Aortic Balloon Pumpingの略)を販売していた会社で3年弱仕事をしていたのよね。
映画内では命を救う画期的な生命維持装置みたいな表現してたけど、身体の大動脈内で風船を心電図に合わせて膨らませるシステムに当時のマ王は「なんて暴力的な機械なんだ」と戦慄した記憶がある。
たった3年弱だけどそこの会社では様々な勉強をさせて頂いたので感謝はしてますが同時に、組織のダークな一面も学習させられたのでマ王としては鑑賞に意欲的にはどうしてもなれなかったのがあった。
特に本作にも描かれてる金の問題は当時から表面化していたので、あまり気持ち良く映画に浸れないと予想してたのが大きい。
何せIABPの本体だけでも小振りの箪笥サイズのクセしてベンツが買える値段。
バルーンだって6桁だよ。
また開発における話にもココでは書けないトコもあったりするしで(軽く30年以上も前の話だが守秘義務は生きている)本作を鑑賞した今はエンタメに製作された物語だったとだけ言っておきたい。
要は、どうぞ泣いて下さい、と過剰な演出が目立っている邦画だったワケだ。
それに我が子や愛する人が不治の病に冒されて周りが奮闘するストーリーなんて古今東西履いて捨てるくらい作られてるので、今更のマ王が感動の末に号泣するとでも思うかね。
まぁ号泣はしたけどね🌀
余談ついでにもう一つ。
世の中は何をどう言おうと結局は金なのである。
資本主義の世界に生きる我々にとって貨幣は生命と同等の価値があるのさ。
身も蓋も無い下品な話なんだけど、御歳55年の人生の一つの現実としての答えだ(自身の答えなのにアンチテーゼの如くマ王は反対派なんだけどねぇ)
一万円の人生と一億円の人生、何方も幸不幸はそれぞれある。
けど種類は別物の幸不幸なのは知ってほしい。
いやいや、金持ちになれとは言って無い。
人間誰しも心を豊かにする金額は決まっているのよ。
ソコの勉強をしてこなかった人間が不平不満を口にして誰かの何かの所為にしながら不幸だと喧伝するし金銭至上主義が横行する引き鉄にもなっている←正に今の社会がソレよ
給料が安い、消費税が高い、米が値上がりしてる。
が、それって誰でもない自分がもっと先に行動に出てれば良かっただけの話なのよ、本当は。
目先の快楽に流されて「今、この瞬間が楽しければイイの❤️」って別に悪ではないよ。
酒も煙草もギャンブルもドラッグも、男や女や愛や恋の切った張ったの話もそう、生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされても尚、それが人生だしその為に生きてるのは恥ずかしく無いのも事実だ。
でもこれら全ての事象には金銭が絡むのだから、生きる行為=金なのを否定する事なんてしてはいけない。
給料が安いならなぜ、勉強しなかった?
消費税が高いならなぜ、当時の政治家に反対しなかった?
米が高いならなぜ、米農家問題を無視してきた?
人間の大多数は只々今日まで楽な方に流されてるだけで何にも抗って生きていない←マ王は抗って負けた人間でもある←無理し過ぎて脳梗塞に負けた
そりゃ死に際の人間が何百万もの金を抱えてあの世に逝けるなら理不尽極まりない話になるけど、進行形でそんな奴は見た事無いしあの世でも金が必要だってんなら天国なんてコッチから願い下げだわな。
我々が生を営む上で幸福を求めるのは自分自身へだけで他人への幸福を与える行為はあまり多く見られない。
ま、本作はその点のみを勉強させられる映画になってたかなと。
アクション映画とほぼ同じリズムで10分に1回くらいは泣ける映画なので計算上は本作1本で10〜12回は泣けると思う。
今日の私は泣きたい気分😢とかならオススメだけど泣くのって案外体力使うから元気に泣ける日に鑑賞をして下さいな。
生粋の邦画ファンなら満点出す内容だけど、正直書くなら「泣ける」よりも「泣かせよう」がアトラクションの如く過激だったのでマ王は涙の様にしょっぱい点数にしました🥲
映画館での鑑賞オススメ度★×1〜★×3(その時の気分で変化する映画)
ジェイソン・ステイサム兄貴とは真逆の映画度★★★★★
守秘義務は律儀に守るマ王度★★★★★(口は固い方)
実話か、すごいなあ
どこまで泣かすねんていうくらい泣かされる映画。一番最初のレポーターまで最後の最後に伏線回収しにくる。
そのシーンが一番泣いてしまった。
素晴らしい家族、工場の従業員の皆さん、医療研究者たち、みんな泣かしにくる。
絶望的な状況の度に自分もつらいのに気丈にそれで、「次はどうするの?」と励ます妻。
妹の前ではいつも明るく振る舞ってるのに陰で泣いてる長女。
なによりも「私の命は大丈夫だから、その知識を他の人のために使って欲しい」と言った佳美。など書いてたら切りが無い。
医大教授の冷たさには憤りを覚え医療従事者たちの頑張りを余計に光らせてくれる。
最後に、教授が仕方なしに謝るシーンは「あほ!ボケ!」と心の中で叫んでた。
医学に貢献するのは何も医者だけじゃないというのが理解できたし
MRIやCTなど医療機器は色んな業種の人たちによって開発されている。
この映画を見るまではIABPバルーンカテーテルの存在は知らなかったけれどお医者さんにはぜひ見て欲しい映画やなあ。
最後まで笑いを取りに行かなかった大泉洋さん、「次はどうするの?」
見終わったら自分も何か諦めない物を見つけたいなあと思った。
それに向かっていったら自分の人生も少し輝いて見えるかも知れない。かな?
未来へ繋げる
思った以上に感動的。「あきらめの悪さ」の素晴らしさ
国際線の映像サービスで鑑賞。
人工心臓なんて無謀な挑戦なのは明らかで、うまく行かない話なんて面白くないだろうと思って観ていませんでした。でも、主人公のセリフにもあった「あきらめの悪さ」が、この映画の大きなテーマで、泣かされました。
そのあきらめの悪さの元は、娘の健気な性格があり、説得力があります。特に彼女の日記が感動的です。
後半の人工心臓から方向転換するところも物語のポイントで、説得力があります。一言では説明できない事情があり、方向転換の決断に共感しました。
映画冒頭のインタビュアーが、実は・・・というのは、ちょっとやりすぎと感じました。この場面のセリフや演出も現実にはあり得なさそうで、不自然さを感じたので、少しだけ減点しました。
全411件中、21~40件目を表示