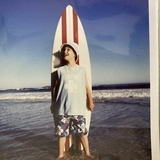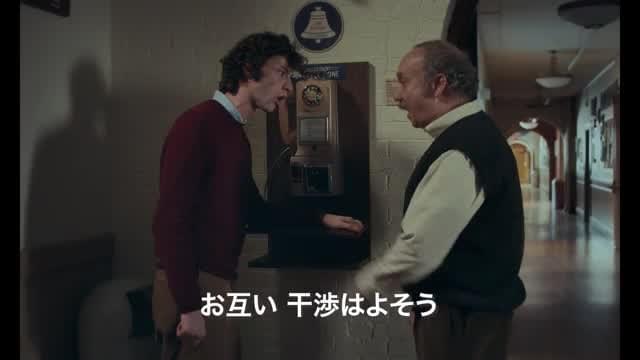ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディのレビュー・感想・評価
全253件中、141~160件目を表示
知らないところ
うん、いい映画だった。
穏やかで優しく、クリスマスにピッタリな作品。公開時期真逆過ぎ。70年代風にデフォルメされた配給・制作会社が何とも可愛らしい。MIRAMAXはこっちの方がいいんじゃない?映画本編も昔ながらのフィルムスタイル。これ、逆に現代風のほうが違和感あると思っちゃうくらいハマってた。
こういう映画はシネコンよりミニシアターで見たい。上映館少ないのにこの映画館でやってたことが奇跡だけど笑 度数高めのお酒を片手に、塩っけの強いナッツでもつまみながら。2回目見る時はしっかり時期合わせて、自分スタイルで見ることにしよう😁
見えてる部分だけがその人の全てでは無い。誰しも過去を持っていて、誰しも知らないところがある。偏見って良くない。良くないと分かっていても、目で見える範囲でその人を判断しちゃうのが人間という生き物であって、見えないところにまで目を向けるって、なかなか難しい。堅物教師・ポールのひとつひとつの行動に心打たれたし、堅物の皮が徐々に剥がれていく様に色々と思うものがあった。ポール・ジアマッティ、すごく良かった。。。
盛り上がるまでに結構時間を要していて、中盤若干退屈なのだけど、2人が仲を深め、互いのいいところ、わるいところを認めあっている姿は何時間だって見れる。評判が良すぎるが故に劇的な展開を期待していた自分がいたが、それほど驚きはなく、物語としては割と普通。ただ、味付けが非常に上手かった。期待は禁物。でもいい映画です。メアリーのような女性からしか得られない心の安らぎってあるよね...。
はっきりとモノが言える関係性の素晴らしさ
ホリディに学校で過ごさねばならない3人、
先生のポール(ポール・ジアマッティ)、生徒アンガス(ドミニク・セッサ)、
そして料理長メアリー(ダバイン・ジョイ・ランドルフ)の織りなす人間ドラマが
実にあったかくて心に沁みました。
先生も生徒も料理長もいろいろと心に抱えているものがあって、
健康じゃないんですよね。
であるがゆえに、言葉がキツかったりするんですね。
それは先生と生徒が同じ薬を飲んでいることがわかったり、
料理長の息子が戦死していたりするので、いろいろと事情を抱えているんです。
だからこそ、ここ3人が心を通わせていくというのは理解できるんですよね。
ポールは厳格な先生でありながら、自分の経歴に嘘をついていたりする、
でも、そこにアンガスは共感できたりするんでしょうね。
3人がボストンへ旅行することによって、
ポールとアンガスがお互いのダメなところを言ってもらうというシーンは
成人発達段階が高くないと、到底受け入れられないのだと思うのですが、
信頼関係ができてくると、それが言える。その関係性こそが人生の宝だなと思いました。
ラストのポールの言動が実に素晴らしく、それでアンガスを救う、
でも自分は去らなければならなくなってしまう、おそらくはそこまでわかっていての行動ですから
感動もひとしおですし、人って自分次第で変われるんだなということを
あらためて学ばせてもらったように思います。
どこがオススメ!?と聞かれると、なかなかこたえづらい作品ではありますが、
ちょっとビターながらも、鑑賞後感が素晴らしい作品です。
できれば、クリスマスシーズンにもう1度観たいですね。
クリスマスムービーの傑作がまた一つ誕生
世の中が盛り上がるクリスマスに、訳あって寂しく過ごすことになるシチュエーションはクリスマスムービーの定番とも言えるが、ヒューマンドラマの名手、アレクサンダー・ペイン監督は1970年のボストンを舞台に、きめ細かく人間を描き、笑いあり涙ありのハートウォーミングなクリスマスムービーの傑作を作った。
1970年の冬、米ボストン郊外の全寮制ハイスクールのバートン校。
クリスマス休暇で生徒も先生も学校を去っていく中、生徒のアンガス(ドミニク・セッサ)は家族で旅行に行く予定だったが、母親が再婚相手との急な予定を入れてしまい学校に残ることになってしまう。
学校の留守番担当の古代史教師のハナム(ポール・ジアマッティ)とこの学校に在籍していた息子をベトナム戦争で亡くした料理長のメアリー(ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ)の3人のクリスマスの出来事を丁寧に描いていく。
教師仲間にも生徒にも嫌われているハナム、心に傷を負っているメアリー、賢いが家庭の事情に反発するアンガスとそれぞれ孤独を抱えた3人が次第に心を通わせていく展開が見事。
とりわけメアリー役のランドルフの悲しみを抱えながらもだんだんと気持ちを解放していく演技は胸を打ち涙を誘う。ランドルフはこの演技でアカデミー助演女優賞を獲得。
また、アンガス役のドミニク・セッサは実際にロケで使われたハイスクールの生徒で、この役に抜擢され見事に演じきったというから驚きだ。
1970年をリアルに表現するフィルム調の質感、実際のハイスクールを使って全編ロケで撮影したという冬のボストン郊外の情景、BGMの70年代のポップソングやクリスマスソングの使い方。ベトナム戦争の暗く重苦しいアメリカの時代背景。
地味ではあるが繊細なドラマを重厚に紡いでいく手腕が見事としか言いようがない。
クリスマスにまた観たくなる心に残る映画だ。
堅物な教師と訳あり生徒の二人が心を開いて行く感じの作品。 本年度ベスト!
観たい映画が多くあり本作の優先順位が下がっていたけど鑑賞出来て良かった!
クスっと笑えるシーンもあり心が暖まる作品だった感じ。
1970年代、マサチューセッツ州にある全寮制の高校の冬休みの出来事を描いたストーリー。
冬休みに先生や生徒が帰省する中、ある理由で帰省せず学校に残る生徒のアンガス。
堅物で皆から嫌われている教師のポールがアンガスの監督役を務める事になり、二人を中心に展開するストーリー。
この二人に加え、学校の食堂の料理長のメアリーが加わって行く感じ。
仲の良くないポールとアンガスが早い段階で心を開いて行く感じで、もう少し仲が悪いシーンがあっても良かったのかも(笑)
堅物の教師のポール。意外と良い人でアンガスをいろんな場所へ連れて行ったりクリスマスプレゼントも用意するけど、そのプレゼントに笑えた。
ボーリングやスケート場の仲良さそうな二人の姿が良かった。
クリスマスや年明けのシーン。
日本人では考えられない位、アメリカでは大切な日だと改めて認識する。
ポールが買ったクリスマスツリーに笑える。
酒好きな自分なので、ジムビームが好きなポールに共感(笑)
スーパーでジムビームを2ドルで買ったんだけど当時はそんなに安かったのか?
気になるところ。
料理長メアリーのポイントも高め。
息子をベトナム戦争で亡くすももの元気に厨房で働くシーンが印象的。
ポール、メアリー、アンガスの三人が本当の親子の様に見える。
後半に起こる、ある出来事。
ポールの優しさが伝わって来る泣けるシーンでポールがアンガスを思う発言に優しさが伝わって来る。
堅物だったポールがとても良い人に感じる。
ラストでポールが車の中である飲み物を飲むシーンが最高でした( ´∀`)
堅物教師 VS 傷心生徒
古き良き反骨の精神
感想
1970年、東部マサチューセッツ州バードンスクール。クリスマスからニューイヤーのホリデイシーズンに、帰省により誰も居なくなった寄宿舎に寮監代行として残る事になった、訳アリの堅物歴史学教師ポールと別な意味で訳ありまくりで居残る事になった学生アンガス。そして、在学中にベトナムへ出征し戦死した息子の母親で寮に調理主任として住込みで働くメアリー。この立場も人生の環境も違う3人が織りなす、複雑で、心の傷みを弄りあう笑いあり、涙ありのペーソスが溢れる人間ドラマ。人は見た目では何を考えているか判らない。また、話をしてみないと人柄はわからない。『だから人生は面白い!」を地で行っている話が展開していく。
教育一筋40年にして堅物、融通のきかない頑固な性格が災いして軽蔑の視線を学生や同僚からも向けられているポール。この学校に入ってくる勉強嫌いの金持ちの子弟達。プレップスクールに入れて一定額以上の高額寄付金を納めれば名門大学への推薦枠を優先的に獲得出来るという事実。金で全てを解決していこうとする父兄と学校運営を良好にする目的の元、拝金主義に偏る学校側に疑念や不信を募らせ、年々頑固さが頑なになり、彼の授業は特に採点が厳しく修了年限内に単位が取得出来ず、大学推薦が決まっているにも関わらず、進学を棒に振る学生もいる。ポールにしてみれば学生本人の学問見識が低いだけだと思っており、何の責任も感じていない。
アンガスは学内でも反骨精神が強い学生。転校を繰り返しており、このバードン校を辞めさせられると後は州兵養成の為に設置されている陸軍学校に行くしかない。学内の成績は上位だが憎まれ口を叩くので教師からも一目置かれ、友人と呼べる者は一人もいなかった。
12月の試験が終わる頃、両親は離婚、母親が親権を獲ったが、母親は間髪を入れずに再婚してしまい、ハネムーンに行くという事でホリデイシーズンは一緒には過ごせない話になる。大好きな父親とも別れる事になりアンガス本人にとっては人生で最悪のホリデイシーズンとなったかに見えたが...。
この学校内の寮で学生達の食事を担当する食事主任のメアリーは最近、最愛の息子をベトナム戦争で失った。息子のベトナムへの従軍は計画的であり、一年間の従軍の後、退役軍人としての免責事項として大学進学の学費が全額国から支給される事を見込んでの行動であったが、帰らぬ人になってしまった。息子を失って最初のホリデイシーズンだったのだ。表面上は明るく振る舞うメアリー。休暇期間になり悲しみが再び彼女の想いに大きく広がっていく。
演出・脚本・俳優◎
人はそれぞれ。性格的にも得て不得手がある。休みの日の寮内に残された三者三様の考え方、感じ方など足りないものをお互い補いながら、そこにある本音と建前、生きる上での苦しみや悩みを互いに理解していく事で絆が生まれてくる。その経験がそれぞれの人生の糧となる様を描いた淡々とした演出が素晴しい。学生の真の人間性を認めていく変わり者教師ポールと黒人女性メアリー、悩み多き青春時代の学生アンガスの姿を歴史ある東部の学園風景と共に1970年の年の瀬のベトナム戦争が深刻化していくアメリカ世相を織り込み構成された見事な脚本。小品ながら味わい深い作品に仕上がっていた。ポール役のポール・ジアマッティは個性際立ついつも記憶に残る俳優。アンガス役のドミニク・セッサ。内向的性格と要領の良さを上手く表現していた。今後の活躍に期待。メアリー役のダバイン・ジョイ・ランドルフは本作で第96回アカデミー優秀助演女優賞を受賞している。
⭐️4
本作で描かれている学校は普通のアメリカ国内にある公立高校(パブリックスクール)や私立普通科高校ではなく中西部湖水周辺、東部に比較的多く所在している東部名門大学に入学するための専門的教育を行っているPreparatory-School 所謂、プレップスクールである。そこに就学する学生をpreppie(プレッピー)と呼ぶこともあるが、尊敬の意味はあまりなくお金持ちのお坊ちゃんお嬢ちゃんを揶揄する蔑称の意味合いが強い
とされる。その点がイギリスのパブリックスクールとは権威的にも格が大きく異なる点である。学校形態としてはプロテスタント系キリスト教主義教育、男女別学、寄宿舎(ホールディング)生活が主流である。この特殊な環境を理解した上で、映画の中で描かれる情景や登場人物の会話を観ていくと話をより理解することが出来た。
人生の学びと他者への理解
ほぼイギリス映画
entre nous
前半がちょっと長いんですね。
もう少し早くアンガスにフォーカスしてもよかったのでは。
こういう家族の事情は友だちにも言えないからつらい。
メアリがあそこで泣いてしまうのも分かるんです。
皆は楽しそうでいいな、自分だって息子がいたら、とかつい考えてしまう。
ひとと過ごすクリスマスもいいけれど、時にはほっておいてほしいこともある。
ハナム先生は今までひとりでクリスマスを過ごしていたのかな。
ひとりでも全然いいと思います。
孤独な3人が“家庭”によって救われる ハートフルストーリー
のっけからレコードの針が盤を引っ掻く音と色褪せた画が出てきて、時代を感じさせる。上手く時代を作り出して引き込まれていく画と音の演出。いい感じに始まって映画に入っていくんですが、主演のポール・ジアマッティ扮する堅物先生が入った瞬間、
これは良き映画かもしれないと感じました。
時は1970年のクリスマスホリディ。ルールに厳格で融通が一切利かず、特異な体臭と古めかしい指導によって生徒から嫌われている独身の教師。成績良好だが、再婚した母がこの時期にハネムーンを予定したがために家に帰れず寮生活を強いられる青年。女手一つで育てた息子が戦死し、一人喪中の寮母。この3人が学校の寮でクリスマスを送るというストーリーの本作・・・
懐かしさと温かさを兼ね備えた名作であると感じました。
寮に残ることになった3人、誰しもが孤独と、それに付随する悩み、それも生い立ちという歴史からくる深い悩みを抱えているんです。それを隠すために、反動ともいえるような態度を取って、結局まわりから嫌われているのかなと。しかし、このホリディで3人はいつしか“家庭的”な生活を取っていくんです。自分の主張をぶつけ、時に深い傷をえぐってしまい、そのたび相手を理解していく。それが激しい論調ではなく静かに、しかし強く伝えるような感じなのがまたいい。観やすいし、なにより深く考えさせられる。相手を理解するとはこういうことなのかとも思ってしまう、大人のビターな感じがいいんです。しかしただぶつかるだけではない。そこには、ほんわかなコメディチックな緩さがあり、いいテイストになっているんです。そして、この“家庭的”な、“家族”のような雰囲気こそ、孤独を癒す最大の薬ではないかと、この映画は問いかけているように思うんです。そう、
“家庭”“家族”の存在の偉大さを、伝えようとしているのではないか。
また、堅物先生が「古代歴史」の先生であることも面白さを引き立てる。個人的に歴史が好きなんですが、彼が語る歴史の意義はとても心に残る。
歴史は過去を語り、そして今を説明する。
歴史によって自分の人生が決まることはない
なかなか深い!物事には過程があり、今の結果があるが、それが未来を縛ることもないということではないかと自分は思っています。
本作を監督したアレクサンダー・ペインは、ハートフルな作品を作るのが巧いと聞いていましたが、その噂通りであったと思います。また堅物教師のポール・ジアマッティ、寮母のディバイン・ジョイ・ランドルフの演技達者は見事ながら、残された青年役のドミニク・セッサの演技は魅力。若人ながらかなり魅力。この3人が魅せたことがより本作の評価を高くした理由です。
“孤独”を“家庭”が救う本作。この魅力、人付き合いが難しくなった現代にこそ、必要なんじゃないかと思います。そういう意味でも、本作は名作です。
青春に期限は無い
心寄せ合う家族像…まだまだ未来はある!
誰もが帰省の喜びに浮き足立つクリスマス休暇
校長をはじめ同僚や生徒からも嫌われてる頑固者の非常勤講師ハナム
カリブ海でのバカンスにテンション上がりまくりだったのに母親の一方的な都合でキャンセルされた生徒アンガス
愛息子を戦争で亡くした料理長メアリー
それぞれの事情でボストンの全寮制男子校バートンに居残りになった年齢人種階級も違う3人の物語
派手さはないがいちいち心に沁み刺さる台詞がじんわり胸に響くのであります
シビアでチクリと世情を風刺している辛めのユーモアにアレクサンダー・ペイン監督の深隠い人間観察力の鋭さを感じました
3人で出掛けた学校関係者のクリスマスパーティ
いつも冷静で凛としているメアリーが取り乱し号泣してしまう
幸せに浸る参加者達の中で一気に哀しみが込み上げてしまったのかと見ている私まで胸が締め付けられる思いでした…
3人でテーブルを囲んだ際メアリーの手料理に
アンガスが感謝を述べる…とても純粋で愛らしい少年のままのシーンが一等のお気に入りです!
70年代の音楽やビンテージっぽい映像は抜群に冴えていましたしオスカー助演女優賞を獲得したダヴィン・ジョイ・ランドルフをはじめ俳優達の演技力アンサンブルの素晴らしさに目が離せませんでしたね
人生は辛い事もあれどそこそこ悪くもないかなぁ
映画の深さと力を得られ世代を超えて楽しめる
この作品をぜひ!皆さんのホリディにご鑑賞下さい⭐️
ファミリー・ツリーやサイド・ウェイ同様
定期的に観たくなる作品になりそうです!
良い映画を見たという満足感
自分以外の者に対する愛情の覚醒
ジアマッティ
ウェルメイドな’70年代風のクリスマス映画。接点のない取り残された人々のぎこちない心の交流。
おいてきぼり
全253件中、141~160件目を表示