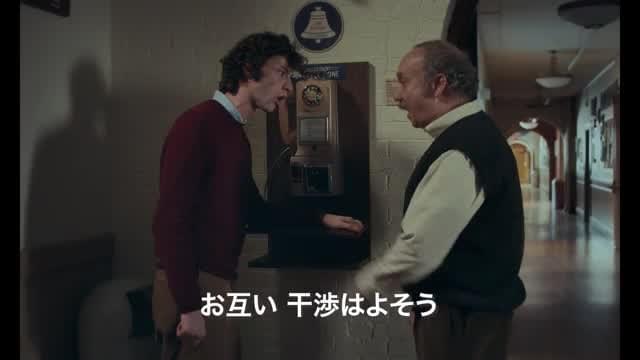ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディのレビュー・感想・評価
全297件中、221~240件目を表示
学級崩壊から始まる人情噺
まずは題名から。ホールドオーバー=holdoverとは、”留任者”とか”残留者”、”残っている人”という意味だそうです。落語に「居残り佐平治」という古典の演目がありますが、英訳すると「The Holdover "Saheiji"」というところになるのでしょうか。「居残り佐平治」で言うところの”居残り”とは、遊郭で金を払えずにそのまま拘束されてしまうという意味であり、計画的に”居残り”をして廓に拘束された佐平治が、幇間の真似をして客から祝儀を貰うという、滑稽で面白おかしい”廓話”でした。
一方本作は、時はベトナム戦争当時、1970年末のクリスマス前後の時期の半月ばかりのお話で、場所はボストン郊外にある全寮制の寄宿学校・バートン校を舞台に、クリスマス休暇で殆どの生徒が家に帰ったり旅行に行ったりする中、家庭の事情で”居残り”をする羽目になったタリーと、彼の監督をするためにやはり”居残り”となった嫌われ者の教師ハナム、そして彼らに食事を給仕する給食担当メアリーの3人の、実にハートウォーミングな”人情噺”でした。
三者三様に複雑な家庭の事情や暗い過去を抱えた彼らでしたが、タリーは手が付けられないような悪ガキだし、ハナムもアカハラ要素たっぷりの教師で、通常の授業が行われている時も全くソリは合っていない感じでした。特に”居残り”になってからはその対立関係がより先鋭に。でも最愛の息子(彼もバートン校の卒業生だった)をベトナム戦争で亡くしたばかりのメアリーの不思議な求心力により、徐々に相互理解が生まれてくる展開に。
一番良かったのが、お互いに包み隠さない本音をぶつけ合うことで、ショックを受けつつも徐々にお互いを人間として認めていく過程でした。特にハナムの強情とも言える生徒に対する厳しい態度が、実は彼自身の学生時代の出来事に由来したものであり、それを聞くとこちらも納得すると同時に、彼への共感が生まれました。たまたま出会った学生時代の友人に嘘を吐く虚栄心も、彼の人間らしさを十二分に表現したエピソードだったと思います。そして既に信頼関係が生まれていたタリーも、調子を合わせてハナムをサポートするあたり、もはや擬似的な親子関係になっていたように見えました。
最後は退学寸前の擬似息子・タリーを、自分の人生にとって最も大切な教職を投げうって助ける擬似父・ハナムのカッコ良さは、実に清々しくかつ感動的なものでした。
今年の米国アカデミー賞作品賞のノミネート作品であり、メアリー役のダバイン・ジョイ・ランドルフは助演女優賞を受賞しただけあって、すこぶる前評判も高かった本作でしたが、期待を遥かに上回る良作でした。
そんな訳で、本作の評価は★4.5とします。
孤独を抱えた者たちの温かなholiday。
寄宿学校に通う子どもたちはクリスマスを家族と過ごすために各々家族の元に帰っていく。そんな中家族と過ごせない事情を持つ数人の生徒と、寄宿学校で最も嫌われ者の教師が寄宿舎に残ることに……。
それぞれの持つ課題や過去の確執、トラウマを乗り越えながら成長していく姿を温かく描いている。
生真面目で皮肉屋、学生や同僚からも嫌われている教師ポール、息子をベトナム戦争で亡くしたメアリー、精神病の父との別れと母の再婚に振り回される生徒……。悩みや問題を抱えた3人が2週間、家族のように支え合い寄り添うことで、新たな希望と変化が起こる。
メアリー演じる女優さんの演技が素晴らしかった。
日本では季節外れな時に上映されているけれど、クリスマス前後に大切な人と観たい映画の一つです。
さようならが温かい
これまでにアカデミー賞脚本賞を2回受賞しているアレクサンダー・ペイン監督の新作。
ポール・ジアマッティ演じる超地味なハナム先生の下手くそ人生に涙。
長期休暇はひとり者には結構ツラい。
1971年の設定。
全寮制の名門男子校のバートン校。
ベトナム戦争でバートン校卒の一人息子を亡くした黒人の学食の料理長メアリー·ラム。
母親が息子との休暇旅行をドタキャンして、再婚相手との新婚旅行をとったため、居残ることになったひねくれものの優等生アンガス·タリー。
糞まじめで、生徒の成績評価も超厳しく、教師仲間からも嫌われている斜視の考古学が専門の歴史教師ポール·ハナム。
トリメチルアミン尿症による体臭も嫌われる要因らしい。
映像の作りも挿入される音楽もレトロ。日本人にはわかりにくいけど、トム・ハンクスのフォレスト・ガンプよりいいと思う。地味たけど。
優しいカントリーフォーク調の主題歌。
オールマン・ブラザーズ・バンドのメモリー·オブ·エリザベスリードもちょっと流れたけど、メインストリームではない。
ボストン美術館に行ったことあり。
すっかり忘れてたけど。
ハーバード大学構内にも行きました。
リスがいっぱいいました。
ボストンといえば食べ物はクラムチャウダー。
アイスクリームにチェリーを載せて、ラム酒をかけ、火を付けてアルコールを飛ばすデザート(名前は忘れた)で意気投合する3人のシーンがよかった。
Penile Cancer in human form「ヒトの形をした陰茎癌」はちょっと何言ってんだかわからない😎
残念だったのはauマンデーのTOHOシネマズ池袋にコメディーポップコーンデート映画と勘違いしてか、はじめからたいして面白くないギャグで声出して笑ったり、喋ったりのバカカップルが同じ列(H)にいた事。エンドロール始まるや
いなや退散しおった。ザマミ。
もう一回日を変えていかなきゃね。名作だもん。
熱中症になりそうな夜に観たけど
自分を除き、この映画を観る人は本物の映画通だと、数々のレビューを読んで思う。重なってしまうが、私が好きなのはアルコールの入ったデザートを出さない融通の利かない店員に悪態をつくポールの姿。自分も生徒たちにそうだったくせに。嘘をつかないはずなのに嘘をついたり、数々の悪態にクスクス笑えるシーンがたくさん。それでいて、少ししんみりさせる場面もある。父親のようになってしまうのではないかと不安を抱えるアンガスに、君は大丈夫と励ますところが、ベタではあるが名優の演技で、すんなりと心に沁みる。笑わせたい、泣かせたいが強過ぎなくて脚本が絶妙。熱中症になりそうな夜ではなく、一人寂しいクリスマスにもう一度観たい映画。
できればクリスマスシーズンに観たかったけど、仕方ないか… オープニ...
こういう映画が好きって人が多いと嬉しい
こういう映画を久しく観てなかった、こういうのが観たかったんだよ。
派手さはないけど、絆が芽生えて、壁を乗り越えて、一歩前進する姿はストレートに感動する。
変に泣かせるような感じもなく、ユーモアも多くて楽しかった。
ラストのほろ苦さも、先生も変わったからこれからも大丈夫と思わせる明るさを残してくれたので全然自分は嫌じゃなかった。
未来ある若者のためにこんな風に動ける先生はかっこよかった。
序盤の先生じゃとてとじゃないけどそんな行動とらなかったろうね。
俳優については申し訳ないくらい知らないのだが、みんなよかった。
特にアンガス役の彼はすごい。
手足がヒョロ長くてもう充分大きいけど、家族や友人のことで傷つき悩みを抱える年頃の若者にはまっていた。
メアリーにもう少しだけフォーカス当たるといいなと思ってしまったが、2人の橋渡しとしてちょうどよい距離感が出てるのもよかった。
あと最後に音楽。よかった。
70年代、みんなオシャレでいいな。
ファイブ・イージー・ピーセス、ネブラスカ
演出と芝居の技術が確かな作品です。
美術、装飾、小道具もしっかりしていて、
舞台となる学校にも歴史を感じさせる要素が随所に散りばめられています。
降雪、積雪の作業も大変な作業です。
多くの映画の定番の設定である、
クリスマスと年明けというのも、
とってつけた感は最低限で、
観客を引き込み、
満足させるパフォーマンスの一要素として
うまく取り込んでいます。
あらゆる技術の調和が安定している本作、
その完成度の高さは多くの賞の候補になるでしょう。
更に印象的なのは、
劇中で2回、スピーディなズームバック!
ズームバック!
ほとんど世界遺産の域です。
ラスト、
1971年の「ファイブ・イージー・ピーセス」の、
アラスカへ向かうジャック・ニコルソンや、
ネブラスカのブルース・ダーンと、
主人公を出会わせたいのかと、、、
もし出会っていたら、
1時間で意気投合、2時間後には大ゲンカ・・・勝手に妄想、
歴史は繰り返す。
このポール・ジアマッティを主演男優賞を受賞させられないアカデミー賞
第96回アカデミー賞において作品賞など5部門でノミネートされた本作品ですが、TOHOシネマズ日本橋は平日(会員サービスデイ)午前中の回としては客入り多め。さすがに注目される作品だけあります。
物語の世界は1970から71年にかけての冬休み、当時よく聴かれていたと思われるポップスがレコードのノイズ込みで流れるオープニングから、全般懐かしさが感じられるルックと王道のストーリーに大変好感が持てます。勿論、細部はきちんと現代的にアップデートされており、例えば裕福な白人家庭に育つ少年に対して、彼の言動にどこか「間抜け味」を漂わせたりをサラッと演出したりなどは決して個人攻撃に見せずに優しさが感じられますし、作中における血の気が多い若者たちの度々ドタバタに対しても、やり過ぎずどこか微笑ましさがあって最後まで穏やかに観続けられます。
キャストの皆さんもれなく素晴らしい演技でそれぞれの役に感情移入しやすく、また言うまでもないですが助演女優賞を受賞したダバイン・ジョイ・ランドルフに納得です。ただ、だからこそ「このポール・ジアマッティを主演男優賞を受賞させられないアカデミー賞」に少々ガッカリするくらい素晴らしい演技と表情で、彼が演じるポール・ハナムという教え子からしたら「ア〇ホールな教師」を物語の進行とともに段々と憎めない存在に思わせ、最終的には慈愛に満ちた人柄にしか見えないハナムに対して胸が熱くなります。
必ずしも「映画館で是非」という作品性ではありませんが、普段この手の作品を敬遠気味の方に対しも「配信でもいいから」観ていただければ納得いただける良作だと思います。私もまた年末頃に深く浸りたい一作でした。
素晴らしかった
映像の質感が、アメリカンニューシネマの時代そのもので、当時作られた幻の名作が発掘されました、と言われたら信じてしまう。『スケアクロウ』と同時上映されていても違和感がない。
はぐれ者の教師と生徒と給食のおばちゃんの3人が寄り添って年末年始を学校で過ごす。お互い仲がいいわけではなく、生徒と先生は決定的に仲が悪い。特にクリスマスは日本とは意味が違って、何がなんでも家族と過ごす重要な日だ。僕が若いころは彼女と過ごすのが当たり前だとされていて、一人で過ごすことがとても惨めに感じたものだけど、その何倍も彼らは心を苛まれていることだろう。
生徒の男の子が本当に世間知らずの甘ったれで、イライラする。彼が同級生と言い合いになるのだけど罵倒がすごい。イギリス映画かと思うほど口が悪い。
そうして過ごすうちにトラブルがあったりしてお互いに気心が知れていく。それがとても丁寧に描かれている。気心が知れすぎて、さらなるトラブルに発展して最終的に先生は職を失う。そんなにクビになるほどの失点ではないと思うが元々校長先生に嫌われていたので、これ幸いとクビにする口実にされたのかもしれない。
その先生がスケートリンクで大学の同級生と会って、つい見栄を張ってしまう場面が見ていて本当に心が苦しくなる。極力等身大であろうと心がけているのだけど、自分ももしあんなふうについ背伸びをしてしまったら、その後何日もベッドで眠れずに叫ぶことになる。
古本市で話しかける売春婦が絶妙で、ぱっと見ないわ~と思うのだけど話しているうちにもしかしてありかな、あれれ?みたいな感じだ。
一体なぜこんな映画を今の時代に作ろうとしたのか意図が分からない。他にも全体像として把握しきれていない感じがする。ただ、誰とも友達になりたいと思えなかったので、また見たい気持ちは今はあまりない。
家族によって傷ついた人たち
物語の主人公は生徒にも同僚にも嫌われている偏屈者の高校教師ポール、その言動で誰をも不快にさせる高校生のアンガス、そして酷く肥満した寄宿舎の料理長の黒人女性メアリー(一人息子を亡くした悲しみ、ストレスで肥満になったのかなあ)の三人。誰もが家族と共に過ごすであろうクリスマスから年明けにかけての10日間ほどをひと気の失くなった広々とした寄宿舎で3人は生活を共にする。そしてこの3人が付かず離れずの関係を保ちながらも互いの心の傷の深さや大きさを認識しその原因を理解していくなかで距離を詰めていく(その過程は決してべたべたしたものではない)。
結局、心の傷の原因は家族にある(わかるだけに沁みる)。自分を理解して欲しくて、そして頼りたくて…。そういう存在が家族であり、その家族に裏切られたと思ったり、頼ることができなくなったと思ったとき、人は本当に深く傷つく。その理由なんて考える余裕もなく。深く傷ついた人は溺れているのだから、もがきながら頼れると思った人にしがみつこうとするんだから仕方ないんだよ。
最後に、家族のいないポールはアンガスを救うことで、自分自身を救ったんだと思う。
※日本でも大ヒットした pop music ヴィーナス、嵐の恋、ノックは三回の3連発で、物語のあった1970年にタイムスリップして僕はこの映画を観てました。途中で流れたキャット・スティーブンスのウインドも懐かしかった(これは日本ではヒットしなかったな)。この時、僕の脳内で快感ホルモンが分泌されました。キャット・スティーブンスの歌は心が癒される。
傑作
単純な様だったが…?!
あったけぇよお。
近頃は切なかったり辛辣だったりする物語に入り浸っていたので、久かたぶりのハートウォーミングストーリー。
よかったよ~。
久しぶりに周りにお勧めできる作品だぁ~。
そうなんだあ〜こういう映画、好きなんだよなァ。
古いけど「アバウト・ア・ボーイ」を思い出しました。
短期間ながら、欧米ホリデーシーズンにまさかの学校居残りというシチュエーションはある種の密室劇のようであり、だからこそ所々の「外出」は観ているこちらもお出かけ気分というか主人公達と共にウキウキした気持ちになる。
そして当然のように起こる”何か”を経て、寮生活に戻るたび、何だかホッとしてしまう感覚は正に「我が家=ホーム」のそれ。起こるべく何かを恐れずに共有して、結果的な喜びも痛みも分かち合う。本作はそういった、まるで家族の正しい、あるべき姿をそれぞれの登場人物に分け与えていくのだ。聖なる季節であるからゆえの最高のプレゼント。
そりゃこの映画の観客だって嬉しくもなるさ。
家庭環境からヤサグレ盛りだったアンガスくん。序盤の校内追いかけっこは、?
はい…それ、私です…(^^;;
お恥ずかし過ぎて多くは語りませんが、個人的に物凄く彼の気持ちが理解できてしまって。年甲斐も無く追いかけてくるポール先生を見る彼の眼差しはすごく楽しそうでしたでしょう?本気で向き合ってくれる存在を渇望していたんだよね。そういう心の機微も上手に描いていたと思う。
劇場内では結構きちんと(?)笑い声が起きていたなあ。観客がこの物語にほぐされているようで嬉しかった。
「いやあ!映画って本当にいいもんですね」
って言いたいー!!(言ってるけど)
映画の感想書いてて、 『暫く泣き続けた』くらいのことをよく、 『号...
映画の感想書いてて、
『暫く泣き続けた』くらいのことをよく、
『号泣した』って書いちゃうことは正直あるけど、
これは、言葉の意味通り本当に『嗚咽』した
声が出そうになるのを抑えるのが大変だった
いや、少し漏れ出てた
「こっち側の目を見て話して」(うろ覚え)の台詞からその後、
泣きっぱなしでところどころ嗚咽
予告からある程度は読めちゃうストーリーだけど、
ここまでぐっとくるとは思わなかった
ストーリーは、
切なすぎるから好きなタイプじゃないけど、
でも作品としては良い内容だった
「The Holdovers」翻訳すると 残留者 みたいな感じ。 ...
「The Holdovers」翻訳すると 残留者 みたいな感じ。
邦題で「置いてけぼりのホリディ」と表現されてますが・・クリスマスに、置いてけぼりを喰らって ボッチクリスマスになってしまった人達のお話し。
いい映画でした。配信待つか、迷ったが・・鑑賞してよかった♪ただ、季節的にはクリスマスシーズンに鑑賞できれば理想的でした・・。
誰一人知っている俳優が出演していませんが・・こういう、出演俳優の名前に頼らない映画に名作は少なくない♪ これもそんな一作♪
私は、ポールであり、アンガスであり、メアリーでもある・・世にはそんな人も少なくないのかもしれない・。
1970年代・・まだ、理性と理想が現実と対峙できて、人の心が現実を動かすことができ時代だったのかもしれない・・。今はどうだろう???・・ポールは?アンガスは?メアリーが救われる世界になっているのか・・。1970年代が、現代、2024年はどうだ???と投げかけた映画なのかもしれない・・。
ポール、アンガス、メアリーが、自らを失わず、幸せにくらせる世界でありたいものです。
全297件中、221~240件目を表示