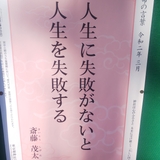リトル・ワンダーズのレビュー・感想・評価
全40件中、1~20件目を表示
新年1本目の映画館鑑賞だったのだけど 年明けぴったりな多幸感(季節...
最高👍
もっと突っ走って~
こういうジャンルたまにいいよね。
誰もが持つ「悪い子」心の冒険ファンタジー
子供は皆「悪いこと」をすることにある種の憧れを持っている。
巨大な倉庫に忍び込みゲーム機を盗んだら楽しいだろうな、というのは子供心の悪い憧れ。
実際には犯罪になるので出来ないことをこの映画は架空のファンタジーとして実現する。
いい意味でこの映画は中学生くらいの学生が学園祭で上映する8ミリ映画を面白いと思うことを好き勝手に入れて撮ったような伸びやかさがある。
ギャングや魔法使いも全部入れてしまえばいいのだ。
リアリティのない架空のファンタジーであることは、ほぼ本物のように見えて実はペイント弾の空気銃を操ったり、バイクを自由に操ったりする最初のシーンで提示される。
そして16ミリフィルムで撮られていることもフィクション感を増幅している。
この大冒険のきっかけも風邪で寝込んでいるママがブルーベリーパイを買ってきてと頼まれて、いつのまにか卵の争奪戦に巻き込まれていく、くだらなさのセンスが効いている。
その冒険の子供っぽさがこの作品の魅力だ。
友情に飢えた魔女の娘のペタルのこまっしゃくれた可愛さが秀逸。
魔法使いの一味の一人として出演もしているウェストン・ラズーリ監督は本作が長編デビュー作だというから驚く。次回作も期待。
グーニーズやスタンドバイミーのような王道子供冒険映画とは違う、ブラックユーモアのインディーズ子供映画の良作と言える。
「こんなレトロあるんだ」
アリスが超魅力的
KODAKの16㍉フィルムで撮影していて、
画質のザラっとした感じやコマ割りの荒さみたいなアナログ感がすごく良かったですね。
フォントなども80年代以前を彷彿とさせるデザインで、音楽も懐かしく、
観客に童心にかえってほしいというのがメッセージなのかなと思いました。
悪ガキは悪ガキですが、
ゲームはお店の倉庫から盗むわ、ゲームがやりたいがために、病床に伏せっているお母さんに
テレビのパスワードを聞きまくり、結果、お題として出たパイ作りに取り組むことになったのを
きっかけに、冒険が始まるんですね。
この動機ややっていることというのは到底看過できないわけですが、
映画なんで細かいことはいいかなとスルーして映画世界に没頭することにしました。
魔法の剣一味を率いる魔女(リオ・ティプトン)が本当に魔女だったりして、
現代×ファンタジーで、若干ダークなファンタジーではありますが、
物語に幅を持たせられたというか、この設定がなかったら凡庸なストーリーに終始して
面白くできなかったように思います。
もうひとりのちびっ子魔女のペタルを演じたローレライ・モートの演技も迫力がありましたし、
なんといってもアリスを演じたフィービー・フェロが超魅力的でしたね。
この子は今後大活躍しそうな予感がしました。とにかくビジュアルが素晴らしいです。
ファンタジーもありながら、ちょっぴり甘酸っぱいほのかな恋心なんかにも触れていて、
大人に童心を感じていただきたい、そんな作品でしたね。
素晴らしかった!
欲張り放題な無軌道キッズムービー
仲良しの子供たちが協力して悪い大人たちに立ち向かう姿を題材にした冒険ドラマでブルーベリーパイを手に入れようとして卵を奪われた3人組が魔女率いる謎の集団と遭遇する様を描きだす。欲張り放題な無軌道キッズムービー。ママの大好物ブルーベリーパイ調達のため悪ガキ集団が食料探しで大奮闘。まるで質感は超大編のRPGのようなめまぐるしいテイ。大人顔負けのキッズムービー。16mmフィルムの撮影でレトロでキュートな痕跡が味わえて、映画として奥深い。デザインセンスの良さが効き過ぎてる。フィクションをノンフィクションのようなデイドリーム感で覆いながらその手腕に痺れる。あれだけ卵の調達に時間や労力を割いたが、ラストのブルーベリーパイのくだりとの対比に笑ってしまった。ペイントガン?のよう小道具の使い方やシチュエーションがうつろう美術の魅せかたも、ティーンの冒険映画としての妙を肉付けする。ウェス・アンダーソン監督が協力してるようなセンスの良さが輝る爽快作になる。
ファンタジー映画
リトル・ワンダース(映画の記憶2024/10/29)
背筋が凍る
うーむ。あまりに残念。
ひとつひとつのピースはすごくいい感じなのに、1枚の絵へと完成することはなく、バラバラの状態で終わっちゃったみたいな、そんな映画。良い映画にはなにが必要なのか、それをすごく考えさせられる。
ゲームをやるためにパイを作る!なーんてとっても可愛い話なのに、やることなすこと全然可愛くなくて、全然話に入り込めない。予告で抱いたワクワクはどこへ?これだと、子どもたちに犯罪を助長させる最低な映画じゃん!
まるでRPGをプレイしているかのようなアドベンチャーっぷりは最高にいい。16mmフィルムで撮影された映像と相まって、子どもの頃に夢中になったゲームの数々を思い出す。作中に登場する子どもたちもみんなゲームに夢中。お菓子を広げて、ジュースを飲んで、画面に釘付けになりながらコントローラーを動かす。うんうん、わかるよぉその感覚。ゲームが世界の中心に回ってる感じ、すっごい懐かしい。
演じている子たちもきっと家ではテレビと睨めっこ。じゃないとこんなハイテンションでいられない。みんな自然な素振りでとっても楽しそう。みんな大物になりそうな、そんな予感がします。
アイテムをゲットした時にさりげなく効果音が流れたり、スコープみたいなので標的を確認したり、至る所にRPG要素があって楽しい映画であることは間違いない。ただ、ゲームのような設定、そして16mmフィルムであるにも関わらず、急に現実的な描写が出てきたり、スマホやGPSといった近代技術を駆使してしまったりと、せっかくの要素が台無しでシンプルにアドベンチャーとして面白くないし、積み上げてきた高揚感が一気にぶち壊れる感じですっかり冷めてしまう。
魔女という設定も結局のところゲームという枠組みに囚われたが故に生まれたものであり、全くもって機能してないし、粗が多すぎて興味すら湧かない。ご都合主義な展開に持っていくがためのもの。まじで余計だし、なんならこのせいでツッコミどころが出てきてしまっている。
悪ガキッズが大暴れ!と謳っていたから、てっきりもっとポップで明るい雰囲気を想像していたら、ビックリするほど暗くて湿っぽい。しかもストーリーに起伏がなく、盛り上がるべきところで盛り上がれていない感じがどうももどかしい。めちゃくちゃ犯罪やるくせに全然ぶち上げてくれないし、そんなんだから普通にダメな事だから!と思わざるを得ない。ちょっとしたイタズラなら良かったのに、迷惑すぎる行動に嫌悪感。これだと可愛いで済まされないからね。ラストも終わりよければすべてよし!みたいな、ハッピーエンドな締めくくりをしているけど、うーん。これは受け入れられない...。
細かなところは大好きだからこそ、素材を生かしきれなかったのが悔しくて悲しい。撮る人が撮ればもっといい映画になったろうに。。。ザンネン。最近期待する映画が尽くコケてしまう。映画の神様よ、どうかわたしにお恵みを...。
満点かゼロ点か
悪ガキたちの行動がどうとかという感想が多いですが、この作品の真骨頂は筋や話の展開ではなく、映像自体の恐ろしいほどのクセです。
これほどクセのある映像を撮るのは、私の知る限り小津安二郎とウェス・アンダーゾンくらいで、表現しようのない後を引くような独特の感触は一世を風靡したツインピークスに匹敵します。
感度の悪い変色した数十年前のフジカラープリントのような色調、アメリカ映画感が全くないのっぺりした俯瞰映像をバックに丸みを帯びた時代遅れのフォントを使ったタイトルバック、目線とズレたカメラアングル、リズム感ゼロの妙なダンス、唐突に現れる魔法や呪文、何を考えているのかわからない宇宙人のような子供たち。
この監督、とんでもないセンスの固まりなのか、自己満足過剰の勘違い男なのか、前者の感想の人は満点を、後者の人はゼロ点をつけるような不思議な作品です。
監督の心の中のおもちゃ箱みたい
AGFAのようなKODAK
本作の映像表現は、レトロな世界観と、
雄大な自然を対比させながら、独特の雰囲気を醸し出している。
しかし、その表現には、意図的なのか否か、
いくつかの疑問が残る。
特に印象的なのは、雄大な山々や森といった自然描写だ。
深い緑と青を基調とした色彩は、
クレジットのフォントの色もグリーンで、
懐かしいAGFAフィルムのようなB/Gの発色を、
KODAKで反映させているのだろう。
しかし、これらの自然が、
ほとんどのシーンでピンボケ気味に描かれている点が特徴的である。
これは、
意図的に自然と人間の距離感を表現しようとしたのかもしれない。
あるいは、絵画の印象派のような雰囲気を出すための、
スタイリッシュな選択なのかもしれない。
しかし、
この表現は、
自然の奥深さや生命力といったものを十分に描き出せているとは言い難い。
むしろ、合成写真のように平面的な印象を与え、
自然の立体感や奥行きが失われているように感じられる。
16mmカメラによる撮影の質感にこだわり、
懐かしい雰囲気を出そうとしているのは理解できる。
しかし、16mmフィルムの選択は、
メリットだけでなく、デメリットも考慮する必要がある。
撮影時の光量、画質の粗さや、
レンズの選択肢の少なさなど(時間をかけて使用するカメラにあうレンズをテストする必要有)、16mmフィルムならではの制約がある。
これらの制約を理解し、
表現したいイメージに合わせて適切なレンズとカメラを選択することが重要だ。
本作では、
16mmフィルムの特性を最大限に活かしているのかどうかは、
不明だった。
特に、自然描写においては、
よりシャープな映像表現が求められたのではないか。
映像表現だけでなく、シナリオや演出においても、
焦点が定まっていない部分が見られる。
特に、子供たちの冒険物語という大枠の中で、自然が果たす役割が曖昧である。自然は、単なる背景として描かれているのか、舞台が森である説得力があいまいだ。
ラスト5分は物語のクライマックスを効果的に表現していた。
しかし、全体的な映像表現の完成度という点では、
やや物足りなさを感じた。
子どもたちの必死さに、
星5つの観客は多いだろう、
だが、
パイを焼く、
卵を買う、
だけにシンプルに注力しておけば、
星5つの観客は5倍以上の人数になっていただろう。
「リトルランボーズ」とは違った。
80年代の子供映画をアップデートしたみたいな
「リトル・ワンダーズ」
面白かった。
無法で暴力的でジュブナイル。
80年代の映画のようでいてスマホは出てくる現代の話。なのに魔法(?)の存在する不可思議さ。
「グーニーズ」っぽい?とチラシから受けていたイメージは丸っきり的外れというワケでも無かった。
視点人物達はミニバイク乗り回し、飛び道具で武装し物を壊し人を撃ち、更には盗みを働きとろくでもない奴らで親の顔が見てみたい(見られます)んだけど、行動原理は子供っぽいし対峙する大人がまあまあヤバイやつで殺害後埋められそう!だし、無事を願わずにいられない。
幼い恋のストーリーが語られるのも良し。
過激ではあるが、吹き替え版があれば娘も連れてもう一度観たいらいだ。
追及:
他の方が指摘されてるように「そもそも母ちゃんが…」というのはあるけど、冒頭の襲撃シーンからして「それ気づくよね?」と言う部分はあるし、リアリティラインがその辺なんだな、と一応飲み込めました。
全40件中、1~20件目を表示