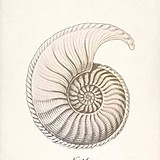霧の淵のレビュー・感想・評価
全18件を表示
環境、ヒーリング
井氷鹿は誰のために、この村に霧をもたらしたのだろうか
2024.5.2 アップリンク京都
2023年の日本映画(83分、G)
奈良県の奥深い村の旅館家族を描くヒューマンドラマ
監督&脚本は村瀬大智
物語の舞台は、奈良県川上村の料理旅館「朝日館」
女将の咲(水川あさみ)は結婚を機に旅館を継いでいて、今では義父のシゲ(堀田眞三)と二人で切り盛りしていた
夫の良治(三浦誠己)とは関係が悪化していて、離婚の話が出ているものの、離婚をすれば相続が受けられない状態だった
娘のイヒカ(三宅朱莉)は中学生になる寸前で、入学式を前に暇をしていて、母とシゲを眺めながら、同級生の達也(大友至恩)と何気ない時間を過ごしていた
ある日、都会から大学生3人(杉原亜実&中山慎悟&宮本伊織)が村の取材にやってきた
旅館に泊まることになり、地元の人たちを招いて勉強会と称する宴会が始まってしまう
ヤスタケ(春増薫)は村の歴史を語り、学生たちは傾聴し、メモを取っていた
その後、村の周辺の案内を任されたイヒカは、かつて映画館があったあたりを案内し、取材のモデルを務めることになった
映画は、淡々とした静かな映画で、時折劇伴とシゲの好きな曲が流れる感じで、イヒカがほとんど喋らないキャラクターになっていた
両親の不和はどうやら「父の浮気」のようで、山林見学の際に父に声をかけていた女性職員が相手のように思えた
声の先を睨むイヒカというわかりやす構図だが、その女性の顔は映し出されない
また、冒頭の離婚協議の際も「声だけ登場する相手」という描かれ方をしていて、両親ともに「画面の外側にいる相手」に話しかけているように描かれている
物語の主題は「隠」であり、「隠れる」「隠される」という二つのニュアンスが含まれていた
冒頭の協議で「隠される相手」と、「どこかに隠れたシゲ」という感じになっていて、これはシゲ自身がイヒカに語った「霧の存在理由」に似ている
霧が立ち込めると見えなくなるが、隠れるにはちょうどいいという言葉があって、シゲは文字通りにどこかに隠れたのだと思う
映画では、シゲの行方ははっきりと明示されないのだが、イヒカはシゲと会える場所を知っているように描かれていた
いずれにせよ、シゲの失踪の理由は語られず、財布もカバンもちゃんと持って出掛けていることだけはわかる
意図的にどこかに行ったのか、それとも何らかの事故に巻き込まれたのかはわからないが、認知症の気が少しだけ描かれていたので、自分自身がわからなくなる前に「隠れた」のだと思う
シゲが消えることで、咲は解放されることにもなるし、良治との関係を続ける必要もなくなって来る
いずれは旅館を畳む時が来るので、その瞬間を意図的に持ってきたように思えた
ちなみに「イヒカは井氷鹿と書く」のだが、これは『古事記』や『日本書紀』などに登場する神様の名前である
井氷鹿は川(井戸とも言われている)からやってきた神様で、川上村にある井光神社にも祀られている
神武天皇を案内し、御船山の尾根にある拝殿にて「進軍の勝利」を祈願したと言われている女神だった
もしかしたら彼女には「視える力」があるのかもしれないが、直接的な引用はないように思えた
幻想と現実
期待度○鑑賞後の満足度○ 奈良県川上村、良い処です。都会人、都会に憧れる人にとっては何もない処だけど人間が生活する最低限のものがあれば良いと思う人には何でも有る処。そこに流れる空気を描いた様な映画。
いやひどいな
どこかで見た絵ばかり
『萌の朱雀』や濱口竜介や深田晃司の、なんちゃって縮小廉価版。映画学校で15分で撮るべき課題製作を延々とみせられた感あり。オープニングまでに「音楽のセンスが悪くて編集のテンポ感が鈍くて照明もへたっぴい」という印象を受けて、結局それが最後まで変わらない。
少女が古い旅館の窓ガラス越しに外を見ているショットが思わせぶりに反復されるが、べつにひどくうまく撮れてはいないのでただ白けるのみ。
ロングもクローズアップも、ほとんどすべてのショットがやはり「スチル写真」としか意識されていないから、シーンが作れない。伸ばした方がよいものを切り、切り上げた方がよいものをだらだら見せる。しかもそこで見せられているものは、ほぼ全部、過去の映画にもっと素晴らしい作例があるものばかり。それらを真面目に見てきていない観客をダマすことはできるだろうが。
このレベルだと、もののはずみでどうでもいいマイナーな映画賞をもらうのが関の山。東京藝大院映画専攻との、格と知性の落差がいたたまれない。
登場人物のバックボーンを想像するということ
映画の楽しみの一つに、登場人物の語られないバックボーンを想像するということがあります。映画自身の完成度にプラスして、表出された演技から過去あったことや心の傷など個人個人の想像力が加わることにより無限の創造物になる可能性があります。
本映画も、登場人物のバックボーンがあまり語られないタイプの映画です。
各役者がそれぞれの演技でそれを補うことで、説明的なシーンはほとんど省略しています。
演者の表現力が試される映画とも言えます。このタイプで、個人的に近年最も良かったのが「アフターサン」でした。
さて本作に立ち返り、どうよと問われると、私にはうまく伝わってきませんでした。それぞれの演者はそれぞれのシーンで熱演していますが。
おそらく今なお残る奈良のノスタルジックな町並みと清らかな大和川の源流と歴史ある林業を全面に出したかったのでしょうが、撮影の問題か光源の問題か、上手に取れていない印象があります。後半のクライマックスシーンも、色々ご苦労されて撮影したと思うのですが、セットや小物など細部を含め切り取った時代が不鮮明(昭和中盤~後半と思われますが)でリアリティが感じられず、めちゃめちゃキレイ!とは感じませんでした。
映画は監督が表現したいことがありますが、予算や納期など限られた条件の下で良いものを作るのは大変だと改めて思いました。
外から来た人、そこで生まれた人
奈良県の山間部にある過疎化した村で父親の実家である旅館を切り盛りする母親と手伝いをする爺ちゃんと12歳の娘をみせる話。
父親は役所勤めか林業か別居して暮らしており離婚話しもチラホラと、シゲ兄こと爺さんが手伝いながらたまにやってくる客を泊めたり村人に食事処を提供したりという状況の朝日館。
序盤は。ストーリーとは何ら関係ない日常会話の様なものをみせたり、BGMを流して日常をみせるだけだったりとなかなかまったり。
これといったものもないまま、突然爺ちゃんが帰って来なくなり、そして旅館はどうするのかと…。
なんだかのペ〜っと投げかけているのかもわからない程度の行き詰まり感はあるけれど、そもそもそう遠くないうちにその状況に陥る訳で、子ども目線で考えたら確かに突然の一大事かも知れないけれど、なんだかぼやっともやっとした作品だった。
霧の淵の村で
全18件を表示