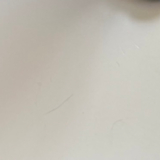あんのことのレビュー・感想・評価
全570件中、281~300件目を表示
心は千々に乱れ、感想も千々に乱れる…
実話をもとにした作品。胸が潰れそうになる。にわかには信じられない現実に驚くばかり。既成の概念が覆される。
毒親のもとに生まれ落ちた悲劇、と一言ですませることもできようが、この作品を鑑賞したあとの心は千々に乱れる。
なんのために、どうして、こんなことになるのかと、頭は混乱し、心はあらぬ方向で救いを求めてしまうのである。
子は親を選べないといわれるが、仏法的思想のなかには、子は親を選んで生まれて来るという考えかたもあるそうだ。
でも、そんな深淵?そうな教えは、この際どうでもよいのである。現実の世界での人の生き死には現実の世界の価値観で判断されればいいことであって。それ以上でも以下でもないのである。でも、である。
糾弾されるべきは母親であり、母親の生きながらの堕地獄は間違いない。地獄の人生を歩むことになるだろう。
この罪深すぎる母を罰するために、この母から生まれ出たとすれば、すこしは溜飲が下がる気もするのである。
まったく見当はずれの感想になったか…。
心は千々に乱れ、そんな感想で自分を納得させるしか方法がないのである。
ひどすぎる!!!
とてもリアリティを感じた空気感
悲しく、辛いストーリーだったが、とてもリアリティを感じた。キャストそれぞれがスクリーンの中で活きていたからだと思う。人は一人では生きられない、また自立して一人で生きてると思っていても、必ず社会の中で、人と関わって生きているのだということを、明確に描いている。人に頼ることは時に自分勝手、甘えてると映るかもしれない、しかし、全て正しく考え正しく出来る人間なんていないのだ。人とのつながり、思いやり。心を保ち、人間が生きるのに必要なこと。改めてこの作品を見て思い返したりした。
あんちゃんのこと
途中からずっと、あんちゃんを応援していた。
頑張りが報われて、幸せになって欲しいと思った。
刑事さんが逮捕された時も、勉強中にペンが書けなくなった時も、一生懸命ハヤトくんをお世話してた時も、がんばれがんばれ、幸せになってくれ、と手に汗握りながら、あんちゃんを応援するような気持ちで観ていた。
ブルーインパルスが映った時、自分はなにしてたかな、と思った。
たしか、仕事が自宅待機になって、働かなくてもお給料もらえてラッキーだとかそんなことを思っていた時期だったと思う。
自分がそうやって呑気に暮らしていた時に、あんちゃんのような人が実際にいたこと、今もそういう人たちがいること。
高校生の時、クラスにあんちゃんにちょっと似た雰囲気の子がいたことを、久しぶりに思い出した。
多分親との関係とかあんまり良くないんじゃないかな、と勝手に思っていた。
今あの子はどうしてるだろうか。
誰か頼むからあんちゃんを助けてくれよ、と映画を観ながら憤っていたのに、自分も現実で誰にも手を差し伸べていないことを自覚させられた。
誰かを助けられる人になりたいと思ったし、助けてと言ってもらえるだけの信頼を得られる人間になりたいと思った。
救われない。
不幸の連鎖。
元々不幸な身の上だったが、光が差し込み、人生が開けていった…かに見えた。
ゾンビの様に群がってくる母親、関わってくれた大人の裏切り、(コロナによる)失業・学校停止等によるコミュニティの喪失。そして疲れ果て、また薬に手を出してしまった事に対する後悔…。
あそこまで不幸な状況に置かれていたのにも関わらず、彼女の心根はとても優しく、素直。だからこそ、傷つき、疲れ果てた。
コロナ開けて、また職に戻り、登り龍のお爺さんと再会する前に、彼女が先に天国へ登ってしまった。何処か一つでも違ったら、また違った結果があったでしょうに。
合掌。
辛い、でも観て良かった
シン積木くずし
けっきょくは環境
こんなにも観たあとに、切ないというか、悔しいというか、なんともいえない感情を抱いた映画はないのではないか。
家に帰る途中も何度もこみ上げてくるものがありました。
けっきょくは環境。いかに環境が大事か、まわりに信頼できる人間がいるか、だな。
衝撃的な映画
kino cinema新宿にて鑑賞。
予告編は観ていたが、これを観た後には「本当に実話なの!」という衝撃が重くのしかかってくる入江悠監督作品🎥
毒母親に売春を強要されヤク中の香川杏(河合優実)は、自分も売春している毒親と身体不調の祖母と団地に暮らしていた。
毒親からは殴る蹴るのDVも受けて荒んだ生活をしていて、小学校も出ていない。
そんな折、一見変わった刑事の多々羅(佐藤二朗)に補導されたことを契機に、赤羽の「元ヤク中どうしの会」に誘われて、あんはヤクを止めて、難しい漢字も書けないので学校にも通い始める。そして、あんに希望が見えかけた生活になっていく。
刑事=多々羅に近づいたジャーナリスト桐野(稲垣吾郎)とあんの三人は、カラオケ行ったり、酒を飲んだりと仲良く過ごしていたが、桐野はなにやら刑事を調べている様子。
そして、決定的な記事を桐野が書いて世間に広まると、赤羽の会も無くなり、新型コロナウイルスが始まり……と、あんの居場所が段々なくなって……。
いやぁ、凄い映画だった‼️
新型コロナウイルスが始まった頃に、こんな事件があったのか!……という驚きとともに、様々な偶然が一人の女性の運命を狂わしてしまう残酷さに圧倒された。
この作品であんを演じた河合優実を初めてスクリーンで観たのが『由宇子の天秤』だった。
しかし、この女優、出演する作品ごとの「役作りが見事」だと思う🙂✌️
あの閉塞感あふれるコロナ禍はじまった頃の出来事を、丹念にスクリーンに映して見せた見事な映画であった✨✨✨
<映倫No.123711>
意外と
とにかく河合優実の演技が素晴らしい。
とにかく河合優実の演技が素晴らしい。脚本、監督は社会派の入江悠。事実に基づく映画、とのことだが、刑事の犯罪、隣の母親から子供を預かる、なども事実だったのだろうか?そうであればば正に事実は小説よりも奇なり、だが。こういう結末になってしまうのはコロナのせいでもあろうが、誰よりも責められるべきは一緒に暮らしてきた母親と祖母ではないか?ハヤト君との束の間の親子ごっこは彼女にも心に残る体験だったろうが、我々映画を観ている者も救われた気がした。以前観た入江悠監督の作品"ビジランテ"には
全く共感できなかったが、これは良かった。
生きてさえいれば、、。
杏は、もがき苦しみながらも確かに生きていた。
ただ一つの願いは普通の人間になりたかっただけ。だから介護の仕事を身につけたかったし、読み書きをちゃんとできるようなりたかったから学校にも行った。
支えてくれる人も沢山いた。特に刑事の多々羅は誠心誠意寄り添ってくれた(後に彼の性犯罪が暴露されるが)。彼がいなければクスリを断つことすら考えなかったと思う。
記者の桐野も養護老人ホームの施設長も働くことや学ぶことの場を提供してくれた。
しかしコロナはその場を容赦なく奪ってしまうし、母親(杏から搾取することしか考えない悪魔)からは必死に逃げてきたのに、結局見つかってしまう。さらに生きる糧になっていた幼い隼人との生活も母親が引き離し、奪ってしまった、、。
杏、。それでも私たち(関わった全ての人々、映画を観ている人々)は、あなたに「生きていて欲しかった」と思います。不寛容な社会だけれども、心ある人はいます。生きてさえいれば助けてくれます。必ず、。
映画タイトル通り、全編、杏の物語です。その杏を演じた河合優実。
すでに数多くの映画、ドラマに出て大注目されてますが、この杏役は主演女優賞級の迫真の演技でした。素晴らしかったです。次回作も楽しです。
河合優実ー(佐藤二朗+稲垣吾郎)=結局は残念
河合優実(香川杏)
確かによかった。この人だけを中心に「円」を描いていれば、良い映画になったのだろう。冒頭と最後、早朝の何もない町を歩く姿こそ、心象風景。この映画はこれで十分。
佐藤二朗(多々羅保)
おそらくは必要なかった。いつもと同じ、それ以上の演技を見せられてはたまらない。最初から、そうだろうなという結果が見えている。グルーミング刑事というのはあまりにも安易な設定。
稲垣吾郎(桐野達樹)
だから、こちらも最初から見えていた。だから、ストーリーには必要なかった。味付けにもならない。
むしろ、毒親の
河井青葉(香川春海)をもう少し食い込ませてみたり、
自分が生きながらえるために、育児を一旦手放す
早見あかり(三隅紗良)を丁寧に描いていれば、
「あんの<こと>」「あんという<こと>」「あんが生きていた<こと>」ということが、
強く描いだされてのだと思うのだが、どうだろうか。
あんが自分の日記、メモ、ノート、
これが「あんの<こと>」なのだが、
それの一部を握りしめ、死へと歩み出し、それへと至った河合優実の演技は見事であっただけに、
この後の、
杏がなくなった後の多々羅と桐野の無駄な映像とセリフは、ストーリーのそれまでを全て台無しにしてしまっており、甚だ残念だった。
#最近、どうも、佐藤二朗の使い道に難渋しているように見える。
稲垣吾郎と佐藤二朗の役は反対じゃないのかな・・。とも思えた。
想定内の落胆
前評判が良く、佐藤二朗氏がどのような善人振りを演じるのか期待を以て観続けたが、想定内の悪役振りだった。
毒親が諸悪の根源で、子どもがそこから抜けられないことで人生を棒に振る物語は多々あるし、その範囲内に落ち着いたのではないか。
介護施設の事務的ミスはがっかりだし、シェルターの保護機能をもっと活用してもらいたかったところである。
稲垣吾郎氏は、少し下手に歌い、佐藤二朗氏は、精一杯歌っていたようだった。
実話は重い
母親からDVを受け続け、売春まで強要され、薬物づけになり、小学校も途中で行かなくなり中学にはまったく行っていない、ほぼ漢字も書けない21歳の女性、それが杏だ。母親の管理下におかえれ身体を売って金を稼いで生きている。
そんな杏に手を差し伸べたのは刑事の多田羅と新聞記者の桐野である。、多田羅に勧められ薬物依存者の集まりに出て徐々に心が氷解していく。そしてリ・スタートをきる。二人の協力を得て住む場所も決まり、働き場を確保し、学校にも行きはじめ杏の人生はうまく回りだす。初めて自由を手にした杏の楽し気な歓びあふれた笑顔がなんとも素敵だ。今までの人生で味わったことのない充実感にあふれていた。
ところが杏の生活はあっけなく逆回転してしまう。多田羅が杏の前から消え、加えてコロナ禍の発生で職場から離れ、学校も閉鎖し社会との扉が閉じられていくのだ。そしてある事柄が起きてしまう。何事にも一生懸命、前向きに対処する杏が健気で本当に心の優しい子だと実感する。満ち足りていた生活にまたも母親の毒牙にかかる。
入江悠監督のオリジナル脚本・監督作品では、「不条理・理不尽に翻弄される」映画が非常にインパクトが強い。「シュシュシュの娘」「ビジランテ」二作品とも逃れられない不条理で理不尽な組織、家族がテーマになっている。「あんのこと」も確かに不条理で理不尽な家庭環境を扱った作品であり、今までの入江監督のテーマと同様である。しかしこの映画は実話である。フィクションとは比較にならない事実なのだ。
入江監督は、主演の河合優実には、翻弄されるままの姿と自分が生きていると実感する二面性、佐藤二朗には、善悪裏表の生き方、河井青葉には、超えてはならない境界を超える壮絶さを与え、入江悠監督が目指した実話の映画の強度、重みを表現しきった。これは事実だと映画として見る者に杏の生きてきた過程を見せつけるのである。見る者はただ圧倒されるしかない、この悲劇に。そして杏の嬉しそうな笑顔も忘れない。杏の無邪気な笑顔。素直に何事にも頑張る杏を見ているから、この事実に何も言えない。
全570件中、281~300件目を表示