コラム:FROM HOLLYWOOD CAFE - 第18回
2001年6月1日更新

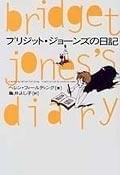

「ねえ、なんで映画って原作モノが多いの?」
このあいだ音楽ジャーナリストの友人に訊かれて、ハッとした。そういえば確かに多い。いまアメリカで公開中の「ブロウ」「ショコラ」「ブリジット・ジョーンズの日記」などはすべて原作小説があるし、これから製作される映画の中にも小説やノンフィクションをもとにしたものがやたらとある。スピルバーグ監督の「マイノリティ・レポート」や「さゆり」、リドリー・スコット監督の「Black Hawk Down」、アンソニー・ミンゲラ監督の「コールド・マウンテン」、コーエン兄弟でブラピ主演の「白の海へ」、ディカプリオ主演の「Catch Me If You Can」など、挙げればきりがないほどだ。映画界全体でどの程度のパーセンテージを占めるのかどうかは分からないけれど、けっこうな割合であることは確かだと思う。特に邦画の場合は、オリジナル作品の方が少ないくらいだ。
で、その理由はつまるところ「楽だから」だと思う。通常映画を作る場合、ディベロップメントという企画開発を経て脚本執筆となるわけだが、小説を元にすればストーリーができ上がっているので、すぐに脚本に取りかかることができる。ディベロップの段階でああでもない、こうでもないとストーリーを練る手間がかからないし、完成形が見えているからゴーサインも出やすい。さらに、ベストセラーの場合、すでにその名が一般に知れ渡っているというメリットがある。

しかし、落とし穴もある。小説のイメージが浸透しているので、下手に映画化すると小説のファンを裏切ってしまう可能性がある。たとえば「ブリジット・ジョーンズの日記」の映画化でレニー・ゼルウィガーが主役に決まったとき、イギリス人のファンは「テキサス生まれのガリガリ女に、ブリジットを演じさせるなんて!」と激怒した(レニーはイギリス訛りをマスターし、体重を一気に増やすことでファンを納得させたが)。
また、小説と映画の根本的な違いにも気をつけなくてはいけない。映画は映像で伝えるメディアだから、主人公の内面がよく描かれている小説があっても、それが面白い映画になるとは限らない(まあ、「ハイ・フィデリティ」のように、キャラクターに内面を語らせてしまうという裏技もあるけど)。また、尺の長さも大きなポイントだ。普通の小説を映画化すると、たいてい2時間の上映時間を優に超えてしまう。だから映画化の際は、小説を切り刻んでスリム化を図らないといけない。いわば物語のエッセンスだけを映画化するということだが、これができないとマット・デイモン主演の例の映画のように一貫性を欠いたものになってしまう(タイトルは明かせないけど、「馬」の映画です)。
小説好きとしては自分の好きな作品がどのように映像化されるか楽しみだけれど、映画ファンとしてみれば、ちょっと複雑な気分だ。もっとオリジナルの映画が観たいよなあ。
筆者紹介

小西未来(こにし・みらい)。1971年生まれ。ゴールデングローブ賞を運営するゴールデングローブ協会に所属する、米LA在住のフィルムメイカー/映画ジャーナリスト。「ガール・クレイジー」(ジェン・バンブリィ著)、「ウォールフラワー」(スティーブン・チョボウスキー著)、「ピクサー流マネジメント術 天才集団はいかにしてヒットを生み出してきたのか」(エド・キャットマル著)などの翻訳を担当。2015年に日本酒ドキュメンタリー「カンパイ!世界が恋する日本酒」を監督、16年7月に日本公開された。ブログ「STOLEN MOMENTS」では、最新のハリウッド映画やお気に入りの海外ドラマ、取材の裏話などを紹介。
Twitter:@miraikonishi





