アンナ・マグダレーナ・バッハの日記
劇場公開日:1985年12月14日
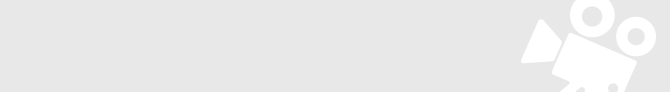
解説
二番目の妻アンナ・マグダレーナ・バッハの目から見たヨハン・セバスチャン・バッハの生涯を描く。監督・脚本はジャン・マリー・ストローブ、ダニエル・ユイレ夫妻、撮影はウーゴ・ピッコーネ、サヴェリオ・ディアマンテ、ジョヴァンニ・カンファレッリ、音楽はレオ・レオニウスが担当。出演はグスタフ・レオンハルト、クリスチアーネ・ラング・ドレヴァンツなど。映画はわずか100足らずのショットによって構成されている。画面に現れるのは演奏する音楽家たちだけで、アンナ・マグダレーナ(クリスチアーネ・ラング・ドレヴァンツ)のナレーションによってバッハ(グスタフ・レオンハルト)の35歳から、死までが語られる。画面で演奏されるバッハの作品は<ブランデンブルク協奏曲第5番BWV1050第一楽章アレーグロ><「ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より第8プレリュードBWV854><メヌエット・フランス組曲第1番第6曲BWV812><ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ第2番BWV1208第1楽章アダージョ><オルガン・トリオ第2番BWB526第2楽章ラルゴ><マニフィカトBWV243第11・12曲><テンポ・ディ・ガボックパルティータ第6番第6曲BWV830><カンタータ第265番「破れ、砕け、こぼて」BWV205第2、3曲バス・レチタティーヴォとアリア><カンタータ第198番「候妃よ、さらに一条の光を」BWV198終結合唱><ケーテン候葬送音楽BWV244 ソプラノ・アリア><マタイ受難曲BWV244冒頭合唱><カンタータ第42番「この同じ安息日の夕」BWV42冒頭シンフォニーアとテノール・レチタティーヴォ>他全24曲。1972年、アンナ・マグダレーナは、バッハの2度目の妻として迎え入れられる。それから29年後の1756年に死ぬまでの間のバッハの創造的苦悩、家庭でのアンナや子供たちへの態度が、これらの音楽の作曲された年月にそって語られる。
1968年製作/西ドイツ・イタリア合作
原題または英題:Chronik der Anna Magdalena Bach
配給:ユーロスペース
劇場公開日:1985年12月14日
スタッフ・キャスト
- 監督
- ジャン=マリー・ストローブ
- ダニエル・ユイレ
- 脚本
- ジャン=マリー・ストローブ
- ダニエル・ユイレ
- 撮影
- ウーゴ・ピッコーネ
- サヴェリオ・ディアマンテ
- ジョヴァンニ・カンファレッリ
- 音楽
- レオ・レオニウス
- 録音
- Louis Hochet
- Lucien Moreau
- Paul Scholer
- 字幕
- 堀越謙三
-

Sebastien_Bachグスタフ・レオンハルト
-

Anna_Mogdalena_Bachクリスチアーネ・ラング・ドレヴァンツ
-

不明Joachim Wolf
-

不明パオロ・カルリーニ
-

不明Hans Peter Boye
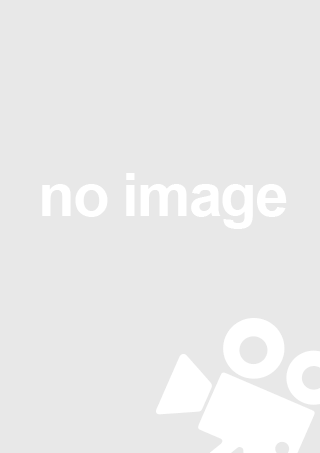
 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 この世界の片隅に
この世界の片隅に ダンケルク
ダンケルク 1917 命をかけた伝令
1917 命をかけた伝令 アリー/ スター誕生
アリー/ スター誕生 RRR
RRR 君の膵臓をたべたい
君の膵臓をたべたい









