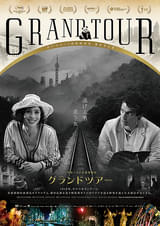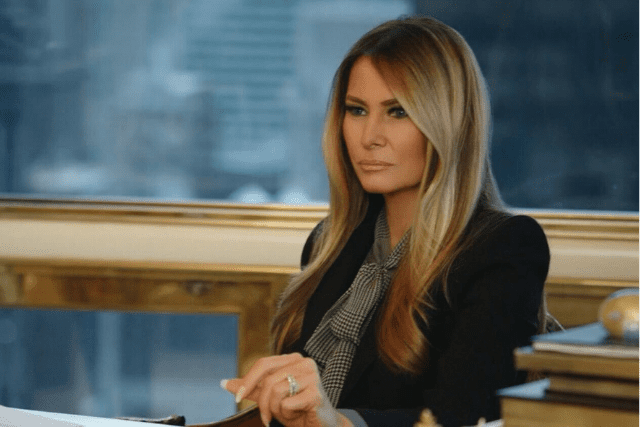このほど、来日したゴメス監督とアソシエイト・プロデューサーとして参加した「大いなる不在」の映画監督、近浦啓氏との対談を映画.comが入手した。2020年1月に1週間程度かけて行われた日本での撮影の裏話から互いが受けた影響、作品に込めた思いまで語り合った。
 「グランドツアー」(C)2024 ‒ Uma Pedra No Sapato ‒ Vivo film ‒ Shellac Sud ‒ Cinéma Defacto
「グランドツアー」(C)2024 ‒ Uma Pedra No Sapato ‒ Vivo film ‒ Shellac Sud ‒ Cinéma Defactoミャンマー/シンガポール/タイ/ベトナム/フィリピン/日本/中国のアジア7カ国でロケを敢行した本作は、逃げる男と追う女が繰り広げる時空を超えた大旅行の行方を、過去と現代、現実と幻想、カラーとモノクロを混在させながら描き出し、観る者を摩訶不思議な境地<グランドツアー>に誘う物語。
――まずは近浦さんがアソシエイト・プロデューサーとして「
グランドツアー」に参加することになった経緯をお伺いできますか。
近浦:2019年に
ミゲル・ゴメス監督が翌年のアジア各国での撮影のチームを組成している中で、友人に紹介していただいたことがきっかけです。あの
ミゲル・ゴメスが日本で撮影をするならぜひ参加したいと思いました。
――撮影は京都、大阪、神戸、長野、岐阜、富山で行われたとのことですが、ロケ地はどのように決められたのでしょうか。
近浦:監督に明確なビジョンがありましたので、「こういう場所で撮影したい」という彼からのオーダーを受けて日本側のロケハンチームがそのイメージに合うものを探して提案をしました。

――日本での思い出深いエピソードがあれば教えてください。
ミゲル:日本に来る前にフィリピンで撮影をしました。フィリピンの撮影の仕方は日本の真逆で、いわゆる“シュート&ラン”でした。無許可で撮影して、警察や当局が来たらチーム全員で逃げるという撮り方です。日本はプラン通りに撮影をするという全く違うやり方で、日本のロケハンチームと私たちポルトガルの撮影チームの間にちょっとした文化的な齟齬が生じました。少しギスギスとした状態になってしまったんです。
そんな折に啓が来てくれて、外交面でまるで魔法のような叡智を授けてくれて、素晴らしい仕事をしてくれました。私たちの間を仲介してくれて、プロデューサーとして費用面でも私たちの懸念を払拭してくれて、理解者が現れたと安堵しました。映画のためにすべきことをしているという認識も新たにすることできました。ぜひまた次の機会があれば参加いただきたいです。

近浦:僕自身も映画作家なので、彼に満足いく画を撮ってもらいたいという思いが一番強かったです。僕が一番心配してたのは、事前にロケハンの写真とか映像を彼に送ってやり取りはしてたものの、ミゲルもサヨムプーも他のポルトガルからのメンバーたちも撮影日に初めてその場に行くことになりますので、限られた時間の中で撮影を終えることができるだろうかということでした。まずは京都の東山で撮影を始めました。スケジュールがぎっちり詰まっていましたが、ミゲルは慌てるそぶりも見せず悠然と構えていました。
撮影車から降りると散歩をするような雰囲気で周辺を歩き回り、ファインダーを覗いて撮るべきフレームを見つけると、彼が撮影監督にレンズのミリ数をそっと伝える。すると撮影チームがすごいスピードで撮影の準備を整えて、さっと撮る。僕はその様子を見て、有機的に仲間が繋がっているロックバンドのようなチームだと思いました。日本側のスタッフは、事前の準備を徹底するという側面が強いこともあり、撮影するはずだった場所で撮らなくなったり、全く想定していない場所で撮影することになったりと即興の割合が高いスタイルに当初は少し戸惑いはあったようですが、皆、時間が経つにつれてその瞬間瞬間を楽しむように変化していったように思えました。

――そのロックバンドのようなチームワークは、アジアをまわって撮影をするなかで培われていったものなのでしょうか。
ミゲル:ロックンロールの精神というのは 50年代に生まれたもので、私は実際演奏などもあまりできないのですが、アドリブ的に世界の美しさを一瞬で捉えるということに関しては、若干アナーキーというか野生的な面もあって、そういう意味ではロックンロール精神を踏襲できたのではないかなと思います。
近浦:僕は当時は、一作目の長編映画(「
コンプリシティ 優しい共犯」)を発表して次の作品の構想を練っていた時期でした。ミゲルの撮影現場に身を置きつぶさに観察できたことで、「こうやって自由に映画を撮っていけるんだ」と。そういう意味で、大きな影響をもらいました。結果、それから3年後に次の作品(「
大いなる不在」)を発表することができたのですが、スタイルというよりスピリットの面で多大な影響を受けました。「
グランドツアー」は、当時完全な脚本はできていなくて、アジアを巡る撮影の旅の中で脚本のアイディアをまとめて、ポルトガルに戻ってから脚本を仕上げる。そういった工程だったと聞いています。撮影のなかで物語を考えながら画を見つけに行ったのか、もしくは画から物語が浮かんできたのか、聞いてみたいです。

ミゲル:自分の考える映画は、アイディアの前に具体的なものから始めることも考えられると思います。例えばカメラの前に通り過ぎる人々や、あるいは家や風景などの現実をどのように捉えるかということがあると思います。この寒さをどうやって表現しようかとか、この家の空間をどう表現しようかとか。そういうものは映画のストーリーとかアイディアの前にあってもいいと思っています。啓は映画監督なので、この点については理解してくれると思います。映画は間接的なところから始められると考えています。
近浦:この作品の見事なラストシーンにも言えることですが、ドキュメンタリーとフィクションの境目、あるいは時空を曖昧にする、しかも非常に大胆でファンタジックなやり方でそれを行う。このようなミゲルの映画作劇は、どういったところから影響を受けたのでしょうか?
ミゲル:具体的なものを撮影するときに場所とか印象も残るのですが、実はその印象の裏にはストーリーがあると思っています。「
グランドツアー」で山のなかにある素晴らしい木造建築で撮影をしたのですが、ちょうどお祭りが開催されていて、夜になると家の中に光が入ってきたんです。それを見たときに50年代のホラー映画の雰囲気を思い出しました。そこでまた私のロックンロール精神が出てきて、チームに幽霊が出てくるようなシーンにしたいと言ったんです。チームは全くそんなことを想定してなかったんですけど、光の前を動いて影を作ったり、ドアをパタパタ動かして音を出したりして撮影を進めました。それで結果的に映画になったときに、日本でのエドワードと虚無僧のシーンは全体的に暗い印象になりました。現実からフィクションが生まれたんです。

――近浦さんは実際に完成した「
グランドツアー」を観てどう感じられましたか。
近浦:特に印象的だったのは、実際のアジア各国で撮った開いた世界のドキュメンタリー的な映像と、逆にそれらの一部を欧州のスタジオで再現して撮影した閉じた世界の映像の対比がとても面白いなと思いました。また、物語の時代設定は20世紀の初頭ではあるものの、それが語られるモノローグの前景で僕たちが目にするものは、例えば現代の大阪・道頓堀の映像だったりしています。そして不思議なことに、最終的には「
グランドツアー」というフィクション映画のなかに全てが深く根付いているように思えました。時空を超えた物語のような不思議な感覚を得ることができました。
ミゲル:褒めていただいて嬉しいのですが、自分にそこまでの能力があるかどうかは疑わしいと思っています。現代に何かを撮影しようとすると、そこにはすでに過去の物語が積み重ねっていると考えています。例えば虚無僧も過去の存在のようですが、彼らは役者ではなく、実際に現代に存在していているんですね。特に京都は近代的なものと歴史的なものが共存していて、ただ単にカメラを向けるだけでそういうさまざまな時代の重なり合いのようなものが撮影できるので、私個人の才能で成し遂げたわけではありません。
近浦:モノローグの言語も、例えば英語だけに統一するのではなくて、エリアごとに各国の言語にしていたことも印象的だったのですが、あれはどういった理由でそうしましたか?

ミゲル:言語を変えることも旅を意味すると思ったのです。もう一つは映画のなかに操り人形が出てきますが、操り人形の世界では、人形と操作する人に主従関係があります。それを考えたときに、外国人のナレーターが主人公のイギリス人を操ることで、力関係を変えるのはどうかと思ったのです。ナレーションをアジア人、人形たちをイギリス人にして西洋と東洋の力関係を逆転させました。エドワードとモリーは、ちょっとずれた感覚でアジアにいて居場所がない状況ですよね。そんな彼らに語りかけるのがアジア人という構図も意識しました。
――近浦さんは
ミゲル・ゴメス監督の作品にはどのような魅力があると思いますか。
近浦:ポルトガルの巨匠であるオリヴェイラ監督の荘厳さと比較すると、ミゲルの場合、もっとそこにユーモアや幻想の要素が入ってくる。クラシックな映画たちとの対話が繰り広げられている中に、すっとセンスのいいユーモアが入ってきて、これが僕は本当に好きです。あなたにとって映画におけるユーモアとはどのように引き出されるものでしょうか?

ミゲル:荘厳な映画は、私は少し怖いと感じます。例えば教会のミサのような真面目な映画は私にとってはありえないと思います。自分が恵まれていると思うのは、パーソナルな映画が撮れるということです。啓のようなプロデューサーに恵まれたおかげですね。こういうモデルの映画を撮りなさいとか押し付けられず、制限もなしに、信頼関係のなかで映画を撮ることができています。
私もその信頼に応えようと最善を尽くすのですが、同時に私自身でいられるんです。自分の好みや人格に対して非常に忠実でいられます。ユーモアは私の人格のなかに含まれています。今世界では、悲しいことや残酷なこと、恐ろしいことがたくさん起きていますが、それと並行して世界は非常にコミカルで面白可笑しい一面もあります。自分の作品や人格としては、そちらを表現していきたいと思うのです。
「グランドツアー」はTOHOシネマズ シャンテ、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下ほか全国公開中。近浦氏による、貴重な撮影裏エピソードを綴ったコラムは、公開劇場で販売されるオフィシャルパンフレットに収録されている。















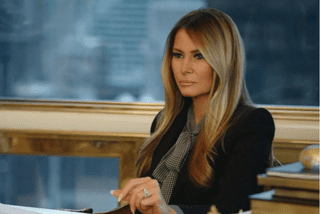 注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集  注目特集
注目特集