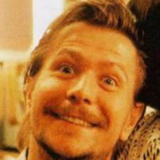ある閉ざされた雪の山荘でのレビュー・感想・評価
全170件中、141~160件目を表示
び、微妙…
東野圭吾さんの小説は昔に何冊か読んだことがあり、面白かった記憶があります。
なので本作は未読ですが、期待して見に行きました
結果、かなり微妙…
まず、閉ざされた山荘といういかにもな舞台が用意されているので、てっきり人の死にパニックになったり、緊張感のある疑心暗鬼の謎解き合戦でもあるのかと思っていましたが、全然そんなことはなく…
全くと言っていいほど謎解きしません!
なんで…
種明かしのシーンも、まぁこの人犯人だよね!って感じだし…
自分を半身不随にした相手を殺そうとしてたのに、ごめんなさい(泣)で許すってどんだけしょぼい殺意なんだよ…
(そもそも、ながらスマホしてるんだから自業自得感ある)
あと、2人にネタばらししなかった理由何?
蚊帳の外感凄い
これなら、全員知ってて全員演技でした!か、2人のキャラ削除でよくない?と思った
あとあと、時折出てきた見取り図のカットは何?
わざわざ何度も入れてきたんだから、部屋の構造や誰がどの部屋にいるとかがキーになるのかと思ってたんだけど、何も無い…
ただの尺稼ぎだったのかな?
それとも、舞台劇って伏線?
舞台劇見ないからピンと来ないんだよね〜
最後のシーンは、これはどこからどこまでがフィクションか曖昧にしてどう考えるかはあなた次第です!笑って感じ?
仲直りエンドはしょうもな過ぎだと思うから、全てフィクション説押すけど…
でもそれなら、カーテンコールの後、車椅子から立ち上がって出ていく方が綺麗なんだよな〜
違和感だらけの設定
タイトルと原作東野圭吾に釣られて観賞してみました。
そんなオーディションなんてある?
違和感だらけの設定でずっとつまらなかったので☆1個にしようかと思ったくらいですが、最後の最後での四重構造目でなんとか☆2個になりました。
原作未読ですがこれは映像化は難しくて、小説で読んだらもう少し面白かったんじゃないかなと予想します。
山荘のほぼワンシチュエーションですから、映像的にも面白味がないです。
舞台劇なら評価できたかも
劇団の最終オーディションという舞台設定で繰り広げられるミステリーですが、あまり映画向けではなかったかもですね。
劇中の様々なカラクリよりも、久我がなぜあの場にいたのか? 久我が感動したはずの雅美がなぜ三次オーディションで落ちたのか? と言った根本的な疑問が何も解決しておらず、ラストシーンを見ると四重構造と解釈するのが自然なのでしょうが、そうすると雅美が事故で下半身付随となったこともウソ? となると、盛り上がりにかけた2時間がなんだったの? ということになります。
まあ、大仰な演技も四重構造と解釈すれば、舞台的になるので理解できなくもないです。
冒頭のアイマスクの存在意義や海を見て驚くセリフなど、初っ端からダメな演出の芝居を見せられたのも、大きいかもしれません。
舞台劇なら気にならないディティールを作り込みすぎたが故に不自然な映画になったのかもしれません。
大塚明夫さんの声はいいね。
ツッコミどころは多いですね。
皆さん書かれている冒頭のバス、主人公が居る理由、井戸の中を見たリアクションなどなど。
あと舞台挨拶中継付きだったので、好きな俳優さんの話を聞きたかったんだけど、主演が全員の話に入ってきて正直…。
普通
東野圭吾原作の本作、ちょっと期待してました。
しかし、なんで重岡さんってあの中に呼ばれたんだろう?ちゃんと鑑賞したつもりだが、最後までわかんなかったです。アリバイ崩しではなく、逆の発想だったのは面白かったが、特にどんでん返し感はなく、伏線が綺麗に決まっているわけでもない…ただ最後の舞台をやりたかったんだろうなぁーその為の映画だったんだろうなぁーって思った。リアルに環境が、クローズされてないので、緊張感も薄い。色々残念。
自分の耳の問題だと思うが、肝心のところが早口でよくわかんないとこありました。盗聴器見つけたら件とか…
魔術師・東野圭吾
三重構造だ、という四重構造で、見ているものからするとそれを包括しさらなる多重構造、というのがネタバレ。
結局この演出方法では誰が出演しても似たものになるだろうね。
役を演じさせているという部分も曖昧で、演じさせている中でそれぞれ人物の本質が浮かび上がる構造なら深みも出ただろうに、多重構造という部分に囚われてしまったのか、つまらない手品を見せられたよう。
原作はどんなだろう。
東野圭吾作品は映像はすぐに浮かぶけれどもいざ実現しようとするとかなり難しい。
制作、監督、脚本の方々が魔術師東野圭吾のマジックに見事に翻弄され騙されたと言えるかもしれない。
誰にも共感できなかった
・好感度いい人がほぼいないし、全員集まってる時の雰囲気も悪く、観てて苦痛だった。
誰にも共感できなかった。
・死体がまったく出てこないので「殺人事件だ!」と言われてもピンとこなかったし、生きてるんだろうなと思いながら観てしまった。
死体なき殺人事件で観客に緊張感を与えるのって難しいですね。
・いろんな細かい設定に無理がありすぎて冷めてしまった
・天音さんの役は潔癖症キャラなのかと思ったら、食べ方は雑だし花瓶についた血なめるし…潔癖ぽい見せ方は何のためだったのか謎
・間取り図の中に登場人物がいる、あの見せ方は面白かった!
・そもそもオーディションで集まってるのに重岡くん以外誰もそこ頑張ってなくてちょっと笑ってしまった。グルの4人も頑張るフリぐらいしてほしい
・全体的にピンとこなかった
期待はずれ
本年一作目の鑑賞でしたが、ミステリーと喧伝していた割には結末や犯人のヒントも早々に提示され、特に感動も衝撃もないまま長々と学芸会的エピローグを見せられた印象。
重岡大毅さんの演技は役に自然な印象、岡山天音さんも好演の印象でしたが、中条あやみさんは転職CMのままの棒立ち演技。森川葵さんは”実力レベチの名女優”という設定に無理があるのか、やたらと重苦しく感情的に大声を出すだけで痛々しい感じがしました。
原作は未読ですが、トリックや謎をストーリーに埋め込もうとすることが前面に立ち過ぎていて、全体的に見ると違和感の多いシナリオであると感じました。
色々と納得いかない
同じ劇団に所属する6人の役者と、フリーの1人の役者の計7人に、新作舞台の最終オーディションの招待状が届いた。オーディションは4日間の日程で行われ、大雪で閉ざされた山荘、という設定で起こる連続殺人事件、を演じることになった。しかしこのオーディションの最中に1人また1人と参加者が消えていき、誰が犯人なのかとお互いが疑心暗鬼になる、という話。
原作未読で鑑賞したので、ストーリーがよくわからないところが多かった。
海辺の路線バスのバス停で降りるシーンから始まるが、眠いから目隠し?って思ってたら、もう取っても良いんだよね?なんてセリフが有り、目隠しの意味は何だったのだろう?
オーディション参加者の中で1人だけフリーの久我和幸がいたが、彼が何のために呼ばれたのかも最後までわからなかった。劇団内の揉め事なら彼は不要では?
そもそも、死体が見つかってないのに殺人事件、って思うか?というのも疑問。
それに、謎解きされても、そんな理由で?と納得いかなかった。
中条あやみ、西野七瀬、堀田真由、森川葵、など、好きな女優が多く出てたのに、彼女たちの魅力が発揮されてなかった。
そういう作品じゃないのかもしれないが、もったいない。
東野圭吾原作なので、たぶん本は面白いのだと思うが、どうも映画になると尺が足りないのか、説明不足なのだろうが、疑問点や納得いかないところが多かった。
脚本が残念だったのだろう。
期待してただけにガッカリだった。
せっかくの出演者たちがもったいない
登場人物が一人ひとり姿を消していく密室劇だが、そもそも、犯人が誰かを推理させるような作りにはなっていないので、ミステリーとしては、まったく盛り上がらない。
新進気鋭の若手俳優を集めている割に、それぞれのキャラクターに魅力が感じられないのは、物足りないとしか言いようがない。
空間が限定された、いかにも演劇的な物語なのに、時々挿入される、部屋の見取り図を俯瞰するような演劇的な演出が、まったく効果を上げていないのも、どうしたものかと思えてしまう。
やがて、事件の動機が明らかになるのだが、姿を消した3人は、首謀者を励ましに行った「良い人たち」だし、首謀者が事故にあったのは必ずしも3人のせいではないので、その動機が単なる「逆恨み」にしか思えない。
そこで、3重構造の事件のカラクリを説明されても、もともと人を殺すほどの動機には思えなかったので、何の驚きも感じないし、むしろ「そりゃそうだろう」と納得してしまった。
それにしても、なぜ、1人だけ劇団に所属していない人間が招集されたのか、その理由が最後まで分からなかった。
首謀者が、部外者である彼をわざわざ事件現場に呼ぶことに、必然性があったとは思えないし、結局、彼の推理によって事件の真相を暴かれてしまったのは、間が抜けているとしか思えない。
百歩譲って、彼を招集する必要があったのだとしても、犯人が万全を期すのであれば、あらかじめ彼に計画を打ち明けて、共犯関係に引き込むべきではなかったのではないか?
あるいは、何も知らなかったと思われる他の2人(終盤は、完全に「蚊帳の外」状態!)にしても、最初から共犯者に仕立てておけば、すべてが上手くいったのではないか?
周到なように見えて、実は穴だらけの犯人の計画が、お粗末に思えて仕方がないのである。
いずれにしても、一番最後に、首謀者が車椅子から立ち上がって、「実は、この物語は4重構造で、今までのことは、すべて舞台の上で演じられたフィクションです」みたいな、身も蓋もないオチにしなかったことだけは、せめてもの救いであるが・・・
エンドロールで余韻も消し飛ぶが、それ以前に構造の穴が大きすぎる
2024.1.12 イオンシネマ京都桂川
2024年の日本映画(109分、G)
原作は東野圭吾の小説『ある閉ざされた雪の山荘で(1992年、講談社)』
ある別荘に集められた7人の劇団員が事件に巻き込まれる様子を描いたシチュエーションスリラー
物語の舞台は、関東の海沿いの某所(ロケ地は千葉県館山市)
そこにあるロッジ「Shiki Villa」にでは、劇団「水滸」の次回作のオーディションが行われることになっていた
集められたのは、劇団のリーダー・雨宮恭介(戸塚純貴)、劇団のトップ俳優・本多雄一(間宮祥太朗)、劇団に出資している会社の令嬢・元村由梨江(西野七瀬)、由梨江への恋愛感情を拗らせている田所義雄(岡山天音)、前回の演劇で公演直前に役を下された中西貴子(中条あゆみ)、劇団の主宰である東郷陣平(大塚明夫)との関係を噂される笠原温子(堀田真由)、そして、劇団員ではない俳優・久我和幸(重岡大毅)の7人だった
久我は前作のパンフを手に彼らを認知し、そこに名前がありながらも来ていない浅倉雅美(森川葵)のことを思い出していた
彼らは別荘に入り、それぞれの部屋に荷物を置く
レストランで働いている久我が調理を担当し、その助手に由梨江がついていた
それをよく思わない田所が因縁をつけるものの、それは劇団員にも疎まれている態度だった
その後、東郷からのルールの説明が遠隔で入り、「ある閉ざされた雪の山荘で」という次回作の「探偵役」をこのオーディションで決めることが告げられる
そして、この事件は連続殺人事件で、犯人に指名された人間から退場するという流れになっていた
翌朝、最初に姿を消したのは、ワガママで貴子とトラブル続きだった温子で、どうやらピアノを弾いていた際にヘッドホンのコードで首を絞められて殺されていたことがわかる
貴子は真っ先に犯人と疑われるものの、死体の移動ができるわけがないと反論する
外部犯、複数犯の可能性も出てきて、現場は疑心暗鬼で満たされていく
そして、2日目には由梨江が姿を消し、彼女の血痕がついたと思われる血まみれの花瓶がリビングで発見されるのであった
映画は、完全ネタバレにふれないと書けない部分があるので、以降は「映画の構造自体をネタバレした状態」で感想を展開する
なので、完全ネタバレを避けたい人は、こので読むのをやめてほしい
映画の率直な感想は「三重構造」の設定は良いが、その構造だと「久我があの場所にいる理由が放置されて終わっている」というものだった
映画は、いわゆる「劇中劇」となっていて、ラストでこの顛末を舞台化したことが判明する内容になっている
物語の構造としては、前回の理不尽に思える落選で劇団を辞める雅美を励まそうとした面子が怒りを買っているというもので、彼らの訪問の後に「雅美が事故に遭った」ということが描かれていた
雅美は彼らを殺したいほど憎んでいて、それを本多が実現させるように見せかけて、実は雅美を騙すほどの演技をしていた、となっている
なので、このオーディションはでっち上げで、ターゲット三人に加えて、カモフラージュで残りの2人が選ばれていることになる
そうなると、嘘のオーディションに部外者が呼ばれるという理由がわからず、本多が探偵役として久我を招き入れたという理由でもない限り、彼がその場にいるのは不自然に思える
このあたりが映画では完全にスルーされているので、劇中劇の構造になっている段階で部外者をどう絡ませるのかまで頭が回っていない状況になっているのではないだろうか
実際のオーディションに乗じてという線もなくはないが、後半で「雅美が書いた脚本を3人に渡している」ので、そうなると東郷と本多が雅美の再生のために結託していることになるが、その線を維持するのは相当難しいように思える
原作では明かされているとか、映画による改変が起こっているとかは言い訳に過ぎず、最もしっくり来るのは「ラストで雅美にネタバレをしないといけないが、あの二人は頭が悪くて無理なので、前回のオーディションで光っていた久我を招き入れた」というものだろう
そして、屋外での秘密の会話を通じて、今後のシナリオの再調整をして、探偵役としてスムーズなネタバラシをさせた、というのが本筋であるように思えた
いずれにせよ、原作ありきの作品だが、この構造の不和に原作者が気づいていないはずがないので、何らかの表記があるが、それを裏付けるものがあるのだと思う
むしろ「部外者」にせずに、新入りにしとけばこの構造になっても問題になっていないのだが、そうなるとどの段階で誰にネタバラシをさせるのか問題が浮上する
新入りの探偵能力など予知できるものではなく、どう考えても結託していないと話にならない
なので、その辺りをキチンと組み込んだ上で久我を配していれば、余計なことを考えずに済んだのではないか、と感じた
演技か、事件か。
感想
スクリーンに映る全てが伏線。
登場人物の行動すべてを疑いたくなる、“謎解き”の枠を超えた驚愕の結末とは?
著作の累計発行部数が1億部を突破した“国民的作家”の東野圭吾が1992年に発表した傑作小説がついに映画化。
原作は未読です。
原作が面白くないのか、脚本が悪いのか、若手俳優陣を見るだけの作品でした。
豪華若手俳優陣の演技を見れただけでも良しですね。
ワクワク感、緊張感がなかったのか退屈してしまいました。
オーディションに参加した唯一の部外者、久我和幸
華と実力を兼ね備えた劇団トップ俳優、本多雄一
公演直前に役を奪われてしまった女優、中西貴子
恋愛感情をこじらせたクセあり怪優、田所義雄
世間知らずなお嬢様女優、元村由梨恵
役のためなら超勝気なワガママ女優、笠原温子
誰よりも優しい劇団リーダー、雨宮恭介
圧倒的な演技力を持つ天才女優、麻倉雅美
※滑車と歯車
※三重構造
※演出:東郷陣平 作:久我和幸
映像化する作品ではない。
題名のとおり、閉ざされた場所で起こる殺人事件です。ミステリでは古典的な設定です。東野圭吾はそれを踏まえ、古典的設定を逆手に展開した小説です。しかし、これを映像化するとなるとかなり困難です。まずは、本格ミステリぽく重々しい雰囲気で引き込まなければなりません。いわくありげな登場人物、歴史ある建物となりますが、そうなるとあまりにも現実感がなくなります。そうなると今時の若者という登場となります。重圧はなくなり軽い始まりとなります。そして「そして誰もいなくなった」のように屋敷で主催者の声が流れます。これをわかりやすくする為に、壁に文字が映し出されます。そして声はどこかのアニメで聴いた事のある声優。これで雰囲気はテレビドラマレベルに落ち緊張感がありません。そして殺人が起こります。ここも映像化により不自然さがあからさまです。更には第2、第3の殺人シーンでは犯人がまるわかりの映像です。ラストは舞台のシーンとなりますが、原作未読者はなんでこうなるの?となります。原作をもっとアレンジすべきでした。
先生の設定も禁止事項も聞く割に先生のお題は無視……
原作未読。
予告がスーパー面白そうだったので時間を見つけてすぐに鑑賞したが、肩透かし。
ミステリー目当てで見に行ったけど、個人的に『面白ければ』そうじゃなくても満足するタイプだったんだけど……大分モヤモヤ。
特に『舞台設定!』(大塚さん特有のイケボ)
って先生がわざわざ言ってるのに誰も(あの4人は仕方ないにしても)演技しないのはなんなん?
それを見られて主役決まるって事理解してる?
しないなら帰ればいいのに……。
あと一人消えたからと言って『毎晩一人づつ消える』
みたいなふんわりとした流れもなんなん?
殺人と決まった訳でもないのに手にロープ結んで『アリバイ』作ろうとするし……。
せめて法則性を先生が言うとか、2日目以降の話では……?
あと井戸の蓋開けて皆で『うわぁ……』って……。
『うわぁ……』じゃなくてさ、何らかの方法で下まで照らすかして覗きなよ!
あといきなり外様の人がなんか探偵に覚醒するし……。
あと最後のアリバイ立証もビデオテープって……。
ビデオテープで証拠を確認して推理を組み立てていくんならわかるけど……。
それが決めてってちょっと……。
あとイヤホンが抜けてなかったから違和感って……いや、だからなんやねんって感じ。
死体も無いのに無理くり絞殺されたとは言い切れないでしょ……。
某コナンみたいに眠らされたのかもしれないし……。
先生のそういう設定も注意も聞く癖に先生のお題は無視……なんなん?
そういう話の導線がいちいち杜撰だったのが気になった感。
ただ、先生と寝て、役を横取りしたようではなかったようなので☆1.5!
つまんない
設定が文章なら想像して成り立つのかな。
とにもかくにも沸き立つなんじゃそりゃ感。あの程度で3人も殺すかね森川さん。
重ちゃんの演技がさすがに精鋭揃いの役者の中では全く魅力がなかった。
キャラが良いだけにキャラに合った演技しかはまんないのかしら。
その他の6人はさすが。
それだけに脚本のへっぽこさが際立つ。
謎解きではなくあっと驚く仕掛けにしたかったのかもやけど死体も無いし死んでないんやろなーとあるいはみんなグルなんかなーとか。まあ死んでない時点でシリアスさも何もなくなってまさかの森川さん登場。
トイレどないしてたんや、、、、
穴だらけのミステリー
原作は未読です。
おそらく、原作はそうでもないのでしょうが、この映画に関しては、穴が多すぎる。特に重岡大毅演じる久我、彼が何故呼ばれたのか分からない。唯一部外者なのだから、いない方が成立し易い筈だ。多分、原作ではその辺りがポイントになってるん筈なのに、映画では探偵としての役割の為にいるとしか思えない。
他にも、どう言ってこのペンションを借りたんだ、とか、行くまでに演出家にその話したらどうすんだ、とか、隠れてる間トイレどうした?、とか、えー、色々ありすぎて、逆に原作が気になりました。
最後、舞台に変換するが、この脚本は映画より舞台に向いていると思う。
誰かが何かを間違えた感がある
微妙な仕上がりなんだよね。
原作・東野圭吾が良くなかった可能性はある。そこは捨てきれないけど、さすがにここまでヌルい話は書かないと思うの。
監督の飯塚健さんもいい作品撮ってるから大丈夫と思う。
脚本の加藤良太さんがどうなのか知らないけど、公式ホームページは『監督・脚本 飯塚健』だから、そんなに書いてないのかな。
色んなギミックがことごとく外してる感じがするんだよね。
監視カメラ映像をすごく使うんだけど、それによる不穏さとか出てこないの。誰視点なのか最後に分かるんだけど、分かったとて……という感じ。
天井に文字を浮かべて音声合成で読み上げてるのもなんだかなあ。文字のフォントは二種類混ぜてるけど、そのセンスもどうであったか。
役者の良さもほぼ活きてないの。このキャスティングでこの話は難しかったのでは。
そこまでメジャーじゃない劇団の俳優さんでやった方が、リアル感がでたんじゃないかと途中で思ったもん。
『水滸』っていう劇団で主演を取るためだけに、ここまで必死になるかなあとも思うのね。
「この劇団で主演はったらすげえぜ!」って宝塚歌劇団しか思いつかないんだけど。
解決編では犯行の動機が語られるんだけど、これ、どっちかっていうと逆恨みだよね。
恨まれる方は、そこまで悪いことしてないと思うよ。
原作ではもう少し納得感あるのかな。脚色で悪くしてる気もする。
ほぼ観るべきところがない作品なんだよね。
これだけの役者を集めて、この作品を作ってしまったら、スタッフの誰かが懺悔の涙を流してるんじゃないかとすら思ったもん。
でも、ミステリの映像化が、多分、難しいんだね。
オドロオドロしい雰囲気出さなきゃいけないから、そんなにコメディタッチでもいけないし。かといってシリアスにいっても、そこまで強いストーリーではない。
金田一耕助を見事に映像化した市川崑とか、ほんとに巨匠だったんだな。
劇団あるあるイジりも多少あり
原作未読。
さすがに設定に無理があり過ぎて入り込めなかったし、ラストもよくわからなかった。
(自分がわかってないだけでもしトンチンカンな事を言ってるのであれば先に謝っておきますが)
そこまで大きくない一軒家に自分一人で歩く事ができない人間が数日間見つからずに隠れ続けたり、最後はいなくなった3人もどこかに隠れていたみたいだけど、現実味が薄過ぎて萎えてしまった。
ピアノ部屋の鏡のドアは自分でさえ最初に見た時から早く開けてよと思うくらい不自然だったし。
また久我が名探偵過ぎだし、そもそも水滸のメンバーでもない久我を誰が招待したのかな?
それとも久我は最初から水滸のメンバーで全て彼が書いた脚本の舞台上の話?(だとすると事故自体もフィクション?)
この辺りはストーリーの肝の部分なのでもう少し明確にして欲しかったと思う。
役者さんたちは若手の主役級ばかり。
特に重岡くんは笑顔や演技が全てウソくさい感じがして面白かった。
中条さんは実は蚊帳の外だったけど一人だけ別次元のスタイルで目を惹いた。
先日観た映画「笑いのカイブツ」の主演だった岡山くんも蚊帳の外の一人だが、若い時の柄本明を彷彿させるくらいひたすら気持ち悪く、高校の部活のジャージ(nishiって刺繍があったので古着?)を稽古着にしてるとかもろに劇団あるある。
役者ファンの方は是非。
演技は良いが、話がつまらなかった❄️
タイトルから、往年の「かまいたちの夜」みたいなものを期待すると、全然違います。演技や演出は悪くないと思いますが、話が面白くないです。大塚明夫さんだけ何かアトラクション感が出て浮いていますし、人狼ゲームみたいな頭能戦が観たかったのです。
全く記憶に残らなかったし感情も揺さぶられなかった
まず、私自身はミステリー小説を全く読まないし、
映画もあまり鑑賞しません。
好きになった作品であれば何度でも見ます。
そうでなければ二度と見ません。
東野圭吾先生の原作小説も読んでいませんが、
ただ「タイトル」を見て、興味を持ち、DVDを購入して鑑賞しました。
映画とは関係ありませんがクリエイティブ系の仕事をしている為、
『モノづくりをする以上、それを見た、聴いた、体験した人に何か主張できる作品』
こそ名作であると考えていますが、
この映画を見終わった時、正直何も残りませんでした。
起承転結の「起」は悪くは無かったとは思います。
舞台設定、キャラクターの人間関係、非日常感の演出は
ミステリー的な『何かが起こりそう』な王道な期待感を醸していました。
しかし2日目になって「事件」が起こった辺りから、
どうにも腑に落ちない事が異常に多く起こります。
・カメラで監視されている事が分かっていて起こる殺人
(これに関しては「転」に繋がる伏線ではあったのでしょうが)
・たいして抵抗もしない犠牲者
・見つからない死体
・突如探偵役のようになる登場人物
・自衛せずにのうのうとそのあとも過ごし続ける参加者
・家の間取り図っぽい謎の演出
・「雪の山荘」という設定がまったく活かされない
その後の進行で結局全て「芝居だった」という事が分かるわけで、
説明口調で『3重構造』となり、転回部から結末部へと進んでいくんですが、
ノックスの十戒を破って、ずっと潜んでいた8人目の登場人物の存在や
(見ている限り、伏線は特に無かったと思いました)
実は誰も死んでなかったという事に大した驚きは無いし、
「すみませんでした」と謝るその様すら芝居味を感じてしまい、
そしてラストシーン。
特に何の説明もなく唐突に舞台のシーンとなり、
探偵役が脚本の作品だったという事で終了……と大体こんな流れでしたが。
小説版の原作がどんな感じなのかは非常に気にはなりました。
これだけ『何も感情が動かなかった』作品。
しかし小説は高評価が多い事を知ったので買おうかなとは思いました。
何故、なにひとつ心が動かなかったのか。感動できなかったのか。
結局「全部芝居なんです。あとはあなたの解釈にお任せします。」という、
投げやりな作りになっていたという印象を、私は強く感じてしまったからかもしれません。
この映画版をもう一度見直す事は、たぶん無いです。
全170件中、141~160件目を表示